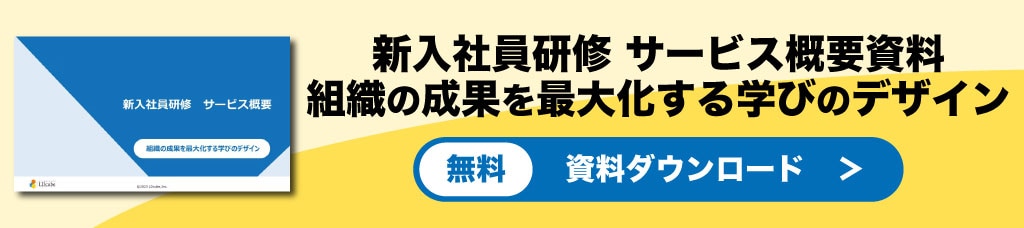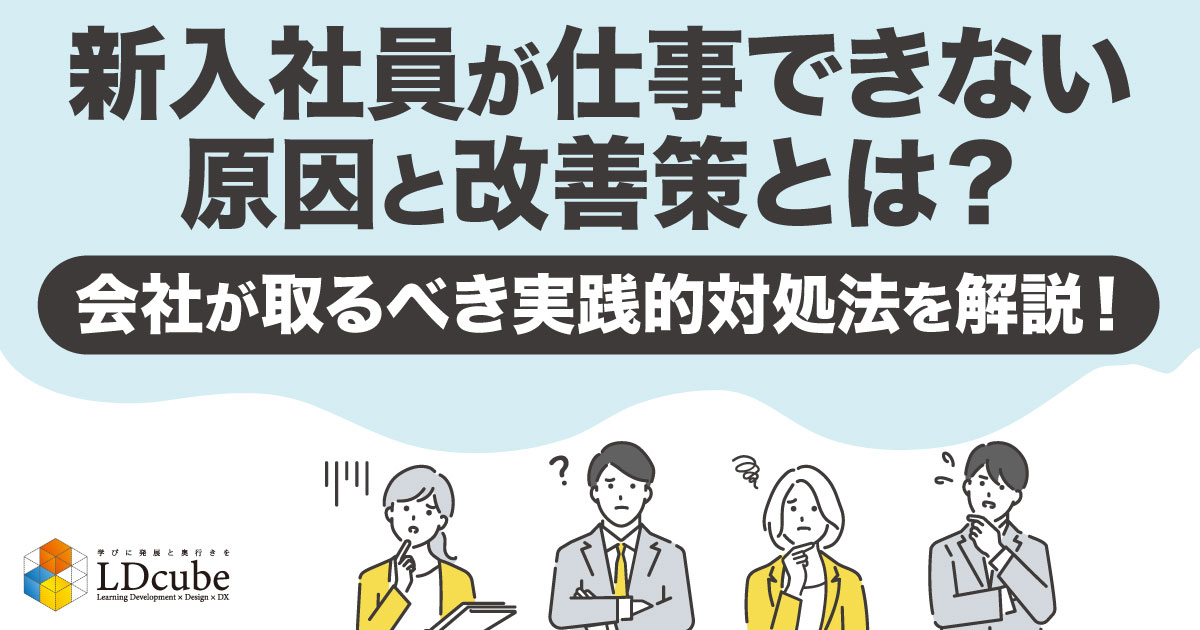
新入社員が仕事できない原因と改善策とは?会社が取るべき実践的対処法を解説!
「新入社員が仕事できない」
「今年の新人は使えない」
といった声は、多くの企業で聞かれる共通の悩みです。人事担当者や上司の方々は、新入社員の育成に頭を抱えているのではないでしょうか。
配属先で早く成果を出してほしいと願う反面、もちろん新入社員が初めから完璧に仕事をこなせるわけではありません。本記事では、新入社員が「できない」と感じられる背景に迫り、その解決策を探ります。
まず、大学で専門的な職業訓練を受けていない場合、具体的なスキルや知識を持たないのは当然のことです。看護師や会計士のように資格を持つ職種であっても、即戦力として活躍するには職場独自のルールやシステムに慣れる時間が必要です。新入社員には段階的な成長を支える育成プログラムが不可欠ですし、適切な期待値の設定が重要になります。
さらに、組織人としての基本的な考え方やスキルを身に付けるための教育も重要です。特に新入社員は、社会人としての振る舞いに不慣れな者も多く、基本的なビジネスマナーやコミュニケーションスキルの習得が求められます。ここで鍵になるのがデジタル技術を活用した学習環境の整備と、OJTの効果的な運用です。
また、環境変化が新入社員の育成に与える影響にも触れ、コロナ禍を背景に変わりつつある職場環境やコミュニケーションの在り方についても検討します。そこで、各企業が持続可能な育成システムを構築するための具体的な改善策を提案します。一人前の社員へと成長させるためのステップを、共に考えていきましょう。
▼2026年度新入社員研修に向けてのトレンドを解説しています。 |
▼新入社員研修についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。
▼新入社員の育成については下記にまとめています。(4部作:企画編・実践編・カリキュラム編・講師ガイド編)
目次[非表示]
- 1.新入社員が仕事できないのは当たり前
- 2.新入社員が仕事できないと感じる時期がポイント
- 2.1.4~6月:できなくて当たり前
- 2.2.7~9月:個人差が出てくる
- 2.3.10~12月:できるようになってくる
- 2.4.1~3月:できないとまずい
- 3.新入社員が仕事できないと感じる背景と現状
- 4.仕事ができないと感じる新入社員の特徴【意識面】
- 5.仕事ができないと感じる新入社員の特徴【スキル面】
- 6.新入社員が仕事できない根本的な原因
- 6.1.研修体系の未整備
- 6.2.学習環境の未整備
- 6.3.OJT体制の未整備
- 6.4.管理者の人材育成意識の欠如
- 6.5.新入社員の個人的資質
- 7.仕事ができる新入社員を育成のための処方箋
- 7.1.①上司への人材育成の重要性の研修実施
- 7.2.②デジタル学習環境の整備
- 7.3.③1年間を通じたオンボーディングプログラムの構築
- 7.4.④体系的な研修実施
- 7.5.⑤学習状況のモニタリング
- 8.新入社員オンボーディングプログラムの事例
- 9.新入社員研修や育成ならLDcubeにお任せ!
- 10.まとめ:新入社員が仕事を学べる環境をつくろう
新入社員が仕事できないのは当たり前

「新入社員が仕事できない」という悩みを抱える人事担当者や管理職の方は多いのではないでしょうか。しかし、冷静に考えてみると、新入社員が最初から仕事ができないのは当然のことです。適切な期待値を設定し、段階的な育成計画を立てることが重要になります。
職業訓練を終えていない職種では仕事はできない
多くの新入社員が配属される事務職、営業職、企画職などは、大学で専門的な職業訓練を受けていない職種です。これらの職種では、業務に必要な具体的なスキルや知識を大学で学ぶ機会がほとんどありません。
例えば、営業職に配属された新入社員が顧客対応に戸惑うのは当然です。大学では顧客との関係構築方法や商談の進め方を学んでいないからです。同様に、企画職に配属された新入社員が企画書作成に苦戦するのも、体系的な企画立案プロセスを学習していないためです。
このような状況を理解せずに「なぜできないのか」と感じるのではなく、「これから教えて育てていく段階」として捉えることが大切です。職業訓練を受けていない分野では、基礎から丁寧に教育する必要があります。
職業訓練を終えている職種とは
一方で、大学や専門学校で職業訓練を終えている職種も存在します。看護師、薬剤師、会計士などがその代表例です。これらの職種では、国家資格や専門資格の取得過程で実務に直結する知識とスキルを習得しています。
しかし、たとえ職業訓練を終えている職種であっても、実際の職場では即戦力として機能するわけではありません。学校で学んだ理論と実際の業務には違いがあり、職場特有のルールや慣習、使用システムなどを新たに覚える必要があります。
例えば、薬剤師として採用された新入社員も、その会社で使用しているオペレーションシステムでの業務フローは初めて経験するものです。基礎的な専門能力はあっても、実際の現場で仕事ができるようになるには一定の期間が必要になります。
職業訓練を終えていても組織人としての教育が必要
どのような職種であっても、組織の一員として働くための考え方やスキルは別途習得が必要です。報告・連絡・相談の方法、会議での発言の仕方、上司や同僚とのコミュニケーション、顧客対応のマナーなど、組織人としての基本的な行動規範は実務経験を通じて身に付けるものです。
特に現代の新入社員は、学生時代にアルバイト経験が少ない人もおり、組織の中で働いた経験そのものが不足している場合が多くあります。そのため、専門的なスキルとは別に、社会人としての基礎的な振る舞いから教育する必要があります。
また、各企業には独自の企業文化や価値観があります。新入社員がその組織になじみ、効果的に貢献できるようになるためには、これらの要素を理解し、実践できるようになることが不可欠です。このプロセスには時間がかかるものと認識し、焦らずに育成していくことが重要です。
新入社員が仕事できないと感じる時期がポイント

新入社員の成長には一定のパターンがあり、時期によって期待値を調整することが重要です。「仕事ができない」と感じる時期を正しく理解することで、適切な支援とフォローアップを提供できます。
4~6月:できなくて当たり前
入社直後の4月から6月は、新入社員が組織に適応する期間です。この時期に仕事ができないのは極めて自然なことで、むしろできる方がまれなケースと考えるべきです。
新入社員は会社のルール、業務の流れ、使用するシステム、職場の人間関係など、全てが初めての経験となります。基本的なビジネスマナーや報告・連絡・相談の方法も、頭では理解していても実践には時間がかかります。
この時期の主な課題は、指示された内容を正確に理解し、分からないことを適切に質問できるようになることです。完璧な成果物を求めるのではなく、学習意欲と改善への取り組み姿勢を評価することが重要になります。
7~9月:個人差が出てくる
入社から3~6カ月が経過すると、新入社員の間で個人差が現れ始めます。基本的な業務の流れを理解し、簡単なタスクを1人で完了できる人がいる一方で、まだ頻繁なサポートが必要な人も出てきます。
この時期の差は、学習能力や経験の違いだけでなく、職場環境への適応度やコミュニケーション能力によっても左右されます。順調に成長している新入社員は、自分から質問や相談をして積極的に学ぼうとする姿勢が見られます。
一方で、まだ十分にできていない新入社員については、個別のフォローアップが必要な時期です。画一的な指導ではなく、個人の特性や課題に応じた支援を検討することが効果的です。
10~12月:できるようになってくる
入社から半年以上が経過すると、多くの新入社員が基本的な業務を自立して行えるようになります。この時期には、定型的な作業であれば1人で完了でき、イレギュラーな状況でも適切に上司に相談できるレベルに達します。
新入社員自身も仕事に慣れてきて、自信を持って業務に取り組めるようになります。また、職場の人間関係も安定し、チームの一員として機能し始める時期でもあります。
ただし、この時期でも複雑な判断が必要な業務や、責任の重い業務については、まだ上司のサポートが必要です。できるようになったからといって、すぐに高度な業務を任せるのではなく、段階的にレベルアップを図ることが重要です。
1~3月:できないとまずい
入社から約1年が経過する1月から3月は、新入社員が一人前の社員として評価される重要な時期です。この段階で基本的な業務ができない場合は、何らかの対策が必要になります。
1年間の経験を積んだ新入社員には、担当業務の基本的な部分を自立して行い、適切な品質で業務が行えることが期待されます。また、新たに入社する後輩の指導や支援にも参加できるレベルが理想的です。
この時期になっても大幅な改善が見られない場合は、配属先の見直し、追加研修の実施、個別指導など、抜本的な対策を検討する必要があります。ただし、個人の責任だけでなく、育成体制や職場環境に問題がなかったかも併せて検証することが大切です。
新入社員が仕事できないと感じる背景と現状

近年、多くの企業で「新入社員が思うように育たない」という悩みが共通して聞かれるようになりました。これは個別企業の問題ではなく、社会全体の変化に起因する構造的な課題として捉える必要があります。
多くの企業で共通して見られる新入社員の課題
人材育成に関する調査データによると、多くの企業が新入社員に対して同様の課題を感じています。最も多く挙げられるのは、主体性の不足、コミュニケーション能力の低さ、基本的なビジネスマナーの理解不足です。
特に顕著なのは、指示待ちの姿勢が強く、自分から積極的に学ぼうとする意識が低い傾向です。また、失敗を恐れる気持ちが強く、チャレンジングな業務に対して消極的になりがちな新入社員が増えています。
これらの課題は、学生時代の経験や教育環境の変化、就職活動の長期化による影響など、複数の要因が複合的に作用した結果と考えられます。単に個人の資質の問題として片付けるのではなく、時代背景を理解した上で対策を講じることが重要です。
コロナ禍が新入社員に与えた影響
2023年以降に入社した新入社員は、学生時代の大部分をコロナ禍で過ごした世代です。この経験は、彼らのコミュニケーション能力や社会性の発達に大きな影響を与えています。
大学生活の多くがオンライン授業となり、サークル活動やアルバイト、就職活動も制限される中で、対面でのコミュニケーション経験が大幅に減少しました。その結果、職場での人間関係構築や、上司・先輩とのコミュニケーションに不安を感じる新入社員が増加しています。
また、リモートワークが普及した職場では、新入社員が孤立しやすい環境も生まれています。従来のように先輩の仕事ぶりを間近で見て学ぶ機会が減り、暗黙知の伝承が困難になっているのが現状です。これらの環境変化を踏まえた、新しい育成アプローチの構築が急務となっています。
参考:
▼新入社員研修のトレンドについては下記で詳しく解説しています。
⇒【2026年版】新入社員研修の最新トレンドとは?設計から継続改善までを完全解説!
仕事ができないと感じる新入社員の特徴【意識面】

新入社員が仕事できないと感じられる要因の多くは、スキル不足よりも意識面の課題に起因しています。適切な意識改革を促すことで、大幅な改善が期待できる領域でもあります。
学生気分が抜けず社会人としての自覚が不足している
多くの新入社員に見られる課題が、学生から社会人への意識転換の遅れです。学生時代は自分のペースで物事を進められましたが、社会人では組織の一員として責任を持って行動することが求められます。
具体的には、時間管理が甘く遅刻や締め切り遅れが頻発したり、服装や身だしなみに無頓着だったり、言葉遣いが学生時代のままで敬語が使えないといった問題が現れます。また、自分の行動が周囲に与える影響を考慮せず、個人の都合を優先してしまう傾向も見られます。
このような状況は、社会人としての責任や役割についての理解不足が根本原因です。学生時代の延長として仕事を捉えているため、プロフェッショナルとしての行動基準が身に付いていません。明確な期待値の設定と、社会人としての行動規範の教育が必要になります。
▼新入社員の社会人としての心構えについては下記で詳しく解説しています。
⇒新入社員研修で教える社会人としての心構えを強化するには?基本マインド8選も解説!
仕事に対する前向きな姿勢が不足している
仕事に対するモチベーションや取り組み姿勢に課題がある新入社員も少なくありません。与えられた業務を単なる作業として捉え、成長や貢献への意識が低い状態です。
このタイプの新入社員は、興味のある業務には積極的に取り組む一方で、地味な基礎業務や雑務に対しては手抜きをしがちです。また、「なぜこの仕事をするのか」という目的意識が希薄で、指示された内容をただこなすだけの受動的な姿勢が目立ちます。
背景には、理想と現実のギャップによる失望感や、自分のキャリアビジョンと現在の業務との関連性が見えていないことがあります。仕事の意味や価値を理解してもらうとともに、小さな成功体験を積み重ねることで前向きな姿勢を育成することが重要です。
指示待ちで主体性や積極性が不足している
現代の新入社員に特に多く見られるのが、指示待ちの姿勢です。上司からの明確な指示がないと動けず、自分で考えて行動することができません。これは、学生時代に正解が用意された環境で過ごしてきた影響が大きいと考えられます。
具体的には、作業が終わっても次に何をすべきか分からず待機している、疑問があっても自分で調べずに誰かが教えてくれるのを待っている、問題が発生しても対処法を考えずに上司に丸投げしてしまうといった行動が見られます。
このような姿勢では、業務の効率性が低下するだけでなく、成長機会を逃してしまいます。自分で考える習慣を身につけさせ、小さな判断から段階的に任せていくことで、主体性を育成する必要があります。
同じミスを繰り返し改善意識が低い
学習意欲や改善意識の不足も、仕事ができない新入社員の特徴の1つです。1度指摘されたミスを繰り返したり、フィードバックを受けても行動が変わらなかったりします。
この背景には、失敗に対する捉え方の問題があります。ミスを学習機会として活用するのではなく、単に叱られる出来事として認識しているため、根本的な改善に取り組もうとしません。また、完璧主義的な傾向があり、ミスを認めることへの抵抗感が強い場合もあります。
改善意識を高めるためには、ミスの原因分析と対策立案を一緒に行い、改善のプロセスを身に付けてもらうことが効果的です。また、改善努力を適切に評価し、成長を実感できる環境を整えることも重要になります。
仕事ができないと感じる新入社員の特徴【スキル面】

スキル面での課題は、適切な研修や指導により比較的短期間で改善が可能な領域です。具体的な問題点を明確にして、段階的なスキルアップを図ることが重要になります。
基本的なビジネスマナーが身に付いていない
最も基本的でありながら、多くの新入社員が苦手とするのがビジネスマナーです。電話応対、来客対応、メールの書き方、会議での振る舞いなど、日常業務に欠かせないマナーが身に付いていません。
具体的には、電話に出るのを躊躇したり、相手の名前を聞き取れなかったり、適切な敬語が使えないといった問題があります。また、メールでは件名の付け方が不適切だったり、宛先の設定ミスがあったり、ビジネス文書としての体裁が整っていないことも多く見られます。
これらのマナー不足は、社外の方との接触がある業務では特に問題となります。企業の信頼性にも関わるため、早急な改善が必要です。体系的なビジネスマナー研修の実施と、日常業務での継続的な指導が効果的です。
▼新入社員研修におけるビジネスマナーについては下記で詳しく解説しています。
⇒新入社員研修で押さえるべきビジネスマナーとは?成功のコツ・マナー定着のポイントを徹底解説
報連相ができずコミュニケーションが取れない
報告・連絡・相談のスキル不足は、新入社員が仕事できないと評価される、大きな要因の1つです。適切なタイミングで必要な情報を共有できず、問題の発見や対処が遅れてしまいます。
多くの新入社員は、何を報告すべきかの判断ができません。ささいなことでも逐一報告してしまったり、逆に重要な問題を報告せずに1人で抱え込んでしまったりします。また、相談するタイミングが分からず、手遅れになってから助けを求めるケースも頻繁に見られます。
効果的な報連相のためには、具体的なルールとフォーマットの提供が必要です。どのような内容をいつ誰に報告するかの基準を明確にし、実践を通じて身に付けてもらうことが重要になります。
▼新入社員研修におけるコミュニケーションについては下記で詳しく解説しています。
⇒新入社員研修でコミュニケーション能力を鍛えるには?ポイントを解説!
仕事の優先順位を付けることができない
複数のタスクを並行して進める際の優先順位付けができないのも、新入社員によく見られる課題です。緊急度と重要度の判断ができず、効率的な作業進行ができません。
この問題により、締め切りの迫った重要な業務が後回しになったり、時間をかける必要のない簡単な作業に長時間を費やしたりします。結果として、全体的な業務効率が低下し、周囲に迷惑をかけることになります。
優先順位付けのスキルは、マトリックスを使った整理方法や時間管理の技法を教えることで改善できます。具体的な業務を例にした実践的な訓練が効果的です。
周囲からのフィードバックを受け入れられない
建設的なフィードバックを素直に受け入れられない新入社員も少なくありません。指摘を批判として受け取り、感情的に反応したり、改善行動に移せなかったりします。
背景には、自己肯定感の低さや完璧主義的な考え方があります。ミスや不足を指摘されることを個人攻撃として捉えてしまい、学習機会として活用できません。また、プライドが高く、先輩や上司からの助言を受け入れることに抵抗を感じる場合もあります。
フィードバックを効果的に受け入れてもらうためには、伝え方の工夫と心理的安全性の確保が重要です。改善点だけでなく良い点も併せて伝え、成長支援の意図を明確にすることで、受け入れやすい環境をつくることができます。
新入社員が仕事できない根本的な原因

新入社員が期待通りに育たない場合、個人の能力や意欲だけでなく、組織的な要因が大きく影響していることが多くあります。根本的な原因を特定し、システマチックに改善することが重要です。
研修体系の未整備
多くの企業で見られる問題が、新入社員研修の体系化不足です。コロナ禍など新入社員が育った環境も大きく変化してきています。場当たり的な研修プログラムでは、必要なスキルや知識を効率的に習得することができません。
典型的な問題として、オンラインも含めた効果的な学習環境をつくろうとせず、集合できるようになったからこれまで通りの集合研修を実施するなどが挙げられます。現在の新入社員はスマホで手軽に学べる環境で育ってきています。そのような環境が整っていないことは学びづらさを感じる要因になります。
また、集合研修をベースにするため研修が春先に集中し、適切なタイミングで学ぶことができずに非効率になっているケースも多く見られます。現代では、オンライン研修などを通じて、配属後も集合することなく学ぶ機会をつくれる時代です。
効果的な研修体系を構築するためには、業務に必要なスキルマップの作成、段階的な学習プログラムの設計、定期的な効果測定と改善が必要です。単発の研修ではなく、年間通じて継続的な学習プロセスとして位置づけることが重要になります。
▼研修体系については下記で詳しく解説しています。
⇒理想的な研修体系とは?構築方法やポイントを徹底解説!
学習環境の未整備
現代の人材育成では、デジタル学習環境の整備が不可欠ですが、多くの企業でその対応が遅れています。新入社員が自主的に学習できる環境がないため、受動的な学習姿勢から脱却できません。
具体的には、eラーニングシステムの未導入、学習コンテンツの不足、モバイル対応の遅れなどが問題となります。また、学習進捗の管理やサポート体制も十分でないため、効果的な自主学習が困難な状況です。
学習環境の整備には、LMS(学習管理システム)などの学習プラットフォームの導入、マイクロラーニングコンテンツの充実、個別化された学習パスの提供などが効果的です。新入社員が必要な時に必要な知識にアクセスできる環境を構築することが重要です。
▼学習プラットフォームについては下記で詳しく解説しています。
⇒学習プラットフォームで人材育成の効率を高めるには?おすすめ運用方法も解説!
OJT体制の未整備
OJT(On-the-Job Training)は新入社員育成の中核的な手法ですが、多くの企業でその運用に課題があります。OJT計画書が存在しなかったり、OJTトレーナー向けの研修が不十分だったりします。
また、OJTの進捗管理や品質管理の仕組みがなく、トレーナーの個人的な資質や経験に依存している状況も見られます。業務が忙しい中でOJTを実施するため、十分な時間を確保できないという問題もあります。
効果的なOJT体制の構築には、トレーナーの選定と育成、OJT計画の策定、定期的な振り返りと改善の仕組み化が必要です。組織全体でOJTの重要性を共有し、必要なリソースを確保することが重要になります。
▼OJTについては下記で詳しく解説しています。
⇒OJT計画とは?テンプレート例や効果的なプランの立て方・注意点
管理者の人材育成意識の欠如
新入社員の直属上司や管理職の人材育成に対する意識の不足も、大きな問題の1つです。プレイングマネジャーとして自分の業務に追われ、部下育成に十分な時間や注意を払えない状況があります。
また、人材育成のスキルや知識が不足している管理職も多く、効果的な指導やフィードバックができません。世代間のギャップへの理解不足や、現代の新入社員の特性に合わない指導方法を続けているケースも見られます。
管理職の育成意識と能力の向上には、人材育成研修の実施、育成成果の評価制度への組み込み、育成のための時間確保などが必要です。組織として人材育成の重要性を明確にし、管理職がその責任を果たせる環境を整備することが重要です。
新入社員の個人的資質
組織的な要因だけでなく、新入社員個人の資質や特性も影響要因の1つです。学習意欲、コミュニケーション能力、ストレス耐性、適応力などの個人差が、育成の効果に大きく影響します。
現代の新入社員には、デジタルネイティブである一方で対面コミュニケーションが苦手、安定志向が強く挑戦を避ける傾向、個人主義的で組織への帰属意識が低いなどの特徴が見られます。これらの特性を理解した上で、個別対応を検討することが必要です。
ただし、個人の資質を理由に育成を諦めるのではなく、その人の特性を生かせる役割や環境を見つけることが重要です。多様な人材が活躍できる組織づくりを進めることで、より効果的な人材育成が可能になります。
仕事ができる新入社員を育成のための処方箋

新入社員が効果的に成長できる環境を整備するために、組織として取り組むべき具体的な改善策を5つの処方箋として提示します。これらを段階的に実装することで、持続可能な人材育成システムを構築できます。
①上司への人材育成の重要性の研修実施
新入社員の直属上司や管理職に対する人材育成研修の実施が最優先課題です。多くの管理職は自身の業務経験を基に指導を行いますが、体系的な育成スキルを学ぶ機会が不足しています。
研修では、現代の新入社員の特性理解、効果的なフィードバック方法、コーチングスキル、目標設定と評価の手法などを習得してもらいます。また、人材育成が組織の成果に与える影響を理解し、育成責任者としての意識を醸成することも重要です。
具体的には、以下の要素を含む研修プログラムが効果的です。
|
②デジタル学習環境の整備
現代の新入社員育成には、デジタル技術を活用した学習環境の整備が不可欠です。いつでもどこでも学習できる環境を提供することで、自主的な学習習慣の形成と効率的なスキル習得が可能になります。
LMS(学習管理システム)の導入により、個人の学習進捗を可視化し、必要に応じて追加サポートを提供できます。また、マイクロラーニング形式のコンテンツを充実させることで、業務の合間に効率的な学習が可能になります。
デジタル学習環境の構築要素:
|
③1年間を通じたオンボーディングプログラムの構築
入社時の集中研修だけでなく、1年間を通じた、継続的なオンボーディングプログラムの構築が重要です。新入社員の成長段階に応じて、適切なタイミングで必要な支援を提供します。
プログラムは、入社前、入社後1カ月、入社後3カ月、入社後6カ月、入社後12カ月のようなフェーズに分けて設計します。各フェーズでの目標を明確にし、達成度を測定することで、個別対応の必要性を判断できます。
オンボーディングプログラムの構成要素:
|
▼新入社員のオンボーディングについては下記で詳しく解説しています。
⇒新入社員のオンボーディングに必要な要件とは?構築と運用の工数についても解説!
④体系的な研修実施
場当たり的な研修ではなく、業務に必要なスキルを体系的に習得できる研修プログラムの構築が必要です。スキルマップを作成し、段階的に能力向上を図れるカリキュラムを設計します。
研修は、知識習得、スキル練習、実践、振り返り改善のサイクルで構成し、継続的な学習を促進します。また、集合研修、オンライン学習、OJT、自主学習を組み合わせたブレンデッドラーニング方式を採用することで、学習効果を最大化できます。
体系的研修の設計原則:
|
▼研修の設計については下記で詳しく解説しています。
⇒効果を生み出す研修設計の方法とは?見直すポイントと成果との関係を解説!
⑤学習状況のモニタリング
新入社員の学習状況と成長過程を継続的にモニタリングし、必要に応じて追加支援を提供する仕組みが重要です。データに基づいた客観的な評価により、効果的な育成計画の調整が可能になります。
モニタリングでは、学習進捗、スキル習得度、業務パフォーマンス、モチベーション状態などを定期的に測定します。また、360度フィードバックや同期間での相互評価なども活用し、多角的な視点から成長状況を把握します。
学習状況モニタリングの要素:
|
▼効果測定については下記で詳しく解説しています。
⇒研修の効果測定・評価を行い、成果につなげる方法とは?ツール活用法も解説!
新入社員オンボーディングプログラムの事例
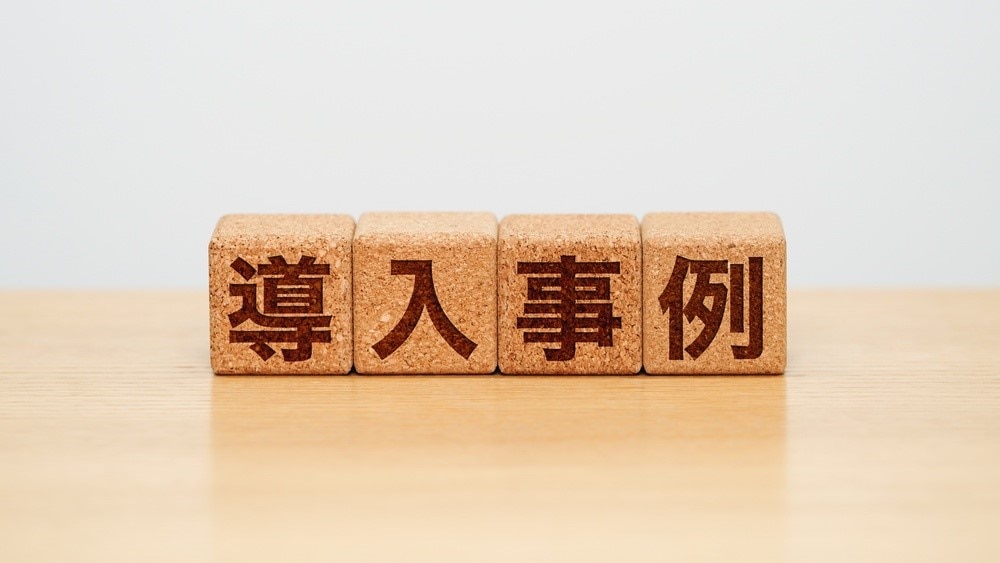
弊社がお手伝いした新入社員オンボーディングプログラムの構築支援の事例を紹介します。
不動産営業のケース
~デジタルOJTとリアルOJTの連動で業績向上へ【UMU活用】~
社員数:3000名以上
事業:住宅メーカー
■ 導入前の課題~環境変化に対応した教育を提供したい~
働き方改革など、時代や環境の変化に伴い、従来通りの詰め込み型教育では新入社員がなかなか育たないという課題を抱えていました。
この課題を解決するため、2018年に新入社員の教育方針を「全社の人材育成システムを確立し、共通認識の下、営業人材を長期的視点で組織的・計画的に育成する」というものに変更しました。
3年で一人前とする本計画の元、
研修は事前学習→集合研修→職場実践サイクルによる、OJTとの連動形式を取る
計画的なロールプレーイングの実施で営業のスキル向上を図る
個々の学習の進捗状況と習得度の把握
をしながら持続的学習を促進していくために、マイクロラーニングによるインプットとAIによるロープレ(ラーニングプラットフォーム:UMU(ユーム)の活用)の導入を決定しました。
■ 取り組みの詳細
①マイクロラーニングによるインプットで本部・現場の負担減へ
現場のハイパフォーマー社員に依頼し、1人当たり2テーマの模範ロープレ動画を提供してもらい、その動画をプラットフォーム上に掲載しました。
動画学習+AIロープレ導入前は現場でのOJTの質にばらつきがあるという課題もありましたが、動画学習の導入を機に、学習の質を均一化することができ、今では入社1年目~3年目の必須コンテンツとなっています。
② 研修後の確認テストで学びの定着を図る
研修の最後にまとめとして、受講生にはプラットフォーム上で確認テストに回答してもらうことで、研修の理解度を測るとともに、学習内容の定着化を図る取り組みをしました。
講師はリアルタイムで受講生たちの理解が浅いポイントが分かり、その場で解説や補足説明を行うことで、効率的な学習を実現できました。
③48のテーマに細分化したロープレの提供で営業スキル向上へ
一人前になるまでに必要な知識を48テーマに細分化し、それをロープレの課題として受講生に提示、順次プラットフォーム上に動画をアップロードしてもらうことで、営業スキルの向上を図っています。
1週間に1本ずつ、模範ロープレ動画を視聴した上で、自身のロープレ動画を提出してもらいます。上司から70点以上の評価を受けることができればテーマクリアという運用を実施することで、デジタルで体系的な学習をしながら、リアルでOJTを促進するという連動を図っています。
■ 導入後の成果
①一人前として必要な知識を漏れなく学習
プラットフォーム導入前は、3年間営業活動をしていても、人によっては現場で遭遇しないテーマもありましたが、48テーマを計画的に展開していくことで、体系的に、漏れのない学習の提供が可能となりました。
②学習と上司からのフィードバック率と業績の相関が分かった
受講生が動画を提出すると、AIからのフィードバックを受けられるため、1人でも自分のロープレにおける啓発ポイントを確認しながら、何度もロープレの練習をすることが可能です。また、トークの中身についても上司からのフィードバックを受けることで、トークのブラッシュアップを図ることができます。
実際に受講生の学習や上司のフィードバック率のランキングデータを確認すると、上位者には好業績者の顔ぶれが並んでおり、学習と上司からのフィードバック率と業績が相関していることが分かりました。
これまで現場でのOJT実施状況は不透明でした。しかし、学習状況やフィードバック率がデータとして可視化することで、実施状況を把握しながら上司の関わりを促進し、全体の学習・育成を促進することができました。
新入社員研修や育成ならLDcubeにお任せ!

新入社員のオンボーディングは企業の成長に直結する重要なプロセスです。LDcubeは多角的なアプローチで効果的なオンボーディングの体制づくりを支援しています。
新入社員育成に関連する人たちとのミーティングを通じて、社内での「一人前」の定義を再確認する支援や、学習プラットフォームの導入支援を行います。そこから新入社員がキーワード検索で必要な情報を即時に学べるオンライン学習環境を整えます。
デジタルコンテンツや自発的に学べるツールの提供により、新入社員はいつでもどこでも効率的に学習を進めることが可能となり、早期に必要なスキルや知識を身に付けることができます。
それだけでなく、LDcubeは外部講師が実施する研修プログラムを自社内で効果的に活用できるように、社内トレーナーの養成の支援も行っています。社内トレーナーが質の高い研修を自ら実施できるようになることで、持続的かつ一貫した教育環境を整えることができます。
また、LDcubeは必要に応じて特定の研修やセミナーを実施することも可能です。新入社員のビジネスマナーやコミュニケーションスキルなどの分野については、LDcubeのスタッフが研修を行い、即戦力となるスキルを習得できるよう支援します。
新入社員のオンボーディングプロセスにはさまざまな工数がかかります。専任者をおいたとしてもやらなければならないことが多岐にわたります。LDcubeは専任者と共に、オンボーディングを効率化し、新入社員の定着率とパフォーマンスを向上させることに向けて伴走します。
▼その他、新入社員研修についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。
まとめ:新入社員が仕事を学べる環境をつくろう
新入社員が仕事できない原因と改善策とは?会社が取るべき実践的対処法を解説! について紹介してきました。
新入社員が仕事できないのは当たり前
新入社員が仕事できないと感じる時期がポイント
新入社員が仕事できないと感じる背景と現状
仕事ができないと感じる新入社員の特徴【意識面】
仕事ができないと感じる新入社員の特徴【スキル面】
新入社員が仕事できない根本的な原因
仕事ができる新入社員を育成のための処方箋
新入社員オンボーディングプログラムの事例
新入社員研修や育成ならLDcubeにお任せ!
新入社員が最初から即戦力ではないことは当然であり、これを理解した上で段階的な育成計画が求められます。
まず、新入社員の業務能力の不足は、多くの場合、職業訓練を受けていない職種に配属されることによるものです。これに対しては、基礎能力からの丁寧な教育が重要です。また、職業訓練を受けている職種でも、実際の職場で即戦力となるには時間が必要で、現場特有の慣習やシステムへの適応が求められます。
さらに、ビジネスマナーやコミュニケーションスキルなど、組織人としての基本行動を習得することもまた重要な課題です。新入社員はさまざまな時期に応じて成長を遂げますが、特に入社からの1年間は段階的なサポートが不可欠です。
これらの課題に対する解決策として、例えばOJTの強化、デジタル学習環境の整備、そして体系的な研修プログラムの導入が有効です。デジタル技術を活用し、自由な時間に学べる環境を構築することで、より自発的かつ効率的な学習が期待できます。また、管理職への育成意識向上の研修を実施することで、指導力やフィードバック能力を向上させ、育成責任をより強く意識してもらうことが重要です。
LDcubeはこうした育成環境の整備を支援し、企業が持続的な人材育成システムを構築できるよう伴走します。新入社員が一人前となるためのプロセスには、組織全体での協力と戦略的なアプローチが求められます。
LDcubeはデジタル学習環境の整備、グループ会社の株式会社ビジネスコンサルタントと連携した、複数の外部講師による品質のそろった集合研修、社内トレーナーの養成支援や教材提供、研修の効果を高めるため学習設計などトータルにご支援が可能です。無料での相談会なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼新入社員育成については下記にまとめました。こちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。