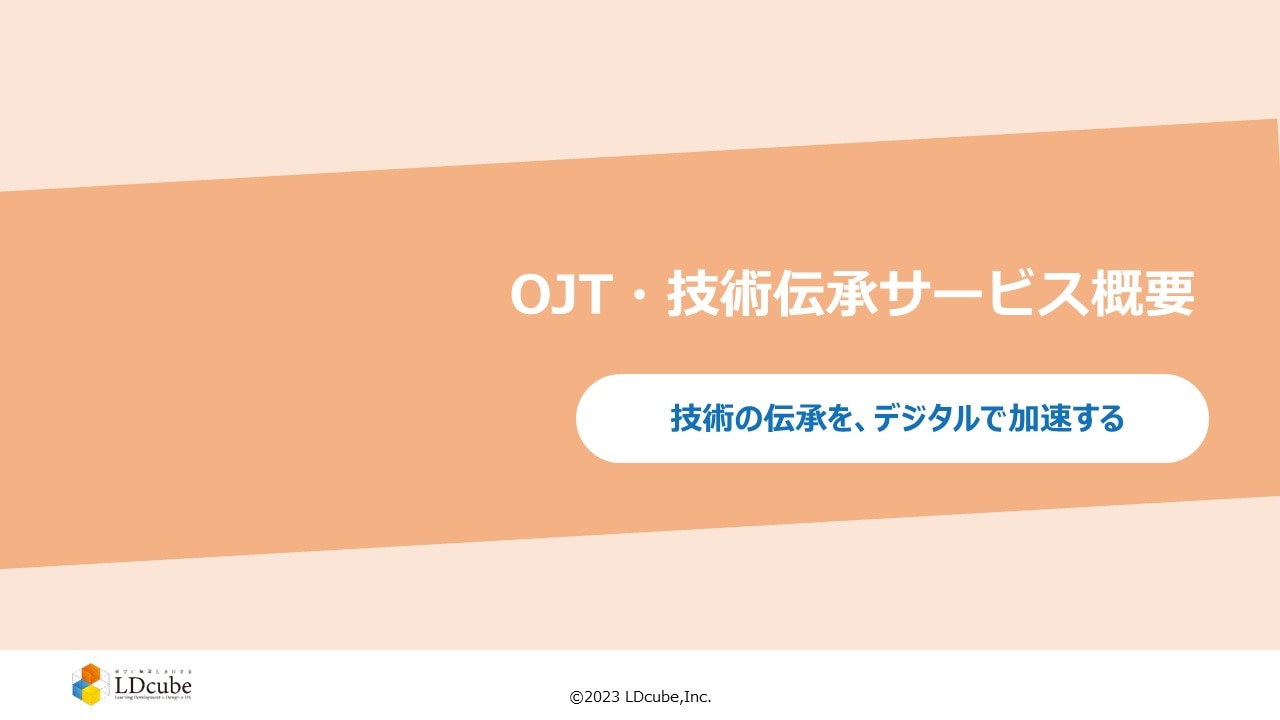学びのDXで実現する、人財育成の効率化と技術伝承
主な実績企業
関電プラント様 岐阜電力様 中日本高速道路様
西日本高速道路メンテナンス九州様
ネクスコ・エンジニアリング東北様
UMUで実現できるインフラ業界の人材育成(技術伝承のDX化)
| 1 |
手軽にマニュアル作成
画像+音声+手書き情報の業務マニュアルを簡単に作成・共有!
スマートフォンで撮影した動画をそのままアップロードすることも可能!


| 2 |
AIによる自動動画作成
ナレーション原稿入りのパワーポイントと話者の写真を読み込ませることで、AIがナレーションを読み上げた動画を作成!
コンテンツ作成の負荷軽減につなげます。
| 3 |
成長につながる学習設計
コンテンツ視聴だけで終わらせない!
学習の理解度を高めるインプット+アウトプットのラーニングデザインで成果につながる学習設計が可能!

技術教育のDX化により期待できる成果
OJTの格差をなくす!
教えるべきことは動画を使って学習の質を均一化。
人によって教えることが違うといった問題を解消。
コミュニケーションギャップをなくす!
分からないことはキーワードを検索。
基礎知識を得た上でやり取りすることで、コミュニケーションを円滑化。
「学んだことが生かされない」をなくす!
失われる技術をなくす!
ベテラン社員のスキル・ノウハウを動画としてマニュアルとすることで、会社の財産として蓄積。
インフラ業界でLDcubeのUMUが選ばれる理由
新入社員・若手社員のオンボーディング
インフラ業界では、安全管理の徹底や専門技術の習得など、入社初期から覚えるべき内容が多く、現場でのOJTだけでは教育が属人的になりやすいという課題があります。
LDcubeが提供するUMUを活用すれば、動画・テスト・実践フィードバックなどを一体化した学習設計が可能となり、座学と現場実践をつなぐ「効果的なオンボーディング環境」を構築できます。
熟練技術者のノウハウ伝承
インフラ業界では、ベテラン技術者が持つ熟練の勘や現場対応力など、マニュアル化しづらい暗黙知が多く存在します。
LDcubeが提供するUMUを活用することで、熟練者の実演動画や音声解説をそのまま教育コンテンツ化し、若手社員が「いつでも・どこでも」学べる環境を整えることができます。
手厚いサポート
インフラ業界では、教育担当者が本業と育成を兼務するケースが多く、研修設計や運用の負担が大きくなりがちです。
LDcubeでは、UMU導入後の設計・運用・改善まで一貫して伴走支援を行うため、教育担当者が安心してデジタル育成を推進できます。
効果測定と改善
インフラ業界では、研修効果が「どの程度現場力の向上につながっているか」を可視化しづらいという課題があります。
LDcubeが提供するUMUは、受講データ・発言内容・理解度テストなどを自動で分析し、学習成果を数値で見える化します。
お客様の声

現場から人を抜かなくても教育が可能になった/関電プラント株式会社
集合研修の見直しを行い、作業責任者の早期育成を目指しUMUを導入しました。教育科目も多く、研修の度に各現場から対象者を研修センターに集めるのは大変でしたが、UMU導入後は、隙間時間で学習ができることや受講生の理解に合わせて学習が進められることが社内でも評価を受けました。現在では原子力事業本部全体でUMUの学習を促進すべく、鋭意取り組み中です。
組織力・人材力の向上を効率的・効果的に実現/岐阜電力株式会社
売上の急成長に伴い、今後の組織拡大を見据えた組織力・人材力の向上が課題でした。他社よりも少ないヘッドカウントで市場で勝つための人財育成を強化するためにUMUを活用。トップメッセージや研修の振り返りコンテンツ、スキルアップのためのeラーニング配信で電気を通して岐阜県をもっと豊かにする人材育成に取り組んでいます。
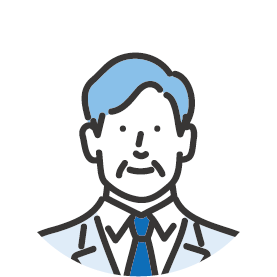

ベテラン社員の経験と技能を可視化/西日本高速道路メンテナンス九州株式会社
スマホでいつでもどこでもコンテンツが確認できる学習プラットフォーム「UMU」の導入により、ベテラン社員が長年培ってきた経験と技能(ノウハウ・暗黙知・コツ)を「見える化」し、若手社員が効率よく習得・伝承できるツールとして活用しています。
お役立ち資料
10分でまるごと理解!「技術伝承」資料ダウンロード
技術伝承とは、熟練技術やスキルの引き継ぎを行うことです。技術伝承は単に自社内だけの問題ではなく、サプライチェーン全体で国際的な競争力を持つためにも、早急に対応すべき事案と言えます。時間がかかるからと後回しにすればするほど、業界全体の停滞にも繋がってしまうリスクをはらんでいるのです。そこでこの本書では、技術伝承におけるボトルネックを明らかにし、スムーズな技術伝承に必要な解決策をお伝えします。
OJT・技術伝承サービス概要資料ダウンロード
現代の日本企業においては、年代別構成の歪みもあり、「ベテラン社員のノウハウを若手に引き継ぐこと(技術伝承)」「先輩社員が現場で効果的に若手を育成すること(OJT)」が、持続的な成長に不可欠です。 本書ではLDcubeとして提供するOJT・技術伝承の課題解決を目指す3STEPのデザインをご案内いたします。
10分でまるごと理解!「オンボーディングプログラム」資料ダウンロード
オンボーディングプログラムとは、新たに企業や組織に加わった人材を仕事や環境に慣れさせ、いち早く戦力化するための取り組みのことを指します。新入社員の定着率向上や早期戦力化などが期待できることから、企業で取り入れられています。本書では、企業の将来の成長を担う若手・若年層に効果的なオンボーディングプログラムの概要やメリット、企画から実施までの流れに加え、企業における実践事例までご紹介します。
Q & A
よくあるご質問
Q.
新人が現場の雰囲気に馴染めず、早期離職してしまいます。どう対応すればよいですか?
A.
初期の3か月間は「作業を教える前にチームに慣れさせる」期間と捉え、メンター制度や定期面談で心理的安全性を確保すると効果的です。
Q.
新人が安全管理の重要性を実感できていません。教育方法に工夫はありますか?
A.
危険体験VRや過去のヒヤリ・ハット事例を教材化し、「なぜルールが必要か」を体感的に学ばせると理解が深まります。
安全管理を怠るとどのようなリスクがあるかを理解することが重要です。
Q.
技術やノウハウがベテランの経験に依存しています。どのように可視化すればよいですか?
A.
熟練者へのヒアリングをもとに「作業判断のポイント」を動画・写真付きで整理し、技術データベース化すると継承が進みます。
データベース化する際には、利用しやすいインターフェースや操作性のあるプラットフォームを活用するなど、そのデータベースが活用されるように工夫することも重要です。
Q.
OJTが人によって教え方がバラバラです。どう標準化すればよいですか?
A.
現場教育の流れをステップ化した「OJTチェックリスト」を作成し、誰が教えても同じ品質で育てられるようにすることがポイントです。
Q.
若手が「自分の成長を実感できない」と感じています。改善策はありますか?
A.
習得したスキルを「見える化」するスキルマップを導入し、上司との面談で定期的に振り返るとモチベーションが上がります。
Q.
ベテランが忙しくて新人指導に時間を割けません。どうすればいいですか?
A.
教育を「個人の善意」ではなく「業務の一部」と位置づけ、指導時間を勤務計画に組み込むことが必要です。
後輩指導や人材育成を評価に組み込むこともおすすめです。
Q.
現場で口頭伝達が多く、情報が属人的です。改善できますか?
A.
学習プラットフォームや社内LMSを活用し、作業手順や注意点をデジタルマニュアル化すると伝達ミスを防げます。
Q.
現場によって教える内容やレベルが違います。統一する方法はありますか?
A.
どの現場でも汎用的な基礎教育などは、デジタルコンテンツとして学習プラットフォーム上で学べるようにすることがおすすめです。そうすることで、誰もが同じ品質の学習をすることが可能になります。
Q.
技術継承に関して、若手が「覚えることが多すぎて大変」と言っています。
A.
いきなり全てを詰め込まず、現場ごとに「優先スキル」「次に学ぶスキル」を段階的に整理することで負担を軽減できます。
Q.
技術継承を体系的に進めたいのですが、何から始めればいいですか?
A.
まず「どの技術を残すべきか」を明確化し、対象者・媒体・スケジュールを定めた継承計画を策定します。
Q.
教育成果をどうやって測ればよいですか?
A.
教育の結果、どの程度「行動変容」が起きたのかを図ることが重要です。成果につなげるための「期待する行動」を取れるようにアクションプランを立て、それを実行するために研修後アンケートでのリマインドを促すことも重要です。
Q.
デジタルツールを使った教育に抵抗感がある社員もいます。どう浸透させればいいですか?
A.
「便利さ」よりも「現場が楽になる」使い方を実演して見せ、小さな成功体験を積ませることが重要です。
CASE
活用事例
Contact