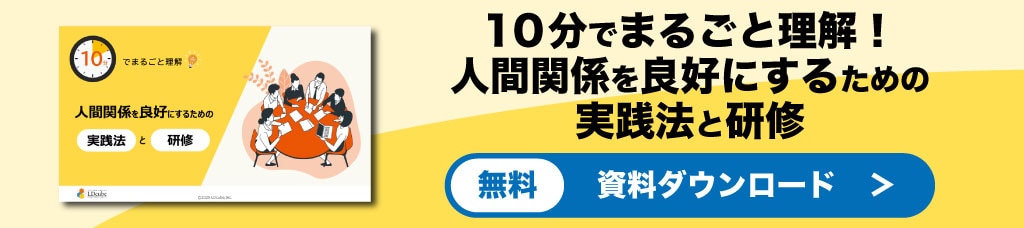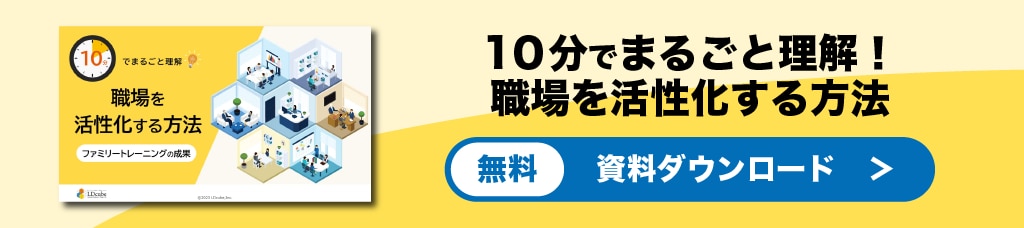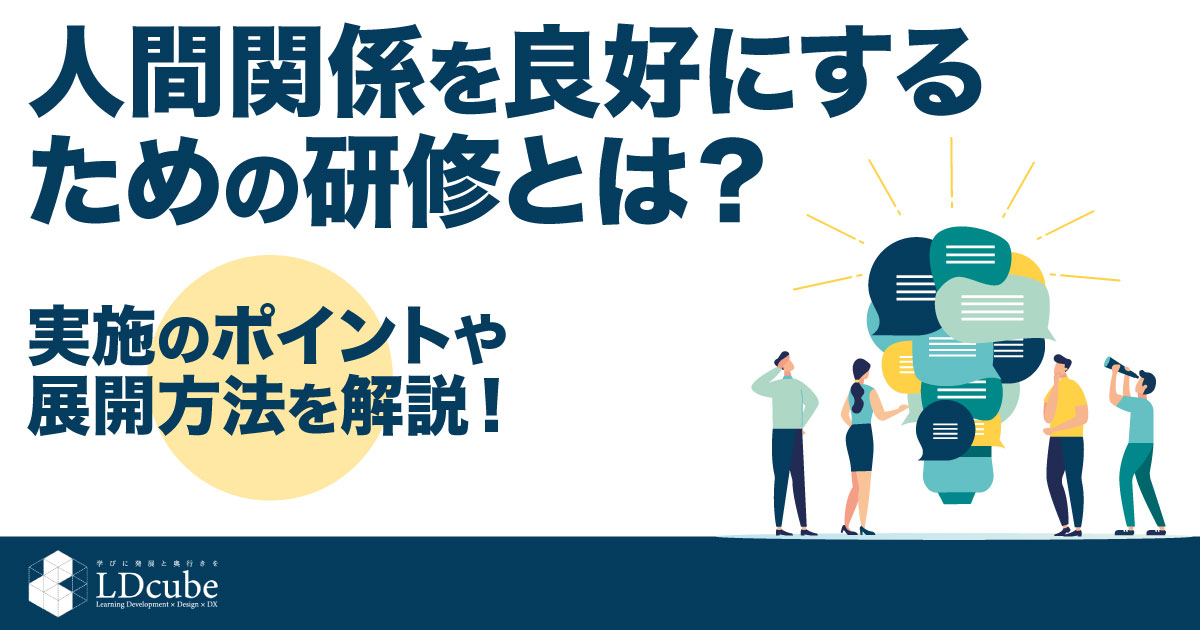
人間関係を良好にするための研修とは?実施のポイントや展開方法を解説!
職場の人間関係に悩む人は少なくありませんが、その背景には多様な価値観や職場文化の違いがあります。
職場の人間関係の悩みは単に個人の性格やスキルの問題にとどまらず、組織全体の風土やコミュニケーションの方法が影響していることも多いのです。こうした複雑な問題を解決するために研修は素晴らしい「きっかけ」となります。
研修は、普段の業務から一歩離れ、メンバー間の関係性を見直す貴重な機会です。
例えば、ある企業が実施した「コミュニケーション研修」では、自己診断ツールを活用し、参加者それぞれの行動スタイルや価値観を把握することから始めました。これにより、職場内での誤解や摩擦の原因が明確になり、新たな理解と気付きが生まれました。
しかし、研修のみで問題が全て解決されるわけではありません。研修はあくまで「第一歩」であり、参加者が自らの学びを職場で生かし続けることが重要です。
また、職場単位での研修実施は、全員が共通のフレームワークを学べるため、現場での実践がスムーズに行われるというメリットがあります。職場全体で学んだ内容を「共通言語」として活用することで、共同での問題解決や対話の質を飛躍的に高めることが可能です。
このように、研修は人間関係改善の「魔法の杖」ではありませんが、組織全体の人間関係を見直し、改善する強力なツールであることは間違いありません。
本記事では、職場の人間関係の改善を考えている人事の方々を対象に、職場単位での研修の進め方や活用すべき自己診断ツール、支援事例などについて解説します。
研修をきっかけに、職場の文化を変え、より良いコミュニケーション環境を構築していきましょう。
▼人間関係についてはテーマに応じて下記で詳しく解説しています。
▼人間関係を良好にするため実践法や研修については下記にまとめています。
目次[非表示]
研修は人間関係改善のきっかけにできる

研修は人間関係改善のきっかけにすることができます。ただし、魔法の杖ではないので、全ての問題を解決できるわけでもありません。ポイントを確認しておきましょう。
研修で人間関係の問題を全て解決できるわけではない
人間関係の問題は複雑で、研修だけで全てを解決することはできません。なぜなら、人間関係のトラブルは個人の価値観や感情、過去の経験、組織文化など多くの要因が絡み合っているからです。
研修はあくまで「気付き」や「学び」の場であり、根本的な解決には日常の実践や継続的な取り組みが不可欠です。
例えば、ある企業で実施したコミュニケーション研修では、参加者の多くが「相手に合わせたアプローチの大切さ」に気付きましたが、実際の職場での行動変容には時間がかかりました。研修後にフォローアップやチーム内での対話の場を設けることで、徐々に関係性が改善されていきました。
このように、研修は人間関係改善の「一助」にはなりますが、「万能薬」ではありません。過度な期待をせず、研修を起点にした継続的な取り組みが重要です。
研修は魔法の杖ではないがきっかけにできる
研修は人間関係を劇的に変える魔法の杖ではありませんが、変化のきっかけにはなり得ます。
その理由は、研修が普段の業務から一歩離れた「安全な学びの場」を提供し、参加者に新たな視点や気付きを与えることができるからです。特に、対話型や体験型の研修では、他者の考え方や感情に触れることが、関係性を見直すきっかけになります。
ある企業で実施した「相互理解」をテーマにしたワークショップでは、普段あまり話さない同僚同士が率直に語り合う機会が生まれ、「相手の意外な一面を知れた」「印象とは違った側面が見えた」といった声が多く聞かれました。
研修は人間関係の改善に向けた「第一歩」として非常に有効です。職場の空気を変えるには、まず一人一人の意識変容が必要であり、研修はそのきっかけとなるのです。
最良のやり方は職場単位での研修実施
人間関係改善を目的とした研修は、職場単位で実施するのが最も効果的です。
なぜなら、実際に日々関わるメンバー同士で学び合うことで、研修内容が現場での行動に直結しやすく、行動変容が促進されるからです。階層別研修のような研修では、受講者が学びを職場に持ち帰っても周囲の理解が得られず、実践が難しいケースが多く見られます。
例えば、ある製造業の現場チームで実施した「チームコミュニケーション研修」では、全員が共通のフレームワークを学んだことで、会話の質が向上し、ミスの報告や相談がしやすくなったという成果が出ました。
このように、職場単位での研修は「共通言語」を生み出し、チーム全体の関係性を底上げする効果があります。人間関係の改善を本気で目指すなら、組織ぐるみの取り組みが不可欠です。
人間関係を研修で改善するために必要な要素

人間関係を研修で改善するためには少なくとも3つの要素が必要です。ポイントを紹介します。
自己理解を深める
人間関係を改善するためには、まず自分自身を理解することが不可欠です。
なぜなら、自分の価値観や感情の傾向、コミュニケーションスタイルを知らなければ、他者との関係性において無意識の摩擦が生まれやすくなるからです。自己理解が深まることで、自分の反応や行動の背景を客観的に捉えられるようになり、冷静な対応が可能になります。
ある企業の研修で「行動特性診断」を用いた自己分析を行ったところ、参加者は「自分が迅速さを重視している」「相手は正確さを重視している」といった価値観の違いに気付きました。相手の価値観を理解することで、職場での対人対応が柔らかくなったという効果がありました。
自己理解は人間関係改善の第一歩です。研修を通じて自分を知ることが、他者との関係性を見直す土台になります。
▼自己理解を深める方法については下記で詳しく解説しています。
⇒自己理解を深める方法とは!5つの情報源について詳しく解説
他者理解を深める
人間関係を良好にするには、相手の立場や価値観を理解する力が必要です。
その理由は、他者の背景や価値観を知らずに接すると、誤解や偏見が生まれやすくなるからです。他者理解が進むことで、相手の言動の意図をくみ取る力が高まり、対話の質が向上します。
例えば、あるチーム向け研修で「他者理解ワークショップ」に取り組んだ結果、メンバー同士の会話が深まり、「相手の大切にしている価値観を理解できた」「自分と価値観が同じ人、違う人がいることが理解できた」といった反応が見られました。
他者理解は信頼関係の構築に直結します。研修を通じて相手の視点に立つ力を養うことが、人間関係改善の鍵となります。
▼他者理解については下記で詳しく解説しています。
⇒他者理解とは?その意味と必要な7つのこと─職場でできる施策も紹介
お互いの違いを認め合う
人間関係を改善するには、違いを否定するのではなく、認め合う姿勢が重要です。
なぜなら、人はそれぞれ異なる価値観や経験を持っており、その違いを受け入れることで、対立ではなく協働が生まれるからです。違いを認めることは、相手を尊重することにつながり、関係性の質を高めます。
ある企業で実施した「ダイバーシティ&インクルージョン研修」では、参加者が自分と異なる考え方や働き方を持つ人との対話を行いました。その結果、参加者が「違いは強みになる」という認識を持つようになり、チーム内の相互補完体制が強化されました。
違いを認め合うことは、職場の人間関係をより柔軟で建設的なものにします。研修はその気づきを促す場として非常に有効です。
人間関係の研修は職場単位が良い理由

人間関係を改善するための研修は職場単位が良いとされていますが、それにはちゃんとした理由があります。ここではその理由を解説します。
人間関係の悩みは職場に起因することが多い
人間関係の悩みの多くは、職場内の関係性に起因しています。
その理由は、職場では業務上の利害や役割、上下関係が絡み合い、日常的な接触頻度も高いため、摩擦が生じやすい環境だからです。個人の性格だけでなく、組織の文化やチームの雰囲気が人間関係に大きく影響します。
ある企業で実施した職場単位のコミュニケーション研修では、「上司の指示が曖昧でストレスを感じていた」「同僚との連携がうまくいかない」といった悩みが共有され、具体的な改善策をチームで話し合う機会が生まれました。
職場単位で研修を行うことで、実際の関係性に即した課題を扱うことができ、より実効性のある人間関係改善につながります。
▼職場での人間関係については下記で詳しく解説しています。
⇒職場の人間関係を改善する【お悩み別で選べる】おすすめの本18選
学ぶ場だけでなく、問題解決の場にできる
職場単位の研修は、単なる学びの場ではなく、実際の人間関係の問題を解決する場にもなります。
なぜなら、同じ職場のメンバーが一緒に参加することで、具体的な課題を共有し、対話を通じて解決策を探ることができるからです。研修が「気づき」だけで終わらず、「行動」につながる設計が可能になります。
ある営業部門で実施した研修では、「報連相がうまくいかない」「感情的なやり取りが多い」といった課題が明らかになり、具体的な改善方法をチームで考える時間を設け、具体的なガイドラインを設定しました。
結果として、研修後の業務連携がスムーズになったという報告がありました。
このように、職場単位の研修は、学びと実践をつなぐ「問題解決の場」として機能します。
お互いの違いを認め合う場にできる
職場単位の研修は、メンバー同士が違いを認め合う貴重な場になります。
その理由は、普段の業務では見えにくい価値観や考え方の違いを、研修という非日常の場で共有することで、相互理解が深まるからです。違いを受け入れることで、関係性が柔軟になり、対立ではなく協力が生まれます。
ある製造現場で実施した「コミュニケーション研修」では、行動特性診断を通じて「自分は慎重派」「相手は楽観派」といった違いを認識し、「相手の行動にイライラしていた理由が分かった」といった声が多く聞かれました。
このように、職場単位の研修は、違いを認め合う文化を育むきっかけになります。人間関係の質を高めるには、まず「違いを知ること」が重要です。
研修後から関わり方を変えられる
職場単位で研修を行うと、研修後すぐに関わり方を変えることができます。
なぜなら、同じ職場のメンバーが共通の学びを得ることで、行動変容のハードルが下がり、実践への移行がスムーズになるからです。個人で学んでも、周囲が変わらなければ行動は定着しづらいですが、職場全体で学べば「変わる空気」が生まれます。
あるIT企業で実施した「フィードバック研修」では、研修後に「フィードバックを日常的に取り入れよう」という共通認識が生まれ、上司・部下間のコミュニケーションが活性化しました。数週間後には、コミュニケーションの質が向上したという報告もありました。
職場単位の研修は、学びをすぐに現場で生かせる環境を整えることができます。人間関係の改善には、学びと実践の連動が不可欠です。
▼職場単位で研修を実施することについては下記で詳しく解説しています。
⇒職場コミュニケーション研修のカギは「職場単位」|効果的に進めるポイントを解説!
人間関係の研修には自己診断ツールを活用しよう

人間関係をテーマにした研修には自己診断ツールの活用が効果的です。人間関係はテーマが広く、ぼんやりとした研修になりがちですが、自己診断ツールを活用することで、具体的で焦点を絞った研修にすることができます。
自己理解と他者理解がしやすくなる
人間関係の研修に自己診断ツールを取り入れることで、自己理解と他者理解が格段にしやすくなります。
その理由は、診断結果を通じて自分の価値観や行動パターンを客観的に把握できるだけでなく、他者との違いも明確になるからです。これにより、無意識のすれ違いや誤解を防ぎ、より良い関係性の構築が可能になります。
例えば、LIFOやMBTI、DiSCなどの診断ツールを活用した研修では、「自分は感情より論理を重視するタイプ」「相手は協調性を大切にするタイプ」といった違いが可視化され、参加者同士の理解が深まりました。結果として、コミュニケーションの質が向上し、職場内の対話がスムーズになったという事例がたくさんあります。
自己診断ツールは人間関係の改善に向けた「気付き」を促す強力なサポートツールです。研修に取り入れることで、学びの深さと実践へのつながりが大きく変わります。
共有することで共通言語にできる
自己診断ツールの結果を職場内で共有することで、共通言語が生まれ、人間関係の改善が加速します。
なぜなら、診断結果をもとにした考え方やそれぞれの価値観が共通認識となり、コミュニケーションのズレを減らすことができるからです。共通言語があることで、相手の行動や反応を理解しやすくなり、対話が建設的になります。
例えば、LIFO診断を活用した研修では、「あの人はCTスタイルだから決断が早い」「私はCHスタイルだから慎重に進めたい」といった言葉が職場内で使われるようになり、相互理解が進みました。これにより、衝突が減り、協力しやすい雰囲気が生まれたという報告もあります。
このように、自己診断ツールは単なる個人の分析にとどまらず、職場全体の関係性を整える「共通言語」として機能します。研修での活用は、組織文化の改善にもつながる有効な手段です。
▼自己診断ツールについては下記で詳しく解説しています。
⇒行動特性診断で自己理解・分析を促す! 性格分析ツールとの違いも解説!
人間関係の研修ならLIFO®がおすすめ!

人間関係の研修なら自己診断ツールLIFO(Life Orientations)を活用した職場単位でのワークショップがおすすめです。
なぜなら、LIFOプログラムは心理学や行動科学をベースにして組み立てられた行動特性診断をベースに、職場単位でワークショップを行うためのワークブックなどのツールも体系的にそろえられているからです。
また、体系立てられたツールの使い方を社内トレーナーの方々にライセンス提供もされており、社内トレーナーの方々が職場単位でワークショップを展開していくことも可能です。下記に概要を紹介します。
■ 自己診断ツールLIFOとは
LIFO(Life Orientations)は、個人の行動スタイルを診断する自己診断ツールです。このツールは、自分の強みや行動パターンを理解するために役立ちます。
LIFOは4つの基本スタイルに基づいており、これらのスタイルはそれぞれ異なる行動特性や価値観を持っています。
自分がどのスタイルに属しているかを知ることで、より良いコミュニケーション方法やストレス時の行動傾向を把握することができます。
■ LIFOを活用したコミュニケーション研修
LIFOを活用したコミュニケーション研修では、まず参加者が自己診断を行い、自分の行動スタイルを理解します。
この診断結果をもとに、どのようにして他者と効果的にコミュニケーションをとるかを学びます。
研修では以下のような内容が含まれます。
|
■ LIFO®プログラムは社内トレーナーで展開可能
LIFO®プログラムは、これまでの活用実績と実用性から、企業内でのトレーニングにおいて自信を持っておすすめできるプログラムです。
社内展開にあたっては、特定の準備と手続きを経ることで、コストを抑えながら、外部講師に委託したかのように、社内トレーナーによる効果的なプログラムを展開することが可能です。以下に、その流れを詳しく説明します。
|
LIFOを活用して社内トレーナーが人間関係の研修を展開している事例

■ 背景・課題:
リコージャパン株式会社では、2010年の販売会社統合以降、各支社の固有の課題に対応できず、教育施策が本部主導で一方的になるなどの課題がありました。
また、コロナ禍以降、会食などの機会が減ったことにより、コミュニケーションの希薄化を招いていました。これらの課題を解決するために、社員自らが強みや弱みを理解し合い、横のつながりを強化する取り組みが求められていました。
■ LIFOプログラム(社内トレーナーライセンス)の導入:
その中で、LIFO(Life Orientations)を導入しました。LIFOの活用を通じて、社員一人一人の個性を診断し、自己理解と他者理解を促進しました。
これにより、非公式なコミュニケーションが減少する中でも、社員同士の相互理解を深めるための新たな手段を提供することができるようになりました。
また、LIFOプログラムライセンスを取得することで、社内トレーナーが自主的に研修を行えるようになり、組織風土改革を進めました。
LDcubeとの協力により、多様なワークショップを展開し、各支社・部門が抱える具体的な課題に対応できるようになりました。
■ 社内展開:
プログラムの展開においては、事前のLIFO診断、ワークショップの実施、職場での実践、効果検証のサイクルを組み込みました。
参加者は、研修後の職場実践を通じて得られたスキルを評価し合い、PDCAサイクルを回すことで、持続的なスキルアップを図っています。
ラーニングプラットフォーム「UMU」を活用し、受講者同士が学び合う環境も整備しました。
■ 社内トレーナーによる研修実施後の反応:
導入後、プログラム受講者の満足度は高く、多くの支社で「対人関係」や「マネジメント能力」などにおいて数値的な改善が見られました。
LIFOを活用したレクチャーは「人」の問題の解決に寄与し、特にアウトプット重視の体験学習が効果的でした。
UMUの活用と一連の学習サイクルの設計により、事務局の負担軽減と学習効果の向上が実現しました。
■ 今後に向けて:
今後は、各支社や部門の課題に寄り添い、人材育成を継続的にサポートすることで、社員個々の自己成長と組織全体の活性化をさらに推進する予定です。
また、LIFO以外のライセンスプログラムも組み合わせ、人材育成のプログラムラインナップを増やしていきます。
これにより、組織内のさまざまな課題を解決し、全体の一体感を更に高められることを期待しています。
▼本事例はインタビュー記事の一部です。インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。
⇒リコージャパン株式会社様 ライセンスプログラム導入事例
まとめ:人間関係の改善のきっかけに研修を活用しよう
人間関係を良好にするための研修とは?実施のポイントや展開方法を解説! について紹介してきました。
研修は人間関係改善のきっかけにできる
人間関係を研修で改善するために必要な要素
人間関係の研修は職場単位が良い理由
人間関係の研修には自己診断ツールを活用しよう
自己診断ツールならLIFOがおすすめ
人間関係の研修を社内トレーナーが展開した事例
LIFOを活用して社内トレーナーが人間関係の研修を展開している事例
研修は人間関係の全ての問題を劇的に解決するものではありませんが、新たな視点や、学びを得る機会を提供する「気付きの場」として重要な役割を果たします。特に、職場単位での実施は、学んだことが実際の行動に直結しやすく、職場全体で共通言語を生み出すことで、関係性の質を大きく向上させます。
人間関係の改善には自己理解と他者理解の深化が不可欠であり、この両方を研修で促進するためには、自己診断ツールの活用が効果的です。ツールを使うことで、参加者は自分自身の行動パターンや価値観を客観的に把握し、それを基に他者との違いを理解できるようになります。結果として、誤解や偏見を減らし、より良質な対話を可能にします。
具体的な方法として、LIFO ®(Life Orientations)などの科学的に構成されたツールを紹介しました。LIFO ®プログラムは、職場単位でのワークショップを通じて、組織全体のコミュニケーションレベルを上げ、相互理解を促進する強力な手段としておすすめです。また、社内トレーナーによる自主的な展開も可能であり、持続的な組織文化の改善につながります。
研修を単なる「イベント」ではなく、日々の実践と改善につながる「プロセス」として位置づけることで、人間関係を根本から改善し、組織全体のパフォーマンス向上に寄与することが期待できます。
株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成などサービスとして提供しています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。