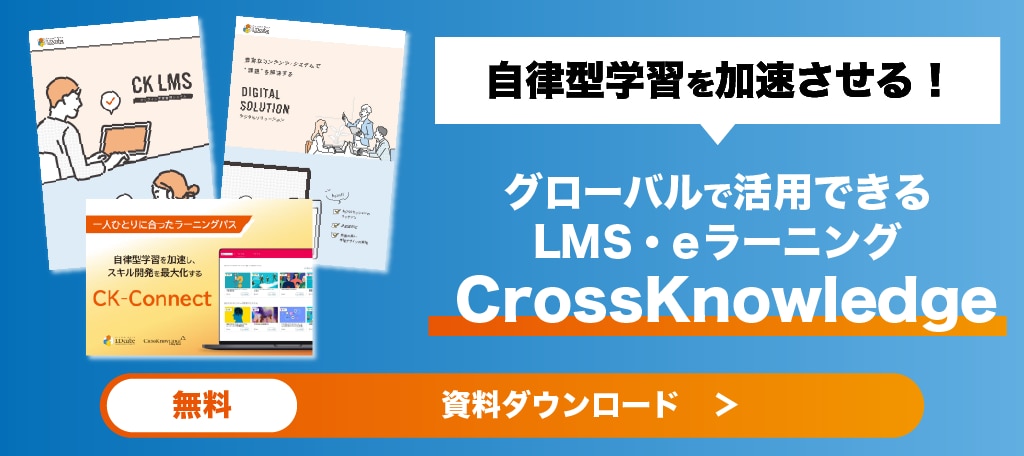学習プラットフォームで人材育成の効率を高めるには?おすすめ運用方法も解説!
近年、リモートワークの普及やDX推進の加速により、企業の人材育成において「学習プラットフォーム」が注目を集めています。従来の対面研修では限界があった時間や場所の制約を解決し、全社員に質の高い教育を効率的に提供できる画期的なソリューションとして、多くの企業が導入を検討しています。
しかし、「学習プラットフォームとは具体的にどのようなものなのか」「自社にとって最適なプラットフォームはどれか」「導入後に成果を上げるにはどうすれば良いか」といった疑問を抱える人事・教育担当者も少なくありません。
本記事では、人材育成のプロフェッショナルとして数多くの企業の教育変革を支援してきた経験を基に、学習プラットフォームの基本概念から選定のポイント、効果的な活用法まで、実践的なノウハウを体系的に解説します。
この記事を読むことで、あなたの組織に最適な学習プラットフォームを選択し、人材育成を成功に導くための具体的な道筋が見えてくるでしょう。
▼LMSについてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。
- 経営の勉強にアプリを活用しよう|おすすめ2選を紹介!
▼LMS選定ポイントについては下記にまとめています。
目次[非表示]
- 1.学習プラットフォームで人材育成の効率を高める
- 2.学習プラットフォームとは?機能や位置づけ
- 3.学習プラットフォームが注目される背景
- 4.学習プラットフォームの種類と特徴
- 4.1.コンテンツ提供メイン型
- 4.2.プラットフォームメイン型
- 4.3.ハイブリッド型
- 5.学習プラットフォームで実現できること
- 5.1.学習の利便性向上
- 5.2.パーソナライズ学習
- 5.3.学習者同士で学び合う
- 5.4.学習を行動変容につなげる細かなフォロー
- 6.学習プラットフォームの運用の工夫
- 6.1.集合研修と組み合わせて運用
- 6.2.オンライン研修と組み合わせて運用
- 6.3.OJTと組み合わせて運用
- 7.学習プラットフォーム活用の支援事例
- 8.まとめ:学習プラットフォームを活用しよう
学習プラットフォームで人材育成の効率を高める

現代の企業が直面する人材育成の課題は、従来の集合研修だけでは解決が困難になっています。
リモートワークの普及、多様な働き方の浸透、人手不足で教える人がいない問題、そして個人のスキルアップニーズの高まりにより、より柔軟で効果的な学習環境の構築が求められています。学習プラットフォームは、こうした課題を解決し、人材育成の効率を飛躍的に向上させる革新的なソリューションです。
デジタルコンテンツで学習効率が高まる
学習プラットフォームの最大の特徴は、デジタルコンテンツを活用することで学習効率を大幅に向上させることです。従来の紙ベースの教材や講師による一方的な講義とは異なり、動画コンテンツ、インタラクティブな教材、シミュレーション機能などを組み合わせることで、学習者の理解度を深めることができます。
また、一度作成したコンテンツは繰り返し利用でき、時間や場所を選ばずアクセス可能なため、学習機会の提供コストを大幅に削減できます。さらに、学習者は自分のペースで進めることができ、理解が不足している部分は何度でも復習できるため、個人の学習スタイルに合わせた最適な学習体験を実現します。
学習行動のデータ取得と分析
学習プラットフォームでは、学習者の行動データをリアルタイムで取得・分析することが可能です。どの教材をどの程度の時間視聴したか、どの部分で学習を中断したか、テストの正答率はどの程度かなど、詳細な学習行動を数値化して把握できます。これらのデータを分析することで、学習者一人一人の理解度や進捗状況を客観的に評価でき、必要に応じて個別指導やサポートを提供することができます。
また、組織全体の学習傾向や課題を可視化することで、研修プログラムの改善点を特定し、より効果的な人材育成戦略の策定が可能になります。
学習行動のデータ活用による再現性向上
収集した学習データを活用することで、成功パターンの再現性を高めることができます。高いパフォーマンスを発揮する従業員の学習行動パターンを分析し、そのノウハウを他の従業員にも展開することで、組織全体のスキルレベルの底上げが図れます。
また、学習効果の高いコンテンツや学習順序を特定し、最適な学習パスを設計することで、短期間でより高い学習効果を得られるようになります。これにより、人材育成の品質を標準化し、属人的な指導に依存しない持続可能な育成体制を構築できます。
学習プラットフォームとは?機能や位置づけ

学習プラットフォームとは、インターネットを通じて学習を行うためのデジタルシステムやサービスの総称です。企業や教育機関が学習プラットフォームを活用することで、従業員や学習者に対して体系的な教育プログラムを提供することができます。クラウドベースで動作するため、時間や場所の制約を受けることなく、多様な学習コンテンツにアクセスできることが最大の特徴です。
学習プラットフォームの基本的な機能
学習プラットフォームには、効果的な学習環境を構築するための多様な機能が搭載されています。主要な機能として、動画やテキストなどの学習コンテンツの配信機能、学習者の進捗状況を管理する受講者管理機能、理解度を測定するテスト・アンケート機能があります。
また、学習者同士がコミュニケーションを取れるディスカッション機能や、学習履歴を分析するレポート機能も重要な要素です。
基本的な機能:
|
これらの機能により、学習者は自分のペースで効率的に学習を進めることができ、管理者は組織全体の学習状況を把握しながら適切な指導やサポートを提供できます。
従来の研修との違いと人材育成における優位性
従来の集合研修と比較すると、学習プラットフォームには明確な優位性があります。最も大きな違いは、時間と場所の制約がないことです。集合研修では全員が同じ時間・場所に集まる必要がありましたが、学習プラットフォームでは各自が都合の良い時間に学習できます。
また、学習ペースも個人に合わせて調整でき、理解が不足している部分を繰り返し学習することが可能です。コスト面でも、会場費や講師料、交通費などの経費を大幅に削減できるため、企業にとって経済的なメリットは非常に大きいといえます。
さらに、学習データの蓄積により、個人の成長過程を客観的に評価でき、より効果的な人材育成戦略の立案が可能になります。
企業の人材育成戦略における学習プラットフォームの位置づけ
現代の企業経営において、学習プラットフォームは単なる研修ツールを超え、戦略的な意味を持ちます。デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進、リモートワークの定着、そして急速な技術革新への対応など、企業を取り巻く環境変化に対応するためには、継続的な学習文化の醸成が不可欠です。学習プラットフォームは、こうした変化に柔軟に対応できる人材を育成するための基盤として機能します。
また、グローバル展開している企業では、世界各地の従業員に統一された品質の教育を提供する手段としても重要な役割を果たしています。人材の多様化が進む中で、個人のキャリア目標や学習スタイルに合わせたパーソナライズされた学習体験を提供することで、従業員エンゲージメントの向上と人材の定着率向上にも寄与します。
学習プラットフォームが注目される背景

近年、学習プラットフォームが企業の人材育成において注目を集める背景には、社会情勢の大きな変化があります。新型コロナウイルス感染拡大をきっかけとした働き方の変化、経済環境の不確実性の高まり、そしてデジタル技術の急速な発展により、従来の人材育成手法では対応が困難な課題が顕在化しています。これらの変化や課題に適応するために、多くの企業が学習プラットフォームの導入を検討しています。
リモートワークの普及と学習ニーズの変化
リモートワークの急速な普及により、従業員の働き方が根本的に変化しました。国土交通省の調査によると、テレワークを継続したいと考える人が約87%に上り、その理由として時間の効率的な利用が最も多く挙げられています。この変化により、オンラインでの学習機会の提供が急務となりました。学習プラットフォームは、物理的な制約を受けることなく、自宅やサテライトオフィスなど、どこからでもアクセス可能な学習環境を提供します。
また、個人の生活スタイルや業務スケジュールに合わせて学習時間を調整できるため、ワークライフバランスを重視する現代の働き方にも適合しています。さらに、リモート環境では対面でのコミュニケーション機会が減少するため、デジタルツールを活用した学習者同士の交流や知識共有の仕組みがより重要になっています。
人材育成コストの課題と効率化の必要性
企業を取り巻く経済環境の不確実性が高まる中、人材育成にかかるコストの最適化は重要な経営課題となっています。従来の集合研修では、会場費、講師料、受講者の交通費、宿泊費、日当など多額の費用が発生します。これらのコストは、参加人数が少ない場合には1人当たりの研修単価が高額になるという課題もあります。学習プラットフォームの導入により、これらの短期的なコストを大幅に削減できるだけでなく、一度作成したコンテンツを繰り返し活用することで、中長期的な投資効果も期待できます。
また、学習効果の測定や分析が容易になることで、投資対効果の可視化も可能になり、より戦略的な人材育成投資の判断ができるようになります。
DX推進と従業員スキルアップの重要性
デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進は、多くの企業にとって生き残りをかけた重要な取り組みとなっています。DXを成功させるためには、従業員のデジタルリテラシーの向上や新しい技術への適応能力の育成が不可欠です。学習プラットフォームは、最新の技術動向やデジタルスキルに関する学習コンテンツを迅速に提供できるため、変化の激しいデジタル時代に対応した人材育成が可能です。
また、AIやデータ分析などの専門性の高い分野においても、段階的な学習プログラムを通じて従業員のスキルアップを支援できます。さらに、学習プラットフォーム自体がデジタル技術を活用したツールであるため、その利用を通じて従業員のデジタル活用能力の向上も期待できるという相乗効果があります。
学習プラットフォームの種類と特徴

学習プラットフォームは、提供するサービスの内容や特徴によって大きく3つのタイプに分類できます。それぞれに異なる強みと適用場面があるため、企業の人材育成の目的や規模、予算などを考慮して最適なタイプを選択することが重要です。各タイプの特徴を理解することで、自社のニーズに最も適した学習プラットフォームを見つけることができます。
コンテンツ提供メイン型
コンテンツ提供メイン型は、豊富な学習コンテンツの提供に重点を置いた学習プラットフォームです。数百から数千の講座が用意されており、ビジネススキル、技術系スキル、資格取得など幅広い分野をカバーしています。
このタイプの最大の特徴は、すでに完成度の高いコンテンツが豊富にそろっており、企業は短期間で多様な研修プログラムを従業員に提供できます。また、専門的な講師によって制作されたコンテンツが多く、品質が保証されているのも大きなメリットです。
|
このタイプは、多様なスキルアップニーズがある大企業や、独自コンテンツの制作リソースが限られている中小企業にも適しています。特に、幅広い職種の従業員に対して一般的なビジネススキルを習得させたい場合には非常に有効です。
プラットフォームメイン型
プラットフォームメイン型は、企業が独自の学習コンテンツを作成・管理するための機能に特化したタイプです。コンテンツ管理システム、受講者管理機能、学習分析機能など、学習環境を構築・運営するためのツールが充実しています。
企業は自社固有の業務知識や社内ルール、独自のノウハウなどを学習コンテンツとして体系化し、従業員に提供できます。このタイプの強みは、企業の個別ニーズに完全に対応できる柔軟性と、社内の暗黙知を形式知として蓄積・共有できることです。
|
特に製造業や専門サービス業など、業界固有の知識やスキルが重要な企業、または企業秘密や独自技術の教育が必要な組織に適しています。
ハイブリッド型
ハイブリッド型は、既製のコンテンツ提供と独自コンテンツ作成機能の両方を併せ持つプラットフォームです。基本的なビジネススキルやマネジメントスキルなどは豊富なライブラリから選択し、企業固有の業務知識や社内規則については独自コンテンツとして作成できます。このタイプにより、企業は限られたリソースで効率的に包括的な学習環境を構築できます。
また、外部コンテンツと内部コンテンツを組み合わせることで、体系的で一貫性のある学習プログラムの設計が可能になります。
|
このタイプは、一定規模以上の企業で、基本的なスキル教育と専門的な業務教育の両方が必要な組織に最適です。段階的にプラットフォームの機能を拡張していきたい企業にもおすすめできます。
学習プラットフォームで実現できること

学習プラットフォームの導入により、従来の研修では実現が困難だった多様な学習体験の提供と効果的な人材育成が可能になります。時間や場所の制約を超えた学習環境の提供から、個人の特性に合わせた学習体験のカスタマイズ、そして学習成果の実務への確実な定着まで、包括的な学習支援を実現できます。これらの機能により、企業は従業員一人一人の成長を促進し、組織全体のパフォーマンス向上を図ることができます。
学習の利便性向上
学習プラットフォームの最も直接的な効果は、学習の利便性を大幅に向上させることです。従業員は自分の都合に合わせて、いつでもどこでも学習にアクセスできるようになります。通勤時間、昼休み、業務の合間など、これまで活用できなかった時間を有効な学習時間として活用できます。
また、スマートフォンやタブレットからもアクセス可能なため、場所を選ばず学習を継続できます。動画コンテンツでは再生速度の調整や一時停止、巻き戻しが自由にでき、理解度に応じて学習ペースを調整できます。
さらに、学習履歴や進捗状況が自動的に保存されるため、中断した箇所から再開でき、長期的な学習計画の管理も容易になります。この利便性により、より多くの従業員が積極的に学習に取り組むようになり、学習への参加率と継続率が大幅に向上します。
パーソナライズ学習
学習プラットフォームでは、従業員一人一人の学習履歴や理解度に基づいて、個別最適化された学習体験を提供できます。パーソナルサーベイを活用した分析により、個人の強みと弱みを特定し、必要なスキルや知識に重点を置いた学習パスを自動生成できます。また、上司から推奨コンテンツをアサインすることも可能です。
|
学習者同士で学び合う
学習プラットフォームは、従業員同士が知識を共有し、互いに学び合う環境を提供します。ディスカッション機能やチャット機能により、学習内容について質問や意見交換ができ、より深い理解を促進できます。同僚からの実体験に基づくアドバイスや、異なる部署からの意見は、座学だけでは得られない貴重な学習機会となります。
また、グループ学習機能を活用することで、チーム単位での課題解決やプロジェクト学習も可能になります。学習成果の共有機能により、優秀な学習者の取り組みを他の従業員が参考にできる環境も構築できます。このような協働学習により、組織全体の知識レベルの底上げと、学習に対するモチベーションの向上が期待できます。
学習を行動変容につなげる細かなフォロー
学習プラットフォームの真の価値は、学習内容を実際の業務における行動変容につなげることです。学習完了後のフォローアップ機能により、学んだ内容を実務でどのように活用しているかを定期的に確認し、必要に応じて追加指導やサポートを提供できます。マイクロラーニングの手法を用いて、学習内容を小さな単位に分割し、学習しやすいコンテンツとして提示することが可能となり、知識の定着と行動への転換を促進できます。
また、学習成果の測定機能により、スキルの向上度合いを客観的に評価し、さらなる学習計画の調整を行えます。上司や同僚からのフィードバック機能も活用し、学習者が実際の業務でどの程度成長したかを多角的に評価できる仕組みを構築できます。
学習プラットフォームの運用の工夫

学習プラットフォームの効果を最大化するためには、単独での活用よりも他の研修手法と組み合わせたブレンデッドラーニングの設計が重要です。従来の集合研修、オンライン研修、実務を通じた学習(OJT)それぞれの特徴と強みを理解し、学習プラットフォームと効果的に組み合わせることで、より包括的で実践的な人材育成プログラムを構築できます。各手法の最適な組み合わせにより、学習効果の向上と定着率の改善を実現できます。
集合研修と組み合わせて運用
学習プラットフォームと集合研修を組み合わせることで、両者の長所を生かした効果的な学習体験を提供できます。まず、集合研修前の事前学習として学習プラットフォームを活用し、基礎知識の習得や前提となる理論の理解を進めておきます。
これにより、集合研修当日は基礎的な説明に時間を割く必要がなくなり、より高度な内容や実践的な演習に集中できます。参加者全員が一定レベルの知識を持った状態で集合研修に臨むため、ディスカッションの質が向上し、より深い学びが期待できます。
集合研修中は、学習プラットフォームで学んだ理論を実際のケーススタディーやグループワークで応用し、知識の定着を図ります。講師はプラットフォームで理解度クイズなどを行いながら、受講者の理解度を確認することで、個別のフォローアップも可能です。
また、集合研修後のフォローアップとして、学習プラットフォーム上で復習コンテンツや応用課題を提供し、学習内容の定着と実務への転換を支援します。このような段階的なアプローチにより、限られた集合研修の時間を最大限に活用しながら、長期的な学習継続を促進できます。
さらに、集合研修での気付きや学習内容を学習プラットフォーム上で共有することで、参加できなかった従業員にも間接的に学習効果を波及させることができます。
オンライン研修と組み合わせて運用
オンライン研修と学習プラットフォームの組み合わせは、完全にデジタル化された学習環境を構築する効果的な手法です。リアルタイムで実施されるオンライン研修の前後に、学習プラットフォームを活用した自己学習を組み込むことで、より充実した学習体験を提供できます。事前学習では、オンライン研修で扱う内容の基礎知識を学習プラットフォームで習得し、研修当日は質疑応答やディスカッション、より高度な内容に時間を集中できます。
オンライン研修中は、チャット機能や画面共有を活用して、学習プラットフォーム上のコンテンツをリアルタイムで参照しながら進行できます。参加者は研修と並行して関連資料を確認でき、より深い理解を得られます。
また、研修中に理解が追いつかない部分があっても、後から学習プラットフォームで復習できるという安心感により、積極的な参加を促進できます。
研修後は、録画された内容を学習プラットフォーム上で保存し、参加できなかった従業員や復習したい従業員がいつでもアクセスできるようにします。さらに、研修で扱った内容の関連コンテンツや応用課題を学習プラットフォーム上で提供し、継続的な学習を支援します。
OJTと組み合わせて運用
OJTと学習プラットフォームの組み合わせは、理論と実践を効果的に結びつける最も実用的なアプローチです。OJTの開始前に、学習プラットフォームで業務に必要な基礎知識や手順を習得しておくことで、実際の業務指導がより効率的に進められます。指導者は基本的な説明に時間を割く必要がなくなり、より高度な技術や業務のコツ、応用的な内容に集中して指導できます。
OJT期間中は、学習プラットフォーム上でマイクロラーニングコンテンツを提供し、日々の業務で遭遇する具体的な課題や疑問に対する解決策を随時学習できるようにします。短時間で完了できるコンテンツを豊富に用意することで、忙しい業務の合間でも継続的に学習を進められます。
また、OJTで学んだ内容や気付きを学習プラットフォーム上で記録・共有する機能を活用し、個人の学習ログを蓄積するとともに、他の従業員の参考になる知識として組織全体で活用できます。
OJT完了後は、習得したスキルの定着度を測定するための評価コンテンツを学習プラットフォーム上で提供し、必要に応じて追加学習や上級コンテンツへの移行を支援します。継続的なスキルアップのための学習パスも提示し、従業員が自主的に成長を続けられる環境を整備します。
この組み合わせにより、OJTで得た実践的な知識と学習プラットフォームで体系化された理論知識が相乗効果を発揮し、より確実で深いスキル習得が可能になります。
学習プラットフォーム活用の支援事例
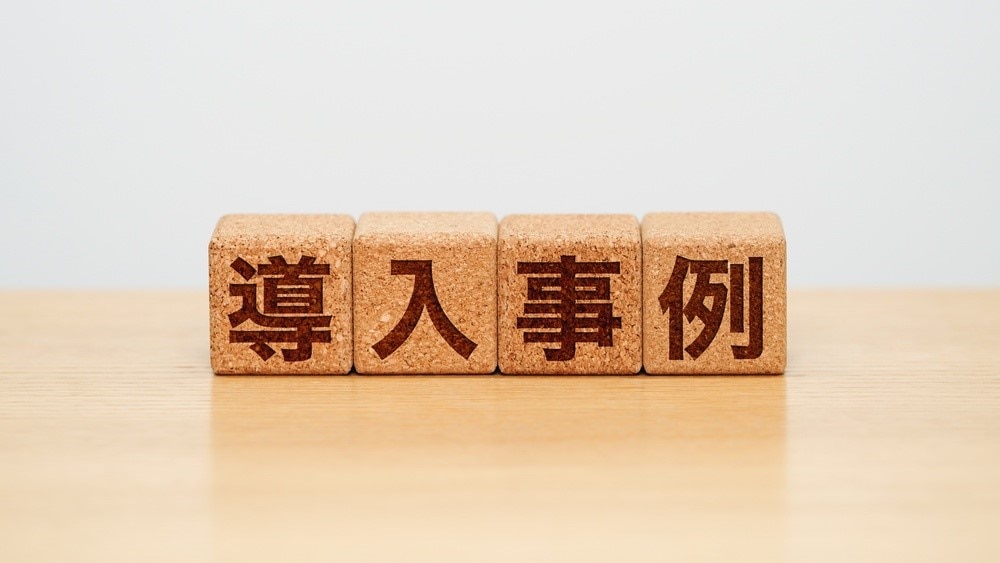
学習プラットフォームの活用を支援した支援事例を2つ紹介します。
パーソナライズ学習でeラーニング受講率100%を達成した事例(専門商社)

支援事例:専門商社(400名)
【これまでの課題】
eラーニングを「必修」にしなければ学習しない
流し見で「完了」することが目的になってしまっている
業務が忙しくて受講することを忘れてしまう ・・・など
【受講率100%を実現】
「必修」「受講期限」の設定がない中で、受講率100%を実現
診断結果を基に自動でリコメンドされるコースを自主的に受講
1人平均5.7コースの受講(多い人は16コースの受講)
今回のポイント
パーソナライズ学習:パーソナル診断結果を基にした個々人に合わせた学習コンテンツ自動配信
いつでも学べる環境:学習者が必要なときに必要な学習にアクセスできる環境
学習データの蓄積:学習者の学習状況をトラッキングするために学習行動のデータを取得
お客さまの声
- 社内ではeラーニングを導入しても、結局やってくれないのではないかという声が出ていました。
なぜなら、eラーニングを「必修」にしないと学習者が積極的に取り組まないといったことがあったからです。同じことを繰り返していても効果は上がらないと思っていましたが、パーソナライズ学習を取り入れたところ、受講率が100%になったので正直驚きました。
また、これまではコンテンツ数にも限りがあり、自社のオリジナルコンテンツの搭載ができなかったのですが、自社オリジナルコンテンツの搭載もできるようになったことで、学習してもらう幅が広がりました。
また、診断結果のレポートには、自身の強みや課題の啓発だけではなく、職場メンバーとの関係性の中で起こりうることや周囲が必要なことについてもアドバイスがあり、そのレポートを基に、他メンバーと対話することで、職場の中でのコミュニケーションが取りやすくなり、仕事がスムーズに進むようになりました。
デジタルとリアルを融合させた部下育成を行っている支援事例(住宅メーカー)
不動産営業の効果的なロープレ事例
デジタルOJTとリアルOJTの連動で業績向上へ【UMU導入事例】
社員数:3000名以上 事業:住宅メーカー
導入前の課題~環境変化に対応した教育を提供したい~
働き方改革など、時代や環境の変化に伴い、従来通りの詰め込み型教育では新入社員がなかなか育たないという課題を抱えていました。
この課題を解決するため、2018年に新入社員の教育方針を「全社の人材育成システムを確立し、共通認識の下、営業人材を長期的視点で組織的・計画的に育成する」というものに変更しました。
3年で一人前とする本計画の元、「研修は事前学習→集合研修→職場実践サイクルによる、OJTとの連動形式を取る」「計画的なロールプレーイングの実施で営業のスキル向上を図る」「個々の学習の進捗状況と習得度の把握」をしながら持続的学習を促進していくために、マイクロラーニングによるインプットとAIによるロープレ(ラーニングプラットフォーム:UMU(ユーム)の活用)の導入を決定しました。
取り組みの詳細
①マイクロラーニングによるインプットで本部・現場の負担減へ
現場のハイパフォーマー社員に依頼し、1人当たり2テーマの模範ロープレ動画を提供してもらい、その動画をプラットフォーム上に掲載しました。
動画学習+AIロープレ導入前は現場でのOJTの質にばらつきがあるという課題もありましたが、動画学習の導入を機に、学習の質を均一化することができ、今では入社1年目~3年目の必須コンテンツとなっています。
②研修後の確認テストで学びの定着を図る
研修の最後にまとめとして、受講生にはプラットフォーム上で確認テストに回答してもらうことで、研修の理解度を測るとともに、学習内容の定着化を図る取り組みをしました。
講師はリアルタイムで受講生たちの理解が浅いポイントが分かり、その場で解説や補足説明を行うことで、効率的な学習を実現できました。
③48のテーマに細分化したロープレの提供で営業スキル向上へ
一人前になるまでに必要な知識を48テーマに細分化し、それをロープレの課題として受講生に提示、順次プラットフォーム上に動画をアップロードしてもらうことで、営業スキルの向上を図っています。
1週間に1本ずつ、模範ロープレ動画を視聴した上で、自身のロープレ動画を提出してもらいます。上司から70点以上の評価を受けることができればテーマクリアという運用を実施することで、デジタルで体系的な学習をしながら、リアルでOJTを促進するという連動を図っています。
導入後の成果
①一人前として必要な知識を漏れなく学習
プラットフォーム導入前は、3年間営業活動をしていても、人によっては現場で遭遇しないテーマもありましたが、48テーマを計画的に展開していくことで、体系的に、漏れのない学習の提供が可能となりました。
②学習と上司からのフィードバック率と業績の相関が分かった
受講生が動画を提出すると、AIからのフィードバックを受けられるため、1人でも自分のロープレにおける啓発ポイントを確認しながら、何度もロープレの練習をすることが可能です。また、トークの中身についても上司からのフィードバックを受けることで、トークのブラッシュアップを図ることができます。
実際に受講生の学習や上司のフィードバック率のランキングデータを確認すると、上位者には好業績者の顔ぶれが並んでおり、学習と上司からのフィードバック率と業績が相関していることが分かりました。
これまで現場でのOJT実施状況は不透明でした。しかし、学習状況やフィードバック率がデータとして可視化することで、実施状況を把握しながら上司の関わりを促進し、全体の学習・育成を促進することができました。
まとめ:学習プラットフォームを活用しよう
学習プラットフォームで人材育成の効率を高める方法とは?おすすめの運用法も解説!について紹介してきました。
学習プラットフォームで人材育成の効率を高める
学習プラットフォームとは?
学習プラットフォームが注目される背景
学習プラットフォームの種類と特徴
学習プラットフォームで実現できること
学習プラットフォームの運用の工夫
学習プラットフォーム活用の支援事例
学習プラットフォームは、デジタル技術を活用して人材育成の効率性と効果性を飛躍的に向上させる重要なツールです。従来の研修方法の制約を解消し、個人に最適化された学習環境を提供することで、組織全体のスキルレベル向上を実現できます。
コンテンツ提供型、プラットフォーム型、ハイブリッド型から、自社のニーズに最適なものを選択し、集合研修やOJTとの組み合わせによってさらなる効果を期待できるでしょう。
変化の激しい現代のビジネス環境において、継続的な学習と成長を支援する学習プラットフォームの導入は、企業の競争力強化にとって不可欠な投資といえます。
株式会社LDcubeは、CrossKnowledgeの日本国内の公式パートナーとしてLMSやeラーニング・マイクロラーニングなどの提供などを行っています。また、UMUの公式パートナーとしてUMUの導入支援や運用支援も行っています。
また、学習プラットフォームの無料デモID発行やデモ体験会、活用事例・導入事例の紹介、料金の案内なども行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
▼関連記事はこちらから。