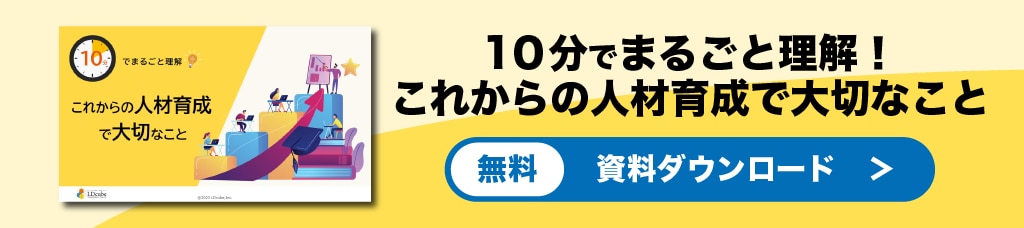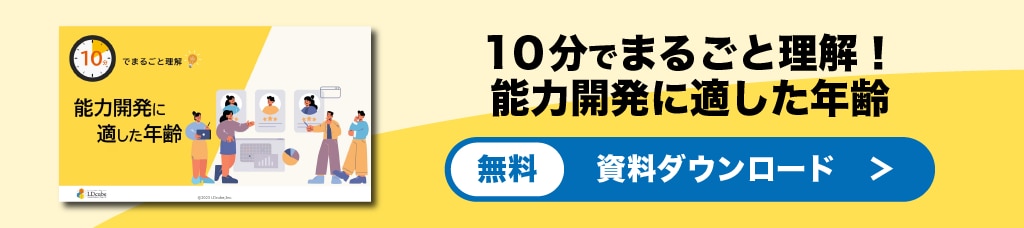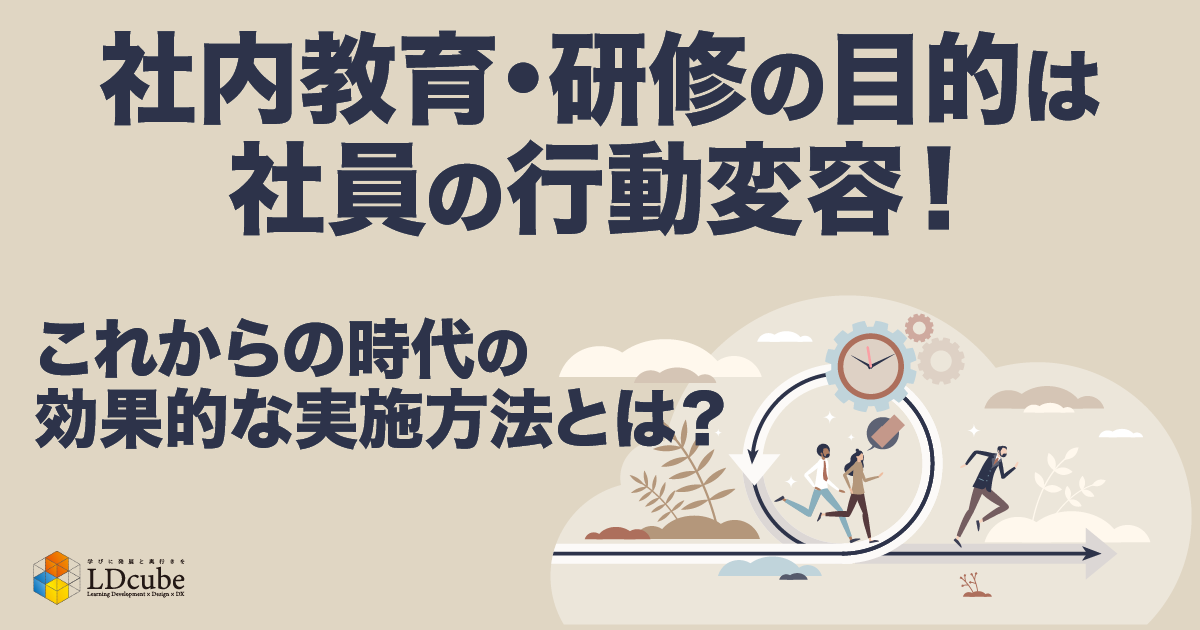
社内教育・研修の目的は社員の「行動変容」|効果的な実施方法とは?
人材不足が深刻化する現代において、企業の持続的成長を実現するためには「社内教育」が欠かせません。しかし、多くの企業が「どのように進めれば効果的なのか」「限られた予算と人員で成果を上げるには」といった課題を抱えています。
社内教育とは、単なる研修の実施ではありません。社員一人一人の能力向上を通じて組織全体の生産性を高め、企業の競争力強化につなげる戦略的な取り組みです。適切に実施すれば、社員のモチベーション向上、離職率の低下、そして業績アップという好循環を生み出すことができます。
本記事では、社内教育を担当することになった方や見直しを検討している方に向けて、効果的な進め方を5つのステップに分けて詳しく解説します。
基本的な考え方から具体的な実践方法、よくある課題の解決策まで、実際の現場で役立つノウハウを網羅的にお伝えします。この記事を読むことで、あなたの会社にとって最適な社内教育の仕組みを構築できるようになるはずです。
▼人材育成についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。
▼新入社員・若手社員・中堅社員向けのおすすめの研修は下記で紹介しています。
▼人材育成で大切なことについては下記にまとめています。こちらからダウンロードできます。
目次[非表示]
- 1.社内教育で業績を向上しよう
- 2.社内教育の目的と重要性
- 2.1.社内教育の目的①「行動変容」
- 2.2.社内教育の目的②「能力開発」
- 2.3.社内教育の目的③「自社らしさの情勢」
- 2.4.社内教育の目的④「持続可能な組織づくり」
- 2.5.社内教育の重要性
- 3.社内教育の具体的な実施方法
- 3.1.集合研修やオンライン研修
- 3.2.eラーニング
- 3.3.OJT(On-the-Job Training)
- 4.社内教育を実施するリソース
- 4.1.社内トレーナー
- 4.2.外部講師
- 4.3.自社作成のeラーニング
- 4.4.専門機関が提供するeラーニング
- 5.社内教育を成功させるポイント
- 5.1.社内教育にかける情熱を持つ
- 5.2.上司の巻き込み
- 5.3.業務につながるテーマ選定
- 5.4.インターバル型の学習デザイン
- 5.5.細かなフォローアップ
- 6.これからの社内教育はデジタル化
- 6.1.コンテンツをデジタル化
- 6.2.集合研修とオンライン研修を使い分ける
- 6.3.反転学習のデザイン
- 6.4.学習プラットフォームで運用
- 6.5.AIの活用
- 7.社内教育を効果的に展開している事例紹介
- 8.効果的な社内教育ならLDcube
- 9.まとめ:社内教育で組織を成長させよう
社内教育で業績を向上しよう

現代のビジネス環境において、企業の持続的成長を実現するために欠かせない取り組みの一つが社内教育です。多くの経営者や人事担当者が「社内教育は本当に業績向上につながるのか」という疑問を抱いているかもしれません。
しかし、適切に設計・実施された社内教育は、確実に組織の成長と業績向上に貢献します。社内教育への投資は、短期的にはコストとして見えるかもしれませんが、中長期的には企業の競争力を大きく左右する重要な戦略的投資なのです。
社内教育は間接的に業績向上に貢献する
社内教育が業績向上に与える影響は、直接的ではなく間接的なものです。従業員が新しい知識やスキルを習得することで、日々の業務効率が向上し、より質の高い成果を生み出せるようになります。
また、教育を通じて従業員のモチベーションが向上すると、自発的な改善提案や創意工夫が増え、組織全体のイノベーション創出力が高まります。さらに、社内教育を充実させることで従業員エンゲージメントが向上し、離職率の低下や優秀な人材の定着につながります。
これらの効果が複合的に作用することで、最終的に売上増加やコスト削減といった業績向上が実現されるのです。教育効果が業績に表れるまでには一定の時間が必要ですが、継続的に取り組むことで確実に組織の成長を支える基盤となります。
社内教育をしないとジリ貧になる
一方で、社内教育を軽視したり、実施しなかったりする企業は、徐々に競争力を失い、ジリ貧状態に陥るリスクが高まります。技術革新やビジネス環境の変化が激しい現代において、従業員のスキルが陳腐化すると、業務効率の低下や品質問題の発生につながります。
また、成長機会を提供されない従業員は、より良い環境を求めて他社に転職する可能性が高くなり、優秀な人材の流出が続くと組織の知識やノウハウが失われてしまいます。
さらに、教育に投資しない企業は、新しい技術やトレンドに対応できず、市場での競争力を維持することが困難になります。人材採用においても、成長環境が整っていない企業は求職者から敬遠され、採用コストの増大や人材不足の深刻化を招きます。
これらの悪循環が続くと、企業の持続的成長は困難となり、最終的には業績悪化や事業継続の危機に直面することになりかねません。
社内教育の目的と重要性

社内教育を効果的に実施するためには、まずその目的を明確にすることが重要です。
単に知識を伝達するだけでなく、組織の成長と従業員の発展を両立させる戦略的な取り組みとして位置づける必要があります。
社内教育の目的①「行動変容」
社内教育の最も重要な目的の一つは、従業員の「行動変容」を促すことです。単に知識を習得させるだけでは意味がなく、学んだ内容を実際の業務で活用し、行動や思考パターンを変化させることが求められます。
例えば、コミュニケーション研修を受講した管理職が、部下との接し方を実際に改善し、チーム運営の質を向上させることが行動変容の成果といえます。
効果的な行動変容を実現するためには、研修内容を日常業務と密接に関連付け、実践的な演習や体験型学習を取り入れることが重要です。
また、研修後のフォローアップや振り返りの機会を設けることで、新しい行動パターンの定着を支援し、持続的な変化を促進できます。
社内教育の目的②「能力開発」
従業員一人一人の能力開発は、社内教育の中核的な目的です。専門技術、ビジネススキル、ヒューマンスキルなど、多様な能力を体系的に向上させることで、個人のパフォーマンス向上と組織全体の競争力強化を同時に実現します。
特に現代では、デジタル技術の急速な発展により、継続的なスキルアップが不可欠となっています。能力開発を効果的に進めるためには、従業員の現在のスキルレベルを正確に把握し、個々のキャリア目標と組織のニーズを照らし合わせた個別化された教育プログラムを設計することが重要です。
また、能力開発の成果を適切に評価し、昇進や昇格の機会につなげることで、従業員のモチベーション向上と組織への貢献意識の醸成を図ることができます。
社内教育の目的③「自社らしさの情勢」
社内教育は、企業の理念やビジョン、価値観を従業員に浸透させ、「自社らしさ」を醸成する重要な役割を担っています。強い企業文化を持つ組織では、従業員が共通の価値観に基づいて行動するため、一貫性のあるサービス提供や意思決定が可能となります。
自社らしさの醸成には、創業の精神や企業の歴史、成功事例の共有、行動指針の具体的な解説などを含む教育プログラムが効果的です。また、管理職層が率先して企業文化を体現し、日常的なコミュニケーションを通じて価値観を伝えることも重要です。
自社らしさが浸透した組織では、従業員のエンゲージメントが向上し、ブランド価値の向上や顧客満足度の向上にもつながります。
社内教育の目的④「持続可能な組織づくり」
長期的な視点で組織の持続可能性を高めることも、社内教育の重要な目的です。変化の激しいビジネス環境において、組織が継続的に成長し続けるためには、従業員が自律的に学習し、適応できる能力を身に付ける必要があります。
持続可能な組織を構築するための教育では、問題解決能力、創造性、変化対応力などの汎用的なスキルの育成に重点を置きます。また、次世代のリーダーを育成するための後継者教育や、知識・ノウハウの継承システムの構築も重要な要素です。
さらに、学習する組織文化を醸成し、従業員が自発的に成長機会を求める環境を整備することで、外部環境の変化に柔軟に対応できる強靭な組織を築くことができます。
社内教育の重要性
現代における社内教育の重要性は、これまで以上に高まっています。人手不足が深刻化する中で、限られた人材で最大の成果を上げるためには、一人一人の生産性向上が不可欠です。
また、デジタル変革の波により、新たな業務の進め方が次々と生まれており、継続的な学習とスキルアップが競争力維持の鍵となっています。
働き方の多様化が進む中で、従業員が成長実感を得られる環境を提供することは、人材の定着と優秀な人材の獲得において重要な差別化要因となります。
さらに、ESG経営や人的資本経営への注目が高まる中、従業員への教育投資は企業価値向上の重要な指標として評価されています。
これらの背景から、社内教育は単なるコストではなく、企業の持続的成長を支える重要な投資として位置づけることが求められています。
▼人的資本経営については下記で詳しく解説しています。
⇒人的資本経営とは?企業の人材を“資産”に変える実践プロセスを事例付きで解説!
社内教育の具体的な実施方法

社内教育を効果的に実施するためには、目的や対象者に応じて適切な教育方法を選択することが重要です。
ここでは、多くの企業で活用されている代表的な教育方法について、その特徴と効果的な活用方法を詳しく解説します。
集合研修やオンライン研修
集合研修は、複数の従業員が同じ場所に集まって実施する教育方法で、講師との直接的なやり取りや参加者同士の交流が可能です。グループワークやディスカッションを通じて、多様な視点を共有し、学びを深める効果があります。
一方、オンライン研修は場所や時間の制約を受けにくく、遠隔地の従業員も参加しやすいというメリットがあります。録画機能を活用すれば、後から復習することも可能で、学習効果の向上が期待できます。
近年では、集合研修とオンライン研修の長所を組み合わせたハイブリッド型の研修も増えており、参加者の状況や研修内容に応じて柔軟に実施形態を選択できます。
そして、効果的な研修を実施するためには、事前の準備とフォローアップが重要で、参加者の理解度確認や行動変容の促進を継続的に行うことが必要です。
eラーニング
eラーニングは、インターネットを活用したデジタル学習システムで、従業員が自分のペースで学習を進められる教育方法です。動画コンテンツ、インタラクティブな教材、クイズ形式の確認テストなど、多様な形式で知識・スキル習得を支援します。
最大の特徴は、時間や場所を選ばずに学習できることで、忙しい業務の合間や通勤時間なども有効活用できます。また、学習進捗の管理が容易で、個人の理解度に応じた個別指導も可能です。
コスト面でも、一度コンテンツを制作すれば多くの従業員が繰り返し利用できるため、長期的には費用対効果が高い教育方法といえます。ただし、実践的なスキルや対人スキルの習得には限界があるため、他の教育方法と組み合わせて活用することが効果的です。
また、学習効果を高めるためには、定期的なコンテンツ更新と、学習者の進捗をサポートする仕組みが重要になります。
OJT(On-the-Job Training)
OJTは実際の業務を通じて行う教育方法で、実践的なスキルと知識を同時に習得できる最も効果的な人材育成手法の一つです。先輩社員や上司が指導者となり、日常業務の中で必要なスキルや知識を段階的に教えていきます。
OJTの基本的な流れは以下の4ステップで構成されます。
|
この方法により、学習者は理論と実践を結びつけながら理解を深めることができます。
OJTの成功には、指導者の質が大きく影響するため、指導者自身への教育やサポート体制の整備が重要です。また、計画的なOJT実施のために、到達目標の明確化、進捗管理、定期的な振り返りの機会を設けることが必要です。
OJTは即戦力育成に優れていますが、指導者の負担が大きくなりがちなため、適切な業務分担と指導時間の確保が課題となります。
OJTには、ばらつきが生じやすいという課題があるため、OJTで教える内容をデジタルコンテンツ化し、ばらつきの軽減を図っていくことも重要です。
▼OJTについては下記で詳しく解説しています。
⇒OJTとは?意味や目的、メリット、Z世代への適応まで全解説!
社内教育を実施するリソース

社内教育を成功させるためには、適切なリソースの選択と活用が重要です。企業の規模や予算、教育目標に応じて、最適なリソースを組み合わせることで、効果的な教育体制を構築できます。
社内トレーナー
社内トレーナーは、自社の従業員が講師役を担う教育リソースです。
最大のメリットは、自社の業務内容や企業文化を深く理解していることで、実務に即した実践的な教育を提供できることです。
また、受講者との距離が近く、質問しやすい環境を作れるため、学習効果の向上が期待できます。コスト面でも、外部講師を招聘するよりも大幅に費用を抑えられるため、限られた費用でも継続的な教育実施が可能です。
一方、社内トレーナーを活用する際の課題は、指導スキルの向上と教育時間の確保です。優秀な実務者であっても、教育スキルは別途習得する必要があるため、トレーナー向けの研修やサポート体制を整備することが重要です。
外部講師
外部講師は、専門分野における豊富な知識と経験を持つプロフェッショナルです。最新のトレンドや他社事例、専門的な技術などを提供できるため、社内では習得困難な高度な知識やスキルの教育に適しています。
また、第三者的な立場から客観的な視点や新鮮な刺激を提供できることも大きなメリットです。外部講師の活用には一定の費用がかかりますが、その分野における専門性の高さと教育経験の豊富さにより、短期間で効果的な学習成果を得ることが可能です。
外部講師を選定する際は、自社のニーズと講師の専門分野のマッチング、実績や評価の確認、費用対効果の検討が重要になります。また、事前の打ち合わせを十分に行い、自社の状況や課題を共有することで、より効果的な教育プログラムを実現できます。
自社作成のeラーニング
自社作成のeラーニングは、企業独自のノウハウや業務手順を体系化したデジタル教材です。自社の実情に完全に合わせた内容で構成できるため、実用性が高く、従業員にとって理解しやすい教育コンテンツを提供できます。
一度制作すれば、何度でも繰り返し利用でき、多くの従業員が同時に学習できるため、長期的には非常にコスト効率が良い教育リソースです。また、内容の更新や修正も自社で行えるため、業務変更や制度改定にも迅速に対応できます。
しかし、質の高いeラーニングコンテンツを制作するには、専門的な知識と技術、相当な時間と労力が必要です。動画撮影、編集、システム構築などの技術的な課題もあり、初期投資も必要になります。
制作リソースが限られている場合は、段階的な制作や外部制作会社との協力も検討する必要があります。
専門機関が提供するeラーニング
専門機関が提供するeラーニングサービスは、豊富な実績と専門知識に基づいて制作された高品質な教育コンテンツを利用できるリソースです。
多様な分野のプログラムが用意されており、企業のニーズに応じて選択できるため、導入のハードルが低く、導入後にすぐに教育を開始できます。
専門機関のeラーニングは、最新の教育手法や技術を取り入れており、学習効果を高める工夫が随所に施されています。
また、学習管理システムによる進捗管理や習得度の測定も容易で、教育効果の可視化が可能です。定期的なコンテンツ更新により、常に最新の情報で学習できることも大きなメリットです。
一方で、自社特有の業務内容や企業文化に完全にマッチしない場合があるため、社内教育や他の教育方法と組み合わせて活用することが効果的です。コスト面では利用人数や期間に応じた料金体系となっているため、利用計画の策定が重要になります。
▼社内トレーナーについては下記で詳しく解説しています。
⇒社内トレーナー導入における成功のコツとは?ポイントを解説!
社内教育を成功させるポイント

社内教育の効果を最大化するためには、単に研修を実施するだけでは不十分です。教育の企画段階から実施後のフォローアップまで、一貫した戦略と具体的なポイントを押さえることが成功の鍵となります。
多くの企業で実践されている効果的なアプローチを参考に、自社の状況に適した取り組みを実施することが重要です。
社内教育にかける情熱を持つ
社内教育を成功させる最も重要な要素は、組織全体、特に経営層と教育担当者の「情熱」です。経営者が人材育成の重要性を真に理解し、継続的な投資を決断することで、組織全体に教育の重要性が浸透します。
教育担当者も、単に業務の一部として取り組むのではなく、従業員の成長と組織の発展への貢献を使命として捉えることが必要です。情熱を持って取り組むことで、教育プログラムの質が向上し、参加者にもその熱意が伝わります。
また、困難な状況に直面した際も、その情熱が、諦めずに改善を続ける原動力となります。情熱を維持するためには、教育成果の可視化や成功事例の共有、教育担当者自身のスキルアップも重要です。
組織として教育への投資意義を明確にし、長期的な視点で人材育成に取り組む文化を醸成することが、持続的な成功につながります。
上司の巻き込み
社内教育の効果を高めるためには、受講者の直属の上司を積極的に巻き込むことが不可欠です。上司が教育の意義を理解し、部下の学習を支援する姿勢を示すことで、教育効果は大幅に向上します。
具体的には、研修前に上司が部下と面談し、学習目標を共有したり、研修中に学んだ内容を職場で実践する機会を意識的に提供したりすることが効果的です。
また、研修後のフォローアップでは、上司が部下の変化を観察し、適切なフィードバックを提供することで、学習内容の定着を促進できます。上司自身も教育プログラムに参加することで、部下指導のスキルを向上させ、組織全体の教育文化を醸成することができます。
ただし、上司の協力を得るためには、管理職向けの説明会や指導方法の研修を実施し、教育における上司の役割と重要性を明確に伝える必要があります。
業務につながるテーマ選定
社内教育を成功させるには、実際の業務と密接に関連したテーマの選定が重要です。受講者が「なぜこの教育を受ける必要があるのか」を明確に理解できるよう、現在の業務課題や将来のキャリア発展に直結する内容を選択することが求められます。
例えば、営業部門であれば顧客対応スキルや提案力向上、製造部門であれば品質管理や安全管理に関する教育が効果的です。テーマ選定の際は、事前に従業員へのアンケートや管理職へのヒアリングを実施し、現場のニーズを正確に把握することが重要です。
また、抽象的な概念だけでなく、具体的な事例やケーススタディーを用いることで、学習内容の実践イメージを明確にできます。業務との関連性が高い教育ほど、学習したことの実践度が向上し、学習効果も高まります。
定期的に教育ニーズの見直しを行い、組織の状況変化に応じてテーマを更新することも必要です。
インターバル型の学習デザイン
効果的な社内教育を実現するためには、一度の集中的な研修ではなく、インターバル型の学習デザインを採用することが重要です。
このアプローチでは、基礎的な知識習得から実践的なスキル向上まで、段階的に学習を進める設計を行います。
|
この設計により、学習者は知識を実際の業務で試行錯誤する機会を得られ、次の学習段階でより深い理解に到達できます。
また、忘却曲線に対抗する効果もあり、長期的な記憶定着にも役立ちます。インターバル学習を成功させるためには、各段階での明確な目標設定と、実践期間中の適切なサポート体制が必要です。
学習管理システムを活用した進捗管理や、メンター制度による個別支援なども効果的な手法として活用できます。
細かなフォローアップ
社内教育の真の成果は、研修終了後の行動変容にあります。そのため、継続的で細かなフォローアップが成功の鍵となります。
効果的なフォローアップには、定期的な面談やアンケート調査、学習成果の発表機会の提供などがあります。
|
各段階で学習内容の実践状況や課題を確認し、必要に応じて追加サポートを提供します。また、受講者同士の情報交換やベストプラクティスの共有を促進することで、相互学習の効果も期待できます。
フォローアップの際は、単に進捗を確認するだけでなく、実践における困難や疑問に対して具体的な解決策を提示することが重要です。
さらに、フォローアップを通じて得られた情報を次回の教育プログラム改善に活用することで、継続的な質の向上を図ることができます。
組織として学習文化を醸成し、従業員が自発的に成長を続ける環境を整備することが、長期的な教育効果の実現につながります。
▼効果的な研修設計については下記で詳しく解説しています。
⇒行動変容を促す研修の設計方法とは?効果的な学習設計で効果を最大化!
これからの社内教育はデジタル化
デジタル技術の進歩により、社内教育の形態は大きく変化しています。従来の集合研修中心のアプローチから、テクノロジーを活用したより効率的で効果的な教育手法への転換が進んでいます。
今後の社内教育では、デジタル技術を戦略的に活用することで、個人の学習スタイルに合わせたカスタマイズされた教育体験を提供できるようになります。
コンテンツをデジタル化
教育コンテンツのデジタル化は、学習効果を向上させる重要な取り組みです。動画コンテンツやインタラクティブな教材により、視覚的で理解しやすい学習体験を提供できます。
複雑な概念やプロセスも、アニメーションや図表を活用することで直感的に理解できるようになります。また、デジタルコンテンツは更新や改良が容易で、最新の情報や事例を迅速に反映できます。
マイクロラーニングの形式で短時間の学習コンテンツを作成することで、忙しい社員でも隙間時間を活用した効率的な学習が可能になります。
さらに、コンテンツの再利用性も高く、一度制作したコンテンツをさまざまな研修で活用できるため、長期的なコスト効率も向上します。
集合研修とオンライン研修を使い分ける
効果的な社内教育を実現するためには、集合研修とオンライン研修それぞれの特性を理解し、適切に使い分けることが重要です。
知識のインプットや基本的なスキル習得にはオンライン研修を活用し、ディスカッションやグループワーク、実践的な演習には集合研修を使用するハイブリッド型のアプローチが効果的です。
オンライン研修は時間と場所の制約が少なく、個人のペースで学習できます。一方、集合研修は参加者同士の交流や講師からの直接的なフィードバックが得られます。
研修の目的や内容に応じて最適な形式を選択することで、教育効果を最大化しながらコストと時間の効率化も実現できます。
反転学習のデザイン
反転学習は、従来の「講義→宿題」の順序を逆転させ、事前学習で基本知識を習得し、研修時間を実践的な活動に充てる学習手法です。受講者は事前にeラーニングで基礎知識を学び、実際の研修では学んだ知識を活用したディスカッションや演習に集中できます。
この手法により、限られた研修時間をより価値の高い活動に活用でき、深い学習と実践的なスキル習得が可能になります。また、受講者は自分のペースで基礎学習を進められるため、研修当日の理解度のばらつきが少なくなり、全体的な学習効果が向上します。
反転学習の導入により、研修の質と効率を同時に高めることができます。
学習プラットフォームで運用
学習プラットフォームの活用により、社内教育の運用効率と効果を大幅に向上させることができます。学習プラットフォームでは、研修の申し込みから受講、進捗管理、成果測定まで一元的に管理できます。
受講者の学習履歴や理解度を詳細に把握し、個別のフォローアップや追加的な学習支援を効率的に実施できます。また、社員は自身の学習状況を可視化でき、主体的な学習計画の立案が可能になります。
管理者側も組織全体の教育状況をリアルタイムで把握し、教育施策の改善や最適化を継続的に実施できます。学習プラットフォームは、社内教育のデジタル化における中核的な基盤となります。
AIの活用
AIの活用により、ロープレトレーニングなどの場面において、人がいなくてもAIを相手に練習することが可能です。AIはいつでもどこでも文句も言わずに練習相手になってくれます。
また、AIは人間にはできない精緻なフィードバックが可能です。流暢さ、ジェスチャー、スピード、表情、明瞭さ、アイコンタクト、キーワード、NGワード、口癖などを事実ベースでデータを示しながらフィードバックしてくれます。
この精緻なフィードバックを基に改善点を明確にし、意識して練習することで、これまでよりも効率的にスキルアップすることが可能です。
また、フィードバックだけでなく、生成AIの活用で会話型のロープレトレーニングもできるため、基礎的な練習から応用的な練習までカバーすることができます。
▼学習プラットフォームについては下記で詳しく解説しています。
⇒学習プラットフォームで人材育成の効率を高めるには?おすすめ運用方法も解説!
社内教育を効果的に展開している事例紹介
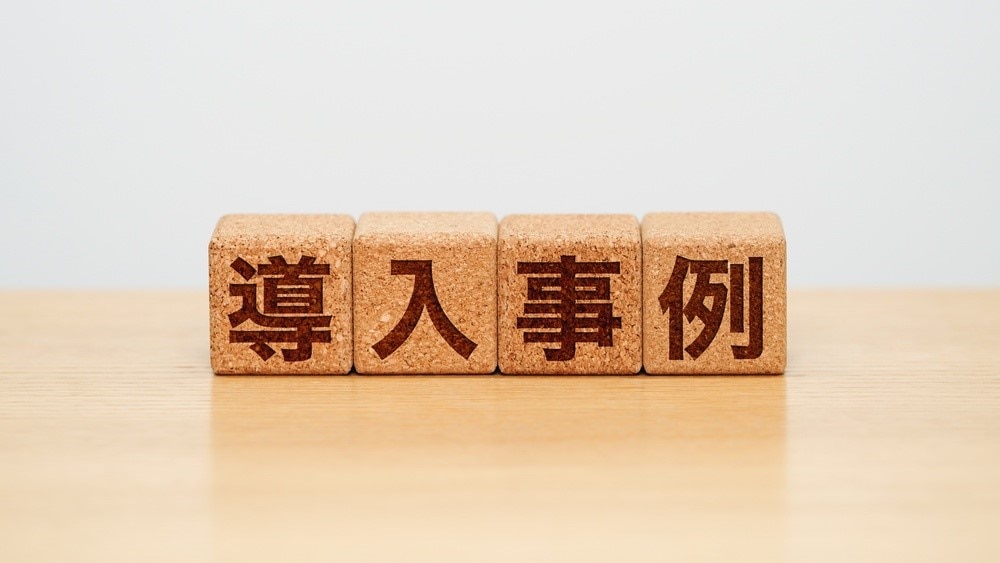
ここでは人材育成策を効果的に展開している事例を紹介します。
社内トレーナーで機動力高く研修を実施し効果を上げている事例

背景・課題:
リコージャパン株式会社では、2010年の販売会社統合以降、各支社の固有の課題に対応できず、教育施策が本部主導で一方的になるなどの課題がありました。
また、コロナ禍以降、会食などの機会が減ったことにより、コミュニケーションの希薄化を招いていました。これらの課題を解決するために、社員自らが強みや弱みを理解し合い、横のつながりを強化する取り組みが求められていました。
LIFOプログラム(社内トレーナーライセンス)の導入:
その中で、LIFO(Life Orientations)を導入しました。LIFOの活用を通じて、社員一人一人の個性を診断し、自己理解と他者理解を促進しました。
これにより、非公式なコミュニケーションが減少する中でも、社員同士の相互理解を深めるための新たな手段を提供することができるようになりました。
また、LIFOプログラムライセンスを取得することで、社内トレーナーが自主的に研修を行えるようになり、組織風土改革を進めました。
LDcubeとの協力により、多様なワークショップを展開し、各支社・部門が抱える具体的な課題に対応できるようになりました。
社内展開:
プログラムの展開においては、事前のLIFO診断、ワークショップの実施、職場での実践、効果検証のサイクルを組み込みました。
参加者は、研修後の職場実践を通じて得られたスキルを評価し合い、PDCAサイクルを回すことで、持続的なスキルアップを図っています。
ラーニングプラットフォーム「UMU」を活用し、受講者同士が学び合う環境も整備しました。
社内トレーナーによる研修実施後の反応:
導入後、プログラム受講者の満足度は高く、多くの支社で「対人関係」や「マネジメント能力」などにおいて数値的な改善が見られました。
LIFOを活用したレクチャーは「人」の問題の解決に寄与し、特にアウトプット重視の体験学習が効果的でした。
UMUの活用と一連の学習サイクルの設計により、事務局の負担軽減と学習効果の向上が実現しました。
今後に向けて:
今後は、各支社や部門の課題に寄り添い、人材育成を継続的にサポートすることで、社員個々の自己成長と組織全体の活性化をさらに推進する予定です。
また、LIFO以外のライセンスプログラムも組み合わせ、人材育成のプログラムラインナップを増やしていきます。
これにより、組織内のさまざまな課題を解決し、全体の一体感を更に高められることを期待しています。
▼本事例はインタビュー記事の一部です。インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。
⇒リコージャパン株式会社様 ライセンスプログラム導入事例
パーソナライズ学習でeラーニング受講率100%を達成した事例

支援事例:専門商社(400名)
【これまでの課題】
eラーニングを「必修」にしなければ学習しない
流し見で「完了」することが目的になってしまっている
業務が忙しくて受講することを忘れてしまう ・・・など
⇒【CK-Connectによるパーソナライズ学習を導入】
【受講率100%を実現】
「必修」「受講期限」の設定がない中で、受講率100%を実現
診断結果を基に自動でリコメンドされるコースを自主的に受講
1人平均5.7コースの受講(多い人は16コースの受講)
今回のポイント
- パーソナライズ学習:
パーソナル診断結果を基にした個々人に合わせた学習コンテンツを自動配信
- いつでも学べる環境:
学習者が必要なときに必要な学習にアクセスできる環境 - 学習データの蓄積:
学習者の学習状況をトラッキングするために学習行動のデータを取得
お客さまの声
AIを活用して3倍の成果を上げた事例
社員数: 8,000名以上
事業:生命保険販売、資産運用
営業研修内容見直しの成果
~入社3カ月後の売上実績が従来の研修受講者と比較して3倍に~
アウトプット中心の学習で実践力を身に付けた上、研修中に学んだことを、動画でいつでもどこでも復習・確認ができる環境を作ることで、学習内容を実践につなげることができるようになりました。
その結果、 Teamsをつないでの従来の研修スタイルで学習した受講生集団と比較 しましたが、営業研修内容をバージョンアップした研修を受けた集団は、従来の研修を受講した集団と比較し、入社3カ月後の売上実績が3倍という飛躍的な成果を出しました。
トレーナースキルに依存せず、均一なレベルの初期教育が可能に
ライブでの講義ではなく、動画を活用した研修運営をすることで、高品質な研修情報を余すことなく再現することが可能となりました。
トレーナーリソースの効果的活用
従来は、毎月入社するキャリア採用社員の導入研修を毎月実施するため、トレーナーの方々はかなりのリソースを割かなければなりませんでした。しかし、マイクロラーニングの導入により初期教育を効率化することで、そのリソースを営業管理職教育に充てることができるようになりました。それにより、現場の指導力強化につなげることができ、学習の好循環を生んでいます。
取り組みの詳細
職種別オンボーディングプログラムを展開
キャリア入社後1カ月間の導入研修をマイクロラーニングを活用した研修にバージョンアップしました。
事前学習、研修当日、事後学習全ての場面においてマイクロラーニングで知識のインプットを行い、研修当日は確認テストの解説や、受講生同士のディスカッション、質疑応答に比重を置くことなどで、カスタマイズ性の高い学習の提供を実現しています。
マイクロラーニングはそれまで社内で活用されていた動画をベースに、新たなコンテンツも社内トレーナーの方が中心となって作成しました。
研修中は特に「学んだことが現場でも生かせそうだ、使えそうだ」と思ってもらうための支援や関わりを重視することで受講生のエンゲージメント向上にもつなげています。
これまでのインプットは社内トレーナーの方がレクチャーしてインプットしていましたが、リニューアルしてからはレクチャーは全て動画に代替しました。
アウトプットを意識した学習デザイン
インプットして終わりにならないように、動画を活用し、受講者が研修で学んだことを生かしながら1人でも何度もAIを相手にセールストークを練習し、動画で提出するという環境を提供されています。
動画を見た研修トレーナーから、直属の上司・先輩から、他部署の上司・先輩から、そして同期からフィードバックを受けることができ、学習の深化につなげています。
また、動画を閲覧した上で学んだことや仕事に生かせそうなことを共有することで、自分の考えを整理しながら、他の受講生の意見に触れながら新たな学びを得るという、学習の相乗効果を生んでいます。
導入前の課題
研修がイベント化してしまっている
集合研修で社員にいくら良い内容を提供しても 、現場に戻った後は目の前の仕事をこなすことに集中してしまい、学んだことがその場限りとなってしまうことが多く見受けられました。
集まった場だけではなく、事前と事後の学習活動を充実化させ、学習を続けながら学んだことを仕事に生かすことができる環境を作るため、 マイクロラーニング・コホート型学習を導入しました。
個人の経験がポケットノウハウになってしまっている
現場で得られた成功事例や失敗事例が個人のものにしかなっておらず、ポケットノウハウ化してしまっていることに課題を感じていました。
個人の学びを暗黙知から形式知に変えていくことで、受講生同士の学びを促進しながら、組織全体のナレッジとして好循環を生み出していきたいという思いがありました。
効果的な社内教育ならLDcube

現代の企業にとって、効果的な社内教育は競争力を維持・向上するために欠かせません。
LDcubeは、そのための最適なソリューションを提供します。外部講師を派遣することが中心の研修会社では「研修の実施=ビジネス」となり、行動変容まで追いかけることが現実的にはあまりできません。
そのため、行動変容までしっかりと追いかけ、研修を意味あるものにするために、LDcubeは研修会社を飛び出しました。現在は、研修実施を中心とせず、行動変容につなげるための社内トレーナーの支援、学習コンテンツや学習プラットフォームの提供を中心に行っています。
LDcubeは学習設計において、明確な行動変容を目的としています。これは単なる知識の習得ではなく、学んだことを業務で活用し、実際の行動変化を促すことを重視しています。具体的には、個々の組織のニーズに合わせたカスタマイズされた研修プログラムを提供し、対象者の業務に即したスキルを効果的に習得させることが可能です。
さらに、LDcubeは最新のテクノロジーを駆使し、デジタルコンテンツやAIを活用した学習体験を提供します。これにより、参加者は自分のペースで、またタイムリーに学習を進めることができます。また、実施後の効果測定はPDCAサイクルに基づいており、研修の成果を定量化し、次回のプログラム改善に役立てます。
そして、LDcubeは企業の業績向上につながる社内教育を実現します。組織が抱える特定の課題解決に向けた研修を通じて、社員一人一人が業務に貢献できる人材へと成長することを支援します。効果的な社内教育をお望みなら、LDcubeにお気軽にご相談ください。
まとめ:社内教育で組織を成長させよう
社内教育・研修の目的は社員の行動変容!これからの時代の効果的な実施方法とは??
- 社内教育で業績を向上しよう
- 社内教育の目的と重要性
- 社内教育の具体的な方法
- 社内教育を実施するリソース
- 社内教育を成功させるポイント
- これからの社内教育はデジタル化
- 社内教育を効果的に展開している事例紹介
- 効果的な社内教育ならLDcube
社内教育は企業の持続的成長を支える重要な投資です。人材不足が深刻化する現代において、既存社員のスキルアップと生産性向上は避けて通れない課題となっています。効果的な社内教育を実現するためには、明確な目的設定から始まり、適切な教育手法とリソースの選択、そして継続的なフォローアップまで、一貫した取り組みが必要です。
特に重要なのは、経営陣の本気度と現場の協力体制です。また、デジタル技術を活用した効率的な教育システムの構築も、今後の競争力維持に欠かせない要素となります。まずは自社の現状を把握し、優先順位の高い分野から段階的に教育体制を整備していくことをおすすめします。社内教育への投資は、必ず組織の成長と発展につながる価値ある取り組みです。
株式会社LDcubeは、時代の変化に合わせて人材育成の施策展開を支援しています。研修やセミナーの実施から、社内トレーナーの養成、デジタルツールの提供などを行っています。
これからの時代に必要な学習行動のデータ取得と活用など、多くの組織からいただいた課題の解決を中心にサービスを提供しております。予算を抑えながら効果を高めたいという目標をお持ちの人事の方々に貢献できると考えています。
無料での研修プログラムの体験会やデジタルツールのデモ体験会、導入事例の紹介なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼これからの人材育成施策を模索する際のお役立ち資料も用意しています。お役立ち資料はこちらからご覧ください。
▼関連記事はこちらから。