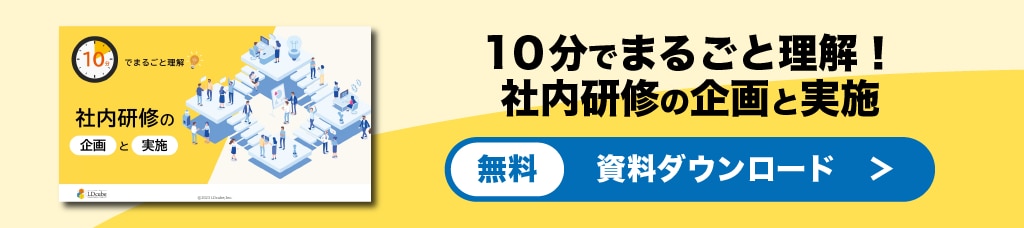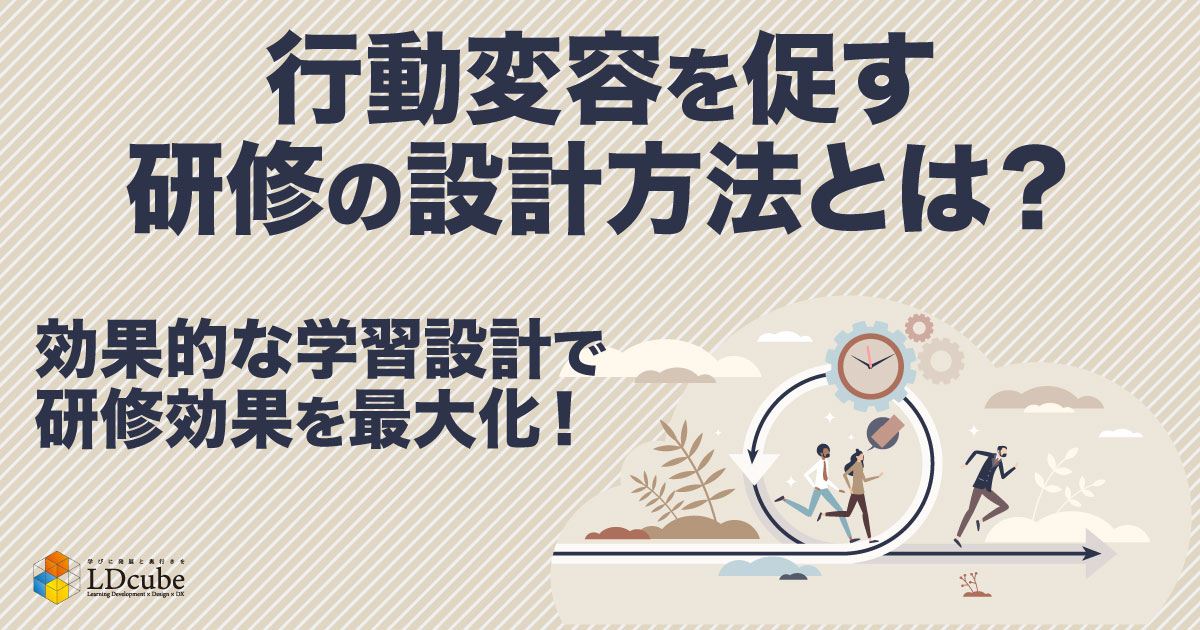
行動変容を促す研修の設計方法とは?効果的な学習設計で効果を最大化!
「研修を実施しても社員の行動が変わらない」「学んだ内容が職場で生かされていない」このような悩みを抱えている人事担当者や研修企画者の方は多いのではないでしょうか。
実際、多くの企業で研修後のアンケートでは高い満足度を得られるものの、実際の業務における行動変容には至らず、研修投資の効果が見えないという課題が発生しています。この問題の根本原因は、研修を設計する際に「行動変容」を意識した学習設計を理解せずに、知識習得だけに焦点を当てた研修を実施していることにあります。
行動変容を実現するには、研修の機会段階から効果的な学習設計を行う必要があります。また、研修の効果を最大化するには、研修前の準備が4割、研修中の実施が2割、研修後のフォローアップが4割という「ブリンカーホフの法則」に基づいた一貫した取り組みが不可欠です。
本記事では、行動変容に向けた学習設計の考え方から具体的な方法、効果測定のポイントまで、実践的なガイドを詳しく解説します。
▼研修設計や効果的なやり方については下記で詳しく解説しています。
▼研修についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。
▼お役立ち資料はこちらからダウンロードできます。
目次[非表示]
- 1.行動変容しない研修は意味がない
- 2.行動変容しない研修よくあるパターン
- 3.研修後の行動変容につなげる4大要素
- 4.研修前の準備で行動変容への意欲を高める方法
- 5.行動変容につなげる為の研修の終わり方
- 5.1.研修中に練習の要素を入れて、試してみる
- 5.2.研修後にやれそうだと感じさせる
- 5.3.実現可能なアクションプランの作成
- 5.4.受講者同士で行動宣言
- 6.研修後のフォローアップで行動変容を定着
- 6.1.職場での受講報告と行動宣言
- 6.2.上司にアクションプランの実現を支援してもらう
- 6.3.定期的なアンケートで行動変容を促進
- 6.4.受講者同士の学習グループで活動状況の共有
- 6.5.定期的な振り返りで継続的な改善を支援する
- 7.研修後の行動変容には社内トレーナーが重要
- 8.研修後の行動変容の効果測定と改善のポイント
- 9.行動変容につなげている研修の支援事例
- 10.まとめ:効果的な学習デザインで行動変容を促そう
行動変容しない研修は意味がない

多くの企業で研修を実施しているにも関わらず、期待した成果が得られないという課題があります。この根本的な原因は、研修が行動変容につながっていないことにあります。
研修は行動変容を経由して業績に貢献する
研修の本来の目的は、従業員の行動を望ましい方向に変化させることです。行動変容とは、業務において課題となっている行動をより望ましい方向に変えることを意味します。研修投資が業績向上に結びつくまでの流れは「研修実施→知識・スキル習得→行動変容→業務改善→業績向上」という段階を経て実現されます。
この流れの中で最も重要なのが行動変容の段階です。いくら優れた知識やスキルを習得しても、実際の業務で活用されなければ意味がありません。研修で学んだ内容が職場での具体的な行動の変化として現れて初めて、投資対効果が生まれるのです。
行動変容しない研修は実施することが目的になっている
行動変容につながらない研修の典型的な問題は、研修を実施すること自体が目的化してしまっていることです。年間研修計画に基づいて機械的に研修を実施し、受講者数や実施回数といった活動指標のみで成果を測定している状況では、本来の目的である行動変容が置き去りにされてしまいます。
このような研修では、受講者は一時的に知識を得ることはできても、職場に戻った際にその知識を実践に移すための動機や環境が整っていません。結果として、研修内容は短期間で忘れ去られ、従来の行動パターンに戻ってしまうことになります。
行動変容につなげる学習デザインが弱い
多くの研修が行動変容に結びつかない理由として、学習デザインの不備が挙げられます。効果的な研修を設計するためには、研修前の準備から研修後のフォローアップまでを一連のプロセスとして捉える必要があります。
ブリンカーホフの法則によると、研修効果に影響する要因は研修前が40%、研修中が20%、研修後が40%とされています。しかし、多くの企業では研修中の内容に注力しすぎて、研修前後の重要性を軽視しているのが現状です。行動変容を実現するためには、この比率を意識した包括的な学習デザインが不可欠です。
行動変容しない研修よくあるパターン

行動変容につながらない研修には、共通した問題パターンがあります。これらのパターンを理解することで、自社の研修設計を見直すきっかけとなります。
研修の目的が曖昧
多くの企業で見られる問題として、研修の目的設定が曖昧であることが挙げられます。「リーダーシップ研修」「コミュニケーション研修」といった名称だけで企画され、具体的にどのような行動変容を期待するのかが明確でない研修では、受講者も何を変えるべきかが分からず、結果として行動変容が起こりません。
効果的な研修を実現するためには、「営業担当者が顧客との関係構築において積極的な提案ができるようになる」「管理職が部下との1on1面談で適切なフィードバックを行えるようになる」など、具体的で測定可能な行動目標を設定することが重要です。
経営戦略と紐づいていない
研修内容が経営戦略や事業目標と連動していない場合も、行動変容が困難になります。人事部門が独自に企画した研修内容が、実際の事業課題や組織の優先事項と乖離していると、受講者は研修の必要性を感じることができません。
経営戦略と連携した研修設計では、事業目標達成のために必要な行動変容を明確にし、その実現に向けた学習内容を組み立てます。このアプローチにより、受講者は研修の意義を理解し、積極的に学習に取り組むようになります。
研修前後のフォローアップが不足している
研修当日の内容に注力しすぎて、研修前の準備や研修後のフォローアップが不十分な場合、行動変容は期待できません。研修前に受講者の現状課題を把握し、学習への動機を高める準備が必要です。また、研修後には学んだ内容を職場で実践するためのサポート体制が不可欠です。
特に研修後のフォローアップは、新しい行動を継続し習慣化するために重要な要素です。上司による支援、同僚との振り返り、定期的な進捗確認などの仕組みがないと、受講者は従来の行動パターンに戻ってしまいます。
研修後の行動変容につなげる4大要素

行動変容を成功させるためには、研修設計において4つの重要な要素を組み込む必要があります。これらの要素を適切に組み合わせることで、研修効果を最大化できます。
①研修前後での上司の巻き込み
行動変容の成功において、上司の関与は大きな要因となります。上司が研修の目的や期待する行動変容を理解し、積極的にサポートすることで、受講者の学習意欲と実践継続が大幅に向上します。
研修前には、上司から受講者に対して研修への期待を伝えてもらい、研修後には学んだ内容を職場で実践する機会を提供してもらうことが重要です。また、上司自身が新しい行動を評価し、フィードバックを与える役割を担うことで、受講者の行動変容を持続的に支援できます。
②研修内容と業務の関連付け
研修で学ぶ内容が実際の業務と密接に関連していることを受講者が理解できるよう設計することが重要です。抽象的な理論だけでなく、日常業務で直面する具体的な課題や状況を題材にした学習内容を組み込むことで、受講者は学習の必要性を実感できます。
|
このような工夫により、受講者は研修内容を「自分事」として捉え、積極的に学習に取り組むようになります。
③シリーズ型の研修デザイン
単発の研修ではなく、複数回に分けて実施するシリーズ型の研修デザインは、行動変容に効果的です。第1回目の研修で基本的な知識やスキルを学び、その後の実践期間を経て、第2回目で振り返りと改善を行うサイクルを繰り返すことで、段階的な行動変容を促進できます。
シリーズ型デザインでは、各回の間に職場での実践課題を設定し、次回の研修で実践結果を共有する仕組みを作ることが重要です。これにより、受講者は継続的に新しい行動を意識し、改善を重ねることができます。
④デジタルツールを使った細かなフォロー
現代の研修設計では、デジタルツールを活用した継続的なフォローアップが不可欠です。LMSや学習プラットフォームを使用して、研修後の学習進捗や行動変容の状況を定期的に確認し、必要に応じてサポートを提供することで、行動変容の定着率を高められます。
デジタルツールを活用し、学習行動のデータを取得することで、受講者個人の学習ペースに合わせたフォローアップが可能になり、集合研修では対応しきれない個別ニーズにも対応できます。また、学習データの蓄積により、研修効果の測定と改善も効率的に行えるようになります。
研修前の準備で行動変容への意欲を高める方法

行動変容を成功させるためには、研修当日よりも研修前の準備が重要です。受講者の学習意欲を高め、行動変容への動機を育成する効果的な準備方法を解説します。
事前課題で現状の課題を認識させる
研修前に事前課題を実施することで、受講者が自分の現状を客観的に把握し、改善の必要性を認識できるようになります。効果的な事前課題では、現在の業務における具体的な行動を振り返らせたり、スキルチェックを行ったりすることで、受講者が「このままではいけない」という課題意識を持てるよう設計します。
例えば、コミュニケーション研修の場合、過去1週間の部下との対話を記録し、自分の傾聴スキルや質問スキルを自己評価してもらうといった課題が効果的です。
このような事前の振り返りを通じて、受講者は研修で学ぶ内容への関心を高め、積極的な学習姿勢で研修に参加するようになります。
上司を巻き込み行動変容への心理的安全性を確保する
受講者が安心して新しい行動に挑戦できる環境を整えることは、行動変容の成功に不可欠です。特に上司との関係性において心理的安全性が確保されていることが重要で、これにより受講者は失敗を恐れずに新しいスキルを実践できるようになります。
|
心理的安全性が確保された職場では、受講者は同調バイアスや現状維持バイアスを克服し、積極的に行動変容に取り組むことができます。
上司から本人へ研修への期待を伝えてもらう
上司から受講者に対して、研修への期待を直接伝えてもらうことで、受講者の学習に対するモチベーションを大幅に向上させることができます。単に人事部から研修案内を送るだけでなく、直属の上司が個別に期待を伝えることで、受講者は研修の重要性を実感し、真剣に取り組むようになります。
効果的な期待の伝え方では、抽象的な内容ではなく、具体的にどのような行動変容を期待しているかを明確に伝えることが重要です。また、その行動変容が受講者自身のキャリア発展や組織への貢献にどのように結びつくかも併せて説明することで、より強い動機付けが可能になります。
上司からの期待が明確に伝わることで、受講者は研修を「やらされている」のではなく、「自分の成長のために参加している」という主体的な意識を持つことができます。
行動変容につなげる為の研修の終わり方

研修の最終段階での取り組みは、受講者が職場で実際に行動変容を起こすかどうかを左右する重要な要素です。効果的な研修の終わり方について解説します。
研修中に練習の要素を入れて、試してみる
研修中にロープレやシミュレーション演習を組み込むことで、受講者は新しいスキルや行動を安全な環境で試すことができます。この練習体験は、職場での実践に向けた自信を醸成し、行動変容への準備となり、実践への移行を促進します。
効果的な練習設計では、受講者の実際の業務状況に近いシナリオを用意し、段階的に難易度を上げていくことが重要です。まず基本的なスキルから練習し、徐々に複雑な状況での対応を体験してもらうことで、受講者は「これなら職場でもできそう」という感覚を得られます。
また、練習後には必ずフィードバックの時間を設け、良かった点を具体的に褒めることで、受講者の自己効力感を高めることができます。
研修後にやれそうだと感じさせる
受講者が研修終了時に「これなら自分にもできそう」という感覚を持てるよう設計することが重要です。この自己効力感は、行動変容の継続において決定的な要因となります。過度に高い目標設定や複雑な手法を押し付けるのではなく、受講者が確実に実践できるレベルから始められるよう配慮が必要です。
|
このような配慮により、受講者は前向きな気持ちで研修を終えることができ、職場での実践に対する不安を軽減できます。
実現可能なアクションプランの作成
研修の最後には、受講者が具体的で実現可能なアクションプランを作成することが重要です。効果的なアクションプランは、SMARTの法則(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限設定)に基づいて設計し、受講者が確実に実行できる内容にする必要があります。
アクションプランでは、「いつ」「どこで」「何を」「どのように」実践するかを明確に記載し、可能な限り具体的な行動レベルまで落とし込みます。例えば、「部下とのコミュニケーションを改善する」という抽象的な目標ではなく、「毎週火曜日の午前中に、部下Aさんと15分間の1on1面談を実施し、今週の業務の進捗と困っていることを聞く」といった具体的な内容にします。
また、実践する際に想定される障害や困難についても事前に検討し、それらを乗り越える方法も併せて計画しておくことで、実行率を高めることができます。
受講者同士で行動宣言
研修の最終段階で、受講者同士がアクションプランを共有し、行動宣言を行うことで、コミットメント効果を高めることができます。他の受講者の前で自分の実践内容を宣言することで、責任感が生まれ、実行への動機が強化されます。
行動宣言では、単にアクションプランを読み上げるだけでなく、なぜその行動を取りたいのかという動機や想いも併せて共有してもらいます。これにより、受講者同士が互いの成長を支援し合う関係性が生まれ、研修後の継続的な学習コミュニティーの基盤となります。
また、宣言内容は記録に残し、後日のフォローアップで活用することで、受講者の実践状況を確認し、必要に応じてサポートを提供できます。
研修後のフォローアップで行動変容を定着

研修で学んだ内容を職場で継続的に実践し、習慣化するためには、研修後のフォローアップが不可欠です。効果的なフォローアップの仕組みについて詳しく解説します。
職場での受講報告と行動宣言
研修終了後、受講者が職場のチームメンバーや上司に対して研修内容と今後の行動計画を報告することで、周囲の理解と協力を得ることができます。この報告プロセスは、受講者自身のコミットメントを強化し、周囲からの支援体制を構築する重要な機会となります。
効果的な受講報告では、学んだ内容を簡潔にまとめるだけでなく、具体的にどのような行動変容を目指すのかを明確に伝えることが重要です。また、同僚や上司に対して、新しい取り組みへの理解と協力を求めることで、職場全体で行動変容を支援する環境を作ることができます。
上司にアクションプランの実現を支援してもらう
上司が受講者のアクションプラン実現を積極的に支援することで、行動変容の成功率は大幅に向上します。上司の役割は、単に進捗を確認するだけでなく、実践の機会を提供し、適切なフィードバックを与えることです。
|
上司が受講者の成長を支援する姿勢を示すことで、受講者は安心して新しい行動に挑戦することができます。
定期的なアンケートで行動変容を促進
研修後の一定期間ごとに、受講者の実践状況や課題を把握するためのアンケートを実施することで、継続的な学習支援が可能になります。このアンケートは単なる評価ツールではなく、受講者の振り返りと改善を促進する重要な仕組みです。
効果的なアンケート設計では、行動の実践状況や成果だけでなく、実践する際の困難点や必要な支援についても質問項目に含めます。回答結果に基づいて、個別のフォローアップや追加の学習機会を提供することで、受講者の継続的な成長を支援できます。
受講者同士の学習グループで活動状況の共有
研修参加者同士で定期的に集まり、実践状況を共有する学習グループを形成することで、相互学習と動機維持の効果が期待できます。同じ課題に取り組む仲間からの刺激や助言は、個人の努力だけでは得られない学習効果をもたらします。
学習グループでは、成功事例だけでなく、失敗や困難についても率直に共有し、解決策を一緒に考える場とすることが重要です。このような相互支援の関係性により、受講者は継続的に学習意欲を維持し、行動変容を促進することができます。
定期的な振り返りで継続的な改善を支援する
研修後1カ月、3カ月、6カ月といった節目で振り返りセッションを実施し、受講者の成長過程を確認することが重要です。振り返りセッションでは、実践してきた行動の効果を検証し、さらなる改善点を見つけ出すことで、継続的な成長サイクルを構築できます。
振り返りの際には、定量的な成果だけでなく、受講者自身の気付きや学びも重視し、次の成長段階に向けた新たな目標設定を支援します。このプロセスを通じて、受講者は自律的な学習者として成長し、長期的な行動変容を実現できるようになります。
研修後の行動変容には社内トレーナーが重要

行動変容を継続的に支援するためには、社内トレーナーの活用が効果的です。外部講師による研修とは異なる独自の価値を提供できる社内トレーナーの重要性について解説します。
組織文化や経営課題を押さえた上でフォローできる
社内トレーナーは、自社の組織文化や経営課題を深く理解しているため、受講者の実践をより効果的に支援することができます。外部講師では把握しきれない組織特有の課題や制約を踏まえた上で、現実的で実行可能なアドバイスを提供できることが大きな強みです。
また、社内の人間関係や業務プロセスを熟知しているため、受講者が新しい行動を実践する際に直面する具体的な障害を予測し、事前に対策を講じることが可能です。このような組織への深い理解に基づくフォローアップにより、行動変容の成功率を高めることができます。
日程や時間など機動力高くフォローできる
社内トレーナーは、外部講師と比較して日程調整や時間確保の面で高い機動力を発揮できます。受講者が困難に直面した際に、迅速にフォローアップセッションを設定したり、個別相談に応じたりすることが可能です。
|
このような機動力の高さにより、受講者は必要な時にタイムリーな支援を受けることができ、行動変容の継続が容易になります。また、社内トレーナーとの日常的な接触により、学習文化の醸成にも貢献できます。
研修後の行動変容の効果測定と改善のポイント
研修の投資対効果を高めるためには、行動変容の効果を適切に測定し、継続的に改善していくことが重要です。効果的な測定と改善の方法について解説します。
アンケート(行動チェックリスト)で変化を可視化する
研修による行動変容を客観的に測定するために、具体的な行動項目を設定した行動チェックリストを活用することが効果的です。このチェックリストでは、研修で学んだ内容に基づく具体的な行動を5段階評価で測定し、研修前後の変化を数値で把握できます。
(行動チェックリスト例)
|
このような具体的な行動項目を設定することで、抽象的な概念ではなく、実際の行動レベルでの変化を測定することができます。定期的な測定により、行動変容の進捗状況を把握し、必要に応じて追加のサポートを提供することが可能になります。
受講者と上司の相互評価で行動変容を確認する
受講者による自己評価だけでなく、上司や同僚からの他者評価を組み合わせることで、より客観的で正確な行動変容の測定が可能になります。自己評価では見えない点や、周囲から見た実際の変化を把握することができます。
相互評価では、同じ評価項目を用いて受講者と上司がそれぞれ評価を行い、その結果を比較検討します。評価の差異がある場合は、その原因を話し合うことで、受講者の自己認識を向上させ、さらなる行動変容を促進することができます。
継続的なPDCAサイクルで研修品質を向上させる
効果測定の結果を基に、研修内容や運営方法を継続的に改善していくPDCAサイクルを構築することが重要です。測定データから得られた気付きや課題を次の研修設計に反映することで、研修の効果を段階的に向上させることができます。
改善のプロセスでは、行動変容が思うように進まなかった要因を分析し、研修前の準備、研修中の内容、研修後のフォローアップのそれぞれについて見直しを行います。このような継続的な改善により、組織全体の人材育成効果を最大化することが可能になります。
行動変容につなげている研修の支援事例
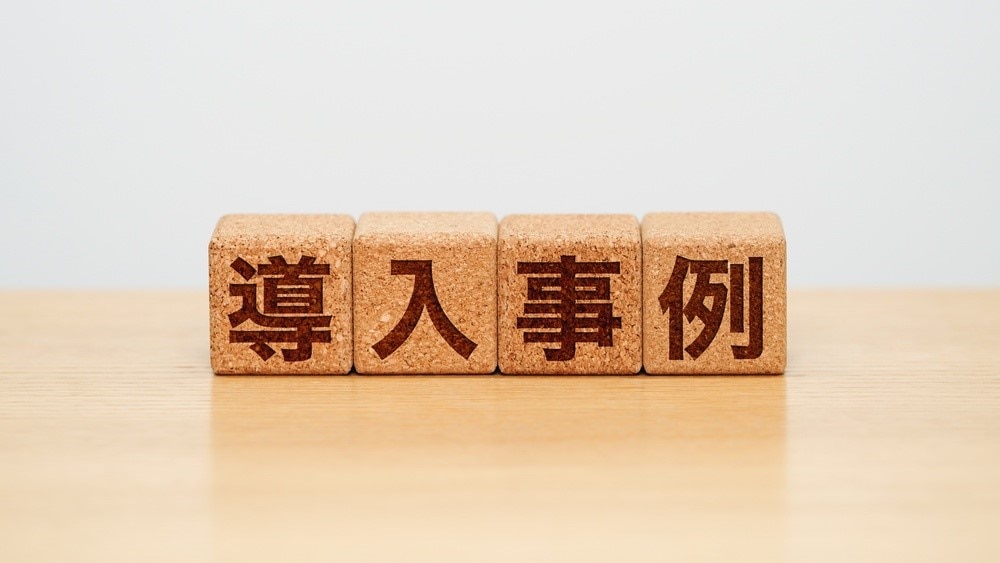
行動変容につなげている研修の支援事例を2つ紹介します。
社内トレーナーが行動変容につなげている事例(リコージャパン)

背景・課題:
リコージャパン株式会社では、2010年の販売会社統合以降、各支社の固有の課題に対応できず、教育施策が本部主導で一方的になるなどの課題がありました。
また、コロナ禍以降、会食などの機会が減ったことにより、コミュニケーションの希薄化を招いていました。これらの課題を解決するために、社員自らが強みや弱みを理解し合い、横のつながりを強化する取り組みが求められていました。
LIFOプログラム(社内トレーナーライセンス)の導入:
その中で、LIFO(Life Orientations)を導入しました。LIFOの活用を通じて、社員一人一人の個性を診断し、自己理解と他者理解を促進しました。
これにより、非公式なコミュニケーションが減少する中でも、社員同士の相互理解を深めるための新たな手段を提供することができるようになりました。
また、LIFOプログラムライセンスを取得することで、社内トレーナーが自主的に研修を行えるようになり、組織風土改革を進めました。
LDcubeとの協力により、多様なワークショップを展開し、各支社・部門が抱える具体的な課題に対応できるようになりました。
社内展開:
プログラムの展開においては、事前のLIFO診断、ワークショップの実施、職場での実践、効果検証のサイクルを組み込みました。
参加者は、研修後の職場実践を通じて得られたスキルを評価し合い、PDCAサイクルを回すことで、持続的なスキルアップを図っています。
ラーニングプラットフォーム「UMU」を活用し、受講者同士が学び合う環境も整備しました。
社内トレーナーによる研修実施後の反応:
導入後、プログラム受講者の満足度は高く、多くの支社で「対人関係」や「マネジメント能力」などにおいて数値的な改善が見られました。
LIFOを活用したレクチャーは「人」の問題の解決に寄与し、特にアウトプット重視の体験学習が効果的でした。
UMUの活用と一連の学習サイクルの設計により、事務局の負担軽減と学習効果の向上が実現しました。
今後に向けて:
今後は、各支社や部門の課題に寄り添い、人材育成を継続的にサポートすることで、社員個々の自己成長と組織全体の活性化をさらに推進する予定です。
また、LIFO以外のライセンスプログラムも組み合わせ、人材育成のプログラムラインナップを増やしていきます。
これにより、組織内のさまざまな課題を解決し、全体の一体感を更に高められることを期待しています。
▼本事例はインタビュー記事の一部です。インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。
⇒リコージャパン株式会社様 ライセンスプログラム導入事例
社内トレーナーが行動変容につなげ、業績向上している支援事例(金融業)
社員数: 8,000名以上
事業:生命保険販売、資産運用
営業研修内容見直しの成果
~入社3カ月後の売上実績が従来の研修受講者と比較して3倍に~
アウトプット中心の学習で実践力を身に付けた上、研修中に学んだことを、動画でいつでもどこでも復習・確認ができる環境を作ることで、学習内容を実践につなげることができるようになりました。
その結果、 Teamsをつないでの従来の研修スタイルで学習した受講生集団と比較しましたが、営業研修内容をバージョンアップした研修を受けた集団は、従来の研修を受講した集団と比較し、入社3カ月後の売上実績が3倍という飛躍的な成果を出しました。
トレーナースキルに依存せず、均一なレベルの初期教育が可能に
ライブでの講義ではなく、動画を活用した研修運営をすることで、高品質な研修情報を余すことなく再現することが可能となりました。
トレーナーリソースの効果的活用
従来は、毎月入社するキャリア採用社員の導入研修を毎月実施するため、トレーナーの方々はかなりのリソースを割かなければなりませんでした。
しかし、マイクロラーニングの導入により初期教育を効率化することで、そのリソースを営業管理職教育に充てることができるようになりました。
それにより、現場の指導力強化につなげることができ、学習の好循環を生んでいます。
取り組みの詳細
職種別オンボーディングプログラムを展開
キャリア入社後1カ月間の導入研修を、マイクロラーニングを活用した研修にバージョンアップしました。
事前学習、研修当日、事後学習全ての場面においてマイクロラーニングで知識のインプットを行い、研修当日は確認テストの解説や、受講生同士のディスカッション、質疑応答に比重を置くことなどで、カスタマイズ性の高い学習の提供を実現しています。
マイクロラーニングはそれまで社内で活用されていた動画をベースに、新たなコンテンツも社内トレーナーの方が中心となって作成しました。
研修中は特に「学んだことが現場でも生かせそうだ、使えそうだ」と思ってもらうための支援や関わりを重視することで受講生のエンゲージメント向上にもつなげています。
これまでのインプットは社内トレーナーの方がレクチャーしてインプットしていましたが、リニューアルしてからはレクチャーは全て動画に代替しました。
アウトプットを意識した学習デザイン
インプットして終わりにならないように、動画を活用し、受講者が研修で学んだことを生かしながら1人でも何度もAIを相手にセールストークを練習し、動画で提出するという環境を提供されています。
動画を見た研修トレーナーから、直属の上司・先輩から、他部署の上司・先輩から、そして同期からフィードバックを受けることができ、学習の深化につなげています。
また、動画を閲覧した上で学んだことや仕事に生かせそうなことを共有することで、自分の考えを整理しながら、他の受講生の意見に触れながら新たな学びを得るという、学習の相乗効果を生んでいます。
導入前の課題
研修がイベント化してしまっている
集合研修で社員にいくら良い内容を提供しても 、現場に戻った後は目の前の仕事をこなすことに集中してしまい、学んだことがその場限りとなってしまうことが多く見受けられました。
集まった場だけではなく、事前と事後の学習活動を充実化させ、学習を続けながら学んだことを仕事に生かすことができる環境を作るため、 マイクロラーニング・コホート型学習を導入しました。
個人の経験がポケットノウハウになってしまっている
現場で得られた成功事例や失敗事例が個人のものにしかなっておらず、ポケットノウハウ化してしまっていることに課題を感じていました。
個人の学びを暗黙知から形式知に変えていくことで、受講生同士の学びを促進しながら、組織全体のナレッジとして好循環を生み出していきたいという思いがありました。
まとめ:効果的な学習デザインで行動変容を促そう
行動変容を促す研修の設計方法とは?効果的な学習設計で研修効果を最大化!について紹介してきました。
行動変容を促す研修を実現するためには、研修前の準備から研修後のフォローアップまでを一連のプロセスとして設計することが重要です。研修の実施だけでなく、上司の巻き込み、実務との関連付け、継続的なサポート体制の構築が成功の鍵となります。
特に重要なのは、受講者の行動変容に向けて効果的な学習設計を行うことです。上司の巻き込み、業務内容とのリンク、シリーズ型の研修展開、デジタルツールを使った細かなフォローまで、それぞれの必要な支援を提供することで、着実な行動変容を実現できます。
効果的な研修設計により、従業員の成長と組織の成果向上を同時に実現し、持続的な競争優位を築くことができるでしょう。今回解説した手法を参考に、自社の研修を見直し、真の行動変容につながる人材育成を実践してください。
LDcubeは、社内研修の内製化をサポートするライセンスプログラムを提供しており、研修のデジタル化や社員の学びを支える環境づくりに注力しています。これにより、現代のビジネス環境において、企業の持続的成長を支える重要な手段として広く活用されています。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。