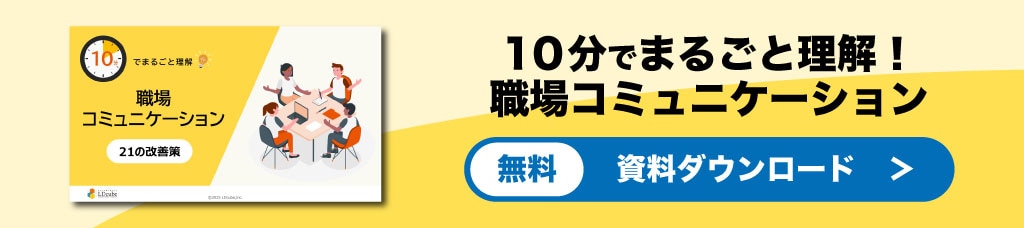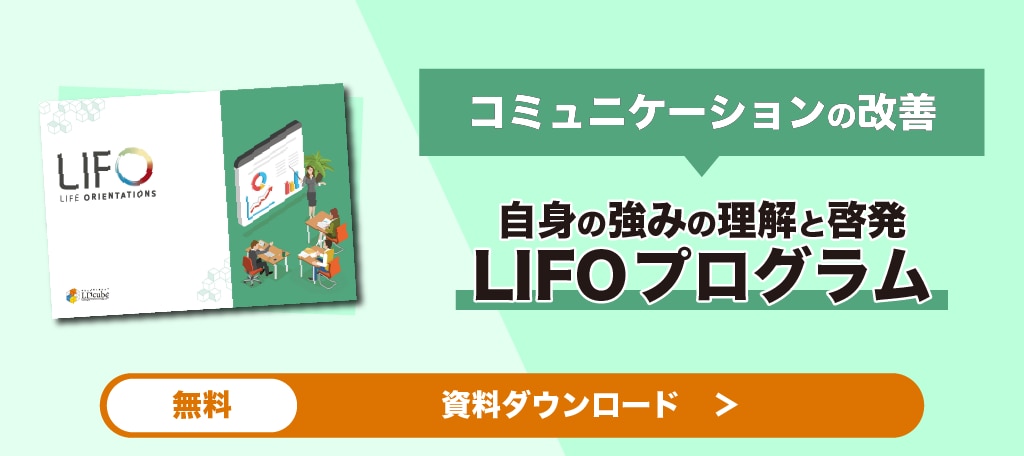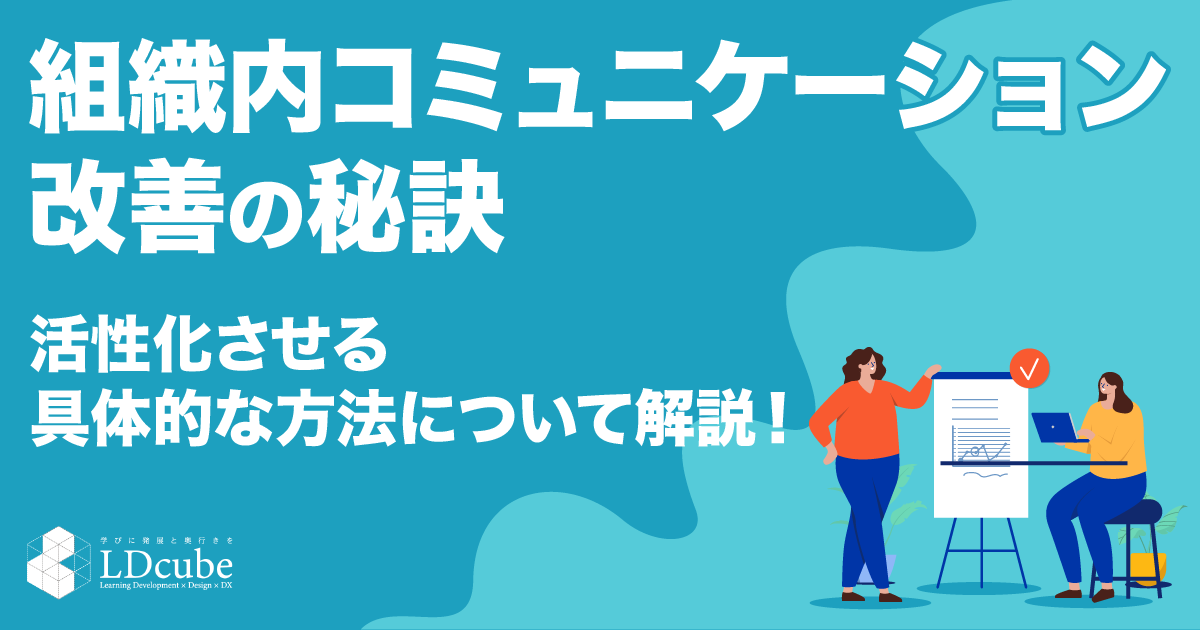
組織内コミュニケーション改善の秘訣とは?活性化させる具体的な方法について解説!
組織内コミュニケーションは、企業の成長と発展に欠かせない重要な要素です。社員間の意思疎通がスムーズに行われることで、生産性の向上やイノベーションの創出、従業員満足度の向上など、さまざまなメリットがもたらされます。
しかし、多くの企業では「報連相が不十分」「部署間の壁が厚い」「経営層と現場の認識にギャップがある」といった組織内コミュニケーションの課題を抱えています。
特に近年は、リモートワークやハイブリッドワークの浸透により、対面を前提とした従来のコミュニケーション方法では対応しきれない新たな課題も生まれています。
分散した環境での情報共有や、オンライン上での関係構築など、組織内コミュニケーションのあり方そのものを見直す必要性が高まっているのです。
本記事では、組織内コミュニケーションの基本的な定義から、不足がもたらすリスク、改善によるメリット、そして具体的な改善アプローチを体系的に解説します。
1on1ミーティングの実施方法や、ビジネスチャットツールの効果的な活用法、経営層からの透明性の高い情報発信方法など、すぐに実践できる方法をステップ形式で紹介します。
組織内のコミュニケーションを見直し、風通しの良い職場環境の構築を目指す方にとって、実践的なガイドとなる内容です。貴社の組織内コミュニケーション改善のヒントとして、ぜひご活用ください。
▼職場コミュニケーションについてはテーマに合わせて下記で解説しています。
▼職場コミュニケーションについて、21の改善策を下記にまとめています。
目次[非表示]
- 1.効果的な組織内コミュニケーションとは?
- 2.組織内コミュニケーションが不足することのリスク
- 3.リモートワーク・ハイブリッドワーク時代の組織内コミュニケーション
- 4.組織内コミュニケーションの活性化がもたらす5つのメリット
- 4.1.企業ビジョンの共有による一体感の醸成
- 4.2.従業員エンゲージメントの向上と定着率の改善
- 4.3.風通しの良い職場環境による心理的安全性の向上
- 4.4.業務効率と生産性の向上
- 4.5.部門間連携によるイノベーションの促進
- 5.組織内コミュニケーションを活性化させる7つのアプローチ
- 5.1.経営層からの透明性の高い情報発信を行う
- 5.2.アンケートによる声の可視化
- 5.3.1on1ミーティングの定期開催
- 5.4.職場単位でのワークショップの開催
- 5.5.社内イベントとチームビルディングによる関係構築
- 5.6.チャットツールによるコミュニケーション強化
- 5.7.オープンスペースとフリーアドレスによる物理的な交流の促進
- 6.組織内コミュニケーションを改善するための3ステップ
- 7.組織内コミュニケーションの活性化ならLIFO®がおすすめ!
- 8.組織内のコミュニケーションにLIFOを活用した支援事例
- 9.まとめ:組織内コミュニケーションの改善で実現する理想的な職場環境
効果的な組織内コミュニケーションとは?

組織内コミュニケーションとは、経営層から管理職、管理職から一般社員へのコミュニケーションなど、企業全体のコミュニケーションがスムーズに機能する状態を指します。組織が適切に機能して連携を取り合うためには、このコミュニケーションが欠かせません。
効果的な組織内コミュニケーションは単なる情報伝達にとどまらず、組織全体の協力体制を構築し、企業の成長と発展を支える重要な要素です。
さまざまな人と多様な手段でコミュニケーションが取れる
効果的な組織内コミュニケーションの特徴は、組織メンバーがさまざまな階層や部署を超えて自由にコミュニケーションが図れることです。経営層と現場社員、異なる部門間、ベテランと新人など、立場や役割の異なる人々が壁を感じることなく対話できる環境が重要です。
また、コミュニケーション手段も多様化しています。対面での会話、メール、ビジネスチャット、ビデオ会議、社内SNSなど、状況や目的に応じて最適な手段を選択できることが、効果的な組織内コミュニケーションの条件となっています。
これにより、緊急度や内容の重要性に合わせた適切な情報伝達が可能になります。
企業の成長と発展に不可欠な組織内コミュニケーション
組織内コミュニケーションは、企業の事業目標を達成するために不可欠な要素です。コミュニケーションが活性化することで、業務効率化や生産性向上が図れるため、自社の製品やサービスを安定的に提供することが可能になります。
特に重要なのは、組織全体でビジョンや目標を共有できることです。経営陣の描く将来像や戦略が全従業員に正確に伝わることで、各自が自分の役割を理解し、主体的に業務に取り組む環境が生まれます。
また、現場からの課題や改善提案が経営層に届くボトムアップの流れも、企業の持続的成長には欠かせません。
変化する働き方と組織内コミュニケーションの関係性
近年、テレワークやフレックスタイム制などの柔軟な働き方が普及し、組織内コミュニケーションの形も大きく変化しています。2020年以降の新型コロナウイルス感染症の流行は、この変化を加速させました。
物理的に離れた環境でも効果的なコミュニケーションを維持するために、デジタルツールの活用や非同期コミュニケーションの重要性が高まっています。
また、週に数回のオフィス出社と在宅勤務を組み合わせるハイブリッドワークが定着する中で、対面とオンラインそれぞれの特性を生かしたコミュニケーション戦略が求められています。
変化する働き方に対応した組織内コミュニケーションを構築できるかどうかが、これからの企業の競争力や組織文化の質を左右する重要な要素となっています。
コミュニケーションの活性化に関する問い合わせはこちらから!
▼職場コミュニケーションについて、21の改善策を下記にまとめています。
組織内コミュニケーションが不足することのリスク

組織内コミュニケーションが機能不全に陥ると、企業はさまざまなリスクに直面します。
企業の上層部が職場での問題を認識しながら放置している状態や、社員同士、経営陣とのコミュニケーションがうまくできていない状況は、業務にさまざまな支障をきたし、最終的には企業の業績や存続さえも脅かす可能性があります。
コミュニケーション不足の問題は小さな兆候から始まりますが、放置すればするほど深刻化していくため、早期の発見と迅速な対応が求められます。
生産性低下と業務効率の悪化
組織内コミュニケーションが不足していると、まずは業務の効率性が大きく損なわれます。情報共有がスムーズに行われないことで、同じ作業を複数の社員が重複して行ったり、すでに解決済みの問題に時間を費やしたりする無駄が生じます。
また、業務のチェック体制が整っていないことが放置されると、確認不足によるミスが増えてクレームにつながる可能性も高まります。これらのミスは単なる品質問題だけでなく、対応のための追加コストや顧客からの信頼低下など、長期的な損失をもたらします。
業務の連携が滞ることで、プロジェクトの進行も遅れがちになり、納期の遅延やサービス提供の遅れといった問題が発生します。こうした業務効率の悪化は、個人の生産性だけでなく、組織全体のパフォーマンスを低下させる要因となります。
従業員満足度低下と離職率上昇
コミュニケーションが不足している組織では、社員は孤立感を抱きやすく、仕事に対するモチベーションが低下します。特に、新入社員とのコミュニケーション不足は、教育不十分で仕事のミスやトラブルが増え、新入社員が仕事を覚える前に離職するという悪循環を生み出します。
また、社員が仕事でのプレッシャーを一人で抱え込む状況が続くと、「自分だけが我慢している」というストレスから組織に対する不満が募ります。こうした心理状態は、徐々に職場環境の雰囲気を悪化させ、周囲の社員にも負の影響を及ぼします。
エンゲージメントの高い社員であっても、コミュニケーションが少ない職場では次第に居心地が悪くなり、最終的には優秀な人材が流出するリスクが高まります。離職率の上昇は、採用・教育コストの増加、ノウハウの流出、残された社員の負担増など、さらなる問題を引き起こします。
部門間のサイロ化
コミュニケーション不足が継続すると、各部門が独自の目標や価値観を持ち、他部門と協力せずに行動する「サイロ化」が進行します。部門間の壁が高くなると、情報共有が困難になり、組織全体としての一貫した戦略実行が阻害されます。
サイロ化した組織では、部門間で重複した業務や矛盾した取り組みが発生しやすくなります。例えば、営業部門が顧客に約束した納期が生産部門の計画と合わないといった状況が生まれ、結果として顧客満足度の低下を招きます。
また、部門ごとの最適化が優先され、全体最適化が疎かになることで、リソースの無駄遣いや非効率な業務プロセスが定着してしまいます。こうした状況は、企業の変革や新しい取り組みの障壁となり、市場環境の変化への対応を鈍らせる要因となります。
心理的安全性の低下と不祥事
組織内コミュニケーションが不足すると、社員が意見や懸念を表明しにくい雰囲気が生まれ、心理的安全性が低下します。問題やリスクを発見しても指摘できない環境では、小さな問題が大きなトラブルに発展するまで見過ごされがちです。
特に深刻なのは、コンプライアンス違反や不正行為のリスク増大です。
社員の帰属意識が欠如し、他人に対して無関心になると、不正が行われていても「関係ない」と見て見ぬふりをする風潮が広がります。信頼関係が構築されていない職場では、問題を報告する文化も根付かず、不正の早期発見や未然防止が難しくなります。
このような環境は、企業不祥事や重大なコンプライアンス違反につながるリスクをはらんでおり、問題が発覚した場合は企業の社会的信用の失墜、法的制裁、そして経営危機を招く可能性があります。
▼心理的安全性については下記で詳しく解説しています。
⇒エドモンドソン博士の視点を解説!心理的安全性がビジネスに必要な理由とは?
▼職場コミュニケーションについて、21の改善策を下記にまとめています。
リモートワーク・ハイブリッドワーク時代の組織内コミュニケーション

2020年以降、新型コロナウイルス感染症の流行により、多くの企業が在宅勤務などのテレワークを導入し、働き方が大きく変化しました。この流れは収束後も続き、オフィスワークとリモートワークを組み合わせたハイブリッドワークが新たな標準となっています。
分散した環境でも業務効率や生産性を維持するためには、組織内コミュニケーションの質をいかに確保するかが重要な課題となっています。
分散型の勤務環境における情報格差の発生と対策
リモートワークやハイブリッドワークでは、物理的に離れた環境で働く社員間に情報格差が生じやすくなります。
例えば、オフィスに出社している社員には自然と伝わる情報が、リモートワーク中の社員には届かないという「情報の非対称性」が発生します。この問題に対処するためには、情報共有の仕組みを意図的に構築する必要があります。
具体的には以下の対策が効果的です。
|
オンライン会議の質を高めるファシリテーション技術
リモート環境では対面でのコミュニケーションに比べて非言語情報が限られるため、オンライン会議は一方通行になりがちで、参加者の集中力維持も課題となります。こうした状況を改善するには、オンライン会議特有のファシリテーション技術が不可欠です。
効果的なオンライン会議のファシリテーションを行うには、以下のポイントを押さえることが重要です。
|
特に重要なのは、オンライン会議の運営ルールを組織内で標準化し、全員が同じ理解のもとで参加できる環境を整えることです。
これにより、リモート環境でも活発な意見交換と効率的な意思決定が可能になります。
非同期コミュニケーションを効果的に活用する仕組み
ハイブリッドワーク環境では、全員が同時に同じ場所にいることが少なくなるため、リアルタイムでのコミュニケーション(同期コミュニケーション)だけでなく、時間差のある非同期コミュニケーションの重要性も高まっています。
非同期コミュニケーションを効果的に活用するためには、次のような仕組みづくりが大切です。
|
複数の連絡手段を使用することで情報共有効率の低さが課題となりやすいですが、ビジネスチャットなどのツールの導入により連絡手段を統一し、効率的な情報伝達を実現することができます。
適切な非同期コミュニケーションツールと活用ルールを整備することで、時間や場所の制約を超えた柔軟な働き方と効率的な情報共有の両立が可能になります。
▼職場コミュニケーションについて、21の改善策を下記にまとめています。
組織内コミュニケーションの活性化がもたらす5つのメリット

組織内コミュニケーションが適切に機能する企業には、さまざまな恩恵があります。例えば、単に情報伝達がスムーズになるだけでなく、組織全体の活力や競争力を高める効果があります。
ここでは、組織内コミュニケーションを活性化させることで得られる5つの主要なメリットについて解説します。これらのメリットを理解することで、コミュニケーション改善に向けた取り組みの重要性がより明確になるでしょう。
企業ビジョンの共有による一体感の醸成
組織内コミュニケーションの活性化により、企業全体で会社が掲げるビジョンや経営理念を共有することができます。経営層の描く将来像や戦略的方向性が全社員に正確に伝わることで、組織としての一体感が生まれます。
この一体感は、社員が「同じ目標に向かって進んでいる」という連帯感を持つことにつながり、業務へのモチベーション向上に寄与します。
特に、ミッションやビジョンが明確に共有されている組織では、社員一人一人が自分の役割と全体の中での位置づけを理解し、主体的に行動するようになります。
また、企業ビジョンの共有は、目標達成に向けた組織全体の方向性をそろえる効果もあります。部署や個人が独自の解釈で動くことなく、一貫した取り組みが可能になり、経営資源の効率的な活用にもつながります。
従業員エンゲージメントの向上と定着率の改善
活発なコミュニケーションが行われる職場では、社員が自分の意見や考えを表明する機会が増え、「会社に貢献している」「価値ある存在として認められている」という実感を得やすくなります。この感覚は従業員のエンゲージメント向上に直結します。
高いエンゲージメントを持つ社員は、自発的に業務改善に取り組み、チームの成果向上に貢献する傾向があります。また、会社に対する帰属意識が強まることで、離職率の低下にも効果があります。優秀な人材の流出を防ぎ、採用・教育コストの削減にもつながる重要な要素です。
特に注目すべきは、若手社員の定着率への影響です。コミュニケーションが活発な職場は新入社員にとって疑問や不安を解消しやすく、早期の離職を防ぐ効果があります。長期的な人材育成の観点からも、組織内コミュニケーションの活性化は重要な施策と言えるでしょう。
風通しの良い職場環境による心理的安全性の向上
組織内コミュニケーションが活性化すると、上下間や横のつながりで気軽に意見を発信しやすい環境が生まれます。このような風通しの良さは、社員が失敗を恐れずにチャレンジしたり、問題点を指摘したりできる「心理的安全性」を高めます。
心理的安全性が確保された職場では、イノベーションが生まれやすくなります。新しいアイデアや改善提案が活発に出され、それを受け入れる土壌があることで、組織全体の創造性と問題解決能力が向上します。
また、悩みや困りごとを相談しやすい環境は、社員のストレス軽減にも効果があります。問題が小さいうちに解決できるため、深刻化を防ぎ、結果として社員のメンタルヘルスの改善にもつながります。
このように、風通しの良い職場環境は、人間関係のトラブル予防や職場の雰囲気改善にも大きく貢献します。
▼心理的安全性の作り方については下記で詳しく解説しています。
⇒「心理的安全性」その本質・作り方とは?今すぐ取り組みたい20の具体策を解説!
業務効率と生産性の向上
コミュニケーションに齟齬や無駄がない組織では、効率的に作業が進められます。情報共有が適切に行われることで、重複業務の削減や決断の迅速化が実現し、業務効率の大幅な向上につながります。
例えば、複数の部署が関わるプロジェクトでは、情報の透明化と共有が進むことで各担当者の役割が明確になり、プロジェクト全体の進行がスムーズになります。
また、問題発生時の報告・連絡・相談がタイムリーに行われることで、早期解決が可能になり、ビジネスへの影響を最小限に抑えられます。
さらに、ナレッジや経験の共有が進むことで、組織全体の学習速度も向上します。ベストプラクティスが共有されることで、個人の成長だけでなく、組織の能力向上につながり、結果として生産性の継続的な改善が実現します。
部門間連携によるイノベーションの促進
組織内コミュニケーションにおいては、企業全体の事業目標を実現させるために、部署間の垣根を越えて連携し合う行動力が求められます。この部門間連携がスムーズになることで、多様な知識や視点が交わり、新たなアイデアやイノベーションが生まれやすくなります。
異なる専門性を持つ部門同士が協力することで、従来では思いつかなかった斬新な解決策が生まれることがあります。例えば、営業部門とエンジニアリング部門が密に連携することで、顧客ニーズに直結した製品開発が可能になるなど、ビジネス成果の向上につながります。
また、部門間の連携強化は、組織全体の問題解決能力を高めます。個別の部署では解決が難しい課題も、複数の部門が協力することで効果的に対処できるようになります。
このように、部門間の壁を低くし、全社的な視点で考え、行動できるという文化を醸成することは、企業の持続的な成長と競争力強化に不可欠な要素となります。
▼職場コミュニケーションについて、21の改善策を下記にまとめています。
組織内コミュニケーションを活性化させる7つのアプローチ

組織内のコミュニケーションを活性化させるためには、計画的かつ戦略的なアプローチが必要です。単に「もっと話し合おう」という掛け声だけでは、真の改善は見込めません。
ここでは、組織内コミュニケーションを効果的に活性化させるための7つの具体的なアプローチを紹介します。これらの方法は、企業規模や業種に関わらず応用可能であり、組み合わせて実施することでより大きな効果を発揮します。
経営層からの透明性の高い情報発信を行う
組織内コミュニケーションの活性化には、まず経営層からの透明性の高い情報発信が欠かせません。企業の方向性や重要な意思決定、業績状況などを定期的に共有することで、社員の信頼感を醸成し、組織全体の一体感を高めることができます。
効果的な情報発信のポイントは、タイミングと内容の適切さです。特に重要な経営判断については、その背景や理由も含めて説明することで、社員の理解と納得が得られやすくなります。また、良いニュースだけでなく課題や問題点も共有する姿勢が、組織の信頼文化を築く基盤となります。
情報の発信方法としては、全社ミーティング、経営層による定期的なメッセージ配信、社内ポータルサイトでの情報共有などが効果的です。特に近年は、ビジネスチャットツールのタスク管理機能やお知らせ機能を活用して、経営層からの方針や意図、経営理念を効率的に伝達する取り組みも増えています。
アンケートによる声の可視化
組織内コミュニケーションを活性化させるためには、社員の声を収集し可視化することが重要です。定期的なアンケート調査は、現場の実情や課題、社員の本音を把握するための効果的な手段です。
アンケートを実施する際のポイントは、以下の点に注意することです。
|
特に重要なのは、アンケート結果を形だけのものにせず、実際の改善につなげる仕組みづくりです。収集した意見や要望に対して、どのような対応を行ったかを明確に示すことで、「声を上げると変わる」という実感を社員に持ってもらうことができます。
これにより、さらなる意見表明が促進され、組織内コミュニケーションの好循環が生まれます。
1on1ミーティングの定期開催
上司と部下で行われる1on1ミーティングは、個別のコミュニケーションを深め、信頼関係を構築するための重要な施策です。
定期的な1on1ミーティングを通じて、業務の進捗確認だけでなく、キャリア開発や個人的な悩み、改善提案などについても話し合う機会を設けることが大切です。
効果的な1on1ミーティングの実施ポイントは以下の通りです。
|
1on1ミーティングは、日常業務では表面化しにくい潜在的な問題や改善アイデアを引き出す機会となります。また、社員一人一人が「自分は見られている、大切にされている」と感じることで、組織への帰属意識やモチベーション向上にもつながります。
特に若手社員の育成や定着率向上においては、この個別コミュニケーションの質が大きな影響を与えます。
▼1on1ミーティングについては下記で詳しく解説しています。
⇒1on1ミーティングとは?目的ややり方、効果を高める工夫を解説!
職場単位でのワークショップの開催
チームや部署単位でのワークショップは、メンバー間の相互理解を深め、共通の課題に対する解決策を協働で考える機会として有効です。
定期的にワークショップを開催することで、日常業務では見えにくいメンバーの考えや強みを発見し、チームとしての結束力を高めることができます。
効果的なワークショップの設計ポイントとしては、以下の要素が挙げられます。
|
ワークショップを通じて多様な意見やアイデアが共有されることで、イノベーションが生まれやすい環境が整います。
また、普段の業務では接点の少ないメンバー同士が交流することで、部署内の情報流通が活性化し、協力体制の強化にもつながります。
▼職場単位でワークショップを行うことが有効な理由については下記で詳しく解説しています。
⇒職場の活性化につなげる方法とは?アイデアやポイントを紹介!
社内イベントとチームビルディングによる関係構築
仕事以外での交流機会を設けることは、社員同士の人間関係を豊かにし、組織のつながりを活性化させる効果的な方法です。
社内イベントやチームビルディング活動を通じて、普段の業務では見ることのできない同僚の一面を知り、相互理解を深めることができます。
効果的な社内イベントやチームビルディング活動としては、以下のようなものが挙げられます。
|
これらの活動を通じて社内の人間関係が豊かになると、業務上のコミュニケーションもよりスムーズになります。
相手の価値観や考え方への理解が深まることで、日常の業務における連携もより円滑に行われるようになり、結果として仕事へのモチベーションアップにもつながるでしょう。
▼チームビルディング研修については下記で詳しく解説しています。
⇒チームビルディング研修を企業で行う際のポイントとは?おすすめ展開法も紹介!
チャットツールによるコミュニケーション強化
ビジネスチャットツールの導入は、組織内コミュニケーションを効率化・活性化させる強力な手段です。
特にリモートワークやハイブリッドワークが増加している現代においては、デジタルツールを活用したコミュニケーション基盤の整備が不可欠となっています。
ビジネスチャットツールが組織内コミュニケーションに与える効果には、以下のようなものがあります。
|
ビジネスチャットの導入にあたっては、単にツールを導入するだけでなく、使用ルールやガイドラインの策定、定期的な活用状況の確認など、定着に向けた取り組みも重要です。
オープンスペースとフリーアドレスによる物理的な交流の促進
オフィス環境の工夫も、組織内コミュニケーションを活性化させる重要な要素です。
特に、オープンスペースの設置やフリーアドレス制の導入は、物理的な交流を促進し、部署を超えたコミュニケーションの機会を創出します。
フリーアドレスを活用する主なメリットには、以下のようなものがあります。
|
オープンスペースやフリーアドレスを効果的に機能させるためには、静かに集中して作業できるスペースと、活発に議論できるコラボレーションエリアのバランスが重要です。
また、デジタルツールとの連携を考慮し、オンラインミーティングを行いやすい環境も整備する必要があります。リモートワークが増えている現代においても、対面でのコミュニケーションの価値は依然として高いです。
オフィスに集まる時間を最大限有効活用できるよう、物理的な環境を工夫することで、デジタルコミュニケーションでは得られない関係構築や創造的な対話を促進することができます。
▼職場コミュニケーションについて、21の改善策を下記にまとめています。
組織内コミュニケーションを改善するための3ステップ

組織内コミュニケーションを改善するためには、一時的な施策ではなく、体系的かつ継続的なアプローチが必要です。
ここでは、組織内コミュニケーションを効果的に改善するための3つのステップを紹介します。これらのステップに沿って計画的に取り組むことで、持続可能なコミュニケーション改革を実現することができます。
STEP1.現状分析と課題の可視化
組織内コミュニケーションの改善の第一歩は、現状を正確に把握し、具体的な課題を可視化することです。現状分析では、組織全体のコミュニケーションの流れや障壁を客観的に評価し、改善すべきポイントを明確にします。
現状分析の方法としては、以下のようなアプローチが効果的です。
|
特に重要なのは、経営層・管理職・一般社員といった異なる立場からの視点を収集することです。同じ組織でも、立場によってコミュニケーション上の課題認識が大きく異なることがあります。
また、部署ごとや拠点ごとの違いにも注目し、組織全体の傾向と局所的な問題を区別して把握することが大切です。
課題が可視化されたら、優先順位を付けて取り組むべき項目を整理します。全ての問題を一度に解決することは難しいため、組織への影響が大きく、比較的短期間で改善可能な課題から着手することで、成功体験を積み重ねていくことが重要です。
STEP2.改善の具体的目標とKPI設定
現状分析で特定した課題に基づき、改善のための具体的な目標とKPI(重要業績評価指標)を設定します。抽象的な「コミュニケーション改善」ではなく、測定可能で具体的な目標を立てることが成功の鍵となります。
効果的なKPI設定のポイントとしては、以下のような要素があります。
|
例えば、「6カ月以内に従業員エンゲージメントスコアを10%向上させる」「1年以内に部門間のコラボレーションプロジェクト数を30%増加させる」など、具体的で測定可能な目標を設定します。
また、改善施策とKPIの関連性を明確にし、どの取り組みがどの指標の改善に寄与するかを整理しておくことも重要です。これにより、施策の効果を正確に評価し、必要に応じて軌道修正を行うことが可能になります。
STEP3.施策の段階的導入と効果測定
目標とKPIが設定されたら、具体的な改善施策を段階的に導入していきます。一度に全ての改革を進めるのではなく、優先度の高い施策から順に実施し、効果を測定しながら進めていくことが重要です。
施策導入と効果測定のサイクルは、以下のようなプロセスで行います。
|
効果測定においては、定量的な指標だけでなく、定性的なフィードバックも重視します。例えば、「会議の効率が上がった」「情報共有がスムーズになった」といった現場の声も、重要な成果指標となります。
また、コミュニケーション改善の取り組みは一過性のものではなく、継続的な改善サイクルとして捉えることが大切です。
定期的に現状を再評価し、変化する組織のニーズや環境に合わせて施策を更新していくことで、持続可能なコミュニケーション文化を築くことができます。
▼職場コミュニケーションについて、21の改善策を下記にまとめています。
組織内コミュニケーションの活性化ならLIFO®がおすすめ!

組織内コミュニケーションの活性化には自己診断ツールLIFO(Life Orientations)を活用した職場単位でのワークショップがおすすめです。
なぜなら、LIFOプログラムは心理学や行動科学をベースにして組み立てられた行動特性診断をベースに、職場単位でワークショップを行うためのワークブックなどのツールも体系的にそろえられているからです。
また、体系立てられたツールの使い方を社内トレーナーの方々にライセンス提供もされており、社内トレーナーの方々が職場単位でワークショップを展開していくことも可能です。下記に概要を紹介します。
自己診断ツールLIFOとは
LIFO(Life Orientations)は、個人の行動スタイルを診断する自己診断ツールです。このツールは、自分の強みや行動パターンを理解するために役立ちます。
LIFOは4つの基本スタイルに基づいており、これらのスタイルはそれぞれ異なる行動特性や価値観を持っています。
自分がどのスタイルに属しているかを知ることで、より良いコミュニケーション方法やストレス時の行動傾向を把握することができます。
LIFOを活用したコミュニケーション研修
LIFOを活用したコミュニケーション研修では、まず参加者が自己診断を行い、自分の行動スタイルを理解します。
この診断結果を基に、どのようにして他者と効果的にコミュニケーションを取るかを学びます。
研修では以下のような内容が含まれます。
|
LIFOを取り入れた研修に参加することで、個人のコミュニケーションスタイルを理解し、それをベースに他者との関係を改善するスキルを獲得できます。
これにより、職場や日常生活でのコミュニケーションがよりスムーズで効果的になることが期待できます。
LIFO®プログラムは社内トレーナーで展開可能
LIFO®プログラムは、これまでの活用実績と実用性から、企業内でのトレーニングにおいて自信を持っておすすめできるプログラムです。
社内展開にあたっては、特定の準備と手続きを経ることで、コストを抑えながら、外部講師に委託したかのように、社内トレーナーによる効果的なプログラムを展開することが可能です。
以下に、その流れを詳しく説明します。
|
組織内のコミュニケーションにLIFOを活用した支援事例

株式会社山梨放送/放送業
導入前の課題
新型コロナウイルス感染症の流行以前は、社内イベントを通じて活発にコミュニケーションが行われていましたが、コロナ禍により社内の人間関係が希薄化し、特に若手社員の早期離職が顕著になりました。
また、放送業界の人手不足と業務の多忙さから、社員教育には力を入れられずにいました。そこで、70周年プロジェクトの一環として「シゴトバ改革」を推進することが決まり、社員が自発的に提案し実行に移すボトムアップ型のアプローチを採用しました。
出会いと導入の決め手
各局や地元企業の事例調査によって、1on1ミーティングが効果的であると分かりましたが、社員の個性を理解するまでには至りませんでした。
キャリアコンサルタントの提案で、相互理解を深めるためにLIFO診断を導入しました。LIFOはその場で診断結果を得られるため、柔軟な勤務時間を抱える社員にも受検しやすく、コミュニケーション改善のツールとして活用が決定されました。
展開ステップと取り組み
1on1ミーティングを実施前に、全社員を対象にLIFOの活用法などを盛り込んだセミナーを実施しました。管理職と一般社員に分けたセミナーで、ミーティングの目的やLIFOの活用法を学びました。
セミナーを契機に、多くの社員が参加し、テーマへの高い関心が示されました。セミナー内容を随時アーカイブとして提供し、参加できなかった社員にも情報を共有しました。
導入後の感想と成果
LIFOの活用で、上司と部下の相互理解が進み、コミュニケーションのきっかけとなりました。1on1ミーティングでは、定期的にLIFOのスコアが話題となるなど、一歩踏み込んだ対話が実現しています。
中には、得られた結果を基に改善に取り組む社員も出始めています。このツールは、管理職のガイドとなり得る可能性があり、引き続きLIFOを活用していく方針です。
取り組みにおける課題と今後の展望
「シゴトバ改革」はボトムアップ式で進行しているため、部署ごとに進捗に差があります。また、1on1ミーティングの目的が理解されず、不満のぶつけ合いになるケースもあるため、意識改革が必要です。
社内通信などでLIFOの考え方を広め、1on1以外にも日常のコミュニケーションやチームビルディングに活用することを目指しています。特に新体制時や社員異動時に効果的であり、職場の活気を向上させることを期待しています。
▼事例の詳細については下記をご覧ください。
⇒株式会社山梨放送様 LIFO導入事例
まとめ:組織内コミュニケーションの改善で実現する理想的な職場環境
組織内コミュニケーションの改善の秘訣とは?活性化させる具体的な方法について解説!について紹介してきました。
- 効果的な組織内コミュニケーションとは?
- 組織内のコミュニケーションが不足することのリスク
- リモートワーク・ハイブリッドワーク時代の組織内コミュニケーション
- 組織内コミュニケーションの活性化がもたらす5つのメリット
- 組織内コミュニケーションを活性化させる7つのアプローチ
- 組織内コミュニケーションを改善するための3ステップ
- 組織内コミュニケーションの活性化ならLIFO®がおすすめ!
- 組織内のコミュニケーションにLIFOを活用した支援事例
組織内コミュニケーションの改善は、単なる情報伝達の効率化にとどまらず、企業の持続的成長と競争力強化の基盤となる重要な取り組みです。本記事で解説してきたように、効果的な組織内コミュニケーションは、生産性向上、従業員満足度の向上、イノベーションの促進など、多岐にわたる価値を組織にもたらします。
組織内コミュニケーションを改善することで実現する理想的な職場環境は、「情報が適切に流れ、全員が目的を共有し、互いに尊重し合いながら協力して成果を創出する場」と言えるでしょう。
このような環境では、社員一人一人が自分の役割と価値を認識し、主体的に業務に取り組むことができます。また、心理的安全性が確保されることで、失敗を恐れずに挑戦し、学び合う文化が醸成されます。
特に現代のビジネス環境においては、リモートワークやハイブリッドワークなど、働き方の多様化が進む中で、意図的かつ戦略的なコミュニケーション設計がこれまで以上に重要になっています。物理的に離れていても心理的な距離を縮め、組織としての一体感を維持するためには、デジタルツールの活用と対面コミュニケーションの最適な組み合わせが鍵となります。
組織内コミュニケーション改善の取り組みは、一朝一夕に成果が出るものではありません。経営層のコミットメントのもとで、現状分析から始まり、具体的目標の設定、施策の段階的導入と効果測定を通じて継続的に改善していくプロセスが必要です。また、組織の成長段階や事業環境の変化に合わせて、コミュニケーション戦略も柔軟に進化させていくことが大切です。
最後に、組織内コミュニケーションの本質は「人と人とのつながり」にあることを忘れてはなりません。どれだけ先進的なツールを導入しても、最終的に重要なのは、互いを理解し尊重する姿勢や、情報の透明性と信頼に基づく関係性です。一人一人が当事者意識を持ち、組織全体のコミュニケーション文化向上に貢献することで、真に強靭で持続可能な組織が実現するのです。
組織内コミュニケーションの改善に終わりはありません。変化し続ける環境の中で、常に最適なコミュニケーションのあり方を模索し、実践していくことが、これからの組織に求められる重要な課題と言えるでしょう。
株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。