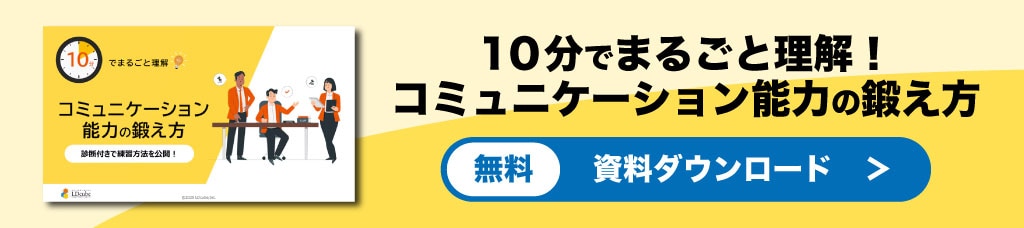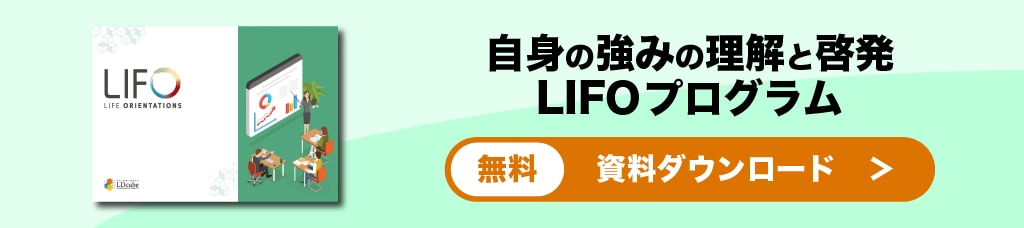効果的な「コミュニケーショントレーニング」とは?日頃から高める実践方法も解説!
コミュニケーションスキルは、ビジネスの成功において欠かせない要素です。しかし、多くの企業ではコミュニケーション不足による仕事の生産性低下や人間関係のトラブルが課題となっています。
このような状況を改善するために注目されているのが「コミュニケーショントレーニング」です。適切なトレーニングを実施することで、社員一人一人の伝える力や聴く力が向上し、組織全体の活性化につながります。
特に近年は、テレワークやハイブリッドワークの普及によって対面でのコミュニケーション機会が減少しており、意識的にコミュニケーション能力を鍛える必要性が高まっています。
本記事では、即効性の高いコミュニケーショントレーニングの実践法を7つご紹介します。アクティブリスニングからフィードバック技術まで、すぐに職場で活用できる手法を解説します。
さらに、これらのトレーニングを組織全体に導入するステップや、継続的な効果を生み出す体制づくりについても詳しく解説していきます。
コミュニケーション能力は一朝一夕で身に付くものではありませんが、適切な方法で継続的に取り組むことで確実に向上します。この記事を参考に、あなたの組織のコミュニケーション課題を解決し、活力ある職場づくりを実現してください。
▼コミュニケーションについては下記で詳しく解説しています。
▼コミュニケーション能力の鍛え方についてのお役立ち資料は下記からダウンロードできます。
目次[非表示]
- 1.コミュニケーショントレーニングは大きく2種類
- 2.コミュニケーショントレーニングとは?企業が注目する理由
- 3.コミュニケーショントレーニングで解決したい組織の課題
- 4.すぐできるコミュニケーショントレーニング7つの実践法
- 4.1.アクティブリスニングの強化
- 4.2.エレベータートークで磨く簡潔な伝達力
- 4.3.ミラーリングで高める非言語コミュニケーション能力
- 4.4.バックトラッキングを活用した、聴く力の向上法
- 4.5.パラフレーズ練習による表現力強化トレーニング
- 4.6.ロープレで実践するコミュニケーション状況再現
- 4.7.建設的なフィードバック交換の訓練
- 5.専門家によるコミュニケーショントレーニング実施の流れ
- 5.1.コミュニケーション上の課題を特定するための現状把握
- 5.2.研修会社などの専門家に相談
- 5.3.課題解決のためのトレーニング内容の企画
- 5.4.コミュニケーショントレーニングの実施
- 5.5.トレーニング効果についての振り返り
- 5.6.実は社内トレーナーという選択肢もある
- 6.コミュニケーショントレーニングの効果を継続させるコツ
- 7.コミュニケーショントレーニングならLIFO®がおすすめ!
- 8.LIFOでコミュニケーショントレーニングを展開した支援事例(日本新薬)
- 9.まとめ:効果的なコミュニケーショントレーニングで組織の活力を高めよう
コミュニケーショントレーニングは大きく2種類

コミュニケーション能力は、ビジネスにおいて最も重要なスキルの1つであり、適切なトレーニングによって誰でも向上させることができます。
コミュニケーショントレーニングは大きく分けて2種類あり、目的に応じて選択することが重要です。
日頃から意識することですぐにできるトレーニング
日常の中で取り入れられるコミュニケーショントレーニングは、特別な準備や環境を必要とせず、すぐに実践できるのが特徴です。
例えば、会議や打ち合わせの場で「アクティブリスニング(積極的傾聴)」を心がけたり、相手の話を最後まで聞く習慣をつけたりすることが挙げられます。
これらの日常的なトレーニングは手軽に行いやすく、日々の生活の中で自然と身に付けられるというメリットがあります。
職場で笑顔であいさつする、メールの文面を読み返して分かりやすさを確認する、相手の立場に立って話を聞くなど、小さな意識の積み重ねが大きな変化をもたらします。
専門家から指導を受けて行うトレーニング
より本格的なコミュニケーション能力の向上を目指す場合は、専門家から指導を受けるトレーニングが効果的です。外部講師を招いた研修や専門機関によるワークショップなどがこれにあたります。
専門家によるトレーニングでは、理論的背景を学びながら、ロープレなどの実践的な演習を通じて体系的にスキルを習得します。
専門家による指導の強みは、客観的な視点からのフィードバックが得られることです。自分では気付かない癖や改善点を専門的な知見から指摘してもらえるため、効率的にスキルアップできます。
また、組織的に展開することで、組織全体で同じ手法を共有できるため、チーム内のコミュニケーション改善にも効果的です。
コミュニケーショントレーニングとは?企業が注目する理由

コミュニケーショントレーニングとは、人と人との情報共有や意思疎通をスムーズに行うための能力を向上させる取り組みです。コミュニケーションの語源はラテン語の「コミュニス(communis)」で、「共有する」「分かち合う」という意味を持ちます。
単に「話す」ことではなく、相手と情報や気持ちを共有し、互いに理解し合うための双方向のプロセスなのです。
ビジネスにおけるコミュニケーション能力の重要性
ビジネスの現場において、コミュニケーション能力はあらゆる業務の基盤となります。社内での情報共有やチームでの協業、顧客との信頼関係構築など、業務のあらゆる場面でコミュニケーションが鍵を握っています。
コミュニケーション能力は4つの要素から構成されています。「言語を用いて自分の考えを伝える力」「非言語(表情や身ぶり)で感情や意図を伝える力」「相手の言葉を正確に理解する力」「相手の非言語的表現から真意を読み取る力」です。これらのバランスが取れていることで、効果的なコミュニケーションが実現します。
特に、リーダーシップを発揮する立場の人材には高度なコミュニケーション能力が求められます。チームの方向性を示し、メンバーのモチベーションを高めるためには、的確に情報を伝え、相手の気持ちに寄り添う能力が不可欠です。
リアルのコミュニケーションが減ってきている
近年のデジタル化とともに、私たちのコミュニケーション方法は大きく変化しています。特に2020年以降の新型コロナウイルスの影響により、テレワークやオンライン会議が普及し、対面でのコミュニケーション機会が大幅に減少しました。
多くの人がコミュニケーションを苦手と感じており、その傾向はリモートワーク環境下でさらに強まっています。
デジタルツールを介したコミュニケーションでは、非言語情報が伝わりにくくなります。メラビアンの法則によれば、コミュニケーションにおいて伝えたいメッセージの55%は視覚的要素、38%は聴覚的要素で伝わるとされており、言葉そのものは7%にすぎないと言われています。
また、リモートワークの普及により、偶発的な会話や雑談の機会も減少しています。このような状況下で、意識的にコミュニケーション能力を高める取り組みの重要性が増しているのです。
▼職場コミュニケーションにおける雑談の有用性については下記で詳しく解説しています。
⇒職場コミュニケーションのカギは雑談にあり|組織的に効果を出すコツを解説!
コミュニケーショントレーニングで得られる3つのメリット
1つ目は「生産性の向上」です。効果的なコミュニケーションは業務の効率化に直結します。指示や情報が正確に伝わることで誤解によるやり直しが減少し、チーム内での認識のズレも最小限に抑えられます。
2つ目は「チームワークと職場環境の改善」です。良好なコミュニケーションは信頼関係の構築に貢献し、チームの一体感を高めます。お互いの考えや感情を理解し合える環境では、メンバー同士の協力が促進され、創造的な議論も活発になります。
3つ目は「顧客満足度と対外的な評価の向上」です。社員のコミュニケーション能力が高まると、顧客とのやり取りもスムーズになります。顧客のニーズを的確に捉え、適切な提案や対応ができるようになることで、顧客満足度が向上します。
コミュニケーショントレーニングで解決したい組織の課題

企業がコミュニケーショントレーニングを導入する背景には、さまざまな組織課題があります。代表的な問題として、社員のコミュニケーション能力の不足、職場の活気の低下、問題の早期発見の難しさなどが挙げられます。
課題の本質を理解することで、より的確なトレーニング方法を選択できます。
コミュニケーション能力が低い社員を減らしたい
コミュニケーション能力が低い社員の存在は、チーム全体の生産性や職場環境に影響を与えます。一方的に話し続ける、相手の話を最後まで聞かない、非言語コミュニケーションに無頓着である、自己中心的なコミュニケーションを取る、フィードバックを受け入れられないといった特徴が見られます。
これらの特徴を持つ社員は、意図せずに情報共有を阻害したり、人間関係に亀裂を生じさせたりする可能性があります。例えば、会議で1人が長々と話し続けると、他のメンバーの発言機会が失われ、多様な視点からの意見交換ができなくなります。
コミュニケーション能力が低い社員を減らすためには、まず自分のコミュニケーションパターンを客観的に認識させることが重要です。会話の録音・録画を振り返る、同僚からのフィードバックを受けるなどの方法が効果的です。
まずは、効果的にコミュニケーションが取れていないということを正しく認識するところから始まります。
活気を高め生産性を向上させたい
職場の活気が低下すると、情報共有が滞り、創造的なアイデアが生まれにくくなり、結果として組織の生産性が低下します。特に、リモートワークの普及により、物理的な距離が心理的な距離にもつながっています。
活気のある職場と活気が低下している職場の大きな違いは、コミュニケーションの質と量にあります。活気ある職場では、業務情報の交換だけでなく、カジュアルな会話や感情の共有も自然に行われています。このような環境では、メンバー間の信頼関係が構築され、心理的安全性が確保されやすくなります。
コミュニケーショントレーニングを通じて、「相手に関心を持つ」「積極的に質問する」「肯定的なフィードバックを増やす」といった具体的な行動を促すことで、職場の活気を高めることができます。
問題を早期にキャッチできるようにしたい
ビジネスにおいて、問題が大きくなる前に早期発見することは非常に重要です。しかし、コミュニケーションが不足していると、問題の兆候を見逃してしまう可能性があります。
問題の早期発見を阻害する要因として、「報告することへの心理的障壁」が挙げられます。多くの場合、社員は自分の失敗や懸念を報告することに抵抗や後ろめたさを感じます。
「問題を起こした責任を問われるのではないか」「無能だと思われるのではないか」といった恐れから、重要な情報を共有しないことがあります。
効果的なコミュニケーショントレーニングでは、問題報告を奨励する文化の醸成を目指します。「失敗から学ぶ姿勢を評価する」「問題提起に対して感謝の意を表す」「非難せずに解決策を共に考える」といった行動を組織全体に浸透させることが重要です。
すぐできるコミュニケーショントレーニング7つの実践法

コミュニケーション能力を高めるためには、日常業務の中で継続的に実践できるトレーニング方法が重要です。特別な準備や環境を必要とせず、すぐに始められる7つの方法を紹介します。
アクティブリスニングの強化
アクティブリスニングとは、単に相手の話を聞くだけでなく、積極的に理解しようとする姿勢で聴くスキルです。このスキルは、信頼関係構築において非常に重要な役割を果たします。
実践するには、まず相手に対して全身で注意を向けることが大切です。視線を合わせ、相手の方に体を向け、スマートフォンなどの気が散る要素を排除します。次に、相手の話を遮らず、最後まで聞く姿勢を持ちましょう。
さらに効果的なのは、適切なタイミングで相づちを打ったり、うなずいたり、質問したりすることです。また、相手の話の要点を自分の言葉で言い換えて確認する「要約」も有効です。多くの反応を示すことで、相手は自分の話をしっかりと聞いてくれているという実感が高まります。
エレベータートークで磨く簡潔な伝達力
エレベータートークとは、エレベーターで数階分の短い時間(30秒〜1分程度)で、相手に自分の伝えたいことを印象的に伝えるスキルです。限られた時間内に要点を絞って話す能力を鍛えるのに最適です。
練習するには、まず伝えたい内容を30秒以内に収まるよう整理します。PREP法(Point-Reason-Example-Point)を活用すると効果的です。最初に結論を述べ、その理由を簡潔に説明し、具体例を挙げ、最後に再度結論を強調する構成です。
日常業務では、上司への報告や同僚との情報共有の際に、意識的に簡潔にまとめる習慣をつけることがおすすめです。余計な言葉を省き、核心を捉えた表現に磨きをかけることで、相手に伝わりやすいコミュニケーション能力が身に付きます。
ミラーリングで高める非言語コミュニケーション能力
ミラーリングとは、相手の動作や姿勢、話し方のテンポなどを自然にまねることで、無意識のうちに親近感や信頼感を醸成するテクニックです。人は自分と似た振る舞いをする相手に対して、無意識に親しみを感じる傾向があります。
実践する際のポイントは、あくまで自然に行うことです。相手の姿勢や話すテンポ、使う言葉のパターンなどを少しずつ取り入れていきます。例えば、相手がゆっくりと話すなら自分もペースを落とすといった具合です。
まず観察力を高めることから始め、相手の特徴的な仕草や話し方のパターンを意識的に観察します。そして、少しずつそれらを自分のコミュニケーションに取り入れていきましょう。
バックトラッキングを活用した、聴く力の向上法
バックトラッキングとは、相手の言った言葉をそのまま繰り返す技術で、カウンセリングなどでも広く用いられています。「相手の話をしっかり聴いている」ことを示すとともに、自分自身の理解を確認する効果があります。
ポイントは、相手の言葉を機械的に繰り返すのではなく、感情や意図にも注意を払いながら、要点を捉えて返すことです。例えば「このプロジェクトは予想以上に難航しています」という発言に対して、「予想以上に難航して、ご苦労されているんですね」と返します。
日常業務では、重要な会議や1対1の対話の場面で意識的に取り入れてみましょう。相手の発言の後に「つまり〜ということですね」と要約するのも良いでしょう。
パラフレーズ練習による表現力強化トレーニング
パラフレーズとは、相手の言ったことや文章を、別の言葉で言い換えるテクニックです。同じ内容でも、言い方を変えることで、より分かりやすく伝えたり、専門用語をかみ砕いて説明したりすることができます。
トレーニング方法としては、専門用語や業界特有の用語を、専門知識のない人にも理解できるように言い換える練習が効果的です。例えば「ROI」を「投資に対してどれだけ利益が出るかを示す指標」と言い換えます。
日常的な練習としては、ニュース記事や専門書の内容を、小学生にも理解できるように説明する練習が役立ちます。また、会議やプレゼンテーションの後に、同じ内容を別の表現で説明し直してみることも効果的です。
ロープレで実践するコミュニケーション状況再現
ロープレ(役割演技)は、実際のビジネスシーンを想定して特定の役割を演じながらコミュニケーションを練習する方法です。理論だけでなく実践的なスキルを身に付けるために非常に効果的です。
効果的に行うためのポイントは、できるだけリアルな状況設定をすることです。例えば「予算削減を伝える上司と、プロジェクト継続を主張する部下」などの具体的なシナリオを設定し、それぞれの立場になりきって会話を進めます。
日常的な実践方法としては、チームメンバー同士でロープレの時間を設けることがおすすめです。10〜15分程度の短い時間でも、定期的に行うことで効果が現れます。
▼ロープレについては下記で詳しく解説しています。
⇒研修でロールプレイングを成功させる!内容例から進め方まで徹底解説!
建設的なフィードバック交換の訓練
フィードバックの交換は、個人のスキルアップと組織の成長の両方に不可欠なプロセスです。しかし、建設的なフィードバックを適切に伝え、また受け取る能力は意識的な訓練が必要です。
建設的なフィードバックを与える際のポイントは、具体的な行動や事実に基づいて伝えることです。「あなたのプレゼンは分かりにくい」という漠然とした批判ではなく、「スライドの文字数が多く、読みづらかった」といった具体的な指摘の方が改善につながります。
日常的な訓練方法としては、チーム内で定期的なフィードバックセッションを設けることがおすすめです。プロジェクト終了時やミーティング後に5分間のフィードバックタイムを設定し、互いに良かった点と改善点を伝え合う習慣をつけましょう。
ポイントは相手の成長を願って行うという点です。間違っても相手を攻撃しようとしてはいけません。
専門家によるコミュニケーショントレーニング実施の流れ

組織全体で体系的にコミュニケーション能力を向上させるためには、専門家による、本格的なトレーニングの導入も検討すべきです。ここでは、効果的に実施するための一般的な流れを紹介します。
コミュニケーション上の課題を特定するための現状把握
まず組織内のコミュニケーションの現状を客観的に把握することが重要です。定量的アプローチとしては、従業員満足度調査にコミュニケーションに関する設問を含めたり、会議の頻度や所要時間、メール量などのデータを分析したりする方法があります。
定性的アプローチとしては、部署ごとのフォーカスグループインタビューや、キーパーソンへの個別ヒアリングが効果的です。「日常的に感じているコミュニケーション上の課題は何か」といった質問を通じて、数値だけでは見えない現場の実情を把握します。
これらの調査結果を分析することで、「部署間の情報連携が弱い」「上司と部下のコミュニケーションに課題がある」など、具体的な課題が明確になります。
研修会社などの専門家に相談
現状把握で特定した課題に基づいて、適切な研修会社や専門家を選定します。選定する際のポイントとしては、まず実績と専門性を確認しましょう。類似した業界での導入実績があるか、自社が抱える課題に対応したプログラムを持っているかを調査します。
次に、複数の候補となる研修会社に提案を依頼し、提案内容を比較検討します。研修会社との打ち合わせを通じて、研修会社側がどれだけ自社の課題を理解しようとしているか、どのような解決策を提案してくるかを見極めることが大切です。
最終的な選定にあたっては、コスト面だけでなく、研修後のフォローアップ体制や効果測定の方法なども含めて総合的に判断します。
プログラムの一部を無料で体験することができるようであれば、体験してみることをおすすめします。
課題解決のためのトレーニング内容の企画
研修会社を選定したのち、具体的なトレーニング内容を企画します。まず、トレーニングの目的と到達目標を明確に設定しましょう。「リーダー層のフィードバックスキル向上」など、具体的な行動変容を目指した目標を掲げます。
次に、対象者に合わせたカスタマイズが必要です。新入社員、中堅社員、管理職など、キャリアステージによって求められるスキルは異なります。また、職種や部署によっても必要なコミュニケーションスキルに違いがあるため、それぞれに最適なプログラム設計が求められます。
トレーニング方法としては、講義形式の知識習得だけでなく、ロープレやグループディスカッション、ケーススタディーなど、実践的な要素を多く取り入れることが効果的です。
コミュニケーショントレーニングの実施
実際のトレーニング実施においては、参加者の主体的な学びを促進する環境づくりが重要です。トレーニングの冒頭では、目的と期待される成果を明確に説明し、参加者の「なぜこのトレーニングが必要なのか」という理解を深めることから始めましょう。
「安全な学習環境」の確保も重要です。参加者が失敗を恐れずに新しいコミュニケーション手法を試せるよう、批判的にならない雰囲気づくりを心がけます。
また、理論と実践のバランスも大切です。知識のインプットの後には必ず実践的なエクササイズを取り入れ、学んだ内容を体験的に理解できるようにしましょう。
トレーニング終了時には、学んだ内容を実際の業務でどのように活用するか、具体的なアクションプランを各自が作成する時間を設けることがおすすめです。
トレーニング効果についての振り返り
トレーニングの効果を最大化し、継続的な改善につなげるためには、トレーニング後の振り返りとフォローアップが不可欠です。短期的な評価としては、トレーニング直後のアンケートが一般的です。参加者の満足度や理解度、実務での活用意欲などを測定します。
中長期的な評価としては、トレーニングから1〜3カ月後に追跡調査を行い、実際の業務上におけるコミュニケーション行動の変化を確認します。また、上司や同僚からのフィードバックも、客観的な変化を把握するのに役立ちます。
振り返りの結果は、次回のトレーニング計画に反映させることが重要です。「効果が高かった内容」「追加の研修が必要な分野」を特定し、PDCAサイクルを回していきましょう。
実は社内トレーナーという選択肢もある
外部の専門家だけでなく、社内にコミュニケーショントレーナーを育成するという選択肢も検討する価値があります。
社内トレーナー制度には、コスト効率の面で優れている、自社の文化や業務に精通したトレーナーによるより実践的なトレーニングが可能になるといったメリットがあります。
社内トレーナー育成のアプローチとしては、まず外部の専門機関でトレーナー養成プログラムを受講した社員がトレーナーとなり、基礎的なコミュニケーションスキルトレーニングを社内で展開する方法があります。
社内トレーナー制度を成功させるポイントは、トレーナーとしてやる気のある人を人選すること、トレーナープログラムを受講したら間をあけずにまずはトレーニングを実施してみることです。
やる気のない方やトレーナー養成プログラム受講後に長期間トレーニングを実施せずにいると、うまくいきません。
▼社内トレーナーに向いている人については下記で詳しく解説しています。
⇒研修講師に向いている人の特徴とは?向き不向きより「やる気」!ポイントを解説!
コミュニケーショントレーニングの効果を継続させるコツ

コミュニケーショントレーニングの効果を長期的に維持し、組織全体に浸透させるためには、継続的な取り組みが不可欠です。ここでは、効果を持続させるためのコツを紹介します。
職場単位でトレーニングを実施する
コミュニケーショントレーニングの効果を最大化するためには、階層別や目的別トレーニングとして実施するのではなく、職場やチーム単位で実施することが効果的です。
同じチームのメンバーが共通の理解や手法を持つことで、日常のコミュニケーションにおいて互いに高め合う環境が生まれます。
ポイントとして、まずリーダーの積極的な関与が重要です。責任者自身が率先してトレーニングに参加し、学んだスキルを実践することで、チーム全体に「コミュニケーション改善は重要である」というメッセージが伝わります。
また、チーム内で共通の目標を設定することも効果的です。例えば「ミーティングでは全員が最低1回は発言する」などの具体的なルールを決め、チーム全体で取り組むことで、個人の負担感が減り、互いに励まし合いながら成長できる環境がつくられます。
日常業務を行いながらフォローアップする
トレーニングの効果を継続させるためには、学んだスキルを日常業務の中で実践し、定着させる仕組みづくりが重要です。1度のトレーニングで行動が完全に変わることはまれであり、継続的な実践とフィードバックのサイクルが必要です。
効果的なフォローアップの方法として、「アクションプランの策定と振り返り」が挙げられます。
トレーニング終了時に各自が具体的な行動計画を立て、定期的に実践状況を振り返るセッションを設けます。短期間で小さな成功体験を積み重ねることで、新しい行動習慣が徐々に定着していきます。
また、上司や同僚からのフィードバックを受ける機会を定期的に設けることも重要です。特に初期段階では、自分では気付かない癖や改善点が多いため、客観的な視点からのアドバイスが成長を加速させます。
社内トレーナーを養成し、定期的なフォローアップを行う
コミュニケーショントレーニングの効果を持続させるためには、組織内にトレーニングの核となる社内トレーナーを育成し、継続的なフォローアップ体制を構築することが効果的です。
社内トレーナーによる定期的なフォローアップは、外部講師を招くよりも柔軟に実施でき、コスト面でも優れています。
効果的な社内トレーナー養成のコツとしては、まず各部門から意欲と適性のある人材を選出することが重要です。コミュニケーションスキルが高く、人材育成に関心のある社員を候補者として、外部の専門機関でトレーナー養成研修を受講させるのが一般的なアプローチです。
社内トレーナーの養成後は、トレーナー同士のコミュニティーを形成し、定期的に情報交換やスキルアップの機会を設けることが大切です。トレーナー自身が成長し続けることで、提供するトレーニングの質も向上します。
コミュニケーションを重視する組織文化の醸成
コミュニケーショントレーニングの効果を長期的に維持し、組織全体に浸透させるためには、「コミュニケーションを重視する組織文化」を醸成することが最も重要です。どれだけ優れたトレーニングプログラムを実施しても、組織文化がそれを支持していなければ、効果は限定的なものにとどまってしまいます。
組織文化の醸成において最も影響力を持つのは、経営層のコミットメントです。経営者や役員が率先してコミュニケーションの重要性を発信し、自ら実践することが求められます。経営方針や事業計画の中に「コミュニケーション力の向上」を明確に位置づけることも効果的です。
また、評価制度にコミュニケーション能力の項目を取り入れることも重要です。「チーム内の情報共有に貢献しているか」「建設的なフィードバックを行っているか」といった観点を昇進や評価の基準に加えることで、組織全体にコミュニケーションの重要性が浸透します。
さらに、定期的なコミュニケーションイベントの開催も文化醸成に役立ちます。四半期ごとの「コミュニケーション成功事例共有会」や、部署間の交流を促すBBQ懇親会などのイベントを開催することで、日常業務の中での実践意欲が高まります。
コミュニケーショントレーニングならLIFO®がおすすめ!

組織内コミュニケーションの活性化には自己診断ツールLIFO(Life Orientations)を活用した職場単位でのワークショップがおすすめです。
なぜなら、LIFOプログラムは心理学や行動科学をベースにして組み立てられた行動特性診断をベースに、職場単位でワークショップを行うためのワークブックなどのツールも体系的にそろえられているからです。
また、体系立てられたツールの使い方を社内トレーナーの方々にライセンス提供もされており、社内トレーナーの方々が職場単位でワークショップを展開していくことも可能です。下記に概要を紹介します。
自己診断ツールLIFOとは
LIFO(Life Orientations)は、個人の行動スタイルを診断する自己診断ツールです。このツールは、自分の強みや行動パターンを理解するために役立ちます。
LIFOは4つの基本スタイルに基づいており、これらのスタイルはそれぞれ異なる行動特性や価値観を持っています。
自分がどのスタイルに属しているかを知ることで、より良いコミュニケーション方法やストレス時の行動傾向を把握することができます。
LIFOを活用したコミュニケーション研修
LIFOを活用したコミュニケーション研修では、まず参加者が自己診断を行い、自分の行動スタイルを理解します。
この診断結果を基に、どのようにして他者と効果的にコミュニケーションを取るかを学びます。
研修では以下のような内容が含まれます。
|
LIFO®プログラムは社内トレーナーで展開可能
LIFO®プログラムは、これまでの活用実績と実用性から、企業内でのトレーニングにおいて自信を持っておすすめできるプログラムです。
社内展開にあたっては、特定の準備と手続きを経ることで、コストを抑えながら、外部講師に委託したかのように、社内トレーナーによる効果的なプログラムを展開することが可能です。
以下に、その流れを詳しく説明します。
|

LIFOでコミュニケーショントレーニングを展開した支援事例(日本新薬)

日本新薬株式会社/医薬品・機能食品事業
導入前の課題
私たちの会社は、コミュニケーションの向上と変化対応力の強化を目指している中で、社内でいくつかの課題に直面していました。
表面的には社員同士のコミュニケーションは取れているように見えましたが、実際には意思疎通が不十分な場面も多く見受けられました。特に、マネジャーとメンバー間や異なる部署間でのコミュニケーションの円滑化が求められていたのです。
また、中途採用が増える中で、オンボーディングを円滑に進めるために、効果的なコミュニケーションツールの導入が必要でした。これに加えて、業界環境の変化に対応し、社員の変化適応力を強化する必要もありました。
出会いと導入
営業チームのコミュニケーションを円滑にするツールを模索している中で、「LIFO」と出会いました。「LIFO」の魅力は、そのプログラムの分かりやすさと社内への展開が容易な点にありました。
他のツールとは異なり、内製研修で効果的に活用できるプログラムであったため、導入が決まりました。
LIFOスコア取得後の詳細な個別レポートは、社員一人一人の特性を理解する「取扱説明書」として機能し、自己理解を深める助けとなりました。役員からの強力な支持を得て、全社展開が迅速に進みました。
展開ステップと取り組み
導入当初、LIFOは営業所長研修の一環として活用され、研修を終えた所長がサブトレーナーとなり、現場での実施を推進しました。
その結果、営業所長はLIFOを用いてチームの構築とコミュニケーションの質を向上させることができました。3年目には、LIFOが全社で共通言語となり、コミュニケーションが大幅に改善しました。
現在はチーム単位でのワークショップを実施し、2024年度には新入社員を含む多くの社員が参加する予定です。この取り組みの成果は、社内だけでなく、外部からも高く評価されています。
導入後の感想・成果
LIFOプログラムの導入により、コミュニケーションの質が向上し、研修を超えて職場活用や人事戦略へのデータ活用の幅が広がりました。
結果として、3年以内の離職率も低い水準で推移しています。職場での活用可能性に関するアンケートでも高い評価を得ており、LIFOが共通言語となることで、活発なコミュニケーションと効果的な施策の運用が進んでいます。
今後の課題と取り組み
今後は、全社員を対象にLIFOを定期的に活用し、コミュニケーションの強化を継続することが重要です。特にオンボーディング施策に重点を置き、新入社員が早期に職場になじめるようサポートしていきます。
データを基にした効果的な人事戦略を構築し、社員特性に応じた配属や異動を実現することで、組織全体の最適化を目指します。最終的には、グループ企業全体での展開を見据えています。このような取り組みを通じて、社員同士の相互理解を深化させ、組織力をさらに強化していきます。
▼事例の全文は下記をご覧ください。
⇒日本新薬株式会社様 LIFO・ITS導入事例
まとめ:効果的なコミュニケーショントレーニングで組織の活力を高めよう
効果的な「コミュニケーショントレーニング」とは?日頃から高める実践方法も解説!について紹介してきました。
- コミュニケーショントレーニングは大きく2種類
- コミュニケーショントレーニングとは?企業が注目する理由
- コミュニケーショントレーニングで解決したい組織の課題
- すぐできるコミュニケーショントレーニング7つの実践法
- 専門家によるコミュニケーショントレーニング実施の流れ
- コミュニケーショントレーニングの効果を継続させるコツ
- コミュニケーショントレーニングならLIFO®がおすすめ!
- LIFOでコミュニケーショントレーニングを展開した支援事例(日本新薬)
コミュニケーション能力は「生まれ持った才能」ではなく、適切なトレーニングと継続的な実践によって誰でも向上させることができるスキルです。
組織におけるコミュニケーショントレーニングの導入は、単なるスキルアップ以上の価値をもたらします。社員間の信頼関係の構築、情報共有の活性化、創造的な議論の促進、顧客満足度の向上など、ビジネスの根幹に関わる、さまざまな面での改善が期待できます。
コミュニケーショントレーニングを効果的に実施するためのポイントは、まず現状のコミュニケーション課題を客観的に把握し、具体的な目標を設定することです。次に、日常的に実践できる基本的なトレーニング方法と、専門家による体系的なトレーニングを適切に組み合わせることが効果的です。そして最も重要なのは、トレーニング後の継続的な実践とフォローアップです。
コミュニケーショントレーニングの導入を検討する際は、短期的な成果を求めるのではなく、組織の持続的に成長するための投資として捉えることが大切です。社員一人一人が「伝える力」と「聴く力」を高め、言語・非言語両面でのコミュニケーション能力を磨くことで、組織全体の活力が高まっていきます。
現代のビジネス環境において、コミュニケーション能力は最も価値のあるスキルの1つです。効果的なコミュニケーションが実現する組織では、情報が滞りなく流れ、問題が早期に発見・解決され、メンバー同士が互いに高め合う好循環が生まれます。そうした環境こそが、変化の激しい時代を生き抜くための組織の強靭さと創造性の源泉となるのです。
株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。