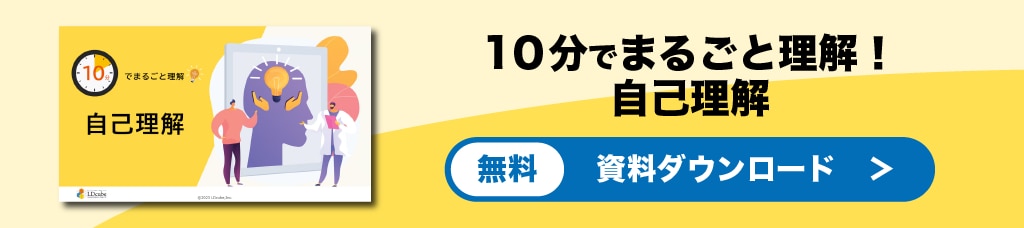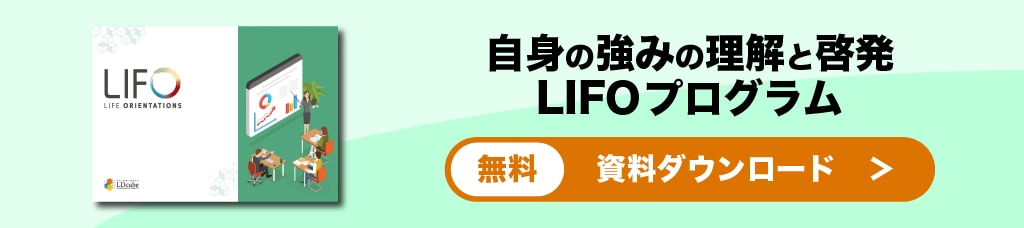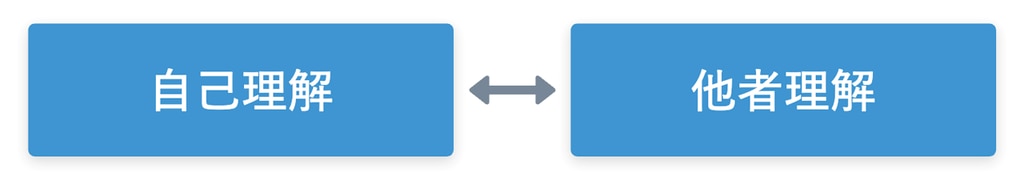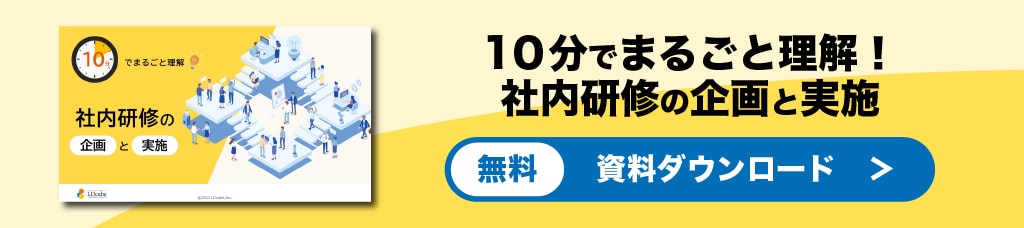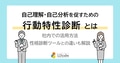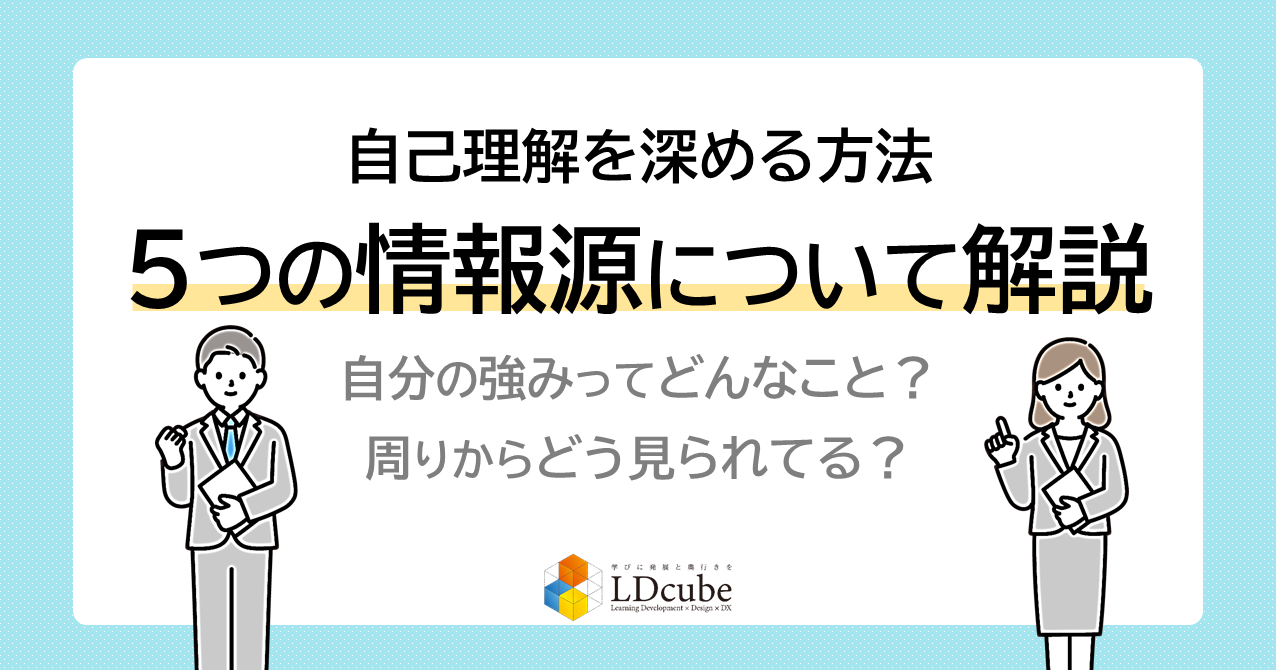
自己理解を深める方法とは!5つの情報源について詳しく解説
「自己理解」は、キャリアの成功や個人の成長にとって非常に重要な要素です。
しかし、多くの人が自分自身を深く理解する機会を持たず、その結果、目的意識を持って行動することが難しくなってしまいます。
では、どのようにすれば自己理解を深め、自分の強みや弱みを理解し、より良いキャリアパスを見つけることができるのでしょうか?
多くの人が直面する「自己理解の不足」について考えてみましょう。
自己理解が不足していると、自分の強みや価値を適切に認識できず、キャリア選択や仕事のパフォーマンスにおいて迷いや不満を感じることが増えます。
その結果、目標が曖昧になり、ストレスが増加し、さらには燃え尽き症候群に陥るリスクもあります。
本記事では、自己理解を深めるための具体的な方法を紹介します。
できることから始めることで、自己理解が深まり、自分に合ったキャリアパスや人間関係を築くための基盤が整います。重要なのは、継続的に自己理解を深める努力を怠らないことです。
自己理解を深めることによって、より充実したキャリアと豊かな人生を築けます。
株式会社LDcubeでは、自己理解を深めるための診断ツールやeラーニング、研修会やワークショップ実施の支援を行っています。
そのようなサービス提供経験を踏まえて、自己理解を深める方法についてご案内していきます。
▼自己理解についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。
▼簡易的に自己理解診断を体験できるよう記事にまとめました。
⇒【プチ診断付き】人間関係で疲れた方へ/少し気が楽になる捉え方のコツ!
目次[非表示]
自己理解を深める5つの方法

自己理解とは、個人の人生における方向性や価値観、行動スタイルを明らかにすることです。自己理解を深めることは、個人やチームがさまざまな活動において成功を収めたり、重要な関わりを持つ人たちに何らかの好影響を与えたりするための明確な方向性や手だてを提供してくれます。
その自己理解を深める方法として、下記5つの情報源の活用が効果的です。
自己理解を深めるための5つの情報源とは、
|
以下、各情報源について掘り下げます。
また、具体的な取り組みの一例としてスキル向上を実現するLIFO®プログラムのご紹介を行います。自己理解を深めることで自分の能力を最大化し、自身の成長とビジネスの発展につなげていきましょう。
自己理解の方法① 自分で考える

情報源の1つ目は「自分で自分のことを考える」というものです。
日常生活を送っている中ではきっかけがないと意外と自分で自分のことは考えないものです。必要性も感じないかも知れません。しかし、時に時間をとって、自分自身のことを考えてみることは自己理解を深める上で有効です。
例えば、「自分は〇〇である」という文章をベースにして○○に当てはまることを数多く考えてみます。実際にやってみると、初めのいくつかはすぐに出てきますが、途中からあまり出てこなくなります。意外と難しいものです。
どれくらいこの文章に当てはまることを挙げられたかで、現在の自己理解の度合いが確認できます。あまり数を出せなかったとしても落ち込むことはありません。これまで意識してこなかったので、出せなかったにすぎません。
普段から振り返りの時間をもち、自分で自分はどのような人間なのだろうかということを意識して過ごすようにしていくことで、ふとした瞬間に「自分ってこういうことが好きなのだな」というように自己理解が深まっていくことが経験できるでしょう。
やってみると分かりますが多くの場合、意外と自分の強みや長所、得意といえる部分を自分で出すことができないケースが多いです。それは自分ではそれが当たり前だと思っているからです。しかし、他者から見ると長所と映っていることはたくさんあります。
そのため、自分で考えるだけではなく、他者から教えてもらうことが重要になります。
自己理解の方法② 他者からの指摘

情報源の2つ目は「他者からの指摘・フィードバック」です。
1つ目の「自分で自分のことを考える」ことを通じて自己理解を深めることには限界があります。自分で考えた以上のものが出てこないからです。
2つ目の情報源は他者の力を借りるものです。他者からの指摘やフィードバックを通じて、気付いていなかった自分に気付き、新たな自分を発見・認識することができます。
どのような人でもこれまでの人生を振り返ると、他者から言われた一言によって自分についての捉え方が変わったという経験があるのではないでしょうか。
研修会などに参加する機会がある場合、時間をとって他者からフィードバックをもらうというセッションがあれば研修中に自己理解を促すことが可能ですが、日常生活の中では家族や仲の良い友人、同僚などにそれとなく聞いてみると自己理解を深める情報を得ることが可能です。
例えば、「自分は営業という仕事は向いていないのではないかと思うのだけど、どう思う?」などです。それに対して家族や友人が答えてくれることの中に自己理解を深める情報があります。
例えば上記の質問に対し「仕事の話をしているときの印象から、確かに話し方が抜群にうまいという印象はないけど、お客さまのことを自分のことのように真剣に考えて、時間をかけて何とか役に立とうとしていることは感じるので、営業が向いていないという感じはしないけどなぁ」という回答が得られたとします。
自分では「話し方がうまくない=営業という仕事が向いていない」と捉えていたとしても、他者からの指摘にある「お客さまのことを自分のことのように真剣に考えている」という行動を無意識的に行っていたとすれば、自分で考えるだけでは気付けないことです。
このように他者から指摘・フィードバックを得ることによって、自分のことについて理解を深めるきっかけを得ることができます。
▼自分だけでは、自己理解を深めることには限界があります。自己理解を深めるためのコーチングプログラムについては下記で解説しています。合わせてご覧ください。
⇨社員の自己理解を促す最高のコーチングプログラムとは!?
自己理解の方法③ 診断ツールの活用

情報源の3つ目は「診断ツールの活用」です。
世の中にはいくつもの自己理解を促すための診断ツールがあります。無料のものから有料のものまで数多く存在します。
時にそのような診断ツールを活用し、自分のことを分析してみたら、その診断ツールの切り口から「自分というのはどのような人間なのか」を確認することができ自己理解を深めることにつながります。
自分で考えることや他者からの指摘には、それを行う人の主観が反映されます。しかし、診断ツールを活用することで、主観ではなく客観的に問題を見つめることを手助けし、自己理解をしやすくします。それが診断ツール活用のメリットです。
LIFO®プログラムのご紹介
ここでは弊社が提供しているLIFO®プログラムについてご紹介します。
LIFO®プログラムは、『LIFO®サーベイ』という自己診断を中核とした、人の強みに焦点を当て、強みを生かすための方法論(プログラム)です。また、強みを使いすぎてしまうと弱みになってしまうという考え方が特徴です。
1967年にアメリカ人のスチュアート・アトキンズ博士とアラン・キャッチャー博士により、行動科学、精神分析、カウンセリング理論をベースに開発されました。LIFO®(ライフォ)という名称は、Life Orientations からとっています。
LIFO®は、 自己理解と他者理解を深め、 個人の行動変化やタテ・ヨコ・ナナメのコミュニケーションや良好な人間関係づくりをポジティブに促進します。
その適用範囲は広く、マネジャー育成や営業社員研修、コーチング、キャリア研修など、企業内人材育成のシーンから、就活中の学生が自分の強みを確認するような場面まで、あらゆる領域で活用されています。
LIFO®プログラムの歴史
1960年前半、アメリカ南カリフォルニア大学のスチュアート・アトキンズ博士とエリアス・ポーター博士は、人間の行動スタイルを調査し、それを診断するツールを開発しました。
その後1967年、両博士はエーリッヒ・フロムの性格分析をベースにして、アブラハム・マズローの欲求段階説、カール・ロジャースの来談者中心カウンセリングなど、現在のポジティブ心理学の根底にある理論を参考にLIFO理論とLIFOサーベイ(診断)を完成させました。
そしてそれは、U.C.L.A.のアラン・キャッチャー博士により世界各国に広められました。
1976年に、株式会社ビジネスコンサルタント(BCon)は、アラン・キャッチャー博士を通じてLIFOを導入し、2001年以降はLIFOの知的財産(IP)オーナーとして、世界21のエージェンシー(代理店)を通じてライセンスを提供しています。
現在、LIFOは24言語で世界66カ国に普及し、累計2万以上の組織、1200万人以上に活用されています。このことは人種や文化の違いを超えるLIFOの有用性を示しています。
2023年4月以降は日本国内でのLIFOプログラムのマーケティングやマネジメントを株式会社LDcubeへと委託して展開しています。
▼LIFOプログラムを活用したお客様の声はこちらから。
⇒1on1ミーティングの取り組み LIFO×YBS山梨放送様
LIFO無料体験はこちらからお申し込みください。
上記のように歴史と実績のあるLIFOプログラムですが、LIFOサーベイの結果を活用して研修会やワークショップで理解を深める機会を持てると効果的です。
会社内では、新入社員研修から役員研修、職種別研修、ビジネススキル研修、選抜研修、職場ワークショップに至るまで幅広く活用いただいています。
▼行動特性診断(LIFO)を活用した自己理解を深めるためワークショップについては下記で詳しく解説しています。⇒行動特性を踏まえた自分・自己理解を深めるワークショップとは!
自己理解の方法④ イメジリィ(想像から)

情報源の4つ目は「イメジリィ(想像をめぐらすことから)」というものです。
これは日常生活の中では情報が得にくいものであり、実際には研修プログラムの中で時間をとって実施されます。概要を簡単にご紹介します。
イメジリィの研修プログラムでは、受講者がインストラクターの指示の従い、目をつぶりインストラクターの話に耳を傾けます。インストラクターが想像をめぐらすようなストーリーを話しますので、その言葉に従いイメージしてみます。
例えば「今、あなたは山を登っています」というストーリーに対して受講者が山を登っている状態を想像するわけですが、既にこの時点で人により想像する山が異なります。
富士山のような山を想像する人もいれば、幼いころに登った近所の山を想像する人もいます。また、登り始めのシーンを想像する人もいれば、山頂についたシーンを想像する人もいます。誰と登っているかも人により異なります。
このプロセスにより、普段意識していない無意識的な自分についての理解をすることが可能になります。
このように受講者がインストラクターのストーリーに従い想像をめぐらし、その後で研修プログラムに参加している他の方とどのような状況を想像したか、なぜそのような想像をしたのかを振り返る中で、自己理解のヒントになる情報を得ることができます。
自己理解の方法⑤ 体の動き・感じ方

情報源の5つ目は「体の動き」というものです。
これも日常生活の中では情報が得にくいものです。実際にはさまざまな体の動きからいろいろな情報を日々受け取っているのですが、研修会などを通じて、体の動きから感じる情報を一般化し理解するという経験がないとピンとこないかもしれません。概要を簡単にご紹介します。
複数名の研修受講者でグループを組み、インストラクターの指示の従い、さまざまなシーンを作り、そこに身を置いた際にどのような感じがするかという情報から自己理解を深めます。
例えば、数名で手をつなぎ半径1メートルほどの円を作ります。その円の中に身を置いたときにどのような感情を抱いたか?その円から出て2~3メートル離れたところからその円を眺めたときにどのように感じるか?というようなワークを繰り返していきます。
人により感じ方は異なります。円の中にいるときに「心地よい」と感じる人もいれば、円の中にいると見られている感じがして「窮屈」と感じる人もいます。
このようにインストラクターの指示に従い、いくつかのシーンを作り、その状況に身を置いた際に体がどのように反応するか、どのような感じがするかを体験した後で、研修に参加している他の方とどのように感じたか、なぜそのように感じたのかを振り返る中で、自己理解のヒントになる情報を得ることができます。
▼5つの情報源を活用しながら自己理解とさらに広い人間理解をしていくにはセルフエスティームについてしることがポイントです。下記で詳しく解説しています。
⇒セルフエスティーム(自尊感情)とは?
自己理解を深めるメリットとデメリット
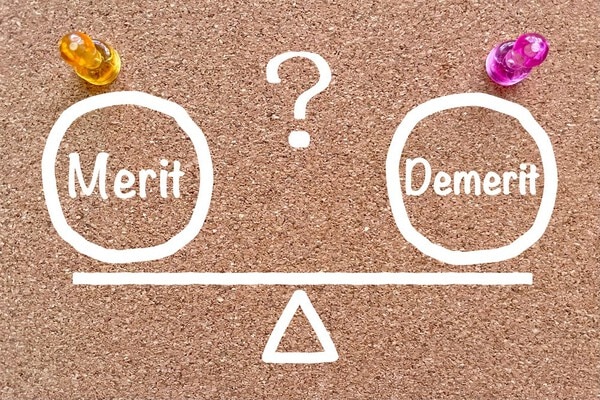
自己理解を深めることは多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。代表的なものを紹介します。
自己理解を深めるメリット
|
※自己理解と他者理解の関係については次章で説明します。
▼自己理解のメリットについては下記で詳しく解説しています。
⇒自己理解を深めるメリットとは?個人と組織に効果をもたらす方法について徹底解説!
自己理解を深めるデメリット
|
これらのデメリットに注意しながらバランスを取ることで、自己理解を効果的に進めることが重要です。
自己理解と他者理解の関係

他者理解を深めるためのキーワードとして、かならずセットで登場するのが、「自己理解」です。 自身の性格、価値観、思考パターンなどをよく理解することは、他者理解の土台となる重要なプロセスです。 なぜなら、自分を深く知れば、自分と他者の共通点や相違点を客観的に認識できるようになるからです。 【自己理解が他者理解につながる理由】
このように、自己理解と他者理解は、表裏一体の関係にあるといえます。 |
(出典:他者理解とは?その意味と必要な7つのこと─職場でできる施策も紹介)
▼他者理解については下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
⇒他者理解とは?その意味と必要な7つのこと─職場でできる施策も紹介
社内講師が自己理解・他者理解を促進している支援事例

リコージャパン株式会社
社員数:18,000名以上
背景・課題:
リコージャパン株式会社では、2010年の販売会社統合以降、各支社の固有の課題に対応できず、教育施策が本部主導で一方的になるなどの課題がありました。また、縦割り組織文化がコミュニケーションの希薄化を招いていました。これらの課題を解決するために、社員自らが強みや弱みを理解し合い、横のつながりを強化する取り組みが求められていました。
LIFOプログラム(社内トレーナーライセンス)の導入:
その中で、LIFOを導入しました。LIFOの活用を通じて、社員一人一人の個性を診断し、自己理解と他者理解を促進しました。これにより、飲み会などでの非公式なコミュニケーションが減少する中でも、社員同士の人間関係を深めるための新たな手段を提供することができるようになりました。
また、LIFOライセンスを取得することで、社内トレーナーが自主的に研修を行えるようになり、組織風土改革を進めました。LDcubeとの協力により、多様なワークショップを展開し、各支社が抱える具体的な課題に対応できるようになりました。
社内展開:
プログラムの展開においては、事前のLIFO診断、ワークショップの実施、職場での実践、効果検証のサイクルを組み込みました。参加者は、研修後の職場実践を通じて得られたスキルを評価し合い、PDCAサイクルを回すことで、持続的なスキルアップを図っています。ラーニングプラットフォーム「UMU」を活用し、受講者同士が学び合う環境を整備しました。
社内トレーナーによる研修実施後の反応:
導入後、プログラム受講者の満足度は高く、多くの支社で「対人関係」や「マネジメント能力」などにおいて数値的な改善が見られました。LIFOを活用したレクチャーは「人」の問題の解決に寄与し、特にアウトプット重視の体験学習が効果的だったとされています。UMUの活用と一連の学習サイクルの設計により、事務局の負担軽減と学習効果の向上が実現しました。
今後に向けて:
今後は、各支社や部門の課題に寄り添い、人材育成を継続的にサポートすることで、社員個々の自己成長と組織全体の活性化をさらに推進する予定です。また、導入されたプログラムは、社員の特性に基づく行動変容を促すとともに、他部門にも勧められる内容として評価されています。
これにより、組織内のさまざまな課題を解決し、全体の一体感を更に高められることが期待されています。
▼本事例はインタビュー記事の一部です。インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。
まとめ
自己理解を深める方法 5つの情報源について解説してきました。
- 自己理解を深める5つの方法
- 自己理解の方法① 自分で考える
- 自己理解の方法② 他者からの指摘
- 自己理解の方法③ 診断ツールの活用
- 自己理解の方法④ イメジリィ(想像から)
- 自己理解の方法⑤ 体の動き・感じ方
- 自己理解を深めるメリットとデメリット
- 自己理解と他者理解の関係
自己理解を深めるには日常から意識することで情報を得られることもありますので、日ごろから意識してみると今まで気付かなかった自分に気付けるかもしれません。自己理解を深めることの大切さを理解し、自己理解を深めるための情報源を知り、日ごろから意識して活動することが大切です。
また、自分だけでは情報源が限られますので、研修会や診断ツールを活用することもおすすめです。自己理解を深めるには、世界中で活用されているLIFO®プログラムの活用が効果的です。
株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。
また、本LIFOプログラムはプログラムの理解を深め、トレーナースキルを習得することで、LIFOプログラムライセンスを取得し、社内外の受講者を対象に研修を展開することが可能です。
- 社内の人材育成施策におけるさまざまな研修の質を高めたい
- 社内トレーナーとして担当する研修をプロさながらの研修にブラッシュアップしたい
- 講師としてお客さまに提供している研修サービスの質を高めたい
- 学生に自己理解を促す機会を提供し、就職活動の質を高めてほしい
- カウンセラーとして自己理解についての理解を深めておきたい
などさまざまな状況でLIFOプログラムを活用いただいています。
企業内の社内トレーナーや個人講師向けに、無料でのLIFOプログラム体験会なども行っています。お気軽にお問い合わせください。
▼LIFOプログラムについての資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。