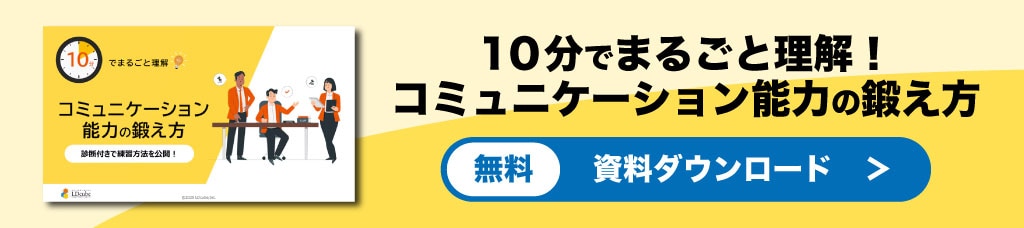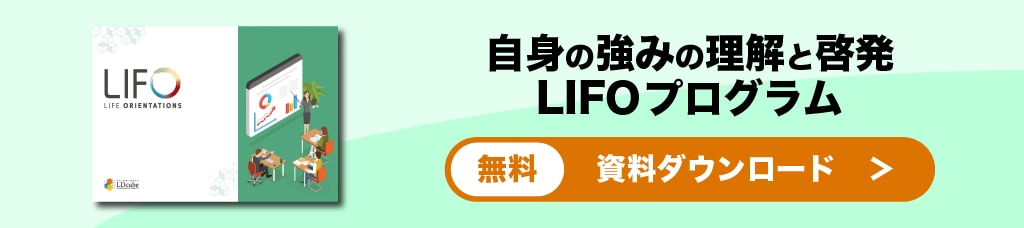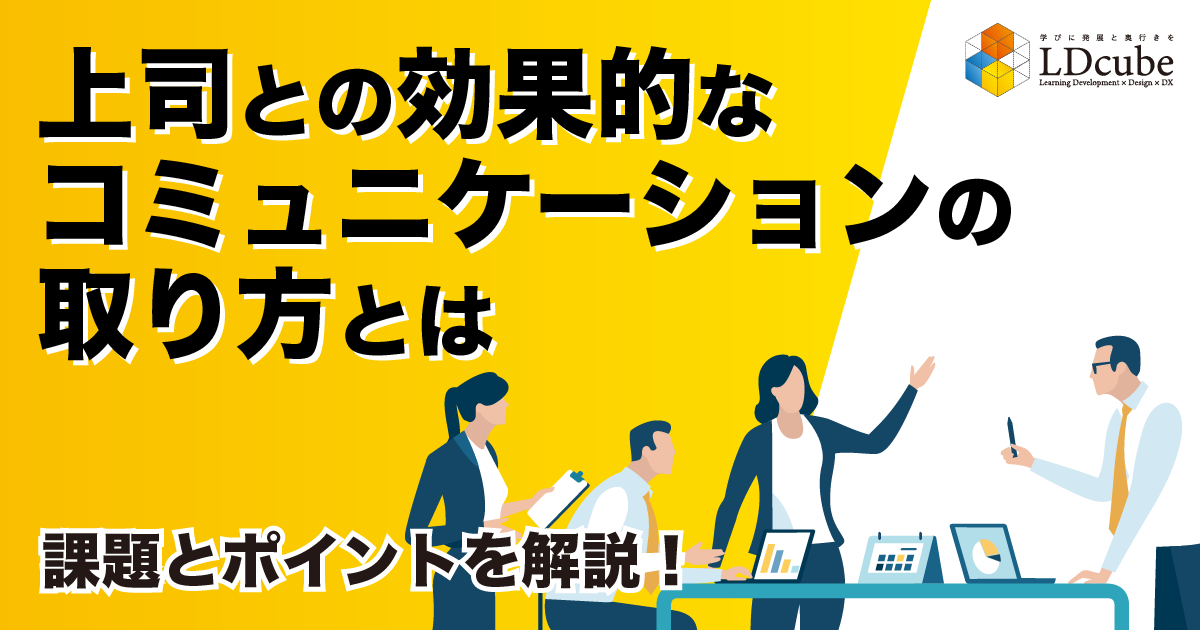
上司との効果的なコミュニケーションの取り方とは?課題とポイントを解説!
「上司に自分の考えがうまく伝わらない」
「上司との関係がぎくしゃくして仕事がしづらい」
「何を言っても伝わった気がしない」
このようなお悩みを抱えていませんか?
企業や組織内における上司とのコミュニケーションは、仕事の成果や職場での評価、さらには毎日の仕事のストレスにまで大きく影響します。うまくいかないと業務効率が下がるだけでなく、自分のキャリア形成にも支障をきたす可能性があります。
特に、世代間ギャップや働き方の多様化、リモートワークの普及により、上司と効果的にコミュニケーションを取ることはますます難しくなっているといえます。多くの社会人が「上司との距離感」や「適切な報告の仕方」に頭を悩ませているのが現状ではないでしょうか。
しかし、上司とのコミュニケーションは特別な才能ではなく、適切な知識と実践テクニックを身に付ければ、誰でも改善できる可能性があるスキルなのです。
本記事では、上司とのコミュニケーションの課題、改善のメリット、原因、実践テクニックシーン別対応方などについて紹介します。
【上司とのコミュニケーション改善のポイント】
|
これらのテクニックを身に付ければ、上司との関係が劇的に改善され、仕事のパフォーマンスアップやキャリア形成にもつながっていくでしょう。
もし、この知識を持っていなければ、上司とのコミュニケーションについて悩み続けてしまうかもしれません。効果的な上司コミュニケーションを身に付け、職場での悩みを解消していきましょう。
▼上司についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。
▼コミュニケーションについてはテーマに合わせて下記で解説しています。
▼コミュニケーション能力の鍛え方についてのお役立ち資料は下記からダウンロードできます。
目次[非表示]
- 1.上司とのコミュニケーションの前提
- 2.上司とのコミュニケーションに悩む人が抱える3つの課題
- 3.上司とのコミュニケーションが円滑になると得られる3つのメリット
- 4.上司とのコミュニケーションがうまくいかない4つの原因
- 5.上司とのコミュニケーションで信頼関係を築く7つの実践テクニック
- 5.1.①上司の価値観を理解して会話の土台をつくる
- 5.2.②質の高い報連相で信頼の基盤を固める
- 5.3.③積極的傾聴で上司の真意をつかむ
- 5.4.④表情やトーンで印象を管理する非言語テクニック
- 5.5.⑤フィードバックを即行動に移して成果を見せる
- 5.6.⑥小さな成功体験の共有で信頼関係を強化する
- 5.7.⑦上司の時間を尊重する効率的な対話術
- 6.状況別・タイプ別の上司コミュニケーション戦略
- 6.1.多忙な上司との短時間で成果を出す情報共有術
- 6.2.指示があいまいな上司から具体的意図を引き出す質問
- 6.3.リモートワークでも信頼を深める定期的な接点作り
- 6.4.厳格な上司との心理的安全性を保つ対話テクニック
- 7.上司・部下のコミュニケーションの改善ならコミュニケーション研修がおすすめ!
- 8.上司・部下のコミュニケーションにLIFOを活用した支援事例
- 9.まとめ:上司とのコミュニケーションで信頼を築き、キャリアを加速させよう
上司とのコミュニケーションの前提

職場での人間関係の中でも、特に上司とのコミュニケーションは多くの人が悩みを抱える部分です。報告や相談がうまくいかないと業務効率が下がるだけでなく、職場でのストレスにもつながります。
しかし、上司との関係を改善するためには、まず基本的な前提を理解することが大切です。効果的なコミュニケーションを築くための土台となる考え方から見ていきましょう。
上司も同じ人間である
上司は権限を持ち、評価する立場にあるため特別な存在のように感じがちですが、根本的には同じ人間です。上司にも感情があり、好みや価値観、得意・不得意があります。また、プライベートの悩みや健康問題を抱えていることもあるでしょう。
時に厳しい指示を出したり、感情的になったりする背景には、上司自身のプレッシャーや責任の重さがあることを理解しておくと、対応がしやすくなります。特に、上司は部下よりも多くの責任を負っていることが多く、経営層との板挟みになっているケースも少なくありません。
上司を「怖い評価者」や「越えられない壁」として見るのではなく、同じ組織で働く「協力者」「先輩」として捉え直すことで、コミュニケーションの糸口が見えてくることもあります。人間同士のつながりを基本に据えることで、お互いを理解し合える関係が構築できるのです。
上司は立場が上の人:礼儀を持って接しよう
上司も同じ人間だからといって、友達のように気軽に接して良いわけではありません。組織内での立場や役割の違いを認識し、適切な礼儀を持って接することが重要です。
ビジネスマナーの基本として、敬語の使用や時間の厳守、約束の順守などは最低限守るべき点です。特に「報告・連絡・相談」は徹底し、上司が状況を把握できるようにすることが信頼関係の基盤となります。
また、上司の時間は貴重であることを認識し、効率的なコミュニケーションを心がけましょう。簡潔に要点をまとめる、必要な資料を事前に準備するなど、相手の立場を尊重する姿勢が大切です。礼儀を持って接することは相手への敬意を示すだけでなく、あなた自身の評価向上にも直結するでしょう。
基本的なマナーを守りながらも、自分の意見や考えをしっかりと伝えられるバランス感覚を身に付けることが、上司とのコミュニケーションの第一歩なのです。
上司とのコミュニケーションに悩む人が抱える3つの課題

上司とのコミュニケーションに悩みを抱える方は少なくありません。「言いたいことが伝わらない」「評価されていない気がする」といった不満や不安を感じている方も多いでしょう。
まずは、多くの人が直面する具体的な課題を理解することで、解決への糸口を見つけていきましょう。
伝えたいことが正確に伝わらない対話の壁
上司に報告や提案をしたつもりでも、意図が正確に伝わっていないというケースは頻繁に起こります。これは単なる言葉の選び方だけでなく、情報の整理方法や伝え方にも原因があることが多いです。
特に、自分にとって当然のことを省略してしまったり、重要な情報と些細な情報の区別が付かなかったりすると、上司は状況を正確に把握できません。また、業界や専門分野の知識の差によって、同じ言葉でも捉え方が異なるケースもあります。
例えば、若い世代が「DX化」という言葉を使う際に、上司世代にとっては具体的にどのような変化を意味するのか伝わりにくいことがあります。
このような対話の壁は、単に「もっと話せば解決する」というものではなく、伝え方の工夫や相手の理解度に合わせた説明が必要となります。自分の伝え方を振り返り、相手に合わせたコミュニケーション方法を見つけることが大切です。
信頼関係の欠如がもたらす評価への影響
上司との間に信頼関係が築けていないと、どんなに優れた仕事をしても適切な評価につながりにくくなります。信頼関係がない状態では、あなたの発言や行動が誤解されやすくなり、些細なミスが大きく見えてしまうこともあるのです。
例えば、締め切りに間に合わなかった場合、信頼関係があれば「何か理由があるのだろう」と考えてもらえる可能性がありますが、関係が希薄だと「責任感がない」と判断されかねません。また、成果を上げても「たまたまうまくいっただけ」と評価されてしまうこともあります。
さらに、信頼関係が薄いと上司はリスクを避けるため、重要なプロジェクトや成長につながる機会をあなたに与えにくくなります。結果として、キャリアの停滞や職場での存在感の低下につながる悪循環に陥ってしまいます
世代間ギャップによる価値観の衝突
多くの場合は、上司と部下の間に年齢差があり、それに伴う価値観や考え方の違いが存在します。これは単なる「古い考え方vs新しい考え方」という単純な対立ではなく、それぞれの世代が経験してきた社会環境や教育背景の違いから生まれるものです。
例えば、デジタルネイティブ世代の若手社員にとって当然のテクノロジー活用が、アナログ時代を経験してきた上司には抵抗感を持って受け止められることがあります。
また、働き方に対する考え方も大きく異なり、ワークライフバランスを重視する人が多い若い世代と、仕事中心の価値観を持つ人が多い上の世代では理想とする働き方にギャップが生じやすいのです。
このような価値観の衝突は、お互いの立場や考え方を理解せずにコミュニケーションを取ると、「考え方が古い」「責任感がない」といった否定的な印象につながりかねません。世代間の違いを認識し、お互いの強みを生かした協力関係を構築することが課題解決への鍵となります。
上司とのコミュニケーションが円滑になると得られる3つのメリット

上司とのコミュニケーションに課題を感じている方は多いですが、この関係を改善することで得られるメリットは非常に大きいものです。単に「職場が居心地よくなる」だけでなく、あなたのキャリアや日々の業務効率にも良い影響を与えます。
ここでは、上司とのコミュニケーションが円滑になることで得られる具体的なメリットを見ていきましょう。
業務効率向上による成果アップと評価向上
上司とのコミュニケーションが円滑になると、業務の指示や方向性が明確になり、無駄な作業や手戻りが減少します。これにより、本来の業務に集中できる時間が増え、生産性が大幅に向上します。
特に報告・連絡・相談(報連相)がスムーズになることで、問題の早期発見・早期解決が可能になり、トラブルを未然に防ぐことができます。上司から的確なアドバイスを適時に受けることで、より高品質な成果物を生み出せるようになるでしょう。
また、上司の意図や期待をしっかりと理解できるようになるため、評価ポイントを押さえた業務遂行が可能になります。結果として、あなたの実力が正当に評価される機会が増え、昇進や昇給などのキャリアアップにもつながります。コミュニケーションの改善は、目に見える形で業績と評価に反映されるといえるのです。
キャリア形成につながる成長機会の獲得
上司との良好な関係は、あなたのキャリア形成に大きく貢献します。上司があなたの能力や志向を理解していれば、成長につながる適切な業務や責任ある役割を任せてもらえる可能性が高まります。
上司との信頼関係が構築できていると、チャレンジングなプロジェクトや新規事業など、スキルアップにつながる貴重な機会を紹介してもらいやすくなります。また、上司が持つ専門知識やノウハウ、業界の人脈などを共有してもらえることも大きなメリットです。
さらに、上司は社内の状況や将来の展望についての情報を多く持っているため、キャリアパスに関する相談にも的確なアドバイスをもらえます。上司を単なる評価者としてではなく、キャリアの先輩・メンターとして関係を構築できれば、長期的な成長につながる支援を得られるでしょう。
職場ストレスの軽減とモチベーション維持
上司とのコミュニケーションがうまくいっていないと、職場に行くこと自体がストレスになりかねません。逆に、良好な関係が築けていれば、日々の業務における心理的負担が大幅に軽減されます。
例えば、分からないことを気軽に質問できる環境や、失敗しても適切なフィードバックがもらえる安心感は、業務へのモチベーションを高め、前向きな姿勢で仕事に取り組める原動力になります。また、自分の意見や提案が尊重されることで、仕事に対する主体性や創造性も発揮しやすくなるでしょう。
さらに、上司との良好な関係は周囲の同僚とのコミュニケーションにも良い影響を与え、チーム全体の雰囲気改善にもつながります。職場における心理的安全性が確保されることで、メンタルヘルスの維持や長期的なキャリア継続にもプラスに作用するのです。
上司とのコミュニケーションがうまくいかない4つの原因

上司とのコミュニケーションがうまくいかない状況に悩んでいる方は多いですが、その背景には具体的な原因があります。問題解決のためには、まずその根本原因を理解することが重要です。
ここでは、多くの職場で見られるコミュニケーション不全の主な原因を4つ解説します。
①立場と役割の違いを理解していない
上司と部下では組織内での立場や担う役割が根本的に異なります。上司は部門全体の成果や長期的な視点での判断を求められる一方、部下は個別の業務や短期的な目標達成に焦点を当てることが多いのです。
この違いを理解せずにコミュニケーションを取ると、お互いの優先事項がずれたまま会話が進みます。例えば、部下が個別タスクの効率化だけを考えた提案をしても、上司は部門全体への影響や他チームとの連携を考慮する必要があるため、単純に受け入れられないことがあります。
また、上司は経営層からの要請を受けて判断しなければならない立場にあることも多く、部下には見えない制約や条件の中で決断を迫られています。このような背景を知らないまま、上司の判断を「理解できない」と感じてしまうと、信頼関係が損なわれる原因になりかねません。
②世代による価値観と経験ギャップの見落とし
上司と部下の間には、年齢差によるコミュニケーションスタイルや価値観の違いが存在します。この違いは単なる「古い・新しい」という単純な対立ではなく、それぞれが育ってきた社会環境や教育背景に根ざした本質的なものです。
例えば、デジタルツールの活用について、若い世代にとっては当然の効率化手段でも、上の世代には「本当に必要なのか」と疑問を感じさせることがあります。また、「報告」の意味や頻度についても、世代によって認識が大きく異なることがあります。
このようなギャップを認識せず、自分の価値観や常識を基準にコミュニケーションを取ると、相手に「理解力がない」「柔軟性がない」といった誤解を与えかねません。世代間の違いを踏まえ、相手の視点や経験を尊重する姿勢が必要です。
③コミュニケーション目的の不明確さ
「何のために」という目的が不明確なままコミュニケーションを取ると、効果的な情報伝達ができません。単に「報告しておかなければ」という義務感だけで行う報告や、具体的な結論を求めないままで行う相談は、お互いの時間を無駄にしてしまいます。
特に上司への報告や相談の際、自分が「何を伝えたいのか」「どのような判断や支援を求めているのか」を明確にしないまま話し始めると、上司は適切な反応や判断ができません。目的があいまいなコミュニケーションは、誤解や齟齬を生み、結果として「話がかみ合わない」状況につながります。
また、上司からの指示に対しても、その背景や目的を理解せずに単に「言われた通りにする」姿勢では、期待される成果を上げられないことがあります。コミュニケーションの目的を明確にし、共有することが重要です。
④状況に合わない伝達手段の選択ミス
現代のビジネス環境では、対面、電話、メール、チャット、ビデオ会議など多様なコミュニケーションツールが使われています。しかし、伝えるべき内容や緊急度に合わない手段を選ぶと、情報が適切に伝わらないことがあります。
例えば、複雑な内容や微妙なニュアンスを含む話題は、文字だけのメールやチャットでは誤解を招きやすいでしょう。逆に、単純な事実確認だけであれば、わざわざ時間を取って対面で話す必要はありません。また、上司の働き方や好みに合わないツールを使うと、そもそも情報が届かないという事態も起こり得ます。
さらに、緊急性の高い内容をメールだけで済ませてしまったり、プライバシーに関わる話題をオープンなチャットで行ったりするなど、状況にそぐわない手段選びも問題です。伝える内容や目的、相手の特性に合わせた最適な伝達手段を選ぶ必要があります。
上司とのコミュニケーションで信頼関係を築く7つの実践テクニック

上司との間に信頼関係を構築することは、円滑なコミュニケーションの基盤となります。ここでは、明日から実践できる具体的なテクニックを7つ紹介します。
これらを継続的に取り入れることで、上司との関係を着実に改善し、職場での存在感と評価を高めていきましょう。
①上司の価値観を理解して会話の土台をつくる
上司とのコミュニケーションを改善するためには、まず相手の価値観や考え方を理解することが大切です。日々の会話や業務の中から、上司が何を大切にしているのか、どのような仕事の進め方を好むのかを観察しましょう。
例えば、細部にこだわる上司なのか、大局を重視する上司なのか、スピードを重視するのか、正確さにこだわるのかなど、仕事に対する姿勢や判断基準を把握します。また、過去の経験や専門分野、得意な領域についても知っておくと、共通の話題を見つけやすくなります。
上司の価値観を理解することで、「なぜそのような判断をするのか」が見えてくるため、指示や意見に対する理解が深まります。この理解を土台として、上司の考え方に沿った報告や提案ができるようになれば、スムーズなコミュニケーションが実現しやすくなります。
②質の高い報連相で信頼の基盤を固める
「報告・連絡・相談」は、上司との信頼関係を築く最も基本的な活動です。単にタイミングよく行うだけでなく、内容の質にこだわることで、その効果は大きく変わります。
質の高い報連相のポイントは以下の通りです。
|
特に重要なのは、問題が発生した場合や計画変更が必要な場合に、早めに相談することです。問題が大きくなる前に上司を巻き込むことで、一緒に解決策を考えるパートナーとしての関係性を築けます。
③積極的傾聴で上司の真意をつかむ
上司の話を「聞く」のではなく、積極的に「聴く」姿勢を持ちましょう。積極的傾聴とは、相手の言葉だけでなく、その背後にある意図や感情まで理解しようとする姿勢です。
具体的な傾聴のテクニックとしては、上司が話している間は目を見て集中すること、適切なタイミングでうなずきや相槌を打つこと、そして必要に応じて質問や確認を行うことが挙げられます。また、上司の言葉を自分なりに言い換えて確認する「パラフレージング」も有効です。
例えば「この資料は明日までに作成してください」という指示を受けた場合、単に「はい」と答えるだけでなく、「明日の何時までに必要でしょうか?特に重視すべき点はありますか?」と確認することで、より正確に意図を把握できます。
積極的傾聴によって上司の真意を理解することは、期待に応える成果を出すための第一歩となります。
④表情やトーンで印象を管理する非言語テクニック
コミュニケーションにおいて、言葉以外の要素が与える影響は予想以上に大きいものです。特に表情、声のトーン、姿勢などの非言語要素は、あなたの印象を大きく左右します。
例えば、報告や相談の際に暗い表情や小さな声では、自信がないという印象を与えかねません。一方で、適度な表情の豊かさや、クリアで落ち着いた声のトーンは、あなたのメッセージに説得力を持たせます。
また、姿勢も重要な要素です。猫背や下を向いた姿勢ではなく、背筋を伸ばし、相手と適切な距離感を保つことで、誠実さや自信が伝わります。加えて、適度なアイコンタクトを心がけることも信頼感を高めるポイントです。
これらの非言語テクニックを意識的に取り入れることで、あなたの言葉がより効果的に伝わり、上司に好印象を与えることができるでしょう。
⑤フィードバックを即行動に移して成果を見せる
上司からのフィードバックやアドバイスを素直に受け止め、すぐに実践に移すことは、信頼関係構築の強力な手段です。これは単に言われたことをそのまま実行するという意味ではなく、建設的な提案として捉え、自分なりに消化して行動に反映させることを指します。
例えば、プレゼンテーションについてアドバイスを受けたら、次の機会には必ずその点を意識して改善を図る、資料作成の方法について指摘を受けたら、すぐに修正して再提出するなど、具体的な行動で示すことが大切です。
フィードバックを行動に移すことで、あなたは「成長意欲が高く、柔軟性のある人材」という評価を得られるでしょう。また、アドバイスを実践して成果が出た場合は、その結果と感謝の気持ちを伝えることも忘れないようにしましょう。
⑥小さな成功体験の共有で信頼関係を強化する
上司との信頼関係を深めるためには、日々の小さな成功体験を共有することが効果的です。プロジェクトの大きな成果だけでなく、日常業務の中での改善点や良い結果を適切なタイミングで報告しましょう。
例えば、「先日ご提案いただいた方法で顧客対応したところ、とても喜んでいただけました」「前回のミーティングでのアドバイスを生かして、効率よく資料作成ができました」など、上司のアドバイスや指導が実を結んだ事例を具体的に伝えます。
このような小さな成功体験の共有は、上司にとっても自分の指導が役立っているという満足感を与え、あなたとの関係をより強固なものにします。また、上司があなたの成長を実感できれば、より重要な仕事を任せてもらえる可能性も高まります。
⑦上司の時間を尊重する効率的な対話術
多くの上司はさまざまな業務や責任を抱えており、常に時間に追われています。そのため、上司の時間を尊重する効率的なコミュニケーション方法を心がけることが重要です。
効率的な対話のポイントは以下の通りです。
|
また、会話の最後には必ず結論や次のアクションを確認し、認識のずれがないようにしましょう。上司の貴重な時間を効率的に活用できる部下は、信頼され、重要な役割を任せてもらえる可能性が高まります。
状況別・タイプ別の上司コミュニケーション戦略

上司とのコミュニケーションは、相手のタイプや状況によって戦略を変える必要があります。
ここでは、よくある状況やタイプ別に、効果的なコミュニケーション戦略を紹介します。自分の上司の特徴や職場環境に合わせて、最適なアプローチを見つけてください。
多忙な上司との短時間で成果を出す情報共有術
常に会議や業務に追われている多忙な上司とは、限られた時間で最大限の効果を得られるコミュニケーション方法が重要です。こうした上司との情報共有では、「PREP法」が効果的です。
PREP法とは、Point(結論)→ Reason(理由)→ Example(具体例)→ Point(結論の再確認)という順序で話を構成する方法です。最初に結論を述べ、その理由や根拠、具体例を簡潔に説明し、最後にもう一度結論を強調します。これにより、短時間でも要点がしっかり伝わります。
また、情報の優先順位を明確にし、「絶対に伝えるべきこと」と「時間があれば伝えること」を事前に整理しておくことも大切です。さらに、資料は視覚的に分かりやすくまとめ、必要な情報にすぐアクセスできるよう工夫しましょう。
多忙な上司にとって、時間を節約してくれる部下は非常に貴重な存在です。効率的なコミュニケーション術を身に付ければ、短い時間でも確実に信頼を獲得できるでしょう。
指示があいまいな上司から具体的意図を引き出す質問
「なんとなく良いものを作って」「使いやすくしておいて」など、あいまいな指示を出す上司は少なくありません。こうした状況では、適切な質問によって具体的な意図を引き出すスキルが重要になります。
具体的な意図を引き出すための質問テクニックには以下のようなものがあります。
|
質問する際は、単に「分かりません」と言うのではなく、自分なりの解釈や案を示した上で確認すると良いでしょう。例えば「〇〇という方向で進めようと思いますが、イメージに合っていますか?」というアプローチです。
あいまいな指示を具体化するプロセスを通じて、上司の思考パターンや判断基準を理解できるようになり、次第に「言われなくても分かる」関係が構築できます。
リモートワークでも信頼を深める定期的な接点作り
リモートワークでは、偶発的な会話や非言語コミュニケーションの機会が減るため、意識的に上司との接点を作る必要があります。オンライン環境でも信頼関係を構築・維持するためには、以下のような工夫が効果的です。
まず、定期的な1対1のミーティングを設定し、業務の進捗だけでなく、課題や成功体験も共有しましょう。15分程度の短い時間でも、定期的に行うことで関係性が維持できます。
また、チャットやメールでのやり取りでは、簡潔さだけでなく、時には親しみやすい表現を取り入れるなど、人間味のあるコミュニケーションを心がけましょう。
オンラインミーティングでは、カメラをオンにして表情を見せることも大切です。また、画面共有機能を活用して視覚的に情報を伝えると理解が深まります。リモート環境では特に「見えない部分」への不安が生じやすいため、通常よりも頻度を高めて進捗報告を行うことも信頼構築につながります。
物理的な距離があっても、このような工夫によって心理的距離を縮め、リモートワークでも強固な信頼関係を築くことが可能です。
厳格な上司との心理的安全性を保つ対話テクニック
厳格で批判的な上司とのコミュニケーションは、プレッシャーを感じやすく心理的な負担が大きいものです。しかし、適切なアプローチで心理的安全性を保ちながら、建設的な関係を築くことは可能です。
まず大切なのは、感情的にならず客観的な姿勢を保つことです。厳しい指摘を受けても、それを個人攻撃と捉えるのではなく、業務改善のためのフィードバックとして受け止める冷静さが必要です。また、批判に対して防衛的になるのではなく、「貴重なご指摘ありがとうございます」と感謝の姿勢を示すことも効果的です。
さらに、上司の期待値を事前に確認し、途中経過を小まめに報告することで、大きなズレが生じるリスクを減らせます。提出物は特に念入りにチェックし、予想される指摘事項は事前に対応しておくなど、先手を打つ姿勢も重要です。
厳格な上司との関係では、一朝一夕に信頼を得ることは難しいかもしれませんが、このような地道な努力を積み重ねることで、徐々に心理的な安全性を高め、建設的な関係へと発展させることができるでしょう。
上司・部下のコミュニケーションの改善ならコミュニケーション研修がおすすめ!

上司・部下のコミュニケーション改善のためには、コミュニケーション能力を高めることが必要です。そこで役立つのがコミュニケーション研修です。研修を通じて、自分の強みと改善点を具体的に把握し、実践的なスキルを身に付けることができます。
そこで1つの有力なツールとして「LIFO(ライフォ)」があります。
自己診断ツールLIFOとは
LIFO(Life Orientations)は、個人の行動スタイルを診断する自己診断ツールです。このツールは、自分の強みや行動パターンを理解するために役立ちます。
LIFOは4つの基本スタイルに基づいており、これらのスタイルはそれぞれ異なる行動特性や価値観を持っています。
自分がどのスタイルに属しているかを知ることで、より良いコミュニケーション方法やストレス時の行動傾向を把握することができます。
LIFOを活用したコミュニケーション研修
LIFOを活用したコミュニケーション研修では、まず参加者が自己診断を行い、自分の行動スタイルを理解します。この診断結果を基に、どのように他者と効果的にコミュニケーションを取るかを学びます。
研修では以下のような内容が含まれます。
|
LIFOを取り入れた研修に参加することで、個人のコミュニケーションスタイルを理解し、それをベースに他者との関係を改善するスキルを獲得できます。
これにより、職場や日常生活でのコミュニケーションがよりスムーズで効果的になることが期待できます。
上司・部下のコミュニケーションにLIFOを活用した支援事例

株式会社山梨放送/放送業
導入前の課題
新型コロナウイルス感染症の流行以前は、社内イベントを通じて活発にコミュニケーションが行われていましたが、コロナ禍により社内の人間関係が希薄化し、特に若手社員の早期離職が顕著になりました。
また、放送業界の人手不足と業務の多忙さから、社員教育には力を入れられずにいました。そこで、70周年プロジェクトの一環として「シゴトバ改革」を推進することが決まり、社員が自発的に提案し実行に移すボトムアップ型のアプローチを採用しました。
出会いと導入の決め手
各局や地元企業の事例調査によって、1on1ミーティングが効果的であると分かりましたが、社員の個性を理解するまでには至りませんでした。
キャリアコンサルタントの提案で、相互理解を深めるためにLIFO診断を導入しました。LIFOはその場で診断結果を得られるため、柔軟な勤務時間を抱える社員にも受検しやすく、コミュニケーション改善のツールとして活用が決定されました。
展開ステップと取り組み
1on1ミーティングを実施前に、全社員を対象にLIFOの活用法などを盛り込んだセミナーを実施しました。管理職と一般社員に分けたセミナーで、ミーティングの目的やLIFOの活用法を学びました。
セミナーを契機に、多くの社員が参加し、テーマへの高い関心が示されました。セミナー内容を随時アーカイブとして提供し、参加できなかった社員にも情報を共有しました。
導入後の感想と成果
LIFOの活用で、上司と部下の相互理解が進み、コミュニケーションのきっかけとなりました。1on1ミーティングでは、定期的にLIFOのスコアが話題となるなど、一歩踏み込んだ対話が実現しています。
中には、得られた結果を基に改善に取り組む社員も出始めています。このツールは、管理職のガイドとなり得る可能性があり、引き続きLIFOを活用していく方針です。
取り組みにおける課題と今後の展望
「シゴトバ改革」はボトムアップ式で進行しているため、部署ごとに進捗に差があります。また、1on1ミーティングの目的が理解されず、不満のぶつけ合いになるケースもあるため、意識改革が必要です。
社内通信などでLIFOの考え方を広め、1on1以外にも日常のコミュニケーションやチームビルディングに活用することを目指しています。特に新体制時や社員異動時に効果的であり、職場の活気を向上させることを期待しています。
▼事例の詳細については下記をご覧ください。
⇒株式会社山梨放送様 LIFO導入事例
まとめ:上司とのコミュニケーションで信頼を築き、キャリアを加速させよう
上司との効果的なコミュニケーションの取り方とは?課題とポイントを解説!について紹介してきました。
- 上司とのコミュニケーションの前提
- 上司とのコミュニケーションに悩む人が抱える3つの課題
- 上司とのコミュニケーションが円滑になると得られる3つのメリット
- 上司とのコミュニケーションがうまくいかない4つの原因
- 上司とのコミュニケーションで信頼関係を築く7つの実践テクニック
- 状況別・タイプ別の上司コミュニケーション戦略
- 上司・部下のコミュニケーションの改善ならコミュニケーション研修がおすすめ!
- 上司・部下のコミュニケーションにLIFOを活用した支援事例
上司とのコミュニケーションは、日常業務の一部にとどまらず、あなたのキャリア発展に直結する重要なスキルです。本記事では、上司も同じ人間であることを認識しつつ、組織における立場の違いを尊重することが基本となることを解説しました。
コミュニケーションがうまくいかない背景には、伝達の壁、信頼関係の欠如、世代間ギャップなどの課題があります。これらを解決することで、業務効率の向上、キャリア形成の機会獲得、職場ストレスの軽減といった明確なメリットが得られます。
うまくいかない主な原因は、立場と役割の違いへの理解不足、価値観のギャップ、目的の不明確さ、不適切な伝達手段の選択などです。これらを克服するために、上司の価値観理解、質の高い報連相、積極的傾聴、非言語コミュニケーションの活用、フィードバックの即時実践などの具体的なテクニックが効果的です。
最後に重要なのは、これらを単なる知識として終わらせず、実際の行動に移すことです。明日から実践できる小さな一歩を踏み出しましょう。
上司とのコミュニケーションは一朝一夕で完璧になるものではありませんが、継続的な努力が信頼獲得とキャリアの加速につながります。ぜひこれらのテクニックを実践し、より良い職場関係の構築にお役立てください。
株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。