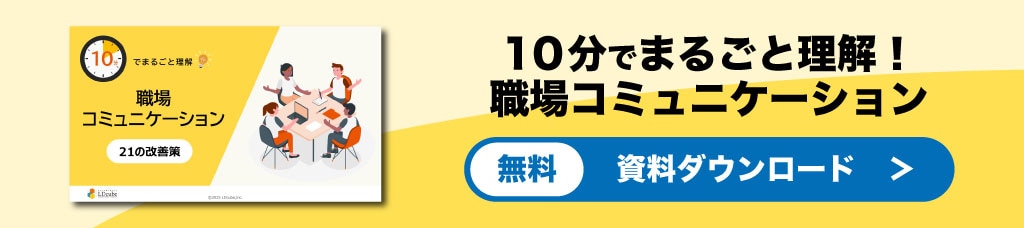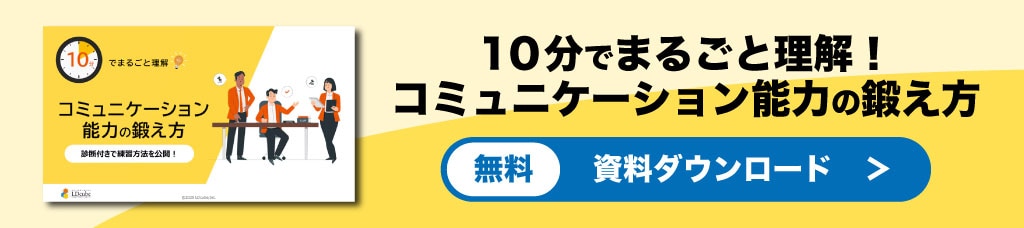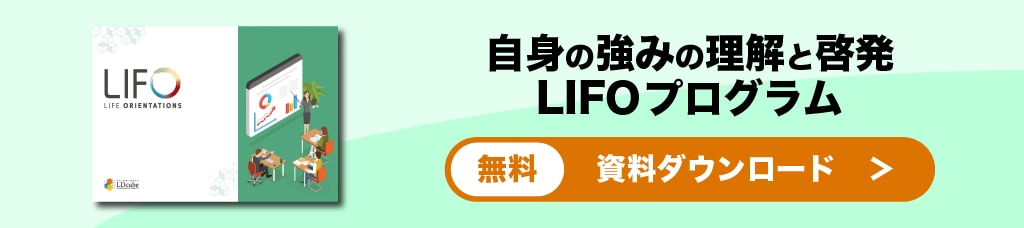仕事で円滑なコミュニケーションを実現する方法とは?ポイントを解説!
仕事の成功において、コミュニケーションの質は重要な役割を果たします。
しかし、多くのビジネスパーソンは日々の業務の中で「もっと円滑にコミュニケーションを取りたい」「意図が正確に伝わらない」という悩みを抱えています。
特にチームリーダーや管理職の方々にとって、効果的なコミュニケーションは単なるスキルではなく、組織の生産性と人材育成に直結する重要な課題です。
本記事では、仕事の場面で即座に実践できる7つのテクニックを中心に、円滑なコミュニケーションの実現方法をご紹介します。
これらのテクニックは、単に「話し方」や「聞き方」といった表面的なスキルにとどまらず、相手との信頼関係構築や組織文化の醸成にまで踏み込んだ本質的なアプローチです。
1on1面談からチーム会議、リモートワーク環境まで、さまざまな職場シーンに対応した実践的な方法と、それを支える環境づくりのポイントも解説します。さらに、人材育成の視点からコミュニケーションスキルを高める具体的な手法もお伝えします。
この記事を読み終えた後には、明日からすぐに実践できる効果的なテクニックを手に入れ、職場での意思疎通をより円滑にする第一歩を踏み出せるでしょう。
▼コミュニケーションについては下記で詳しく解説しています。
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
目次[非表示]
- 1.仕事で円滑なコミュニケーションを取るためのポイント
- 2.仕事で円滑なコミュニケーションが必要な2つのパターン
- 3.パターン①社内・職場でのコミュニケーションは職場単位で解決しよう
- 4.パターン②社外のステークホルダーとのコミュニケーションはスキルを磨こう
- 5.仕事で円滑なコミュニケーションがもたらす3つの効果
- 6.仕事で円滑なコミュニケーションを実現する7つの即効テクニック
- 7.仕事で円滑なコミュニケーションを支える環境づくり
- 8.仕事を円滑にするコミュニケーションのカギとなる自己理解と他者理解
- 9.仕事・コミュニケーションを円滑にするには「職場単位」のワークショップが最適
- 9.1.「職場単位」が効果的な理由
- 9.2.ワークショップの概要
- 10.仕事・コミュニケーションの円滑化にはLIFO®がおすすめ!
- 11.LIFOでコミュニケーショントレーニングを展開した支援事例(日本新薬)
- 12.まとめ:仕事の成果を高める、円滑なコミュニケーションの実践
仕事で円滑なコミュニケーションを取るためのポイント

職場でのコミュニケーションは、業務の効率化だけでなく人間関係の構築にも大きく影響します。
ここでは、職場で円滑なコミュニケーションを実現するための基本的なポイントを解説します。
|
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
仕事で円滑なコミュニケーションが必要な2つのパターン
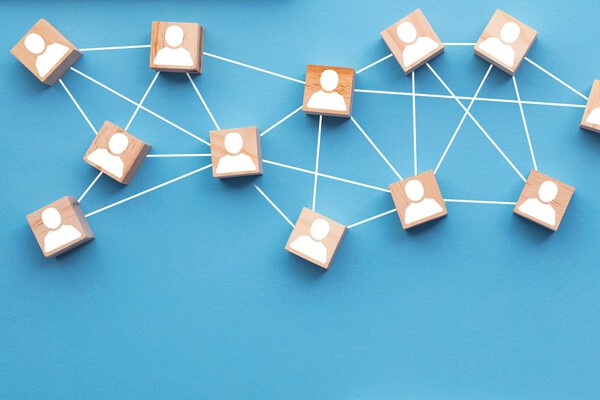
職場におけるコミュニケーションは、大きく分けて社内と社外の2つのパターンがあります。それぞれ対象や目的、必要なスキルが異なるため、状況に応じた適切なアプローチが求められます。
ここでは、それぞれのパターンの特徴と重要性について解説します。
パターン①社内・職場でのコミュニケーション
社内でのコミュニケーションには、同僚同士の横のコミュニケーション、上司と部下の縦のコミュニケーション、部署を超えた全体のコミュニケーションがあります。
特に重要なのは、日常的な情報共有や進捗報告、業務上の相談など、業務を円滑に進めるための意思疎通です。社内コミュニケーションが活発な職場では、必要な情報がタイムリーに共有され、問題が早期に発見・解決されやすくなります。
また、心理的安全性が高まり、メンバーが自分の意見や懸念を気軽に表明できる環境が整います。これにより、チーム全体の知識やスキルが共有され、業務効率と成果の向上につながります。
パターン②社外のステークホルダーとのコミュニケーション
社外とのコミュニケーションでは、顧客、取引先、協力会社、投資家などさまざまなステークホルダーとの関係構築が重要になります。社内とは異なり、組織文化や前提知識が共有されていないため、より明確で丁寧なコミュニケーションが求められます。
特に重要なのは、相手の立場や関心事を理解し、それに合わせた情報提供や提案を行うことです。例えば顧客とのコミュニケーションでは、専門用語を避け、顧客視点での説明が必要です。
また、長期的な信頼関係の構築を意識し、一方的な情報発信ではなく、相手の声に耳を傾け、フィードバックを積極的に取り入れる姿勢が大切です。社外と適切にコミュニケーションを取ることは、ビジネス機会の創出や企業イメージの向上につながります。
パターン①社内・職場でのコミュニケーションは職場単位で解決しよう

社内・職場でのコミュニケーション課題は、個人の努力だけでは解決が難しいケースも多くあります。組織的なアプローチで職場単位での改善に取り組むことで、より効果的かつ持続的な変化を生み出すことができます。
ここでは、職場単位でコミュニケーションを改善するための具体的な方法を紹介します。
職場単位でのワークショップの実施
コミュニケーション改善のためのワークショップは、チーム全体の意識共有と実践的なスキル向上に効果的です。例えば、「Good&new」というワークショップでは、メンバーが順番に「良かったこと」や「新しい発見」を共有し、互いに称賛し合います。
このような場を通じて、ポジティブなコミュニケーションの習慣が形成されていきます。
また、ロープレ形式で、難しい状況でのコミュニケーションを練習することも有効です。具体的なシナリオを設定し、フィードバックを通じてより良い対応方法を学ぶことができます。
ワークショップは、一度きりではなく定期的に実施することで、継続的な改善と定着が図れます。
職場でのガイドラインを設定する
職場内でのコミュニケーションにおける基本ルールやガイドラインを、チーム全体で話し合って設定することも重要です。例えば、「会議での発言機会を平等に設ける」「相手の意見を最後まで聞く」「建設的なフィードバックを心掛ける」などの基本原則を明確にします。
また、情報共有の方法(どのような情報をどのツールで共有するか)や緊急時の連絡体制なども含めると良いでしょう。チーム全員が参加して作成することで、自分たちのルールとして認識され、順守意識が高まります。
ガイドラインは形式的なものではなく、定期的に振り返りの機会を設け、実際の状況に合わせて柔軟に更新していくことが大切です。このようなプロセスを通じて、チーム特有のコミュニケーション文化が育まれていきます。
▼職場単位でのワークショップ実施については下記で詳しく解説しています。
⇒行動特性を踏まえた自分・自己理解を深めるワークショップ(研修)とは!
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
パターン②社外のステークホルダーとのコミュニケーションはスキルを磨こう

社外のステークホルダーとの円滑なコミュニケーションは、ビジネスの成功に直結します。組織を代表する位置づけで外部と接する機会が多い場合は、個人のコミュニケーションスキルを高める取り組みが特に重要です。
ここでは、社外コミュニケーションのスキルを効果的に向上させる方法を解説します。
コミュニケーション研修の実施
社外とのコミュニケーションスキルを向上させるには、体系的な研修がとても効果的です。特にクライアントや取引先とやり取りする機会が多い社員には、専門的な研修プログラムを提供することをお勧めします。
具体的には、傾聴力を高めるトレーニング、状況に応じた話し方の使い分け、非言語コミュニケーションの活用法、効果的なプレゼンテーション技術などが含まれます。
また、異文化コミュニケーションの研修も、グローバルなビジネス環境では欠かせません。研修では座学だけでなく、ロープレやケーススタディーを取り入れることで、実践的なスキルを身に付けることができます。
▼コミュニケーション研修については下記で詳しく解説しています。
⇒コミュニケーション研修とは何をする?目的や具体的な内容・進め方
学んだスキルを意識して使う
研修で学んだスキルは、意識して実践することで初めて身に付きます。例えば、重要な商談の前に「今日は特にアクティブリスニングを意識しよう」など、具体的な目標を立てて臨むことが効果的です。
また、会議やプレゼンテーション後に自己評価の時間を設け、「相手の反応はどうだったか」「もっと良い伝え方はなかったか」と振り返ることも大切です。上司や同僚からのフィードバックを積極的に求め、客観的な視点を取り入れることも効果的な学習方法です。新しいスキルの定着には時間がかかるため、焦らず継続的に実践することが重要です。
継続的に意識して練習する
コミュニケーションスキルの向上は一朝一夕では達成できません。継続的な意識と練習が不可欠です。日々の業務の中で小さな機会を見つけて練習することが効果的です。例えば、社内メールの書き方を工夫する、簡単な電話応対で丁寧な対応を心掛ける、など身近なところから始めましょう。
また、模範となる優れたコミュニケーターの話し方や対応を観察し、学ぶことも有効です。さらに、コミュニケーションに関する書籍やオンラインコースなどを活用して、自己学習を続けることも大切です。スキル向上の過程を記録し、定期的に振り返ることで、自分の成長を実感しながら、さらなる改善点を見つけることができます。
▼コミュニケーションの練習については下記で詳しく解説しています。
⇒コミュニケーション能力を高める効果的な練習法とは?|職場実践ガイド
▼コミュニケーション能力の鍛え方についてのお役立ち資料は下記からダウンロードできます。
仕事で円滑なコミュニケーションがもたらす3つの効果

円滑なコミュニケーションは職場にさまざまなポジティブな変化をもたらします。単なる情報伝達の効率化だけでなく、組織全体の活性化や企業の成長につながる重要な要素です。
ここでは、職場で円滑なコミュニケーションを実現することで得られる主な効果について解説します。
業務効率の向上と時間短縮
円滑なコミュニケーションは、業務プロセスの効率化と時間短縮に直結します。指示や情報が明確に伝わることで、誤解や認識の齟齬が減少し、手戻りや修正作業が少なくなります。
例えば、プロジェクトの初期段階で目標や役割分担が明確に共有されていれば、途中での大幅な軌道修正が必要になる可能性は低くなります。
また、疑問点があった際に気軽に質問できる環境があれば、不明確なまま作業を進めて後から大きな修正が必要になるといった事態を避けられます。適切なタイミングでの情報共有が行われることで、全体の業務フローがスムーズになり、結果として生産性の向上につながります。
チームの一体感と信頼関係の構築
良好なコミュニケーションは、チームメンバー間の信頼関係と一体感を醸成します。オープンで誠実なコミュニケーションが日常的に行われる環境では、メンバー同士が互いの考えや価値観を理解し、尊重する文化が育まれます。
これにより「心理的安全性」が高まり、メンバーが自分の意見や懸念を躊躇なく表明できるようになります。そうした環境では、創造的なアイデアが生まれやすく、問題解決も迅速に行われます。
また、メンバー同士が互いの強みや弱みを理解していれば、自然な助け合いも生まれ、チーム全体のパフォーマンスが向上します。強い一体感と信頼関係に基づくチームは、困難な状況や急な変化にも柔軟に対応できる強靭さを持ちます。
社員の成長スピードの加速
円滑なコミュニケーションが実現している職場では、社員の成長スピードが加速します。上司や先輩からの適切なフィードバックが日常的に行われることで、若手社員は自分の強みや改善点を客観的に認識し、効率的にスキルアップできます。
また、部門を越えた知識やノウハウの共有が活発に行われることで、組織全体の知的資産が個々の社員の成長を支える基盤となります。さらに、経営理念や戦略が明確に伝わっていれば、社員は自分の業務の意義や方向性を理解した上で主体的に行動できるようになります。
そうした環境では、社員のモチベーションと自律性が高まり、自己成長への意欲も強くなります。結果として、個人の成長が組織全体の成長につながる好循環が生まれます。
▼コミュニケーション能力の鍛え方についてのお役立ち資料は下記からダウンロードできます。
仕事で円滑なコミュニケーションを実現する7つの即効テクニック

職場でのコミュニケーションを即座に改善するためには、具体的なテクニックを意識的に実践することが効果的です。
ここでは、明日からすぐに実践できる、7つの即効性の高いテクニックを紹介します。日常的なコミュニケーションの中で少しずつ取り入れていくことで、職場の人間関係や業務効率の向上につながるでしょう。
①自己開示による信頼関係構築
適切な自己開示は、相手との距離を縮め、信頼関係を構築する効果があります。仕事に関する考え方や価値観、過去の経験などを共有することで、相手は「この人はどんな人なのか」を理解しやすくなります。
特に上司や先輩の立場にある人が、過去の失敗談や克服した課題について話すことは、部下や後輩に安心感を与え、本音で話せる関係づくりに役立ちます。
ただし、プライベートな話題はTPOを考慮し、相手との関係性に応じて開示の程度を調整することが大切です。自己開示は一方的ではなく、相手の反応を見ながら対話の中で自然に行うことがポイントです。
②相手への関心と承認を効果的に表現する
相手への関心を示し、良い点を認め、伝えることは、相手のモチベーションを高め、良好な関係構築に効果的です。
日々の業務の中で、相手の頑張りや成果、工夫している点などに気付いたら、具体的に褒めるよう心掛けましょう。「いつも丁寧な仕事をしていますね」「あの提案は視点が新しくて参考になりました」など、具体的なポイントを挙げて伝えると説得力が増します。
また、相手の興味や関心事について質問し、話を聞くことも、関心を示す重要な方法です。このような承認と関心の表現は、職場の雰囲気を明るくし、互いを高め合う文化の醸成につながります。
③相手の話を積極的に傾聴する
積極的な傾聴は、相手の信頼を得るための基本スキルです。傾聴とは単に黙って聞くだけでなく、相手の話に対して適切な反応を示しながら理解を深めていくプロセスです。
具体的には、相槌を打つ、要点を確認する、理解したことを言い換えて返す、適切な質問をするなどの技術が含まれます。
また、傾聴中は相手の話を遮らず、自分の意見や解決策を急いで提示しないよう注意しましょう。目線を合わせる、前のめりの姿勢を取るなど、非言語コミュニケーションも重要です。
相手が「自分の話を真剣に聞いてもらえている」と感じることで、本音を話しやすくなり、より深い意思疎通が可能になります。
④状況に応じた適切な話題選びと事前準備
円滑なコミュニケーションのためには、状況や相手に合わせた話題選びが重要です。業務関連の話題だけでなく、時事ネタやスポーツ、趣味など、気軽に話せる共通の話題を持っておくと会話のきっかけになります。
特に初対面の相手や緊張感のある場では、あらかじめ数個の話題を準備しておくと安心です。
また、重要な会議やプレゼンテーションの前には、伝えるべき内容を整理し、相手の興味や関心に合わせた切り口を考えておくことも効果的です。
話題選びの際は、政治や宗教など意見が対立しやすいテーマや、他者の悪口・陰口など不快感を与える可能性のある話題は避けるよう注意しましょう。
⑤PREP法を活用した明確な意図の伝達
PREP法(プレップ法)は、自分の考えを論理的かつ説得力を持って伝えるための効果的な方法です。PREP法では、最初に結論(Point)、次に理由(Reason)、そして具体例(Example)を示し、最後に再度結論(Point)を述べるという順序で話を組み立てます。
この方法を使うと、聞き手は話の要点を理解しやすく、なぜそのような結論に至ったのかの理由も明確に把握できます。
新しいプロジェクトの提案をする際の例:
|
上記のような構成で伝えると効果的です。
⑥非言語コミュニケーションを活用する
言葉だけでなく、表情、声のトーン、姿勢、ジェスチャーなどの非言語コミュニケーションも、メッセージを効果的に伝える重要な要素です。
例えば、相手の目を見て話す、適度な笑顔を心掛ける、前向きな姿勢を取るなどの工夫で、伝えたい内容がより明確に、好意的に受け止められやすくなります。メラビアンの法則によれば、コミュニケーションの印象は言語情報よりも非言語情報の影響が大きいとされています。
オンライン会議の場合も、カメラをオンにする、アイコンを適切なものにするなど、相手に配慮した姿勢が大切です。
自分の非言語的な表現を意識することで、より豊かで効果的なコミュニケーションが実現できます。
⑦建設的なフィードバックで相互成長を促す
フィードバックは、互いの成長を促すための重要なコミュニケーション手法です。効果的なフィードバックを行うには、まず相手の良い点を具体的に認め、その上で改善点を建設的に伝えることが大切です。
「サンドイッチ法」と呼ばれる、肯定的なコメント→改善点→肯定的なコメントという順序で伝える方法も効果的です。
改善点を伝える際は、相手の人格ではなく特定の行動や成果物に焦点を当て、「〜すべきだった」という評価ではなく「〜するとさらに良くなる」という前向きな提案として伝えましょう。
また、フィードバックを受ける側も、防衛的にならず、貴重な学びの機会として受け止める姿勢が重要です。相互に建設的なフィードバックを交換できる関係は、個人とチーム双方の成長を加速させます。
▼コミュニケーション能力の鍛え方についてのお役立ち資料は下記からダウンロードできます。
仕事で円滑なコミュニケーションを支える環境づくり

個人の努力だけでなく、組織としてコミュニケーションを促進する環境を整えることも重要です。適切な環境があれば、メンバー一人一人のコミュニケーションが活性化し、組織全体の連携がスムーズになります。
ここでは、円滑なコミュニケーションを支える環境づくりのポイントを解説します。
心理的安全性を高めるリーダーの言動と習慣
心理的安全性とは、自分の意見や懸念を表明しても否定されたり罰せられたりしないという確信が共有された状態です。リーダーの言動はこの心理的安全性の構築に大きく影響します。
具体的には、リーダー自身が積極的に自己開示を行い、自分の失敗談を共有することで、「完璧でなくても大丈夫」というメッセージを伝えられます。
また、メンバーからの質問や意見に対して「良い質問ですね」「興味深い視点ですね」と肯定的に反応し、建設的な対話を促進することも重要です。
さらに、ミーティングでは全員に発言の機会を設け、異なる意見も尊重する姿勢を示すことで、多様な視点が歓迎される雰囲気が醸成されます。心理的安全性の高いチームでは、創造的なアイデアが生まれやすく、問題の早期発見・解決も促進されます。
円滑なコミュニケーションを促進するツール活用
適切なコミュニケーションツールの導入と活用は、情報共有と意見交換を効率化します。チャットツールやビデオ会議システムなどのデジタルツールは、場所や時間に縛られないコミュニケーションを可能にし、特にリモートワークの増加に伴い重要性が高まっています。
ただし、ツールの導入だけでは不十分で、「どのツールをどのような目的で使うか」という利用ルールを明確にすることが大切です。
目的に応じたツールの使い分け例:
|
また、社内SNSや感謝を共有するプラットフォームなどを導入することで、日常的なポジティブなコミュニケーションも促進できます。ツールの選定と運用ルールの策定には、実際のユーザーである社員の意見を取り入れることが成功のカギとなります。
定期的なコミュニケーション機会の設計
計画的かつ定期的なコミュニケーションの機会を設けることで、組織内の情報流通と関係構築が促進されます。
効果的なコミュニケーション機会の例:
|
これらの機会は、業務進捗の共有だけでなく、メンバー間の相互理解を深める貴重な機会となります。特にランチタイムは比較的リラックスした雰囲気で会話ができるため、普段は話す機会の少ないメンバー同士の、コミュニケーションのきっかけになります。
定期的な「読書・対話会」「ブレーンストーミングセッション」など、創造的な対話の場を設けることも、新しい発想や改善案を生み出すのに役立ちます。
これらの機会を設計する際は、参加者の多様性と自発性を重視し、形式的な場にならないよう工夫することが大切です。定期的なコミュニケーション機会は、組織の一体感と活力を高める基盤となります。
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
仕事を円滑にするコミュニケーションのカギとなる自己理解と他者理解
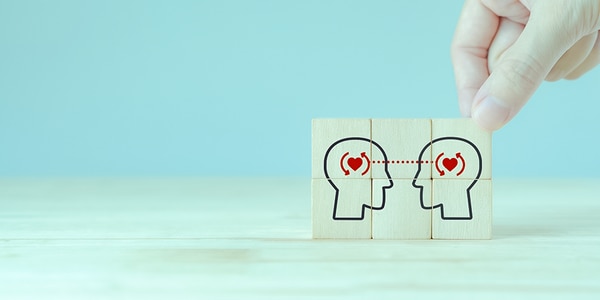
仕事を円滑にするコミュニケーションのカギは、テクニックや仕組みだけでなく、コミュニケーションの基盤となる「自己理解」と「他者理解」です。
自分自身のコミュニケーションスタイルや価値観を理解し、同時に他者の多様性を受け入れることで、より深い相互理解が可能になります。
本章では、コミュニケーション不全の改善に役立つ自己理解と他者理解のアプローチについて解説します。
仕事を円滑にするコミュニケーションと自己理解・他者理解の関係性
仕事を円滑にするコミュニケーションは、自己と他者に対する理解が重要です。自分のコミュニケーションスタイルや価値観、思考パターンを理解していないと、無意識に相手に誤解を与えたり、一方的なコミュニケーションになったりしがちです。
同様に、相手の特性や背景を理解せずにコミュニケーションを取ると、メッセージが適切に伝わらず、誤解や摩擦が生じやすくなります。
例えば、自分が「直接的で率直な表現」を好むタイプだと自覚せずに、全ての人に対して同じようにコミュニケーションを取ると、「婉曲的な表現」を好む相手には攻撃的に映る可能性があります。逆に、相手が「具体的な指示を求めるタイプ」であることを理解せずに抽象的な表現で指示を出すと、混乱や不安を招くでしょう。
自己理解と他者理解が深まると、こうした「ズレ」を認識し、相手に合わせたコミュニケーション方法を選択できるようになります。また、誤解が生じた際にも、その背景を理解して建設的に対処することが可能になります。
コミュニケーション不全の解消には、この「相互理解の深化」が不可欠なのです。
自己理解を深める方法
自己理解を深めるには、自分のコミュニケーションスタイルや行動パターン、価値観などを客観的に観察し、認識することが重要です。以下に、自己理解を深めるための具体的な方法を紹介します。
まず、各種の行動特性診断やコミュニケーションスタイル診断を活用する方法があります。LIFO(Life Orientations)、MBTI(マイヤーズ・ブリッグス・タイプインディケーター)、DISC、エニアグラムなどの診断ツールは、自分の特性を理解する手がかりになります。
また、日々の振り返りも効果的です。1日の終わりに「今日のコミュニケーションでうまくいったこと・いかなかったこと」を簡単にメモする習慣をつけると、自分のパターンが見えてきます。特に、感情が強く動いた場面を振り返ることで、自分の価値観や反応パターンに気付くことができます。
さらに、信頼できる人からのフィードバックを求めることも重要です。自分では気付かない自分の特徴や影響を、他者の視点から教えてもらうことで、より客観的な自己理解が可能になります。
定期的な内省の時間を設けることも効果的です。
「自分が大切にしている価値観は何か」「どのような環境で最もエネルギーを感じるか」「ストレスを感じるときの反応パターンは何か」といった問いを自分に投げかけることで、自己理解が深まります。
▼自己理解を深める方法については下記で詳しく解説しています。
⇒自己理解を深める方法とは!5つの情報源について詳しく解説
他者理解を深める方法
他者理解を深めるためには、相手の視点に立って考える想像力と、相手の特性を受け入れる柔軟性が求められます。以下に、他者理解を深めるための具体的なアプローチを紹介します。
最も基本的なのは、積極的に「聴く」姿勢です。相手の話を途中で遮らず、自分の考えを押し付けるのではなく、相手の言葉に真摯に耳を傾けます。特に、「なぜそう考えるのか」という背景や文脈を理解することが重要です。
また、非言語コミュニケーションにも注意を払いましょう。相手の表情、声のトーン、姿勢などからも多くの情報を読み取ることができます。特に、言葉と非言語メッセージに不一致がある場合は、そこに重要な手がかりが隠されていることが多いです。
多様性への理解も他者理解のカギとなります。異なる文化的背景、世代、専門分野、性格などが、コミュニケーションスタイルにどのような影響を与えるかを学ぶことで、「違い」を問題ではなく、豊かさとして捉えることができるようになります。
さらに、「確認の質問」を積極的に行うことも効果的です。「あなたの言っていることを確認させてください」と前置きして相手の発言を言い換えたり、「もう少し詳しく教えてください」と掘り下げたりすることで、誤解を防ぎ、相手への理解を深めることができます。
▼他者理解については下記で詳しく解説しています。
⇒他者理解とは?その意味と必要な7つのこと─職場でできる施策も紹介
自己理解・他者理解で仕事とコミュニケーションを円滑にする
自己理解と他者理解が深まると、仕事とコミュニケーションが円滑になり以下のような変化が生まれます。
まず、相手に合わせたコミュニケーション方法を選択できるようになります。例えば、詳細を重視する相手には具体的な情報を提供し、全体像を重視する相手にはコンセプトや目的を強調するなど、相手の特性に合わせた伝え方が可能になります。
また、誤解や摩擦が生じた際にも、それを個人的な問題ではなく「スタイルや価値観の違い」として捉えられるようになり、より建設的な対話が可能になります。「あなたが悪い」「私が正しい」という二項対立ではなく、「私たちはどうすれば相互理解できるか」という協働的なアプローチが取れるようになります。
さらに、チーム内の多様性を強みとして生かすことができるようになります。異なる視点や特性を持つメンバーがそれぞれの強みを発揮し、互いの弱みを補完し合うことで、チーム全体のパフォーマンスが向上します。
自己理解と他者理解を深めるには時間と努力が必要ですが、これらは仕事やコミュニケーションを円滑にするための重要な投資となります。
組織としても、こうした相互理解を促進するための研修やワークショップを定期的に実施することで、コミュニケーション文化の変革を支援することが重要です。
▼自己理解と他者理解を深めることを診断付きで体験できるように解説しています。
⇒コミュニケーション能力を鍛える具体的な方法とは?診断付きで練習方法を公開!
▼コミュニケーション能力の鍛え方についてのお役立ち資料は下記からダウンロードできます。
仕事・コミュニケーションを円滑にするには「職場単位」のワークショップが最適

これまで見てきたように、仕事とコミュニケーションを円滑にするにはさまざまなアプローチがありますが、特に効果的なのが「職場単位」で行うワークショップです。
なぜ職場単位のアプローチが効果的なのか、具体的にどのようなワークショップが有効なのかについて解説します。
「職場単位」が効果的な理由
仕事とコミュニケーションの円滑化には、個人の意識やスキルの向上だけでなく、職場全体の文化や関係性の変革が不可欠です。「職場単位」でのワークショップが効果的である理由は、以下のような点にあります。
まず、仕事・コミュニケーションの円滑化は「関係性の問題」であり、個人だけでは解決できない課題です。1人がコミュニケーションスキルを向上させても、周囲の環境が変わらなければ、組織全体の改善にはつながりません。職場単位のアプローチなら、メンバー全員が同じ理解と目標を共有することで、持続的な変化が可能になります。
また、日常的にコミュニケーションを取り合うメンバー同士が一緒に学び、実践することで、すぐに実務に生かせる具体的な改善策が見つかりやすくなります。「自分たちの職場」という具体的な文脈の中で学ぶことで、抽象的な理論ではなく、実践的な解決策を見いだすことができます。
さらに、ワークショップの場での体験を通じて、普段のコミュニケーションでは表面化しないような、深い相互理解ができることも大きなメリットです。普段とは異なる環境で対話することで、新たな気付きや関係性の変化が生まれやすくなります。
ワークショップの概要
効果的なコミュニケーションワークショップは、一般的に以下のような要素で構成されます。
まず、「現状把握と課題の共有」から始めます。自職場のコミュニケーションの現状を客観的に評価し、具体的にどのような課題があるのかを全員で共有します。この段階では、匿名のアンケートやカードワークなどを活用して、率直な意見が出やすい環境をつくることが重要です。
次に、「コミュニケーションスタイルの相互理解」を深めます。各メンバーのコミュニケーションスタイルや価値観、働き方の特徴などを、診断ツールなどを用いて可視化し、お互いの「違い」への理解を深めます。これにより、「相手の行動の意図」を正しく理解できるようになり、誤解や摩擦が減少します。
そして、「具体的な改善策の策定」に移ります。課題とメンバーの特性を踏まえ、自分たちの職場に最適なコミュニケーションのルールや仕組みを全員で考えます。この際、全員が当事者意識を持って参加し、自分たちで決めたルールという認識を持つことが重要です。
最後に、「アクションプランの作成とフォローアップ」で締めくくります。決定した改善策を具体的な行動計画に落とし込み、誰がいつまでに何をするのかを明確にします。また、定期的な振り返りの機会を設定し、継続的な改善サイクルを回していく仕組みを作ります。
ワークショップの実施には、以下のようなポイントが重要です。
|
このようなワークショップは、単発で終わらせるのではなく、半年〜1年に1度程度の頻度で定期的に実施することで、継続的な改善効果が期待できます。また、日常業務の中でも定期的に振り返りの機会を設けることで、ワークショップの効果を持続させることができます。
職場単位のワークショップは、仕事・コミュニケーションの円滑化だけでなく、チームの一体感やメンバーの帰属意識を高める効果もあります。「自分たちの職場を自分たちで良くしていく」という共通体験は、チームの結束力を強め、職場の活性化につながります。
▼職場単位でのワークショップについては下記で詳しく解説しています。
⇒行動特性を踏まえた自分・自己理解を深めるワークショップ(研修)とは!
仕事・コミュニケーションの円滑化にはLIFO®がおすすめ!

仕事・コミュニケーションの円滑化には自己診断ツールLIFO(Life Orientations)を活用した職場単位でのワークショップがおすすめです。
なぜなら、LIFOプログラムは心理学や行動科学をベースにして組み立てられた行動特性診断をベースに、職場単位でワークショップを行うためのワークブックなどのツールも体系的にそろえられているからです。
また、体系立てられたツールの使い方を社内トレーナーの方々にライセンス提供もされており、社内トレーナーの方々が職場単位でワークショップを展開していくことも可能です。下記に概要を紹介します。
自己診断ツールLIFOとは
LIFO(Life Orientations)は、個人の行動スタイルを診断する自己診断ツールです。このツールは、自分の強みや行動パターンを理解するために役立ちます。
LIFOは4つの基本スタイルに基づいており、これらのスタイルはそれぞれ異なる行動特性や価値観を持っています。
自分がどのスタイルに属しているかを知ることで、より良いコミュニケーション方法やストレス時の行動傾向を把握することができます。
LIFOを活用したコミュニケーション研修
LIFOを活用したコミュニケーション研修では、まず参加者が自己診断を行い、自分の行動スタイルを理解します。
この診断結果を基に、どのようにして他者と効果的にコミュニケーションを取るかを学びます。
研修では以下のような内容が含まれます。
|
これにより、職場や日常生活でのコミュニケーションがよりスムーズで効果的になることが期待できます。
LIFO®プログラムは社内トレーナーで展開可能
LIFO®プログラムは、これまでの活用実績と実用性から、企業内でのトレーニングにおいて自信を持っておすすめできるプログラムです。
社内展開にあたっては、特定の準備と手続きを経ることで、コストを抑えながら、外部講師に委託したかのように、社内トレーナーによる効果的なプログラムを展開することが可能です。
以下に、その流れを詳しく説明します。
|
LIFOでコミュニケーショントレーニングを展開した支援事例(日本新薬)

日本新薬株式会社/医薬品・機能食品事業
導入前の課題
私たちの会社は、コミュニケーションの向上と変化対応力の強化を目指し、社内でいくつかの課題に直面していました。
表面的には社員同士のコミュニケーションは取れているように見えましたが、実際には意思疎通が不十分な場面も多く見受けられました。特に、マネジャーとメンバー間や異なる部署間でのコミュニケーションの円滑化が求められていたのです。
また、中途採用が増える中で、オンボーディングを円滑に進めるために、効果的なコミュニケーションツールの導入が必要でした。これに加えて、業界環境の変化に対応し、社員の変化適応力を強化する必要もありました。
出会いと導入
営業チームのコミュニケーションを円滑にするツールを模索している中で、「LIFO」と出会いました。「LIFO」の魅力は、そのプログラムの分かりやすさと社内への展開が容易な点にありました。
他のツールとは異なり、内製研修で効果的に活用できるプログラムであったため、導入が決まりました。
LIFOスコア取得後の詳細な個別レポートは、社員一人ひとりの特性を理解する「取扱説明書」として機能し、自己理解を深める助けとなりました。役員からの強力な支持を得て、全社展開が迅速に進みました。
展開ステップと取り組み
導入当初、LIFOは営業所長研修の一環として活用され、研修を終えた所長がサブトレーナーとなり、現場での実施を推進しました。
その結果、営業所長はLIFOを用いてチームの構築とコミュニケーションの質を向上させることができました。3年目には、LIFOが全社で共通言語となり、コミュニケーションが大幅に改善しました。
現在はチーム単位でのワークショップを実施し、2024年度には新入社員を含む多くの社員が参加する予定です。この取り組みの成果は、社内だけでなく、外部からも高く評価されています。
導入後の感想・成果
LIFOプログラムの導入により、コミュニケーションの質が向上し、研修を超えて職場活用や人事戦略へのデータ活用の幅が広がりました。
結果として、3年以内の離職率も低い水準で推移しています。職場での活用可能性に関するアンケートでも高い評価を得ており、LIFOが共通言語となることで、活発なコミュニケーションと効果的な施策の運用が進んでいます。
今後の課題と取り組み
今後は、全社員を対象にLIFOを定期的に活用し、コミュニケーションの強化を継続することが重要です。特にオンボーディング施策に重点を置き、新入社員が早期に職場に馴染めるようサポートしていきます。
データを基にした効果的な人事戦略を構築し、社員特性に応じた配属や異動を実現することで、組織全体の最適化を目指します。最終的には、グループ企業全体での展開を見据えています。このような取り組みを通じて、社員同士の相互理解を深化させ、組織力をさらに強化していきます。
▼事例の全文は下記をご覧ください。
⇒日本新薬株式会社 行動特性診断の活用で実現する、他者に合わせたコミュニケーションの活性化
まとめ:仕事の成果を高める、円滑なコミュニケーションの実践
仕事で円滑なコミュニケーションを実現する方法とは?ポイントを解説!について紹介してきました。
- 仕事で円滑なコミュニケーションを取るためのポイント
- 仕事で円滑なコミュニケーションが必要な2つのパターン
- パターン①社内・職場でのコミュニケーションは職場単位で解決しよう
- パターン②社外のステークホルダーとのコミュニケーションはスキルを磨こう
- 仕事で円滑なコミュニケーションがもたらす3つの効果
- 仕事で円滑なコミュニケーションを実現する7つの即効テクニック
- 仕事で円滑なコミュニケーションを支える環境づくり
- 仕事を円滑にするコミュニケーションのカギとなる自己理解と他者理解
- 仕事・コミュニケーションを円滑にするには「職場単位」のワークショップが最適
- 仕事・コミュニケーションの円滑化にはLIFO®がおすすめ!
- LIFOでコミュニケーショントレーニングを展開した支援事例(日本新薬)
コミュニケーションの基本ポイントからパターン別のアプローチ、即効性のあるテクニック、そして環境づくりまで、多角的に解説しました。
職場でのコミュニケーションは、ビジネス成果に直結する重要な要素です。円滑なコミュニケーションにより、業務効率の向上、チームの一体感と信頼関係の構築、社員の成長スピードの加速といった効果が期待できます。しかし、効果的なコミュニケーションは自然に生まれるものではなく、個人と組織の双方が意識的に取り組むことが必要です。
個人レベルでは、「聴く」と「話す」のバランス、自己開示、相手への関心と承認の表現、積極的な傾聴など、日々の実践を通じてスキルを高めていくことが大切です。特に即効性の高い7つのテクニックは、明日からすぐに実践できるものばかりです。小さな変化から始めて、徐々にコミュニケーションの質を高めていきましょう。
一方、組織レベルでは、心理的安全性を高める風土づくり、効果的なツールの活用、定期的なコミュニケーション機会の設計など、環境面からのアプローチも欠かせません。リーダーの言動や組織の制度・仕組みが、個人のコミュニケーション行動に大きな影響を与えることを認識し、戦略的に環境を整えていくことが重要です。
円滑なコミュニケーションの実現には特効薬はなく、地道な積み重ねが必要です。しかし、その成果は必ず組織の力となって現れます。この記事で紹介した方法を参考に、自分自身と組織のコミュニケーションをさらに良いものにしていきましょう。一人ひとりの小さな変化が、やがて組織全体の大きな変革につながるのです。
株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。