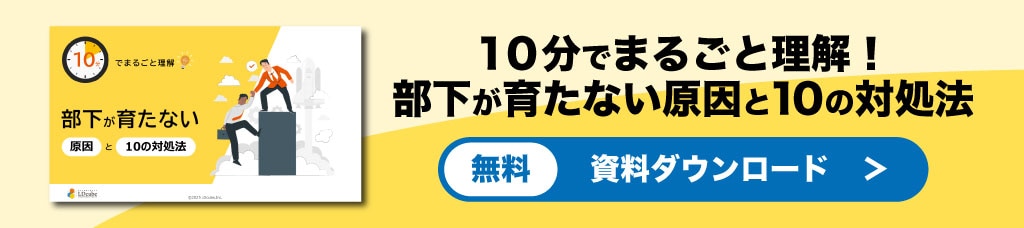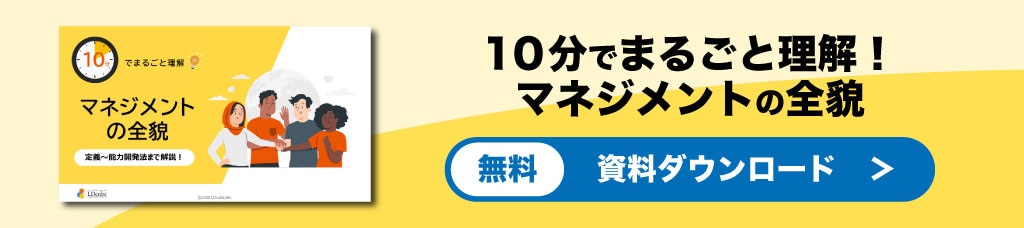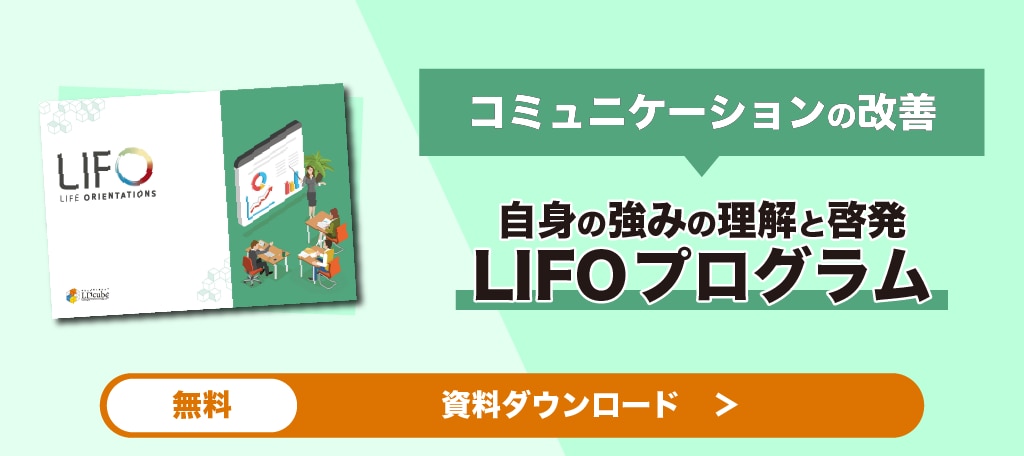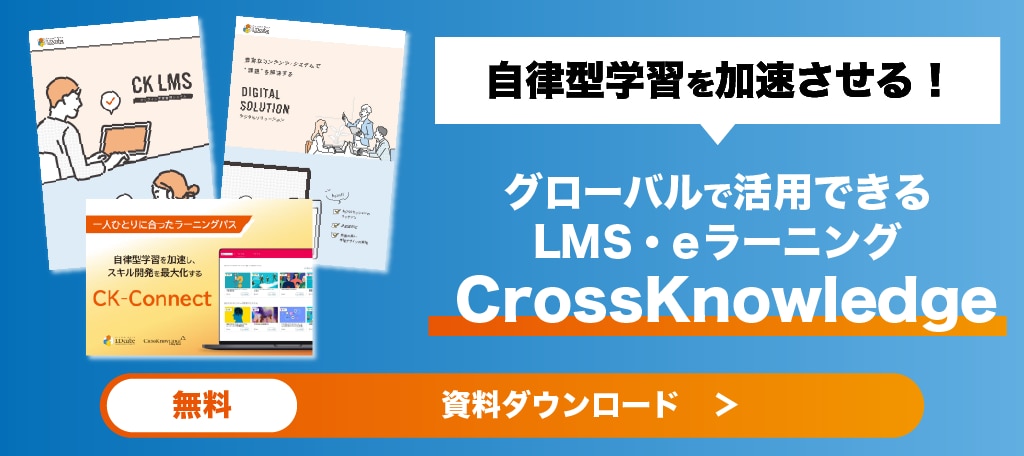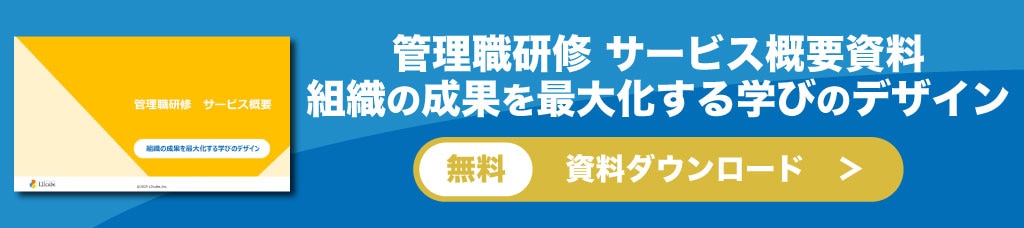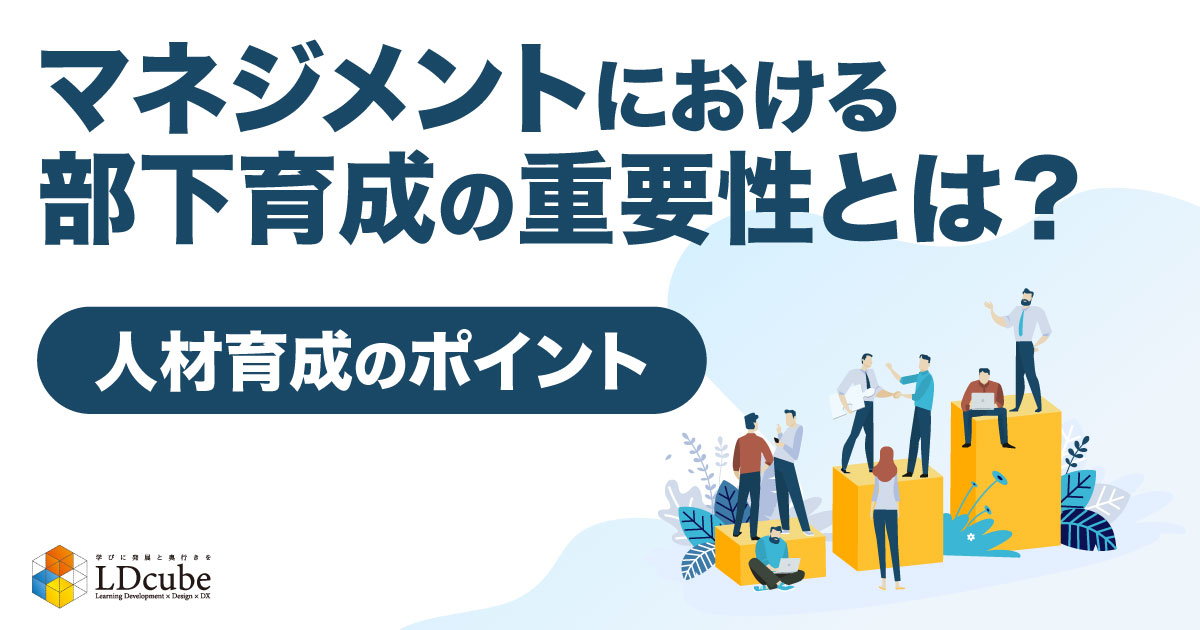
マネジメントにおける部下育成の重要性とは?人材育成のポイントを解説!
「部下が指示待ちで主体性がない」「育成方法が分からず場当たり的になってしまう」このような悩みを抱える管理職の方は多いのではないでしょうか。
実際に、多くの企業で、
「部下が育たない」
「主体的な人材を育てられない」
「次の管理職候補が育たない」
といった課題が深刻化しています。そのような中で、マネジメントにおける部下育成の重要性を認識し、意図して取り組んでいくことで、部下育成は確実に成功へと近づいていきます。
本記事では、部下育成に悩む管理職の方に向けて、実践的なマネジメントスキルと具体的な5つのステップを詳しく解説します。単なる理論ではなく、現場ですぐに活用できる手法を中心に、主体的に動ける人材を育てるためのノウハウをお伝えします。
記事を読み終える頃には、部下育成のために何をすればよいかが分かり、自信を持って部下育成に取り組むための具体的な道筋が見えてくるでしょう。
▼管理職研修については下記で解説しています。
▼マネジメントについてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。
▼部下育成やマネジメントについての資料は下記からダウンロードできます。
目次[非表示]
- 1.部下育成はマネジメントの最重要タスク
- 2.マネジメントでの部下育成の重要性と課題
- 3.マネジメントでの部下育成に必要なスキル
- 4.部下育成を成功させるマネジメント5ステップ
- 4.1.ステップ1:部下の現状把握と目標設定
- 4.2.ステップ2:信頼関係の構築と心理的安全性の確保
- 4.3.ステップ3:挑戦的な仕事の機会を提供(タスクアサイン)
- 4.4.ステップ4:継続的なフィードバック
- 4.5.ステップ5:パーソナライズした学習環境の提供
- 5.組織の部下育成力を高める2つのアプローチ
- 6.主体的な部下を育成するマネジメント実践法(組織開発アプローチ)
- 7.部下育成の効果を高める組織的マネジメント(デジタル学習環境の構築)
- 7.1.デジタル学習環境の構築
- 7.2.OJTのデジタル化を進める
- 7.3.OJTとOff-JTを効果的に組み合わせる
- 7.4.学習行動のデータを活用する
- 8.部下育成をうまく展開している支援事例紹介
- 9.まとめ:マネジメントにおいて部下育成は最重要
部下育成はマネジメントの最重要タスク

現代の管理職にとって、部下育成は単なる業務の1つではなく、組織の将来を決定づける最重要タスクです。優秀な人材の育成は、組織の競争力向上や持続的成長の基盤となります。
最初の上司で新入社員の人生が決まる!?
新入社員の初期キャリアにおいて、上司の影響力は絶大です。1970年代~1980年代にかけて行われた研究により、新入社員が入社して3年間の直属上司との垂直的交換関係(上司と部下のやり取り)が入社13年後の昇進昇格に直接的な影響があることが明らかにされています。
つまり、入社して3年間の上司との関わりが人生に大きな影響を与えるのです。上司の言動や態度は、新入社員の仕事に対する価値観や姿勢を形作る重要な要素となります。将来のキャリアパスにおけるロールモデルとしても機能し、仕事の意義や社会的価値の理解を導く存在でもあります。
また、適切な指導と機会提供により、スキル習得の質と速度は大きく変化します。実践的なフィードバックの質は、スキルの定着に直結し、失敗から学ぶ機会を適切に提供することで、成長を加速させることができます。さらに、日々の承認や指導を通じて、仕事への意欲に直接的な影響を与え、適切な目標設定と達成感の提供により、成長意欲を持続させる重要な役割も担っています。
・参考:経営行動科学第2巻第1号「管理職へのキャリア発達ーー入社13年目のフォローアップーー」
仕事を与える上司は部下育成がうまい
部下育成が得意な上司に共通するのは、単に指示を出すだけでなく、成長につながる「仕事を与える」能力に長けていることです。これらの上司は、部下の現在のスキルレベルを正確に把握し、適度な挑戦を含む業務を割り振ります。
効果的な仕事の与え方には、段階的な権限委譲、明確な目標設定、そして継続的なサポートが含まれます。部下が新しいスキルを身に付けながら成果を上げられるよう、適切なバランスで挑戦とサポートを提供することで、部下の成長を加速させることができるのです。
▼仕事を与える上司については下記で詳しく解説しています。
⇒部下が育ちにくい原因と10の対処法とは!「仕事」を与えない上司の部下は育たない?
マネジメントでの部下育成の重要性と課題

部下育成の成功は、単に個人の成長にとどまらず、組織全体の競争力向上に直結する重要な要素です。しかし、多くの管理職が育成に関する課題を抱えているのが現実です。
部下育成がもたらす組織への影響
効果的な部下育成は、組織に多面的なメリットをもたらします。まず、適切な育成を受けた社員は離職率が低く、長期的な人材定着につながります。また、スキルアップした部下が高いパフォーマンスを発揮することで、チーム全体の生産性が向上します。
さらに重要なのは、次世代のリーダー候補を計画的・継続的に育成できることです。現在の管理職が部下育成に労力をかけることで、将来の組織運営を担う人材のパイプラインを構築できます。部下育成の文化が根付いた組織では、学習意欲の高い優秀な人材が集まりやすくなり、組織文化の向上にも寄与します。
多くの管理職が抱える部下育成の悩み
現実的には、多くの管理職が部下育成に関して深刻な悩みを抱えています。最も多い悩みは「部下が指示待ちになってしまう」ことです。自発的に行動してほしいと思いながらも、結果的に部下の主体性を育てられていないケースが頻発しています。
また、部下のモチベーション管理に苦慮する管理職も多いです。個々の価値観や目標が多様化する中で、一人一人に適したアプローチを見つけることが困難になっています。さらに、現代ではプレイングマネジャーが多く、プレーヤーとして自身の業務に追われ、マネジャーとして部下育成に十分な時間を確保できないという時間的制約も大きな課題となっています。
部下育成に失敗する典型的なパターン
部下育成の失敗には、いくつかの典型的なパターンが存在します。感情的で高圧的な態度を取ってしまうケースでは、部下が恐怖心から萎縮し、自発的な行動を取れなくなります。また、失敗してしまうことを恐れて簡単にこなせる仕事しか任せない管理職の下では、部下は成長機会を得られず、能力開発が停滞してしまいます。
計画性のない場当たり的な関わりも失敗の原因となります。明確な目標設定がなく、体系的な育成計画が存在しない環境では、上司も部下も成長方向性を見失ってしまいます。さらに、一方的な指導に終始し、部下の意見や考えを聞かない管理職の下では、部下の主体性や創造性が育まれることはありません。
マネジメントでの部下育成に必要なスキル

効果的な部下育成を実現するためには、管理職が特定のスキルを習得し、実践することが不可欠です。これらのスキルは相互に関連し合いながら、部下の成長を促進します。
コミュニケーション能力
部下育成の基盤となるのがコミュニケーション能力です。単に情報を伝えるだけでなく、部下の話を真摯に聞く傾聴スキルが重要となります。部下が抱える課題や悩みを理解し、適切なアドバイスを提供するためには、まず相手の状況を正確に把握することが必要です。
効果的な質問を投げかけることで、部下自身に考えさせ、気付きを促すことも重要なスキルです。「どう思う?」「なぜそう考えたの?」といったオープンクエスチョンにより、部下の思考力を育成し、主体的な行動を引き出すことができます。また、信頼関係の構築には一貫性のある言動と、部下への敬意を示すコミュニケーションが欠かせません。
目標設定力
部下の成長を促すためには、明確で達成可能な(しっかりやれば達成できる)目標設定が不可欠です。目標は具体的で測定可能である必要があり、部下が自分の進歩を実感できるものでなければなりません。目標設定でのポイントは、上司が一方的に目標を設定するのではなく、部下との対話を通じて合意形成することです。
部下自身が目標設定に参加することで、コミットメントが高まり、主体的な取り組みが期待できます。また、大きな目標を小さなステップに分解し、段階的な達成感を味わえるような設計も重要です。定期的な進捗確認と必要に応じた軌道修正により、目標達成に向けた継続的なサポートを提供します。
タスクアサイン力
部下の成長には、適切な業務・仕事の割り振り、つまりタスクアサインが重要な役割を果たします。なぜなら、仕事を通じて人は成長するからです。
効果的なタスクアサインのポイント:
|
このような適切なタスクアサインにより、部下の能力向上と組織全体の成長を実現できます。
フィードバック力
継続的で建設的なフィードバックは、部下育成において最も重要なスキルの1つです。ポジティブフィードバックにより部下の良い行動を強化し、改善が必要な点については具体的で実行可能な提案を行います。フィードバックのタイミングも重要で、Here&Now(今、ここで)で適切な内容を伝えることが効果を最大化します。
フィードバックは部下の人格ではなく、具体的な行動や成果に焦点を当てることが大切です。また、一方的に評価を下すのではなく、部下の自己評価を聞き、対話を通じて改善策を共に考える姿勢が求められます。
▼フィードバックのやり方については下記で詳しく解説しています。
⇒効果的なフィードバックのやり方とは?心構えと具体的な手法を解説!
部下育成を成功させるマネジメント5ステップ

効果的な部下育成を実現するためには、体系的なアプローチが重要です。以下の5つのステップを順序立てて実践することで、持続的な成長を促進できます。
ステップ1:部下の現状把握と目標設定
部下育成の第一歩は、現在の状況を正確に把握することです。定期的な面談を通じて、部下のスキルレベル、キャリア志向、課題などを詳細に確認します。この際、部下の自己評価と上司の客観的評価を突き合わせることで、より正確な現状認識が可能になります。意外と部下が等身大の自分をつかむことは難しいです。
現状把握ができたら、部下と協力して具体的な目標を設定します。目標は測定可能で期限が明確であることが重要です。また、組織の目標と個人の目標を整合させ、部下が組織貢献を実感できるような設定を心がけます。目標設定の過程で部下の意見を積極的に取り入れることで、コミットメントを高めることができます。
ステップ2:信頼関係の構築と心理的安全性の確保
効果的な部下育成には、上司・部下の間の信頼関係が不可欠です。心理的安全性が確保された環境では、部下は失敗を恐れずに新しいことにチャレンジできます。信頼関係を築くためには、約束を守る、部下の話を真摯に聞く、状況に合わせて感謝や謝罪を適切に表現するといった当たり前の行動が重要です。
また、部下の価値観や考え方を尊重し、多様性を受け入れる姿勢を示すことも大切です。上司が自分の価値観を押し付けるのではなく、部下の個性を理解し、それぞれに適したアプローチを取ることで、より深い信頼関係を構築できます。定期的なコミュニケーションを通して部下が安心して相談できる環境を整えましょう。
ステップ3:挑戦的な仕事の機会を提供(タスクアサイン)
部下の成長を促進するためには、現在のスキルレベルより少し高い挑戦的な仕事をアサインすることが重要です。簡単すぎる仕事では成長につながらず、難しすぎる仕事では挫折の原因となってしまいます。部下の能力を正確に評価し、適度な挑戦を含む業務を割り振ることで、成長機会を創出します。
権限委譲も重要な要素です。最初は詳細な指導や指示とサポートを提供しながら、徐々に部下の裁量権を拡大していきます。この段階的なアプローチにより、部下は自信を持って責任を引き受けられるようになります。また、失敗を許容し、学習機会として捉える文化を醸成することも大切です。
ステップ4:継続的なフィードバック
建設的なフィードバックは、部下の成長を加速させる重要な要素です。成果や行動に対して、タイムリーで具体的なフィードバックを提供することで、部下は自分の強みと改善点を明確に理解できます。ポジティブフィードバックにより良い行動を強化し、改善が必要な点については具体的で実行可能な提案を行います。
フィードバックは部下の人格ではなく、具体的な行動や成果に焦点を当てることが重要です。また、一方的に評価を伝えるのではなく、部下の自己評価を聞き、対話を通じて改善策を共に考える姿勢が求められます。1on1ミーティングなどの定期的な場を設け、継続的なコミュニケーションを維持しましょう。
ステップ5:パーソナライズした学習環境の提供
部下一人一人の学習スタイルや成長に合わせた学習環境を提供することで、学習効果を最大化できます。OJTによる実践的な学習、Off-JTによる体系的な知識習得、eラーニングによる自己学習環境など、多様な学習機会を組み合わせて活用します。
部下の興味関心や将来のキャリア目標を考慮し、個別の学習計画を策定することも重要です。研修参加の機会提供、資格取得支援、他部署との連携プロジェクトへの参加など、部下の成長意欲を刺激する多様な機会を用意します。学習の進捗を定期的に確認し、必要に応じて計画を調整することで、持続的な成長を支援できます。
組織の部下育成力を高める2つのアプローチ

効果的な部下育成を組織全体で実現するためには、個人の努力だけでなく、組織的なアプローチが必要です。組織レベルでの育成力向上には、主に2つの戦略的アプローチがあります。
管理職に対して研修を行い、組織開発力を高める
管理職に対する研修は、組織開発力を高めるために重要です。ここで言う組織開発とは、アンケートやインタビューを活用して課題を見える化し、その課題について職場メンバーで対話を重ねながら、自分たちで解決していくプロセスを指します。このようなアプローチを管理職が主導できるようになることで、組織のパフォーマンス向上が期待できます。
研修においては、管理職がリーダーシップスキルやコミュニケーションスキルを磨くことが求められます。これによって、管理職はチームメンバーと効果的に対話を行い、課題を迅速に発見し、解決策を共に考えるリーダーシップを発揮することができます。そして、対話プロセスを通じて、管理職は現場の視点を持ちながら、組織の戦略を実行する橋渡し役としての役割を果たします。
職場メンバーと共に課題解決のプロセスを進めることで、組織内のコミュニケーションが活性化し、メンバーの参画意識(エンゲージメント)が向上します。このような取り組みが、組織の競争力を高め、持続可能な成長へとつながっていくのです。
デジタル学習環境を構築する
第二のアプローチは、テクノロジーを活用した、効率的な学習環境の構築です。
デジタル学習環境の構築要素:
|
さらに、学習履歴の分析により、効果的な育成パターンを特定し、継続的な改善を図ることが可能になります。
主体的な部下を育成するマネジメント実践法(組織開発アプローチ)

組織開発の視点から部下育成に取り組むことで、指示待ちの部下を主体的に動ける人材へと変革できます。このアプローチでは、現場の実態を深く理解し、対話を通じて解決策を導き出すことを重視します。
現場のインタビューや観察を通じて現状の課題をつかむ
効果的な育成を行うためには、まず現場で実際に何が起こっているかを正確につかむことが重要です。部下との個別面談だけでなく、実際の業務場面を観察し、チーム全体の動きを理解します。この過程では、表面的な問題だけでなく、根本的な課題やボトルネックを特定することが目的です。
インタビューでは、部下が感じている困りごとや不安、やりがいを感じる瞬間などを詳しく聞き取ります。また、他部署との連携状況や業務フローの問題点なども含めて、包括的な現状分析を行います。このような丁寧な現状把握により、部下のモチベーション低下や主体性不足の真の原因を明らかにできます。
課題を基に対話の時間を持つ
現状把握で明らかになった課題を基に、部下との建設的な対話の機会を設けます。この対話では、上司が一方的に解決策を提示するのではなく、部下自身に問題の本質を考えさせ、解決の方向性を見つけてもらうことが重要です。
対話を通じて、部下が自分の状況を客観視し、改善の必要性を自ら認識できるよう促します。「なぜこの問題が起こっていると思う?」「どうすれば改善できると思う?」といった問いかけにより、部下の思考を深め、当事者意識を高めることができます。この過程で、上司は聞き手に徹し、部下の考えを引き出すことに集中します。
対話を通じて解決策を自ら検討し行動へ移す
対話で課題が整理されたら、部下が主体的に解決策を検討し、実行に移せるよう支援します。上司は答えを教えるのではなく、部下が自分で考え抜いて見つけた解決策を尊重し、実行を後押しします。部下が自ら導き出した解決策は、コミットメントが高く、継続的な取り組みが期待できます。
実行段階では、定期的な進捗確認とフィードバックを行い、必要に応じて軌道修正をします。失敗を恐れずにチャレンジできる環境を整え、試行錯誤を通じた学習を促進することで、部下の問題解決能力と主体性を同時に育成できます。
部下育成の効果を高める組織的マネジメント(デジタル学習環境の構築)

デジタル技術を活用した学習環境の構築により、部下育成の効率性と効果性を大幅に向上させることができます。従来の対面指導だけでは限界のあった課題を、テクノロジーの力で解決する組織的アプローチです。
デジタル学習環境の構築
効果的なデジタル学習環境の構築には、LMS(学習管理システム)の導入が基盤となります。LMSにより、学習コンテンツの配信、進捗管理、評価システムを統合的に運用できます。また、マイクロラーニングの手法を取り入れることで、短時間で集中的な学習を可能にし、忙しい業務の合間でも継続的なスキルアップを実現できます。
インタラクティブなコンテンツの活用も重要な要素です。動画教材、シミュレーション、クイズ形式の理解度確認などを組み合わせることで、受動的な学習から能動的な学習への転換を図れます。さらに、モバイルデバイス対応により、場所を選ばない学習環境を提供し、部下の学習意欲を継続的に維持できます。
OJTのデジタル化を進める
従来の対面によるOJTで教えていたことをデジタルコンテンツ化することで、指導の質と効率を向上させることができます。業務手順を動画で記録し、いつでも参照可能な教材として活用することで、一度の説明で終わることなく、繰り返し学習が可能になります。また、人によって教える内容が違うなどのばらつき問題を解消することにもつながります。
LMS上で進捗管理することで、OJTの進捗を可視化し、指導者と学習者の双方が活動状況を確認できます。また、オンライン会議ツールを使った遠隔指導により、物理的な制約を超えた柔軟な指導体制を構築できます。これにより、経験豊富な指導者のノウハウを組織全体で効率的に活用することが可能になります。
OJTとOff-JTを効果的に組み合わせる
OJTとOff-JTを効果的に組み合わせる際、デジタル学習環境を活用することが重要です。OJTでは日常の業務を通して実践的なスキルを習得しますが、OJTをデジタル化することで必要な時に必要な知識やスキルが学べるとともに、リアルタイムでのフィードバックを得ることができます。
一方、Off-JTでは対面でのやり取りを重視し、深い理解やコミュニケーションスキルの向上を図ります。ここでのディスカッションやワークショップの内容はデジタルプラットフォームに記録し、参加者がいつでも振り返ることができるようにすることで、学びの定着が促進されます。
このように、OJTで培ったスキルをOff-JTで理論的に補完し、デジタル環境で再確認することで、学習プロセスが効率化され、業務の生産性向上につながります。デジタルと対面の手法を組み合わせた学習方法は、現代のビジネスの多様なニーズに適応する柔軟性をもたらします。
学習行動のデータを活用する
デジタル学習環境の最大のメリットは、学習行動のデータ取得と活用です。個々の部下の学習ペース、理解度、つまずきポイントなどを客観的なデータとして把握し、個別最適化された育成計画を立案できます。学習データの分析により、効果的な学習パターンや改善すべき教材を特定し、継続的な質の向上を図れます。
また、組織全体の学習状況を可視化することで、育成施策の効果測定や改善方針の決定に活用できます。データに基づいた科学的なアプローチにより、感覚的な育成から脱却し、より確実な成果を生み出す育成システムを構築することが可能になります。
部下育成をうまく展開している支援事例紹介
ここでは部下育成をうまく展開している支援事例を紹介します。
社内トレーナーで機動力高く研修を実施し効果をあげている事例

背景・課題:
リコージャパン株式会社では、2010年の販売会社統合以降、各支社の固有の課題に対応できず、教育施策が本部主導で一方的になるなどの課題がありました。
また、コロナ禍以降、会食などの機会が減ったことにより、コミュニケーションの希薄化を招いていました。これらの課題を解決するために、社員自らが強みや弱みを理解し合い、横のつながりを強化する取り組みが求められていました。
LIFOプログラム(社内トレーナーライセンス)の導入:
その中で、LIFO(Life Orientations)を導入しました。LIFOの活用を通じて、社員一人一人の個性を診断し、自己理解と他者理解を促進しました。
これにより、非公式なコミュニケーションが減少する中でも、社員同士の相互理解を深めるための新たな手段を提供することができるようになりました。
また、LIFOプログラムライセンスを取得することで、社内トレーナーが自主的に研修を行えるようになり、組織風土改革を進めました。
LDcubeとの協力により、多様なワークショップを展開し、各支社・部門が抱える具体的な課題に対応できるようになりました。
社内展開:
プログラムの展開においては、事前のLIFO診断、ワークショップの実施、職場での実践、効果検証のサイクルを組み込みました。
参加者は、研修後の職場実践を通じて得られたスキルを評価し合い、PDCAサイクルを回すことで、持続的なスキルアップを図っています。
ラーニングプラットフォーム「UMU」を活用し、受講者同士が学び合う環境も整備しました。
社内トレーナーによる研修実施後の反応:
導入後、プログラム受講者の満足度は高く、多くの支社で「対人関係」や「マネジメント能力」などにおいて数値的な改善が見られました。
LIFOを活用したレクチャーは「人」の問題の解決に寄与し、特にアウトプット重視の体験学習が効果的でした。
UMUの活用と一連の学習サイクルの設計により、事務局の負担軽減と学習効果の向上が実現しました。
今後に向けて:
今後は、各支社や部門の課題に寄り添い、人材育成を継続的にサポートすることで、社員個々の自己成長と組織全体の活性化をさらに推進する予定です。
また、LIFO以外のライセンスプログラムも組み合わせ、人材育成のプログラムラインナップを増やしていきます。
これにより、組織内のさまざまな課題を解決し、全体の一体感を更に高められることを期待しています。
▼本事例はインタビュー記事の一部です。インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。
⇒リコージャパン株式会社様 ライセンスプログラム導入事例
パーソナライズ学習でeラーニング受講率100%を達成した事例
支援事例:専門商社(400名)
【これまでの課題】
|
⇒【CK-Connectによるパーソナライズ学習を導入】
【受講率100%を実現】
|
今回のポイント
|
お客さまの声
デジタルとリアルを融合させた部下育成を行っている支援事例
不動産営業の効果的なロープレ事例
デジタルOJTとリアルOJTの連動で業績向上へ【UMU導入事例】
社員数:3000名以上 事業:住宅メーカー
導入前の課題~環境変化に対応した教育を提供したい~
働き方改革など、時代や環境の変化に伴い、従来通りの詰め込み型教育では新入社員がなかなか育たないという課題を抱えていました。
この課題を解決するため、2018年に新入社員の教育方針を「全社の人材育成システムを確立し、共通認識の下、営業人材を長期的視点で組織的・計画的に育成する」というものに変更しました。
3年で一人前とする本計画の元、「研修は事前学習→集合研修→職場実践サイクルによる、OJTとの連動形式を取る」「計画的なロールプレーイングの実施で営業のスキル向上を図る」「個々の学習の進捗状況と習得度の把握」をしながら持続的学習を促進していくために、マイクロラーニングによるインプットとAIによるロープレ(ラーニングプラットフォーム:UMU(ユーム)の活用)の導入を決定しました。
取り組みの詳細
① マイクロラーニングによるインプットで本部・現場の負担減へ
現場のハイパフォーマー社員に依頼し、1人当たり2テーマの模範ロープレ動画を提供してもらい、その動画をプラットフォーム上に掲載しました。
動画学習+AIロープレ導入前は現場でのOJTの質にばらつきがあるという課題もありましたが、動画学習の導入を機に、学習の質を均一化することができ、今では入社1年目~3年目の必須コンテンツとなっています。
② 研修後の確認テストで学びの定着を図る
研修の最後にまとめとして、受講生にはプラットフォーム上で確認テストに回答してもらうことで、研修の理解度を測るとともに、学習内容の定着化を図る取り組みをしました。
講師はリアルタイムで受講生たちの理解が浅いポイントが分かり、その場で解説や補足説明を行うことで、効率的な学習を実現できました。
③ 48のテーマに細分化したロープレの提供で営業スキル向上へ
一人前になるまでに必要な知識を48テーマに細分化し、それをロープレの課題として受講生に提示、順次プラットフォーム上に動画をアップロードしてもらうことで、営業スキルの向上を図っています。
1週間に1本ずつ、模範ロープレ動画を視聴した上で、自身のロープレ動画を提出してもらいます。上司から70点以上の評価を受けることができればテーマクリアという運用を実施することで、デジタルで体系的な学習をしながら、リアルでOJTを促進するという連動を図っています。
導入後の成果
① 一人前として必要な知識を漏れなく学習
プラットフォーム導入前は、3年間営業活動をしていても、人によっては現場で遭遇しないテーマもありましたが、48テーマを計画的に展開していくことで、体系的に、漏れのない学習の提供が可能となりました。
② 学習と上司からのフィードバック率と業績の相関が分かった
受講生が動画を提出すると、AIからのフィードバックを受けられるため、1人でも自分のロープレにおける啓発ポイントを確認しながら、何度もロープレの練習をすることが可能です。また、トークの中身についても上司からのフィードバックを受けることで、トークのブラッシュアップを図ることができます。
実際に受講生の学習や上司のフィードバック率のランキングデータを確認すると、上位者には好業績者の顔ぶれが並んでおり、学習と上司からのフィードバック率と業績が相関していることが分かりました。
これまで現場でのOJT実施状況は不透明でした。しかし、学習状況やフィードバック率がデータとして可視化することで、実施状況を把握しながら上司の関わりを促進し、全体の学習・育成を促進することができました。
まとめ:マネジメントにおいて部下育成は最重要
マネジメントにおける部下育成の重要性とは?人材育成のポイントを解説!について紹介してきました。
部下育成は、マネジメントにおける最も重要な責務であり、組織の将来を決定づける戦略的投資です。効果的な育成を実現するためには、コミュニケーション能力、目標設定力、タスクアサイン力、フィードバック力の4つのスキルを習得し、体系的な5つのステップを実践することが重要です。
個人レベルでの取り組みに加えて、組織全体で育成力を高める仕組みづくりも欠かせません。管理職研修による組織開発と、デジタル学習環境の構築という2つのアプローチを組み合わせることで、持続的で効果的な部下育成システムを構築できます。
部下育成に投資した時間と努力は、必ず組織の競争力向上という形で還元されます。今日から実践できることから始めて、部下の成長と組織の発展を同時に実現していきましょう。
株式会社LDcubeはCrossKnowledge社のパートナーであり、世界中で高い評価を得ているマネジメントスキルを学ぶための学習コンテンツを提供ししています。また、CrossKnowledgeの提供するCK-Connectを活用することで、パーソナライズ学習を実現することも可能です。パーソナライズ学習は、未来の学習のあり方を変える可能性を秘めています。
無料のセミナーやデモ体験会なども行っていますので、お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。