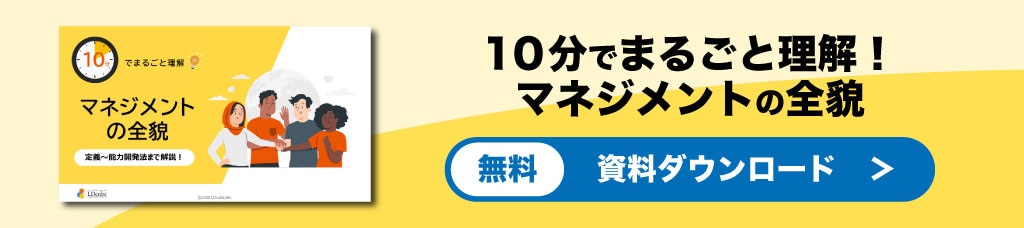組織マネジメント成功事例5選|停滞期・急成長期などの場面別に解説
「最近、会社のマネジメントがうまくいっていない…」
「より生産性が高く、社員が働きやすい組織を作るために、どのようなマネジメントをすればいい?」
より良い組織づくりを目指している役職者もしくは代表であるあなたは、上記のような悩みを抱えており、解決策を見つけるために組織マネジメントの事例を調べているのではないでしょうか。
そこでこの記事では、組織マネジメントに成功した企業の事例5つを、「直面した危機・行った対策・得られた結果」の3つの流れでご紹介します。
組織マネジメントに成功した企業5選 | ||
2010年の経営破綻からたった2年で史上最高の営業利益を更新!JALフィロソフィによる完全復活 | ||
どの宿泊施設でも社員一人ひとりが最良の結果を目指す!自律的な組織で企業が成長 | ||
2016年の組織崩壊から4年で上場!失ったカルチャーを取り戻しリーディングカンパニーへ | ||
数十億円の不良在庫を解消!50人→300人への急成長フェーズの失敗から大躍進 | ||
30人規模の崩壊から熱量の高い160人の組織に!採用への注力と方向性の明確化で成長 | ||
それぞれの組織の停滞期や急成長フェーズなど、さまざまなパターンで発生した事例を集めました。
重要なのは、組織マネジメントに成功している企業の事例を複数確認したうえで、共通点を見出して自社のマネジメントに生かすことです。
そこで本記事では、事例の紹介に加えて、成功事例に共通する組織マネジメントを成功させる秘訣についても、詳しく解説します。
本記事を読めば、自社の組織マネジメントを成功させる方法がわかり、より生産性が高く社員が働きやすい会社づくりを目指せるでしょう。
ぜひ、最後までお読みください。
▼組織や人材、マネジメントについてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。
▼マネジメントについては下記資料にまとめています。無料でダウンロードできます。
▼組織や人材、マネジメントについてのお問い合わせはこちらから。
目次[非表示]
「JALフィロソフィ」を社員に浸透させ企業再生|日本航空株式会社

1つ目の事例は、大手航空会社である日本航空株式会社です。
2024年3月末時点で従業員数が13,000名を超える大企業ですが、かつて経営破綻という大きな危機に直面し、組織マネジメントの見直しを迫られました。
課題 | 事業会社として戦後最大の負債を抱え、2010年に経営破綻 |
対策 | JALフィロソフィを浸透させる取り組み |
結果 | 2012年に史上最高の営業利益を出し再上場 |
直面した危機:事業会社で戦後最大の負債を抱えて経営破綻
日本航空は、2010年1月に会社更生法の適用を申請し、経営破綻しました。
直接的な原因は2008年のリーマンショックでしたが、採算性の甘さや国際競争への消極的な姿勢など、脆弱な企業体質が背景にあったと指摘されています。
当時の日本航空は赤字続きで、抱えた負債額は2兆3,000億円。事業会社として、戦後最大の規模でした。
これを受けて同年2月に会長に就任したのが、当時京セラ株式会社の名誉会長だった稲森和夫氏です。
稲森氏は、経営破綻を引き起こすまでに至った日本航空の企業体質を抜本的に見直すために、組織を改革するマネジメントを行いました。
対策:「JALフィロソフィ」を浸透させて社員の意識改革を行う
日本航空が行った組織マネジメント方法として効果的だったのが、「JALフィロソフィ」の制定と全社員への浸透です。
経営破綻前の日本航空では、企業理念や行動指針を策定しても浸透せず、社員の意識がバラバラでした。
そこで、行動指針となる以下のようなフィロソフィを作り、責任感や一体感、採算意識を育もうとしたのです。
JALフィロソフィの一部(抜粋) | |
第1部 すばらしい人生を送るために | 第1章 成功方程式(人生・仕事の方程式) |
第2章 正しい考え方をもつ | |
第3章 熱意をもって地味な努力を続ける | |
第2部 すばらしいJALとなるために | 第1章 一人ひとりがJAL |
第2章 採算意識を高める | |
第3章 心をひとつにする | |
経営破綻から1年後に誕生したJALフィロソフィを全社員に浸透させるために、以下のような施策が行われました。
|
JALフィロソフィをまとめた手帳を多言語化して発行し、全社員にJALフィロソフィを意識してもらうのが始まりでした。
さらに、JALフィロソフィを浸透させるために毎年勉強会を実施。
フィロソフィが必要とされる背景や、職場ごとの実践事例などを紹介して理解を深めました。
当時は懐疑的な社員が多かったものの、継続的なフィロソフィ浸透の取り組みにより、社員の意識も変わっていったのです。
得られた結果:史上最高の営業利益 & 再上場
組織マネジメントの取り組みとして、JALフィロソフィの浸透を継続的に行った日本航空は、経営破綻からわずか2年で以下のような結果を得ました。
|
全社員が責任感を持ち、自身の行動が収支に繋がるという意識を持って一丸となって業務に取り組んだ結果、日本航空は生まれ変わりました。
社員が同じ方向を向くことで一体感が生まれ、企業価値が高まったのです。
日本航空の事例から、社員数が多い大企業であっても、全社員が共通の価値観を持てるように意識改革を行うことが大切であるとわかります。
日本航空の事例からわかる組織マネジメント成功のポイント |
◎全社員にフィロソフィを浸透させ、一体感を生み出す |
価値観共有と双方向対話で自律的な組織を実現|株式会社星野リゾート

2つ目の事例は、総合リゾート運営会社である株式会社星野リゾートです。
軽井沢の旅館から、国内外で多様なコンセプトの宿泊施設を運営する有名企業へと成長したのは、エンパワーメントを忠実に実践した成果です。
しかし、実はチームの「現場力」に課題を感じた過去もあります。
課題 | 現場力の低いチームの運営 |
対策 | 価値観の共有と相互コミュニケーションの徹底 |
結果 | 社員が自ら動く自律的な組織の実現 |
直面した危機:自ら行動できない現場力の低いチームの運営
星野リゾートは国内外で宿泊施設を運営しているからこそ、各所で組織づくりの課題に直面することがあります。
バリの宿泊施設では、現地の社員が「自らアイデアを出したり行動したりせず、言われたことをやる」形で仕事をしていたために、組織づくりに苦戦しました。
ホテルでは、現場で働く社員の行動がお客様の満足度に直結します。
自らアイデアを出して行動する現場力がなければ、お客さまの満足度向上に繋がりません。
そこで、星野リゾートでは現場力を高めるための組織マネジメントを行いました。
行った対策:価値観の共有とフラットな組織づくり
星野リゾートは、現場力を高めるために以下の対策を行いました。
|
「世界で通用するホテル運営会社になる」というビジョンを目指すために、価値観を明文化して全社員に共有しました。
意識すべき価値観が明確になれば、社員もそれに従って行動できるようになります。
社員が常に価値観と照らし合わせて提案や行動をすることで、現場力を高めていきました。
また、全社員が率直に意見を言い合いながら最適なアクションを考えられるように、フラットな組織づくりを徹底しました。
- 対等に議論できるよう全社員に経営情報を公開する
- 役職で呼び合うことを禁止する
- 総支配人の個室のような「偉い人信号」をなくす
現社長の星野佳路氏が軽井沢の旅館を受け継いだ当初から行ってきた上記のような方法で、どの宿泊施設でもフラットな組織づくりを進めました。
上司と部下の双方向コミュニケーションが活性化されていれば、情報共有がスムーズにでき、生産性が高まります。
経営層の判断を待つのではなく、現場でお客さまに接している社員が自ら考えて行動できれば、お客さまの満足度向上に繋げることが可能です。
得られた結果:一人ひとりが最良の結果を目指す自律的な組織の実現
現場力を高める組織マネジメントを行ったことで、星野リゾートは以下のような結果を得ました。
|
全社員が同じ価値観で働いているため、どの宿泊施設でも社員が最良の結果を目指して行動しています。
星野リゾートの事例から、ビジョンや価値観を共有して双方向コミュニケーションを活性化させることで、社員が自ら動けるようにマネジメントすることが大切だとわかります。
株式会社星野リゾートの事例からわかる組織マネジメント成功のポイント |
◎ビジョンや価値観を共有し、意見を言い合える組織づくりを行う |
心理的安全性の確保とバリュー再構築で逆転|株式会社グッドパッチ

3つ目の事例は、デザインのリーディングカンパニーである株式会社グッドパッチです。
2011年9月に土屋尚史氏が創業した当初は、企業文化の重要性を理解したうえで運営されていました。
しかし、2016年に社員数が急増したフェーズで組織の成長とマネジメント方法が噛み合わなくなった結果、組織崩壊が発生しました。
課題 | 組織の急成長フェーズで組織崩壊 |
対策 | 心理的安全性を確保しバリューを浸透させる取り組み |
結果 | エンゲージメントスコアの改善と上場 |
直面した危機:組織崩壊により年間離職率が40%を超える
グッドパッチの組織崩壊は、2016年から2017年にかけて起こりました。
まず、社員数が60人から100人へと急激に増えたフェーズで、適切なマネジメントを行える人材が存在しなかったために、社員の成長を促進できませんでした。
その結果、古参メンバーと新メンバーの間で意思疎通ができずに対立し、幹部も含めた人材が大量に離職。年間離職率は、40%を超えてしまいます。
さらに、モチベーションクラウドにて社員が会社に共感する度合いであるエンゲージメントを調査した結果、ランクは最高評価であるAAAより6段階も下のCCCとなりました。
会社の在り方や経営方針に不満を抱えたメンバーが増え、全社員が使うコミュニケーションツールに怪文書が投稿されるなど、治安の悪い組織になってしまったのです。
土屋氏は、失われた企業文化を再び取り戻すために、改めて組織マネジメントに注力しました。
行った対策:心理的安全性の確保とバリューの再構築
グッドパッチが行った組織マネジメント方法として、以下が挙げられます。
|
そもそも組織が成長するスピードに合わせてマネジメントできる人材が揃っておらず、幹部メンバーも大量離職したことから、経営層を補強するための人材採用に力を入れました。
そのうえで、ユニットごとに心理的安全性を確保する取り組みを実施しました。
創業当初はオープンなチャンネルに誰かが情報を投稿すると、コメントが盛り上がる文化があったグッドパッチ。
しかし、組織崩壊時には全体チャットに投稿すると厳しい発言ばかり飛んでくるという、心理的安全性が確保されていない環境になっていました。
そこで土屋氏は、マネジャー達に自分のユニットの心理的安全性を確保しようと呼びかけます。
オンラインとオフラインの相互コミュニケーションを増やしながら、安心して発言できる環境づくりを進めました。
また、組織崩壊時に浸透に失敗したバリューの再構築も、グッドパッチが行った組織マネジメント方法のひとつです。
力強いコンセプトを達成するためには、バリューという土台が重要だと判断し、有志のメンバーと再構築を進めました。
|
まず、会社の価値観を洗い出すワークショップを、東京オフィスとベルリンオフィスを含めた全社員で行いました。
その後、バリューを浸透させるためにマネジャー層と浸透施策を考えて実行。
バリューを表すポスターやトロフィー、ステッカーなどがデザインされ、新卒社員も含めて全社員を巻き込んだ施策が行われたのです。
▼心理的安全性については下記で詳しく解説しています。
⇒「心理的安全性」その本質・作り方とは?今すぐ取り組みたい20の具体策を解説!
得られた結果:上場しエンゲージメントスコアが最高ランクに
全社員を巻き込んだ組織マネジメント施策により、一度失ったカルチャーを少しずつ取り戻していったグッドパッチは、以下のような結果を得ました。
|
組織崩壊というどん底を経験したところから、企業文化を改めて醸成する取り組みを進め、今やグッドパッチはデザインのリーディングカンパニーとなりました。
グッドパッチの事例から、急成長フェーズで社員数が一気に増えても、全社員が共通の目標に向かって支え合えるようにマネジメントする必要があるとわかります。
株式会社グッドパッチの事例からわかる組織マネジメント成功のポイント |
◎全社員にバリューを浸透させ、言いたいことが言い合える環境を確保する |
理念経営と戦略策定からの目標設定でヒット商品誕生|株式会社I-ne

4つ目の事例は、ヘアケア・ボディケアブランド「BOTANIST」などのヒット商品を多数手がけるビューティーテックカンパニーである株式会社I-neです。
50人規模から300人規模に組織が急成長した際に、適切な組織マネジメントを行えなかった結果、膨大な不良在庫の発生や社員の大量離職などの問題が起こりました。
課題 | 大量採用による共通認識の欠落で膨大な不良在庫発生 |
対策 | 理念を浸透させる経営と戦略策定の強化 |
結果 | 多数のヒット商品の誕生と上場 |
直面した危機:商品がヒットせず膨大な不良在庫発生 & 社員の離職
2007年に大西洋平氏が創業し、2015年にBOTANISTがヒットした頃のI-neは小規模な組織で、組織の統制も取れていました。
しかし、BOTANISTのヒットで売上が急成長した結果、各所で人員不足が深刻化します。
採用を加速させるため、フィロソフィにマッチするかどうかよりもスキルで採用を行い、3年間で社員数は50人から300人に急拡大しました。
経営メンバーの目が全体に届かなくなり、ヒット商品を生み出すための共通認識が失われる事態に陥ったのです。
その結果、2017年からの2年間では新規リリースした商品がヒットせず、数十億円の不良在庫を抱えました。
また、理念に共感しないメンバーが増えたことで、日々の業務やコミュニケーションにも違和感が発生してしまいます。
2015年から2017年に採用した約200人のうち80人が2020年末に退職し、残った社員も大半が不満を抱えている状態でした。
組織崩壊ともいえる現状を目の当たりにした大西氏は、組織マネジメントの改革に踏み切ります。
行った対策:理念経営の実施と戦略策定の強化
I-neが組織マネジメントを変革する際にまず行ったのが、社長と創業メンバーの改革会議です。
組織崩壊しかけていた当時は、社長を含む役員全員に大規模組織の経営知見が不足していました。
そのため、改革会議でこれまでの組織マネジメントを反省したうえで、知識のインプットや外部人材の採用、顧問の活用をしながら300人規模の組織を動かす仕組みを整えました。
そして組織変革のために行ったのが、以下の取り組みです。
|
創業当時のI-neは、ベンチャー気質なメンバーで構成されていたため、理念を浸透させる取り組みをしなくても全社員が同じ方向を向いていました。
しかし、大量採用を行った結果理念の解釈が異なるメンバーが増え、社内コミュニケーションに齟齬が発生する事態になっていたのです。
そこで、理念マッチを重視した採用を行う、全社総会でフィロソフィを伝える時間を設けるなどの方法で理念経営を進めました。
また、組織崩壊時のI-neでは、戦略が詰めきれておらず無駄や失敗を多く発生させていました。
そこで、ミッションから逆算した目標を掲げ、ゴールするための戦略を策定しました。
経営計画を考え抜き、全社員の行動目標に落とし込むことで、全員が同じ方向を向いて業務に取り組めるようにしたのです。
得られた結果:ヒットブランドが多数誕生しプライム市場への上場変更
組織マネジメントの改革を行った結果、I-neは以下のような結果を得ました。
|
I-neの事例から、組織が急成長する段階で全社員にフィロソフィを浸透させ、全員が同じ大目標に向かって行動できる仕組みづくりが重要とわかります。
株式会社I-neの事例からわかる組織マネジメント成功のポイント |
◎全社員にフィロソフィを伝え、同じ場所に向かえる仕組みをつくる |
バリューの浸透と明確な目標設定で強い組織を実現|株式会社ダイニー

5つ目の事例は、飲食のインフラになることを目指し、POSレジやモバイルオーダーのシステムを提供している株式会社ダイニーです。
社長が採用よりもプロダクト開発に注力した結果、徐々に組織の雰囲気が悪くなり、組織崩壊が起こりました。
課題 | 組織の拡大に伴いカルチャーに合わない人材が増加 |
対策 | バリューの浸透と長期的 & 短期的な目標の設定 |
結果 | 熱量が高い社員が働く強い組織を実現 |
直面した危機:組織拡大でカルチャーに合わない人材が増え組織崩壊
2018年に山田真央氏が創業したダイニーは、2021年に大きな危機を迎えます。
30〜40人規模の組織が、社長が気づいたときには組織崩壊していました。
社員のやる気がなく、トラブルが頻発し、誰かが会議で意見を出すと水を差すメンバーが発生。
数ヶ月前まで活気があったにもかかわらず組織が崩壊した原因は、社長が採用に関わらなくなったことでした。
当時の山田氏は、採用を人事の仕事と捉えて自身は関わらなくなり、プロダクト開発に注力していました。
その結果、組織の拡大に伴ってダイニーのカルチャーに合わない人が増えてしまったのです。
組織が険悪なムードになっていることに気づいた山田氏は、組織マネジメントについて改めて考え直しました。
行った対策:バリューの浸透と長期的および短期的な目標の決定
ダイニーの組織マネジメントとして行われたのは、主に以下の施策です。
|
入口となる採用の段階でカルチャーにフィットする人材を迎えるため、社長が採用プロセスに関わるようになりました。
組織に合う人材を迎えたあとは、会社の空気を変えるためにバリューの浸透に着手します。
創業時から存在していたバリューは抽象度が高く、日々の業務に落としこむのが難しかったため、バリューに紐づいた強いメッセージをオフィスの壁に貼り出しました。
そして、ロードマップの作成により、全社員が向かうべき方向を明確にしました。
10年と1年のマップは社長が作成し、四半期からは現場の社員が中心となって作ることで、将来的な方向性と今やるべきことがわかります。
方針を明確にすることで、全社員が同じ目線で仕事に取り組めるようにしたのです。
得られた結果:熱量の高いメンバーで構成される強い組織に
組織崩壊から4年後の2025年、ダイニーは生まれ変わりました。
|
2024年9月にはシリーズBラウンドで総額74.6億円の資金調達を実施し、さらなる新規事業の展開や事業拡大を目指しています。
ダイニーの事例から、全社員にバリューを浸透させて組織をまとめることや、未来の方向性を示して日々のやるべき業務を明確にすることが、組織マネジメントにおいて重要とわかります。
株式会社ダイニーの事例からわかる組織マネジメント成功のポイント |
◎カルチャーにフィットする人材を採用したうえで、向くべき方向を明確にする |
事例から紐解く組織マネジメントを成功させる3つの秘訣

ここまでで、組織マネジメントの成功事例を知ることができたあなたは、早速自社のために行動を起こそうとしているかもしれません。
そこで大切なのは、それぞれの事例に共通する成功の秘訣を知り、自社の対策に落とし込むことです。
5つの成功事例からわかる、組織マネジメントを成功させるための3つの秘訣は、以下の通りです。
|
自社の組織マネジメントを成功させるために、詳細を確認しましょう。
ビジョンやミッションを明確に設定し全社員に浸透させる
組織マネジメントの成功事例では、ビジョンやミッションを明確に設定したうえで、全社員に浸透させる取り組みを行う企業がいくつもありました。
マネジメントに失敗した企業は、ビジョンやミッションを定めていたものの社員に浸透しておらず、飾りになっているケースが多いです。
ビジョンやミッション、バリュー、フィロソフィなどには、企業の存在意義や目指す姿、行動指針、価値観などが表れます。
企業としてどうありたいか、どうなっていきたいかを明文化することで、全社員が目指すものが明確になります。
数ヶ月かけてもいいので、改めて会社全体を見直して言語化しましょう。
経営層のみ、または経営層に人事担当者数名を加えたチームを組んで決めることで、議論をまとめながらその後の浸透フェーズを速やかに進められます。
ビジョンやミッションを設定するだけは終わらず、全社員に浸透させる取り組みを行えば、組織が一体となって協力する文化が醸成されるでしょう。
戦略を策定し長期的な目標を共有する
組織マネジメントに成功した企業の事例を見ると、戦略を策定したうえで、全社員と長期的な目標を共有しているケースが多いとわかります。
戦略を徹底的に考え抜いておらず、創業期の勢いで何となく決めてしまった結果、組織が拡大するフェーズで社員がバラバラになってしまったという失敗は多いです。
企業が抱えているミッションを達成するための戦略を策定することで、進むべき道が明確になります。
例えば以下のように、達成したい目標を時期ごとに洗い出してみてください。
10年後 | 東証スタンダード市場に上場する |
5年後 | 1年間の利益を●億円以上にする |
1年後 | 事業拡大のために●人採用する |
ゴールに到達するための道がわかれば、いつまでに何をすればいいかという長期的な目標が見えてくるでしょう。
長期的な目標を決めることで、逆算して短期的な目標を決められます。
長期的な組織目標を達成するための短期的な個人目標を決めれば、社員は今やるべきことが企業の将来に繋がっていると実感でき、モチベーションを高く持って働けるでしょう。
心理的安全性を確保して双方向コミュニケーションを活性化する
組織マネジメントに成功した企業に共通しているのが、心理的安全性の確保です。
特に、組織崩壊を経験した企業では、社員の心理的安全性が確保されていなかったケースが多く見られます。
自ら意見を出して行動しようとしても、それを毎回否定されれば誰も行動しなくなってしまうでしょう。
組織マネジメントでは、率直に意見を出して行動しても、否定されることがなく安全であると全社員が思える環境づくりが必要です。
心理的安全性が確保された環境では、経営層からメンバーへの指示だけでなく、メンバーからも経営層に意見が言える双方向コミュニケーションが活性化します。
全社員が何でも言い合える組織をつくることで、信頼関係の構築や認識齟齬の防止に繋がります。
結果的に社員のモチベーションが高まり、組織エンゲージメントの向上にも繋がるでしょう。
▼組織マネジメントで考えるべき心理的安全性については、下記で詳しく解説しています。
本気で組織マネジメントを機能させるなら上層部の自己研鑽が不可欠

組織マネジメントを成功させるためには、全社員の意識改革や環境づくりなどをしなければならないことがお分かりいただけたと思います。
つまり、経営に近い場所にいる上層部が率先して行動を起こさなければ、組織マネジメントは成功しません。
経営陣や管理職の方々は、自己研鑽を積んで自社に適した組織マネジメントを考える必要があります。
上層部の知識やマネジメントスキルを高めるためには継続的な研修が効果的ですが、コストや日程調整の面で外部トレーナーの活用は難しいと考えることもあるでしょう。
そのような場合は、株式会社LDcubeが提供する社内トレーナー養成講座を活用してみてはいかがでしょうか。
上層部が社内トレーナーとなり、組織マネジメントを変革! |
LDcubeの社内トレーナー養成講座は、プロの研修講師が活用しているプログラムを自社の社員が教えられるようになるプログラムです。
ライセンスの取得により、プロクオリティの研修を外部に委託せず自社で展開できるようになります。
社内トレーナー養成講座が終わったあとも、研修プログラムの作成や実施時の疑問点などを専門スタッフに相談できるため、常に内容をブラッシュアップして上層部の組織マネジメント力を高められます。
組織マネジメントに役立つプログラム | |
個人の強みを理解してコントロールすることで、対人関係の円滑化を図る →LIFOを用いたマネジメントスキルを磨くワークショップ「MSS」も! | |
高い生産性で物事に取り組み、他者と協働するための対人関係の柔軟性を身に付ける | |
革新的な行動がとれる人材を育成する | |
逆境を乗り越えて成長する人材を育成する | |
今の組織を本気で変えたい、もっと社員が働きやすい環境をつくりたい。
そのように考えている方は、組織マネジメント力を高めるために社内トレーナーの養成を検討してみてください。
▼社内トレーナーについては下記で詳しく解説しています。
⇒社内トレーナー導入における成功のコツとは?ポイントを解説
まとめ
この記事では、組織マネジメントに成功して危機を乗り越えた企業の事例を紹介してきました。
組織マネジメントに成功した企業5選 | ||
2010年の経営破綻からたった2年で史上最高の営業利益を更新!JALフィロソフィによる完全復活 | ||
どの宿泊施設でも社員一人ひとりが最良の結果を目指す!自律的な組織で企業が成長 | ||
2016年の組織崩壊から4年で上場!失ったカルチャーを取り戻しリーディングカンパニーへ | ||
数十億円の不良在庫を解消!50人→300人への急成長フェーズの失敗から大躍進 | ||
30人規模の崩壊から熱量の高い160人の組織に!採用への注力と方向性の明確化で成長 | ||
事例からわかる組織マネジメント成功の秘訣は、以下の通りです。
|
より生産性が高く、社員が働きやすい職場を作るために、本記事がお役に立てることを願っています。
株式会社LDcubeでは、社内トレーナーを養成する支援を行っています。
上層部が自己研鑽しながら社内研修を実施することで、より良い組織づくりを実践できるでしょう。
プロの研修講師が実際に行っているプログラムを使えるため、質の高い社内研修を行えるようになります。
ご興味がある方は、お気軽にご相談ください。
▼マネジメントの全貌についてまとめた資料は下記からダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。