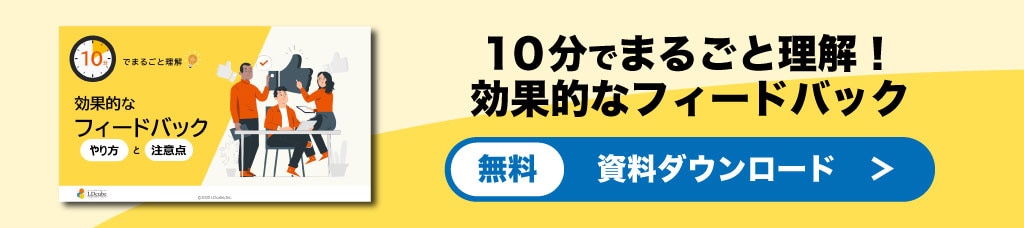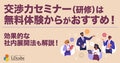効果的なフィードバックのやり方とは?心構えと具体的な手法を解説!
「部下へフィードバックをしているのに、なかなか行動が変わらない」
「どのようなやり方でフィードバックを行えば効果的なのか分からない」
このような悩みを抱えている管理職の方は多いのではないでしょうか。
フィードバックは、部下の成長を促し、活動の軌道修正を促し、組織全体のパフォーマンスや生産性を向上させるための重要なマネジメント手法です。しかし、適切なやり方を知らずに実践すると、逆に部下のモチベーションを下げてしまったり、信頼を損なってしまったりするリスクもあります。
特に近年、働き方の多様化やハラスメント意識の高まりにより、多くの企業で適切なフィードバックや業務指導をためらってしまうことが課題となっています。人と組織の成長においては、フィードバックについて適切に理解し、効果的に実践することが求められています。本記事では、サンドイッチ型やSBI型をはじめとする具体的な手法と、実践する際のポイントや注意点を詳しく解説します。
正しいフィードバックのやり方を身に付けることで、部下の自発的な成長を促し、チーム全体の目標達成につなげていきましょう。
▼関連記事はこちらから。
目次[非表示]
- 1.効果的なフィードバックのやり方
- 1.1.具体的で分かりやすい内容を伝える
- 1.2.適切なタイミングで実施する
- 1.3.建設的な内容にする
- 2.フィードバックはやり方よりもタイミング
- 3.フィードバックのやり方を学ぶ前提
- 3.1.相手の成長を願ってする行為
- 3.2.鏡の役割
- 3.3.相手との信頼関係を構築する
- 4.ビジネスにおけるフィードバックとは何か
- 4.1.ビジネスにおけるフィードバック
- 4.2.フィードバックが注目される理由
- 4.3.フィードバックの目的と効果
- 5.フィードバックの基本的な種類
- 5.1.ポジティブフィードバック
- 5.2.ネガティブフィードバック
- 6.代表的なフィードバックのやり方
- 6.1.サンドイッチ型
- 6.2.SBI型
- 6.3.360度フィードバック
- 7.フィードバックのやり方を組織に定着させる
- 7.1.フィードバックの重要性やり方についての研修を行う
- 7.2.フィードバックを大切にする文化を醸成する
- 7.3.管理者が率先してフィードバックする
- 7.4.1on1ミーティングを活用する
- 7.5.メンバー同士でフィードバックし合う
- 8.フィードバックのやり方注意点
- 8.1.避けるべきフィードバックの方法
- 8.2.ハラスメントにならないための配慮
- 8.3.相手の人格を否定しない伝え方
- 9.フィードバックのやり方の前に自己理解と他者理解
- 10.まとめ:適切なフィードバックのやり方を定着させよう
効果的なフィードバックのやり方

フィードバックを効果的に行うためには、基本的な原則を理解し、適切な手法を身に付けることが重要です。
具体的で分かりやすい内容を伝える
効果的なフィードバックの最も重要な要素は、具体性です。抽象的な表現では、受け手によって解釈が異なってしまい、本来の意図が正確に伝わりません。
例えば、「もっと頑張って」「資料が分かりにくい」といった曖昧な表現ではなく、「顧客への提案書の3ページ目の文章が分かりにくいので、箇条書きで表現し直して」「グラフのフォントサイズを14ポイント以上にして、重要な項目を太字で強調しましょう」など、具体的で実行可能なアドバイスを提供することが大切です。
また、相手の経験レベルや現在のスキルに応じて、実現可能な範囲での改善点を示すことで、フィードバックの効果を最大化できます。
適切なタイミングで実施する
フィードバックの効果は、実施するタイミングによって大きく左右されます。最も効果的なのは、対象となる行動や出来事が発生した直後に行うことです。
時間が経過すると、具体的な状況や当時の心境を忘れてしまうため、フィードバックの内容が相手に響きにくくなります。理想的には、その日のうち、遅くとも翌日までには実施することを心掛けましょう。
定期的な1on1ミーティングも有効ですが、フィードバックについては即座に行うことで、効果を高めることができます。
建設的な内容にする
フィードバックは常に建設的で前向きな内容を心掛けることが重要です。単なる批判や指摘ということではなく、相手の成長と行動改善を目的とした内容にしましょう。
問題点を指摘する場合でも、「なぜそれが問題なのか」「どのように改善できるのか」を明確に示し、解決策を一緒に考える姿勢を持つことが大切です。また、改善点だけでなく、良い点も併せて伝え、相手のモチベーションを保ちながら成長を促すことができます。
フィードバックはやり方よりもタイミング

フィードバックの効果を決定する最も重要な要素は、実施するタイミングです。どれほど優れた手法を用いても、適切なタイミングを逃せば効果は大幅に減少します。
Here & Now(今、ここで)
最も効果的なフィードバックは「Here & Now(今、ここで)」の原則に基づいて行われます。これは、対象となる行動や出来事が発生した現場で、可能な限り即座に実施することを意味します。
その場でフィードバックを行うことで、相手は具体的な状況や自分の行動を鮮明に思い出すことができ、指摘内容を正確に理解できます。また、感情や思考のプロセスも記憶に残っているため、なぜそのような行動を取ったのかを振り返りやすく、より深い学習につながります。
例えば、プレゼンテーション直後に「先ほどの説明で、グラフの部分をもう少しゆっくり話していただけると、より伝わりやすかったですね」と伝えることで、具体的な改善点を即座に認識できます。
There & Thenでは効果が薄い
一方、「There & Then」(あの時、あそこで)のフィードバックは効果が大幅に低下します。時間が経過すると、人は具体的な状況や当時の感情を忘れてしまい、フィードバックの内容を抽象的にしか捉えられません。
例えば、1週間前のプレゼンテーションについて「あの時の説明は速すぎました」と言われても、相手は具体的にどの部分が速かったのか、なぜ速くなったのかを思い出すことが困難です。結果として、同じミスを繰り返すリスクが高まります。
定期的な面談やレビューも重要ですが、日常的な即座のフィードバックと組み合わせることで、より効果的な人材育成が実現できます。
フィードバックのやり方を学ぶ前提

効果的なフィードバックを実践する前に、根本的な考え方や姿勢を理解することが重要です。技術的な手法よりも、まずは基本的な心構えを身に付けましょう。
相手の成長を願ってする行為
フィードバックの最も重要な前提は、相手の成長を心から願う気持ちです。単なる指摘や評価ではなく、相手がより良い方向に向かうことを支援する行為として捉える必要があります。
この姿勢があることで、フィードバックの内容や伝え方が自然と建設的になり、相手も前向きに受け止めやすくなります。「この人は自分の成長を考えてくれている」と感じてもらえれば、厳しい内容であっても素直に受け入れてもらえる可能性が高まります。
また、成長を願う気持ちは、フィードバックする側の表情や声のトーンにも表れるため、言葉以上に相手に伝わる重要な要素です。相手の可能性を信じ、長期的な視点で成長を支援する意識を持ちましょう。
鏡の役割
フィードバックは、相手にとっての「鏡」のような役割を果たします。自分では気付きにくい行動や癖、強みや改善点を客観的に映し出す機能があります。
人は自分の行動を主観的にしか見ることができないため、他者からの客観的な視点は非常に貴重です。ただし、鏡のように正確で偏りのない情報を提供することが重要であり、個人的な感情や偏見を排除した視点が求められます。
相手との信頼関係を構築する
フィードバックの効果は、実施者と受け手の信頼関係によって大きく左右されます。信頼関係が築かれていない状態では、どれほど的確な指摘であっても、相手は防衛的になりがちです。
現代では、信頼関係を構築できていない相手へのフィードバックは時にハラスメントと受け取られることがあるので、注意が必要です。特に言葉遣いや表現に不適切なものが含まれないよう気を配りましょう。
日頃から積極的にコミュニケーションを取り、相手の良い点を認めて伝えることで、信頼関係を築くことができます。また、フィードバックを一方的な評価ではなく、対話の機会として捉え、相手の意見や考えも聞く姿勢を示すことが大切です。
ビジネスにおけるフィードバックとは何か

フィードバックの具体的な手法を学ぶ前に、まずはフィードバックとは何かという基本的な概念を理解することが重要です。
ビジネスにおけるフィードバック
ビジネスにおけるフィードバックとは、相手の行動や結果に対して、口頭や文章を通じて評価や指摘を行う育成手法のことです。一般的には、上司やマネジャーが部下やチームメンバーに対して実施するコミュニケーション手法として位置付けられています。
重要なのは、フィードバックは相手の人格や性格に対する評価ではなく、あくまでも「行動」や「結果」に焦点を当てた客観的な評価であるということです。主観的な判断ではなく、事実に基づいた具体的な情報を伝えることで、相手が自分の現状を正確に把握し、改善や成長につなげることができます。
また、フィードバックは一方向の評価ではなく、双方向のコミュニケーションとして機能することが理想的です。受け手の意見や考えも聞きながら、共に解決策を見つけていく対話的なプロセスとして捉えることが重要です。
フィードバックが注目される理由
現代の環境変化の中、フィードバックが特に注目されている背景には、主に2つの大きな変化があります。
まず、マネジメント対象の多様化が挙げられます。従来の年功序列制度から実力主義への移行、再雇用制度の導入、外国人や障害者の雇用促進などにより、年齢、国籍、経験、価値観などが異なる多様なメンバーをマネジメントする機会が増加しています。このような状況では、画一的な指導方法では効果が期待できないため、個々の特性に応じた適切なフィードバックが求められています。
もう一つは、ハラスメント問題への意識の高まりです。管理職は「指摘が相手を傷つけてしまうのではないか」「どこまでの発言がハラスメントにあたるのか」といった懸念を抱えており、結果的に必要な指導を避けてしまうケースが増えています。しかし、部下の成長には適切な指摘が不可欠であり、正しいフィードバック手法の習得が重要視されています。
フィードバックの目的と効果
フィードバックの目的は、相手の成長を促進することです。客観的な視点から評価を伝えることで、相手は自分の行動や成果を多角的に捉えることができるようになります。
具体的な効果として、以下のような点が期待できます。まず、目標達成に向けた軌道修正が可能になります。間違った方向に努力している場合には適切な方向性を示し、良い取り組みについては継続を促すことで、効率的な成長を支援できます。
また、適切なフィードバックは相手のモチベーション向上にもつながります。自分の努力や成果が正当に評価されていることを実感できれば、仕事への意欲が高まり、さらなるパフォーマンス向上が期待できます。さらに、定期的にフィードバックを行うことは上司と部下の信頼関係を深める効果もあり、チーム全体のコミュニケーション向上にも寄与します。
フィードバックの基本的な種類

フィードバックには大きく分けて2つの基本的な種類があり、それぞれ異なる目的と効果を持っています。効果的なフィードバックを行うためには、状況に合わせて適切に使い分けることが重要です。
ポジティブフィードバック
ポジティブフィードバックは、相手の望ましい行動や成果に対して肯定的な評価を伝える手法です。主な目的は、相手の自己効力感を高め、モチベーションを向上させることにあります。
良い行動を具体的に褒めることで、「何が評価されているのか」を明確に伝え、その行動の継続・強化を促すことができます。また、承認欲求を満たすことで、仕事への意欲や自信の向上にもつながります。特に新入社員や経験の浅いメンバーに対しては、自信を育てる重要な手段となります。
ネガティブフィードバック
ネガティブフィードバックは、改善が求められる行動・結果に対して指摘を行う手法です。適切に実施されれば、相手が自ら問題点に気付き、主体的な改善を促すことができます。
重要なのは、単なる批判ではなく、建設的な改善提案として伝えることです。問題点を指摘する際には、具体的な改善方法も併せて示すことで、相手が前向きに取り組めるように配慮する必要があります。ただし、過度なプレッシャーや否定的な表現は避け、相手の成長を支援する姿勢を保つことが大切です。
代表的なフィードバックのやり方

フィードバックにはさまざまな手法がありますが、ここでは特に効果的で実践しやすい、3つの代表的な手法を詳しく解説します。
サンドイッチ型
サンドイッチ型フィードバックは、「褒める→指摘→褒める」の流れで構成される手法です。最初と最後にポジティブな内容を挟むことで、ネガティブな指摘を相手が受け入れやすくする効果があります。
この手法の最大のメリットは、相手の自尊心を傷つけることなく改善点を伝えられることです。特に新入社員や経験の浅いメンバー、自信を失いがちな状況にある人に対しては有効です。
例えば、「資料作成のスピードが速くて助かります。ただ、誤字脱字が少し目立つので、最後に見直しの時間を設けるとより良くなりますね。内容は分かりやすくまとまっているので、今後も期待しています」といった形で伝えます。
ただし、ポジティブな内容に挟まれることで、肝心の改善点が印象に残りにくくなるリスクもあるため、重要な指摘については別の手法を検討することも必要です。
SBI型
SBI型は、Situation(状況)、Behavior(行動)、Impact(影響)の順序で構成されるフィードバックのやり方です。事実を踏まえた客観的な情報を段階的に伝えることで、相手に納得感を与えることができます。
まず「Situation」で具体的な状況を設定し、次に「Behavior」で観察した行動を客観的に述べ、最後に「Impact」でその行動がもたらした結果や影響を説明します。
例えば、「今朝のチームミーティングで(状況)、あなたが積極的に質問をして議論を活発にしてくれましたね(行動)。おかげでチーム全体の理解が深まり、良いアイデアもたくさん出ました(影響)」という具合です。
この手法は、ポジティブ・ネガティブ両方のフィードバックに活用でき、特に論理的思考を重視する相手や、具体的な根拠を求める人に効果的です。
360度フィードバック
360度フィードバックは、対象者を中心に、上司、同僚、部下、他部署など、さまざまな立場の人々から評価を受ける手法です。多面的な視点からの評価により、より客観的で総合的な人物像を把握することができます。
この手法の最大の特徴は、評価者の主観や偏見の影響を最小限に抑えることができる点です。また、普段接点の少ない、他部署のメンバーからの意見も含めることで、新たな気付きや発見につながる可能性があります。
ただし、実施には相応の時間と労力が必要であり、頻繁に行うことは現実的ではありません。年1回程度の実施が一般的で、日常的なフィードバックと組み合わせて活用することが重要です。
フィードバックのやり方を組織に定着させる

個人がフィードバックのスキルを身に付けても、組織全体に定着しなければ本当の効果は期待できません。組織レベルでフィードバック文化を根付かせるための取り組みを紹介します。
フィードバックの重要性やり方についての研修を行う
組織全体でフィードバック文化を定着させるためには、まず管理職を中心とした研修の実施が不可欠です。フィードバックの基本的な考え方から具体的な手法まで、体系的に学習する機会を提供しましょう。
研修では、フィードバックの目的や効果、実際の手法だけでなく、ハラスメントにならないための注意点や、相手の特性に応じた伝え方のコツなども含めることが重要です。また、ロープレ形式で実際にフィードバックを練習する機会を設けることで、理論だけでなく実践的なスキルも身に付けることができます。
研修後は定期的なフォローアップを行い、実際の職場での活用状況を確認し、継続的なスキル向上を支援することも大切です。
フィードバックを大切にする文化を醸成する
フィードバックが組織に根付くためには、それを重視する文化の醸成が求められます。「フィードバックは相手の成長を願ってする行為」「建設的な意見交換は組織の発展につながる」といった価値観を組織全体で共有しましょう。
具体的には、フィードバックを積極的に行った管理職を評価制度で評価したり、優秀なフィードバック事例を社内で共有したりすることで、フィードバックの重要性を組織として示すことができます。
管理者が率先してフィードバックする
組織の上層部や管理職が率先してフィードバックを実践することで、その重要性が組織全体に伝わります。トップダウンでフィードバック文化を推進することで、現場レベルでの実践も促進されます。
管理職は自らがロールモデルとなって、部下への適切なフィードバックを継続的に行うとともに、時には部下からのフィードバックも積極的に受け入れる姿勢を示すことが重要です。職場の文化は管理者の行動が大きく影響します。管理者がフィードバックについて正しく理解し、率先垂範で正しく行うことはフィードバックを大切にする文化醸成につながります。
1on1ミーティングを活用する
定期的な1on1ミーティングは、フィードバックを実践するための絶好の機会です。週1回または月1回程度の頻度で、上司と部下が1対1でじっくりと話し合う時間を設けることで、日常業務では伝えきれない詳細なフィードバックが可能になります。
1on1ミーティングでは、業務の進捗確認だけでなく、部下の成長や悩み、キャリアについても話し合い、より深いレベルでのコミュニケーションを図ることができます。継続的な実施により、信頼関係も深まり、フィードバックの効果がさらに高まります。
メンバー同士でフィードバックし合う
上司から部下への一方向的なフィードバックだけでなく、同僚同士や部下から上司への多方向のフィードバックも推進しましょう。これにより、組織全体の学習効果が高まり、より多様な視点からの気付きが得られます。
ピアフィードバックの仕組みを導入することで、チームメンバー全員がフィードバックのスキルを向上させることができ、組織全体のコミュニケーション能力の底上げにつながります。
フィードバックのやり方注意点

フィードバックは適切に行えば大きな効果を期待できますが、方法を誤ると人間関係の悪化や相手のモチベーション低下を招く恐れがあります。実施時の注意点を理解し、安全で効果的なフィードバックをするように意識しましょう。
避けるべきフィードバックの方法
効果的なフィードバックを行うためには、まず避けるべき方法を理解することが重要です。感情的になって相手を批判したり、曖昧で抽象的な表現を使ったりすることは、相手の混乱や不快感を招くだけで建設的な結果につながりません。
特に、公開の場での否定的なフィードバックは相手の自尊心を大きく傷つけ、パワハラと受け取られる可能性があります。改善が必要な内容については、必ずプライベートな場所で、1対1で伝えることが基本です。また、過去の失敗を繰り返し持ち出したり、他の人と比較したりすることも避けるべきです。
|
ハラスメントにならないための配慮
現代の職場では、ハラスメントに対する意識が高まっており、フィードバック実施時にも細心の注意が必要です。最も重要なのは、相手の行動や結果に焦点を当て、人格や性格について言及しないことです。
また、相手の立場や状況を考慮し、一方的に話すのではなく、相手の意見や考えも聞く双方向のコミュニケーションを心掛けることが大切です。威圧的な態度や言葉遣いは避け、常に相手の成長を支援する姿勢を保ちましょう。
相手の人格を否定しない伝え方
フィードバックでは、「あなたはダメだ」「やる気がない」といった人格や意欲を否定する表現は絶対に避けなければなりません。代わりに、「この行動を改善すると、より良い結果が期待できます」「次回はこのような方法を試してみてください」など、具体的で建設的な表現を使いましょう。
相手の努力や良い点も併せて認めることで、改善点の指摘がより受け入れられやすくなります。また、相手の背景や価値観を理解し、個々の特性に応じた伝え方を工夫することも重要です。
▼ハラスメントの種類などについても理解しておきましょう。
⇒【最新|ハラスメントの種類一覧表】40のハラスメント詳細とリスクを解説
フィードバックのやり方の前に自己理解と他者理解

フィードバックを効果あるものにするためには、フィードバックを行う自分自身についての理解を深めることと、フィードバックを行う相手についての理解を深め、相手に合わせたフィードバックを行うことが大切です。
自己診断ツール「LIFO」を使って自己理解を深める
まず、効果的なフィードバックを行うためには自己理解が欠かせません。そのために有用なのが、自己診断ツール「LIFO」です。LIFOは、自分の行動スタイルや価値観を客観的に理解するためのツールであり、特に仕事や人間関係における自身の強みと改善点を明らかにします。
具体的には、LIFOは4つの行動スタイルに分類し、どのスタイルが自分に最も当てはまるかを診断します。この診断を通じて、自分の行動スタイルが明確になると、自分自身の強みをどのように生かすか、どのように他者と協力するかといった行動指針が得られます。LIFOは自己理解を深め、フィードバックを行う際にも自己の特徴・傾向を把握しやすくしてくれるのです。
自己診断ツール「LIFO」を使って他者理解を深める
次に、他者を理解することもフィードバックの効果を高める重要な要素です。LIFOは、他者の行動スタイルを理解するのにも役立ちます。なぜなら、LIFOは共通のフレームワークを提供し、他者の好む行動パターンや価値観を予測しやすくするからです。
例えば、チームメンバーがどの行動スタイルを好んでいるかを理解することで、どのような状況で気持ちよく働けるのかを推測できます。具体的には、人をサポートすることを好むスタイルの人が多い場合、チームの連携を重視することが重要です。もしくは、分析することを好むスタイルの人が多い場合にはデータや具体的な計画を示しながら関わることが求められます。
このように、LIFOを活用することで他者の行動スタイルを理解し、職場運営に生かすことができます。
相手に合わせたフィードバックを行う
フィードバックを行う際には、自己理解と他者理解の成果を活用し、相手に合わせたフィードバックを心掛けることが重要です。具体的には、相手のLIFOスタイルを踏まえたアプローチをすることで、相手がフィードバックを受け入れやすくなり、望ましい行動変化を促します。
例えば、結果を重視することを好むスタイルの人には簡潔で端的なフィードバックが効果的です。彼らは迅速にアクションを起こすことを好むので、結論から伝えるアプローチが適しています。対照的に、新たなことを好むスタイルの人には、新しい視点や創造的な提案を盛り込むと効果的です。
このように、自己および他者の理解を基にしたフィードバックにより、コミュニケーションの質が向上し、チーム全体の成長も期待できます。
まとめ:適切なフィードバックのやり方を定着させよう
効果的なフィードバックのやり方とは?心構えと具体的な手法を解説!について紹介してきました。
効果的なフィードバックのやり方
フィードバックはやり方よりもタイミング
フィードバックのやり方を学ぶ前提
フィードバックとは何か
フィードバックの基本的な種類
代表的なフィードバックのやり方
フィードバックのやり方を組織に定着させるには
フィードバックのやり方注意点
フィードバックのやり方の前に自己理解と他者理解
効果的なフィードバックは、個人の成長と組織の発展を支える重要な要素です。具体的で建設的な内容を適切なタイミングで伝えること、相手との信頼関係を基盤とすること、そして多様な手法を状況に応じて使い分けることが成功の鍵となります。
個人のスキル向上だけでなく、組織全体でフィードバック文化を定着させることで、メンバー同士が互いに学び合い、継続的に成長できる環境を構築できます。
研修の実施、管理者の率先垂範、1on1ミーティングの活用など、段階的な取り組みを通じて、フィードバックが日常的に行われる組織づくりを目指しましょう。
適切なフィードバックのやり方を身に付け、組織に定着させることで、個人と組織の両方が持続的に発展する理想的な職場環境を実現できます。
株式会社LDcubeでは、フィードバック文化の醸成に向け、LIFO診断を活用した「職場でのフィードバック」ワークショップができるツールや、社内トレーナーの養成を支援しています。関心ある方はお気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。