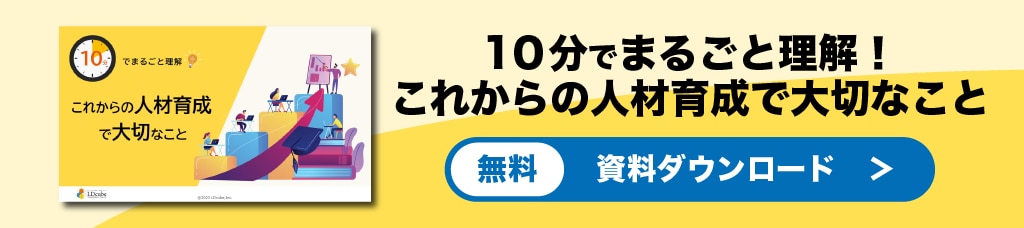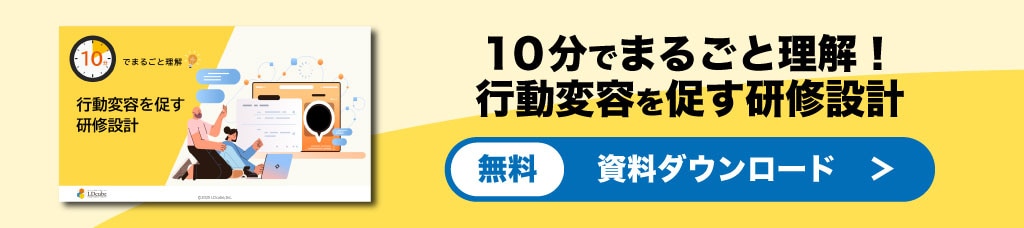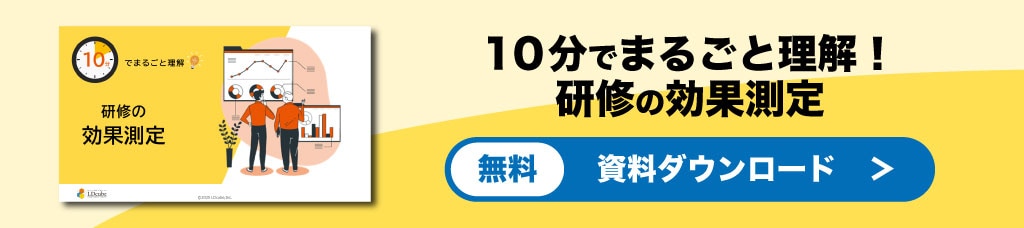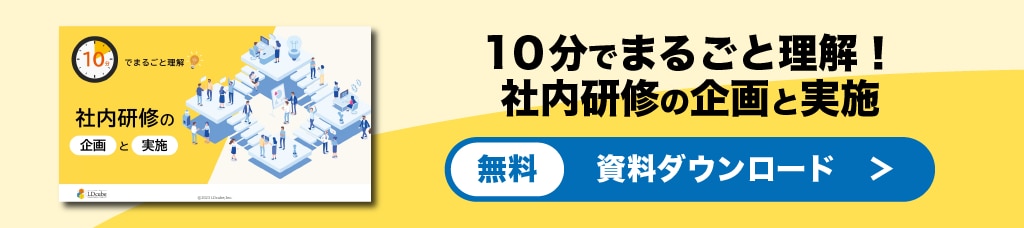人材育成のコンサルタント選びは「行動変容」を軸にしよう!ポイントを解説!
近年、多くの企業が直面する課題の1つは「研修を行ったのに社員の行動が変わらない」ということです。その結果、研修に投じた時間やコストが無意味になることを恐れています。
実際、企業が期待するのは、研修を通じて社員が新たなスキルを身に付け、それを業務で積極的に活用すること。つまり、単なる知識習得ではなく、業務における具体的な「行動変容」が非常に重要です。
そのため、人材育成のコンサルタントを選ぶ際は、研修の内容やカリキュラムだけでなく、行動変容をどうやって引き起こすかに注目すべきです。研修や制度設計、またはデジタルツールの活用といった手段にばかり目を向けがちなコンサルタントは、「形だけの」成果に終わりかねません。
重要なのは、それが実際の行動変化につながるかどうか。コンサルタント自身が行動変容を第一に考え、その成果を明確に測定できる支援を行っているかを見極めることが大切です。
その一方で、社内に育成の専門家を育てることで、継続的な人材育成が可能となるケースもあります。社内トレーナーの活用は、企業風土に即した効果的なプログラムを組むことができ、外部に頼るだけでは得られないメリットを享受できます。
あなたの企業が直面する具体的な課題を解決するための適切なパートナーを選び、未来の成長につながる効果的な人材育成プランを築くことが、何よりも重要です。
本記事では、人材育成コンサルタントの種類や見極めるポイント、一般的な費用感など解説しながら、これからの時代も見据え人材育成を本質的に進めていくポイントについて事例を交えながら解説していきます。
▼人材育成についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。
▼人材育成で大切なことについては下記にまとめています。
▼行動変容を促す人材育成設計については下記にまとめています。
目次[非表示]
- 1.人材育成のコンサルタント選びは「行動変容」を軸にしよう
- 1.1.研修の目的は「行動変容」
- 1.2.研修制度の設計や研修実施は手段
- 2.人材育成のコンサルタントは大きく3種類
- 2.1.研修ベースのコンサルタント
- 2.2.制度設計ベースのコンサルタント
- 2.3.ツールベースのコンサルタント
- 3.人材育成コンサルタントの限界
- 4.人材育成コンサルタントを見極めるポイント
- 4.1.施策の目的を明確にしているか
- 4.2.行動変容について言及しているか
- 4.3.効果測定を取り入れているか
- 5.人材育成コンサルタントの費用相場
- 5.1.一般的な費用の目安
- 5.2.費用対効果の考え方
- 5.3.社内に人材育成コンサルタントを養成するのも手
- 6.これからの人材育成コンサルタントに必要なこと
- 6.1.デジタル化に対応する
- 6.2.データを活用する
- 6.3.自分の稼働ではなく効果にコミットする
- 7.これからの人材育成のあるべき姿
- 8.社内で人材育成コンサルタントを養成し展開している事例
- 9.人材育成コンサルタントに相談するならLDcube
- 10.まとめ:人材育成の目的は「行動変容」
人材育成のコンサルタント選びは「行動変容」を軸にしよう

人材育成のコンサルタント選びは研修内容やカリキュラムではなく「行動変容」を軸にしましょう。それは研修の目的が行動変容だからです。ポイントを解説します。
研修の目的は「行動変容」
人材育成における研修の最終的な目的は「行動変容」を促すことです。知識の習得やスキルの向上は手段であり、実際の業務での行動が変わらなければ、研修の成果とは言えません。
企業が研修を実施する理由は、業績向上や組織力の強化など、ビジネスをする上で成果に直結する行動を取れる人材の育成を期待しているからです。つまり、研修によって社員が「何を知ったか」ではなく、「何をするようになったか」が重要なのです。行動が変わることで、業務の質が向上し、組織全体のパフォーマンスが高まります。
例えば、マネジメント研修を受けた管理職が、部下との1on1ミーティングを定期的に実施するようになったとします。これは知識の習得だけでなく、実際の行動が変わった証拠です。このような行動変容が積み重なることで、職場のコミュニケーションが改善され、離職率の低下や生産性向上につながります。
研修の成果を測るには、受講者の行動がどのように変わったかを見極めることが不可欠です。人材育成のコンサルタントを選ぶ際は、「行動変容」を軸にした設計・支援ができるかどうかを重視しましょう。
研修制度の設計や研修実施は手段
研修制度の設計や研修の実施は、あくまで「行動変容」を実現するための手段です。制度やプログラムそのものが目的化してしまうと、本来の成果が得られなくなります。
多くの企業では、研修制度の整備や研修の実施そのものに注力しがちですが、それだけでは社員の行動は変わりません。制度が整っていても、受講者が実務に生かせなければ意味がなく、研修が「やっただけ」で終わってしまう危険性があります。重要なのは、制度や研修が「行動変容」にどうつながるかという設計思想です。
例えば、eラーニングを導入しても、受講後に業務で使う場面がなければ、知識は定着せず行動も変わりません。一方で、研修後に上司との振り返り面談を制度化することで、学びを業務に落とし込む機会が生まれ、行動変容が促進されます。このように、制度や実施方法は「行動変容」を支える仕組みとして設計されるべきです。
人材育成のコンサルタントを選ぶ際は、制度設計や研修実施の「手段」だけでなく、それが「行動変容」にどうつながるかを重視しているかを確認しましょう。成果につながる支援ができるかどうかが、選定のポイントです。
▼行動変容につながる研修については下記で詳しく解説しています。
⇒社内教育・研修の目的は社員の「行動変容」|効果的な実施方法とは?
人材育成のコンサルタントは大きく3種類

人材育成のコンサルタントは大きく3種類あります。それぞれ得意とする分野の違いにより提供するサービスが異なってきます。
研修ベースのコンサルタント
研修ベースのコンサルタントは、社員のスキルや知識の向上を目的とした研修プログラムの企画・実施を中心に支援します。現場での「学びの場」を提供することに特化しています。
このタイプのコンサルタントは、特定のテーマ(例:リーダーシップ、コミュニケーション、マネジメントなど)に関する研修を通じて、社員の行動変容を促します。研修設計やファシリテーションに長けており、受講者の理解度や参加意欲を高める工夫が豊富です。
例えば、管理職向けのマネジメント研修を提供するコンサルタントは、ケーススタディーやロープレを活用し、実践的なスキル習得を支援します。研修後にはフォローアップ研修やeラーニングを組み合わせることで、学びの定着と行動変容を図ります。
研修ベースのコンサルタントは、現場での「学び」を重視する企業に適しています。短期的なスキルアップやテーマ別の育成ニーズに応えるには、非常に有効な選択肢です。
制度設計ベースのコンサルタント
制度設計ベースのコンサルタントは、人材育成を組織戦略と連動させるための仕組みづくりを支援します。研修だけでなく、育成体系全体の設計に強みがあります。
このタイプのコンサルタントは、育成方針の策定からキャリアパス、評価制度、研修体系の構築までを一貫して支援します。人材育成を「制度」として定着させることで、継続的な成長を促す仕組みを整えることができます。
例えば、ある企業が「次世代リーダー育成」を目的に制度設計を依頼した場合、コンサルタントは選抜基準、育成ステップ、評価指標などを設計し、社内で運用できる仕組みを構築します。これにより、育成が属人的ではなく、組織的に行えるようになります。
制度設計ベースのコンサルタントは、長期的な人材戦略を描きたい企業に最適です。育成を仕組み化し、組織全体で人材を育てる土台を整えることができます。
ツールベースのコンサルタント
ツールベースのコンサルタントは、デジタルテクノロジーや学習管理システム(LMS)、アセスメントツールなどを活用して、人材育成の効率化と可視化を支援します。
近年、研修のデジタル化やDXが進む中で、ツールを活用した育成支援のニーズが高まっています。ツールベースのコンサルタントは、学習履歴の管理、効果測定、個別最適化などを実現するための専門的な支援が可能です。
例えば、LMSを導入して社員の学習進捗を可視化したり、アンケートツールを使って行動変容を測定したりすることで、育成の成果をデータで把握できます。これにより、育成施策の改善や経営層への報告もスムーズになります。
ツールベースのコンサルタントは、育成の「見える化」や「効率化」を重視する企業に適しています。デジタルテクノロジーを活用して、育成の質とスピードを高めたい場合に有効です。
▼人材育成コンサルタントは資格がなくてもできますが、資格については下記で詳しく解説しています。
⇒人材育成のトレーナー認定資格とは?養成講座や研修を紹介!
人材育成コンサルタントの限界

人材育成コンサルタントは得意分野に応じて、実は限界を持ち合わせています。この点についてはあまり語られることはありませんが、限界が存在するのです。
研修ベースのコンサルタントは研修で完結してしまう
研修ベースのコンサルタントは、研修の企画・実施には強みがありますが、研修後のフォローや組織全体への定着支援が弱く、研修で完結してしまう傾向があります。
多くの場合、研修ベースのコンサルタントは「研修を実施すること」でビジネスが成立しており、受講者の行動変容や業務への応用まで踏み込んだ支援は契約範囲に入っていないのです。ただ、研修後の職場での実践や、上司との連携、評価制度との接続などがないと、学びが一過性のものになってしまいます。
例えば、コミュニケーション研修を実施し、評判良く終了したとしても、職場で活発にコミュニケーションを取る文化が育っていなければ、受講者は学んだスキルを使うに至らず、行動は変わりません。研修だけで終わると、企業としての人材育成効果は限定的になります。
研修ベースのコンサルタントを活用する際は、研修後のフォロー体制や職場への定着支援があるかどうかを確認することが重要です。研修はあくまで「スタート」であり、育成のゴールは行動変容です。
制度設計ベースのコンサルタントは研修ノウハウがない
制度設計ベースのコンサルタントは、育成体系や評価制度の構築には強みがありますが、現場での研修実施や学習設計のノウハウが不足しているケースが多くあります。
制度設計に特化したコンサルタントは、戦略や仕組みづくりに長けている一方で、実際の研修現場で何が効果的か、どのように学習を設計すべきかという実践的な知見が乏しいことがあります。その結果、制度は整っていても、現場での運用がうまくいかず、育成が形骸化するリスクがあります。
例えば、キャリアパスや研修体系を設計しても、研修を実施して受講者に期待する行動を伝え、新たなスキルを学ぶ機会を提供できなかったり、また研修を実施しても研修内容が現場のニーズに合っていなかったり、受講者のレベルに合っていないと、制度は機能しません。制度と研修が連動していないと、人材育成の成果は出にくくなります。
制度設計ベースのコンサルタントを選ぶ際は、研修が実施できるか、学習設計の知見があるかどうかを確認しましょう。制度と研修が連動してこそ、育成は成果につながります。
ツールベースのコンサルタントはシステム屋さんになりがち
ツールベースのコンサルタントは、LMSやアセスメントツールなどの導入支援に強みがありますが、育成の本質である「行動変容」への視点が弱く、システム導入が目的化してしまうことがあります。
ツール導入は育成の効率化や可視化に役立ちますが、ツールそのものが育成を実現するわけではありません。ツールベースのコンサルタントがシステム寄りになりすぎると、育成の目的や行動変容への設計が抜け落ち、単なる「システム屋さん」になってしまうリスクがあります。
例えば、LMSを導入しても、コンテンツが受講者のニーズに合っていなかったり、学習後のフィードバックや行動変容へのサポートがなかったりすると、ツールは活用されずに終わってしまいます。ツールは手段であり、育成の目的に沿った設計が不可欠です。
ツールベースのコンサルタントを選ぶ際は、システムだけでなく育成設計や行動変容への理解があるかを確認しましょう。システム導入が目的化してしまうと、人材育成の本質が見失われます。
人材育成コンサルタントを見極めるポイント

人材育成コンサルタントを活用する場合の見極めるポイントについて紹介します。
施策の目的を明確にしているか
人材育成コンサルタントを選ぶ際は、施策の目的を明確にしているかどうかが重要な判断基準です。目的が曖昧なままでは、成果につながる支援は期待できません。
人材育成は「何のために行うのか」が明確でなければ、研修や制度設計が形骸化してしまいます。目的が明確であれば、育成施策の方向性が定まり、組織の課題解決や目標達成に直結する支援が可能になります。逆に、目的が不明確なまま進めると、現場とのズレが生じ、投資対効果も見えづらくなります。
例えば、「若手社員の定着率を高めたい」という目的が明確であれば、コンサルタントはエンゲージメント向上やキャリア支援に焦点を当てた施策を提案できます。一方で、目的が「とりあえず若手社員に研修を行う」では、成果につながる支援は難しくなります。
人材育成コンサルタントを見極める際は、施策の目的を明確に言語化し、それに基づいた提案ができるかを確認しましょう。目的が明確であるほど、成果につながる支援が期待できます。
行動変容について言及しているか
優れた人材育成コンサルタントは、施策の成果として「行動変容」について言及します。単なる知識習得ではなく、実際の業務での行動が変わることを重視しているかが重要です。
人材育成の本質は、社員の行動が変わり、組織の成果につながることです。行動変容を意識していないコンサルタントは、研修を「やっただけ」、制度を「つくっただけ」で終わる可能性が高く、実務への効果が見えづらくなります。行動変容を軸にした設計ができるかどうかが、コンサルタントの力量を測るポイントです。
例えば、マネジメント研修を実施した後に、「部下との1on1を定期的に実施するようになった」「フィードバックの質が向上した」といった行動変容が見られれば、研修は成功と言えます。こうした変化を意識して支援できるコンサルタントは、成果に直結する提案が可能です。
人材育成コンサルタントを選ぶ際は、行動変容を成果として捉えているかを確認しましょう。行動が変わることで、初めて人材育成施策は意味を持ちます。
効果測定を取り入れているか
人材育成の成果を可視化するためには、効果測定の仕組みが不可欠です。コンサルタントが効果測定を取り入れているかどうかは、信頼性を見極める重要なポイントです。研修終了時のアンケートで満足度が高いだけでは意味がありません。
人材育成施策は「やって終わり」ではなく、成果を検証し、改善につなげることが求められます。効果測定があることで、施策の妥当性や投資対効果を把握でき、経営層への報告や次の施策設計にも生かせます。測定を行わない場合、育成の成果が曖昧になり、研修の評判の良しあしだけでイベント化してしまいます。
例えば、行動チェックリストによる定期的なリマインドやフォロー、LMSによる学習履歴の分析などを活用すれば、受講者の行動変容やスキル向上を定量的に把握できます。こうしたデータを基に、施策の改善や再設計が可能になります。
人材育成コンサルタントを見極める際は、効果測定の仕組みを持っているか、または導入支援ができるかを確認しましょう。成果を「見える化」できるコンサルタントこそ、信頼できるパートナーです。
▼効果測定については下記で詳しく解説しています。
⇒研修の効果測定を行い、成果につなげる方法とは?ツール活用法も解説!
人材育成コンサルタントの費用相場

人材育成コンサルタントに依頼する際には費用がかかります。ここでは一般的な費用や費用対効果の考え方、またコンサルタントに依頼するのではなく、社内にコンサルタントを育成するという手段についても紹介します。
一般的な費用の目安
人材育成コンサルタントの費用は、支援内容や期間、対象人数によって大きく異なりますが、一般的な相場を把握しておくことで、適切な予算計画が立てやすくなります。
費用は「研修単発型」「制度設計型」「ツール導入支援型」等の、支援内容や形式によって異なります。例えば、1日間の集合研修であれば30万円〜50万円程度が相場ですが、制度設計や長期的な育成支援になると、支援にかかる日数が増えることとなり、数百万円〜数千万円規模になることもあります。ツール導入支援では、活用するツールにもよりますが、初期費用(50万~100万)と月額利用料(1人2000円など)が発生するケースが多いです。
人材育成コンサルタントの費用は内容によって幅があります。まずは自社の課題と目的を明確にし、それに見合った支援内容と費用感を把握することが大切です。
費用対効果の考え方
人材育成コンサルタントの費用は「コスト」ではなく、「投資」として捉えるべきです。費用対効果を正しく評価することで、納得感のある意思決定が可能になります。
育成施策の成果は短期的には見えにくいものの、社員の行動変容や業績向上、離職率の低下など、長期的な効果が期待できます。費用対効果を考える際は、単に「いくらかかったか」ではなく、「どのような変化が起きたか」を評価する視点が重要です。
例えば、100万円の研修を実施し、管理職のマネジメント力が向上した結果、部下の離職率が10%改善されたとします。この改善によって採用・教育コストが削減され、生産性も向上すれば、投資以上のリターンが得られたと考えることもできます。
費用だけで判断せず、施策の成果や組織へのインパクトを含めて費用対効果を評価しましょう。人材育成は、未来の企業価値を高めるための重要な投資です。
社内に人材育成コンサルタントを養成するのも手
外部コンサルタントに頼るだけでなく、社内に人材育成の専門家を育てることも、長期的には有効な選択肢です。
社内に人材育成の知見を持つ人材がいれば、外部に依存せずに継続的な育成施策を展開できます。また、自社の文化や業務に精通しているため、より実態に即した施策設計や運用が可能になります。初期投資は必要ですが、長期的にはコスト削減や内製化による柔軟な対応が期待できます。
例えば、社内の人事担当者が学習設計や研修実施、効果測定のスキルを習得すれば、外部コンサルタントに頼らずとも、研修や行動変容の促進を自社で展開できるようになります。さらに、現場との連携もスムーズになり、人材育成の効果も高まります。
人材育成の内製化は、コスト面だけでなく、組織の自立性や持続可能性を高める上でも有効です。外部支援と並行して、社内に人材育成の専門家を育てることも検討してみましょう。
▼研修の費用については下記で詳しく解説しています。
⇒研修実施に伴う費用とは?外部講師から内製化する相場まで徹底解説!
これからの人材育成コンサルタントに必要なこと

現代は環境変化が激しい時代です。そのような中で、これからの人材育成コンサルタントに求められることも変わっていきます。ポイントを解説します。
デジタル化に対応する
これからの人材育成コンサルタントには、研修や人材育成施策のデジタル化に対応できる力が不可欠です。オンライン環境での学習支援やツール活用が求められます。
働き方の多様化やリモートワークの定着により、従来の集合研修だけでは対応しきれない場面が増えています。eラーニング、LMS(学習管理システム)、マイクロラーニングなど、デジタルツールを活用した育成が主流になりつつあります。コンサルタントには、これらのツールを生かした設計・運用の知見が求められます。
例えば、全国に拠点を持つ企業が、管理職研修をオンラインで実施する場合、単なる動画配信ではなく、インタラクティブな設計や進捗管理、フォローアップの仕組みが必要です。デジタル化に対応できるコンサルタントは、こうした複雑な設計を支援できます。
人材育成の現場は急速にデジタル化しています。これからのコンサルタントには、ツールを使いこなし、オンラインを積極的に滑油して成果を出せる支援力が求められます。
データを活用する
人材育成の成果を高めるためには、データを活用した設計と改善が不可欠です。集合研修を実施するだけでは何のデータも取得できません。これからのコンサルタントには、学習行動のデータを取得し活用するデータリテラシーが求められます。
人材育成施策の効果を可視化し、改善につなげるには、定量的なデータの収集と分析が必要です。受講者の学習履歴、理解度クイズの結果、行動チェックリストの推移などのデータを活用することで、より精度の高い育成が可能になります。データに基づいた意思決定ができるコンサルタントは、経営層からの信頼も得やすくなります。
例えば、LMSを活用して受講者の進捗や理解度を分析し、理解が浅い部分に対して追加コンテンツを提供することで、学習効果を高めることができます。また、研修後の行動チェックリストのデータを基に、次回施策の改善点を明確にすることも可能です。
これからの人材育成コンサルタントには、感覚ではなくデータに基づいた支援が求められます。データ活用は、人材育成の質と成果を高める鍵です。
自分の稼働ではなく効果にコミットする
これからの人材育成コンサルタントは、自分の稼働日数ではなく、「人材育成施策の効果」にコミットする姿勢が求められます。
従来のコンサルタントは、研修の実施や制度設計など「稼働日数」に対して報酬を得るスタイルが一般的でした。しかし、企業が求めているのは「効果」であり、行動変容や業績向上など、目に見える変化です。効果にコミットするコンサルタントは、施策の設計から運用、改善までを一貫して支援し、きちんと効果測定を行います。
例えば、ある企業が「若手社員の定着率向上」を目的に育成施策を依頼した場合、効果にコミットするコンサルタントは、研修だけでなく、職場でのフォロー体制や評価制度の見直しまで提案します。結果として、離職率が下がれば、企業にとっての価値は非常に高くなります。
これからの人材育成コンサルタントは、「何をしたか」ではなく「何が変わったか」に重きを置くべきです。効果にコミットする姿勢こそ、信頼されるコンサルタントの条件です。
これからの人材育成のあるべき姿

コロナ禍を経て、働き方やライフスタイルが大きく変わってきています。そのような中では、人材育成のあり方も変化しています。これからの人材育成のあるべき姿について解説します。
学習環境を整える(いつでも・どこでも・なんどでも)
これからの人材育成では、「いつでも・どこでも・なんどでも」学べる環境づくりが不可欠です。実社会での問題解決行動は「いつでも・どこでも・なんどでも」スマホで必要な情報を検索し、学習して、問題解決しています。社内の学習にも同様の環境があることが理想です。その学習の柔軟性が、社員の成長スピードと定着率を高めます。
従来の集合研修では、時間や場所の制約があり、学習機会が限定的でした。しかし、働き方の多様化やリモートワークの普及により、社員が自分のペースで学べる環境が求められています。eラーニングやマイクロラーニング、LMSなどのデジタルツールを活用することで、学習の自由度が格段に向上します。
例えば、営業職の社員が移動中にスマホで短時間の動画学習を行い、必要な知識をその場で習得できるようになれば、業務ですぐに活用することが可能になります。また、何度でも繰り返し学べる設計にすることで、理解度の差にも対応できます。
人材育成の成果を高めるには、学習の「自由度」と「継続性」が重要です。いつでも・どこでも・なんどでも学べる環境を整えることが、これからの育成の基本です。
基本的に社内トレーナーが研修を実施
これからの人材育成では、社内トレーナーによる研修実施が基本となります。弊社LDcubeが行った調査では60%の組織で研修は社内トレーナーが実施しているということが分かっています。企業文化を理解した人材が育成を担うことで、実践的かつ定着しやすい学びが実現します。
外部講師による研修は専門性が高い一方で、企業文化や業務内容とのズレが生じることがあります。社内トレーナーであれば、現場の課題や組織の方針を踏まえた内容で研修を設計・実施できるため、受講者の納得感や実践意欲が高まります。また、継続的な育成が可能になる点も大きなメリットです。
例えば、社内のベテラン社員がトレーナーとして若手向けのOJT研修を行うことで、実務に即したノウハウが伝えられ、現場での即戦力化が進みます。さらに、社内トレーナーが育成文化を醸成することで、組織全体の学習意欲も高まります。
人材育成の質と継続性を高めるには、社内トレーナーの活用が鍵です。自社の状況に合った育成を実現するために、社内で育成を担える人材を育てることが重要です。
リソース不足を外部コンサルタントで補う
社内だけでは対応しきれない育成ニーズやリソース不足は、外部コンサルタントの力を借りて補うことが効果的です。内製と外部支援のバランスが、人材育成の質を左右します。
人材育成には、設計・実施・評価といった多くの工程があり、すべてを社内で担うのは難しい場合があります。特に新しいテーマ(DX、リーダーシップ、心理的安全性など)や専門的な設計が必要な場面では、外部の知見を活用することで、スピードと質を両立できます。
例えば、社内に研修設計のノウハウがない場合、外部コンサルタントに学習設計や効果測定の支援を依頼することで、社内トレーナーが安心して研修を実施できる環境が整います。また、一時的なリソース不足にも柔軟に対応できます。外部コンサルタントを適切に活用することで、育成の質とスピードを高め、持続可能な育成体制を構築できます。
社内で人材育成コンサルタントを養成し展開している事例

■ 背景・課題:
リコージャパン株式会社では、2010年の販売会社統合以降、各支社の固有の課題に対応できず、教育施策が本部主導で一方的になるなどの課題がありました。
また、コロナ禍以降、会食などの機会が減ったことにより、コミュニケーションの希薄化を招いていました。これらの課題を解決するために、社員自らが強みや弱みを理解し合い、横のつながりを強化する取り組みが求められていました。
■ LIFOプログラム(社内トレーナーライセンス)の導入:
その中で、LIFO(Life Orientations)を導入しました。LIFOの活用を通じて、社員一人一人の個性を診断し、自己理解と他者理解を促進しました。
これにより、非公式なコミュニケーションが減少する中でも、社員同士の相互理解を深めるための新たな手段を提供することができるようになりました。
また、LIFOプログラムライセンスを取得することで、社内トレーナーが自主的に研修を行えるようになり、組織風土改革を進めました。
LDcubeとの協力により、多様なワークショップを展開し、各支社・部門が抱える具体的な課題に対応できるようになりました。
■ 社内展開:
プログラムの展開においては、事前のLIFO診断、ワークショップの実施、職場での実践、効果検証のサイクルを組み込みました。
参加者は、研修後の職場実践を通じて得られたスキルを評価し合い、PDCAサイクルを回すことで、持続的なスキルアップを図っています。
ラーニングプラットフォーム「UMU」を活用し、受講者同士が学び合う環境も整備しました。
■ 社内トレーナーによる研修実施後の反応:
導入後、プログラム受講者の満足度は高く、多くの支社で「対人関係」や「マネジメント能力」などにおいて数値的な改善が見られました。
LIFOを活用したレクチャーは「人」の問題の解決に寄与し、特にアウトプット重視の体験学習が効果的でした。
UMUの活用と一連の学習サイクルの設計により、事務局の負担軽減と学習効果の向上が実現しました。
■ 今後に向けて:
今後は、各支社や部門の課題に寄り添い、人材育成を継続的にサポートすることで、社員個々の自己成長と組織全体の活性化をさらに推進する予定です。
また、LIFO以外のライセンスプログラムも組み合わせ、人材育成のプログラムラインナップを増やしていきます。
これにより、組織内のさまざまな課題を解決し、全体の一体感を更に高められることを期待しています。
▼本事例はインタビュー記事の一部です。インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。
⇒リコージャパン株式会社様 ライセンスプログラム導入事例
人材育成コンサルタントに相談するならLDcube

人材育成コンサルタントの活用を検討されているのであれば、ぜひLDcubeにご相談ください。LDcubeはこれまでの人材育成コンサルタントの限界を突破するために設立した背景があります。お役に立てることがあると思います。
研修会社出身で研修のノウハウがある
LDcubeは、研修会社から分割して設立しており、豊富な研修ノウハウを持っています。だからこそ、実践的で成果につながる人材育成支援が可能です。
研修の現場を知っているからこそ、受講者の反応や学習定着の難しさ、現場とのギャップなど、実務に即した課題に対応できます。単なる理論やテンプレートではなく、企業ごとの課題に合わせた柔軟な設計ができることが強みです。
例えば、管理職向けの研修では、単なる知識提供ではなく、現場での実践を促す研修後のフォロー体制までを含めた支援を行います。これにより、研修が「やって終わり」ではなく、行動変容につながる設計が可能になります。
研修の成果を本気で出したいなら、研修現場も知るLDcubeが最適です。研修会社出身だからこそ、実践的で成果に直結する支援ができます。
ツールを組み合わせて効果にコミット
LDcubeは、研修だけでなく、LMSやアセスメントツールなどを組み合わせて、人材育成の「効果」にコミットする支援を行っています。
人材育成は「やったかどうか」ではなく、「何が変わったか」が重要です。LDcubeは、研修の設計だけでなく、学習履歴の管理や行動変容の測定など、ツールを活用して成果を可視化し、改善につなげる仕組みを提供しています。
例えば、研修後に行動チェックリストでの細かなフォローを実施し、受講者のマネジメント行動がどう変化したかをデータで確認します。さらに、LMSを活用して学習進捗を管理し、必要に応じて追加コンテンツを提供することで、学習の定着率を高めます。
LDcubeは、ツールを単なるオプションではなく、人材育成成果を最大化するための「仕組み」として活用します。効果にコミットする姿勢が、他社との違いです。
研修会社の限界突破のために分社した背景
LDcubeは、従来の研修会社の限界を突破するために分社化された、新しい形の人材育成支援企業です。だからこそ、柔軟で本質的な支援が可能です。
従来の研修会社では、研修提供が中心で、学習設計や効果測定、ツール活用などを通じて、研修後の行動変容の領域には踏み込めないケースが多くありました。LDcubeはその限界を感じ、より本質的な人材育成を実現するために、独立した専門組織として立ち上げました。
例えば、ある企業では「研修は良かったが、現場で生かされていない」という課題がありました。LDcubeは、研修後の職場定着支援や社内トレーナーの育成までを一貫して支援し、人材育成の成果を組織全体で実感できるようにしました。
LDcubeは、研修会社の枠を超えた支援を実現するために生まれた存在です。人材育成の本質に向き合い、企業の成長に本気でコミットするパートナーとして選ばれています。
まとめ:人材育成の目的は「行動変容」
人材育成のコンサルタント選びは「行動変容」を軸にしよう!ポイントを解説!について紹介してきました。
人材育成のコンサルタント選びは「行動変容」を軸にしよう
人材育成のコンサルタントは大きく3種類
人材育成コンサルタントの限界
人材育成コンサルタントを見極めるポイント
人材育成コンサルタントの費用相場
これからの人材育成コンサルタントに必要なこと
これからの人材育成のあるべき姿
社内で人材育成コンサルタントを養成した事例
人材育成コンサルタントに相談するならLDcube
人材育成のコンサルタント選びにおいて、最も重要な視点は「行動変容」です。本記事で解説した通り、人材育成の目的は単なる知識の取得やスキルの向上ではありません。最終的には、実際の業務においてどのように行動が変わり、組織としての成果がどれだけ向上したかが評価基準となります。このため、研修や制度設計は行動変容を支える手段であることを常に意識することが求められます。
また、人材育成のコンサルタントには「研修ベース」「制度設計ベース」「ツールベース」といったタイプがあり、それぞれの強みと限界があります。研修ベースのコンサルタントは、知識を伝えることには優れていますが、その効果を持続させるためのフォローが不足しがちです。一方、制度設計ベースのコンサルタントは長期的な育成戦略を描くのが得意ですが、研修の現場感覚に欠けることがあります。そしてツールベースのコンサルタントは、デジタル化の推進に強みを持ちますが、行動変容への貢献が見えにくいことが課題です。
人材育成における真の成果を達成するには、これらの限界を克服し、目的を明確に定め、行動変容を成果として位置づけることが不可欠です。デジタル化やデータ活用など、これからの時代に求められる新しい手法も駆使しつつ、個別企業のニーズに合った実践的な施策作りが重要です。最後に、社内に人材育成の専門家を育成し、内製化を進めることで、持続可能かつ柔軟な育成体制を築くことが、組織の成長への鍵であると締めくくります。
株式会社LDcubeでは、効果的な学習設計についてのコンサルティングや各種施策の実行支援を行っています。プロの外部講師が活用している研修プログラムを社内トレーナーの方々にも提供しています。これらの研修プログラムを活用いただくことで、プロさながらの研修を社内でも展開することができます。
また、研修の充実化をはかるためのeラーニングやLMS、経営シミュレーションアプリなどの提供も行っています。これらを使いこなすことで、社内講師でもかなり充実した研修を展開することが可能となります。
無料でのプログラム体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。