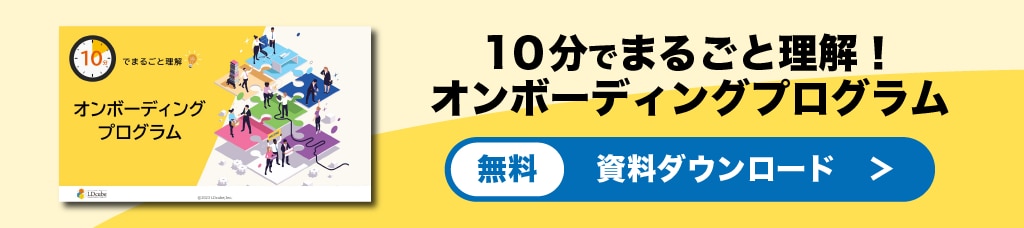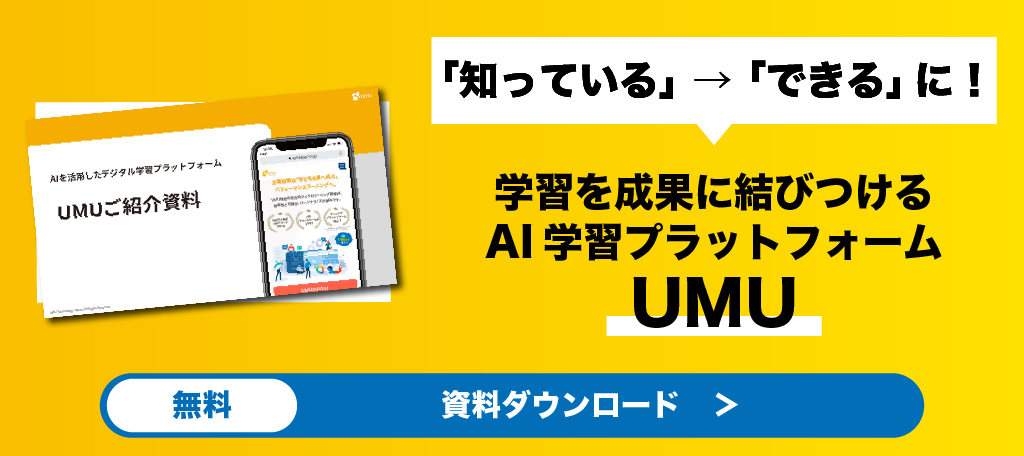オンボーディングとOJTの違いとは?異なる目的や取り組みを理解しよう!
新しいメンバーを迎える際には、「オンボーディング」と「OJT(On the Job Training)」という言葉をよく耳にしますが、具体的に何が違うのでしょうか?
この疑問を解消できれば、新メンバーの早期戦力化や離職率の低減に大きく役立つはずです。
この記事では、まず「オンボーディング」とは何か、その基本的な定義をご説明します。
次に、「OJT」の詳細について掘り下げ、両者の違いを明確にしていきます。
具体的には、①実施の目的、②担当者の違い、③実施期間、④学習内容という4つの観点から比較し、それぞれの特長を明らかにします。
さらに、オンボーディングと集合研修との違いについても触れ、どのようなプログラムが効果的であるかについての指針を示します。
この記事を読むことで、「オンボーディング」と「OJT」の違いを正確に理解し、これらを効果的に活用するための知識を得ることができます。
また、オンボーディングをより効果的に行うためのデジタルツールや具体的な成功事例についても学べます。
新人の成長をサポートし、組織の強化に直結するオンボーディングとOJTの賢い選び方を、ぜひ一緒に考えていきましょう。
▼オンボーディングについてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。
▼OJTについてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。
▼オンボーディングについては下記資料にまとめています。
目次[非表示]
- 1.そもそもオンボーディングとは
- 2.OJT(On the Job Training)とは
- 3.オンボーディングとOJTの違い
- 4.オンボーディングと集合研修の違い
- 4.1.オンボーディングプログラムの特徴
- 4.2.集合研修の特徴
- 5.オンボーディングのメリット
- 6.効果的なオンボーディングプロセス
- 7.オンボーディングプロセスの設計と実施における5つのポイント
- 7.1.①個別化されたオンボーディングプランの作成
- 7.2.②OJTとの効果的な連動
- 7.3.③定期的なフィードバックと評価システムの導入
- 7.4.④テクノロジーを活用したオンボーディング手法
- 7.5.⑤協力体制の確立
- 8.オンボーディングに役立つ2つの要素
- 8.1.①eラーニング
- 8.2.②LMS(学習管理システム)
- 9.デジタルツールを活用したオンボーディング事例
- 10.まとめ
そもそもオンボーディングとは
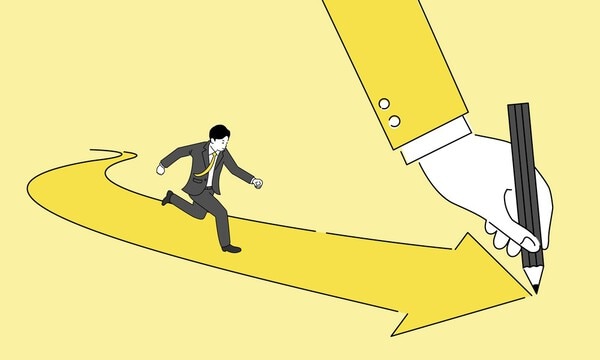
オンボーディングとは、新たに入社した社員にいち早く仕事や環境に慣れてもらうために企業でサポートする取り組みのことをいいます。
船や飛行機などに乗りこむことを意味する英語の「on-board」が語源であり、新たに加わった乗組員の育成やサポートをする取り組みが由来です。
現在は人事用語として企業で用いられており、新入社員に仕事の流れや企業のルールを早い段階で習得させ、企業への定着と戦力化を目的として実施されています。
オンボーディングは新人研修と同じものと思われがちですが、新卒社員だけではなく、中途社員や既存社員もサポートの対象です。
短期的な取り組みとして実施される新人研修とは異なり、オンボーディングは継続的な育成・サポートをするという考え方から中長期的に実施されます。
▼オンボーディングについては下記にまとめてします。
OJT(On the Job Training)とは

OJTとはOn the Job Trainingの略称であり、 業務の実践的な訓練を通して新入社員を育成する取り組みです。
さまざまな企業で取り入れられており、実際の業務を行いながら上司や先輩社員に仕事のノウハウをレクチャーしてもらいます。
OJTは新入社員の即戦力化が目的であり、一般的に3ヶ月~1年程度の期間で実施されます。実際に現場で働く社員から直接教えてもらえるため、仕事を早く覚えやすいことがメリットです。
しかし、OJTは指導者の能力によって左右される部分があることから、得られる効果に幅が出る可能性があります。
▼OJTの全体像については下記で解説しています。合わせてご覧ください。
⇒効果的なOJTとは?意味と目的、新時代の学習環境の作り方を解説
オンボーディングとOJTの違い

オンボーディングとOJTには、以下のような違いがあります。
オンボーディング | OJT | |
実施する目的 | ・組織への順応・定着 | ・業務における必要な知識の習得 |
担当者 | ・人事部門 | ・対象者の上司 |
実施期間 | ・入社後から平均3ヶ月程度 | ・3ヶ月~1年程度 |
学習内容 | ・一般常識 | ・現場により近い内容の知識やスキル |
オンボーディングとOJTは、新入社員を育成・サポートするという意味では同じですが、目的や学習内容などに明確な違いがあります。
ここでは、それぞれの違いについて詳しく解説します。
①実施する目的
オンボーディングは、新入社員の組織への順応や定着を軸に、能力の発揮や即戦力化を目的としています。
一方、OJTは所属する部署における業務の必要知識やスキルの習得が主な目的です。
いずれも目的は似ていますが、オンボーディングは仕事と環境への適応を含めて総合的なサポートであるのに対し、OJTは仕事メインのサポートを行う傾向にあります。
②担当者
オンボーディングでは、人事部門や人事開発部門、配属部門の教育担当者が新入社員の育成・サポートを行います。
一方OJTでは、所属部署の上司や先輩社員、チームの教育担当者が新入社員の育成・サポートを行います。
オンボーディングは企業の幅広い人員が新入社員と関わりサポートするのに対し、OJTでは実際に働く現場の社員中心に教育が行われることが主な違いです。
いずれも既存社員とコミュニケーションを取り交流する取り組みであることから、新入社員と既存社員の関係性を築くのに有用です。
③実施期間
オンボーディングは入社後から平均3ヶ月程度実施されますが、その後も定期的なミーティングや面談など継続的なサポートが行われる場合があります。
一方OJTでは、一般的に3ヶ月から1年間行われる傾向にあり、企業の方針や業務内容によって変動します。
オンボーディングは仕事だけではなく、環境への適応や人間関係の構築など、新入社員が企業に馴染めるようにサポートする性質上、長期的に実施されるケースも少なくありません。
OJTは仕事メインの教育手法であるため、業務内容や新入社員の学習状況に応じて実施期間が調整されます。
④学習内容
オンボーディングは、一般常識や社内ルール、経営理念や企業文化、仕事に必要な知識やスキルなど、企業の一員として成長できるように総合的に学習させることが特徴です。
一方OJTでは、実地訓練を行いながら現場により近い知識やスキルの習得が主な学習内容になっています。
いずれも新入社員の育成において有用な教育手法ですが、重点を置く学習内容が異なります。
▼計画的にオンボーディングを行うことができれば良いですが、OJTで放置状態になってしまうことも少なくありません。その点下記で解説しています。
⇒OJT放置のリスクと対処法!新人の退職を防ぎ効果的に育成するコツ!
オンボーディングと集合研修の違い

オンボーディングと従来の集合研修は、新たに入社する社員が、特に初期段階で職務に対応できるようにするオリエンテーションという点で共通の目的を持っています。しかし、その手法や目指す結果には差異が見られます。
オンボーディングプログラムの特徴
オンボーディングとは、新規採用者が組織に適応し、早期に生産活動を開始できるようサポートするプロセスです。
組織の文化、目標、ビジョンを伝えることで新規採用者が役割を理解し、他の従業員との関係を構築し、持続する生産力を発揮できるように助けます。
オンボーディングは数ヶ月にわたる長期間をカバーし、新規採用者が自分の職務に完全に適応するまで続きます。
集合研修の特徴
従来の集合研修は主に特定のスキルや知識の習得を目的としています。
指導者が特定のテーマについて講義を行い、参加者がその情報を吸収し、理解する形式で行われます。
集合研修は一定の時間枠内で行われ、一部の研修は数日以内に完了することがあります。
そのため、オンボーディングと集合研修の主な違いは、前者が組織文化の理解や職務理解を持って組織への定着を目指すのに対し、後者は特定のスキル習得に重きを置く点です。さらに、オンボーディングは長期間にわたる統一した体験を提供し、集合研修は短期間で特定の学習目標を達成することが特徴です。
▼オンボーディングや集合研修を駆使しながら新人を即戦力化していくポイントは下記で解説しています。⇒成果を出す新入社員の育て方とは?即戦力化の前提・ポイントを解説!
オンボーディングのメリット

オンボーディングプログラムを構築することは下記のようなメリットがあります。
(オンボーディングプログラムのメリット)
|
新メンバーの早期戦力化を助ける手段になる
オンボーディングプログラムを展開することで、新メンバーが入社してから一人前としてパフォーマンスを発揮できるようになるまでの教育を効果的に行うことができます。
デジタルコンテンツでプログラムを整えておくことで、学ぶ機会が消費されて終わることがありません。それにより育成の再現性を高めることにもつながります。
オンボーディングプログラムの存在は、新たに採用した戦力が早い段階から期待される役割を発揮し、企業の業績向上に貢献できるようになるきっかけをつくることができます。
新メンバーの職場への定着率を向上させる手段になる
オンボーディングプログラムとして定めた教育を行うことで、新メンバーを1人も見逃さずに面倒を見ることにつながります。
またデジタルコンテンツで学習環境を整えることで必要な人が必要な時に学習できるようになります。
このような学習環境があることは、入社してまだ日の浅いメンバーにとっては不安を払しょくするツールとなります。
オンボーディングプログラムの存在は早期の離職を防止して、職場への定着率を向上させる一手段になります。
効果的なオンボーディングプロセス
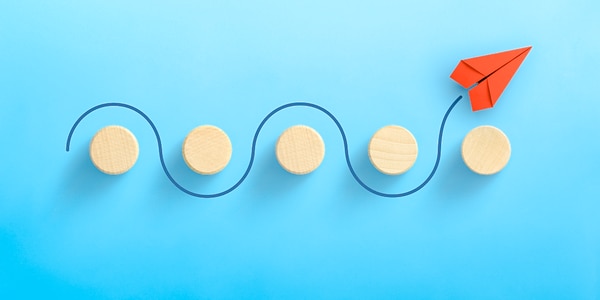
効果的なオンボーディングは、入社前から入社後1年程度までの長期的な視点で設計する必要があります。プロセス全体は大きく以下の3つのフェーズに分けられます。
フェーズ | 内容 |
1.プレオンボーディングフェーズ |
|
2.初期適応フェーズ |
|
3.成長発展フェーズ |
|
各フェーズでは、「受け入れ体制の整備」「教育プログラムの実施」「メンタリング・サポート」「進捗確認とフィードバック」という4つの要素を、状況に応じて適切に組み合わせていきます。
オンボーディングプロセスの設計と実施における5つのポイント

オンボーディングの成功には、計画的な設計と効果的な実施が不可欠です。
個別化されたプランの作成から組織全体での協力体制の構築まで、プログラムを成功に導くための5つの重要なポイントについて、具体的な実施方法とともに解説します。
①個別化されたオンボーディングプランの作成
効果的にオンボーディングを実施するには、画一的なアプローチではなく、個々の新入社員や中途社員の特性や経験に応じた柔軟なプランが必要です。
新卒採用者と中途採用者では必要なサポートが異なり、また同じ中途採用者でも、前職での経験や業界知識によって求められる支援は大きく変わってきます。
個別化されたプランを作成する際の重要な観点は以下です。
|
②OJTとの効果的な連動
オンボーディングは現場でのOJT活動と効果的に連動させ、単なる業務指導にとどまらない、包括的な育成支援の仕組みとして設計する必要があります。OJTトレーナーには、業務知識の伝達役としてだけでなく、組織文化の伝道者としての役割も期待されます。
効果的なOJTとの連動を実現するには、OJTトレーナー自身の育成も重要です。OJTトレーナーに対して以下のようなトレーニングと支援を提供することで、プログラムの質を高めることができます。
|
▼OJTトレーナー研修については以下で詳しく解説しています。
⇒OJTトレーナー研修とは?45%が未実施!内容や実施方法を解説!
③定期的なフィードバックと評価システムの導入
新入社員や中途社員の成長を支援するためには、適切なタイミングで建設的なフィードバックを行うことが不可欠です。フィードバックは、単なる評価ではなく、成長を促進するための対話として位置付ける必要があります。
効果的なフィードバックの実施方法として、以下のような段階的なアプローチが推奨されます。
|
④テクノロジーを活用したオンボーディング手法
デジタル技術の進化により、オンボーディングプロセスをより効率的に実施することが可能になっています。
オンラインラーニングプラットフォームやコミュニケーションツールを活用することで、以下のような効果が期待できます。
|
▼オンボーディングをシステムで効率化するポイントは以下で解説しています。
⇒オンボーディングをシステムで効率化!現場教育と全社教育で選択すべきツールの違いを解説!
⑤協力体制の確立
オンボーディングの成功には、人事部門、配属部署、OJTトレーナー、そして経営層を含めた組織全体の協力が不可欠です。
各関係者の役割と責任を明確にし、定期的な情報共有と調整の場を設けることで、一貫性のあるサポート体制を構築することができます。
特に重要となる連携ポイントは以下です。
|
▼オンボーディングのプロセスについては下記で詳しく解説しています。
⇒オンボーディングの流れと実施目的を徹底解説!効果的なプロセスを紹介
オンボーディングに役立つ2つの要素

ここでは、オンボーディングに役立つ要素を2つ紹介します。
①eラーニング
eラーニングは、オンボーディングに役立つ要素の1つです。
eラーニングを利用する際は、学習コンテンツの配信だけではなく、学習者がアウトプットできる機能が備わったものを選ぶことをおすすめします。
学習プラットフォームの『UMU』であれば、学習コンテンツの配信に加え、学習者同士または指導者と意見交換やフィードバックができる機能が備わっています。
集合研修にありがちな一方通行の学習ではなく、学習内容に対する疑問や質問などの相談ができるため、新入社員の知識・スキルの定着に有用です。
②LMS(学習管理システム)
LMS(学習管理システム)は学習コンテンツの配信に加え、学習者一人ひとりの進捗状況や成績などの管理ができるシステムです。
LMSを選ぶ際は、学習成果が見える化できるものを選ぶことをおすすめします。受講履歴や学習成果のデータは、育成方針の策定や学習コンテンツの最適化に有用です。
『UMU』であれば学習成果の見える化はもちろん、実際の業務を想定した学習や反転学習を取り入れた研修運営ができます。
入社時に学習しておいてほしいことをUMU上にまとめておくことで、より効率的な初期教育の実現が可能です。
デジタルツールを活用したオンボーディング事例

デジタルツールを活用しオンボーディングを効果的に展開した事例を紹介します。
社員数:100名以上
事業:土木建築工事、建設工事の設計と監理
課題
技術教育に十分な時間を割けない
テラン社員が現場作業に追われ、若手社員の技術教育を十分にできていないという課題がありました。また、時間だけでなく、人員にも余裕がないため、本来教えるべき技術やノウハウが現場で伝達できていないという事態に陥っていました。
OJT格差と離職率が上昇
現場のOJTは主にベテラン社員が担当していましたが、人によって言うことが違う、厳しい口調の上司が多いなど、 OJT格差がありました。
その結果、若手社員の離職率が高くなり、新入社員の採用に悪影響が出ました。
取り組みの詳細
全社プロジェクトの立ち上げ
課題解決のため、人を介さず業務知識が学べるコンテンツの配信環境を構築するプロジェクトを立ち上げました。まずは各現場で「わが社の新人に必要な学習内容は何か」という観点で棚卸しを行いました。このプロジェクトの初期は、中堅社員をコンテンツ作成作業の中心に据えました。
全社員アンケートを実施
現場所長や各部署の社員を対象とした「現場に配属になった際に覚えてほしい事」アンケートを実施しました。そこで集まった声を基にし、業務フローと照らし合わせながら、必要なコンテンツリストをブラッシュアップしました。
コンテンツ作成のサポート体制を強化
中堅社員の目線でコンテンツ作成を行った結果、自身が新入社員だった頃の感覚を忘れていることもあり、どのようなポイントを伝えれば新入社員にとって分かりやすいかという観点が抜けた内容になっていました。また、コンテンツ一つ一つの情報量が多い事や、自身が普段当たり前のように行っている業務を、コンテンツに落とし込むことができないという課題が浮上しました。
そこで具体的な作業に関するコンテンツの作成を若手社員が担当するように切り替えました。また、各部に配置したアシスタントによる動画撮影・編集のバックアップなどのコンテンツ作成サポートの強化を行いました。
取組後の成果
若手社員の知識習得レベルの底上げ
若手社員が中心となり、自身が新入社員だった頃の目線を思い出しながらコンテンツ作成を行い、2年間で600個が完成しました。これにより、初めて業務を覚える新入社員にとっても分かりやすく、必要な情報が十分に揃った学習環境を提供することができました。
また、マイクロラーニングの考え方に基づき、全ての動画コンテンツの長さを5分以内収めました。これによって、隙間時間に効果的な学習をすることが可能になりました。
その結果、新入社員の知識習得レベルの底上げにつながりました。
OJT格差の是正とコミュニケーションの活性化
コンテンツを活用した教育によって社員の学習の機会が標準化されたことで、OJT格差が縮小しました。また、業務内容については新入社員と若手社員がベテラン社員に習い、現場で活用するスマートフォンやタブレットなどについては上司が新入社員と若手社員から学ぶという動きも出てくるようになりました。
この動きは、ベテラン社員と新入社員、若手社員のコミュニケーションの活性化にもつながっています。
入社希望者の増加
UMUを導入したことが、県内の入社希望者数の増加につながりました。
新卒の採用説明会やメディアの取材において、 UMUを使った取り組みの紹介をすることで教育体制の良さをアピールすることができ、県内の学生が選ぶ建設業知名度ランキング1位を獲得し、学生たちから選ばれる企業になっています。
まとめ
この記事では、オンボーディングとOJTについて以下の内容で解説しました。
- オンボーディングとは
- OJTとは
- オンボーディングとOJTの4つの違い
- オンボーディングと従来の集合研修の違い
- ンボーディングに役立つ2つの要素
- デジタルツールを活用したオンボーディング事例
オンボーディングとOJTは、新入社員を育成・サポートする観点では共通点がありますが、実施目的や学習内容は異なります。
オンボーディングは仕事や環境を含めた新入社員の順応を目的としているのに対して、OJTは仕事にいち早くなれて即戦力化に重点を置いています。
また、オンボーディングと従来の集合研修にも違いがあります。
新入社員の育成においてはどちらも有用な教育手法ですが、早期離職の防止や人間関係の構築を重視するのであればオンボーディングがおすすめです。
『LDcube』では、AI技術を搭載した学習プラットフォーム『UMU』を提供しています。
UMUには「学習の科学」の要素が取り入れられており、学んだことを成果やパフォーマンスにつなげるための最適な機能が充実しています。
実際にUMUを運用している経験値を踏まえ、企業における効果的な運用とパフォーマンス向上をサポートします。
事例のようにUMUを導入したオンボーディングの展開により、メンバーのエンゲージメントを高めることができ、採用においても入社希望者が増加するという結果が得られています。
これはUMUの導入により、社内の人材育成プロセスが改善されたことを示しています。
このようにデジタルツールを活用したオンボーディングプログラムの構築・展開は会社全体の成功につながる施策として注目くされています。
どのようなことが実現できるのかなどについて、無料のデモ体験会なども行っています。お気軽にお問い合わせください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。