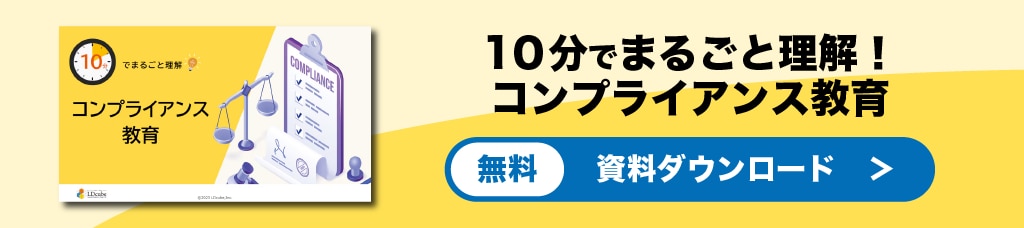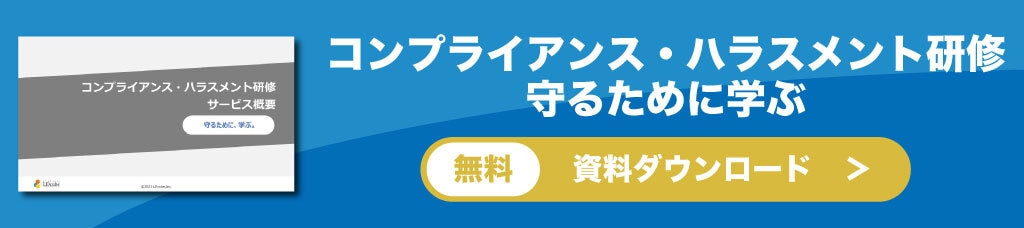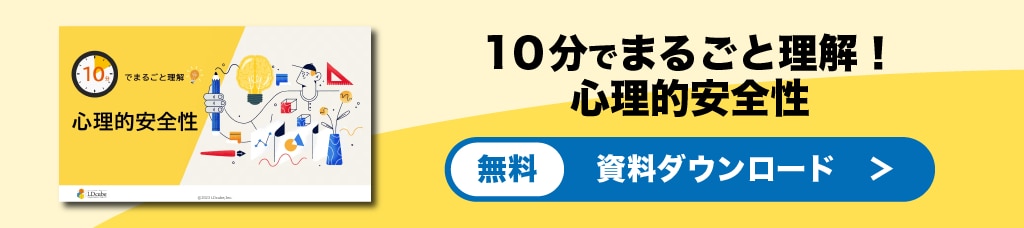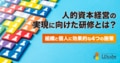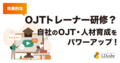コンプライアンス研修で不祥事防止!?テーマ・ネタ切れを乗り越えるアイデア例を紹介!
企業においてコンプライアンスを遵守することは、単なる法令順守ではなく、信頼と企業価値を高めるために不可欠な要素です。しかし、コンプライアンス研修は時に退屈で難解に感じられ、社員の関心を引きつけることが難しい場合があります。
では、どうすればコンプライアンス研修を効果的かつ興味深いものにすることができるのでしょうか?
まず、多くの企業が直面するコンプライアンス研修の一般的な課題を考えてみましょう。多くの場合、法的な用語や規則が多く含まれているため、社員は内容が難解で理解しづらいと感じます。また、単調な説明が続くと興味を失いやすく、重要なポイントが伝わらないことも少なくありません。このような状況では、研修の目的であるコンプライアンス意識の向上や実践には繋がりにくいのが現状です。
本記事では、コンプライアンス研修を魅力的かつ効果的にするための具体的なネタやアイデアを紹介します。この記事で紹介するアイデアを取り入れることで、社員の関心を引きつけつつ、コンプライアンスの重要性をしっかりと伝えることができます。
また、新たな学習形態であるコホート型学習についても詳細に解説していきます。研修をさまざまな工夫をして展開することで、コンプライアンス研修が単なる法令の暗記から、実践的で関心の高い学びへと変わります。
重要なのは、参加者が自分の行動にどう影響を与えるかを理解し、積極的に学ぶ姿勢を持つことです。企業の信頼と価値を守るために、コンプライアンス研修は欠かせません。
この研修を効果的かつ魅力的にするためのネタを取り入れて、社員全員がコンプライアンスの重要性を深く理解し、実践できる環境を作り上げてみませんか?その結果、企業全体の健全な成長が見込めるでしょう。
▼コンプライアンス特集ページを作成しました。ハラスメントとの違いや種類、学習方法まで体系的に解説しています。 |
▼ コンプライアンスについてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。
▼コンプライアンス教育についてまとめておきました。施策検討の材料にお役立てください。
目次[非表示]
コンプライアンス研修のネタのアイデア

(コンプライアンス研修のネタ)
|
社内事例を活用する
コンプライアンス研修の内容は、一般的なルールや法令だけではなく、社内の具体的な事例を取り入れることでリアリティを増すことが可能です。
過去の失敗例や成功例、そしてその原因や結果を共有することで、参加者は抽象的なルールだけではなく、その具体的な適用を理解することができます。
社内で実際に発生したコンプライアンス違反があれば、それをどのように解決したのか、どのような教訓を得たのか、どのような対策を講じているのかなど、具体的なエピソードとともに共有します。
身近な事例であるとともに、不正に対し適切に対応した事例は、今後の対処法を学ぶ良い機会となります。
また、クリーンな業績を上げた部署の事例を用いて、コンプライアンスを徹底する事の重要性を伝えることも有効です。
外部の事例を活用する
社内事例だけでなく、外部の事例も研修のネタとして効果的です。
特に他社の事件事例などは、参加者の関心を引きつけるとともに、自社が同じような状況に直面したときの対応を考える好機となります。
事例をまとめてケースを作成し教材とすると良いでしょう。
他社の失敗例について深掘りし、それがなぜ起こったのか、どのような結果につながったのか、自社が同じ問題に直面した場合どう対応すべきかなどの討論することで、さらなる理解を促進できます。
また、良いコンプライアンスを実現している企業の事例を紹介することで、成功の道筋を示し、参加者のモチベーションを高めることもできます。
社会的な情勢を取り入れる
社会的な情勢やトレンドを研修に取り入れることで、新鮮なネタを提供することができます。
最近では行き過ぎた成果志向やパワハラ環境によるコンプライアンス問題が浮上しています。
このような社会的なトレンドを取り入れることで、現実感を持ってコンプライアンスを学ぶことができます。
新聞やニュースで報道される最新の情報を時事ネタとして研修テーマにすることでリアリティを出すことができます。
また、それらのニュースがもたらす新しい社会状況やビジネス環境を前提としたディスカッションを行うことで、現実に即したコンプライアンスへの理解を深めることができます。
実践的なネタを考える
コンプライアンスは理論だけではなく、実践に基づいた学びが重要です。
具体的な実践的なシナリオを提供し、どのように行動すべきかディスカッションを行うことで、含蓄のある研修になります。
リアルな問題解決の場として、研修を位置づけることが可能です。
シミュレーションやショートケース実習を加えることで、スキルと理論のバランスを取ることができます。
参加者が具体的な状況や問題に直面したときに、どのように対応すべきかなどを想像しながら学ぶことで、具象的な理解を深めることができます。
受講者の関心のある事件や事例を取り入れる
研修は常に進化し続けるべきものです。参加者からのフィードバックを収集し、それを次回のネタづくりに反映させることで、研修の質を高めつつ、ネタ切れ感を解消することができます。
具体的には、研修の終了時にアンケートを収集したり、定期的に意見を募ったりするなどして、参加者の声を直接拾うことが重要です。
参加者が興味のある事例や世の中で起きている事件などを題材として取り上げることで、興味関心を持ってもらえることもあります。
受講者の関心ある題材を取り上げることで、より効果的で興味深いものにしていくことができます。
コンプライアンス研修のネタ切れ感に悩む方は、社内外の事例活用、社会的情勢に目を配る、実践的なシナリオ提供、そして積極的なフィードバック収集を試すと良いでしょう。
また、インプットだけでなく、ショートケースやクイズなどを活用し、具体的に取るべき行動がイメージできるようにしておくことも重要です。
新鮮なネタでコンプライアンス研修を充実させ、社員一人一人が日々の業務でコンプライアンスを意識できる環境をつくっていきましょう。
そもそもコンプライアンス研修とは?

そもそもコンプライアンス研修とは、企業の従業員に対して実施される教育・研修の一つで、法令遵守や倫理規範の理解を深め、不適切な行動を取らないよう指導するものです。
具体的には、労働法規、業界固有の法規などの法律、企業倫理、セクハラやパワハラなどの防止、情報管理などについて学びます。
研修の目的は従業員一人一人が正しい判断と行動をすることであり、それによって企業が法令違反から自身を守ると同時に、信用と評価を維持・向上させることです。
新入社員から管理職、経営者まで全員が正しい認識をもっておくことが重要です。
会社の規模や取り組むべき課題に応じて、研修の内容や方法はさまざまあります。
コンプライアンス研修をしても不祥事が起きてしまう理由

|
研修の内容ややり方のミスマッチ
研修内容が難解であり、または社員が単に受け身で参加しているため、学んだことを自分の行動に生かせていない可能性があります。
また、1度だけ研修を受けただけでは、その内容を忘れてしまうことがあります。
定期的な研修やフォローアップが必要です。研修は継続的に行っていたとしても企業が研修を行うだけで、その他施策の実行やフォローアップがない場合もあります。
社員もそれを感じ取り、「本気で取り組んでいない」と思われてしまうこともあります。
企業文化がコンプライアンス意識を育てていない
上層部の行動や意識が満足に反映されていない、または社内で不正行為が見逃されるなど、コンプライアンス違反が許容されている文化が存在する場合、研修だけでは解決できません。社員の行動への影響は研修よりも上司や幹部クラスの言動の方が大きいのです。
昨今の不祥事の多くは正しいかどうか判断できないから起きているのではなく、組織文化が不祥事を生んでいるケースが多いです。
心理的安全性を提唱したエイミー・C・エドモンドソン博士によると、「失敗は自分で作りだしている。
心理的安全がなければほぼ必然的に間違いが発生します。
間違いが発生する要因は一つではなく、高い成果基準と低い心理的安全性の組み合わせが必然的に間違いを生むのです」と警鐘をならしています。
つまり、高い成果基準を求めながら、心理的安全性が低い組織では不祥事のリスクが高いと言えます。
これは非常に大切なポイントです。皆さんの組織は大丈夫でしょうか?
心理的安全性を高め、何かあった際には気軽に上司や同僚や専門窓口に相談できる文化を醸成していくことが求められています。
▼心理的安全性を高める研修については下記で解説しています。合わせてご覧ください。
⇒心理的安全性の研修はどう企画する?具体的な研修内容や設計のポイント
▼心理的安全性についての詳細はこちらをご覧ください。
コンプライアンス研修の効果を高める新たな学習法

これまでにない新しい教育形態として、eラーニングや反転学習が注目されています。
その進化形とも言える「コホート型学習」について解説します。
従来の自己学習の課題
従来のeラーニングや反転学習の形式では、学習意欲の維持や、自己学習の継続が課題とされてきました。
自分だけで学習を進めるため、どうしてもモチベーションが下がりやすいものです。
特に期間を決めずに自由に学習できる形式では、つい先送りにしてしまうという人も多いのではないでしょうか。
加えて学習を進める上で質問などがある場合に、すぐに質問できる相手がいないというのも大きな悩みでした。
自己学習の最中に出てくる疑問点やわからない箇所について、タイムリーに解決するのが難しいのが現状です。
コホート型学習とは?
そんな問題点を克服するための新たな学習スタイルが「コホート型学習」です。
この学習方法は、一定の期間、同じテーマについて学ぶグループを「コホート(仲間・チームメイトという意味)」と呼び、同じコースを一緒に進めていくスタイルのことを指します。
Web会議やチャットツールを利用してオンラインで交流しながら、講義を受けたり課題をこなしたりといった具体的な形を取ることが多いです。
それぞれの学習者が同じテーマを学ぶことで、学習内容についての深い理解や新たな視点を得ることが可能となります。
コホート型学習のメリット
最大のメリットは、同じコースを一緒に学習することで、自己学習の孤独感やモチベーションの低下を防ぐことが可能となる点です。
一緒に学ぶことで、お互いに切磋琢磨しながら学んでいくことができます。
さらに、学ぶ仲間がいることで、わからない箇所や疑問点を共有することができます。
互いに知識を深めたり、新たな視点を共有したりと、単独の学習では得られない多角的な理解が得られます。
また、講師からもタイムリーにフィードバックをもらうことができる点もメリットと言えます。
質問や疑問を直接講師に投げかけてすぐに解決できるため、学習の進行が滞ることなく、確実にスキルや知識を身につけていくことが可能となります。
▼ 展開にはライブファシリテーターが必要です。ライブファシリテーターについてはこちらをご覧ください。
コホート型学習のデメリット
一方で、デメリットがあります。
一つは、一定期間のスケジュールに沿って進められるため、自身のペースで自由に学習を進めることが難しい点です。あらかじめ設定されたスケジュールに合わせなければならず、そのペースについていくことが求められます。
また、参加者間のスキルレベルがバラバラである場合、上級者と初心者が混在していると、初心者がついていけない、あるいは上級者にとってはペースが遅いと感じることがあるでしょう。
そのため、この点については事前に参加者のスキルレベルを確認して設定する注意が必要です。
さらに、オンラインでのコミュニケーションに慣れていないと、コミュニケーション自体がストレスに感じることもあります。
▼ 効果的な学習設計のためには柔軟性が重要です。構造化し過ぎると学習疲労を招きます。
学習疲労についてはこちらをご覧ください。
コホート型学習の活用
コホート型学習は、継続的な学習の支えとなり、学習者同士のネットワーキングの場ともなるため、新たな学習方法として大いに注目されています。
自己学習の課題を克服し、学びを深め、新たな視点を得るためには、ぜひ1度試してみてはいかがでしょうか。
一緒に学習する仲間がいることでモチベーションアップにつながり、深い学びを得ることができます。
一定のスケジュールに沿って進めるための自由度は失われるものの、それを補うだけの価値があると言えるでしょう。
新しい学び方に挑戦することで、さらなる成長を期待できます。
コンプライアンス研修に活用できるコンテンツ

心理的安全性がつくる恐れのない職場コース①②
【コース概要】
組織やチームにとって重要な内容であるにもかかわらず、自分の考えを言わず、質問を控え、黙っていたことが何度ありますか?
従業員が安心して発言できるようにするには、心理的に安全な環境を整える必要があります。本コースでは、対人関係の不安がいかに組織をむしばむか、そして、その乗り越え方をさまざまな事例を通じて学習します。
【講師略歴】
エイミー・C・エドモンドソン
エイミー・C・エドモンドソンは、ハーバード・ビジネススクールのノバルティス記念講 座教授として、リーダーシップとマネジメントを教えています。
2年に1度発表される経営思想家の世界的なランキング、Thinkers50では、2011年、2013年、 2015年、2017年に選出され、2017年にはTalent Awardも受賞しました。
リーダーシップ、チーミング、組織学習に関する教育や執筆に従事し、ハーバード・ビジネス・レビューやカリフォルニア・マネジメント・レビューなどの経営誌や一流 の学術誌に寄稿しています。
心理的安全性に関する先駆的な研究で最もよく知られており、過去15年間に わたって経営、医療、教育分野のさまざまな学術研究に貢献してきました。
『恐れのない組織――「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす』(英治出版)や『チームが機能するとはどういうことか――「学習力」と「実行力」を高める実践アプローチ』(英治出版)などの著書があります。
更なる高みを目指すコーチングコース①②③
【コース概要】
キャリアアップの段階で誰しも経験するのが停滞期です。伸び悩んでしまうのです。
なぜなら、これまで成功に導いてくれたやり方が道を阻むものになっているからです。
どうすれば自分の道を阻んでいるものを見極めることができるでしょうか?
本コースでは、すでに高いレベルにいる人のどこに問題があるのかを学習します。リーダーシップの弱点を取り除き、前進するための手引きとなるでしょう。
【講師略歴】
マーシャル・ゴールドスミス
マーシャル・ゴールドスミス博士は、世界トップクラスのエグゼクティブ・トレーナー、コーチ、作家です。
博士はトップリーダーに結果を出させる卓越した手腕によって、150人以上のCEOとその経営陣が職場の変化に対応できるよう支援してきました。
成功した人々が自身と部下のために前向きで持続的な行動改善を実現できるよう手助けすることが、博士の使命です。
博士は40年にわたる経験を生かし、トップクラスのCEOや経営幹部が信念や行動の制約を克服し、さらに成功できるようサポートします。
また、ニューヨーク・タイムズのベストセラーリスト入りした『トリガー 自分を変えるコーチングの極意』『コーチングの神様が教える「前向き思考」の見つけ方』『コーチングの神様が教える「できる人」の法則』の3冊をはじめ、32の言語に翻訳された40冊の本も執筆/編集しています。
▼ビジネスにおけるコーチングについての詳細はこちらをご覧ください。
まとめ:コンプライアンス研修に使えるネタ
コンプライアンス研修で不祥事防止!ネタ切れを乗り越えるアイデアを紹介! について解説してきました。
コンプライアンス研修は企業不祥事を未然に防ぐためにとても重要な取り組みです。継続的に実施する必要もあります。
しかしながら研修を行っていても不祥事が起きているという現実もあります。
それは研修や制度の問題ではなく、企業文化の問題も大きなものです。
不祥事を起こさない企業文化を醸成していくためには、これまでのコンプライアンス研修のみならず、組織内の心理的安全性を高めるアプローチやトップダウンではない、現場の意見を引き出すコーチングアプローチも重要です。
そのようなテーマを題材にしながら、インプット学習のみならず、グループでディスカッションしながら学習を進めるコホート型学習で、文化醸成のきっかけを作っていきましょう。
LDcubeでは、一般的なコンプライアンス・ハラスメントのeラーニングのみならず、世界レベルのMBA教授によるマイクロラーニングなどのサービスを提供しています。
無料のデモIDの発行も行っています。お気軽にお問い合わせください。
▼関連資料は以下よりダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。