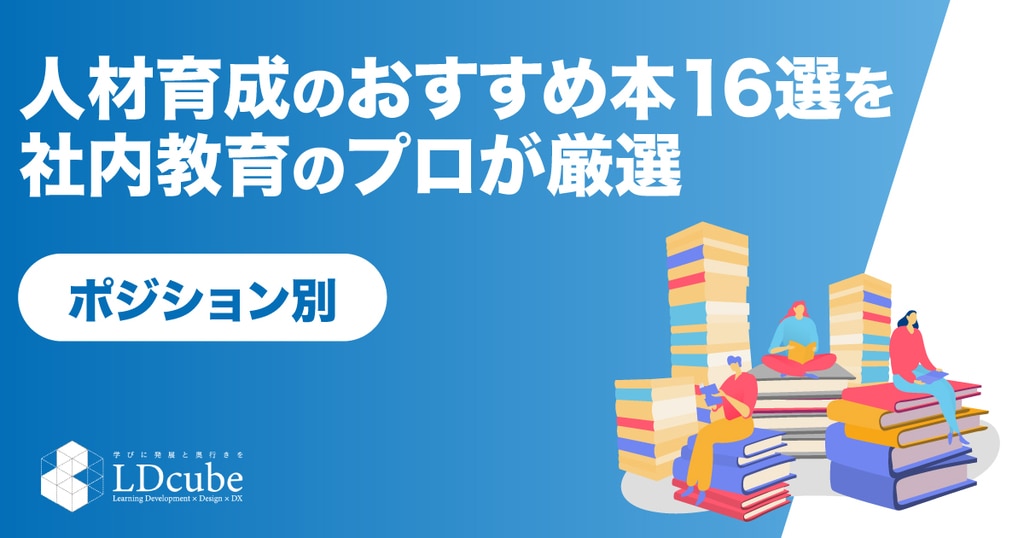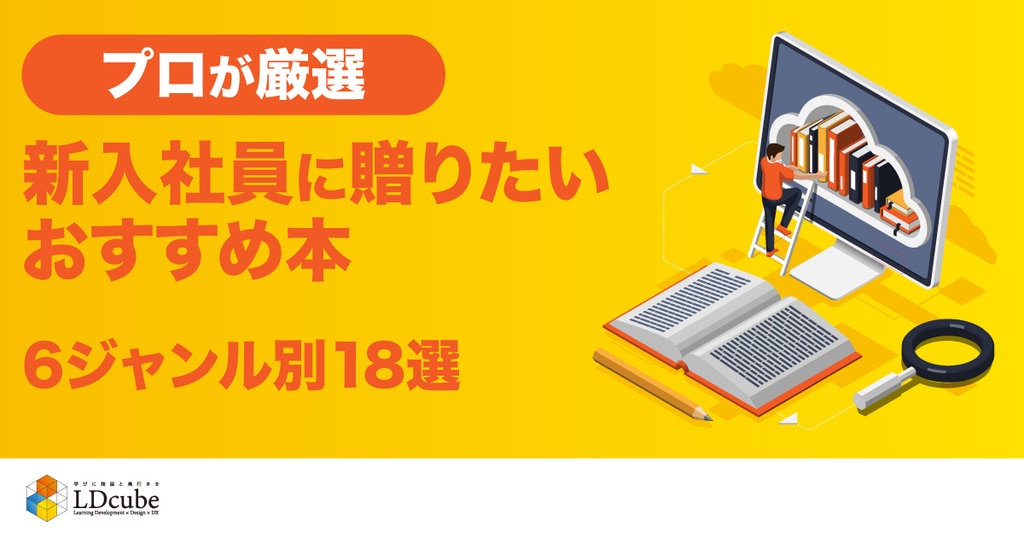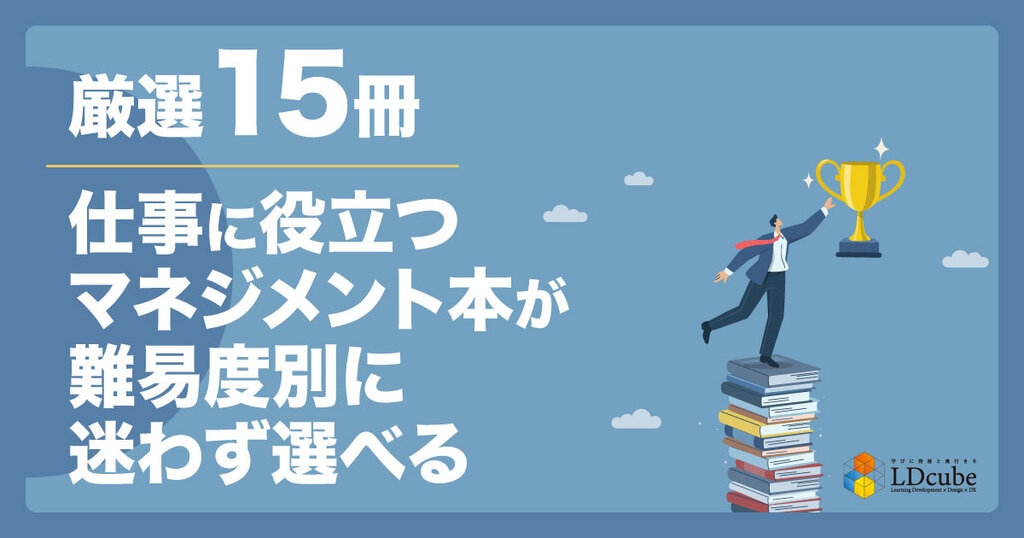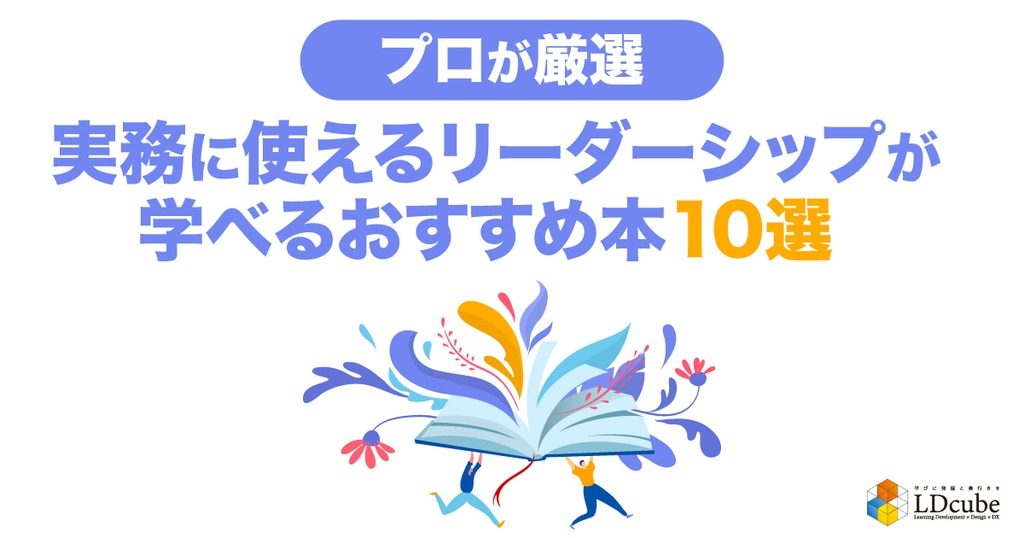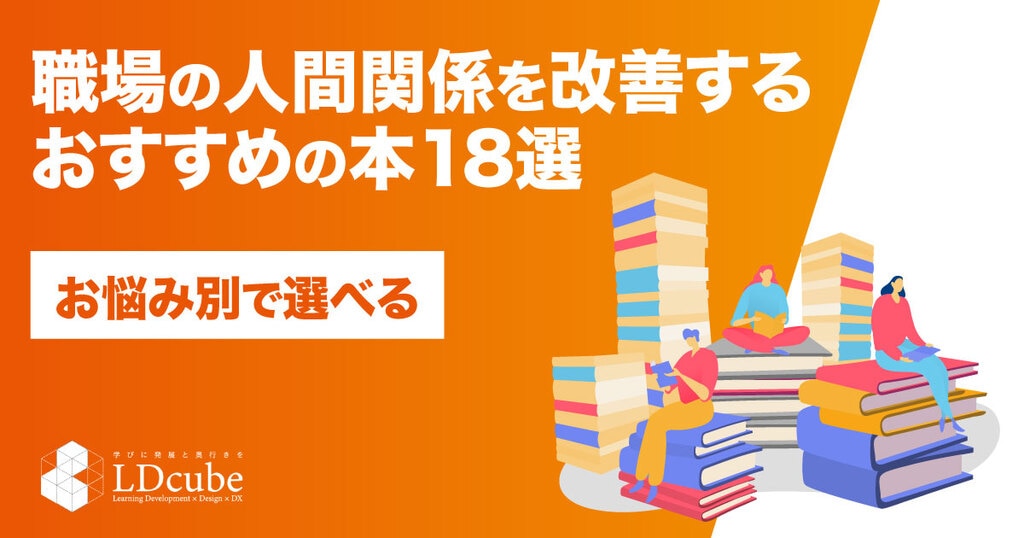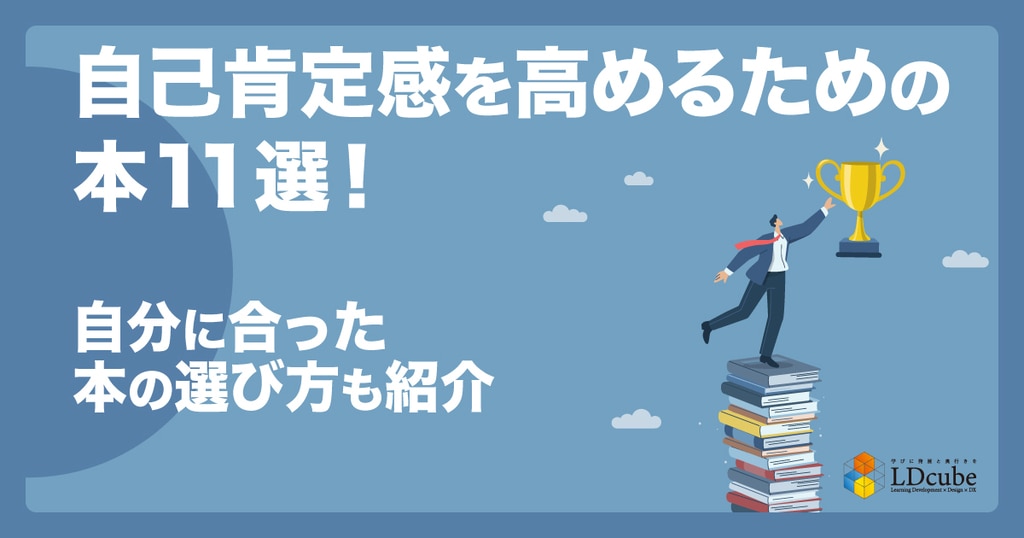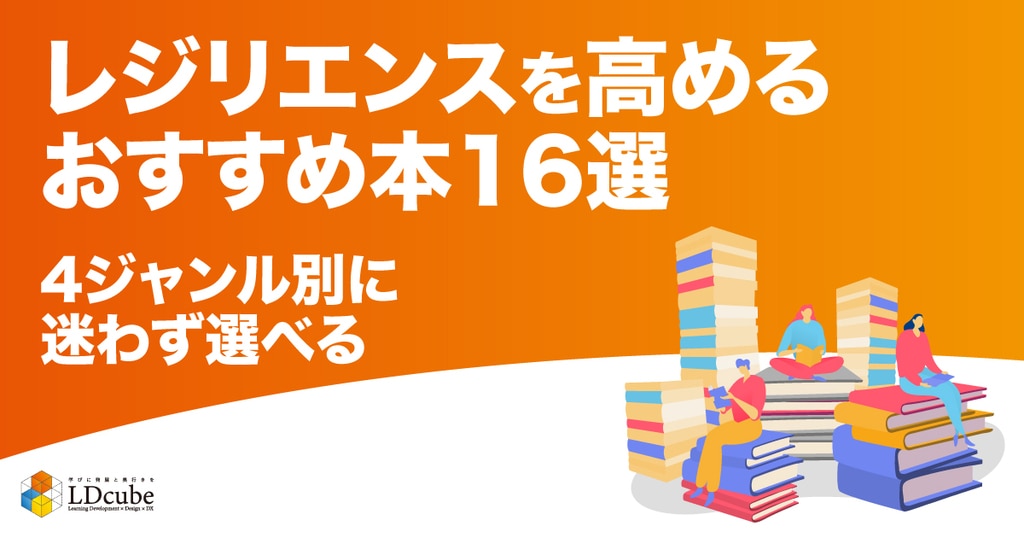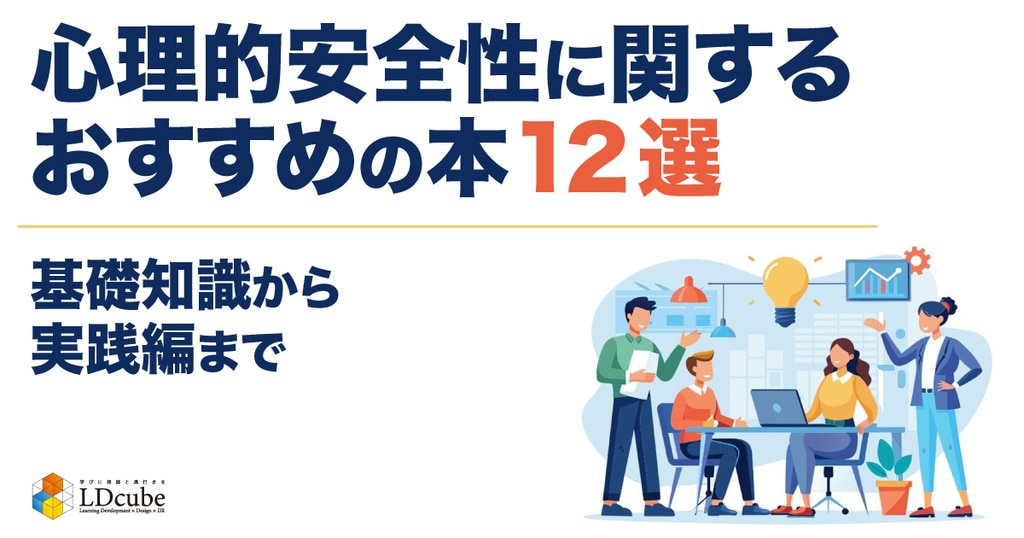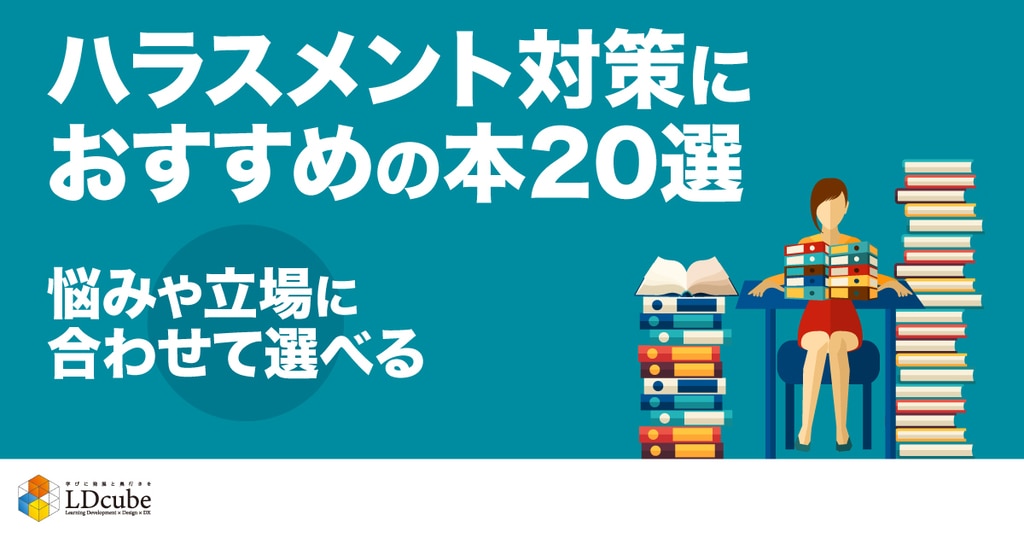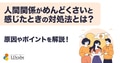会社内での読書会(対話会)のやり方とは?展開ステップやコツを解説!
「本を読むだけではなく、対話を通じて深い学びを得る」という読書会の魅力をご存じでしょうか。読書会は単なる読書の延長ではなく、組織の活性化やチームビルディング、人材育成にも効果的なツールとして有効です。
しかし、「読書会を始めたいけれど、具体的なやり方が分からない」「一度試したけれど、うまく続かなかった」という声もよく聞かれます。
読書会のやり方は、目的や参加者によって大きく変わります。対話型、持ち寄り型、課題図書型など、形式もさまざまです。また、オンラインとオフラインでそれぞれに適した進め方があります。特に重要なのは、単に本の内容を確認するだけでなく、参加者同士の対話を通じて新たな視点や気付きを得られる環境をつくることです。
本記事では、読書会を成功させるための5つのステップを中心に、目的別の運営ポイントや失敗しないためのコツを詳しく解説します。人材育成担当者の方はもちろん、チームリーダーやコミュニティー運営者、読書愛好家の方まで、あらゆる場面で活用できる読書会のやり方をご紹介します。読書の価値を高め、人と人をつなぐ場をつくるための実践ガイドとして、ぜひ参考にしてください。
▼人材育成に関連したおすすめ書籍は下記で詳しく解説しています。
目次[非表示]
読書・対話会はやり方次第で効果抜群!

読書会は単に本の感想を共有する場ではありません。適切なやり方で運営することで、組織や個人に大きな効果をもたらします。本記事では読書・対話会の効果的なやり方を詳しく解説します。
実務レベルの底上げを図れる
読書・対話会は参加者の実務スキルを向上させる効果的な手段です。業務に関連した書籍を選定し、その内容について深く対話することで、知識を実践に結びつける思考が生まれます。
単に本を読むだけでなく、その内容について他者と対話することで、新たな視点や気付きが生まれ、業務への応用力が高まります。
社内のコミュニケーション活性化の一助となる
リモートワークが増えた現代では、偶発的な交流の機会が減少しています。読書・対話会は共通のテーマについて語り合う「待ち合わせ場所」として機能し、部署や役職を超えたコミュニケーションを促進します。
参加者同士が本の内容を通じて自分の考えや経験を共有することで、お互いの価値観や考え方への理解が深まり、社内のコミュニケーションが活性化します。
学ぶ習慣づくりにできる
定期的な読書・対話会の開催は、参加者の学習習慣の形成に役立ちます。「次回までに読んでおく」という適度な締め切りが生まれることで、忙しい日常の中でも読書の時間を確保するきっかけになります。
また、他の参加者との対話を通じて得られる新たな気付きや視点は、学ぶ楽しさを実感させ、自発的な学習意欲を高める効果があります。
人材育成における読書・対話会とは?

読書・対話会とは、同じ本を読んだ参加者が集まり、その内容について対話を行う場です。単なる感想の共有にとどまらず、本の内容から得た気付きや学びを深め、実践につなげることを目指します。
読書・対話会が持つ3つの効果と可能性
読書・対話会には以下の3つの主要な効果があります。
|
これらの効果により、単独での読書よりも深い理解と実践への応用が可能になります。
さらに、継続的な開催によって組織内の学習文化の醸成や、共通言語の形成にもつながる可能性を秘めています。
読書・対話会の目的
読書・対話会の目的は参加者や組織のニーズによってさまざまです。一般的には以下のような目的が考えられます。
|
目的を明確にすることで、適切な書籍選定や運営方法を決定することができます。読書・対話会を始める際には、まずこの目的設定を丁寧に行うことが成功の鍵となります。
人材育成に読書・対話会が効果的な理由
読書・対話会が人材育成に効果的な理由は主に以下の点にあります。
|
これらの要素が組み合わさることで、読書・対話会は、単なる知識習得の場にとどまらず、実践的なスキルや思考力を養う上で、効果的な人材育成の場となります。
読書・対話会のやり方|展開ステップ

読書・対話会を効果的に実施するためには、準備から実施、振り返りまでの一連のステップを押さえることが重要です。以下に具体的な展開ステップを紹介します。
ステップ1:目的を明確にする
読書・対話会を始める際は、まず「なぜ読書・対話会を行うのか」という目的を明確にしましょう。目的によって選ぶ本や運営方法が変わってきます。
例えば、「特定の業務スキルを向上させたい」「チームビルディングを促進したい」「学習する組織文化をつくりたい」など、具体的な目的を設定することで、その後の進め方が明確になります。
目的が決まったら、それを参加者と共有し、全員が同じ方向を向いて参加できるようにすることが大切です。この共通理解があることで、対話の質も高まります。
ステップ2:テーマ・日程を決め、参加者を募る
目的に沿ったテーマや書籍を選定し、開催日程を決定します。日程は定例化することで参加者の予定が立てやすくなり、継続性が高まります。例えば「毎月第2火曜日の17時から」など、固定の日時を設定するとよいでしょう。
参加者を募る際は、強制参加ではなく自発的な参加を促すことが重要です。興味関心のある人が集まることで、対話の質が高まります。また、部署や役職を超えた多様なメンバーが参加することで、さまざまな視点からの意見が生まれやすくなります。
ステップ3:読書範囲を決めて事前に読んでおく
1回あたりの読書範囲を適切に設定することが重要です。多すぎると参加者の負担になり、少なすぎると深い対話ができません。弊社で実施している経験値から、1週間ごとに読書・対話会を行う場合、50〜70ページ程度が適切と感じています。参加者の業務の忙しさや本の難易度を考慮して調整しましょう。
参加者には事前に範囲を伝え、読んでおくよう依頼します。読書の際には、印象に残った箇所にマーカーを引いたり、疑問点や気付きをメモしたりしておくと、対話の際に役立ちます。
ステップ4:ブレークアウトで対話する
読書・対話会の中心となるのが対話のセッションです。特に参加者が多い場合は、5〜6人程度の小グループに分けて対話を行うと効果的です。Zoomなどのオンラインツールを使用する場合は、ブレ-クアウトルーム機能を活用しましょう。
対話の際は、全員が発言できるよう配慮することが重要です。最初に1人ずつ簡単な感想を述べる時間を設けることで、全員が声を出し、その後の対話がスムーズになります。
ステップ5:感想や学びを可視化できる場を用意しておく
対話の内容を記録し、可視化することで学びを深め、後から振り返ることができます。チャットやMiro(ミロ)などのオンラインツールを活用し、参加者が気付きや感想を書き込める場を用意しておくと効果的です。
可視化することで、発言が苦手な人も書くことで参加しやすくなり、また対話の流れや全体像が把握しやすくなります。さらに、次回の読書・対話会へのつながりも生まれやすくなります。
ステップ6:振り返りと継続の仕組みを構築する
読書・対話会の最後には振り返りの時間を設け、参加者が学んだことや気付きを共有します。この振り返りが次回への期待につながり、継続的な参加を促進します。
また、1冊を読み終えた際には、全体を通しての振り返り会を行うことも効果的です。読書・対話会の運営方法について参加者からフィードバックを得ることで、次回の改善点が見えてきます。継続のためには、参加者の負担にならない頻度と範囲を設定し、定期的に開催することが重要です。
読書・対話会の効果的なやり方

読書・対話会を効果的に進めるためには、対話の質を高めるためのいくつかのポイントがあります。ここでは具体的なやり方を紹介します。
読んできた範囲について感想や気付き、学びを1人ずつ共有する
読書・対話会の始まりは、参加者全員が読書から得た感想や気付きを共有することから始めます。順番に1人ずつ話す機会を設けることで、全員が発言でき、さまざまな視点が集まります。
この際、「最も印象に残った箇所とその理由」「疑問に思った点」「自分の経験と結びついた部分」などの観点を示しておくと、参加者が話しやすくなります。発言の長さは5分程度を目安にし、全員が平等に発言できるよう配慮しましょう。
他者の感想、気付き、学びを踏まえ感じたことについて対話する
全員の初期の感想共有が終わったら、そこから生まれた共通のテーマや興味深い点について深く対話します。この段階では、「〇〇さんの意見を聞いて思ったこと」「それについて自分はこう考える」といった形で、他者の発言を受けて自分の考えを述べることを促します。
対話を活性化させるために、ファシリテーターは「それはどういう意味ですか?」「具体例はありますか?」「他の方はどう思いますか?」といった質問を投げかけることも効果的です。
自社の業務に生かせることなどについて対話する
理論的な理解だけでなく、実践へのつながりを意識した対話を心掛けましょう。「この考え方を自分たちの業務にどう生かせるか」「明日から実践できることは何か」といった観点で対話することで、学びが実際の行動変容につながります。
具体的な業務課題と結びつけて考えることで、抽象的な内容も自分ごととして捉えられるようになります。参加者それぞれの部署や役割によって異なる視点が生まれ、互いに学び合う機会となります。
知見のあるメンバーからコメントし、学びを深める
可能であれば、テーマに関する知見や経験が豊富なメンバーに参加してもらい、適宜コメントをもらうことで学びがさらに深まります。ただし、専門的な意見が対話を一方通行にしてしまわないよう、注意が必要です。
専門家からのコメントは、対話の最後にまとめて行うか、途中で簡潔に挟む程度にし、参加者主体の対話を損なわないようにします。また、専門的な視点だけでなく、現場での実践経験に基づくアドバイスが特に価値を持ちます。
読書・対話会を成功させるやり方のコツ
読書・対話会を長く継続し、効果を最大化するためのコツを紹介します。これらのポイントを押さえることで、参加者の満足度を高め、継続的な学びの場を創出することができます。
実務に直結したテーマ・書籍を選ぶ
読書・対話会の効果を高めるためには、参加者の実務に直結したテーマや書籍を選ぶことが重要です。「なぜこの本を読むのか」「これを読むことで何が得られるのか」が明確であれば、参加者のモチベーションも高まります。
|
選書の際は、参加者からも候補を募り、多数決で決めるなど、参加意識を高める工夫も効果的です。
さらに、書籍選定には「読みやすさ」と「内容の深さ」のバランスも重要な要素です。あまりに難解な専門書だと読破のハードルが高くなり、逆に内容が薄すぎると対話が深まりません。特に読書会を始めたばかりの段階では、比較的読みやすく、それでいて対話の素材となる問いかけが豊富な書籍を選ぶことをおすすめします。
また、書籍のジャンルにも変化をつけることで、参加者の興味を持続させることができます。例えば、ビジネス書だけでなく、時にはリーダーの自伝や歴史書、小説なども取り入れ、多角的な視点から学べるようにするのも一つの方法です。実務との関連が一見分かりにくい書籍でも、読み終えた後に「この内容をどう業務に生かせるか」という対話テーマを設定することで、意外な気付きが生まれることもあります。
オンラインで定例化し、負担を少なくして実施する
読書・対話会の継続には、参加者の負担を最小限にする工夫が欠かせません。オンライン開催にすることで移動時間が不要となり、場所を問わず参加できるメリットがあります。
|
また、業務時間内に実施できれば理想的ですが、難しい場合は終業直後の時間帯などを活用するとよいでしょう。
オンライン開催の際は、参加のハードルを下げるためのいくつかのポイントがあります。例えば、カメラオンを強制せず、状況に応じて柔軟に対応することで、自宅や通勤途中などさまざまな環境からの参加が可能になります。また、チャット機能を積極的に活用して発言が苦手な方も参加しやすくする工夫も有効です。
ハイブリッド形式(対面とオンラインの併用)の読書会も選択肢の一つですが、実施する場合は対面参加者とオンライン参加者の間に情報格差や発言機会の不均衡が生じないよう注意が必要です。例えば、対面で集まっているグループとオンライン参加者をつなぐ役割の人を設けたり、専用のマイクやスピーカーを用意したりするなど、全員が平等に参加できる環境づくりを心掛けましょう。
少人数で対話できる環境をつくる
対話の質を高めるには、全員が発言できる少人数のグループ構成が効果的です。全体の参加者が多い場合は、4〜6人程度のグループに分けて対話を行いましょう。
|
グループ分けの際は、部署や役職が偏らないよう配慮し、多様な視点が交わる環境をつくることが重要です。
また、グループの構成メンバーを定期的に変えることも検討すべきポイントです。固定メンバーだと関係性が深まる一方で、マンネリ化や特定の人間関係の固定化が起こりやすくなります。定期的にメンバーをシャッフルすることで、新鮮な対話が生まれ、組織全体の相互理解も促進されます。
グループに1人マネジャーやファシリテーターを置く
対話を活性化させ、全員が参加できる環境をつくるためには、各グループにファシリテーターを置くことが効果的です。ファシリテーターの役割は以下の通りです。
|
ファシリテーターは必ずしも上司や専門家である必要はなく、読書テーマについてある程度の知見を持っている人が担当するとよいでしょう。また、役割を持ち回りにすることで、全員がファシリテーションスキルを身に付ける機会にもなります。
効果的なファシリテーションのためには、事前の準備も重要です。ファシリテーター向けの簡単なガイドラインを作成しておくと、初めて役割を担う人でもスムーズに進行できます。例えば、「最初の5分は全員の一言感想、次の20分は印象に残った箇所についての対話、最後の5分は実務への応用について話し合う」といった時間配分の目安や、「沈黙が続いたときの質問例」「対話を深めるための問いかけ例」などを記載しておくとよいでしょう。
また、グループ内の対話の様子を定期的に振り返り、ファシリテーターの役割や進め方について全員で改善点を話し合うことも重要です。これにより、組織に最適なファシリテーション方法が徐々に形成されていきます。
読書・対話会でよくある失敗と解決策

読書・対話会を運営していく中で直面しやすい課題と、その解決策を紹介します。これらの対策を知っておくことで、トラブルを未然に防ぎ、より効果的な読書・対話会を実現できます。
参加者が発言しない問題と解決策
読書・対話会で最も多い課題の一つが、一部の参加者が発言せず、対話が活性化しないことです。この問題に対する解決策は以下の通りです。
|
また、初めのうちは指名することも有効ですが、強制的にならないよう配慮し、「もしよければ」といった声かけを心掛けましょう。
対話が脱線するときの軌道修正テクニック
活発な対話の中で話題が脱線することはよくありますが、あまりに本題から外れると時間が無駄になります。軌道修正には以下のテクニックが有効です。
|
ただし、一見脱線したように見える対話が新たな気付きをもたらすこともあるため、柔軟な判断も必要です。
参加者の温度差を解消するファシリテーション方法
参加者によって準備の度合いや関心の強さに差があると、対話の質が低下する恐れがあります。この温度差を解消するためのファシリテーション方法を紹介します。
|
また、参加の自由度を高め、無理なく続けられる環境を整えることも重要です。
読書・対話会の継続を阻む要因と具体的対策
多くの読書・対話会が途中で立ち消えになる原因と、それを防ぐための対策を紹介します。
|
継続のためには、参加者全員が「この場に参加する価値がある」と実感できることが最も重要です。短期的な効果だけでなく、長期的な学びの場としての意義を共有していきましょう。
読書・対話会 弊社実施事例

ここでは弊社で実際に行っている読書・対話会の事例を紹介します。この事例を参考に、自社に合った形で取り入れていただければ幸いです。
毎週月曜日17:00~18:00で定例開催
弊社では毎週月曜日の夕方、1時間の読書・対話会を定例開催しています。週の始まりに学びの時間を設けることで、その週の業務にも良い影響を与えています。時間帯は就業時間内の最後の1時間とし、業務との両立がしやすいよう配慮しています。
事前に日程を固定することで、参加者は予定を立てやすくなり、継続的な参加が実現しています。また、欠席者が出ても、欠席者に読書自体は行ってもらい、対話会の感想共有フォームへの投稿を行うことで、補っています。曜日・時間固定の定例開催としていることで、安定した開催を確保しています。
実務につながる書籍を選定
弊社の読書・対話会では、以下のような観点で実務につながる書籍を選定しています。
|
選書は対話会の感想を共有するオンラインフォーム上の投稿を確認しながら、参加者の興味関心と業務上求められることのバランスを取りながら決定しています。
1回の読書範囲は50~70ページ程度
参加者の負担を考慮し、1回あたりの読書範囲は50〜70ページ程度に設定しています。本の難易度や内容の濃さによって調整することもありますが、基本的にはこの範囲内で設定しています。
読書範囲は毎回の読書・対話会の中で、次回の範囲を通知し、十分な準備時間を確保しています。また、読む際のポイントや着目してほしい点なども併せて共有することで、対話の質を高める工夫をしています。
Zoomを使ってブレークアウトで対話
全社リモートワークがベースとなっている環境を生かし、Zoomを使ったオンライン開催を基本としています。参加者は、毎回4〜6名ずつのブレークアウトルームに分け、全員が発言できる環境を整えています。
対話後には、オンライン上のフォームに感想を投稿して気付きを可視化し、参加者同士で共有します。さらに、対話のグループを超えた参加者の感想にも触れられるように展開しています。対話での直接的な意見共有と、書き込みの両方の方法を活用することで、学びに奥行きを持たせています。
参加者の声
実際に読書・対話会に参加している社員からは、以下のような声が寄せられています。
|
特に若手社員からは、先輩社員の知見や経験に触れる貴重な機会として高く評価されています。また、管理職からは「チームメンバーの考え方や価値観を知る機会になっている」という声も聞かれます。
まとめ:読書会を人材育成に生かそう
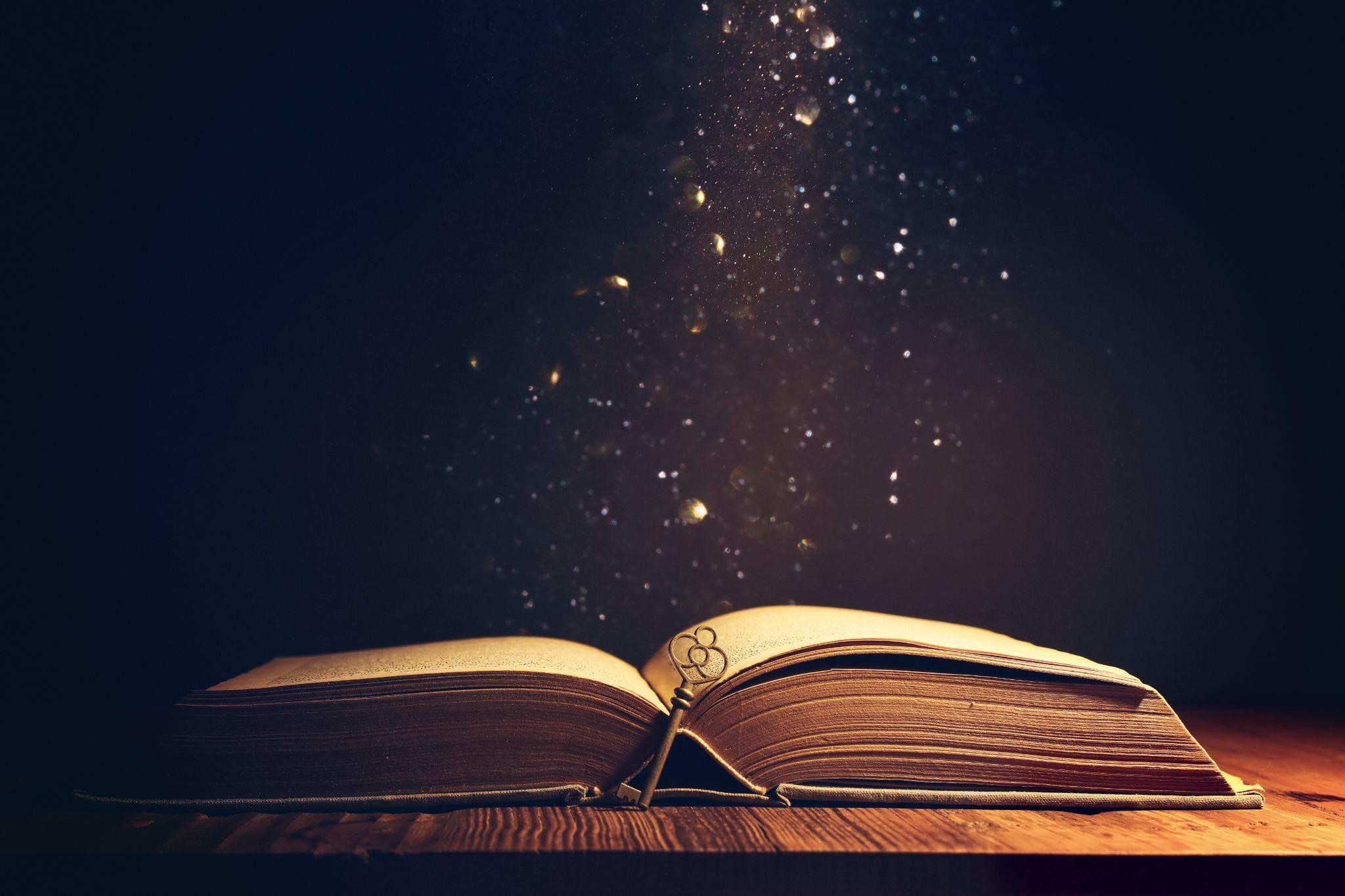
明確な目的設定と、それに沿った書籍選定・運営方法が重要です。全員が発言できる少人数グループ構成や、対話を促進するファシリテーションなど、参加者の主体性を引き出す工夫も必要です。
継続のためには、定例化や負担軽減、成果の可視化などの取り組みが効果的です。振り返りの機会を設け、常に改善しながら進めることで、より効果的な読書・対話会へと発展させられます。
読書・対話会は本の感想共有の場を超え、組織の学習文化を醸成し、コミュニケーションを活性化させる強力なツールです。ぜひ自社の人材育成に役立ててください。
株式会社LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。
人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。
LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。
▼関連記事はこちらから。