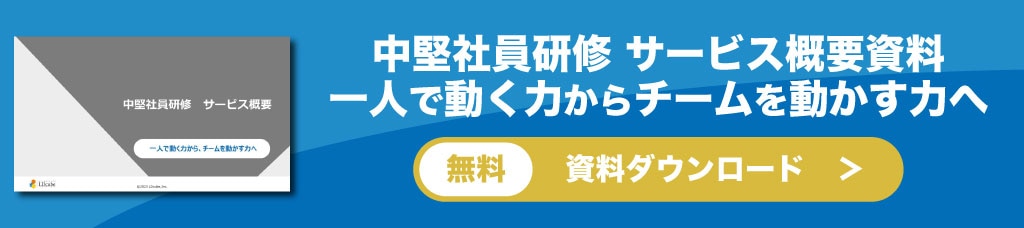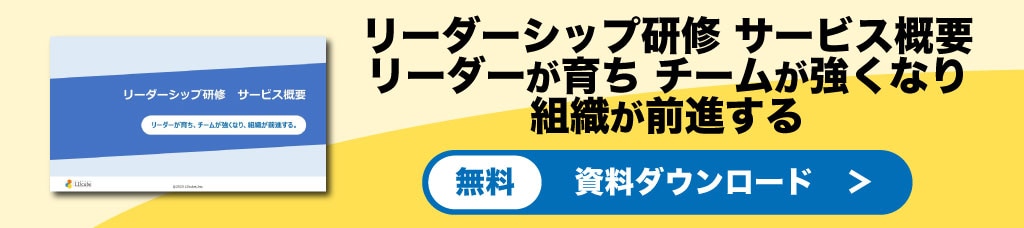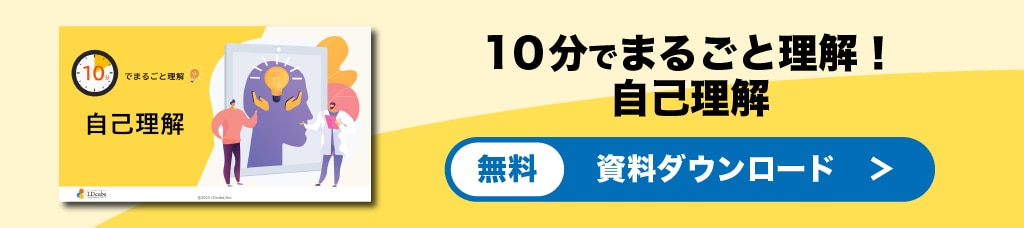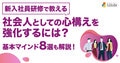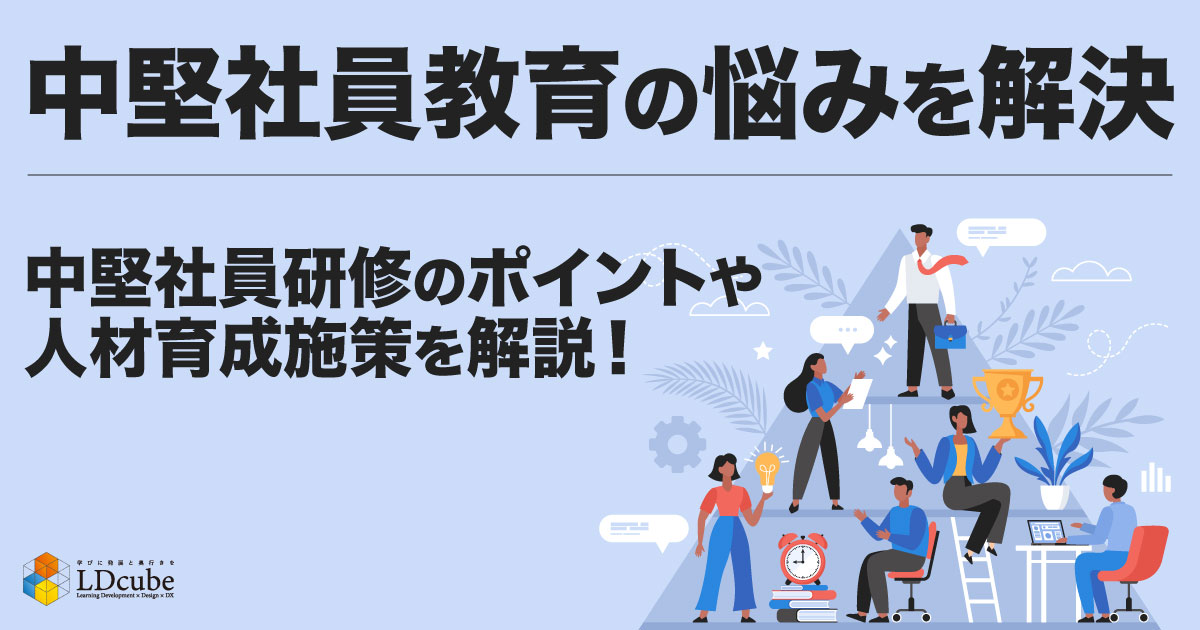
中堅社員教育の悩みを解決!研修のポイントや育成施策を解説!
中堅社員の教育は、企業がさらなる成長を目指す上で欠かせない重要な施策です。
なぜなら、中堅社員は現場のエース的存在であり、現場の実務を遂行させる上で重要な役割を果たしているからです。また、多くの場合は5年~10年程の勤続経験があり、社内の文化や風土も熟知しており、次世代のリーダー候補としての期待も大きい階層です。
しかし、現代の中堅社員教育は一筋縄ではいきません。
従来の中堅社員教育は、とにかく実務や業務に集中させ、日々の仕事の中で数々の修羅場を乗り越えながら、さまざまな経験とスキルを身に付けてきました。そして、そのモチベーションは「管理職になりたい」「もっとお金を稼ぎたい」「社会的ステータスを得たい」といったことにあったと感じます。
しかし、現代の中堅社員教育は大きく変わってきています。より個別かつ柔軟な教育が求められています。
現代は働き方改革やリモートワークが当たり前になり、キャリアの多様化と流動化が大いに進んでいる時代です。また、ライフプランの柔軟性も向上している中で、20代後半~30代前半となる中堅社員には、「仕事」に対する一様ではないモチベーションが働いています。
従って、従来のように「実際の業務の中で育てきる」ことは困難となり、また、管理職になりたがらない中堅社員の増加から、「キャリアのステップアップ」もモチベーションとはなりづらい時代になりました。
実際、管理職になりたがらない若手世代(20代~30代)はどのくらい増えているのでしょうか?
パーソル総合研究所が毎年行っている「働く10,000人の就業・成長定点調査」によると、調査が開始された2018年以降では、2025年は20代・30代ともに「現在の会社で管理職になりたい」と回答した割合は最も低い結果となりました。20代では2022年比で8.8ポイント、30代では2018年比で9.9ポイント下がっていることが分かります。
「Q.今後どのようなキャリアを考えていますか?」という質問に対して、
「A.現在の会社で管理職になりたい」と回答した割合
20代(全業種) | 30代(全業種) | |
2018年 | 33.8% | 30.4% |
(略) | ||
2021年 | 36.4% | 29.4% |
2022年 | 31.0% | 26.8% |
2023年 | 32.2% | 27.2% |
2024年 | 28.2% | 23.6% |
2025年 | 27.6% | 20.5% |
「現在の会社で管理職になりたい」と回答した割合の推移(一般社員・従業員、係長相当のみに聴取)※パーソル総合研究所「働く10,000人の就業・成長定点調査」を基に筆者作成
出典:今後どのようなキャリアを考えていますか? – 働く10,000人の就業・成長定点調査 – パーソル総合研究所
このように、現代の中堅社員教育は困難を極めています。
本記事では、そのような中で効果的に中堅社員を教育するポイントやおすすめの実施形式、具体的施策を紹介します。
結論からお伝えすると、最も重要なポイントは「自己理解を深める」ことです。中堅社員が自己理解を深めることは、自身のキャリアを真剣に考えるきっかけとなるだけでなく、日々の業務の中リーダーシップ発揮の仕方や、仕事の進め方を改善するための1番のキーファクターとなり得ます。
ぜひ最後までご覧いただき、貴社の中堅社員教育を効果的なものとしてください。
▼中堅社員教育については、以下でも詳しく紹介しています。
▼中堅社員教育に関連する資料は以下からダウンロードできます。
目次[非表示]
- 1.中堅社員の教育は自己理解を深めることからはじめよう
- 1.1.自己理解の重要性
- 1.2.自己理解がもたらす効果
- 1.3.具体的なアプローチ
- 2.なぜ今、中堅社員の教育が難しいのか
- 2.1.職務レベルが高い
- 2.2.管理職になりたがらない
- 2.3.自身のこだわりが強い
- 2.4.離職リスクが高い
- 3.中堅社員教育を成功させるポイント
- 3.1.実務に即した教育内容
- 3.2.視点を上げ、視野を広げる
- 3.3.実務から離れ、自己内省を促す
- 3.4.他者からのフィードバックを得る
- 4.中堅社員教育のおすすめ実施形式
- 4.1.短期集中の集合研修
- 4.2.インターバル型のオンライン研修
- 4.3.パーソナライズeラーニング
- 4.4.会社の枠を出る越境学習
- 4.5.次世代リーダープロジェクト
- 4.6.経営シミュレーション
- 5.中堅社員教育の具体的な施策
- 5.1.プロジェクトリーダーへの抜擢
- 5.2.若手社員育成を兼ねた「メンター制度」の導入
- 5.3.上司との1on1ミーティングの導入
- 5.4.成功体験やスキルの一般化
- 5.5.マネジメントスキルの学習
- 5.6.挑戦を促す仕組みづくり
- 6.中堅社員教育でよくある質問と解決策
- 7.中堅社員教育を効果的に実施している事例
- 8.まとめ:中堅社員教育ならLDcubeにおまかせ!
中堅社員の教育は自己理解を深めることからはじめよう

中堅社員は、企業の成長を左右する重要な存在です。彼らは、現場の推進力となるだけでなく、次世代のリーダー候補としての期待を背負っています。
しかし、現代における中堅社員の教育は、これまでとは異なるアプローチが求められています。そこで、本章では、中堅社員教育の鍵となる「自己理解を深める」プロセスについて詳しく見ていきます。
自己理解の重要性
これまでの中堅社員教育では、実務を通じた経験の蓄積が主軸となっていました。しかし、現在では「働き方改革」や「リモートワーク」の普及により、個人のキャリア観や価値観が多様化しています。このような状況下で、画一的な教育方法が通用しなくなってきています。そのため、中堅社員が自己を理解し、自身の価値観やキャリア目標を明確にすることが、教育の出発点となります。
自己理解がもたらす効果
自己理解を深めることは、以下のような効果をもたらします:
|
具体的なアプローチ
自己理解を深めるプロセスは、さまざまな手法を組み合わせることで実現します:
|
中堅社員が自己理解を深めることは、自己成長だけでなく、企業にとっても大きな利益をもたらします。自己理解を教育の中心に据えることで、彼らの潜在能力を引き出し、企業の未来を切り拓く力となるのです。
▼自己理解を深める方法やツールについては、以下で詳しく紹介しています。
なぜ今、中堅社員の教育が難しいのか

現代企業が直面する最も大きな課題の1つに、中堅社員の教育が挙げられます。かつては、経験を積んで管理職を目指すことが中堅社員の主要なモチベーションであり、それに基づいた教育が一般的でした。
しかし、現代のビジネス環境の変化により、その様相は大きく変わっています。これから、なぜ中堅社員の教育が困難になっているのか、その背景を詳しく探ってみましょう。
職務レベルが高い
中堅社員は、そのキャリアの中で既に高い職務レベルと専門性を身に付けています。彼らは業務プロセスを深く理解し、戦略的な思考と実行力を兼ね備えています。そのため、画一的で基礎を重視した教育プログラムでは、必ずしも彼らのさらなる成長を保証することができません。
中堅社員にとって必要なのは、既に持っているスキルをさらに発展させ、応用力やリーダーシップを強化するためのカスタマイズされた教育プログラムです。
このようなプログラムは、社員一人一人のニーズや持っている強み、成長の方向性をしっかりと見極め、それに応える内容であることが求められます。
これには、企業が柔軟かつ的確な現状把握を持って教育内容を設計することが必要であり、一筋縄ではいかない複雑さがあります。
管理職になりたがらない
最近のさまざまな調査結果が示すように、若い世代の中で管理職を目指す意欲が低下しています。パーソル総合研究所の調査結果を見ると、20代と30代の管理職志望者の割合はここ数年で一貫して下降線をたどっています。2025年にはそれぞれ27.6%と20.5%にまで落ち込んでいます。
この背景には、管理職が求める責任や負担が、ワークライフバランスの重要性を増した現代において、必ずしも個人のライフスタイルやキャリア目標に合致しないことがあります。
さらに、テクノロジーの進化や組織のフラット化によって、管理職以外のルートでも十分に高い社会的評価や収入を得られる可能性が増していることも一因です。
このような状況では、企業は従来の管理職への道だけでなく、多様なキャリアの選択肢を提供し、他の形で社員を動機付ける方法を探る必要があります。
自身のこだわりが強い
中堅社員は、一定程度の業務経験を通じて自分なりのやり方や価値観を強く持ちがちです。これらが新しいスキルや考え方の導入を妨げる要因になることもしばしばあります。
長年の経験によって養われた自信や、自らの業務に対するこだわりは素晴らしいものですが、それが新たな変革を受け入れる柔軟性を損なうリスクも孕んでいます。
このような固執はしばしば、組織全体の変革や進化を遅延させる要因になることがあります。企業はこのようなこだわりを柔らかく受け止めつつ、他の視点や方法論を取り入れる柔軟性を促進する必要があります。
それを実現するためには、社内でオープンなコミュニケーションを奨励し、多様な考え方の重要性を伝える文化づくりが求められます。また、中堅社員が自己変革を実現できるよう、心理的な安全性を確保し、安心して新しいことに挑戦できる環境を整えることが重要です。
離職リスクが高い
中堅社員は、そのスキルや経験から他社からも引く手あまたの存在であり、転職の意向が高まる傾向にあります。特に、働き方改革が進む現在のビジネス環境においては、柔軟な働き方やプロフェッショナルな業務環境を求める動きが活発です。
中堅社員が求めるのは単に高い報酬や地位だけでなく、自分に合った働き方、成長の機会、そして自らの価値が認められる環境です。これらの条件が整う企業へと転職を考えるのは自然な流れです。
企業としては、彼らを引き留めるための戦略として、長期的なキャリアパスの明確化や持続可能な成長機会の提供を図る必要があります。
このための具体的な施策として、個々の社員のキャリアや人生設計に沿った、柔軟なキャリア開発の支援や、社員が自社に貢献する実感を得ることのできるプロジェクトの提供、そして公正で明確な評価基準を設けることが挙げられます。
こうしたアプローチを取ることで、中堅社員の企業へのエンゲージメントを高め、離職リスクを低減させることが可能になります。
中堅社員教育を成功させるポイント

中堅社員教育の成功には、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。中堅社員は、多くの場合既に経験とスキルを兼ね備え、日々の業務においても何らかのリーダーシップを発揮しています。
彼らがさらに成長し、より高い段階へとステップアップするためには、企業として効果的な教育プログラムを構築することが不可欠です。この章では、その成功のためのポイントを詳しく探っていきます。
実務に即した教育内容
まず、中堅社員に対しては実践的かつ実務に直結した教育内容が求められます。彼らは通常、日々の業務を効率的に遂行する能力を持っており、抽象的な理論よりも具体的なスキルや知識を習得することが必要です。
例えば、プロジェクトマネジメントや交渉力、データ分析スキルなど、即座に役立つ内容を盛り込むことで、彼らの学習意欲を高め、成長を促進します。
これに加え、実務における成功事例や失敗談を共有することで、より現実的な学びの機会を提供することが可能です。
視点を上げ、視野を広げる
次に、中堅社員の視点を上げ、視野を広げることが重要です。専門的な知識やスキルを磨くことは確かに大切ですが、それだけでは不十分です。彼らには、より高いレベルで組織全体の動きを理解し、広い視野で物事を捉える力が求められます。
具体的には、経営の視点や市場のトレンド、グローバルな視座を持てるようなトレーニングを提供することです。これにより、中堅社員は自身の役割を超えて考え、より包括的な問題解決能力を身に付けることができます。
実務から離れ、自己内省を促す
また、時には実務から離れ、自己内省を促す時間を設けることも重要です。中堅社員は日々多忙を極めており、自身のキャリアを振り返る余裕を持てないことが多くあります。
定期的に業務を離れ、自分のこれまでの実績や現在の位置、今後の目標などを振り返る機会を提供することで、自己理解を深め、より効果的なキャリアプランを形成する手助けとなります。
ワークショップ等を活用し、意図的に内省の機会を提供することが望ましいでしょう。
他者からのフィードバックを得る
最後に、他者からのフィードバックを得ることも中堅社員にとって不可欠です。客観的な視点からの意見や評価は、自らの強みや改善すべき点に気付くきっかけとなります。
上司だけでなく、同僚や部下、さらには社外の専門家からのフィードバックを得ることで、より多角的な自己評価が可能となります。
これにより、中堅社員は自らの成長課題を認識し、より的確な行動を取ることができるようになります。
中堅社員教育のおすすめ実施形式

中堅社員の教育を効果的に実施するためには、教育形式を選択することも重要です。
形式一つで教育効果が大きく変わってくるため、自社のニーズに合ったものを採用することが求められます。ここでは、中堅社員教育における推奨される形式について詳しく解説します。
短期集中の集合研修
短期集中の集合研修は、限られた時間で集中的にスキルを習得するための効果的な方法です。この形式は、専門家や講師から直接学ぶことができ、リアルタイムでの質疑応答や討論を通じて理解を深めることができます。
また、同じ会社や業種内の参加者とのネットワーク形成も可能であり、情報交換や意見共有によって、さらなる学びを得ることができます。
インターバル型のオンライン研修
場所を限定せずに学べるオンライン研修は、非常に効果的です。特にインターバル型のオンライン研修は、学習内容を一定期間で分割し、受講者が自分のペースで進めることが可能です。
この形式は、仕事の合間を活用して継続的に学べるため、多忙な中堅社員にとって非常に適しています。また、オンデマンドで視聴できるコンテンツを用意することで、復習や自己啓発に役立ちます。
パーソナライズeラーニング
中堅社員はおのおので異なるスキルやキャリア目標を持っています。そのため、一人一人に合ったパーソナライズされたeラーニングプラットフォームを利用することが推奨されます。
この形式では、受講者の進捗に応じたカスタマイズされたカリキュラムを提供できるため、個別の成長ニーズに応じた高い教育効果が期待できます。
また、受講者の学習履歴を分析し、改善が必要なポイントを具体的に指摘できることも、パーソナライズeラーニングならではの強みです。
▼パーソナライズ学習については、以下で詳しく解説しています。
⇒パーソナライズ学習とは?進化する人材育成手法について解説!
会社の枠を出る越境学習
会社の枠を出た越境学習は、異業種交流や他業界との接点を持つことで、新しい知見や視点を得るための有効な手段です。
これにより、中堅社員は異なる文化やビジネスアプローチから学ぶことができ、自身の価値観や業務プロセスを見直すきっかけになります。
また、他業界の専門家とのネットワーク形成は、新たなビジネスチャンスやイノベーションを生む可能性も秘めています。
次世代リーダープロジェクト
実際のプロジェクトを通じて、中堅社員のリーダーシップを育成するためには、次世代リーダープロジェクトの実施が効果的です。
このプロジェクトでは、実際のビジネス課題に取り組み、解決策を模索する中でリーダーとしての判断力や統率力を養うことができます。
また、プロジェクトの進行を通して、他の社員との協働やチームビルディングを経験することで、より実践的なリーダーシップスキルが身に付きます。
▼次世代リーダー育成のポイントについては、以下で詳しく解説しています。
⇒次世代リーダー育成の【最重要ポイント】はタスクアサイン!
経営シミュレーション
経営シミュレーションは、架空の企業を経営することで経営判断の経験を積むことができる教育形式です。このシミュレーションは、実際の市場や経済環境を模倣しており、戦略立案や資源配分、リスク管理について学びます。
こうした経験は、中堅社員にとって、現実の業務における意思決定力を大いに高めてくれるため、経営に対する理解を深め、将来的な経営層へのステップアップに寄与するものです。
▼経営シミュレーション学習については、以下で詳しく解説しています。
⇒経営シミュレーションとは?人材育成の新手法・研修について解説
これらの実施形式を自社の目的やニーズに合わせて取り入れることで、中堅社員教育がより効果的に行われることを期待できます。
中堅社員教育の具体的な施策

中堅社員を効果的に教育するためには、実践的かつ個々のニーズに応じた施策を実施することが求められます。
ここでは、成功した企業が採用している具体的な施策をいくつか紹介し、それぞれの利点と注意点について詳しく解説していきます。
プロジェクトリーダーへの抜擢
中堅社員をプロジェクトリーダーに抜擢することは、彼らに実践的なリーダーシップを発揮する機会を提供します。これにより、自信を持って意思決定を行う能力が養われ、結果としてスキルの向上や自己効力感の向上につながります。
企業文化に基づいた意思決定の重要性を学ばせることも目標の1つです。しかしながら、適切な研修やサポートを欠かせない点も重要です。
初めてのリーダーシップ経験では、失敗のリスクもあるため、失敗を経験から学びに変えるためのフォローやフィードバック体制を整える必要があります。
若手社員育成を兼ねた「メンター制度」の導入
メンター制度は、中堅社員が若手社員を指導する仕組みです。これにより、教えることで自らのスキルを再確認し、コミュニケーション能力や問題解決能力が向上します。
また、若手社員にとっても、身近な先輩からのアドバイスを受けることで、安心感を持てるという利点があります。ただし、メンターとしての役割を中堅社員に負担と感じさせないよう、適切なフォローを行うことが求められます。
あくまでも自発的な参加を促し、負担ではなく成長の機会と感じられるよう配慮することが重要です。
上司との1on1ミーティングの導入
1on1ミーティングは、中堅社員とその上司が定期的に個別面談を行う機会です。
この取り組みを通じて、中堅社員は業務上の悩みや自身の啓発課題について率直に相談でき、上司からのフィードバックやアドバイスを受け取れます。これにより、業務上の課題が早期に解決され、自身の成長を実感しやすくなります。
また、ピープルマネジメントの一環として、上司側も中堅社員のモチベーションやパフォーマンスをより深く理解できるため、組織全体のパフォーマンス向上に寄与します。
成功体験やスキルの一般化
中堅社員が業務で得た成功体験やスキルを一般化し、全社的な資産として活用することは、企業全体の知識の底上げにつながります。具体的には、研修やワークショップを通じてその知見を共有したり、社内の知識データベースを構築することで再利用可能にしたりすることが考えられます。この活動を通じて、中堅社員自身も当事者意識を持ち、その成長が組織の成長に直結するという視点を持つことができます。
マネジメントスキルの学習
中堅社員に対してマネジメントスキルを学習する機会を提供することも重要です。管理職を目指す者だけでなく、専門職としてのキャリアを積む過程においても、チームの一員としてのマネジメント能力は重要なスキルです。
具体的には、リーダーシップ、タイムマネジメント、リソース管理、人材育成などのトレーニングを行います。これらのスキルは、チームやプロジェクトの成功に直接寄与するため、高度な専門性を持つ中堅社員にとっても重要な資産となるでしょう。
挑戦を促す仕組みづくり
中堅社員が新たな挑戦を行える環境の整備も欠かせません。例えば、社内ベンチャー制度の導入や新規プロジェクトの立ち上げなどが考えられます。
これにより、社員は自身のアイデアを実現する機会を得て、自然なモチベーションの向上が期待できます。挑戦が失敗に終わった場合も、それを学びの機会として捉えることができる文化づくりが重要です。
これらの施策を組み合わせることで、中堅社員の成長を促し、組織全体のパフォーマンスを向上させることができます。
中堅社員教育でよくある質問と解決策
中堅社員の教育には多くの課題が伴いますが、それに対する有効な解決策を理解することで、より効果的な教育プログラムを実現することが可能です。
ここでは、よくある質問に対する解決策をQA形式でご紹介します。
Q. | 忙しい現場で中堅社員をどうやって教育すべきですか? |
|---|---|
A. | 現場が忙しく、教育の時間を確保するのが難しい場合、インターバル型のオンライン研修やパーソナライズeラーニングを活用することをおすすめします。これにより、中堅社員は自分のペースで学びを進めることができ、業務に支障をきたすことなくスキルアップが可能です。 |
Q. | 教育に投資しても中堅社員がすぐに離職するリスクに対してどう対応すべきですか? |
|---|---|
A. | 中堅社員が教育後に離職するリスクを完全に無くすことは難しいですが、教育と離職防止施策を組み合わせることでそのリスクを低減することが可能です。中堅社員のキャリアビジョンを尊重し、彼らのニーズや目標を考慮した教育内容を提供することで、会社へのエンゲージメントを高めましょう。さらに、成長の機会や成果のフィードバックを通じて、彼らの貢献度を実感させる仕組みが重要です。 |
Q. | 中堅社員へリーダーシップを効果的に教育するにはどうすればいいでしょうか? |
|---|---|
A. | リーダーシップ教育は実務からの経験を重視することが求められます。プロジェクトリーダーへの抜擢や次世代リーダープロジェクトへの参加など、具体的な役割を担わせることで実践的なリーダーシップスキルを養うことができます。また、フィードバックを受ける機会を設定し、リーダーシップを発揮した際の成功体験や改善点を認識させることが重要です。 |
Q. | モチベーションの低い中堅社員をどうやって教育すれば良いでしょうか? |
|---|---|
A. | モチベーションが低い社員には、まずその原因を特定することが重要です。彼らの個別のニーズや関心を把握し、それに合わせた教育内容を設計することが鍵です。また、自己理解を深めることを目的とした自己内省を促す教育や、他者とのコミュニケーションを通じたフィードバック制度を導入することで、内発的な動機を引き出すことが可能です。 |
Q. | 専門性の高い中堅社員への、効果的な教育方法はありますか? |
|---|---|
A. | 専門性の高い社員に対しては、その専門性を組織内で効果的に生かせるスキルを身に付けさせることが効果的です。専門性の高い中堅社員は、得てしてこだわりが強く、自信過剰になる傾向が少なくありません。他者との関わりの中で組織の成果を最大化させるための、ヒューマンスキルを磨くことがおすすめです。 |
Q. | 若手指導を嫌がる中堅社員にはどのように教育すれば良いでしょうか? |
|---|---|
A. | 若手指導に抵抗を感じている中堅社員には、まずメンター制度を導入し、指導の意義や楽しさを体験してもらうことが良い方法です。指導がどのように自身の成長につながるかを実感できるよう、指導方法を共に学ぶ機会を設けると効果的です。また、中堅社員自身の成功体験を若手に伝える機会を提供し、指導すること自体がキャリアの価値を高めることを認識させることが重要です。 |
Q. | 中堅社員教育の効果測定をどう行うべきでしょうか? |
|---|---|
A. | 教育の効果測定は、定量的および定性的な評価手法を組み合わせて行うことが望ましいです。定量的な指標には、パフォーマンス評価、目標達成度、離職率などがあります。一方、定性的な指標としては、フィードバック調査や自己評価、360度評価を活用して、社員の成長実感や変化を確認することが重要です。定期的に測定を行い、得られたデータを基に教育プログラムを改善することが、新たな成長への鍵となります。 |
Q. | 効果的な評価制度をどのように構築すれば良いでしょうか? |
|---|---|
A. | 中堅社員教育における効果的な評価制度は、目標の明確化と結果の公正な評価に基づくものが理想です。各社員に応じた具体的な目標を設定し、その達成に向けた進捗状況を定期的に評価することが必要です。また、結果だけでなくプロセスや行動面を評価する仕組みを設けるとより良いです。これにより、社員の成長過程をきちんと評価でき、彼らの自己成長を促すことができます。企業文化にあったフィードバックの仕組みや、評価後のフォローアップ体制を整えることで、社員のモチベーション維持につながります。 |
中堅社員教育を効果的に実施している事例

株式会社フジマート四国様 LIFO・HEP導入事例
自己理解促進ツールの活用で、研修内製化と職場コミュニケーション活性化を実現
導入前の課題
親会社である株式会社フジで人材育成業務を担っていた際、「何をすればよいのか分からない」という状況に直面しました。当時、社員の成長を支援するための明確な方法が分からず、多くの課題が存在していました。
しかし、「SDS(セルフエスティーム・ディベロップメント・セミナー)」という公開講座を受講し、自己理解の重要性に気付きました。当社の人財育成においてもこの経験を活かし、社員が自分の強みを再認識できる共通言語を構築したいと考えました。
社員が自信を持って業務に取り組める環境を提供することは、人材育成上の重要な課題であると認識しました。
(現在、SDSは「HEP(ヒューマン・エレメント・プログラム)」と名称が変わっています)
出会いと導入の決め手
LIFO(Life Orientations)の導入は、その「分かりやすさ」と「強みに焦点を当てた内容」が決め手となりました。特に若手社員に適しており、彼らが自分の強みを理解し成長するための基盤を作れると考えました。
従来の研修では弱点克服に重きが置かれていましたが、LIFOは強みを生かすアプローチを採用しており、現代の若手社員にとって効果的です。
ヒューマンスキルの向上が必要な環境の中で、LIFOは若手社員が成長し、将来的には次世代の育成を担える人材になる手助けになると考えました。
展開ステップと取り組み
管理部門においてLIFOを共通言語として活用し、自己理解と他者理解を促進しました。特に店長本部社員研修や主任研修でLIFOプログラムを導入し、職場での共通言語化を目指しました。
この取り組みを通じて、強みを活かす文化が徐々に浸透しています。LIFOは自己理解を基に業務に活かすことが可能で、「強みの過剰使用」を避けるため、定期的にスコアを測定し、内省を促しています。
導入後の感想・成果
LIFOの導入は、職場でのコミュニケーションの質を向上させ、自己肯定感を高める組織文化を醸成しました。特にフィードバック時に強みに焦点を当てることで、ポジティブでアサーティブな指導が可能となりました。
一方で、マネジャー層においては、行動スタイルの特徴に偏りが見られ、今後は特定のスキルを効果的に発揮できる人材の育成が求められます。
内製による研修実施が定着し、講師自身が実体験を交えた研修が高い効果を上げています。新入社員研修による過去の離職率改善の成功を活かし、若手社員向けLIFO研修も計画しています。
課題と今後の展望
研修後の行動変容を促進し、社員が内省を繰り返すための仕組みが必要です。心理的安全性が高い職場を目指し、LIFOやHEPを活用してマネジャー層の行動変容を促します。
また、ジョブローテーションを活用し、多様な経験を積む機会を提供します。組織全体で強みを活かし合い、共通言語に基づいた人材育成を推進し、より良い職場環境を築くことを目指します。
▼インタビュー記事全部は以下からご覧ください
⇒株式会社フジマート四国様 LIFO・HEP導入事例
▼自己理解を深めるワークショップについては、以下も併せてご覧ください。
⇒行動特性を踏まえた自分・自己理解を深めるワークショップ(研修)とは!
▼自己理解を深め成長を促す行動特性診断ツール「LIFO」については以下資料をダウンロードください。
まとめ:中堅社員教育ならLDcubeにおまかせ!
ここまで、中堅社員教育の重要性とその難しさ、そして効果的な施策について詳しく解説してきました。中堅社員は企業の中核を担い、次世代のリーダーとして期待される存在です。彼らの成長は、組織全体の成果や未来を左右する大きな要素となるため、適切な教育が求められます。
まず、教育施策の出発点として重要なのは「自己理解を深める」ことです。中堅社員が自己の強みや啓発課題について深く理解することで、より効果的な自らの成長戦略を描くことができるでしょう。また、それぞれの社員に合った実務に即した教育内容や、柔軟なキャリアパスの提供も不可欠です。
さらに、彼らの視点を広げ、異なる職務や部門との協働を通じた総合力の向上、そして他者からのフィードバックを活用した内省プロセスが重要です。これにより、中堅社員自身が持つリーダーシップを自然に発揮し、組織にポジティブな影響をもたらすことが期待できます。
中堅社員の教育には、多様な実施形式とアプローチが考えられます。短期集中型の研修やインターバルを活用したオンライン学習、経営シミュレーションなど、実際の業務に応じた知識とスキルを習得するための機会を提供すると共に、越境学習やプロジェクト型の取り組みにより、多様な経験を積むことが求められます。
これらの施策を実現し、組織の成長に影響を与えたいと考える企業の皆さまは、ぜひLDcubeのサービスをご検討ください。
LDcubeは、さまざまな教育のニーズに対応したプログラムを提供し、中堅社員の成長を全力でサポートします。一人一人の社員が持つ可能性を最大限に引き出し、組織全体の持続的な成長を実現するために、私たちにお手伝いをさせてください。
必要な教育の形は千差万別です。あなたの組織に最も適した方法で、中堅社員を次のステージへと導くお手伝いを、ぜひLDcubeにおまかせください。今こそ、時代に合わせた中堅社員教育を進め、企業の未来を共に創造していきましょう。
▼関連資料はこちらから
▼関連記事はこちらから