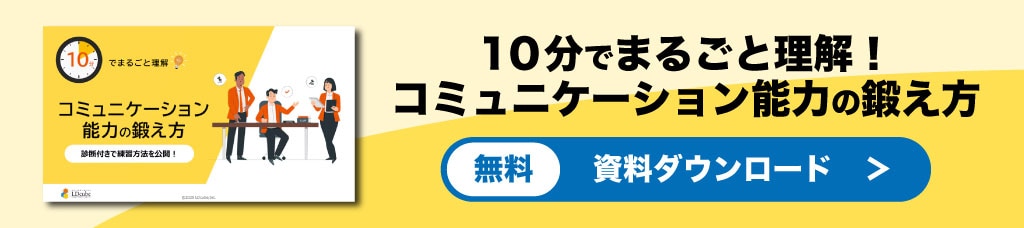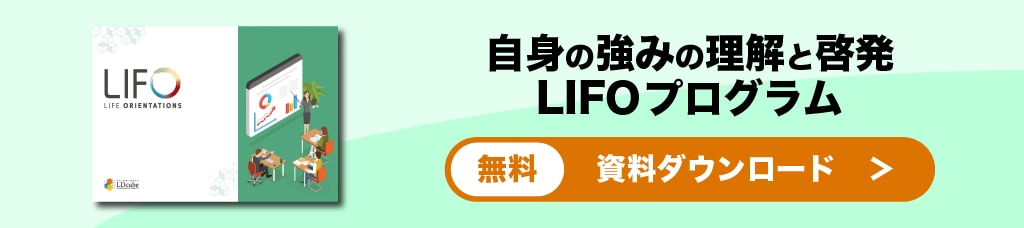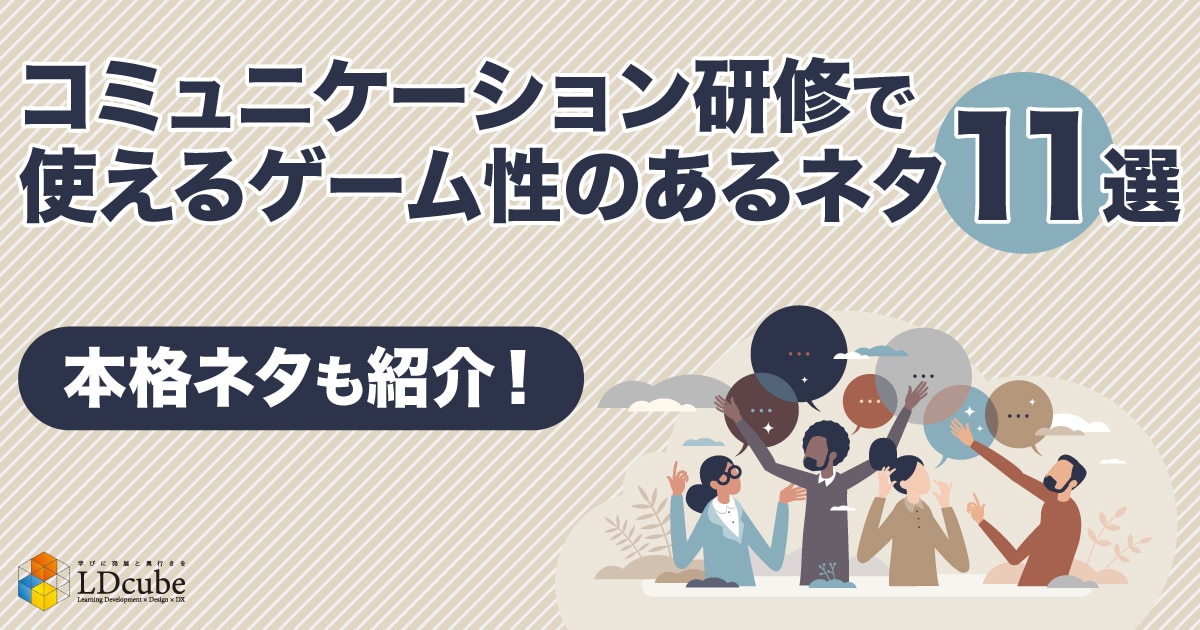
コミュニケーション研修で使えるゲーム性のあるネタ11選|本格ネタも紹介!
社内のコミュニケーション不足に悩んでいませんか?
リモートワークの浸透や世代間ギャップにより、チーム内の意思疎通に課題を感じている企業は少なくありません。そこで効果を発揮するのがコミュニケーション研修です。しかし、ただ講義を聴くだけの研修では、参加者の集中力は続かず、学びも定着しにくいものです。
コミュニケーション研修を成功させる鍵は、参加者が積極的に関わり、楽しみながら学べる「ネタ」にあります。効果的な研修ネタを取り入れることで、参加者は自然とコミュニケーションを実践でき、その経験が実務にも生かされるようになります。
本記事では、厳選したコミュニケーション研修で使える効果的なネタを11個紹介します。少人数向け、大人数向け、オンライン向けと場面別に分類し、それぞれの特徴や実施方法を解説します。また、ただ「楽しかった」で終わらせず、研修効果を最大化するためのポイントもお伝えします。
明日からすぐに実践できる内容ばかりですので、ぜひ自社の研修に取り入れてみてください。職場のコミュニケーションが活性化し、チームの結束力や生産性の向上につながるはずです。
▼コミュニケーションについてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。
▼コミュニケーションの鍛え方や研修についての資料は下記からダウンロードできます。
目次[非表示]
- 1.コミュニケーション研修にネタを取り入れるメリットと成功のポイント
- 2.すぐに実践できる!少人数向けコミュニケーション研修のネタ4選
- 2.1.アイスブレークに最適!5分で実施できる自己紹介ネタ
- 2.2.チームの距離を縮める!自己開示を促す対話型ネタ
- 2.3.信頼関係を構築する!協力型コミュニケーションゲームネタ
- 2.4.問題解決力を高める!ディスカッション型ワークネタ
- 3.大人数でも盛り上がる!グループ向けコミュニケーション研修のネタ4選
- 3.1.準備がなくてもすぐできる!チーム対抗コミュニケーションゲームネタ
- 3.2.情報共有力を鍛える!伝達型コミュニケーションワークネタ
- 3.3.多様性を尊重する!意見交換型ディスカッションネタ
- 3.4.全員参加型!大人数でも実施できるアクティビティネタ
- 4.オンラインでも効果抜群!リモート向けコミュニケーション研修のネタ2選
- 5.プロが使う万能なコミュニケーション研修のネタ「LIFO®」
- 6.コミュニケーション研修のネタを効果的に実施するための4つのステップ
- 7.LIFOを活用して社内トレーナーがコミュケーション研修を展開している事例
- 8.まとめ:効果的なコミュニケーション研修ネタで職場の活性化を実現しよう
コミュニケーション研修にネタを取り入れるメリットと成功のポイント

企業の生産性向上や組織力強化には円滑なコミュニケーションが欠かせませんが、講義形式の研修だけでは実践的なスキル向上に限界があります。
そこで注目されているのが、ゲームやアクティビティなどの「ネタ」を取り入れたコミュニケーション研修です。参加者が楽しみながら主体的に学ぶことで、より効果的な学習体験を提供できます。
コミュニケーション研修にネタを取り入れる3つの効果
コミュニケーション研修に「ネタ」を取り入れることで、参加者の学びと成長につながる効果が期待できます。
また、カジュアルな雰囲気の中で自然なコミュニケーションが生まれ、普段は見られない一面が引き出されます。
|
効果的なコミュニケーション研修のネタの選び方
コミュニケーション研修の効果を最大化するには、適切なネタ選びが重要です。単に楽しいだけでなく、目的や参加者の特性に合わせて選びましょう。
まず研修目的を明確にすることが大切です。「チームワーク強化」か「情報共有の円滑化」か、目的に合ったネタを選ぶことで効果は大きく変わります。
また、参加者の特性も考慮しましょう。初対面が多い場合は自己紹介要素を含むネタが、部署間の壁がある場合は協力型ゲームが効果的です。
|
コミュニケーション研修を「楽しかった」で終わらせない実践方法
コミュニケーション研修の課題は、「楽しかった」だけで終わり、行動変容につながらないことです。この課題を克服するには、研修の構成と事後フォローに工夫が必要です。
効果的な研修では、ネタ実施後に必ず振り返りの時間を設けます。具体的な行動にひも付けた振り返りで、体験を学びに変換するのです。
また、学びを実務に接続するアクションプランを立てることも重要です。
|
これらの方法を組み合わせることで、実践的で効果の高いコミュニケーション研修を実現できます。研修は「点」ではなく「線」として捉え、継続的な成長のプロセスとして設計しましょう。
すぐに実践できる!少人数向けコミュニケーション研修のネタ4選

少人数での研修は、参加者一人一人が積極的に関わることができ、より深い学びが期待できます。ここでは、2~10名程度の少人数グループですぐに実践できるコミュニケーション研修のネタを4つご紹介します。
どれもシンプルなルールで特別な準備や道具を必要としないため、明日からでも気軽に取り入れられます。
アイスブレークに最適!5分で実施できる自己紹介ネタ
研修の始まりに緊張感をほぐすアイスブレークとして、「私の好きなもの」という自己紹介ネタがおすすめです。
各参加者に自分の好きなもの(趣味、食べ物、場所など)を3~5個、紙に書き出してもらいます。順番に発表し、なぜそれが好きなのかも簡単に説明してもらいます。発表後は他のメンバーから質問タイムを設け、会話を広げていきます。
このネタの魅力は、自分の好きなものを通じて自然と個性が表れることです。共通点が見つかれば会話が発展しやすくなり、普段の業務では見えない趣味や価値観が垣間見えることで新たな発見が生まれます。5分程度で実施できる点も、時間に制約のある研修に適しています。
チームの距離を縮める!自己開示を促す対話型ネタ
「ブラインドトーク」は、カジュアルな形で本音の交流を促すネタです。
全員が公園で会話をしているという設定で、1人が「寝落ち」します。寝落ちした人は目を閉じます。残ったメンバーは「寝落ちした人への感謝」「その人のすごいところ」「さらに良くなるためのアドバイス」などを話し合います。5分程度話し合った後、寝落ちした人が目を開け、話し合っていた内容への感想を述べます。
普段は直接伝えにくい本音のメッセージを安全な環境で共有でき、建設的なフィードバックを含めることでメンバーの成長につながる対話が生まれます。オンラインでの実施も可能で、カメラをオフにして同様に進めることができます。
信頼関係を構築する!協力型コミュニケーションゲームネタ
「伝言ゲーム」は、情報伝達の正確さと協力の重要性を学べる実践的なネタです。
さまざまな図形が描かれた用紙を準備し、参加者を「話し手」と「聞き手」のペアに分けます。話し手は聞き手に図形を言葉だけで説明し、聞き手はその説明を聞いて図形を再現します。数字を使ったり指差したりといった直接的な指示は禁止です。5~10分の制限時間後、元の図形と再現された図形を比較して振り返ります。
このネタでは「相手に伝わる説明の仕方」「確認の重要性」「共通言語の構築」といったビジネスコミュニケーションの本質を体験できます。振り返りで「どのような説明が分かりやすかったか」「誤解はどこで生じたか」を話し合うことで、日常業務での改善につなげられます。
問題解決力を高める!ディスカッション型ワークネタ
「南極ゲーム」は、南極で遭難したという設定で、生存に必要なアイテムの優先順位を決めていく合意(コンセンサス)形成ゲームです。参加者は限られた情報の中で、論理的思考と説得力のある意見を求められます。
最初に個人で順位付けを行った後、チームでディスカッションして合意形成を目指します。最後に専門家の模範解答と比較して、個人とチームの成績を評価します。
このネタの特徴は、個人の判断とチームでの合意形成を比較できる点です。通常、適切に話し合ったチームの成績は個人の平均より高くなり、「多様な意見を集約する価値」を実感できます。
振り返りでは「意見の対立をどう解消したか」などを共有し、実際の業務での合意形成に生かせる学びを引き出します。
大人数でも盛り上がる!グループ向けコミュニケーション研修のネタ4選

大人数での研修では、全員が積極的に参加できる工夫が必要です。15名以上のグループでは一部の参加者だけが活躍しがちですが、適切なネタを選べば全員が主体的に関わることができます。
ここでは、部署を超えた交流や組織全体のコミュニケーション活性化に役立つ研修ネタを4つご紹介します。
準備がなくてもすぐできる!チーム対抗コミュニケーションゲームネタ
「共通点探しゲーム」は、短時間で参加者同士の関係性を深めることができる効果的なアイスブレークです。
複数名でグループを組み、時間を決めて、お互いの共通点をできるだけ多く見つけ出します。このゲームを通じて、コミュニケーション能力の向上とチーム内の相互理解を深めることができます。
結果発表は、グループごとに共通点の数を集計し、全員が立った状態から「1つ、2つ、3つ…」と数えていき、自分のグループの共通点の数になったら座ります。これを続けて、最後まで立っていることができたグループが優勝です。
情報共有力を鍛える!伝達型コミュニケーションワークネタ
「ポジション当てゲーム」は、断片的な情報を集約して全体像を把握する能力を鍛えるネタです。参加者をグループに分け、各メンバーには断片的な情報カードを配ります。口頭でのコミュニケーションのみで情報を共有し、野球のポジション表を完成させます。
大人数でも同時並行で複数のグループに分かれて取り組めるため、20~50名程度の大規模研修でも実施可能です。情報の伝え方や質問の仕方など、情報共有の本質を体験できる点も魅力です。
振り返りでは「どのように情報を整理したか」「誤解が生じた原因は何か」を共有し、日常業務での報告・連絡・相談の質向上につなげます。複数の部署から参加者を集めることで、組織全体の情報共有力強化にも役立ちます。
多様性を尊重する!意見交換型ディスカッションネタ
「ワールドカフェ」は、多様な視点を活用して協調的な対話を促進するワークショップです。この手法は特定のテーマや問題を深く掘り下げることを目的としています。
参加者は小グループに分かれ、リラックスしたカフェ風の環境で、テーマに関する問いについて自由に話し合います。対話は15〜30分のセッション(ラウンド)で行い、模造紙やふせんで記録を残します。各テーブルにはホストが設定され、対話内容を共有しセッションを円滑に進めます。
参加者は一定時間後にテーブルを移動し、新たなグループで対話を続け、新しい視点やアイデアを交わします。全てのラウンド終了後、全体で意見を共有し、ビジュアルツールを用いてアイデアを整理します。
全員参加型!大人数でも実施できるアクティビティネタ
「ヒューマングラフ」は、参加者全員が誕生日順に1列に並ぶシンプルなアクティビティです。声を出したり筆記具を使ったりすることは禁止で、身ぶり手ぶりのみでコミュニケーションを取ります。
それを行うことで、言語によらないコミュニケーションの重要性を体感することができます。
また、演習を進めていく中で、全体を調整するリーダーが自然と現れるなど、組織内でのコミュニケーションの期待役割を学ぶこともできます。準備も特に必要なく、広いスペースさえあれば実施可能なため、大規模研修のアイスブレークとしても最適です。
▼その他コミュニケーションワークショップについては下記で詳しく解説しています。
オンラインでも効果抜群!リモート向けコミュニケーション研修のネタ2選

リモートワークの普及に伴い、オンラインでのコミュニケーション研修の需要が高まっています。対面とは異なる環境でのコミュニケーションには特有の難しさがありますが、オンラインならではの特性を生かしたネタを取り入れることで効果的な研修が可能です。
ここでは、ZoomやTeamsなどの一般的なビデオ会議ツールで実施できる、オンライン環境に最適化された研修ネタを3つご紹介します。
リアルとオンラインを組み合わせたコミュニケーション研修ネタ
「オンライン読書・対話会」はリアルな本(ここではテーマとしてコミュニケーションに関するものなど)を配布し、参加者には事前に読んできてもらいます。
オンライン会議システムのブレークアウト機能を使って、ランダムにグループを割り振り、グループ内で本を読んでの気付きや学び、自分の身近な事例などの紹介を行います。
このネタの特徴は、事前に本を読んでおく必要があり、その時点から学習が始まる点です。そして、同じ本を読んでいても感じ方や関心を持つポイントが人それぞれ違うということに気付くとともに、テーマとして設定した本の内容についても理解を深めることができます。
一定時間が経過したらグループメンバーを入れ替えて進めるなどすると、常に新鮮な状況で進めていくことができます。
時間や場所を選ばない非同期型コミュニケーション研修ネタ
「自分史ワーク」は、グローバル企業や時差のある拠点間でも実施できる非同期型のコミュニケーション研修ネタです。
参加者は自分の経歴や成長過程に関する質問(「人生の転機となった出来事」「仕事で最も大切にしていること」など)に回答し、コメントとしてまとめます。それをMiroなどのオンラインホワイトボードツール上にコメントを投稿します。
他のメンバーは都合の良いタイミングでコメントを確認後、質問やコメントを残します。それに対して元の作成者が返答するという流れです。
このネタの特徴は、じっくりと考えて表現できる点です。即興の対話が苦手な人でも自分のペースで考えをまとめられるため、より深い自己開示が期待できます。また、時差のある拠点間でも実施可能です。
運用のポイントは、明確な期限設定と進行管理です。「1週間以内にコメントを投稿する」「3日以内に全員分にコメントする」など、具体的なスケジュールを設けましょう。
また、定期的なオンラインミーティングで気付きを共有する機会を設けると、非同期と同期のコミュニケーションを組み合わせた効果的な研修になります。
プロが使う万能なコミュニケーション研修のネタ「LIFO®」

これまでご紹介したコミュニケーション研修のネタは、どれも即効性があり手軽に導入できるものばかりです。ここでは、一歩進んで、プロのトレーナーやコンサルタントが活用している本格的なツール「LIFO(ライフォ)」について解説します。
LIFOは行動科学に基づいた行動特性診断ツールであり、あらゆる規模や形態のコミュニケーション研修に応用できる万能なネタです。
自己診断ツール「LIFO」
LIFO(Life Orientations)は、1967年にアメリカで開発された行動特性診断ツールです。個人の価値観や行動特性を4つの基本スタイルに分類し、コミュニケーションや対人関係の特徴を可視化します。
4つの基本スタイルは以下のとおりです。
|
LIFOの特徴は、「良いスタイル・悪いスタイル」という評価をしない点です。各スタイルには強みと過剰使用時の弱みがあり、自分や他者のコミュニケーションパターンを理解することで、より効果的な対人関係を構築できます。
実施方法としては、参加者にLIFO診断に回答してもらい、自分の行動特性を可視化します。その後、各スタイルの特徴を学び、理解を深めていきます。
少人数でも大人数でも実施可能
LIFOの大きな魅力は、参加人数を問わず実施できる点です。個人診断から始まるため、5名程度の少人数チームから、100名を超える大規模研修まで、規模に応じたプログラム設計が可能です。
少人数での実施では、メンバー全員のスタイルを共有し、チーム内の多様性について深く議論できます。「このチームにはCTスタイルが多いがCHスタイルは少ない」といった特徴が見えてくると、チームの意思決定プロセスや課題解決アプローチについての洞察が得られます。
大人数の場合は、同じスタイルの参加者同士でグループを作り、各スタイルの強みと弱みについて議論した後、混合グループでの共有を行う方法が効果的です。また、部署単位での傾向分析も可能で、部署間のコミュニケーション摩擦の原因理解にもつながります。
集合でもオンラインでも実施できる
LIFOは、対面形式でもオンライン形式でも効果的に実施できます。対面形式では、参加者のスタイルを色分けしたネームカードで可視化したり、スタイル別に教室内で立ち位置を変えたりといった、物理的空間を活用したアクティビティが可能です。
オンライン形式では、事前に診断を完了してもらい、ビデオ会議中に結果を共有する方法が一般的です。バーチャルホワイトボードやブレークアウトルームを活用することで、対面と遜色ない学習体験を提供できます。
社内トレーナーが実施できる
LIFOは認定トレーニングを受けることで社内トレーナーも実施可能になります。外部講師に依頼する必要がなく、自社の文化や課題に合わせたカスタマイズが容易な点も大きな魅力です。
社内トレーナーが育成されると、新入社員研修からリーダーシップ開発まで、さまざまなレベルの人材育成プログラムにLIFOを組み込むことができます。また、チーム内の対立解消や部署間連携の強化など、具体的な課題解決にも活用可能です。
継続的な活用により、組織全体で共通言語が生まれ、「あの人はCTスタイルだから、最初に結論から伝えよう」「このチームはCHスタイルが多いから、詳細な根拠を示そう」といった、実践的なコミュニケーション改善につながります。
単発の研修ではなく、組織文化に根付いた長期的な改善ツールとして価値を発揮するでしょう。
コミュニケーション研修のネタを効果的に実施するための4つのステップ

これまでさまざまなコミュニケーション研修のネタをご紹介してきましたが、どれだけ良いネタであっても、実施方法を誤ると十分な効果を得られません。「楽しかった」という感想で終わり、実際の行動変容につながらないというのは、コミュニケーション研修でよく見られる課題です。
ここでは、コミュニケーション研修のネタを効果的に実施し、確実に成果を出すための4つのステップを解説します。この流れに沿って実施することで、一過性のイベントではなく、真の組織変革につながる研修が実現できるでしょう。
目的に合ったコミュニケーション研修のネタを選ぶ
効果的なコミュニケーション研修の第一歩は、研修目的に合った適切なネタを選ぶことです。漠然と「コミュニケーション能力を高めたい」ではなく、より具体的な目標を設定しましょう。
まず、組織の現状課題を明確にします。「部署間の連携不足」「情報共有の遅れ」「チーム内の信頼関係の希薄化」など、具体的な問題点を洗い出してください。
次に、その課題解決につながる能力を特定します。「活発な意見交換」「正確な情報伝達」「相互理解の促進」など、伸ばしたい能力を絞り込みましょう。
課題と目標が明確になったら、それに最適なネタを選びます。
例えば、部署間の壁を取り除きたい場合は「共通点探しゲーム」のようなチーム対抗型のネタ、情報共有を促進したい場合は「ポジションあてゲーム」のような伝達型のネタが適しています。また、参加者の特性や実施環境も考慮に入れることが大切です。
ネタ選びの最終確認として、「このネタを実施した後、参加者にどのような変化を期待するか」を明確にしておきましょう。
盛り上がりと学びのバランスを取る
コミュニケーション研修では、「楽しさ」と「学び」のバランスを適切に取ることが、効果的な研修の鍵となります。
バランスの取り方として、以下の点に注意しましょう。
|
コミュニケーション研修の学びを定着させる
せっかくの研修での気付きも、日常業務に戻ると忘れてしまいがちです。研修効果を持続させるためには、学びを定着させる仕組みづくりが欠かせません。
学びの定着に効果的な方法として、以下のアプローチを検討してください。
|
コミュニケーション研修ネタの成果を可視化する
コミュニケーション研修の効果を客観的に評価し、次の施策に生かすためには、成果の可視化が重要です。
成果可視化のアプローチとして、以下の方法が効果的です。
|
成果の可視化は、次回の研修改善だけでなく、経営層への価値証明や参加者自身のモチベーション維持にも有効です。目に見えにくいコミュニケーション能力の変化を、意識的に「見える化」する努力が重要といえるでしょう。
LIFOを活用して社内トレーナーがコミュケーション研修を展開している事例

背景・課題
リコージャパン株式会社では、2010年の販売会社統合以降、各支社の固有の課題に対応できず、教育施策が本部主導で一方的になるなどの課題がありました。
また、コロナ禍以降、会食などの機会が減ったことにより、コミュニケーションの希薄化を招いていました。これらの課題を解決するために、社員自らが強みや弱みを理解し合い、横のつながりを強化する取り組みが求められていました。
LIFOプログラム(社内トレーナーライセンス)の導入
その中で、LIFO(Life Orientations)を導入しました。LIFOの活用を通じて、社員一人一人の個性を診断し、自己理解と他者理解を促進しました。
これにより、非公式なコミュニケーションが減少する中でも、社員同士の相互理解を深めるための新たな手段を提供することができるようになりました。
また、LIFOプログラムライセンスを取得することで、社内トレーナーが自主的に研修を行えるようになり、組織風土改革を進めました。
LDcubeとの協力により、多様なワークショップを展開し、各支社・部門が抱える具体的な課題に対応できるようになりました。
社内展開
プログラムの展開においては、事前のLIFO診断、ワークショップの実施、職場での実践、効果検証のサイクルを組み込みました。
参加者は、研修後の職場実践を通じて得られたスキルを評価し合い、PDCAサイクルを回すことで、持続的なスキルアップを図っています。
ラーニングプラットフォーム「UMU」を活用し、受講者同士が学び合う環境も整備しました。
社内トレーナーによる研修実施後の反応
導入後、プログラム受講者の満足度は高く、多くの支社で「対人関係」や「マネジメント能力」などにおいて数値的な改善が見られました。
LIFOを活用したレクチャーは「人」の問題の解決に寄与し、特にアウトプット重視の体験学習が効果的でした。
UMUの活用と一連の学習サイクルの設計により、事務局の負担軽減と学習効果の向上が実現しました。
今後に向けて
今後は、各支社や部門の課題に寄り添い、人材育成を継続的にサポートすることで、社員個々の自己成長と組織全体の活性化をさらに推進する予定です。
また、LIFO以外のライセンスプログラムも組み合わせ、人材育成のプログラムラインナップを増やしていきます。
これにより、組織内のさまざまな課題を解決し、全体の一体感をさらに高められることを期待しています。
▼本事例はインタビュー記事の一部です。インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。
⇒リコージャパン株式会社様 ライセンスプログラム導入事例
まとめ:効果的なコミュニケーション研修ネタで職場の活性化を実現しよう
本記事では、さまざまな状況に適したコミュニケーション研修ネタ11選を紹介しました。少人数向けの自己紹介ネタから大人数向けのチーム対抗ゲーム、オンライン環境に最適化されたリモートネタまで、幅広いバリエーションをカバーしています。
これらのネタを活用する最大のメリットは、参加者が楽しみながら自然なコミュニケーションを体験できる点です。ただし効果を最大化するには、目的の明確化、適切なネタ選び、効果的な振り返り、学びの定着と成果の可視化という4つのステップが重要となります。
組織のコミュニケーション課題は多様です。部署間の壁、情報共有の不足、信頼関係の希薄化など、それぞれの課題に対応したネタを選ぶことでピンポイントな改善が期待できます。さらに高度なアプローチとしては、LIFOのような診断ツールの導入も検討する価値があるでしょう。
コミュニケーション能力の向上は継続的な実践があってこそ実現します。研修を一過性のイベントではなく組織変革のプロセスとして捉え、日常業務への落とし込みとフォローアップを大切にしてください。
本記事で紹介したネタを活用し、メンバー同士が互いを理解し合い、自由に意見を交わしながら協力して課題を解決できる、活力ある職場づくりを目指しましょう。
株式会社LDcubeでは、LIFOプログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFOプログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。