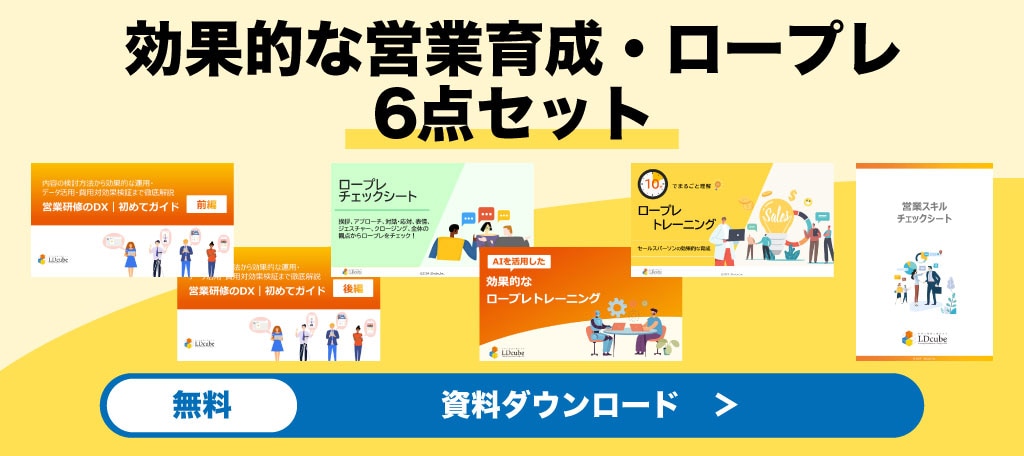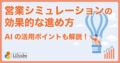これからの時代の営業勉強会とは?成功させるポイントを解説!
営業力の向上は多くの企業が抱える重要な課題です。市場競争が激化する中、営業チームの一人一人が高いパフォーマンスを発揮できるかどうかが、企業の売上や成長に直結します。そして、営業パーソンのパフォーマンスを高めるための効果的な方法の1つが「営業勉強会」です。
営業勉強会とは、営業スキルの向上や知識の共有を目的とした、社内での学習機会のことです。ただ、「勉強会を開いても成果が出ない」「一時的な盛り上がりで終わってしまう」という声も少なくありません。せっかく時間と労力をかけるなら、本当に営業スキルの向上につながる勉強会にしたいものです。
効果的な営業勉強会を実施するには、明確な目的設定から始まり、適切なコンテンツの選定、効果的な進行方法、そして実施後のフォローアップまで、さまざまな要素を考慮する必要があります。特に重要なのは、「知識を得るだけ」の座学に終わらせず、実践につながる内容にすることです。
本記事では、営業勉強会を成功させるための7つのステップを、準備段階から実施、そして効果測定まで体系的に解説します。営業チームをマネジメントする管理者や営業部隊のパフォーマンス向上を営業企画部門の方、人材育成担当者の方々にとって、実践的で即効性のある情報をお届けします。
「どのタイミングで勉強会を開催すべきか」「どんなスキルを重点的に教えるべきか」「効果的なロールプレーイングの方法は?」など、現場で直面する疑問にも答えていきます。この記事を参考に、あなたの会社の営業力を底上げする、実りある勉強会を実現させましょう。
▼営業研修やロープレトレーニングについてはテーマに合わせて下記で解説しています。
▼営業研修やロープレについてのお役立ち資料を6点セットにしました。下記からダウンロードできます。
目次[非表示]
- 1.営業勉強会のデジタル化で業績を上げられる
- 2.営業勉強会とは?実施する目的と重要性重要性とは?
- 3.営業勉強会を開催すべき3つのタイミング!
- 4.営業勉強会を成功させるために行うべき事前準備
- 5.営業勉強会で継続的・重点的に学ぶべき内容
- 6.営業勉強会で成果につなげるための効果的な進行方法
- 6.1.講義と演習の最適な配分
- 6.2.グループワークの活用
- 6.3.講義部分を録画する
- 7.営業勉強会で効果的にロールプレーイングを実施する方法
- 8.営業勉強会後、成果につなげるための効果的な流れ
- 8.1.①録画した講義をテーマごとに分割し、マイクロラーニングを作成する
- 8.2.②理解度クイズをセットにする
- 8.3.③動画提出課題をセットにする
- 8.4.④意見投稿フォームを用意する
- 8.5.⑤ ①~④をプラットフォーム上で運用する
- 9.営業勉強会の効果を具体的に測定する方法とは
- 10.営業勉強会の講師は誰がやるのが最適といえるか?
- 11.営業勉強会を定期的・継続的に開催し成果につなげるコツ
- 12.営業勉強会でよく陥りがちな失敗とその対策
- 12.1.一方的な講義形式に陥らないために
- 12.2.現場で使えない「机上の空論」を避ける方法
- 13.アウトプットを意識した営業勉強会で成果を上げた支援事例
- 14.まとめ:効果的な営業勉強会が組織にもたらす価値
営業勉強会のデジタル化で業績を上げられる

従来の対面式営業勉強会に加えて、デジタルツールを活用することで、学習効果を高め、業績向上につなげることができます。
デジタル化された営業勉強会は、単なる知識の伝達にとどまらず、実践的なスキル向上と継続的な学習環境の構築に貢献します。
勉強会の内容を踏まえてアウトプット練習をする
デジタル環境では、学んだ内容をすぐに実践形式でアウトプットできる点が大きなメリットです。例えば、商品説明のポイントを学んだ後、自身の説明動画を録画して提出するといった課題が可能になります。
営業のトークスクリプトを学んだ後、それを応用した自分なりのトークを録音し、フィードバックを受けるという仕組みも構築できます。このようなアウトプット練習は、知識の定着率を大幅に高め、実践での応用力を養います。
繰り返し勉強できる
デジタル化された営業勉強会コンテンツは、何度でも視聴できるという大きなメリットがあります。一度の勉強会では理解しきれなかった内容も、録画された映像を繰り返し視聴することで徐々に理解が深まります。
特に複雑な商品知識や高度な営業テクニックについては、繰り返し学習することで習得が進みます。営業現場で「あのポイントをもう一度確認したい」と思ったときにすぐにアクセスできる環境は、実践的な営業力向上に大きく貢献します。
いつでもどこでも学習できる
デジタル化された営業勉強会のコンテンツは、時間や場所の制約を受けません。移動中や待ち時間、自宅でのリラックスした環境など、営業パーソンそれぞれのベストなタイミングで学習できます。
全国各地に営業拠点がある場合や、外出が多い営業スタイルの企業では特に効果を発揮します。地理的・時間的な制約がなくなることで、全社で統一された営業ノウハウの共有が実現し、営業力の標準化にもつながります。
内容について参加者同士で学び合う
デジタル環境を利用することで、勉強会後も参加者同士が継続的に意見交換やディスカッションを行うことが可能になります。チャットツールを活用して「この商品の説明で工夫している点」「お客さまからよくある質問とその回答例」などの情報共有が促進されます。
こうした参加者同士の学び合いは、インプット重視の勉強会では得られない多角的な視点や実践的なノウハウの蓄積につながり、組織全体の営業力向上に大きく貢献します。テキストだけでなく、実際の商談録音や成功事例の動画なども共有することで、より具体的な学習が可能になります。
▼営業研修での動画活用については下記で詳しく解説しています。
⇒営業研修での動画活用でスキルを高め業績向上につなげるには?メリットや作成方法を解説!
営業勉強会とは?実施する目的と重要性重要性とは?

営業勉強会とは、営業チームのスキル向上と組織全体の営業力強化を目的とした学習の場です。
単なる商品知識の共有にとどまらず、営業プロセスの改善、成功事例の分析、実践的なトークスキルの向上など、多岐にわたる目的で実施されます。
営業勉強会が注目される理由
近年、営業勉強会が多くの企業で注目されている背景には、以下のような要因があります。
まず、デジタル化の進展により従来の営業手法が通用しなくなってきていることが挙げられます。顧客はインターネットで多くの情報を入手できるようになり、営業パーソンに求められる役割や価値提供の方法が変化しています。
こうした状況に対応するためには、継続的な学習と情報共有が不可欠です。
また、商品やサービスの高度化・複雑化が進んでいることも理由の1つです。高度な商品知識やソリューション提案力を身に付けるためには、体系的な学習の機会が必要となっています。
さらに、営業ノウハウの「属人化」という課題を抱える企業も少なくありません。一部の優秀な営業パーソンに依存する体制から脱却し、組織全体の営業力を底上げするためには、ノウハウの共有と標準化が重要です。営業勉強会はそのための有効な手段となります。
営業勉強会と一般的な研修との違い
営業勉強会と一般的な研修には、いくつかの重要な違いがあります。
一般的な研修が「教える側」から「学ぶ側」への一方向的な知識やスキルの伝達になりがちなのに対し、営業勉強会では参加者同士の相互学習や実践的なワークを重視します。成功している営業パーソンの、具体的なトークや商談の進め方などを共有し、それを各自が自分のスタイルに取り入れていくプロセスが大切にされます。
また、一般的な研修が「基礎知識の習得」を目的とするのに対し、営業勉強会では「現場での実践力向上」に焦点が当てられます。そのため、ロールプレーイングなどの実践的な演習が多く取り入れられるのも特徴です。
さらに、研修が単発で完結することが多いのに対し、営業勉強会は継続的な学習プロセスの一部として位置づけられます。勉強会で学んだことを実践し、その結果を次の勉強会で共有するといったPDCAサイクルを回すことで、継続的な成長を促します。
▼営業研修のおすすめについては下記で詳しく解説しています。
⇒営業研修おすすめ27選!新人・中堅・ベテランの階層別に深掘り紹介
営業勉強会を開催すべき3つのタイミング!
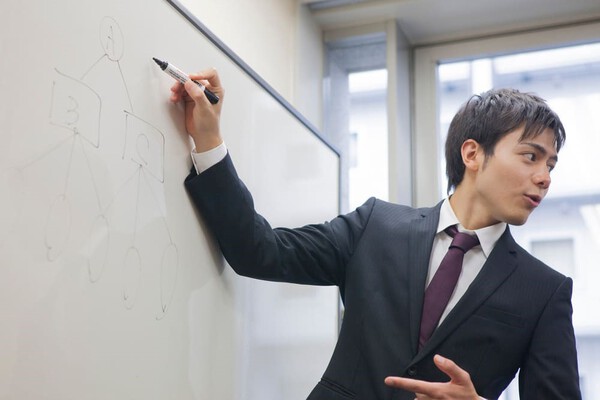
営業勉強会は定期的に開催するのも効果的ですが、特に効果を発揮するタイミングがあります。
適切なタイミングで実施することで、営業チームの課題解決や業績向上に直結させることができます。
新商品・サービスのリリース時
新しい商品やサービスをリリースする際は、営業勉強会を開催する絶好のタイミングです。新商品の特徴、競合商品との差別化ポイント、想定される顧客の質問とその回答例などを共有することで、発売開始直後から効果的な営業活動が可能になります。
特に技術的に複雑な商品や、これまでにないコンセプトの商品の場合は、営業パーソンが自信を持って説明できるようになるまでに時間が掛かります。リリース前に十分な営業勉強会を実施することで、この立ち上げ期間を短縮できます。
特定の商品・サービスの販売を強化したい時
既存の商品やサービスの中で、特に注力したいものがある場合も営業勉強会の好機です。例えば、利益率の高い商品の販売を強化したい場合や、市場のニーズが高まっている商品に戦略的にシフトしたい場合などが該当します。
この場合の営業勉強会では、単に商品知識を深めるだけでなく、「なぜこの商品に注力するのか」という戦略的背景や、「どのような顧客にアプローチすべきか」といった具体的な販売戦略まで共有することが重要です。
営業成績にばらつきがある時
営業チーム内で成績に大きなばらつきがある場合は、営業勉強会を通じて底上げを図るべきタイミングです。高業績者の商談プロセスや顧客とのコミュニケーション方法を分析し、具体的なノウハウとして共有することで、チーム全体の営業力向上につなげることができます。
このタイプの勉強会では、単なる成功事例の紹介にとどまらず、「なぜうまくいったのか」という成功要因の分析や、「どのようなステップで商談を進めたのか」という具体的なプロセスの共有が効果的です。
優秀な営業パーソンへの依存度が高い時
特定の営業パーソンに売上が集中している状態は、組織としてリスクが高い状態です。その人材が退職したり、長期休暇を取ったりした場合に大きな影響を受けるためです。こうした状況では、優秀な営業パーソンのノウハウを組織の資産として共有・蓄積するための営業勉強会が重要になります。
優秀な営業パーソンが持つ暗黙知を形式知化し、他のメンバーも活用できるようにすることで、組織全体の営業力を高め、特定個人への依存リスクを軽減できます。
組織規模の拡大や変革期
営業チームの規模が拡大する時期や、組織変革を進める時期も、営業勉強会が効果を発揮するタイミングです。新しいメンバーが増えたり、営業プロセスの見直しがあったりする際に、勉強会を通じて組織の営業スタイルや価値観を共有することで、チームの一体感を醸成できます。
このようなタイミングでの勉強会は、単なるスキルアップの場ではなく、組織文化の形成や共通言語の構築にも貢献します。特に急成長している企業や事業再編を行っている企業にとって、重要な取り組みとなります。
営業勉強会を成功させるために行うべき事前準備
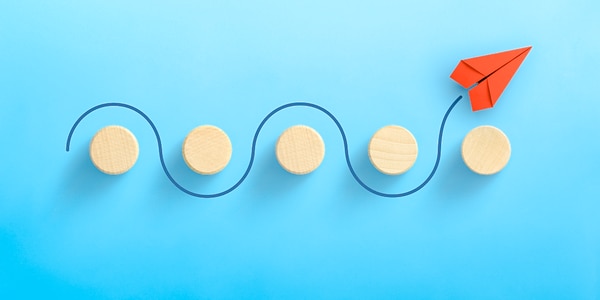
営業勉強会の成功は事前準備に掛かっています。綿密な準備を行うことで、参加者の学習効果を最大化し、実際の営業活動への応用がスムーズになります。
ここでは、効果的な営業勉強会を実施するための重要な準備ステップを解説します。
現状の課題を明確にする
最初に、現状の営業活動における課題を明確にすることが重要です。「なぜ営業勉強会が必要なのか」という根本的な問いに答えることから始めましょう。
営業データの分析を行い、以下を具体的に把握します。
|
また、営業パーソンとの1on1面談や匿名アンケートを実施して、現場が感じている課題や困りごとを収集することも有効です。
現場の声を反映させることで、より実践的で価値ある勉強会になります。
参加者のレベルとニーズを把握する
営業勉強会の参加者の経験レベルやスキルセット、具体的なニーズを事前に把握することが大切です。新人営業パーソンが多い場合と、経験豊富なベテラン営業パーソンが中心の場合では、最適な内容や進め方が大きく異なります。
参加者のスキルレベルを把握するために、事前アンケートや営業成績のデータ分析を行いましょう。
特に重要なのは、参加者がどのような知識やスキルを身に付けたいと考えているかという「学習ニーズ」の把握です。これにより、参加者のモチベーションを高める内容設計が可能になります。
テーマを決める
収集した情報を基に、営業勉強会のテーマを具体的に決定します。テーマは具体的かつ実践的であることが重要です。
「営業力の向上」といった抽象的なテーマではなく、「新商品Aの効果的な提案方法」「初回訪問での信頼関係構築テクニック」など、具体的なテーマを設定しましょう。
テーマが決まったら、達成目標を明確にします。「この勉強会を通じて参加者にどのようなスキルや知識を身に付けてもらいたいか」「勉強会後にどのような行動変容を期待するか」を具体的に定義しておくことで、内容の焦点が絞られ、効果測定もしやすくなります。
資料を作成する
勉強会で使用する資料は、内容の理解を促進し、後から振り返る際の参考になるものです。効果的な資料作成のポイントとして、以下の点に注意しましょう。
資料は視覚的に理解しやすいデザインを心がけ、図表やイラストを適切に活用します。また、実際の営業現場で使える具体例やケーススタディーを豊富に盛り込むことで、理解が深まります。
さらに、勉強会後も参照できるよう、詳細な説明や補足情報も含めておくと良いでしょう。
テーマに合わせた理解度クイズを用意する
学習内容の定着を図るために、テーマに合わせた理解度クイズを事前に用意しておくことが効果的です。クイズは単なる知識のチェックだけでなく、実践的な判断力や応用力を試すものが理想的です。
例えば、「この顧客の発言に対して、最も適切な返答はどれか」といった選択式の問題や、「この商品の主な特徴を3つ挙げてください」といった記述式の問題を用意しておきます。これらのクイズは勉強会中に実施するだけでなく、デジタルツールを活用して勉強会後のフォローアップにも活用できます。
営業勉強会で継続的・重点的に学ぶべき内容

営業勉強会の効果を最大化するためには、取り上げる内容を戦略的に選定することが重要です。
単なる商品知識の伝達にとどまらず、実践的な営業スキルの向上につながる内容を盛り込むことで、参加者の実務での成果につなげることができます。
商品やサービスの内容
最も基本的かつ重要な学習内容が、自社の商品やサービスに関する正確で深い知識です。営業パーソンが自信を持って顧客に説明できるレベルの理解が必要です。
商品やサービスの基本的な機能や特徴だけでなく、開発背景や技術的な強み、類似商品との差別化ポイントなど、多角的な知識を提供しましょう。特に重要なのは、「なぜこの商品・サービスが顧客の課題解決に役立つのか」という価値提案の視点です。
また、頻繁に寄せられる質問やよくある誤解とその対応方法についても共有することで、実際の商談での対応力が高まります。商品知識は単なる情報の暗記ではなく、顧客視点での価値理解につなげることが大切です。
商品やサービスの導入事例
実際の導入事例や成功事例は、営業活動において非常に説得力のある材料となります。営業勉強会では、典型的な成功事例をいくつか詳しく取り上げることで、参加者の提案力を高めることができます。
事例紹介では、導入前の顧客の課題や状況、導入プロセスでの工夫、導入後の効果や変化などを具体的に解説します。数値データや顧客の声を交えることで、説得力が増します。
また、単に成功事例だけでなく、導入時の障壁や懸念点とその克服方法についても触れることで、実際の営業シーンでの想定問答に備えることができます。異なる業種や規模の顧客事例を複数用意することで、さまざまな顧客タイプへの対応力も向上します。
商品やサービスの効果的な提案方法
商品知識があっても、効果的な提案ができなければ成約には結びつきません。営業勉強会では、商品・サービスの効果的な提案方法について具体的に学ぶことが重要です。
提案の基本的な流れや、ターゲット顧客ごとの訴求ポイントの違い、顧客の反応に応じた提案内容の調整方法などを解説します。特に効果的なのは、好業績者による実演やロールプレーイングを交えた実践的な学習です。
また、提案資料の効果的な使い方や、プレゼンテーションのコツ、オンライン商談と対面商談それぞれの特性に合わせた提案テクニックなども重要な学習内容です。提案は商品知識を生かすための「技術」であり、継続的な練習と改善が必要な分野です。
その他重点テーマ
上記の基本的な内容に加えて、営業チームや市場の状況に応じた重点テーマを設定することも効果的です。
例えば以下のようなテーマが考えられます。
|
営業勉強会で成果につなげるための効果的な進行方法
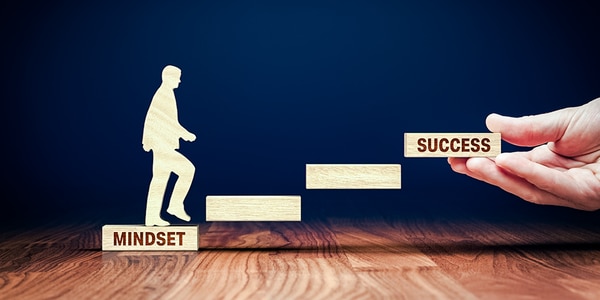
営業勉強会の内容が充実していても、進行方法が適切でなければ学習効果は限定的になってしまいます。
参加者の集中力を維持しながら、学びを最大化するための効果的な進行方法について解説します。
講義と演習の最適な配分
営業勉強会では、一方的な講義だけでなく、参加者が主体的に学ぶ演習の時間をバランスよく配分することが重要です。成人学習の原則として、単に聞くだけよりも実際にやってみることで学習の定着率が高まることが知られています。
講義パートでは、理論や背景知識を簡潔に伝え、演習パートでは学んだ内容を実践的に活用する機会を提供します。例えば、商品知識の講義を15分行った後、その商品の効果的な提案ロープレを15分間ずつペアワークで練習するといった構成が効果的です。
特に営業スキルの向上を目的とする場合は、講義と演習の比率を1:2程度にすることで、実践的なスキルの習得が促進されます。また、演習の前後に短い振り返りの時間を設けることで、学びの定着がさらに高まります。
グループワークの活用
営業勉強会の効果を高めるために、グループワークを積極的に取り入れることをおすすめします。グループワークは参加者間の相互学習を促進し、多様な視点や考え方に触れる機会を提供します。
効果的なグループワークのポイントとして、まず適切なグループ人数を考慮します。一般的には3〜5名程度が最適で、全員が発言の機会を持てるようにします。また、グループの構成メンバーを工夫することも重要です。経験レベルが異なるメンバーを混ぜることで、ベテランから新人へのノウハウ共有が自然に行われます。
グループワークのテーマは具体的で、成果物が明確なものが望ましいです。例えば「この商品の主要な3つのセールスポイントを、異なる業種の顧客向けにそれぞれ整理する」といった課題が効果的です。
グループでの議論を促進するためのワークシートや参考資料も用意しておくと良いでしょう。
講義部分を録画する
営業勉強会の効果を長期的に持続させるためには、講義部分を録画しておくことが非常に有効です。録画しておくことで、参加者は後から内容を復習できるだけでなく、当日欠席した営業パーソンも学習内容にアクセスできるようになります。
録画する際のポイントとして、映像の画質やサウンドの明瞭さに注意を払うことが重要です。特にスライドの文字が読めることや、講師の声がはっきり聞こえることを確認しましょう。また、長時間の録画よりも、テーマごとに10〜15分程度に区切られた短い動画の方が、後から視聴しやすく効果的です。
録画した内容は社内のラーニングプラットフォームに保存し、簡単にアクセスできるようにしておきます。必要に応じて内容にタグ付けやインデックスを作成すると、必要な情報を素早く見つけられるようになります。
営業勉強会で効果的にロールプレーイングを実施する方法

ロールプレーイングは営業勉強会において最も効果的な学習手法の1つです。実際の商談場面を想定した練習を通じて、理論的な知識を実践的なスキルへと昇華させることができます。
ここでは、効果的なロールプレーイングの実施方法について解説します。
オンラインで行う
現代のビジネス環境では、オンラインでのロールプレーイングが重要性を増しています。オンラインでのロールプレーイングは、実際のオンライン商談に近い環境で練習できるという大きなメリットがあります。特にコロナ禍以降、オンライン商談の機会が増加していることから、オンラインでの商談スキルを磨くことは不可欠です。
オンラインでロールプレーイングを行う際は、使用するビデオ会議ツールの機能を最大限に活用します。画面共有機能を使って提案資料を見せながらの説明練習や、チャット機能を活用した補足情報の伝え方なども含めて練習できます。また、録画機能を使えば、後から自分のパフォーマンスを客観的に振り返ることが可能になります。
オンラインロールプレーイングでは、対面時とは異なる注意点もあります。例えば、カメラ目線や音声の明瞭さ、背景環境の整備など、オンライン特有の要素にも気を配る練習ができます。
ブレークアウトで3人1組で行う
ロールプレーイングを効果的に実施するためには、3人1組のグループ構成が理想的です。この形式では、1人が営業役、1人が顧客役、そして1人が観察者・フィードバック役を担当します。
3人1組の構成には、いくつかの重要なメリットがあります。まず、営業役と顧客役の2人だけでは気づかない点を、第三者の視点で観察者が指摘できます。また、ロールプレーイングに直接参加していない時間も、観察者として学びがあるため、時間の有効活用につながります。
実施の際は、オンライン会議ツールのブレークアウトルーム機能を活用して、複数のグループが同時並行で練習できるようにします。各グループには明確なシナリオとタイムテーブル(例:営業役10分、フィードバック5分、役割交代)を提供し、全員が各役割を経験できるようにローテーションします。
勉強会後にロープレの練習ができる場を用意する
営業勉強会の効果を最大化するためには、1回限りのロールプレーイングではなく、継続的に練習できる環境を整備することが重要です。定期的な「ロープレ練習会」を設けることで、スキルの定着と向上が図れます。
具体的には、週1回の「朝ロープレ」や月2回の「スキルアップセッション」など、定期的に短時間でロールプレーイングを行う機会を設けます。これらのセッションでは、その時々のホットトピック(新商品の提案方法や、よくある顧客の反論への対応など)をテーマにすることで、実践的な内容になります。
また、自主的なロールプレーイング練習を促進するために、オンラインプラットフォーム上に「練習部屋」を常設しておくのも効果的です。営業パーソン同士が空き時間を利用して自発的に練習できる環境があると、学びの文化が醸成されていきます。
▼ロープレのテンプレートについては下記で詳しく解説しています。
⇒営業ロープレのテンプレートとは?一般的な実施の流れを解説!
営業勉強会後、成果につなげるための効果的な流れ

営業勉強会を開催した後も、学習効果を最大化するためのフォローアップが重要です。
勉強会当日に得た知識やスキルを定着させ、実践につなげるための具体的な流れを解説します。
①録画した講義をテーマごとに分割し、マイクロラーニングを作成する
勉強会で録画した講義内容を、5〜10分程度の短いセグメントに分割することで、効果的なマイクロラーニングコンテンツを作成できます。人間が集中できる時間はどんどん短くなっているという研究結果もあり、短く区切られたコンテンツの方が、学習効率が高まります。
例えば、1時間の商品知識の講義であれば、「商品の基本機能」「競合製品との比較」「導入事例」「よくある質問と回答例」といったテーマ別に分割します。各セグメントには明確なタイトルとタグを付け、必要な時に素早く目的の内容にアクセスできるようにします。
マイクロラーニングは営業パーソンの移動時間や空き時間を活用した学習を可能にし、繰り返し視聴することで知識の定着を促進します。特に新人営業パーソンにとっては、自分のペースで基本知識を学べる貴重なリソースとなります。
②理解度クイズをセットにする
学習内容の定着度を高めるために、マイクロラーニングのセグメントごとに理解度クイズをセットにすることが効果的です。クイズは単なるテストではなく、学習者が自分の理解度を確認し、重要ポイントを再確認するための手段です。
クイズの形式としては、選択式の問題だけでなく、「この状況でどう対応するか」という実践的な判断を問う問題や、「この商品のセールスポイントを3つ挙げてください」といった記述式の問題も効果的です。理解度クイズは、正解・不正解だけでなく、補足説明や解説を含めることで学習効果がさらに高まります。
また、理解度クイズの結果を可視化することで、営業パーソンの学習モチベーションを高めることができます。例えば、チーム内でのランキング表示や、達成バッジの付与といったゲーミフィケーション要素を取り入れることも一案です。
③動画提出課題をセットにする
マイクロラーニングと理解度クイズに加えて、学んだ内容を実践するための動画提出課題を設定することで、知識の活用力が高まります。例えば、「新商品の特徴を2分以内で説明する動画」や「想定される顧客の疑問に答えるロープレ動画」などを提出する課題が効果的です。
動画提出課題のメリットは、学習者が実際にアウトプットする機会を得られることにあります。人前で話す練習になるだけでなく、自分の説明の仕方や表現方法を客観的に振り返ることができます。
また、提出された動画に対して上司やトレーナーからフィードバックがあれば、さらに効果的な学習サイクルが構築できます。
動画撮影のハードルを下げるために、スマートフォンでの簡易撮影でもOKとすることや、最初は非公開での提出から始めるなどの配慮も大切です。慣れてきたら、優秀な事例を社内で共有するなど、ナレッジの横展開にも活用できます。
④意見投稿フォームを用意する
営業パーソン同士が知識や経験を共有するための意見投稿フォームを用意することで、集合知を活用した学習環境が構築できます。例えば、「このトークがうまくいった」「この説明方法が顧客に評判が良かった」「この質問にどう答えるべきか」といった実践的なノウハウについて、情報の交換の場となります。
意見投稿フォームは単なる質問箱ではなく、営業現場からのフィードバックを収集する重要なチャネルです。ここで集められた情報は、次回の勉強会のテーマ設定や内容改善に生かせるだけでなく、営業マニュアルの更新にも役立てることができます。
効果的な運用のためには、定期的に投稿内容を整理・分析し、有用な情報をハイライトしたり、特に参考になる投稿に対して「いいね」機能などで評価できる仕組みを設けたりすると良いでしょう。営業管理職やトレーナーからのコメントも積極的に行うことで、活発なコミュニケーションが生まれます。
⑤ ①~④をプラットフォーム上で運用する
上記の取り組みを効果的に実施するためには、一元管理できるプラットフォーム上で運用することが理想的です。社内のラーニングマネジメントシステム(LMS)やラーニングプラットフォームを活用することで、学習者の利便性が高まり、管理側の運用効率も向上します。
プラットフォームの選定においては、使いやすさを最優先することが重要です。複雑な操作が必要なシステムでは、営業パーソンの利用率が低下してしまいます。スマートフォンからのアクセスのしやすさや、通知機能の充実度、動画の視聴・アップロード機能の使い勝手なども重要な選定基準です。
また、学習データの分析機能があるプラットフォームを選ぶことで、「どの営業パーソンがどのコンテンツをどれだけ学習したか」「理解度テストのスコアはどうか」といった情報を把握でき、効果測定や次回の勉強会計画に生かすことができます。
営業勉強会の効果を具体的に測定する方法とは

営業勉強会は実施して終わりではなく、実施後にその効果を測定しておくことも重要です。効果測定の流れとポイントを紹介します。
① 勉強会で扱ったテーマの業績をウオッチする
営業勉強会の効果を測定するためには、まず勉強会で扱ったテーマに関連する具体的な業績データを追跡することが重要です。
例えば、新しい商品を勉強会で取り上げた場合、新しい商品に関連する売上や顧客獲得数、成約率の変化をモニタリングします。
期間を明確に定め、勉強会の開催前後での数字を比較することで、直接的な効果を把握することができます。
ここで注意する点は、業績にはさまざまな外部要因が影響を与えるため、勉強会のテーマだけに起因する変化なのかを慎重に見極めることが求められます。
② 参加者の学習行動のデータをウオッチする
次に、参加者の学習行動や姿勢に関するデータも観察します。具体的には、勉強会への参加率、勉強会後のフォローアップ活動(例えば、復習や実践の記録)、さらには自己評価や上司のフィードバックなどを含みます。
これらのデータを集めることで、参加者が勉強会の内容にどれだけ積極的に取り組んでいるかを理解することができるでしょう。
このような定量的および定性的なデータの収集は、勉強会の効果をより具体的に測定する上で欠かせません。
③ ①②の相関を調べてみる
最後に、①で収集した業績データと②で収集した学習行動データの相関を調べます。これにより、営業勉強会が業績に影響を与えたかどうか、どのような学習行動がより大きな効果をもたらしたかを理解できます。
統計的な手法を用いて相関分析を行うと、勉強会の内容が直接成果に貢献したかどうかを客観的に判断することが可能です。
例えば、勉強会後に特定の新しいスキルを実践した営業パーソンの成績が有意に向上していることが確認できれば、その勉強会が効果的であったと結論付けることができるでしょう。
この一連のプロセスを通じて、営業勉強会の効果をより正確に評価し、今後の勉強会の内容や形式を改善するための貴重なインサイトを得ることができます。
営業勉強会の講師は誰がやるのが最適といえるか?

営業勉強会の成否を決める、重要な要素の1つ、講師の選定です。適切な講師を選ぶことで、参加者の学習意欲が高まり、内容の信頼性や実践性も向上します。
ここでは、営業勉強会の講師として誰を起用すべきかについて解説します。
基本的に社内講師が行う
営業勉強会は基本的に社内講師が担当することをおすすめします。社内講師には、自社の商品・サービスについての深い理解や、実際の営業現場での経験、顧客特性の把握など、外部講師にはない強みがあります。
社内講師を起用するメリットとして、以下の点が挙げられます:
|
ただし、社内講師が効果的な勉強会を実施するためには、適切な準備と研修が必要です。
「営業がうまい人」が必ずしも「教えるのがうまい人」とは限らないため、講師となる人材には、資料作成のサポートやプレゼンテーション研修を行うなどの支援が有効です。
高業績者が行う
営業成績が優秀な高業績者を講師として起用することで、参加者の関心とモチベーションを高めることができます。
実際に成果を出している人物からの指導は説得力があり、「自分もできるようになりたい」という前向きな気持ちを引き出します。
高業績者を講師とする際のポイント:
|
また、高業績者の勘やセンスに依存した「再現性の低い手法」ではなく、他のメンバーも実践できる「再現性の高い手法」を重点的に共有するよう事前に調整することが重要です。
社内の商品やサービスの専門家が行う
商品知識や技術的な内容を深く学ぶ勉強会では、社内の商品・サービスの専門家(製品開発者、技術者、マーケティング担当者など)を講師として招くことが効果的です。
第一線で商品開発に携わる専門家からの説明は、単なるマニュアルでは得られない深い理解につながります。
専門家を講師とする際のポイントとして、以下の点に注意しましょう。
|
また、専門家と営業パーソンの橋渡しとなるモデレーター役を設けることで、より効果的な知識共有が可能になります。
モデレーターは、専門的な内容を営業視点で整理したり、参加者の疑問を代弁したりする役割を担います。
▼営業研修の講師については下記で詳しく解説しています。
⇒営業研修・セミナーは社内講師での実施が最適!?おすすめの理由を紹介!
営業勉強会を定期的・継続的に開催し成果につなげるコツ

営業勉強会は一度きりのイベントではなく、定期的に開催することで真の効果を発揮します。
継続的な学習環境を構築するための定期開催のコツについて解説します。
定期開催を習慣化させるスケジューリング法
営業勉強会を組織の文化として定着させるためには、計画的かつ効果的なスケジューリングが重要です。単発のイベントではなく、継続的な学習サイクルとして位置付けるための工夫が必要です。
効果的なスケジューリングのポイントとして、まず固定の曜日・時間帯を設定することが挙げられます。例えば「毎月第2火曜日の午前」といった具体的な設定にすることで、参加者も予定を立てやすくなります。
また、年間スケジュールを事前に公開し、各回のテーマも明確にしておくことで、参加者は自分に特に関連するテーマの回に重点的に参加するといった計画も立てられます。
営業のピークシーズンや四半期末などの繁忙期を避けたスケジューリングも重要です。参加者が「忙しくて参加できない」という状況を減らすことで、継続的な参加を促進できます。
さらに、短時間で頻繁に行う形式(例:週1回の30分勉強会)と、じっくり時間をかける形式(例:四半期に1回の半日勉強会)を組み合わせることで、学習効果を高めることができます。
継続的な参加を促す仕掛けづくり
営業勉強会の定期開催を成功させるためには、参加者のモチベーションを維持し、継続的な参加を促す仕掛けが欠かせません。
単なる「参加義務」ではなく、自発的に参加したいと思わせる工夫が必要です。
効果的な仕掛け:
|
さらに、単調さを避けるために、さまざまな形式(講義型、ワークショップ型、パネルディスカッション型など)を取り入れたり、時には外部講師を招いたりするなど、新鮮さを維持する工夫も大切です。
営業勉強会でよく陥りがちな失敗とその対策

営業勉強会を実施する際には、よくある落とし穴を事前に認識し、適切な対策を講じることが重要です。
ここでは、多くの企業で見られる典型的な失敗パターンとその対策について解説します。
一方的な講義形式に陥らないために
営業勉強会でよく見られる失敗の1つは、講師からの一方的な講義形式になってしまうことです。参加者は受動的に情報を聞くだけの状態となり、学習内容の定着率が低下するとともに、集中力も維持できなくなります。
この問題を解決するための対策としては、まず「90分講義型」よりも「30分講義+30分演習+30分振り返り」といった構成にすることが効果的です。また、講義中でも定期的に参加者に質問を投げかけたり、簡単なペアワークを取り入れたりすることで、能動的な参加を促すことができます。
デジタルツールを活用した双方向性の確保も重要です。例えば、オンライン投票ツールを使った即時アンケートや、チャット機能を活用した質問募集など、参加者が気軽に意見や質問を発信できる環境を整えましょう。講師の話を聞くだけでなく、参加者同士がディスカッションする時間を確保することも、一方通行を避けるために有効です。
参加者の経験レベルや役割に応じたグループ分けも検討しましょう。全員に同じ内容を一律に提供するのではなく、経験や役割に応じたコンテンツを提供することで、より効果的な学習が実現します。
現場で使えない「机上の空論」を避ける方法
もう1つの典型的な失敗は、勉強会で学んだ内容が実際の営業現場で使えない「机上の空論」になってしまうことです。理論的には正しくても、実際の商談シーンでは適用できないような内容では、参加者の信頼を失い、次回以降の参加意欲を削いでしまいます。
この問題を解決するためには、まず実際の営業現場で直面している具体的な課題やシナリオを題材にすることが重要です。営業日報や顧客からのフィードバック、失注分析などから得られる「リアルな課題」を取り上げ、それに対する解決策を考える形式が効果的です。
また、成功事例だけでなく、失敗事例も積極的に共有し、「何がうまくいかなかったのか」「どうすれば改善できたのか」を分析することも有用です。失敗から学ぶことで、より実践的な知識が得られます。
さらに、勉強会の内容を実践した結果を次回の勉強会で共有する「アクションラーニングサイクル」を構築しましょう。前回学んだことを実践してみて、「うまくいったこと」「難しかったこと」を共有し、さらに改善策を考えるというサイクルを回すことで、より現場に即した学びへと発展させることができます。
アウトプットを意識した営業勉強会で成果を上げた支援事例

社員数: 8,000名以上
事業:生命保険販売、資産運用
営業勉強会内容見直しの成果
~入社3カ月後の売上実績が従来の研修受講者と比較して3倍に~
アウトプット中心の学習で実践力を身に付けた上、研修中に学んだことを、動画でいつでもどこでも復習・確認ができる環境を作ることで、学習内容を実践につなげることができるようになりました。
その結果、 Teamsをつないでの従来の研修スタイルで学習した受講生集団と比較 しましたが、営業勉強会内容をバージョンアップした研修を受けた集団は、従来の研修を受講した集団と比較し、入社3カ月後の売上実績が3倍という飛躍的な成果を出しました。
トレーナースキルに依存せず、均一なレベルの初期教育が可能に
ライブでの講義ではなく、動画を活用した研修運営をすることで、高品質な研修情報を余すことなく再現することが可能となりました。
トレーナーリソースの効果的活用
従来は、毎月入社するキャリア採用社員の導入研修を毎月実施するため、トレーナーの方々はかなりのリソースを割かなければなりませんでした。
しかし、マイクロラーニングの導入により初期教育を効率化することで、そのリソースを営業管理職教育に充てることができるようになりました。
それにより、現場の指導力強化につなげることができ、学習の好循環を生んでいます。
取り組みの詳細
職種別オンボーディングプログラムを展開
キャリア入社後1カ月間の導入研修を、マイクロラーニングを活用した研修にバージョンアップしました。
事前学習、研修当日、事後学習全ての場面においてマイクロラーニングで知識のインプットを行い、研修当日は確認テストの解説や、受講生同士のディスカッション、質疑応答に比重を置くことなどで、カスタマイズ性の高い学習の提供を実現しています。
マイクロラーニングはそれまで社内で活用されていた動画をベースに、新たなコンテンツも社内トレーナーの方が中心となって作成しました。
研修中は特に「学んだことが現場でも生かせそうだ、使えそうだ」と思ってもらうための支援や関わりを重視することで受講生のエンゲージメント向上にもつなげています。
これまでのインプットは社内トレーナーの方がレクチャーしてインプットしていましたが、リニューアルしてからはレクチャーは全て動画に代替しました。
アウトプットを意識した学習デザイン
インプットして終わりにならないように、動画を活用し、受講者が研修で学んだことを生かしながら1人でも何度もAIを相手にセールストークを練習し、動画で提出するという環境を提供されています。
動画を見た研修トレーナーから、直属の上司・先輩から、他部署の上司・先輩から、そして同期からフィードバックを受けることができ、学習の深化につなげています。
また、動画を閲覧した上で学んだことや仕事に生かせそうなことを共有することで、自分の考えを整理しながら、他の受講生の意見に触れながら新たな学びを得るという、学習の相乗効果を生んでいます。
導入前の課題
研修がイベント化してしまっている
集合研修で社員にいくら良い内容を提供しても 、現場に戻った後は目の前の仕事をこなすことに集中してしまい、学んだことがその場限りとなってしまうことが多く見受けられました。
集まった場だけではなく、事前と事後の学習活動を充実化させ、学習を続けながら学んだことを仕事に生かすことができる環境を作るため、 マイクロラーニング・コホート型学習を導入しました。
個人の経験がポケットノウハウになってしまっている
現場で得られた成功事例や失敗事例が個人のものにしかなっておらず、ポケットノウハウ化してしまっていることに課題を感じていました。
個人の学びを暗黙知から形式知に変えていくことで、受講生同士の学びを促進しながら、組織全体のナレッジとして好循環を生み出していきたいという思いがありました。
まとめ:効果的な営業勉強会が組織にもたらす価値
これからの時代の営業勉強会とは?イベントで終わらせず成功させるポイントなどを徹底解説!について紹介してきました。
- 営業勉強会のデジタル化で業績を上げられる
- 営業勉強会とは?その目的と重要性
- 営業勉強会を開催すべき3つのタイミング
- 営業勉強会を成功させるための事前準備
- 営業勉強会で学ぶべき内容
- 営業勉強会の効果的な進行方法
- 営業勉強会でのロールプレーイング実施法
- 営業勉強会後の効果的な流れ
- 営業勉強会の効果を測定する方法
- 営業勉強会の講師は誰がやる?
- 営業勉強会を定期開催するコツ
- 営業勉強会でよくある失敗とその対策
- アウトプットを意識した営業勉強会で成果を上げた支援事例
営業勉強会は、単なる知識伝達の場ではなく、組織全体の営業力を底上げし、持続的な成長を実現するための重要な取り組みです。本記事で解説してきたように、適切なタイミングでの開催、綿密な事前準備、実践的な内容設計、効果的な進行方法、そしてデジタルツールを活用したフォローアップが、営業勉強会の成功を左右します。
特に重要なのは、1回限りのイベントではなく、継続的な学習サイクルとして営業勉強会を位置づけることです。勉強会で学んだことを実践し、その結果を次の勉強会で共有し改善するというPDCAサイクルを回すことで、組織全体の営業力は着実に向上していきます。また、デジタル化によって「いつでも・どこでも・繰り返し」学べる環境を整備することで、学習効果を最大化できます。営業勉強会を通じて、営業ノウハウの共有と標準化、コミュニケーションの活性化、成功体験の横展開が促進され、組織としての一体感も醸成されます。
これらの取り組みは、短期的な売上向上だけでなく、長期的な組織力強化と競争優位の確立にもつながるでしょう。営業という「人」が中心となる職種だからこそ、継続的な学習と成長の機会を提供する営業勉強会の価値は計り知れません。本記事で紹介した手法を参考に、御社の営業力向上に役立つ効果的な営業勉強会を実現してください。
LDcubeはリアルとデジタルを組み合わせた、最新の営業勉強会のサポートを行っています。無料のデモ体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードいただけます。
▼関連記事はこちらから。