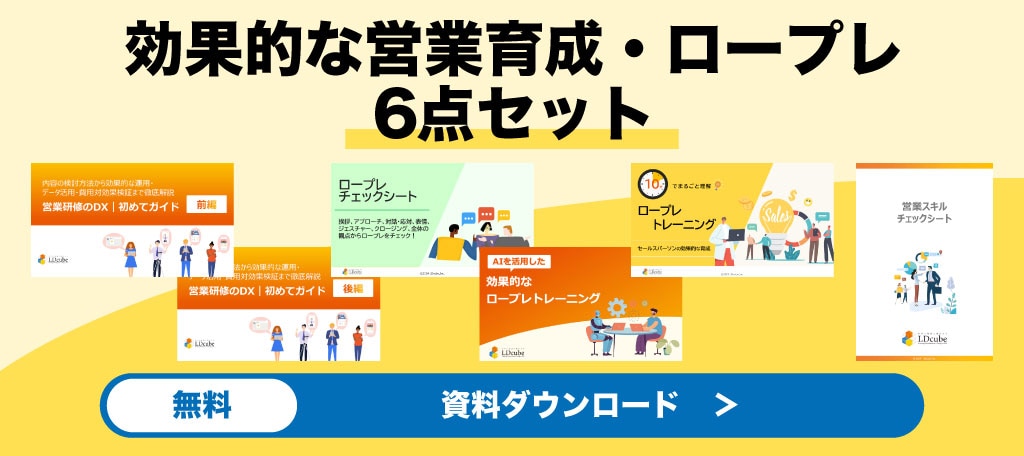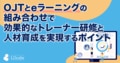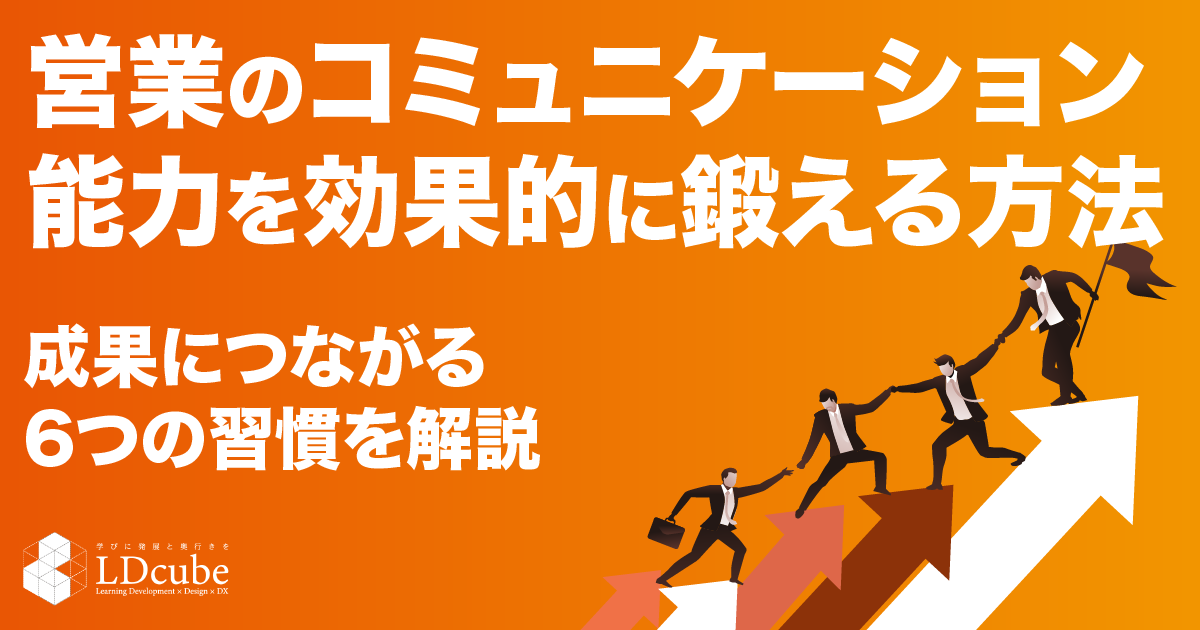
営業のコミュニケーション能力を効果的に鍛える方法とは?成果につながる6つの習慣を解説
「なかなか成約に結びつかない…」
「もっと顧客との会話をスムーズに進められたら…」
そのような悩みを抱える営業パーソンは少なくありません。営業の成果を左右する要素はさまざまですが、その中でも「コミュニケーション力」は最も重要なスキルの一つです。
顧客との信頼関係構築、ニーズの把握、提案、クロージングまで、営業のあらゆるシーンでコミュニケーションがカギを握ります。しかし、「営業コミュニケーションを高めたい」と思っても、具体的に何をすべきか迷ってしまうことも多いのではないでしょうか。
実は、成果を出している営業パーソンには共通する「コミュニケーションの習慣」があります。単なるその場しのぎのテクニックではなく、日々意識して実践することで自然と身に付いた習慣こそが、安定した営業成果につながるのです。
本記事では、営業成績を着実に向上させる「6つのコミュニケーション習慣」を紹介します。傾聴力、ニーズ発掘、信頼構築、説得力ある伝え方、継続的な自己改善など、成功している営業パーソンが実践している具体的な方法を解説します。
これらの習慣を日々の営業活動に取り入れることで、あなたの営業コミュニケーション力は確実に向上し、成約率アップにつながるでしょう。
▼営業ロープレの特集ページを作成しました。動画で解説しています。是非ご覧ください。 |
▼営業研修やロープレトレーニングについてはテーマに合わせて下記で解説しています。
▼営業やロープレでのスキルアップについてのお役立ち資料をセットしました。
目次[非表示]
- 1.営業の成果はコミュニケーション能力で決まる!
- 2.営業のコミュニケーション能力が成果に直結する理由
- 3.営業のコミュニケーション能力が高い人の特徴
- 4.営業のコミュニケーション能力は日々の習慣で確実に伸びる
- 5.習慣①アクティブリスニングを実践する
- 6.習慣②効果的な質問を心がける
- 7.習慣③適切なボディーランゲージを使う
- 8.習慣④さまざまな人と交流する
- 9.習慣⑤コミュニケーションの練習を続ける
- 10.習慣⑥振り返りの時間を持つ
- 11.営業のコミュニケーション能力を高めるために研修できっかけをつくろう!
- 11.1.自分のコミュニケーションスタイルを把握する
- 11.2.相手に合わせたアプローチのポイントを学ぶ
- 11.3.日々意識することを設定する
- 12.営業コミュニケーション研修を社内講師で展開した支援事例
- 13.職場でのコミュニケーション研修ならLIFO®がおすすめ!
- 14.まとめ:営業コミュニケーション力の向上で成果を上げる実践ステップ
営業の成果はコミュニケーション能力で決まる!

「あと一歩で契約に至らない…」「お客さまの本当のニーズがつかめない…」「提案を最後まで聞いてもらえない…」
このような悩みを抱える営業パーソンは少なくありません。多くの場合、その原因はコミュニケーション能力にあります。営業における成功と失敗を分けるのは、製品知識や営業テクニックだけではなく、お客さまとの信頼関係を構築し、真のニーズを引き出せるかどうかなのです。
コミュニケーションの語源はラテン語の「Communis(コミュニス)」で「分かち合うこと」を意味します。つまり、単に自社の製品やサービスを一方的に説明するのではなく、顧客と価値観や情報を共有し、共感を得ることが重要です。
メラビアンの法則によれば、相手に与える印象は、ボディーランゲージ(55%)、声のトーン(38%)、言葉の内容(7%)で構成されると言われています。つまり、何を話すかよりも、どのように話すかが重要です。
成果を出す営業パーソンに共通するのは、高いコミュニケーション能力を持っていることです。彼らは顧客の言葉に耳を傾け、真のニーズを引き出し、分かりやすく価値を伝え、さらには顧客の非言語的なサインを読み取ることができます。そして何より、これらのスキルを日々の習慣によって着実に伸ばしています。
コミュニケーション能力を高める習慣を取り入れることで、顧客との信頼関係を構築し、商談の成約率を高め、長期的な取引関係へとつなげることができるでしょう。さあ、あなたも営業コミュニケーション力を磨いて、成果を最大化しましょう。
営業のコミュニケーション能力が成果に直結する理由

営業活動において、コミュニケーション能力が高さによって、成果に大きな差が生じます。
優れたコミュニケーション能力を持つ営業パーソンは、単に話がうまいだけでなく、顧客の心理を理解し、ニーズを引き出し、適切なタイミングで効果的な提案ができます。その成果は直接的に営業成績という結果に表れます。
なぜコミュニケーション能力が営業成果に直結するのか、具体的に見ていきましょう。
顧客との信頼関係構築が営業成績を向上させる
営業の基本は信頼関係の構築です。どんなに優れた商品やサービスでも、顧客が営業パーソンを信頼していなければ、その価値を認めてもらうことは難しいでしょう。優れたコミュニケーション能力を持つ営業パーソンは、初回の接触から誠実さを示し、顧客との間に信頼の架け橋を築きます。
信頼関係の構築において重要なのは「誠実さ」です。例えば、質問に対して答えられないことがあった場合、曖昧な回答をするのではなく「確認して後ほどご連絡します」と正直に伝えることで、顧客は「この人は信頼できる」と感じます。また、約束を必ず守り、小さな約束も大切にする姿勢が信頼を育みます。
顧客は単に製品やサービスだけでなく、それを提供する「人」を信頼して購入を決断することが多いのです。高いコミュニケーション能力によって築かれた信頼関係は、一度きりの取引ではなく、継続的な取引や紹介につながります。実際、既存顧客からの追加購入やリピート率の向上は、新規顧客の獲得よりもコストがかからず、効率的に売上を伸ばすことができます。
顧客ニーズを正確に把握できるから提案の的確性が高まる
営業において最も重要なのは、顧客が抱える課題やニーズを正確に把握することです。コミュニケーション能力が高い営業パーソンは、効果的な質問とアクティブリスニングを通じて、顧客自身も明確に認識していないような潜在的なニーズまで引き出すことができます。
例えば、「御社の現状の課題は何ですか?」という直接的な質問ではなく、「現在のシステムを使う中で、どのような点に不便を感じていますか?」「理想的な状態はどのようなものでしょうか?」といった質問を通じて、顧客の真のニーズを深掘りします。そして、相手の話に真摯に耳を傾け、表情や声のトーンなどの非言語コミュニケーションからも情報を読み取ります。
顧客のニーズを正確に把握できれば、的確な提案が可能になります。これにより「この営業担当者は自分の課題を理解している」という信頼感が生まれ、提案内容への納得度が高まります。結果として、商談の成約率が向上し、顧客満足度も高まります。
効果的な説得と反論対応で成約率が上がる
優れたコミュニケーション能力を持つ営業パーソンは、顧客の反論や懸念に対して適切に対応することができます。彼らは製品やサービスの特徴を単に列挙するのではなく、顧客にとっての具体的なメリットを、データや事例を用いて論理的に説明します。
例えば、「この製品は操作が簡単です」と抽象的に説明するのではなく、「この製品を導入した他社では、従業員の研修時間が平均40%削減され、業務効率が25%向上しました」と具体的な数字を示すことで説得力が増します。また、顧客の業界や状況に合わせた事例を提示することで、共感を得やすくなります。
さらに、価格や導入リスクなどへの懸念に対しても、単に反論するのではなく、顧客の不安を理解した上で解決策を提示することが重要です。「確かにご懸念の点は理解できます。実は他のお客様も同様の心配をされていましたが…」と共感を示してから説明することで、抵抗感を和らげることができます。
このように、高いコミュニケーション能力によって効果的な説得と反論対応ができれば、顧客は安心して購入を決断できるようになり、成約率が大幅に向上します。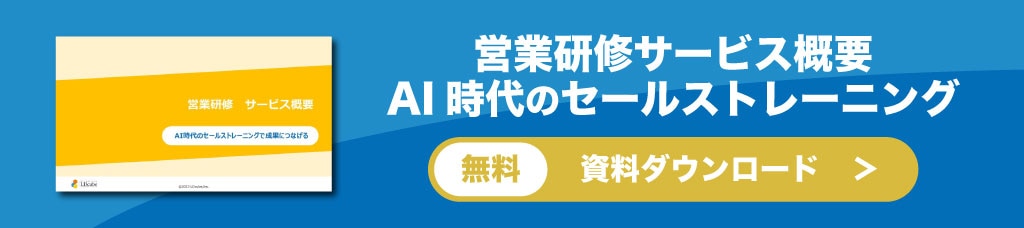
営業のコミュニケーション能力が高い人の特徴

優れた営業成績を上げる人々を観察すると、彼らには共通するコミュニケーション特性があることが分かります。単に話がうまいということではなく、顧客との対話全体を効果的に管理する能力を持っています。
どのような特徴があるのか、具体的に見ていきましょう。
顧客の話を引き出し、傾聴できる
コミュニケーション能力が高い営業パーソンの最大の特徴は、「傾聴力」が優れていることです。
彼らは顧客の話を途中で遮ることなく、最後まで聞く忍耐力を持っています。また、単に黙って聞いているだけではなく、相手の話に合わせて適切なタイミングで相槌を打ち、時には「つまり、〇〇ということでしょうか?」とオウム返しをして内容を確認します。
彼らは言葉だけでなく、顧客の表情や声のトーン、身ぶり手ぶりといった非言語的なコミュニケーションにも注意を払います。例えば、顧客が特定の話題に触れた際の微妙な表情の変化や、熱心に話す際の声のトーンの変化から、その人が真に関心を持っている点を見抜くことができます。
さらに、優れた質問力によって顧客の本音を引き出します。「はい」「いいえ」で答えられるクローズな質問ではなく、「その課題について、もう少し詳しく教えていただけますか?」「その機能を重視される理由は何でしょうか?」といったオープンな質問によって、顧客は自然と本音を話すようになります。
このように、傾聴と適切な質問によって顧客の真のニーズを把握することが、優れた営業パーソンの第一の特徴です。
相手の立場に立って考える共感力と柔軟な対応力がある
コミュニケーション能力が高い営業パーソンは、優れた共感力を持ち、常に相手の立場に立って物事を考えることができます。彼らは顧客の業界知識や課題に関する理解を深め、「お客さまがどのようなことに困っているのか」「何を実現したいのか」といった点を常に意識しています。
この共感力は言葉にも表れます。例えば、業界特有の専門用語を適切に使いこなし、顧客の状況に合わせた事例を交えて説明することで、「この人は自分たちの業界を理解している」という安心感を与えます。また、顧客の価値観を尊重し、たとえ自分と異なる意見であっても、否定せずに受け入れる姿勢を持っています。
さらに、状況に応じて柔軟に対応する能力も持ち合わせています。
例えば、プレゼンテーションの途中で顧客が特定の点に強い関心を示した場合、予定していた流れを変更してその話題を掘り下げたり、顧客の行動スタイルに合わせてコミュニケーションスタイルを変えたりすることができます。緊張している顧客には穏やかに接し、忙しい顧客には手短に要点を伝えるといった具合に、相手に合わせた対応ができます。
このような共感力と柔軟な対応力によって、顧客は「この人なら自分の課題を解決してくれる」と感じ、信頼関係が深まっていきます。
複雑な内容を分かりやすく伝える説明力を持っている
優れた営業パーソンは、複雑な製品やサービスの内容を、顧客がイメージしやすいように噛み砕いて説明する能力を持っています。専門用語や業界特有の言い回しを多用するのではなく、顧客の知識レベルに合わせた言葉を選び、必要に応じて図や比喩を用いて視覚的にも理解しやすくします。
彼らは「PREP法」などの構造化された説明方法を活用します。まず結論(Point)を述べ、次にその理由(Reason)を説明し、具体例(Example)を示し、最後に結論を再度強調(Point)するといった流れです。このような構造化された説明により、顧客は情報を整理しながら理解することができます。
優れた営業パーソンが用いる説得力を高める手法:
|
特に成功事例や導入事例を紹介することで、顧客は自社への適用をより具体的にイメージできるようになります。
このように、複雑な内容を分かりやすく伝えることによって、顧客の理解と納得を促し、購入の意思決定を後押しします。
営業のコミュニケーション能力は日々の習慣で確実に伸びる

「コミュニケーション能力は生まれつきのもので、後天的に身に付けるのは難しい」と思っている方もいるかもしれません。しかし、これは大きな誤解です。コミュニケーション能力は、適切な方法で継続的に練習することで、誰でも確実に向上させることができるのです。
コミュニケーション能力の向上は、ジムでの筋トレに似ています。一度や二度のトレーニングではなく、適切な方法で継続的に取り組むことで、少しずつ確実に成果が表れるものです。そして重要なのは、「習慣化」することです。日々の営業活動の中で意識的にコミュニケーションスキルを磨く習慣を身に付ければ、自然と能力が向上していきます。
優れた営業パーソンは皆、自分なりのコミュニケーション習慣を持っています。彼らは意識的に顧客の話に耳を傾け、効果的な質問をし、相手の立場に立って考え、分かりやすく説明する努力を日々続けています。これらの習慣は、最初は意識して行動する必要がありますが、繰り返すうちに自然と身に付いていきます。
ここからは、営業のコミュニケーション能力を高める6つの習慣を紹介します。これらの習慣を日々の営業活動に取り入れることで、あなたのコミュニケーション能力は確実に向上し、営業成績にも大きく反映されるでしょう。全てを一度に取り入れる必要はありません。まずは一つか二つから始めて、少しずつ習慣化していくことをおすすめします。
それでは、成果を出す営業パーソンの、6つのコミュニケーション習慣について、具体的に見ていきましょう。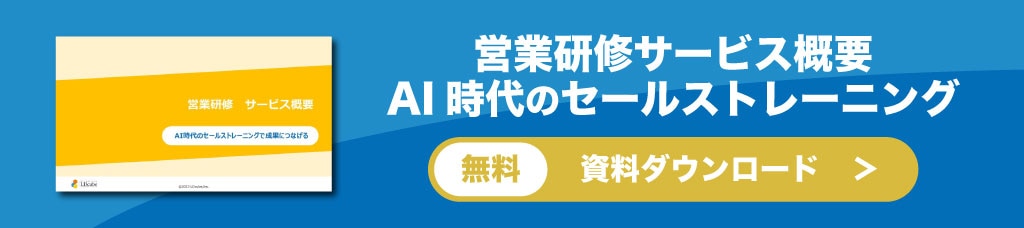
習慣①アクティブリスニングを実践する

営業のコミュニケーションで最も重要なのは、実は「話す力」ではなく「聴く力」です。アクティブリスニング(積極的傾聴)とは、単に相手の言葉を受け取るだけでなく、積極的に相手の意図を理解しようとする姿勢で聴くことです。
この習慣を身に付けることで、顧客との信頼関係構築が格段に進み、ニーズの正確な把握が可能になります。
営業シーンで活きるアクティブリスニングの実践法
アクティブリスニングを実践するには、まず相手に100%の注意を向けることが大切です。
スマートフォンや資料といった気が散るものから目を離し、顧客に集中しましょう。そして、相手の話に合わせて適切なタイミングで相槌を打ちます。「なるほど」「そうなんですね」といった言葉や、うなずきによって「あなたの話を聞いています」というメッセージを伝えることができます。
効果的なテクニックとして、「要約」と「確認」があります。顧客の話の要点を自分の言葉でまとめて「つまり、○○ということでしょうか?」と確認することで、理解の正確性を高めるとともに、顧客に「話をきちんと聞いてもらえている」という満足感を与えることができます。
また、沈黙を恐れないことも重要です。
顧客が考えを整理している時間を尊重し、すぐに話題を変えたり自分の意見を述べたりするのではなく、相手のペースに合わせましょう。質問をする際も、「はい」「いいえ」で答えられる閉じた質問ではなく、「どのような点が課題だと感じていますか?」といったオープンな質問を心がけ、顧客の言葉を引き出しましょう。
非言語コミュニケーションから顧客の本音を読み取る技術
アクティブリスニングでは、言葉だけでなく非言語コミュニケーションからも情報を読み取ることが重要です。顧客の表情、姿勢、声のトーン、身ぶり手ぶりなどから、言葉では表現されていない感情や本音を察知できるようになりましょう。
例えば、プレゼンテーション中に顧客が腕を組んだり、視線を逸らしたりする場合は、提案内容に抵抗を感じているサインかもしれません。逆に、前のめりの姿勢や頻繁なうなずきは、関心を示しているサインです。声のトーンが上がったり、話すスピードが速くなったりする点にも注目しましょう。これは特定の話題への興奮や関心を示している可能性があります。
また、複数人での商談では、意思決定者と影響力を持つ人物の反応を特に注視することが大切です。彼らの微妙な表情の変化や、お互いの視線のやり取りなどから、真の関心事やグループ内の力関係を読み取ることができます。
非言語コミュニケーションの読み取りは、訓練によって上達します。商談後に「相手のどのようなサインに気付いたか」を振り返る習慣をつけることで、徐々に繊細な変化にも気付けるようになるでしょう。
日常から営業に生かせる傾聴力トレーニング
傾聴力は営業の場だけでなく、日常生活の中でも鍛えることができます。友人や家族との会話でも意識的にアクティブリスニングを実践してみましょう。話の内容を頭の中で要約する練習や、相手の言葉を自分の言葉で言い換えて確認する習慣をつけることが効果的です。
具体的なトレーニング方法としては、以下のようなものがあります。
|
また、録音した自分の会話を聞き返すことも効果的です。自分が相手の話をどれだけ遮っているか、質問は適切か、相槌のタイミングはどうかなどを客観的に分析します。
アクティブリスニングは、営業成績に直結する重要なスキルです。顧客の声に真摯に耳を傾け、言葉の奥にある真のニーズや感情を理解できるようになれば、的確な提案が可能になり、成約率は大きく向上するでしょう。
習慣②効果的な質問を心がける

アクティブリスニングと並んで重要なのが、効果的な質問をする習慣です。質問は単に情報を集めるだけでなく、顧客自身が気付いていなかった課題やニーズを掘り起こし、深い対話を生み出すための強力なツールです。
適切な質問によって商談の流れをコントロールし、顧客の真のニーズを引き出すことができます。
効果的な質問で顧客の真のニーズを引き出す営業トーク
効果的な質問は、顧客との対話を深め、真のニーズを明らかにします。
質問には大きく分けて「クローズド・クエスチョン」と「オープン・クエスチョン」の2種類があります。クローズド・クエスチョンは「はい」「いいえ」で答えられる質問で、特定の事実を確認する際に有効です。一方、オープン・クエスチョンは「どのように」「なぜ」「どのような点が」などで始まる質問で、顧客の考えや感情を引き出すのに適しています。
営業トークでは、この2種類の質問をバランスよく使い分けることが重要です。例えば、「現在のシステムに不満はありますか?」(クローズド)と確認した後、「どのような点に不便を感じていますか?」(オープン)と掘り下げると効果的です。また、「具体的には」「もう少し詳しく」といった言葉を添えることで、より詳細な情報を引き出すことができます。
効果的な質問順序の例を挙げると、まず状況を把握する質問(「現在どのような業務プロセスをお使いですか?」)から始めます。
次に、課題を明確にする質問(「そのプロセスでどのような困難がありますか?」)、そして影響を探る質問(「その課題によってどのような影響が出ていますか?」)へ進み、最後に理想の状態を確認する質問(「理想的にはどのような状態を実現したいですか?」)で締めくくるという流れが効果的です。
潜在的ニーズを発掘する戦略的質問テクニック
顧客が明確に認識している顕在ニーズだけでなく、気付いていない潜在ニーズを発掘することが、優れた営業パーソンの真価です。潜在ニーズを発掘するためには、戦略的な質問テクニックが役立ちます。
「そもそも質問」は既存の前提や常識を疑う質問です。
例えば「そもそもなぜその方法で行っているのですか?」と尋ねることで、顧客が当たり前と思っている業務プロセスの非効率性に気付かせることができます。「もし~だったら?」という仮説質問も効果的です。「もし作業時間が半分になったら、どのような変化が生まれますか?」といった質問は、顧客に新たな可能性を想像させます。
「比較質問」も潜在ニーズを引き出すのに役立ちます。
「他社と比較して、どのような点が優位ですか?また、改善が必要な点は?」と尋ねることで、競合との差別化ポイントや課題を浮き彫りにできます。「未来質問」として「3年後、御社はどのような状態になっていたいですか?」と尋ねれば、顧客の長期的なビジョンや戦略的課題が見えてきます。
また、「周辺質問」も有効です。
直接的な業務だけでなく、関連する部門や前後の工程について質問することで、全体最適化の視点からのニーズを発見できます。例えば「この業務の前後の工程ではどのような課題がありますか?」と尋ねることで、部門間の連携に関する潜在ニーズが見えてくるかもしれません。
これらの戦略的質問を使いこなすコツは、質問の目的を明確にし、顧客との信頼関係を築いた上で使用することです。また、質問攻めにならないよう、相手の状況や反応を見ながら適切なペースで進めることも重要です。
潜在ニーズを引き出す質問は、顧客に新たな気付きを与え、あなたを単なる営業担当者ではなく、ビジネスパートナーとして認識させる強力なツールとなります。
習慣③適切なボディーランゲージを使う

メラビアンの法則によれば、コミュニケーションにおいて相手に与える印象は、言葉の内容はわずか7%であり、声のトーンが38%、ボディーランゲージが55%を占めると言われています。つまり、何を話すかよりも、どのように話すかの方が重要なのです。
営業のプロフェッショナルは、この非言語コミュニケーションの力を最大限に活用し、適切なボディーランゲージを意識的に取り入れる習慣を身に付けています。
表情や声のトーンは明るい雰囲気にする
表情は「感情の窓」と言われるほど、私たちの内面を雄弁に物語ります。営業シーンでは、自然な笑顔と明るい表情を心がけることで、顧客に親しみやすさと誠実さを伝えることができます。特に初対面の印象は重要で、最初の7秒で相手はあなたについての印象の大部分を形成すると言われています。
自然な笑顔をつくるコツは、頬の筋肉だけでなく、目の周りの筋肉も使うことです。いわゆる「目が笑っている」状態をつくると、真の笑顔に近づきます。毎日鏡の前で練習することで、自然な笑顔を身に付けることができます。また、商談に入る前に深呼吸をして心を落ち着かせ、ポジティブな気持ちを思い出すことも効果的です。
声のトーンも印象を大きく左右します。声の高さ、速さ、大きさ、抑揚などを意識的にコントロールしましょう。一般的には、やや低めの声でゆっくりと話す方が信頼感を与えると言われています。また、重要なポイントで声の大きさや速さに変化をつけると、顧客の注意を引きつけることができます。興味や熱意を伝えるには、声に抑揚をつけて話すことが効果的です。
実践としては、スマートフォンで自分の声を録音して聞き返す習慣をつけましょう。自分の声の特徴や改善点を客観的に把握することができます。また、お気に入りの話し手(アナウンサーやプレゼンターなど)の話し方を観察し、参考にするのも良い方法です。
身ぶり手ぶりは大きめにする
適切な身ぶり手ぶりは、メッセージの理解を助け、話に生き生きとした印象を与えます。研究によれば、身ぶり手ぶりを交えた説明は、言葉だけの説明と比べて記憶に残りやすいことが分かっています。
営業シーンでは、やや大きめの身ぶり手ぶりを意識的に取り入れましょう。小さな動きは自信のなさや消極性を印象づけてしまうことがあります。特に重要なポイントを強調する際には、手のジェスチャーを効果的に使うことで、言葉の印象を強めることができます。
効果的な身ぶり手ぶりのコツは、自然さと目的を持った動きです。ただ手を動かすのではなく、話の内容に合わせた意味のある動きを心がけましょう。例えば、数字を示す際には指で数を表したり、比較する際には両手を使って違いを視覚的に示したりすることが効果的です。
また、姿勢も重要です。背筋を伸ばし、肩を開いた姿勢は自信と誠実さを示します。逆に、背中を丸めたり腕を組んだりする閉じた姿勢は、防衛的な印象を与えてしまいます。商談中は定期的に姿勢を意識し、開放的な姿勢を保つように心がけましょう。
効果的なアイコンタクトを使う
アイコンタクト(視線の合わせ方)は、信頼構築において極めて重要な要素です。適切なアイコンタクトは、「あなたに関心がある」「誠実に対応している」というメッセージを相手に伝えます。逆に、視線をそらし続ける営業パーソンに対して、顧客は不信感を抱きやすくなります。
日本人は欧米人と比較してアイコンタクトが少ない傾向がありますが、営業シーンでは意識的にアイコンタクトを増やすことが効果的です。ただし、じっと見つめすぎると相手に圧迫感を与えてしまうため、適度な加減が重要です。一般的には、会話中の50〜70%程度アイコンタクトを維持するのが理想とされています。
複数の顧客がいる場合は、話している間に全員と均等にアイコンタクトを取ることを心がけましょう。特に意思決定者とのアイコンタクトは重要ですが、他の参加者を無視すると悪い印象を与えてしまいます。
アイコンタクトのコツは、自然さと一貫性です。緊張していると視線が泳いでしまいがちですが、意識的に相手の目を見る習慣をつけることで改善できます。初めは3〜4秒程度のアイコンタクトから始め、徐々に自然に維持できるよう練習しましょう。
これらのボディーランゲージは、意識して練習することで必ず上達します。日常生活の中でもボディーランゲージ意識的に取り入れ、自然な習慣として身に付けることで、営業シーンでも自然と効果的なボディーランゲージが使えるようになるでしょう。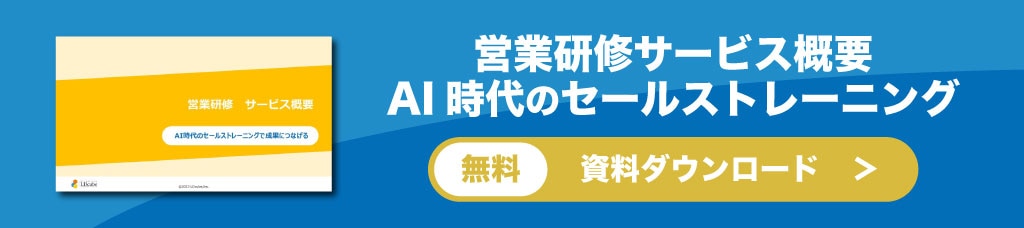
習慣④さまざまな人と交流する

コミュニケーション能力を高めるには、多様な人々との交流が欠かせません。さまざまなバックグラウンド、性格、コミュニケーションスタイルを持つ人と接することで、柔軟な対応力が養われ、顧客とのコミュニケーションがより円滑になります。
成功している営業パーソンの多くは、意識的に人脈を広げ、日常的に多様な人々と交流する習慣を持っています。
さまざまな人と交流し、コミュニケーションの絶対量を増やす
コミュニケーション能力の向上には、単純に「量」が重要です。会話の機会を増やし、さまざまな人と交流することで、コミュニケーションの筋肉が鍛えられていきます。これは、どのようなスポーツも練習量が成長のカギとなるのと同じ原理です。
社内では、自分の部署以外の人とも積極的に交流しましょう。異なる部署の人は異なる視点や知識を持っているため、会話から新たな気付きが得られます。また、昼食や休憩時間を利用して雑談する機会をつくることも効果的です。雑談は一見無駄に思えるかもしれませんが、実は円滑なコミュニケーションの基礎を築く重要な活動です。
社外でも、業界セミナーや交流会、勉強会などに積極的に参加しましょう。同業他社の人との交流は、業界の動向や共通の課題について話し合う貴重な機会となります。また、全く異なる業界の人と交流することにも視野を広げ、新たな発想を得るきっかけとなります。
コミュニケーションの絶対量を増やすことで、さまざまな状況や相手に応じた対応力が自然と身に付き、営業シーンでの柔軟なコミュニケーションにつながります。
相手のコミュニケーションスタイルをつかむ
人はそれぞれ異なるコミュニケーションスタイルを持っています。相手のスタイルを理解し、それに合わせたアプローチをすることで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。効果的なコミュニケーションは信頼関係の構築や目標達成のカギとなるため、ビジネスシーンでも日常生活でも重要なスキルです。
相手の話し方や反応の特徴を観察することで、そのスタイルを見極めることができます。適切に対応することで、誤解を減らし、より円滑な人間関係を築くことができるでしょう。
一般的なコミュニケーションスタイルは、以下の4つに分けられます。
|
相手のコミュニケーションスタイルを見極めるには、会話の内容や話し方、身ぶり手ぶり、反応の仕方などを注意深く観察しましょう。
例えば、質問の仕方や決断の下し方、会議での発言パターンなどから、そのスタイルを推測することができます。また、相手の好む環境や仕事の進め方、ストレス下での反応なども手がかりになります。
自分とは異なるスタイルの人とコミュニケーションする際は、柔軟に自分のアプローチを調整することが重要です。このような適応力は、多様な人々と効果的に協働するために不可欠なスキルと言えるでしょう。
相手に受け入れられやすいアプローチをする
相手のコミュニケーションスタイルを理解したら、次はそれに合わせたアプローチを心がけます。これは相手に合わせて自分を変えるということではなく、相手が最も受け入れやすい方法でコミュニケーションすることを意味します。
理想型の顧客には、相手の理想としている姿を確認し、その理想にフィットしているということを伝えていきましょう。そして、意義や目的を強調し、多くの人の役に立つことを示しましょう。世のためや人のためになるということに価値を感じてくれるでしょう。
論理型の顧客に対しては、提案の裏付けとなるデータや研究結果を準備し、論理的な説明を心がけましょう。感情的なアピールよりも、ROIや費用対効果といった具体的な数値を示すことが効果的です。質問にも正確に答え、不明点があれば「調査して後ほどご連絡します」と伝えることで信頼を築けます。
結論型の顧客には、時間を尊重し、簡潔かつ直接的なコミュニケーションを心がけましょう。プレゼンテーションは要点を絞り、結論から述べるようにします。選択肢を提示する際も、「AとBがありますが、御社の状況ではAがおすすめです」というように、あなたの提案を明確に伝えると良いでしょう。
感情型の顧客には、まず信頼関係の構築に時間をかけます。商談の冒頭で雑談の時間を設け、相手の話に共感を示しましょう。提案では、導入企業の声や事例を交えて、人間的な側面からの価値も伝えることが効果的です。また、サポート体制や導入後のフォロー体制についても詳しく説明すると安心感を与えられます。
相手に合わせたアプローチは、練習を通じて自然に身に付きます。日々の交流の中で意識的に実践し、反応を観察することで、徐々に洗練されていくでしょう。ただし、あくまで自然体であることを忘れないようにしましょう。演技じみた対応は逆効果となりますので、自分らしさを保ちながら相手に寄り添うバランス感覚が重要です。
▼相手に合わせたアプローチを診断付きで練習できる方法を公開しています。
⇒コミュニケーション能力を鍛える具体的な方法とは?診断付きで練習方法を公開!
習慣⑤コミュニケーションの練習を続ける

どのようなスキルも練習なしには上達しません。特にコミュニケーション能力は、意識的な練習と反復によって飛躍的に向上します。
一流のアスリートが試合前に何度も練習を重ねるように、優れた営業パーソンも重要な商談やプレゼンテーションの前に練習を欠かしません。
練習によって自信がつき、実際の商談での余裕が生まれるのです。ここでは、効果的なコミュニケーションの練習方法を紹介します。
頭の中でコミュニケーションのイメトレを行う
イメージトレーニング(イメトレ)は、実際の行動の前に頭の中でシミュレーションする方法です。スポーツ選手がパフォーマンス向上のために活用している手法ですが、営業コミュニケーションにも非常に効果的です。
商談やプレゼンテーションの前に、静かな場所で数分間の時間を取り、その場面を鮮明にイメージしましょう。顧客との会話の流れ、自分の説明、想定される質問と回答などを頭の中で具体的に思い描きます。できるだけ詳細に、視覚、聴覚、感覚など多感覚的にイメージすることがポイントです。
特に難しい質問や反論への対応をイメージしておくことで、実際にそのような状況が起きたときに冷静に対応できるようになります。「この提案は予算オーバーだ」「他社の製品との違いは何か」といった予想される質問に対して、最適な回答をイメージしておきましょう。
また、成功した状態をイメージすることも重要です。顧客が満足そうに頷いている様子、契約書にサインする場面など、ポジティブな結果をイメージすることで、自信と前向きなマインドセットが育まれます。
イメトレは移動中や待ち時間など、隙間時間を利用して行うことができます。日常的に実践することで、コミュニケーションの質と自信が着実に向上するでしょう。
一人で動画を撮影しコミュニケーションの癖をつかむ
自分のコミュニケーションスタイルを客観的に見るには、実際の様子を録画して分析することが非常に効果的です。スマートフォンを使って、自分のプレゼンテーションや営業トークを録画し、振り返ってみましょう。
録画を見返す際には、以下のポイントに注目します:
|
最初は自分の姿を見ることに抵抗を感じるかもしれませんが、これは非常に価値ある学習体験です。多くの人は、自分では気付いていなかった癖や改善点を発見します。
例えば、「思ったより早口だった」「『えーと』という言葉を多用している」「腕を組んで防衛的な姿勢になっている」といった点に気付くことができます。
特に効果的なのは、成功している営業パーソンや話し手のプレゼンテーションと自分のものを比較することです。彼らの効果的な技術を観察し、自分のスタイルに取り入れることで、短期間で大きく成長することができます。
定期的に録画と振り返りを行い、改善点を一つずつ意識的に修正していくことで、コミュニケーションスキルは着実に向上します。
AIを相手に練習する
テクノロジーの進化により、AIを活用したコミュニケーション練習も可能になりました。AIチャットボットやバーチャルアシスタントを相手に、営業トークやプレゼンテーションの練習をすることで、リアルタイムのフィードバックを得ることができます。
AIを活用するメリットは、いつでもどこでも、何度でも練習できる点です。人を相手にすると気まずさや緊張から何度も繰り返せないことも、AIなら何度でも挑戦できます。また、特定のシナリオや顧客のタイプに合わせた練習が可能で、実際の商談で起こりうるさまざまな状況に備えることができます。
例えば、「予算に非常に厳しい顧客」「技術的な詳細にこだわる顧客」「迅速な意思決定を求める顧客」など、さまざまなペルソナを設定し、それぞれに合わせたアプローチを練習することができます。AIからのフィードバックを基に、自分のアプローチを改善していくことで、実際の商談での対応力が向上します。
ただし、AIはあくまで補助ツールであり、実際の人間との練習も合わせて行うことが理想的です。同僚や先輩とのロールプレーイングや、信頼できる人からのフィードバックは、AIだけでは得られない価値ある学びをもたらします。AIと人間両方を練習相手として賢く活用することで、効率的にコミュニケーション能力を高めることができるでしょう。
習慣⑥振り返りの時間を持つ

コミュニケーション能力を着実に向上させるために欠かせないのが「振り返り」の習慣です。どんなに多くの商談やコミュニケーションの機会があっても、その経験から学びを得なければ成長は限られます。
トップセールスパーソンの多くは、日々の営業活動を丁寧に振り返り、そこから学びを得る習慣を持っています。この振り返りのプロセスを通じて、成功パターンを強化し、失敗から教訓を得ることができます。
毎日寝る前に簡単に振り返る
日々の営業活動を振り返るのに理想的なタイミングは、一日の終わり、特に寝る前の静かな時間です。たった5〜10分でも、意識的に振り返りの時間を持つことで、大きな効果が得られます。
振り返りのポイントは、その日のコミュニケーションで「うまくいったこと」と「改善できること」の両方に目を向けることです。
例えば、「今日の商談で顧客の本音を引き出せた質問は何だったか」「プレゼンのどの部分に顧客が最も関心を示したか」といったポジティブな側面と、「説明が冗長になってしまった箇所はどこか」「顧客の反論にもっと効果的に対応できたか」といった改善点の両方を考えます。
特に重要なのは、コミュニケーションの細部に注目することです。例えば、特定のフレーズや質問が顧客の反応を引き出したなら、それを意識的に記憶し、次回に生かしましょう。また、顧客が混乱や抵抗を示した瞬間があれば、どのような言い回しや説明方法が原因だったかを分析します。
この日々の振り返りは、形式的である必要はありません。静かに目を閉じて思い返すだけでも効果的です。大切なのは、日々の小さな気付きの積み重ねが、長期的に見れば大きな成長につながるという意識を持つことです。
気付いたことがあればメモしておく
振り返りの効果を最大化するためには、気付きや学びをメモに残す習慣が非常に効果的です。人間の記憶は曖昧で、時間の経過とともに薄れていきます。重要な気付きも、記録しなければ数日後には忘れてしまうかもしれません。
メモを取る方法は、デジタルでもアナログでも、自分に合った方法を選びましょう。スマートフォンのメモアプリ、ノート、営業日誌など、アクセスしやすく継続できる形式が理想的です。重要なのは、簡潔かつ具体的に記録することです。
例えば、「今日の○○社との商談で、『御社の現状のシステムでどのような点に不便を感じていますか?』という質問をしたところ、顧客が詳細に課題を話し始めた。この質問は効果的だった」といった具体的な記録が、後々の参考になります。
また、「プレゼン中に技術的な説明が長くなりすぎて、顧客の関心が薄れた。次回はもっと簡潔に、ベネフィットを中心に説明する必要がある」といった反省点も価値ある気付きです。
特に効果的なのは、成功した商談と失敗した商談の両方をメモすることです。成功事例からは再現可能な有効なテクニックを学び、失敗事例からは今後回避すべきポイントを明確にすることができます。これらの記録は、時間の経過とともに、あなた自身の「営業コミュニケーションの教科書」となります。
また、商談直後は記憶が鮮明なので、できるだけ早くメモを取ることをおすすめします。次の訪問先への移動中や、オフィスに戻ってすぐなど、できるだけ早いタイミングで記録しましょう。スマートフォンの音声メモ機能を使えば、移動中でも簡単に記録することができます。
改善点を意識して生活する
振り返りで見つけた改善点は、意識的に日常生活に取り入れることで定着します。例えば、「話すスピードが速すぎる」という改善点を見つけたなら、日常の会話でもペースを緩めることを意識しましょう。家族や友人との会話、電話応対など、あらゆる場面が練習の機会となります。
改善点を一度に多く取り入れようとすると、かえって混乱してしまいます。まずは一つか二つの重要な改善点に絞り、それらが自然と身に付くまで続けることが効果的です。例えば、最初の1週間は「アクティブリスニングの実践」、次の1週間は「効果的な質問の活用」というように、段階的に取り組むのがおすすめです。
また、改善点を目に見える場所に貼っておくのも効果的な方法です。デスクやスマートフォンの待ち受け画面など、頻繁に目にする場所に短い言葉で書いておくことで、常に意識することができます。「聴く→質問する→確認する」「顧客の言葉をそのまま使う」といったシンプルなリマインダーが、日々の行動変容を促します。
さらに、信頼できる同僚や上司にフィードバックを求めることも価値があります。自分では気付かない癖や改善点を指摘してもらうことで、より客観的な視点からコミュニケーションスキルを磨くことができます。「最近、○○を意識して取り組んでいるのですが、どう思いますか?」と具体的に尋ねることで、的確なフィードバックが得られるでしょう。
このように、振り返りを通じて得た気付きを日常生活に意識的に取り入れることで、コミュニケーション能力は着実に向上します。一つ一つの小さな改善の積み重ねが、長期的には大きな変化をもたらします。振り返りと実践のサイクルを続けることで、あなたのコミュニケーション能力は、営業成績に直結する強力な武器となるでしょう。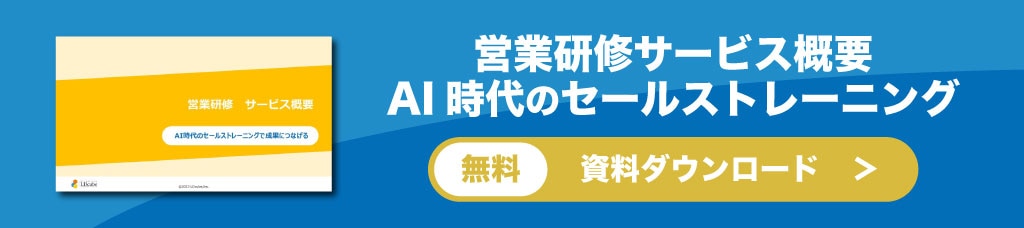
営業のコミュニケーション能力を高めるために研修できっかけをつくろう!

日々の習慣に加えて、専門的な研修を受けることで、営業のコミュニケーション能力は飛躍的に向上します。研修は新たな視点や技術を学ぶだけでなく、自分自身のコミュニケーションスタイルを客観的に見直す貴重な機会となります。
自分のコミュニケーションスタイルを把握する
コミュニケーション能力を高めるための第一歩は、自分自身のコミュニケーションスタイルを正確に把握することです。研修ではさまざまな診断ツールやフィードバックを通じて、自分の強みと弱みを明確にできます。
例えば、自分が「論理型」なのか「感情型」なのか、あるいは「結論型」か「理想型」なのかといったコミュニケーションスタイルの特徴を知ることで、自己理解が深まります。自分の強みを積極的に生かし、弱みを意識的に改善することで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。
また、研修ではビデオ録画やロールプレーイングなどを通じて、自分では気付かない癖や習慣を発見することもできます。例えば、「話すスピードが速すぎる」「相手の目を見ていない」「専門用語を多用している」など、改善すべきポイントが明らかになるでしょう。
相手に合わせたアプローチのポイントを学ぶ
効果的な営業コミュニケーションでは、相手のスタイルに合わせたアプローチが重要です。
研修では、さまざまな顧客のスタイルの特徴と、それぞれに効果的なコミュニケーション方法を学ぶことができます。
|
こうしたスタイル別アプローチを研修で学び、実践することで、さまざまなタイプの顧客と効果的にコミュニケーションを取る能力が身に付きます。
相手のスタイルを見極め、適切なアプローチを選択することが、営業成績向上のカギとなるのです。
日々意識することを設定する
研修で学んだことを実務に生かすためには、日々意識して取り組む具体的な目標を設定することが重要です。研修の最後には、各自が「コミュニケーション改善プラン」を作成し、すぐに実践できる具体的な行動目標を明確にします。
例えば、「毎日最低3人の顧客に対してアクティブリスニングを実践する」「商談の前に相手のタイプを予測し、適切なアプローチを計画する」「週に1回は自分のトークを録音して振り返る」といった具体的な目標を設定します。
また、研修後も継続的に学びを深めるために、定期的なフォローアップや自己啓発のための読書なども重要です。コミュニケーション能力の向上は一朝一夕では達成できないため、長期的な視点で継続的に取り組むことが成功へのカギとなります。
営業コミュニケーション研修を社内講師で展開した支援事例
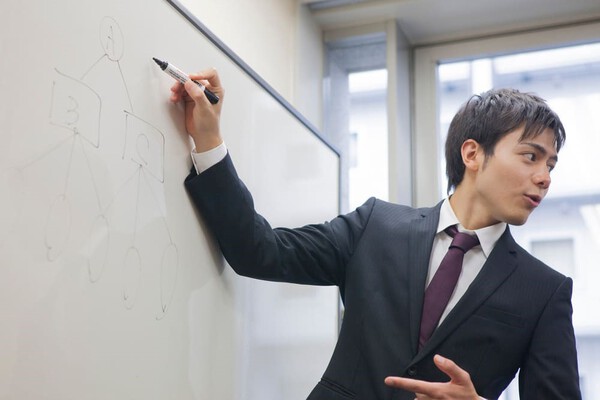
社員数: 2,000名以上
事業:医薬品、機能食品の製造・販売
導入前の課題
コロナ禍による営業スタイルの変化と職場のコミュニケーション減少
~打開のカギを握るのは営業所長~
製薬業界の取り巻く環境変化の一つとして、withコロナ時代においてテレワークが推進され、営業所内での「対面でのコミュニケーション」は圧倒的に減少していました。
特にコロナ前まではできていた横や斜め(同僚間や別部門)の関わりが少なくなり、業務上の全ての判断や相談がラインの上長に集中するようになりました。出社することで自然と社内情報が入ってきていた環境が、コロナ禍によりなくなってしまいました。
また、MR(医薬情報担当者)の情報提供活動においてもオンラインでの対応が求められるようになり、新しい方法を模索しないといけない状況になりました。
営業所内の目標達成や職場内のコミュニケーション向上のカギは営業所長が握っていることから、営業所長がリーダーシップを発揮し、問題解決をしていくための方法を探していました。
取り組みの詳細
営業所長による職場ワークショップを完全オンラインで実施
~半年間で7割以上の営業所に展開~
MRを取り巻く環境変化に合わせて、マインドやスキル強化の一つとしてLIFOプログラムの導入を決めました。
3年でLIFOを社内の共通言語にすることを目指して、まずは2020年5月に営業部門の教育担当4名がLIFOプログラムライセンスを取得しました。
次に営業所長がリーダーシップを発揮し、自職場の問題解決を行うスキルを習得するために、営業所長対象にマネジメント実践スキル講座(MSS認定講座)を実施しました。
講座を通じて、職場の問題解決のための道具とスキルを身に付けた営業所長は各職場にてチームづくりワークショップを実施しました。
4名のプログラムライセンス取得者(ライセンシー)は営業所長への個別指導や相談会など、職場展開に向けてのサポートを積極的に行いました。
コロナ禍ということもあり、プログラムライセンス取得から、MSS認定、ワークショップ実施まで全てオンラインで実施し、半年間で7割以上の営業所に展開していきました。
2021年度以降、新任営業所長はMSS認定講座を受講し、LIFOという道具とスキルを身に付ける機会を作っています。
2023年度現在では全ての営業所でチームづくりワークショップの実施が完了し、2巡目以降は各職場の課題に合わせてタイムマネジメントや期待役割などのテーマで実施しています。
導入の成果
「コミュニケーションの改善が期待できる!」「他部署へもLIFOを推薦したい!」の声多数
ワークショップ実施後に行ったアンケートでは、7割以上の方が「LIFO診断を受けて、自己理解ができた」、「部署内のグループワークの実施により他者理解ができた」、「LIFOの実施によりコミュニケーションの改善が期待できる」と回答をいただいています。
また、営業所長の9割近くの方が「LIFOの導入を他部署へも推薦したい」と回答いただきました。
タイムマネジメントのワークショップを実施した営業所においては、チーム活動を効果的に進めるためのガイドラインを決めることで、チームの結束力が高まったといった声もありました。
営業部門での評判を聞き、人事部門でもLIFOプログラムライセンスを取得し、経営幹部を巻き込むと同時に、本社の各部門においてもワークショップを順次進めています。
導入から3年が経過し、LIFOが社内の共通言語になりつつあります。
職場でのコミュニケーション研修ならLIFO®がおすすめ!

職場でのコミュニケーション研修には自己診断ツールLIFO(Life Orientations)を活用した研修プログラムがおすすめです。
なぜなら、LIFOプログラムは心理学や行動科学をベースにして組み立てられた行動特性診断をベースに、職場単位でワークショップを行うためのワークブックなどのツールも体系的にそろえられているからです。
また、体系立てられたツールの使い方を社内トレーナーの方々にライセンス提供もされており、社内トレーナーの方々が職場単位でワークショップを展開していくことも可能です。下記に概要を紹介します。
自己診断ツールLIFOとは
LIFO(Life Orientations)は、個人の行動スタイルを診断する自己診断ツールです。
このツールは、自分の強みや行動パターンを理解するために役立ちます。LIFOは4つの基本スタイルに基づいており、これらのスタイルはそれぞれ異なる行動特性や価値観を持っています。
自分がどのスタイルに属しているかを知ることで、より良いコミュニケーション方法やストレス時の行動傾向を把握することができます。
LIFOを活用したコミュニケーション研修
LIFOを活用したコミュニケーション研修では、まず参加者が自己診断を行い、自分の行動スタイルを理解します。この診断結果をもとに、どのようにして他者と効果的にコミュニケーションを取るかを学びます。
研修では以下のような内容が含まれます。
|
LIFOを取り入れた研修に参加することで、個人のコミュニケーションスタイルを理解し、それをベースに他者との関係を改善するスキルを獲得できます。
これにより、職場や日常生活でのコミュニケーションがよりスムーズで効果的になることが期待できます。
LIFO®プログラムは社内トレーナーで展開可能
LIFO®プログラムは、これまでの活用実績と実用性から、企業内でのトレーニングにおいて自信を持っておすすめできるプログラムです。
社内展開にあたっては、特定の準備と手続きを経ることで、コストを抑えながら、外部講師に委託したかのように、社内トレーナーによる効果的なプログラムを展開することが可能です。
以下に、その流れを詳しく説明します。
|
これにより、参加者はより実践的な、日常業務につながる研修を受けることが可能です。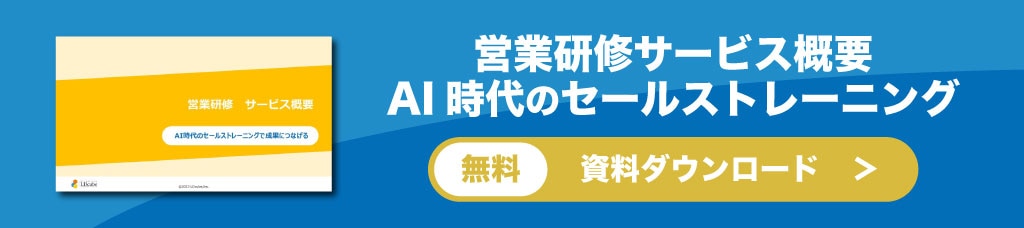
まとめ:営業コミュニケーション力の向上で成果を上げる実践ステップ
営業のコミュニケーション能力を効果的に鍛える方法とは?成果につながる6つの習慣を解説!について紹介してきました。
- 営業の成果はコミュニケーション能力で決まる!
- 営業のコミュニケーション能力が成果に直結する理由
- 営業のコミュニケーション能力が高い人の特徴
- 営業のコミュニケーション能力は日々の習慣で確実に伸びる
- 習慣①アクティブリスニングを実践する
- 習慣②効果的な質問を心がける
- 習慣③適切なボディーランゲージを使う
- 習慣④さまざまな人と交流する
- 習慣⑤コミュニケーションの練習を続ける
- 習慣⑥振り返りの時間を持つ
- 営業のコミュニケーション能力を高めるために研修できっかけをつくろう!
- 営業コミュニケーション研修を社内講師で展開した支援事例
- 職場でのコミュニケーション研修ならLIFO®がおすすめ!
営業における成功はコミュニケーション能力によって大きく左右されます。営業のコミュニケーション能力は、顧客との信頼関係構築、真のニーズの把握、効果的な説得といった成約に直結する要素を支える基盤です。そして何より、この能力は日々の習慣を通じて誰でも着実に向上させることができます。
本記事で紹介した6つの習慣ーーアクティブリスニング、効果的な質問、適切なボディーランゲージの活用、多様な人との交流、継続的な練習、振り返りーーは、営業成績を向上させたい全ての営業パーソンにとって実践価値のある内容です。これらの習慣を一度に取り入れる必要はありません。まずは自分が最も改善したい領域から始め、少しずつ習慣化していくことが大切です。
コミュニケーション能力の向上は、一夜にして実現するものではありません。しかし、日々の小さな努力の積み重ねが、やがて大きな成果となって表れます。
例えば、アクティブリスニングを意識することで顧客の真のニーズを引き出せるようになれば、より的確な提案が可能になり、成約率は自然と高まります。効果的な質問によって顧客も気付いていなかった潜在ニーズを発掘できれば、競合他社との差別化につながります。
また、コミュニケーション能力の向上は営業成績だけでなく、キャリア全体にポジティブな影響をもたらします。社内での信頼関係構築、チームワークの向上、リーダーシップの発揮など、ビジネスパーソンとしての総合的な価値を高めることにつながるのです。
今日から始められることとして、まずは自分のコミュニケーションの現状を客観的に振り返ってみましょう。強みは何か、改善点は何か、そしてどの習慣から始めるべきかを考えます。そして、選んだ習慣を一つずつ意識的に実践していきましょう。
最初は意識して行う必要がありますが、繰り返すうちに自然と身に付き、やがてあなたのコミュニケーションスタイルの一部となります。
最後に、コミュニケーション能力の向上は終わりのない旅です。常に学び、実践し、振り返ることで、継続的に成長していきましょう。営業の世界は常に変化していますが、優れたコミュニケーション能力は、どのような時代や環境でも価値を失わない普遍的なスキルです。
この記事で紹介した習慣を取り入れ、あなたの営業コミュニケーション力を磨き続けることで、より多くの成果を上げられることを願っています。
株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会やeラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など、幅広くご支援をしています。また、AIチャットボットを活用したセールスロープレのデジタル化の支援や、無料デモ体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。