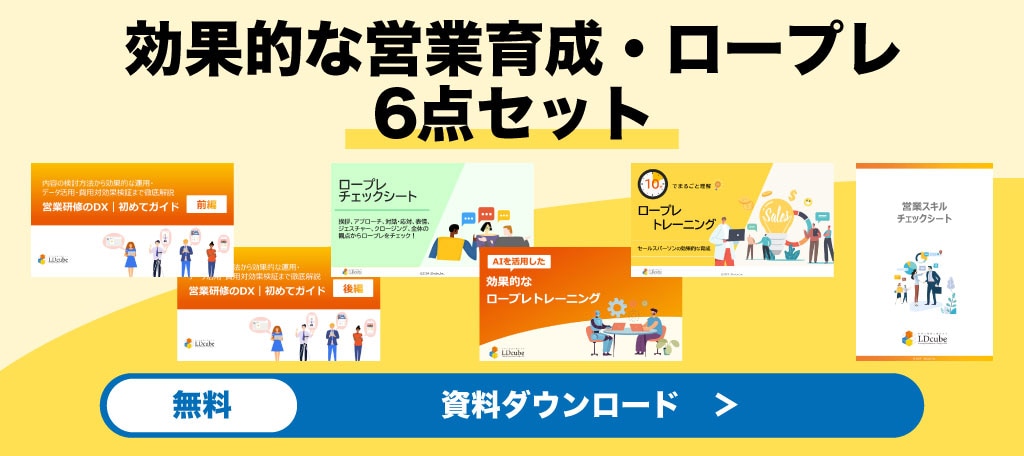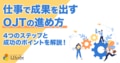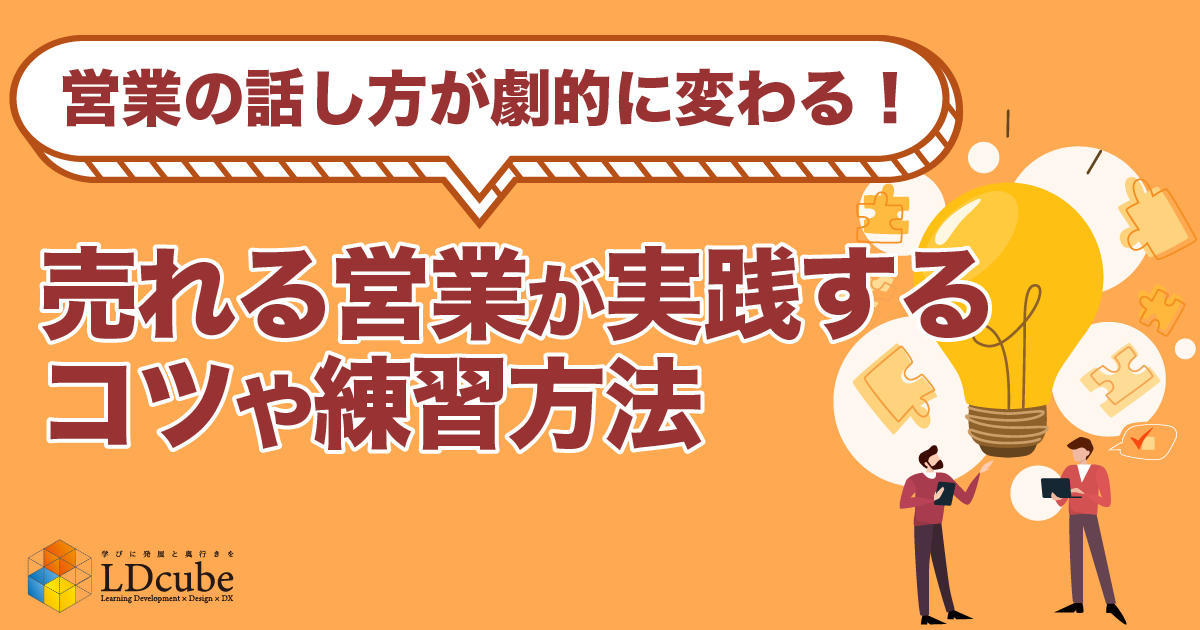
営業の話し方が劇的に変わる!売れる営業が実践するコツや練習方法とは?
営業という仕事において、話し方一つで成果は大きく変わります。顧客との商談で、あなたの言葉選びや話し方がどれだけ重要な役割を果たしているか、意識したことはありますか?
実は、成果を上げている営業パーソンには、共通する話し方のパターンがあります。顧客の信頼を獲得し、スムーズに商談を進められる営業パーソンは、声のトーンや間の取り方、言葉選びなど、細部にまでこだわったコミュニケーションを実践しているのです。
一方で、なかなか成果が上がらない営業パーソンにも特徴的な話し方があります。専門用語を多用する、一方的に話し続ける、顧客のペースを無視して進めるなど、信頼関係を損なうようなコミュニケーションの特徴が見られます。
「もっと効果的な話し方を身に付けたい」「顧客との会話をスムーズに進めたい」「商談での成約率を上げたい」
そんな悩みを抱える営業パーソンは少なくないでしょう。
本記事では、ベテラン営業が実践している話し方のテクニックを、基礎から応用まで体系的に解説します。声のトーンの調整から、質問の仕方、クロージングまで、明日から使える実践的なノウハウをお伝えします。これらのテクニックを身に付ければ、あなたの営業トークは必ず変わります。
▼営業研修やロープレトレーニングについてはテーマに合わせて下記で解説しています。
▼営業育成やロープレについてのお役立ち資料を6点セットにしました。下記からダウンロードできます。
目次[非表示]
- 1.営業の業績は話し方で決まる!
- 2.なぜ営業では話し方が重要なのか
- 3.顧客に信頼される営業の、話し方のコツとは
- 3.1.いきなり課題を聞かない
- 3.2.いきさつや背景を聞く
- 3.3.例え話などを使って、現状についての認識を聞く
- 3.4.課題に切り込み、課題を押さえる
- 4.成果を上げている営業が実践する基本的な話し方
- 5.顧客が話したくなる営業トークの組み立て方
- 6.営業パーソンが使うべき効果的な質問テクニック
- 7.営業の話し方の前提
- 8.営業の話し方を磨くステップ
- 8.1.①自己理解を深める
- 8.2.②他者理解を深める
- 8.3.③相手に合わせた話し方を取り入れる
- 9.営業の話し方を鍛えるなら社内講師が最適
- 10.まとめ:話し方を磨けば誰でも営業はうまくなる
営業の業績は話し方で決まる!

「なぜあの営業パーソンはいつも成果を上げているのだろう?」と不思議に思ったことはありませんか?
実は、営業成績の差は商品知識やセールススキルだけでなく、「話し方」によって大きく左右されることが分かっています。
売れる営業パーソンとそうでない営業パーソンの間には、明確な「話し方の差」が存在します。トップセールスの多くは、顧客心理を理解し、信頼を勝ち取るための話し方を身に付けているのです。
同じ商品を扱っていても、ある営業パーソンは成約率が20%を超えるのに対し、別の営業パーソンは5%にも満たないという状況は珍しくありません。この差は単なる運や経験だけでなく、顧客とのコミュニケーション方法、特に「話し方」に秘密があります。
話し方を変えるだけで、顧客の受け取る印象は劇的に変わります。声のトーン、スピード、間の取り方、使う言葉の選び方—これらの要素を意識的に調整することで、顧客の信頼を獲得し、成約へと導くことができるのです。
次章以降では、営業のプロが実践している話し方のコツを詳しく解説します。これらのテクニックを身に付ければ、あなたも顧客と信頼関係を築き、成果を上げる営業パーソンへと成長できるでしょう。
なぜ営業では話し方が重要なのか

営業において話し方が成功を左右する鍵となります。優れた商品やサービスがあっても、それを効果的に伝えられなければ意味がありません。
顧客の心を動かし、信頼を勝ち取るためには、適切な話し方が不可欠なのです。
以下では、営業で話し方が重要である理由について解説します。
説明力の差が成約率を大きく左右するため
同じ商品を扱う営業パーソン同士でも、成約率に大きな差が生まれるのはなぜでしょうか。その要因の一つが「説明力」です。
顧客は単に商品の機能やスペックを知りたいわけではありません。それを使うことで得られるメリットや、自分の課題がどう解決されるのかを理解したいのです。高い説明力を持つ営業パーソンは、顧客視点に立ち、具体的なイメージを喚起する言葉選びができます。
例えば、単に「このシステムは処理速度が従来比200%です」と伝えるのではなく、「このシステムを導入すれば、今まで30分かかっていた作業がわずか15分で終わるようになり、その浮いた時間で他の業務に集中できるようになります」と説明することで、顧客は具体的なメリットをイメージできるのです。
また、難解な専門用語を多用せず、顧客が理解しやすい言葉で説明することも重要です。説明力の高い営業パーソンは、顧客の反応を見ながら、理解度に合わせて説明の深さや言葉遣いを調整することができます。
会話が顧客との信頼構築の役割を果たすため
ビジネスの世界では「人は人から買う」という言葉があります。これは、顧客が商品そのものだけでなく、それを提案する営業パーソンとの信頼関係に基づいて購入を決断するという真理を表しています。
信頼関係の構築において、会話は最も重要なツールです。単に商品説明を一方的に行うのではなく、顧客の話に耳を傾け、共感し、適切な質問を投げかけることで、顧客は「この人は自分のことを理解してくれている」と感じるようになります。
話し方は、営業パーソンの人柄や誠実さ、専門性を伝える重要な手段でもあります。例えば、顧客の質問に対して自信を持って回答できるか、分からないことは正直に認められるか、といった点が信頼性の判断材料となります。
また、言葉だけでなく、声のトーンや表情、姿勢といった非言語コミュニケーションも信頼構築に大きな影響を与えます。真摯な態度で相手に向き合い、相手のペースに合わせた話し方をすることで、顧客は心を開き、より本音ベースの会話ができるようになるのです。
顧客に信頼される営業の、話し方のコツとは

営業において顧客からの信頼を獲得することは、成約への最短ルートです。ここでは、信頼関係構築に効果的な営業の話し方のコツを、ヒアリングの流れに沿って解説します。
これらのコツを実践すれば、顧客との会話がスムーズになり、より深い信頼関係を築くことができるでしょう。
いきなり課題を聞かない
できる営業パーソンが初回の商談でまず気を付けるのは、「いきなり課題を聞かない」ということです。初対面の営業パーソンに対して、顧客はまだ警戒心を持っています。その状態で「御社の課題は何ですか?」と尋ねても、表面的な回答しか得られないことが多いのです。
信頼関係ができていない段階では、顧客は本音を話しにくいものです。特に自社の弱みや問題点に関わる課題は、簡単に打ち明けられるものではありません。
そのため、商談の序盤は、まず顧客の会社や業界に関する基本的な情報を確認し、相手の緊張をほぐすことに集中しましょう。
例えば「御社の主力商品について教えていただけますか?」「最近の業界の動向はいかがですか?」など、答えやすい質問から始めることで、顧客との会話のリズムを作っていきます。
いきさつや背景を聞く
顧客の警戒心が少し解けてきたら、次に「いきさつや背景」について質問していきます。この段階では、現在の状況に至るまでの経緯や背景情報を収集することが目的です。
例えば、「現在のシステムはいつ頃から導入されているのですか?」「これまでどのような方法で業務を進めてこられたのですか?」といった質問を通じて、顧客の状況をより深く理解していきます。
背景情報を聞くことで、表面的には見えない潜在的なニーズや課題のヒントを得ることができます。また、顧客の話に真摯に耳を傾ける姿勢を示すことで、「この営業パーソンは自分の話をきちんと聞いてくれる」という信頼感を醸成することができるのです。
例え話などを使って、現状についての認識を聞く
背景情報を把握したら、次に現状認識について質問していきます。このとき効果的なのが、例え話や具体例を交えた質問です。
例えば、「他社様では、データ入力に多くの時間を取られ、本来の分析業務に支障が出ているケースが多いのですが、御社ではいかがでしょうか?」というように、同業他社の事例を例え話として使うことで、顧客は自社の状況を客観的に考えやすくなります。
例え話を使うことには、もう1つ重要な効果があります。それは顧客が「自分だけが困っているわけではない」と安心感を得られることです。同じような課題を持つ企業が他にもあり、それを解決した実績があることを示唆することで、顧客は自社の課題についても前向きに話せるようになります。
課題に切り込み、課題を押さえる
ここまでの会話で信頼関係が構築できてきたら、いよいよ核心である「課題」について掘り下げていきます。この段階では、それまでに得た情報を基に、具体的な課題について質問します。
「先ほどのお話から、データ集計に時間がかかり、月末の報告書作成が大変とのことですが、具体的にどのような点で苦労されていますか?」のように、顧客が既に話した内容に言及しながら質問することで、より深い課題の本質に迫ることができます。
課題をしっかりと把握したら、それを言語化して顧客に確認することも重要です。「つまり、現在の課題は、データ処理の効率化と報告書が自動生成されると助かるということでしょうか?」と整理することで、顧客と課題認識を共有し、解決策の提案へとスムーズに進むことができます。
成果を上げている営業が実践する基本的な話し方

成果を上げている営業パーソンには、話し方において共通する特徴があります。これらは単なる「話術」ではなく、顧客との信頼関係を構築するための基礎となる要素です。
ここでは、成果を上げている営業が日々実践している話し方のテクニックを紹介します。
信頼感を生む適切な声のトーンと間の取り方
声のトーンと間(ま)の取り方は、言葉の内容と同じくらい重要なコミュニケーション要素です。できる営業パーソンは、この非言語的要素を効果的に活用して信頼感を醸成しています。
声のトーンについては、落ち着いた低めの声で話すことが基本です。高すぎる声や早口は緊張や焦りの表れと受け取られがちで、信頼感を損なう可能性があります。特に重要なポイントを伝える際は、やや声のトーンを落として話すことで、相手に「重要な情報が来た」という印象を与えることができます。
間の取り方も同様に重要です。話し続けるのではなく、適切なタイミングで「間」を入れることで、相手に考える時間を与え、理解を促進します。例えば、重要なポイントを伝えた後や、質問を投げかけた後には、少し間を置くことで、相手が内容を咀嚼する時間を確保します。
成果を上げている営業パーソンは、顧客の反応を見ながら臨機応変に声のトーンや間を調整します。顧客が興味を示しているときは活気のあるトーンで、慎重な判断を要する話題では落ち着いたトーンで、というように場面に応じた使い分けができるのです。
顧客のペースを見極めて会話を展開する
成果を上げている営業パーソンは、「顧客のペースに合わせる」という基本を徹底しています。これは心理学で言う「ペーシング」というテクニックで、相手との信頼関係を短時間で構築するのに効果的です。
具体的には、相手の話すスピード、声の大きさ、言葉遣い、表情などを観察し、それに近づけていくことを意識します。例えば、ゆっくり話す顧客に対しては、こちらもテンポを落として話します。専門用語を多用する顧客には、同じような専門用語を使って話すことで、共通言語での対話が可能になります。
また、顧客の発言や関心に即座に反応し、それを会話に取り入れることも重要です。例えば、顧客が「コスト削減が今の最優先課題です」と言えば、その後の説明ではコスト面の効果を中心に話を展開するといった具合です。
このように顧客のペースやニーズに合わせた会話を展開することで、顧客は「自分のことを理解してくれている」と感じ、信頼関係の構築が進みます。
専門用語を日常語に置き換えて説明する
できない営業パーソンの特徴として、「専門用語が多い」という点が挙げられます。自社製品に関する専門知識をアピールしたいという気持ちから、つい業界用語や社内用語を多用してしまうのです。
しかし、顧客にとってなじみのない専門用語は、理解の障壁となるだけでなく、「何を言っているのか分からない」というストレスや不信感を生む原因になります。
成果を上げている営業パーソンは、複雑な専門用語や概念を、顧客が理解しやすい日常的な言葉に置き換えて説明します。例えば、IT業界の営業なら「このシステムはAPI連携が可能です」という専門的な説明ではなく、「このシステムは他の業務システムと簡単に情報をやり取りできるので、二重入力の手間がなくなります」というように、メリットを含めた平易な表現に置き換えます。
特に初回の商談や、技術的な背景がない顧客との会話では、専門用語の使用を最小限に抑え、必要に応じてかみ砕いた説明を加えることが重要です。顧客の理解度や専門性に応じて、説明の深さや用語の難易度を調整できることも、優れた営業パーソンの特徴と言えるでしょう。
顧客が話したくなる営業トークの組み立て方

成功する営業トークの鍵は、顧客からより多くの情報を引き出すことにあります。顧客が本音で話したくなるようなトークを組み立てることで、より深いニーズの理解と信頼関係の構築が可能になります。
ここでは、顧客が自然と話したくなる営業トークの組み立て方を解説します。
具体的な導入事例を交えて商品価値を伝える
顧客は抽象的な説明よりも、具体的な事例を通じて商品やサービスの価値を理解する傾向があります。できる営業パーソンは、抽象的な機能やスペックだけでなく、それがどのように実際の課題解決に役立ったかを示す「導入事例」を効果的に活用します。
例えば、「このシステムは処理速度が速いです」という抽象的な説明ではなく、「A社様では、このシステムを導入後、月次報告書の作成時間が40時間から8時間に短縮され、経営判断のスピードが格段に向上しました」というように具体的な事例と数字で説明することで、顧客は自社での活用イメージを描きやすくなります。
導入事例を話す際のポイントは、顧客と似た業種や規模の企業の例を選ぶことです。「同じような課題を持つ他社はこうして解決した」という話は、顧客の共感を呼びやすく、自社の状況についても話したいという気持ちを引き出します。
また、事例を語る際には、課題→導入→効果という流れを意識し、特に導入前後の変化を具体的に伝えることで、より説得力を持って商品価値を伝えることができます。
相手の言葉を引用しながら共感を示す
顧客が話しやすい雰囲気をつくる上で、「共感」は非常に重要な要素です。特に効果的なのが、顧客の発言を引用しながら共感を示す方法です。
例えば、顧客が「データ集計に時間がかかって困っています」と話した場合、「データ集計に時間がかかるというのは、本当に大変な問題ですよね。特に月末のような締め切りが迫っている時期は、余計にストレスになりますね」と、顧客の言葉を取り入れながら共感を示します。
この「オウム返し」とも呼ばれるテクニックは、顧客に「自分の話をしっかり聞いてくれている」「自分の問題を理解してくれている」という安心感を与えます。ただし、単に言葉を繰り返すだけでは不自然に感じられるため、自分の経験や知見を加えて共感を深めることが重要です。
また、「さすがですね」「それは素晴らしい取り組みですね」といった肯定的な言葉を適切に使うことも、顧客が安心して話せる環境づくりに役立ちます。このように相手を認め、尊重する姿勢を示すことで、顧客はより本音で話したいと感じるようになります。
重要なメリットを複数の切り口で伝える
営業トークにおいて、商品やサービスの重要なメリットは、一度だけでなく複数の切り口から繰り返し伝えることが効果的です。人は一度聞いただけでは十分に理解・記憶できないことが多いため、特に重要なポイントは異なる表現や文脈で複数回伝えることで、顧客の理解と納得を深めることができます。
例えば、あるシステムの「業務効率化」というメリットを伝える場合、以下のように複数の切り口から説明します。
|
このように同じメリットでも異なる角度から伝えることで、顧客にとっての価値がより具体的になり、「自分たちにとって本当に必要なものなのか」という観点から考えやすくなります。
また、顧客自身の関心に合った切り口に反応が見られたら、そこを深掘りする質問を投げかけることで、顧客の本音を引き出すきっかけにもなります。
営業パーソンが使うべき効果的な質問テクニック

営業において「質問力」は、顧客の真のニーズを引き出すための重要なスキルです。適切な質問を適切なタイミングで投げかけることで、顧客との会話を深め、信頼関係を構築することができます。ここでは、営業パーソンが習得すべき効果的な質問テクニックを紹介します。
オープン・クエスチョンで課題を深掘りする
オープン・クエスチョンとは、「はい」「いいえ」では答えられない、自由な回答を促す質問形式です。「何」「どのように」「なぜ」「どのような」などで始まる質問がこれにあたります。
例えば、「現在のシステムでどのような課題を感じていますか?」「その問題が解決したら、どのような変化が期待できますか?」といった質問です。
オープン・クエスチョンの効果は主に以下の3つです。
|
特に「なぜ」という質問は、問題の根本原因を探るのに効果的です。例えば、「なぜそのような方法を選ばれたのですか?」「その決断に至った理由は何ですか?」といった質問により、表面的な課題の背後にある真のニーズを把握することができます。
ただし、オープン・クエスチョンばかりだと会話が散漫になる可能性があるため、クローズド・クエスチョンと組み合わせて使うことが重要です。
相手の答えやすい質問から徐々に掘り下げる
効果的な質問の順序も、顧客の本音を引き出す上で重要な要素です。いきなり核心に迫る質問をすると、顧客は警戒して本音を話さなくなることがあります。
理想的な質問の順序は、まず答えやすい基本的な質問から始め、徐々に掘り下げていくというものです。例えば、以下のような流れが効果的です。
|
このように段階的に質問を深めていくことで、顧客は自然と本音を話せるようになります。
また、初めの質問で得た回答を次の質問に生かすことで、「しっかり話を聞いている」という印象を与え、信頼関係の構築にも役立ちます。
クローズド・クエスチョンで会話のテンポを作る
クローズド・クエスチョンとは、「はい」「いいえ」や選択肢から選ぶような、答えが限定される質問形式です。
例えば、「今年度中の導入をお考えですか?」「AとBどちらのプランが近いイメージでしょうか?」といった質問です。
クローズド・クエスチョンには以下のような効果があります。
|
特に商談の初期段階や、顧客との関係構築が十分でない段階では、クローズド・クエスチョンを多めに使うことで、顧客の負担を減らしながら必要な情報を収集できます。
また、商談の終盤で合意を取る際にも効果的です。例えば「この商品の導入により、月間約30時間の業務時間削減が期待できますが、これは御社の課題解決になりますか?」といった形で、明確な合意を得ることができます。
ただし、クローズド・クエスチョンばかりだと、尋問のような印象を与えたり、表面的な情報しか得られなかったりするため、オープン・クエスチョンとのバランスが重要です。顧客の反応や会話の流れを見ながら、二つの質問タイプを適切に使い分けることが、効果的な営業トークの秘訣です。
▼営業の心理学テクニックについては下記で詳しく解説しています。
⇒営業の心理学テクニック14選|商談の成功率が上がるすぐに使えるアプローチを解説!
営業の話し方の前提

これまで営業のさまざまな話し方のテクニックを紹介してきましたが、効果的な話し方を身に付ける前に理解しておくべき重要な前提があります。
それは、コミュニケーションの本質に関わる基本的な考え方です。ここでは、営業の話し方を考える上で欠かせない3つの前提を解説します。
相手も人間であり、個性がある
営業の現場ではついつい「顧客」という抽象的な存在として相手を捉えがちですが、忘れてはならないのは、顧客も1人の人間であり、固有の個性を持っているということです。
人はそれぞれ異なる価値観、経験、性格、コミュニケーションスタイルを持っています。例えば、直接的な表現を好む人もいれば、婉曲的な表現を好む人もいます。データや論理を重視する人もいれば、感情や直感を大切にする人もいます。細かい説明を求める人もいれば、要点だけを知りたい人もいます。
こうした個人差を無視して、全ての顧客に対して同じ話し方をしても、効果的なコミュニケーションは成立しません。営業の話し方を考える際には、まず「相手はどのような人なのか」を理解することが出発点となります。
顧客一人一人の個性を尊重し、その人に合った話し方を心掛けることが、信頼関係構築の第一歩です。そのためには、先入観や思い込みを排除し、相手の言動をよく観察する姿勢が不可欠です。
相手の個性に合わせた話し方が大切
相手の個性を理解した上で次に重要なのは、その個性に合わせた話し方を選択することです。これは「ミラーリング」や「ペーシング」と呼ばれるテクニックの本質でもあります。
例えば、論理的な思考の持ち主には、データや根拠を示しながら順序立てて説明することが効果的です。一方、感情的な判断を重視する人には、具体的な事例やストーリーを交えながら、感情に訴えかける話し方が響きやすいでしょう。
また、話すスピードや声のトーン、使う言葉なども、相手に合わせて調整することが重要です。早口の人に対しては少し早めに、ゆっくり話す人にはゆったりとしたペースで話すことで、無意識のうちに「この人は自分と波長が合う」という印象を与えることができます。
ただし、単に相手のまねをするのではなく、自然な形で相手のスタイルに寄り添うことがポイントです。不自然な合わせ方をすると、かえって不信感を抱かせることになります。
個性を理解するには自己理解が必要
他者の個性に合わせた話し方をするためには、まず自分自身のコミュニケーションスタイルを理解することが不可欠です。なぜなら、自分の癖や傾向を知らなければ、相手との違いも把握できず、適切な調整もできないためです。
例えば、自分が論理的な説明を好む傾向があることを自覚していれば、感情的な判断を重視する顧客に対しては意識的にストーリーや事例を増やすといった調整ができます。また、自分が早口であることを認識していれば、ゆっくり話す顧客と会話する際に意識的にペースを落とすことができるでしょう。
自己理解を深めるには、以下のような方法が効果的です。
|
こうした自己分析を通じて自分のコミュニケーションの特徴や癖を把握することで、相手との違いを認識し、より柔軟に対応できるようになります。
営業の話し方のテクニックを学ぶ前に、まずこれらの前提を理解し、自己理解と他者理解を深めることが、効果的なコミュニケーションへの第一歩となるのです。
▼他者理解については下記で詳しく解説しています。
⇒他者理解とは?その意味と必要な7つのこと─職場でできる施策も紹介
営業の話し方を磨くステップ

営業の話し方を向上させるには、単に理論を学ぶだけでなく、実践を通じて段階的にスキルを磨いていくことが重要です。
ここでは、効果的な営業トークを身に付けるための3つのステップを解説します。
①自己理解を深める
営業の話し方を改善する第一歩は、自分自身のコミュニケーションの特徴や傾向を理解することです。まずは自己分析を行い、現状の話し方の長所と短所を客観的に把握しましょう。
自己理解を深めるための具体的な方法としては、商談や電話を録音して後で聞き返す方法が効果的です。自分の言葉遣い、声のトーン、話すスピード、間の取り方などを客観的に確認することで、気付かなかった癖や改善点が見えてきます。
また、信頼できる同僚や上司に自分の話し方についてフィードバックを求めるのも有効です。「どのような印象を受けるか」「改善すべき点はどこか」など、具体的な質問をすることで、自分では気付かない視点を得ることができます。
自己理解のポイントは、単に欠点を探すのではなく、自分の強みや個性も含めて総合的に把握することです。例えば、論理的な説明が得意、共感力が高い、豊富な業界知識がある、といった強みを生かしながら、改善点を補っていく姿勢が大切です。
▼自己理解については下記で詳しく解説しています。
⇒自己理解を深める方法とは!5つの情報源について詳しく解説
②他者理解を深める
自己理解ができたら、次に顧客をはじめとする他者への理解を深めることが重要です。効果的な営業トークは、相手を理解することなしには成立しないからです。
他者理解の第一歩は、相手の言動をよく観察することです。話すスピードや間の取り方、使う言葉、ボディーランゲージなどから、相手のコミュニケーションスタイルや性格的特徴を読み取ります。
例えば、以下のような観察ポイントがあります。
|
また、人間の行動スタイルを研究したLIFOプログラムなどを学ぶことで、人の行動スタイルを体系的に理解することもできます。こうした知識は、顧客の行動スタイルを見極め、適切な対応を選択する際の参考になります。
他者理解で大切なのは、単に相手を分類することではなく、一人一人の固有性を尊重しながら、コミュニケーションを円滑にするためのヒントを得ることです。
▼LIFOプログラムについては下記をご覧ください。
⇒自身の強みの理解と啓発「LIFO」
③相手に合わせた話し方を取り入れる
自己理解と他者理解を深めた上で、最後のステップは実際に相手に合わせた話し方を実践することです。これは単なる模倣ではなく、相手との信頼関係を構築するためのアプローチです。
まず、相手のコミュニケーションスタイルに合わせて、自分の話し方を調整します。例えば、以下のような調整が考えられます。
|
また、相手の使う言葉や表現を取り入れることも効果的です。例えば、顧客が「投資対効果」という言葉を使うなら、こちらも同じ言葉を用いることで、共通の言語で対話している印象を与えられます。
実践の段階では、最初から完璧を目指すのではなく、徐々に自分のレパートリーを増やしていくことが大切です。例えば、まずは相手の話すスピードに合わせることから始め、慣れてきたら声のトーンや間の取り方などにも注意を向けるというように段階的に進めていきましょう。
そして何より大切なのは、相手への敬意と誠実さです。テクニックだけに頼ると不自然さが生まれ、かえって信頼を損なう可能性があります。相手のスタイルに合わせつつも、自分の誠実さや個性を失わないバランス感覚を持つことが、真の意味での営業話法の習得には不可欠です。
▼下記では、本章で説明した自己理解から相手に合わせた話し方を取り入れるポイントをプチ診断付きで体験的に解説しています。
⇒【プチ診断付き】人間関係で疲れた方へ/少し気が楽になる捉え方のコツ!
営業の話し方を鍛えるなら社内講師が最適

営業の話し方を効果的に鍛える場づくりの一つとして、社内講師の活用が挙げられます。
特に、自社の営業現場を熟知した社員を講師として育成することで、より実践的で効果の高い研修を実現することができます。
ここでは、社内講師による研修のメリットと具体的な活用方法について解説します。
自社商材を売ったことがある経験を持っている
営業コミュニケーション研修を担当する場合、「自社商材を売ったことがある経験」という観点は非常に重要です。社内講師が自社商材の営業経験を持っていることにより、受講者に対して納得度を高めることができます。
この点は外部講師にはどう頑張っても補えない点です。外部講師の場合、受講者は「どうせ自社商材を売ったこともなければ、現場すらも知らないだろう。」と口には出さなくても思っています。
その点、自社商材を売ったことがある社内講師が研修を進めるだけで、受講者の納得度合いは格段に高くになります。
自社商材をよく理解している
社内講師の最大の強みは、自社の商材や市場特性を深く理解していることです。この知識を生かすことで、より具体的で実践的な研修内容を提供することができます。
例えば、商品説明のロールプレーイングでは、実際の商談で頻出する質問や懸念事項に基づいたシナリオを設定できます。また、業界特有の商習慣や顧客特性を踏まえた、現場で即活用できるコミュニケーション技術を指導することが可能です。
さらに、過去の成功事例や失敗事例を具体的に共有することで、より実践的な学びを提供できます。
研修内容を自社にフィットさせやすい
社内講師は、自社の企業文化や営業スタイルを理解しているため、研修内容を組織の実情に合わせて最適化することができます。営業現場の実態や課題を熟知しているからこそ、より実効性の高いプログラムを設計することが可能です。
具体的には以下のようなメリットがあります。
社内講師ならではのメリット:
|
これらの特徴により、研修で学んだスキルを確実に業務に生かすことができます。
外部機関の教材を活用する
社内講師による研修を効果的に実施するためには、外部機関の教材やツールを適切に活用することも重要です。
外部の専門機関が提供する体系的な教材やフレームワークを基礎として、そこに自社独自のケーススタディーやノウハウを組み合わせることで、より充実した研修プログラムを構築することができます。特に、基本的なコミュニケーションスキルや営業フローに関する部分は、実績のある外部教材を活用することで、効率的な学習を実現できます。
また、定期的に外部機関のアップデート情報を取り入れることで、最新のトレンドや手法を研修に反映させることも可能です。
このような外部リソースの活用により、社内講師の負担を軽減しながら、質の高い研修を継続的に提供することができます。
まとめ:話し方を磨けば誰でも営業はうまくなる
営業の話し方が劇的に変わる!売れる営業が実践するコツや練習方法とは?について紹介してきました。
- 営業は話し方で業績が決まる!
- なぜ営業では話し方が重要なのか
- 顧客に信頼される営業の、話し方のコツとは
- 成果を上げている営業が実践する基本的な話し方
- 顧客が話したくなる営業トークの組み立て方
- 営業パーソンが使うべき効果的な質問テクニック
- 営業の話し方の前提
- 営業の話し方を磨くステップ
- 営業の話し方を鍛えるなら社内講師が最適
本記事では、営業の成功に直結する「話し方」のテクニックについて解説してきました。顧客との信頼関係構築を基本に、相手の話に共感し、個性に合わせたコミュニケーションを取ることの重要性を見てきました。
効果的な営業トークのためには、専門用語を避ける、質問を適切に使い分ける、具体的な事例を交えて話すといった基本技術が欠かせません。さらに、自己理解と他者理解を深めることで、より高度な話し方が身に付きます。
これらのスキルは特別な才能ではなく、意識的な練習と経験によって誰でも習得できるものです。日々の営業活動の中で少しずつ実践し、振り返りを行うことで、必ず上達していきます。
営業の話し方を磨くことは、単に営業成績を向上させるだけでなく、あらゆるビジネスシーンでのコミュニケーション能力を高めることにつながります。この記事が、あなたの営業力向上の一助となれば幸いです。
株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。