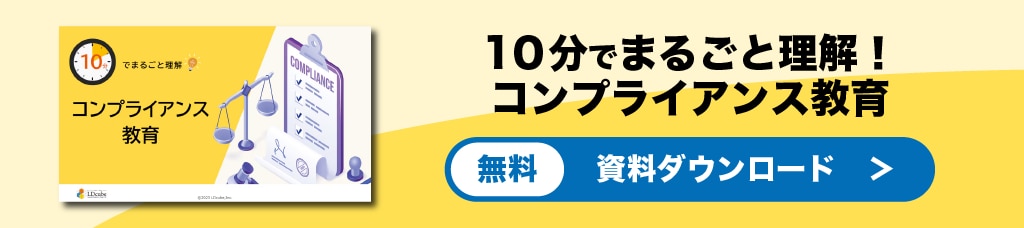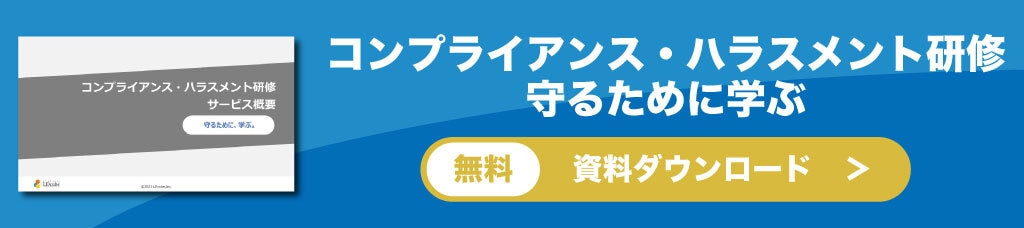コンプライアンス研修は動画教材で効率化!効果的な展開方法を解説!
コンプライアンス研修は、今や企業経営において欠かせない重要な取り組みとなっています。SNSの普及やハラスメント意識の高まりを背景に、コンプライアンスの重要性はますます増大しており、効果的な研修方法が求められています。
そのような中、多くの企業が注目しているのが「動画」を活用したコンプライアンス研修です。従来の集合型研修と比較して、場所や時間の制約がなく、コスト効率も高いという特徴があります。
コンプライアンス違反は企業の社会的信用を大きく損ない、最悪の場合は倒産にまで追い込まれるケースもあります。このようなリスクを回避するためにも、全社員が適切なコンプライアンス意識を持つことが不可欠です。
本記事では、コンプライアンス研修における動画活用のメリットを詳しく解説するとともに、効果的な研修動画の内容や活用方法、導入手順までを網羅的にご紹介します。
人事担当者や研修責任者の方はもちろん、経営層の方々にとっても、コンプライアンス体制強化に役立つ情報が満載です。動画を活用した効率的な研修方法を知り、企業リスクの低減と組織の健全な発展につなげましょう。
▼コンプライアンス特集ページを作成しました。ハラスメントとの違いや種類、学習方法まで体系的に解説しています。 |
▼ コンプライアンスについてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
目次[非表示]
- 1.コンプライアンス研修を動画で実施する2つのねらい
- 2.コンプライアンス研修を動画で実施する5つのメリット
- 3.コンプライアンス研修で効果のある動画例
- 3.1.コンプライアンスについて専門家が解説する動画
- 3.2.コンプライアンスの事例を共有する動画
- 3.3.ハラスメントのイメージがつかみやすいドラマ仕立ての動画
- 3.4.予防につながる関連テーマの学習動画
- 4.コンプライアンス研修動画の効果的な活用方法
- 4.1.知識学習は動画で行う
- 4.2.動画を見た上でオンライン研修を行う
- 4.3.オンライン研修を通じてアクションプランを策定する
- 4.4.アクションプランを職場で実践する
- 4.5.実践した結果をグループチャットで共有する
- 4.6.実践結果の共有から学び合う
- 5.コンプライアンス研修での動画の活用ステップ
- 6.コンプライアンス研修に活用できる動画例
- 7.まとめ:コンプライアンス研修動画の活用で企業リスクを効率的に低減しよう
コンプライアンス研修を動画で実施する2つのねらい

コンプライアンス研修を動画で実施する主な目的は、組織全体のリスク回避と信頼性向上にあります。東京商工リサーチの調査によれば、コンプライアンス違反が原因で倒産した企業は年間320社にも上ります。
また、従業員による不適切な行為や経営陣の問題発言によって、消費者からの信頼を失い、業績を落とした企業も少なくありません。動画研修のねらいを詳しく見ていきましょう。
コンプライアンスについて意識させる
コンプライアンスは単なる法令遵守にとどまらず、企業や組織が社会的責任を果たすための基本姿勢です。動画研修の第一のねらいは、従業員一人一人にコンプライアンスの重要性を認識させることにあります。
コンプライアンスとは、「①国が定めた法律や政令②社内規則③社会倫理」という3つのルールを守ることです。動画を通じて具体的な事例を視覚的に伝えることで、抽象的になりがちなコンプライアンスの概念を分かりやすく伝え、日常業務における意識向上を促します。
特に、情報漏洩やデータ改ざん、ハラスメント行為など、具体的な違反事例を動画で示すことで、「自分ごと」として捉えやすくなり、従業員の倫理観の醸成につながります。
関連テーマも含めて啓発し予防する
動画研修の第二のねらいは、コンプライアンス違反を未然に防ぐための予防的啓発にあります。法令違反だけでなく、社内ルールや社会倫理に関わる幅広いテーマについて学ぶことができます。
具体的には以下のような関連テーマを含めた包括的な研修が可能です。
|
これらのテーマを動画で分かりやすく伝えることで、従業員が日常業務の中で「何が問題となるのか」を具体的にイメージでき、コンプライアンス違反の予防につながります。
また、万が一社内でコンプライアンス違反が発生した場合の対処方法や通報窓口の利用方法なども含めることで、早期発見・早期解決を促進します。
コンプライアンス研修を動画で実施する5つのメリット

従来のコンプライアンス研修は対面での講義形式や紙資料の配布が一般的でしたが、近年は動画を活用した研修が注目されています。動画研修には、効率性と効果の両面で大きなメリットがあります。
ここでは、コンプライアンス研修を動画で実施する際の5つの主要なメリットについて解説します。
場所や時間の制約を受けない
動画研修の最大のメリットは、場所や時間の制約から解放されることです。従来の集合型研修では、参加者全員が同じ時間に同じ場所に集まる必要がありましたが、動画研修ではそのような制約がありません。
従業員は自分の都合の良い時間に、オフィスや自宅など好きな場所で研修を受けることができます。特に複数の拠点を持つ企業や、シフト制で働く従業員が多い業種では、全員が同時に集まることが難しいため、この柔軟性は非常に重要です。
また、出張や休暇中の従業員も、インターネット環境さえあれば研修を受けることができるため、研修の漏れを防ぐことができます。
全社員に同じ内容を共有できる
動画研修では、全ての従業員に一貫した内容を伝えることができます。講師による対面研修の場合、実施回数や講師によって内容や質にばらつきが生じる可能性がありますが、動画研修ではそうした懸念がありません。
特にコンプライアンスのような重要なテーマでは、情報の正確性と一貫性が求められます。動画なら経営方針や重要なポリシーを経営陣から直接伝えることも可能で、メッセージの重要性を強調できます。
また、日本語以外の言語が必要な多国籍企業では、同じ内容を複数の言語で提供することも容易になります。
研修にかかるコストを大幅に削減できる
動画研修は長期的に見てコスト削減につながります。従来の研修では以下のようなコストが発生していました。
|
動画研修では、制作費用が初期投資として発生しますが、一度作成すれば何度でも活用でき、追加コストなしで多くの従業員に展開できます。
更新が必要な場合も、全面的な再制作ではなく部分的な編集で対応できるため、長期的には大幅なコスト削減が可能です。
繰り返しの視聴で知識定着につながる
動画研修の大きなメリットは、従業員が必要に応じて繰り返し視聴できることです。一度の研修で理解できなかった内容も、何度も視聴することで理解を深めることができます。
特にコンプライアンスのような浸透が必要なテーマでは、反復学習が知識の定着に効果的です。従業員は自分のペースで学習を進め、理解が難しい部分を重点的に復習することができます。
また、日常業務の中で疑問が生じた際に、すぐに関連部分を確認できるレファレンス性もメリットの一つです。これにより、研修内容が実務に生かされる確率が高まります。
視聴データを活用した受講管理ができる
動画研修では、視聴履歴や理解度テストの結果などのデータを収集・分析することが可能です。
これにより、以下のような受講管理が効率的に行えます。
|
こうしたデータは研修プログラムの改善にも役立ちます。理解が難しいと判明した部分は、次回の動画制作時により分かりやすく解説するなど、継続的な改善が可能になります。
また、コンプライアンス研修の実施記録は、監査や第三者評価の際の証拠としても活用できるため、組織のリスク管理にも貢献します。
コンプライアンス研修で効果のある動画例

コンプライアンス研修を動画で行う際には、内容や表現方法によって効果が大きく異なります。
ここでは、目的別に効果的なコンプライアンス研修動画の具体例を紹介します。それぞれの特徴を理解し、自社の研修に最適な動画形式を選ぶ際の参考にしてください。
コンプライアンスについて専門家が解説する動画
専門家による解説動画は、コンプライアンスの基本概念や法的背景を正確に伝えるのに適しています。法務担当者や外部の専門家が登場し、コンプライアンスの重要性や具体的な法令について分かりやすく説明することで、従業員の理解を深めることができます。
この形式の動画では以下のような内容が効果的です。
|
専門家による解説は信頼性が高く、特に経営層や管理職向けの研修に適しています。また、法令改正があった際の最新情報を伝える更新用動画としても有効です。
コンプライアンスの事例を共有する動画
実際に起きたコンプライアンス違反の事例を取り上げた動画は、抽象的な概念を具体化し、「自分たちの会社でも起こりうる問題」として認識させるのに効果的です。過去の実例を学ぶことで、似たような状況での対処法を身に付けることができます。
事例共有動画では、以下のような構成が効果的です。
|
実在する企業の事例を扱う場合は、特定の企業を批判するのではなく、教訓として取り上げる姿勢が重要です。
また、自社内で起きた(または起きかけた)事例を匿名化して共有することで、より身近な問題として捉えることができます。
ハラスメントのイメージがつかみやすいドラマ仕立ての動画
ハラスメントのようなテーマは、言葉での説明だけでは伝わりにくい面があります。ドラマ形式の動画を用いることで、どのような言動がハラスメントに該当するのか、またそれによって被害者がどのような精神状態になるのかを視覚的に伝えることができます。
ドラマ仕立ての動画には以下のような特徴があります。
|
東映株式会社が提供する「人権のすすめ」シリーズのような動画は、職場におけるハラスメントやDEI(多様性・公平性・包括性)の問題を、独立したミニドラマで描き、「気付き」を促す効果的な教材例です。
予防につながる関連テーマの学習動画
コンプライアンス違反を未然に防ぐためには、直接的な法令遵守だけでなく、関連するテーマについても学ぶことが重要です。予防的アプローチを取り入れた学習動画は、問題が大きくなる前に対処するための知識を提供します。
関連テーマとしては以下のようなものが考えられます。
|
これらのテーマは直接的なコンプライアンス違反を扱うものではありませんが、健全な組織文化を育み、結果としてコンプライアンス意識の向上につながります。特に管理職研修や定期的な啓発活動に適しています。
コンプライアンス研修動画の効果的な活用方法

コンプライアンス研修の効果を最大化するためには、動画をただ視聴するだけでなく、総合的な研修プログラムの一部として活用することが重要です。
ここでは、コンプライアンス研修動画を効果的に活用するための具体的な方法を段階的に解説します。
知識学習は動画で行う
コンプライアンス研修の第一段階として、基本的な知識やルールの理解には動画学習が最適です。
法令や社内規定などの情報は、テキストだけでは理解しづらく記憶に残りにくいものですが、視覚と聴覚の両方を使った動画学習により効率的に吸収することができます。
動画学習のポイントは以下の通りです。
|
このステップでは、一方的な情報提供に終わらせるのではなく、従業員が能動的に学べるよう工夫することが大切です。
視聴後に小テストや確認問題を設けることで、理解度を確認するとともに、重要ポイントの定着を図ることができます。
動画を見た上でオンライン研修を行う
動画での基礎知識習得後は、オンラインでのライブ研修を組み合わせることで理解を深めることができます。ビデオ会議システムを活用したオンライン研修では、動画で学んだ内容について質疑応答や議論を行うことができます。
オンライン研修では以下のような活動が効果的です。
|
この段階では、一方通行の学習から双方向のコミュニケーションへと発展させることで、「知っている」から「理解している」へとレベルアップすることが目標です。
オンライン研修を通じてアクションプランを策定する
知識の獲得と理解を深めた後は、学んだ内容を実践に移すためのアクションプランを策定します。部署や役職ごとに具体的な行動計画を立てることで、コンプライアンス意識を日常業務に定着させることができます。
アクションプラン策定のポイントは以下の通りです。
|
例えば、「ハラスメント防止」というテーマであれば、「週1回のチーム会議で5分間のハラスメント防止トピックを共有する」といった具体的な行動計画に落とし込みます。
アクションプランを職場で実践する
策定したアクションプランを実際の職場で実践することが、コンプライアンス研修の真の目的です。この段階では、知識が行動に変わり、組織文化として定着していくことを目指します。
実践段階での支援策としては以下のようなものが効果的です。
|
管理職には、部下の実践状況を支援・監督する役割があることを明確にし、組織全体での取り組みとして位置付けることが重要です。
実践した結果をグループチャットで共有する
アクションプランの実践結果や気付きをグループチャットやイントラネットなどで共有することで、個人の経験を組織の知恵へと発展させることができます。オンラインでの情報共有は、時間や場所を選ばず、リアルタイムでのコミュニケーションを可能にします。
効果的な共有のポイントは以下の通りです。
|
このような情報共有により、他の従業員も同様の状況での対応方法を学ぶことができ、組織全体のコンプライアンス意識の向上につながります。
実践結果の共有から学び合う
最終段階として、共有された実践結果や気付きから組織として学び、次のコンプライアンス研修や取り組みに生かしていくことが重要です。定期的な振り返りミーティングやオンラインフォーラムを通じて、継続的な改善サイクルを構築します。
学び合いの場では以下のような活動が効果的です。
|
こうした学び合いの場を定期的に設けることで、コンプライアンスへの取り組みが一過性のイベントではなく、組織文化として定着していくことを促進します。
コンプライアンス研修での動画の活用ステップ

コンプライアンス研修に動画を活用する際には、計画的なアプローチが重要です。
ここでは、効果的な研修動画を選定し活用するための実践的なステップを紹介します。自社の状況や目的に合わせて、最適な動画研修プログラムを構築するための指針としてください。
目的の設定(再確認)
コンプライアンス研修動画を活用する前に、まず研修の目的を明確にすることが重要です。目的が曖昧なままでは、適切な動画選定ができず、期待する効果も得られません。
以下のような観点から目的を具体化しましょう。
|
例えば、「ハラスメント防止」が目的であれば、単に「ハラスメントについて学ぶ」という漠然とした目標ではなく、「管理職がハラスメントの定義を理解し、チーム内の問題行動を特定・改善できるようになる」といった具体的な目標を設定します。
目的に沿った動画選定
設定した目的に基づいて、最適な研修動画を選定します。
市販の既製動画を活用する場合も、自社制作する場合も、以下のポイントを考慮して選定することが重要です。
|
特に重要なのは、視聴者の関心を引き、「自分ごと」として捉えられる内容であることです。抽象的な概念の説明だけでなく、具体的な事例や身近なシナリオを含んだ動画が効果的です。
汎用的なテーマは外部の動画を活用コンプライアンスの基本概念や一般的なテーマについては、専門機関や研修サービス会社が提供する高品質な既製動画を活用することがコスト効率の面で優れています。
以下のような汎用的なテーマは外部動画の活用が適しています。
|
外部動画を選ぶ際のチェックポイントは以下の通りです。
|
東映株式会社の「人権のすすめ」シリーズのようなコンテンツは、ドラマ形式で描かれており、視聴者の感情移入を促し効果的な学習につながります。
こうした専門性の高い既製動画を基盤としつつ、自社の状況に合わせた補足説明を加えることで、より効果的な研修が実現できます。
自社事例は社内制作の動画を活用
一方、自社特有の課題や事例については、内製の動画が効果的です。自社の実情に即した内容は、従業員にとって最も身近で理解しやすく、実践に結びつきやすいという特徴があります。以下のようなテーマは自社制作が適しています。
|
社内制作の動画は、必ずしも高額な制作費をかける必要はありません。以下のような低コストでの制作方法も効果的です。
|
豪華な映像を重視するよりも、具体的で実用的な内容の動画を作ることが重要です。自社の実例に基づいた「リアル」な内容は、高額な制作費をかけた一般的な内容よりも効果的なことが多いです。
コンプライアンス研修に活用できる動画例
心理的安全性がつくる恐れのない職場コース①②
【コース概要】
組織やチームにとって重要な内容であるにもかかわらず、自分の考えを言わず、質問を控え、黙っていたことが何度ありますか?
従業員が安心して発言できるようにするには、心理的に安全な環境を整える必要があります。本コースでは、対人関係の不安がいかに組織をむしばむか、そして、その乗り越え方をさまざまな事例を通じて学習します。
【講師略歴】
エイミー・C・エドモンドソン
エイミー・C・エドモンドソンは、ハーバード・ビジネススクールのノバルティス記念講 座教授として、リーダーシップとマネジメントを教えています。
2年に1度発表される経営思想家の世界的なランキング、Thinkers50では、2011年、2013年、 2015年、2017年に選出され、2017年にはTalent Awardも受賞しました。
リーダーシップ、チーミング、組織学習に関する教育や執筆に従事し、ハーバード・ビジネス・レビューやカリフォルニア・マネジメント・レビューなどの経営誌や一流 の学術誌に寄稿しています。
心理的安全性に関する先駆的な研究で最もよく知られており、過去15年間に わたって経営、医療、教育分野のさまざまな学術研究に貢献してきました。
『恐れのない組織――「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす』(英治出版)や『チームが機能するとはどういうことか――「学習力」と「実行力」を高める実践アプローチ』(英治出版)などの著書があります。
まとめ:コンプライアンス研修動画の活用で企業リスクを効率的に低減しよう
コンプライアンス研修に動画を活用することは、現代のビジネス環境において非常に効果的なアプローチです。動画研修は時間と場所の制約を受けず、全社員に一貫した内容を効率的に伝えることができます。
また、繰り返しの視聴による知識定着や、データを活用した受講管理など、従来の研修方法にはない多くのメリットがあります。
効果的なコンプライアンス研修のためには、単に動画を視聴するだけでなく、「知識学習→オンライン研修→アクションプラン策定→実践→結果共有→学び合い」というステップを意識した総合的なプログラムが重要です。
特に、学んだ内容を職場で実践し、その結果を共有して組織全体で学び合う循環を作ることが、コンプライアンス文化の定着には欠かせません。
動画選定においては、汎用的なテーマには質の高い既製動画を活用し、自社特有の課題には内製動画を組み合わせるハイブリッドなアプローチが効率的です。どちらの場合も、単なる知識伝達ではなく、「自分ごと」として捉えられる具体的な事例や実践方法を含めることがポイントとなります。
企業を取り巻くコンプライアンスリスクは年々高まっており、SNSの普及や社会的価値観の変化により、以前は問題視されなかった行為も厳しく批判される時代になっています。
こうした変化に対応し、企業の持続的な成長と信頼構築を実現するためにも、効果的なコンプライアンス研修動画の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
株式会社LDcubeではコンプライアンスセミナーに活用できるeラーニング、マイクロラーニング、LMSなどの提供を行っています。
コースごとの価格設定もあれば、受講人数に制限を設けない全社員受け放題プランなど、費用についてもバリエーションを用意しております。
また不祥事の起きない会社づくりに向け、心理的安全性を高めるeラーニングや研修、職場ミーティングなどを組み合わせ、総合的な支援もしています。
さらに無料のデモIDの発行や実績・導入事例の紹介も行っていますので、お気軽にご相談ください。
▼関連記事はこちらから。