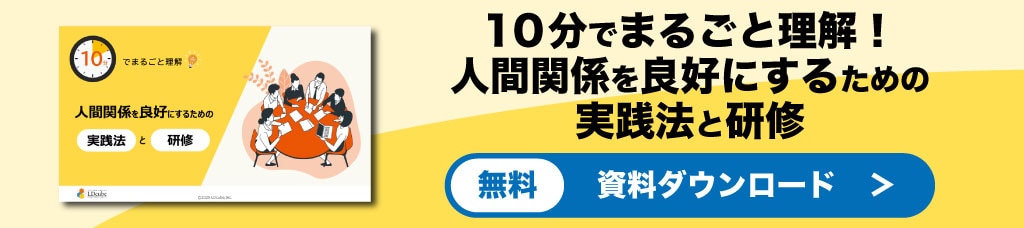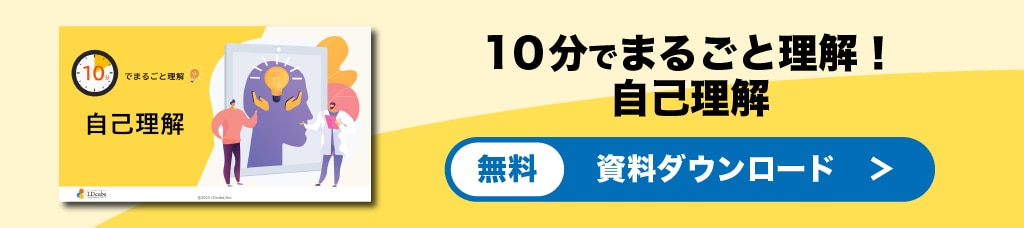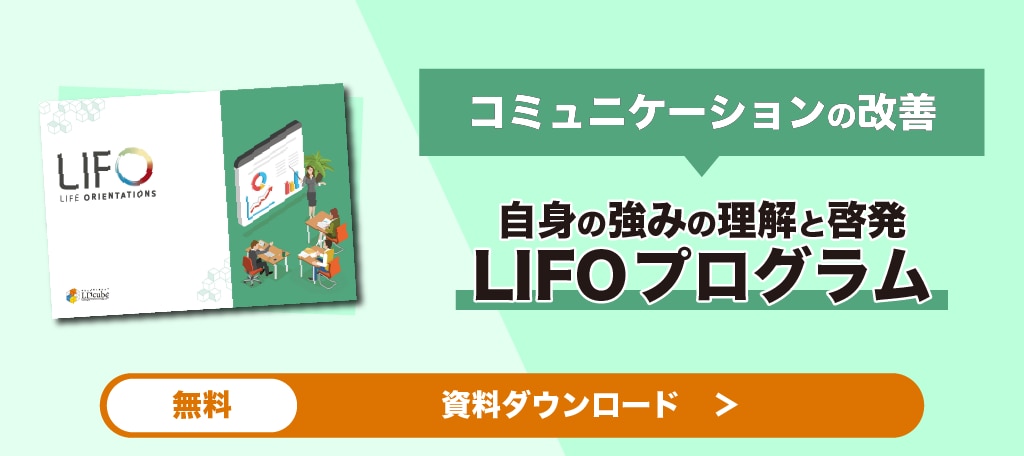人間関係がめんどくさいと感じたときの対処法とは?原因やポイントを解説!
人間関係がめんどくさいと感じることは、誰にでも起こりうる自然なことであり、悪いことではありません。
職場で上司の機嫌を伺うことに疲れたり、愚痴を聞かされるばかりでストレスを感じたり、人間関係に悩みを持ったりすることは珍しくありません。このような感情は決して特別なものではなく、多くの人が日常的に経験していることです。
特に社会人になると、さまざまな価値観を持つ人と関わる機会が増えます。時に自分が苦手と感じる人との接点があり、自分の感情や意見を抑えて相手に合わせなければならない状況も少なくありません。
「なぜこんなにめんどくさく感じるのだろう」と自分を責めてしまうこともあるかもしれませんが、これは自分を守るための自然な心理的反応であり、自分自身を大切にするためのサインでもあるのです。
本記事では、人間関係がめんどくさいと感じる5つの心理的原因を深掘りするとともに、そう感じやすい具体的なシチュエーションを紹介します。
さらに、めんどくさいと感じたときのおすすめの対処法も紹介します。これらの対処法は、職場や日常生活で実践できる具体的な方法です。人間関係のストレスを軽減し、自分らしく生きるためのヒントが満載です。
めんどくさいと感じる人間関係とうまく付き合いながら、自分の心を守る方法を一緒に考えていきましょう。
▼人間関係についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。
▼人間関係を良好にするための実践法と研修については下記にまとめています。
目次[非表示]
- 1.人間関係がめんどくさいと感じるのは正常な反応である
- 2.人間関係がめんどくさいと感じる5つの心理的原因
- 3.人間関係がめんどくさいと感じやすいシチュエーション
- 4.人間関係がめんどくさいと感じたときの即効性のある対処法
- 4.1.対処法1:表面的な付き合いをする
- 4.2.対処法2:相手との心理的距離を取る
- 4.3.対処法3:自分の感情に素直になる
- 4.4.対処法4:自分のペースを優先する
- 4.5.対処法5:複数の居場所でバランスを保つ
- 4.6.対処法6:カウンセリングなどの専門家に相談する
- 4.7.対処法7:環境そのものを変える
- 5.めんどくさい人間関係でも職場で実践すべき3つのマインド
- 5.1.最低限の礼儀と対応
- 5.2.自分の意見を持ち、過度に同調しない
- 5.3.悪口や陰口を避ける
- 6.人間関係のめんどくささを軽減するコツ
- 7.人間関係のめんどくささを改善するには職場単位での研修が手っ取り早い
- 8.研修を社内講師で展開した支援事例
- 9.まとめ:人間関係がめんどくさいと感じても自分らしく生きるために
人間関係がめんどくさいと感じるのは正常な反応である

「人間関係がめんどくさい」と感じることは、多くの人が経験する自然な感情です。職場での人間関係や友人関係に疲れを感じ、ときには全ての人間関係から逃げ出したくなることもあるでしょう。
このような感情は決して特別なものではなく、むしろ健全な反応の一つと言えます。
人間関係がめんどくさいと感じるのは変化のある証し
人間関係がめんどくさいと感じるとき、それはあなた自身が成長している証拠かもしれません。
ビジネスパーソンとして成長する過程で、役職の変化や新しいプロジェクトの担当、スキルの向上に伴い、周囲の期待や要求が変わることがあります。これにより、人間関係も次第に変化し、これまでとは異なる新しい関係性が生まれることがあります。
例えば、昇進した場合、これまでの同僚が部下になり、上下関係が生まれることで、コミュニケーションの仕方が変わるかもしれません。また、新たにプロジェクトリーダーになると、異なるチームや部署との連携が求められ、場合によっては利害関係の調整が必要となります。
こうした変化は、自己の成長やキャリアの進展を示すものですが、新しいルールや期待に適応するためのエネルギーが求められるため、「めんどくさい」と感じてしまうことがあります。
この「めんどくささ」は、成長の痛みとも言えるもので、これを乗り越えることでさらなる成長の機会を得ることができます。
つまり、人間関係におけるこうしたストレスをうまく管理し、柔軟に適応していくことは、ビジネスパーソンとしてのレジリエンスや人間力を高める貴重なプロセスでもあります。
この視点から見ると、「めんどくさい」と感じること自体が、あなたが新しいステージに進んでいることを示しているのです。
変化のないところに成長はない
変化とは新しい状況や環境に適応することで、新たな挑戦が生まれることです。ビジネスの世界では、技術の進化、市場の変動、顧客のニーズの変化など、絶えず変化が起こっています。
こうした変化に対応しない限り、環境の変化に取り残され、競争力を失うリスクが高まります。従って、変化に取り組むことは、時代に即したスキルや知識を更新し続けるために不可欠なのです。
成長とは、自己の能力や理解を深めることを意味します。多くの場合、コンフォートゾーンを越えて新しいことに挑戦することで実現します。
そこで、変化は成長のための刺激となり、新しい課題を通じて問題解決能力やクリエイティビティ、リーダーシップを養う機会を提供します。例えば、新しいプロジェクトを担当したり、異なる役職の責任を引き受けたりすることで、それまで経験したことのないスキルや知識を得ることが可能です。
つまり、変化がない状態では、現状に満足し、成長の機会を逃してしまう恐れがあります。反対に、変化を受け入れ、新しいことに挑戦することが、ビジネスパーソンとしての質を高め、長期的なキャリアの成功につながります。
めんどくささを乗り越えた先に成長がある
めんどくささを乗り越えた先に成長があります。人間関係のめんどくささを単に避けるのではなく、それと向き合うことで得られる成長は計り知れないものです。
例えば、職場で難しい上司や同僚との関わりに対処する過程では、自己理解が深まり、自分の価値観や強み、弱みを再認識する機会が得られます。これが自己成長を促す土台となります。
困難な人間関係に直面することで、コミュニケーション能力が向上します。具体的には、相手のニーズや感情を理解し、適切に対応するための共感力が育まれます。
また、自分の意見や感情を誤解なく伝えるための表現力が磨かれます。さらに、ストレスフルな状況を乗り越える中で、心の余裕を保つ力、すなわちレジリエンスが強化されます。めんどくさいと感じる状況を乗り越えるたびに、対人関係のスキルは確実に向上していきます。
これらの経験から培われた共感力や表現力、レジリエンスといった能力は、ビジネスシーンだけでなく、私生活においても非常に価値のあるものです。人間関係の困難に一時的な不快感に終わらせず、長期的な視点で向き合うことが、真の成長につながります。
このようにして得られたスキルは、将来的に直面するさらなる挑戦を乗り越えるための大きな財産となります。
人間関係がめんどくさいと感じる5つの心理的原因

人間関係がめんどくさいと感じる背景には、さまざまな心理的要因が存在します。これらの原因を理解することで、自分自身の感情と向き合い、より健全な関係を築くための第一歩となるでしょう。
原因1:過度な気遣いと自己抑制
人間関係がめんどくさいと感じる最も一般的な原因の一つが、過度な気遣いと自己抑制です。常に相手の感情や反応を気にして、自分の本音を抑え込む習慣が身に付いていると、次第に人との関わりそのものに疲労感を覚えるようになります。
特に日本社会では「空気を読む」ことが重視され、自分の気持ちよりも集団の調和を優先する傾向があります。毎回の会話や行動で「この発言は相手を傷つけないだろうか」「この行動は迷惑にならないだろうか」と過度に考え続けることは、大きな負担となります。
自分の感情や意見を表現せずに我慢し続けると、徐々に人間関係そのものが息苦しく感じられるようになってしまうのです。
原因2:他者からの評価への過剰意識
他者からどのように見られているかを過度に気にする心理状態も、人間関係をめんどくさく感じる大きな原因です。「周囲からの評価」や「他人の目」を気にしすぎると、本来の自分らしさを発揮できなくなります。
SNSの普及により、他者の反応をすぐに確認できる現代社会では、この傾向がさらに強まっています。「いいね」の数や反応を気にしたり、常に集団の中で自分の立ち位置を確認したりする習慣が、精神的な疲労を引き起こすことがあります。
自分の言動や選択が他者にどのように映るかを過剰に意識することで、コミュニケーションの自然さが失われ、人間関係そのものが負担に感じられるようになるのです。
原因3:内向的な性格
内向的な性格の人は、外向的な人と比べて人間関係にエネルギーを消費しやすい傾向があります。内向的な人にとって、社交的な場や多くの人との交流は、エネルギーを大量に消費する活動なのです。
内向的な人は1人の時間や静かな環境で充電する時間が必要です。そのため、連続的な人間関係や長時間の社交的な活動は、精神的な疲労を引き起こしやすくなります。
自分の性格的な特性を理解せず、外向的な環境に無理に適応しようとすると、人間関係全般に対して「めんどくさい」という感覚を強く持つようになることがあります。自分のペースを大切にすることが、内向的な人が人間関係を健全に保つカギとなります。
原因4:過去のトラウマ体験
過去に人間関係で深く傷ついた経験がある場合、新しい関係に対して無意識に防衛反応が働き、人間関係全般をめんどくさいと感じるようになることがあります。裏切られた経験や激しい対立、いじめなどのトラウマは、人との関わりに対する恐れや不信感を植え付けます。
過去のトラウマ体験が解決されないまま残っていると、似たような状況に遭遇したときに過剰な警戒心や不安を感じやすくなります。「また傷つけられるのではないか」「また同じ失敗をするのではないか」という恐れが、人間関係に対するネガティブな感情を強化し、関わり自体をめんどくさく感じさせるのです。
このような場合は、過去の経験と現在の状況を区別して捉えることが重要になります。
原因5:完璧主義による理想と現実のギャップ
完璧主義の傾向が強い人は、人間関係においても高い理想を持ちがちです。「こうあるべき」という理想の関係性と現実とのギャップに苦しみ、人間関係をめんどくさいと感じることがあります。
完璧主義の傾向が強い人は自分に対しても厳しい基準を持っているため、自分の言動や選択に過度に責任を感じたり、小さな誤解や摩擦も大きな失敗と捉えたりする傾向があります。
また、相手に対しても高い期待を持ちやすく、その期待が満たされないとき失望感を抱きます。このような理想と現実のギャップが、人間関係全般に対する疲労感や「めんどくささ」につながるのです。完璧を求めすぎず、人間関係の不完全さを受け入れる柔軟性が大切になります。
人間関係がめんどくさいと感じやすいシチュエーション

人間関係がめんどくさいと感じるのは、特定の状況や環境によって引き起こされることが多くあります。日常生活の中で特に人間関係の負担を感じやすいシチュエーションを理解することで、適切な対処法を見つける手がかりになるでしょう。
職場の人間関係
職場は、自分が選んだわけではない多様な人々と長時間過ごす場所であるため、人間関係がめんどくさいと感じやすい代表的な環境です。特に上司の機嫌を伺わなければならない状況や、同僚との競争的な関係は大きなストレス要因となります。
職場では、仕事の効率や生産性よりも人間関係の維持が優先されることもあり、本来必要のないコミュニケーションや調整に時間とエネルギーを費やさなければならないことがあります。
また、組織の階層構造によって自分の意見や感情を素直に表現できない状況も、関係性をめんどくさく感じる原因となります。特に「仕事の話」と「プライベートな交流」の境界があいまいな職場環境では、人間関係の負担が増大しやすくなるでしょう。
嫉妬やマウンティング
嫉妬の対象になったり、マウンティングを受けたりする状況は、人間関係を著しくめんどくさく感じさせる要因です。他者から必要以上に比較されたり、自分の成果や特性を否定されたりすると、関係性を維持するモチベーションが低下します。
嫉妬やマウンティングの背景には、相手の不安や劣等感がある場合が多いのですが、受け手としては理不尽な攻撃と感じることもあるでしょう。「また嫌な思いをするのではないか」という警戒心が生まれると、コミュニケーション自体が負担になります。
特に、表面上は友好的でありながら、裏では批判や否定をしているような関係は、信頼関係を損ない、人間関係全般に対する疲労感を引き起こすことになります。
愚痴やうわさ話
常に愚痴やうわさ話を聞かされる環境は、心理的な負担が大きく、人間関係をめんどくさいと感じる典型的な状況です。他者の否定的な情報や評価を共有することで関係性を築こうとする集団では、自分自身も同様に評価される不安が生じます。
愚痴やうわさ話の多い環境では、「自分が席を外したとき、自分のことが話題になっているのではないか」という不信感が芽生えやすくなります。
また、常にネガティブな話題に囲まれていると、全体的な気分の低下にもつながります。さらに、愚痴やうわさ話に同調することを期待されると、自分の価値観や倫理観との間で葛藤が生じ、人間関係そのものが重荷に感じられるようになるのです。
集団行動や暗黙のルール
集団行動や暗黙のルールに従わなければならない状況は、個人の自由や選択を制限し、人によっては人間関係をめんどくさく感じさせることがあります。
「みんな一緒に」という同調圧力や、明文化されていない「こうすべき」というルールは、特に個性を大切にする人にとって大きなストレスとなります。
職場の飲み会や社内イベントへの参加が半ば強制的である場合、プライベートな時間や個人の意思が尊重されないことへの不満が蓄積します。また、「前例踏襲」の名の基に非効率なプロセスが続けられる環境も、人間関係の負担感を増大させます。
個人の多様性や自律性が認められず、集団の同質性が過度に重視される状況では、人間関係全体がめんどくさく感じられるようになるのです。
逆に暗黙のルールに従っていれば良いとも言えるので、このような状況をめんどくさいと感じず、むしろ楽とい人もいます。それゆえに状況が改善されないことが多いのです。
人間関係がめんどくさいと感じたときの即効性のある対処法

人間関係がめんどくさいと感じる状況は誰にでも訪れます。そのようなとき、すぐに実践できる効果的な対処法を知っておくことで、心の負担を軽減し、より健全な人間関係を維持することができます。ここでは、即効性のある7つの対処法を紹介します。
対処法1:表面的な付き合いをする
全ての人間関係を深める必要はありません。特に職場など、関わらざるを得ない環境では、表面的な付き合いにとどめることも一つの賢明な選択です。これは決して冷たい態度を取るという意味ではなく、適切な距離感を保つことを意味します。
具体的には、業務上必要なコミュニケーションは丁寧に行いながらも、プライベートな情報の共有は最小限にとどめるという方法があります。ま
た、会話のトピックを趣味やニュースなど、中立的な話題に限定することで、感情的な領域まで巻き込まれることを避けることができます。「仕事は仕事」と割り切り、必要以上に深い関係を求めないことで、人間関係の負担を大幅に減らすことが可能です。
この方法を実践する際の重要なポイントは、一貫性を保つことです。突然態度を変えると、相手に不信感を与えてしまいます。最初から適度な距離感を意識し、徐々に自分にとって心地よい関係性を構築していきましょう。また、表面的な付き合いは決して「嘘をつく」ことではありません。
誠実さを保ちながらも、全てを開示する必要はないのです。自分の心の健康を守るための境界線を設けることが、長期的には良好な人間関係の維持につながります。
対処法2:相手との心理的距離を取る
めんどくさいと感じる相手との間に、心理的な距離を置くことは効果的な対処法です。これは物理的に離れるということではなく、相手の言動や態度に過度に反応しないよう、心の中で一定の距離を保つことを意味します。
実践方法としては、相手の発言や行動を「気にしない」という姿勢を意識します。また、相手に対して過度な期待を持たないことも重要です。完璧な理解や対応を期待せず、相手の限界や個性をあるがままに受け入れる姿勢が、人間関係のストレスを軽減します。
心理的距離を取る際に効果的なのが「観察者の視点」を持つことです。自分がその場面の登場人物ではなく、少し離れた位置から状況を観察しているかのようにイメージしてみましょう。これにより、相手の言動に対する感情的な反応が弱まり、より冷静な対処ができるようになります。
対処法3:自分の感情に素直になる
人間関係がめんどくさいと感じるとき、その感情を否定せず、自分の本当の気持ちに素直になることが大切です。自分の感情を正直に認識し、受け入れることから始めましょう。
具体的な方法としては、日記やメモに自分の感情を書き出してみることが効果的です。「なぜこの関係がめんどくさいと感じるのか」「どのような場面で特にストレスを感じるのか」を整理することで、問題の本質が見えてくることがあります。
また、信頼できる友人や家族に正直な気持ちを打ち明けることも、心の負担を軽減する助けになります。自分の感情を認識し、表現することで、次のステップである具体的な行動に移りやすくなるのです。
感情を認識する際には「ネガティブな感情にも意味がある」という視点が重要です。例えば、怒りは境界線を侵害されたときのサイン、不安は何かリスクを感じていることのサインかもしれません。感情は私たちに重要な情報を提供してくれるものなのです。
また、感情を言語化する際には具体的に表現することが効果的です。単に「イライラする」ではなく、「相手が約束を守らないときに信頼感が損なわれてイライラする」というように、より詳細に感情とその原因を把握することで、効果的な対処法が見えてくるでしょう。
対処法4:自分のペースを優先する
人間関係がめんどくさいと感じるとき、自分の心地よさや自分のペースを最優先にすることが重要です。他者のペースに合わせすぎることで疲労感が増す場合は、意識的に自分の時間や空間を確保する習慣をつけましょう。
実践方法としては、1日の中に「自分だけの時間」を必ず設けることが効果的です。例えば、朝の30分間を自分のための時間として確保したり、昼休みに一人で過ごす時間をつくったりすることで、心のバランスを保ちやすくなります。
また、無理な予定や自分のエネルギーを著しく消費する約束は、勇気を持って断ることも必要です。「自分の心の健康を守ること」は、長期的には周囲との良好な関係構築にもつながる大切な自己ケアなのです。
自分のペースを守るための具体的な方法として、予備時間の確保があります。予定と予定の間に予備時間をおくことで、心の切り替えやリフレッシュの時間を確保できます。
また、「エネルギー管理」の視点も重要です。自分のエネルギーレベルを常に意識し、疲れているときには無理をせず休息を取りましょう。さらに、「NO」と言える能力を育てることも大切です。全ての誘いや依頼を受ける必要はなく、自分の優先順位に基づいて選択することが、健全な人間関係の構築につながります。
対処法5:複数の居場所でバランスを保つ
一つの環境や人間関係に依存しすぎると、そこでの問題が自分の心全体に大きな影響を与えてしまいます。複数の居場所や人間関係を持つことで、心理的なバランスを保ちやすくなります。
具体的には、職場以外に趣味のコミュニティや地域の活動に参加するなど、異なる環境での人間関係を構築することが効果的です。それぞれの場所で異なる自分の側面を表現できると、一つの関係に過度に依存することなく、全体としての充実感を得やすくなります。
また、オンラインコミュニティや趣味のグループなど、自分の興味や価値観を共有できる場所を見つけることで、「理解されている」という安心感を得ることができます。
複数の居場所を持つ際のポイントは「多様性」です。異なるタイプの集団や活動に参加することで、さまざまな視点や価値観に触れることができます。例えば、競争的な職場環境と協力的な趣味のグループなど、異なる特性を持つコミュニティに所属することで、心の柔軟性が高まります。
また、これらの居場所を通じて「自分らしさ」の異なる側面を表現できることも重要です。職場では見せない自分の一面を趣味の場で発揮することで、全人格的な充実感を得られるようになるのです。
対処法6:カウンセリングなどの専門家に相談する
人間関係の問題が長期間続いたり、日常生活に支障をきたしたりする場合は、専門家のサポートを受けることも効果的な対処法です。カウンセラーやセラピストは、客観的な視点から問題を整理し、具体的な対処法を提案してくれます。
カウンセリングでは、自分では気付かなかった人間関係のパターンや、無意識の反応パターンが明らかになることがあります。
また、職場のメンタルヘルス相談窓口やEAP(従業員支援プログラム)など、企業が提供するサポートサービスを利用することも検討してみましょう。専門家からの支援を受けることは、自分自身を大切にするための積極的な行動であり、より健全な人間関係を構築するための重要なステップとなります。
専門家への相談を検討する際の障壁として「相談するほどの問題ではない」と考えてしまうことがありますが、予防的なカウンセリングも非常に有効です。問題が深刻化する前に専門家のサポートを受けることで、早期解決が可能になります。
対処法7:環境そのものを変える
どうしても改善が見られない場合は、環境そのものを変えることも選択肢の一つです。職場の異動や転職、住環境の変化など、より根本的な解決策を検討することもときには必要です。
環境を変えることを検討する前に、まずは現状での改善可能性を十分に探ることが大切です。しかし、長期間にわたり状況が改善せず、心身の健康に影響が出ている場合は、勇気を持って変化を選ぶことも自己防衛のために重要です。
新しい環境に移る際は、過去の経験から学んだことを生かし、より健全な人間関係を構築するための意識的な努力を続けることが、同じパターンの繰り返しを防ぐポイントとなります。
環境変化を決断する際の判断基準として、「現状の環境が自分の価値観や目標と一致しているか」を問うことが有効です。自分の大切にしている価値観と環境の価値観が根本的に異なる場合、長期的な適応は難しいかもしれません。
また、変化を恐れる心理として「既知の不快よりも未知の不安を選びたくない」という心理が働きがちですが、変化には新たな可能性も含まれています。環境を変える前に「自分が持ち込みがちなパターン」を認識しておくことで、新しい環境でも同じ問題を繰り返さないための準備ができるでしょう。
めんどくさい人間関係でも職場で実践すべき3つのマインド

最低限の礼儀と対応
人間関係がめんどくさいと感じる相手に対しても、社会人として最低限の礼儀と対応を維持することが重要です。あからさまに無視したり、冷たい態度を取ったりすることは、かえって職場の雰囲気を悪化させ、自分自身の評価にも悪影響を及ぼす可能性があります。
具体的には、あいさつや基本的なコミュニケーションを丁寧に行い、業務上必要な対応をプロフェッショナルに行うことが大切です。感情的になりすぎず、冷静さを保ちながらも、完全に壁をつくらない程度の距離感を意識しましょう。
「必要以上に良好な関係を築く必要はないが、敵対関係をつくらない」というスタンスが、職場での人間関係の負担を軽減しながらも、業務の円滑な進行を可能にします。
自分の意見を持ち、過度に同調しない
人間関係を円滑にするためとはいえ、自分の意見や価値観を完全に押し殺してまで他者に同調することは避けるべきです。特に倫理的な問題や重要な決断に関しては、自分の意見をしっかりと持ち、必要に応じて表明することが大切です。
過度な同調は、一時的には関係の摩擦を避けられますが、長期的には自己否定や自尊心の低下につながります。意見の相違があっても、「考え方の違い」として受け止め、相手を尊重しながらも自分の立場を適切に伝える姿勢が重要です。
全ての人と完全に意見が一致することはありませんし、健全な関係においては多様な意見や視点が尊重されます。自分らしさを保ちながら、相手と適切な距離感を持った関係を構築することが、職場での人間関係の負担を軽減するカギとなるでしょう。
悪口や陰口を避ける
人間関係がめんどくさいと感じる相手について、悪口や陰口を言うことは絶対に避けるべきです。一時的なストレス発散になると思っても、長期的には自分自身の評判や職場環境にネガティブな影響を与えます。
悪口や陰口は、聞いている側に「自分が席を外したときも、同じように話されているのではないか」という不安や不信感を与えます。また、悪口を言っている人自身も信頼性を損ない、「陰で何を言うか分からない人」というレッテルを貼られかねません。
めんどくさいと感じる相手についての不満は、信頼できる職場外の友人や家族に限定して話すか、あるいは日記などに書き出して対処するようにしましょう。
人間関係のめんどくささを軽減するコツ

人間関係のめんどくささを完全になくすことは難しいかもしれませんが、その負担を軽減し、より心地よい関係を築くためのコツがあります。最後に、長期的な視点で人間関係の質を向上させるための方法を見ていきましょう。
自己理解を深める
人間関係のめんどくささを軽減するためには、まず自分自身をよく理解することが重要です。自分の価値観、好み、許容範囲、コミュニケーションスタイルなどを把握することで、どのような関係が自分に合っているのかが明確になります。
具体的には、「どのような状況でストレスを感じやすいか」「どのようなタイプの人と関わるとエネルギーを消費するか」などを観察し、パターンを見つけることが有効です。また、自分の強みや弱み、感情の変化に敏感になることで、感情的な反応を制御しやすくなります。
自己理解が深まれば、自分に合った距離感や関わり方を選択できるようになり、人間関係の負担が自然と軽減されるでしょう。
▼自己理解を深める方法については下記で詳しく解説しています。
⇒自己理解を深める方法とは!5つの情報源について詳しく解説
他者理解を深める
自分を理解するのと同様に、相手の価値観や行動パターンを理解することも、人間関係のめんどくささを軽減するのに役立ちます。相手の言動の背景にある考え方や感情を想像してみることで、不必要な誤解や摩擦を減らすことができます。
例えば、攻撃的な態度の背景には不安や恐れがあることが多く、過度に世話を焼く人は承認欲求が強い可能性があります。このように相手の行動の背景を理解することで、個人的に受け取らずに客観的に対応できるようになります。
また、相手の強みや良い面に目を向け、多面的に捉える習慣をつけることで、関係性に対するポジティブな感情が増し、めんどくささを感じにくくなるでしょう。
▼他者理解については下記で詳しく解説しています。
⇒他者理解とは?その意味と必要な7つのこと─職場でできる施策も紹介
他者に合わせたアプローチで適切な関係を築く
全ての人に同じ関わり方をするのではなく、相手の特性や関係性に合わせたアプローチを取ることで、人間関係の質を向上させることができます。一人一人に合った距離感や関わり方を意識的に選ぶことが大切です。
例えば、詳細な説明を好む人には丁寧に情報を伝え、感情を重視する人には共感的な姿勢で接するといった具合に、相手に合わせたコミュニケーションを心がけましょう。
また、全ての人と親密な関係を築く必要はなく、相手との相性や状況に応じて、深い関係から表面的な付き合いまで、適切な関係のレベルを選択することが重要です。
相手の特性を理解し、適切な距離感で関わることができれば、互いにとって心地よい関係を築きやすくなります。人間関係のめんどくささは、相手と自分の特性の不一致から生じることが多いため、相手に合わせたアプローチを取ることで、不必要な摩擦やストレスを減らすことができるのです。
▼相手に合わせたアプローチを体験的に学べる記事もご覧ください。
⇒【プチ診断付き】人間関係で疲れた方へ/少し気が楽になる捉え方のコツ!
人間関係のめんどくささを改善するには職場単位での研修が手っ取り早い

人間関係の良い職場をつくるには、組織的なアプローチが効果的です。特に、職場単位での研修は、共通の理解と実践的なスキルを身に付ける上で非常に有効な手段です。
全員が同じ目標に向かって取り組むことで、より迅速な改善が期待できます。
上司も部下も同じ研修を受けられる
研修の効果を最大限に高めるために、職場の全メンバーが参加することが重要です。
全員が同じ研修プログラムに参加することで、以下の効果が期待できます。
|
リアルな職場を題材にできる
実際の職場の課題や状況を研修の題材として使用することで、より実践的な学びが可能になります。
具体的な事例を基に議論することで、現実的な解決策を見いだすことができます。
|
職場でのコンセンサスが得やすい
全員が同じ研修を受けることで、改善に向けた方向性の共有と合意形成がスムーズになります。
研修で学んだ内容を実践する際も、全員が同じ理解を持っているため、スムーズな解決策の導入が可能です。
|
社内トレーナーで展開可能
研修の内容を理解し、実践できる社内トレーナーを育成することで、継続的な改善活動が可能になります。
外部講師に頼らず、自社の文化や特性に合わせた研修プログラムを展開できることは、大きなメリットをもたらします。
|
▼職場単位で研修を行うことが効果的である理由については下記で詳しく解説しています。
⇒職場の活性化につなげる方法とは?アイデアやポイントを紹介!
研修を社内講師で展開した支援事例
社員数: 2,000名以上
事業:医薬品、機能食品の製造・販売
導入前の課題
コロナ禍による営業スタイルの変化と職場のコミュニケーション減少~打開のカギを握るのは営業所長~
製薬業界の取り巻く環境変化の一つとして、withコロナ時代においてテレワークが推進され、営業所内での「対面でのコミュニケーション」は圧倒的に減少していました。
特にコロナ前まではできていた横や斜め(同僚間や別部門)の関わりが少なくなり、業務上の全ての判断や相談がラインの上長に集中するようになりました。出社することで自然と社内情報が入ってきていた環境が、コロナ禍によりなくなってしまいました。
また、MR(医薬情報担当者)の情報提供活動においてもオンラインでの対応が求められるようになり、新しい方法を模索しないといけない状況になりました。
営業所内の目標達成や職場内のコミュニケーション向上のカギは営業所長が握っていることから、営業所長がリーダーシップを発揮し、問題解決をしていくための方法を探していました。
取り組みの詳細
営業所長による職場ワークショップを完全オンラインで実施~半年間で7割以上の営業所に展開~
MRを取り巻く環境変化に合わせて、マインドやスキル強化の一つとしてLIFOプログラム(※)の導入を決めました。3年でLIFOを社内の共通言語にすることを目指して、まずは2020年5月に営業部門の教育担当4名がLIFOプログラムライセンスを取得しました。
次に営業所長がリーダーシップを発揮し、自職場の問題解決を行うスキルを習得するために、営業所長対象にマネジメント実践スキル講座(MSS認定講座)を実施しました。講座を通じて、職場の問題解決のための道具とスキルを身に付けた営業所長は各職場にてチームづくりワークショップを実施しました。
4名のプログラムライセンス取得者(ライセンシー)は営業所長への個別指導や相談会など、職場展開に向けてのサポートを積極的に行いました。コロナ禍ということもあり、プログラムライセンス取得から、MSS認定、ワークショップ実施まで全てオンラインで実施し、半年間で7割以上の営業所に展開していきました。
2021年度以降、新任営業所長はMSS認定講座を受講し、LIFOという道具とスキルを身に付ける機会をつくっています。2023年度現在では全ての営業所でチームづくりワークショップの実施が完了し、2巡目以降は各職場の課題に合わせてタイムマネジメントや期待役割などのテーマで実施しています。
(※)LIFOプログラム(Life Orientations プログラム)は、個人の価値観や行動特性の傾向を分析し、コミュニケーションやリーダーシップ、タイムマネジメント、人間関係の改善などにおける効果を高めるために用いられる能力開発プログラムです。 |
導入の成果
「コミュニケーションの改善が期待できる!」「他部署へもLIFOを推薦したい!」の声多数
ワークショップ実施後に行ったアンケートでは、7割以上の方が「LIFO診断を受けて、自己理解ができた」、「部署内のグループワークの実施により他者理解ができた」、「LIFOの実施によりコミュニケーションの改善が期待できる」と回答をいただいています。
また、営業所長の9割近くの方が「LIFOの導入を他部署へも推薦したい」と回答いただきました。
タイムマネジメントのワークショップを実施した営業所においては、チーム活動を効果的に進めるためのガイドラインを決めることで、チームの結束力が高まったといった声もありました。
営業部門での評判を聞き、人事部門でもLIFOプログラムライセンスを取得し、経営幹部を巻き込むと同ときに、本社の各部門においてもワークショップを順次進めています。導入から3年が経過し、LIFOが社内の共通言語になりつつあります。
まとめ:人間関係がめんどくさいと感じても自分らしく生きるために
人間関係がめんどくさいと感じたときの対処法とは?原因やポイントを解説!について紹介してきました。
人間関係がめんどくさいと感じるのは正常な反応である
人間関係がめんどくさいと感じる5つの心理的原因
人間関係がめんどくさいと感じやすいシチュエーション
人間関係がめんどくさいと感じたときの即効性のある対処法
めんどくさい人間関係でも職場で実践すべき3つのマインド
人間関係のめんどくささを軽減するコツ
人間関係のめんどくささを改善するには職場単位での研修が手っ取り早い
研修を社内講師で展開した支援事例
人間関係がめんどくさいと感じることは誰もが経験する自然な感情です。その背景には、過度な気遣い、他者評価への過剰意識、内向的な性格などの心理的要因があります。特に職場環境や嫉妬、マウンティングが発生する状況では、この感覚が強まりやすくなります。
対処法としては、表面的な付き合いにとどめる、心理的距離を取る、自分のペースを優先するなどの方法が効果的です。職場では最低限の礼儀を保ちながらも、悪口は避け、過度に同調しないことが重要です。
長期的には自己理解と他者理解を深め、相手に合ったアプローチで適切な関係を築くことが、めんどくささを軽減するカギとなります。人間関係の難しさは成長の機会でもあります。自分を大切にしながら、適切な距離感で他者と関わっていきましょう。
職場の人間関係の改善に向けては、職場単位での研修が手っ取り早いです。全てを解決できるわけではありませんが、人間関係のめんどくささを解消するきっかけになるでしょう。
株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広く支援しています。
無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。