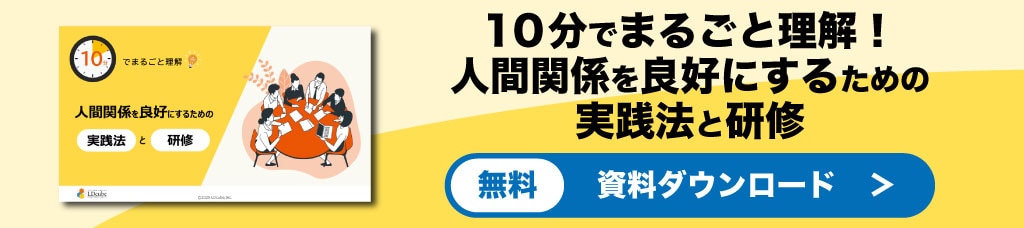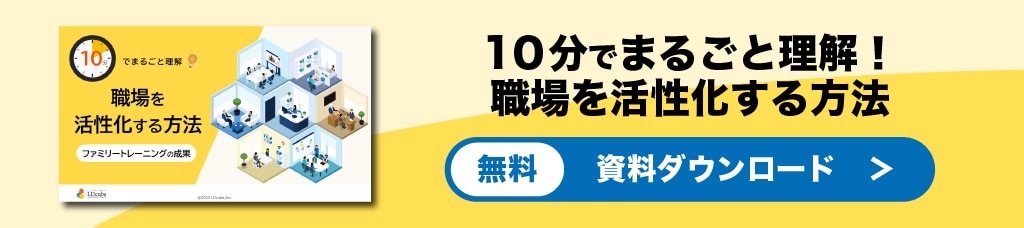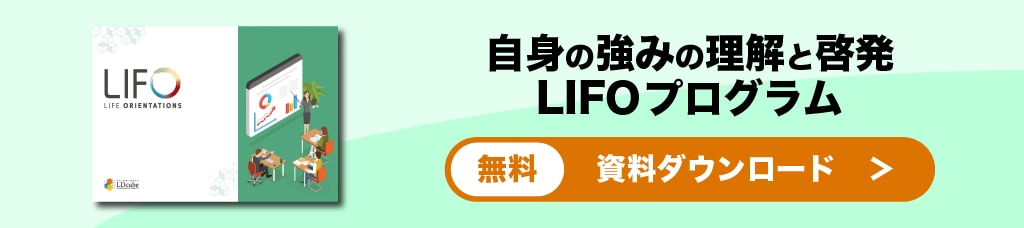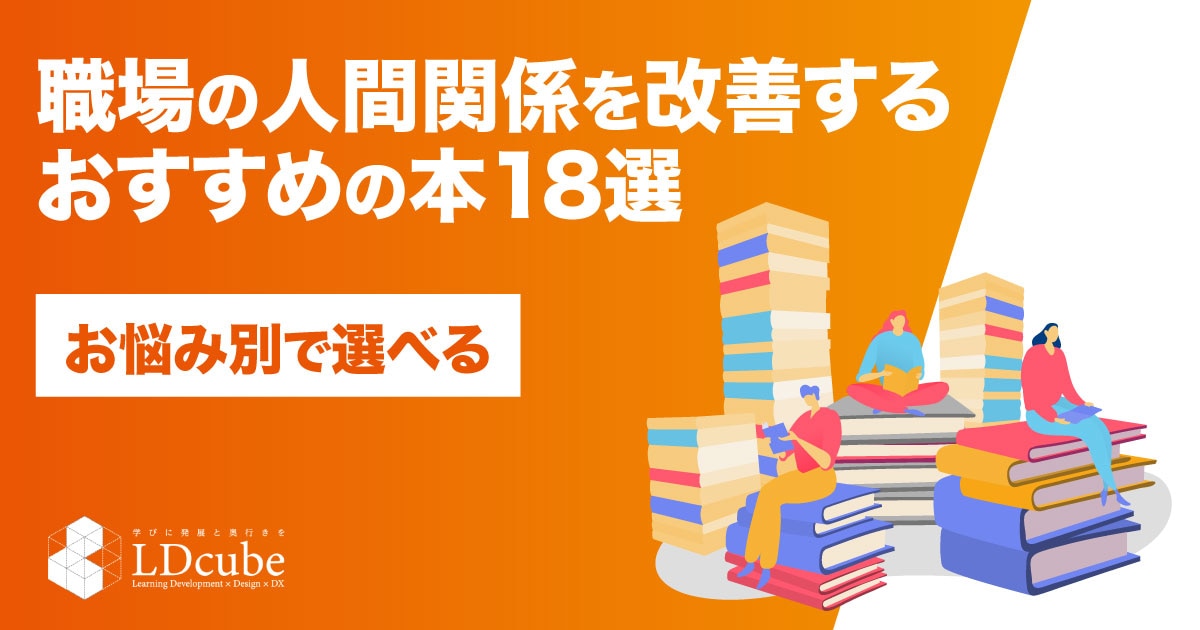
職場の人間関係を改善する【お悩み別で選べる】おすすめの本18選
「職場の人間関係に関する本のおすすめが知りたい」
「仕事関係の人間関係を改善できるおすすめの本が知りたい」
と考えていませんか?
職場の人間関係はスムーズであればあるほど業務も進めやすくなるため、良好にしたい方も多いのではないでしょうか。
そのような方のために、企業の研修サポートを通して様々な職場の課題に熟知した私たちLDcubeが、職場の人間関係にまつわるおすすめの本を以下の通り厳選しました。
【職場の人間関係にまつわるおすすめの本18選一覧】
書籍名 | 概要(一文程度で) |
「しんどさ」を感じている人に向けて、心の負担を軽くする考え方や行動のコツを紹介 | |
職場や社会で理不尽な相手(=アホ)に振り回されないための考え方や実践的な方法を解説 | |
上司のタイプ別に職場でのコミュニケーションを円滑にし、関係を改善するための具体的な方法を解説 | |
上司との関係を円滑にし、仕事で成果を上げるための具体的なコミュニケーション術を解説 | |
コミュニケーションの質を高めるために「聴く」ことの重要性を理論的かつ実践的に解説 | |
職場においてストレスを引き起こす「困った人たち」からのストレス対処法を学べる | |
同僚へのフォローによるストレスを軽減する方法や、自分自身を守る術を解説 | |
部下との人間関係の悩みを解消し、より良いコミュニケーションを築くための具体的な方法を解説 | |
職場やビジネスシーンで「人に気持ちよく動いてもらう」ための具体的な方法を体系化 | |
「完全にわかりあうことは不可能」という前提に立ちながらも、対話を通じて共有できる部分を探し、関係性を築く方法を提案 | |
部下の行動を促し、成長を後押しするための具体的な「言葉がけ」の技術を解説 | |
仏教の教えをもとに、心のムダな反応を抑えることで悩みや苦しみから解放され、人生をよりラクに生きるための具体的な方法を解説 | |
「自己欺瞞(箱)」を理解し、抜け出すことで、職場などでの人間関係を改善する方法を解説 | |
「アドラー心理学」をもとに、他人の評価や期待に縛られず、自分らしく生きる方法を解説 | |
職場の「めんどくさい人」との関係に悩む人に向けて、具体的な対処法や心理学的なアプローチを解説 | |
カーネギーが人間関係の本質を探求し、人を動かすための30の原則を体系化した自己啓発書 | |
「聴く」ことの重要性を科学的に解き明かし、深く聴くことで人間関係を改善する方法を提案 | |
心理的安全性を高めるための具体的な方法を、日本の組織文化に合わせて解説 |
ご自身の悩みに合う本を上記の中から選びましょう。
ただし本を読んだからといって、人間関係の悩みが解決するわけではありません。
本を読みっぱなしにしてしまい、学んだことを実践しなければ、いつまでも人間関係の課題に悩まされ続ける可能性があるでしょう。
そのため「いかに本で読んだことを実践に活かすか」が重要になります。
本記事では、職場の人間関係に関するおすすめの本をご紹介するだけでなく「本で学んだことを実践で活かすためのポイント」もあわせて解説します。
本記事の内容は以下のとおりです。
本記事の内容 |
|
本記事を読むことで、ご自身の悩みに合う職場での人間関係のおすすめ本を知ることができます。
またそれだけでなく、本で学んだことを人間関係の中で実践できるようになり、悩みの解決へと近づくことができるでしょう。
ぜひ最後までお読みください。
▼社内での「読書会(対話会)」のやり方については下記で詳しく解説しています。
▼人間関係についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。
▼人間関係を良好にするための実践法と研修については下記にまとめています。
目次[非表示]
- 1.職場における人間関係にまつわる本の選び方
- 2.対上司×気疲れ・ストレスタイプにおすすめの本2選
- 3.対上司 × スキル・対処法不足タイプにおすすめの本3選
- 3.1.上司へのすごい伝え方
- 3.2.仕事ができる人に変わる上司への接し方3選
- 3.3.まず、ちゃんと聴く。
- 4.対同僚・部下 × 気疲れ・ストレスタイプにおすすめの本3選
- 4.1.困った上司・やっかいな同僚
- 4.2.職場の同僚のフォローに疲れたら読む本
- 4.3.部下をもつ人の職場の人間関係
- 5.対同僚・部下 × スキル・対処法不足タイプにおすすめの本3選
- 6.誰に対しても気疲れ・ストレスを感じるタイプにおすすめの本4選
- 6.1.反応しない練習
- 6.2.自分の小さな「箱」から脱出する方法
- 6.3.嫌われる勇気
- 6.4.職場のめんどくさい人から自分を守る心理学
- 7.誰に対してもスキル・対処法が不足しているタイプにおすすめの本3選
- 8.読むだけでは意味がない!読んだことを実践するのが重要
- 9.人間関係の本で学んだことを実践に活かすための3つのポイント
- 9.1.簡単な行動からひとつずつ実践する
- 9.2.本に書かれた内容を自分に置き換えて考える
- 9.3.振り返りをする
- 10.組織内の人間関係を改善するには研修の実施もおすすめ
- 11.まとめ
職場における人間関係にまつわる本の選び方
まずは職場における人間関係の悩みを明らかにしたうえで、その悩みに合う本を選びましょう。
人間関係の本とはいえ、「上司の言動がストレスになる」「部下との接し方がわからない」など、悩みの種類はさまざまであり、それぞれの悩みに適切にアプローチできる本は異なります。
そのため、まずは「悩みの対象は誰か」「どのようなタイプの悩みがあるか」という二軸でご自身の人間関係の悩みの種類を特定してから、おすすめの本を探しましょう。
具体的に職場の人間関係の悩み別におすすめの本をご紹介すると以下のとおりです。
【悩み別のおすすめ本一覧】
悩みの対象 | 悩みのタイプ | おすすめの本 |
|---|---|---|
対上司 | 【気疲れ・ストレスタイプ】 | |
【対人スキル・対処法不足タイプ】 | ||
対同僚・部下 | 【気疲れ・ストレスタイプ】 | |
【対人スキル・対処法不足タイプ】 | ||
全般 | 【気疲れ・ストレスタイプ】 | |
【対人スキル・対処法不足タイプ】 |
職場の人間関係は、主に「上司」「同僚・部下」の2つに大別でき、場合によっては誰に対しても人間関係にまつわる悩みを抱えていることもあるでしょう。
そのため、本記事では「上司」「同僚・部下」「全般(誰に対しても)」を対象にした悩みにアプローチできる本をご紹介しています。
また悩みのタイプについては、大きくは以下の2つに大別できます。
ご自身の悩みのタイプがわからない場合は、以下を参考にし、どちらのタイプがご自身の状況に多く当てはまるかをチェックして、判断しましょう。
【悩みのタイプ診断】
悩みのタイプ | 当てはまる人 |
気疲れ・ストレス | 相手の態度・発言の「受け取り方」に課題があり気疲れやストレスを感じる
|
対人スキル・対処法不足 | 自身の態度・発言など「発信」の仕方に課題があり人間関係がうまくいかない
|
それでは2章以降で、お悩み別におすすめの本を解説していきます。
対上司×気疲れ・ストレスタイプにおすすめの本2選

まずは上司の態度・発言の「受け取り方」に課題があり気疲れやストレスを感じる人に、おすすめの本を以下2冊ご紹介します。
上司の態度・発言の「受け取り方」に課題があり気疲れやストレスを感じる人 |
◆職場の「しんどい」がスーッと消える大全/石原加受子 ◆頭に来てもアホとは戦うな!/田村耕太郎 |
それぞれ見ていきましょう。
職場の「しんどい」がスーッと消える大全
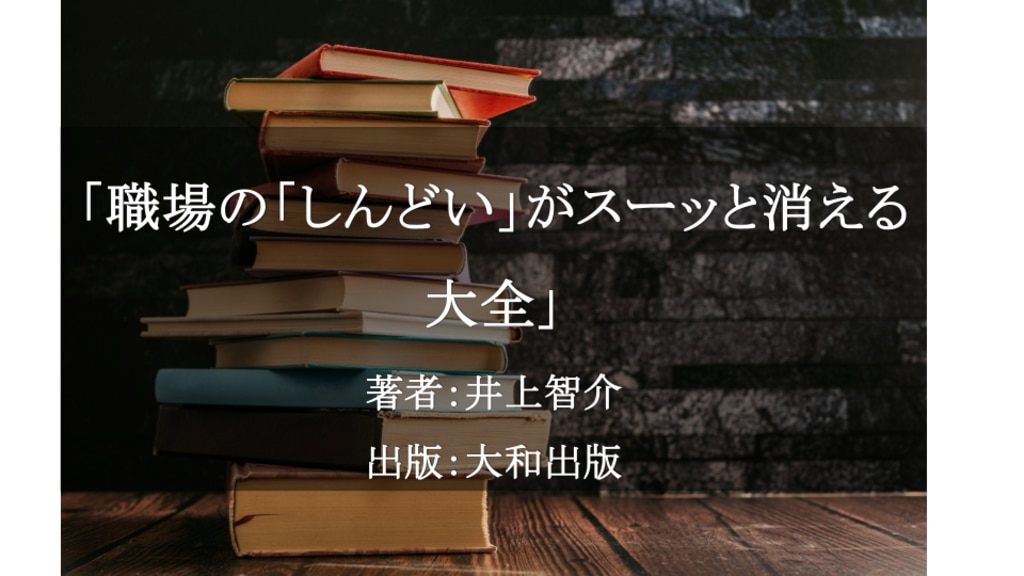
対上司×気疲れ・ストレスタイプにおすすめの本1冊目は井上智介著の「職場の『しんどい』がスーッと消える大全」です。
出版社 | 大和出版 |
筆者 | 井上智介 |
値段 | 1,870円(税込) |
出版年月日 | 2019年8月31日 |
ページ数 | 256ページ |
詳細(出版社公式サイト) | |
Kindle | あり |
本の概要
この本は、職場の人間関係や業務で「しんどさ」を感じている人に向けて、精神科医であり産業医である著者が、心の負担を軽くする考え方や行動のコツを紹介しています。
具体的には、以下のような内容を解説しています。
【目次】
|
このように、この本は職場で「しんどい」思いをしている人に対し、どのような心の持ち方・考え方、対処をすればいいのかを寄り添いながら解説してくれています。
おすすめポイント
本書は、現場の事例を取り上げて具体的・実践的な解決策を提示してくれている点が魅力です。
例えば、以下のような内容が書かれています。
- 仕事を押しつけられそうな時の対処法
- 相談や断るときに有効なトーク例
上記のような明日からでも使えるテクニックが記載されており、上司に対して感じるストレスを軽減できるでしょう。
実際に読者からは以下のような声が寄せられています。
【読者レビュー】
|
このように上司の態度や発言がストレスになっている人にとって、役立つ内容であると評価されています。
職場での「しんどい」を感じる瞬間に役立つヒントが詰まっているため、特に以下の方におすすめです。
こんな人におすすめ |
|
頭に来てもアホとは戦うな!
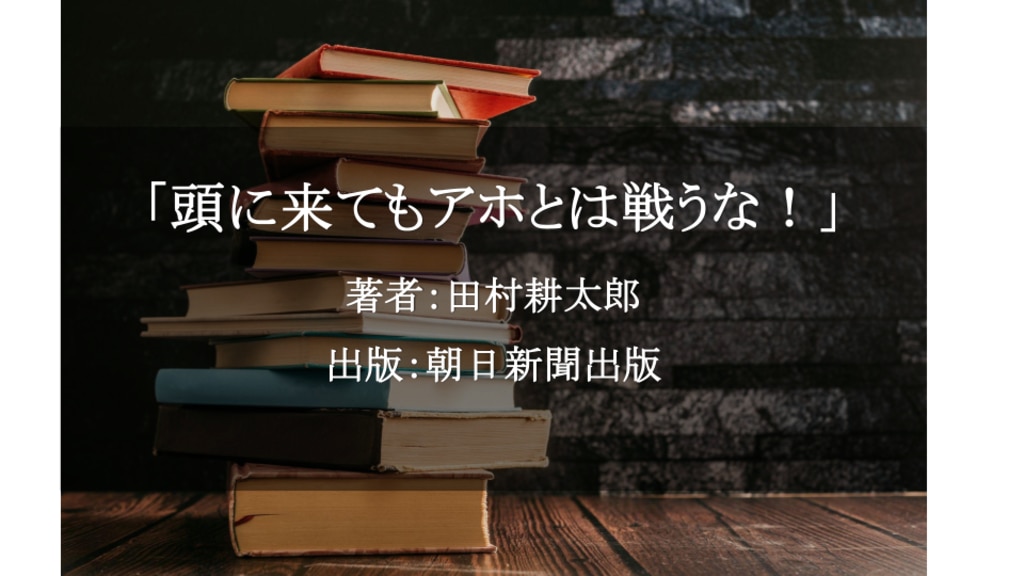
対上司×気疲れ・ストレスタイプにおすすめの本2冊目は田村耕太郎著の「頭に来てもアホとは戦うな!」です。
出版社 | 朝日新聞出版 |
筆者 | 田村耕太郎 |
値段 | 1,430円(税込) |
出版年月日 | 2014年7月8日 |
ページ数 | 224ページ |
詳細(出版社公式サイト) | |
Kindle | あり |
本の概要
本書は職場や社会で理不尽な相手(=アホ)に振り回されず、自分の時間を有効に使うための考え方や実践的な方法を解説したビジネス書です。
著者の田村耕太郎氏が、自身の経験と失敗をもとに「アホ」との無駄な戦いを避け、成果を出すためのコツを提案しています。
具体的な内容は以下のとおりです。
【目次】
|
このように「アホ」とは戦わず、「自分自身と向き合う」ことで人生の目的達成に集中する姿勢を提案する内容になっています。
おすすめポイント
本書は、理不尽な相手(=「アホ」)に振り回されず、ストレスを軽減させるための考え方が学べる点が魅力です。
上司を「アホ=理不尽な相手」として本書を読めば、上司に対して自分自身はどのような態度でいればいいのか、その答えが見えてくるでしょう。
例えば、以下のような考え方や振る舞い方を学ぶことができます。
- 理不尽な態度を取ってくる人を冷静に受け流す技術
- 弱い人が大好物の「アホ」に振り回さないための、自信満々な態度の取り方(振る舞い方)
実際にこの本を読んだ人からは、以下のような声が挙がっています。
【読者レビュー】
|
こうした声からも、上司をストレスに感じている人にとって、実際の現場で役立つ内容であることがわかります。
そんな本書は、上司にストレスを感じる人の中でも、特に以下に当てはまる人におすすめの書籍といえるでしょう。
こんな人におすすめ |
|
対上司 × スキル・対処法不足タイプにおすすめの本3選

次に上司に対してどのようにコミュニケーションを取ればいいのかわからない人に、おすすめの本を以下3冊ご紹介します。
自身の態度・発言などによって上司との関係がうまくいかない人におすすめの本3選 |
◆上司へのすごい伝え方/斉藤由美子 ◆仕事ができる人に変わる上司への接し方3選/まさしお ◆まず、ちゃんと聴く。/櫻井 将 |
それぞれ見ていきましょう。
上司へのすごい伝え方
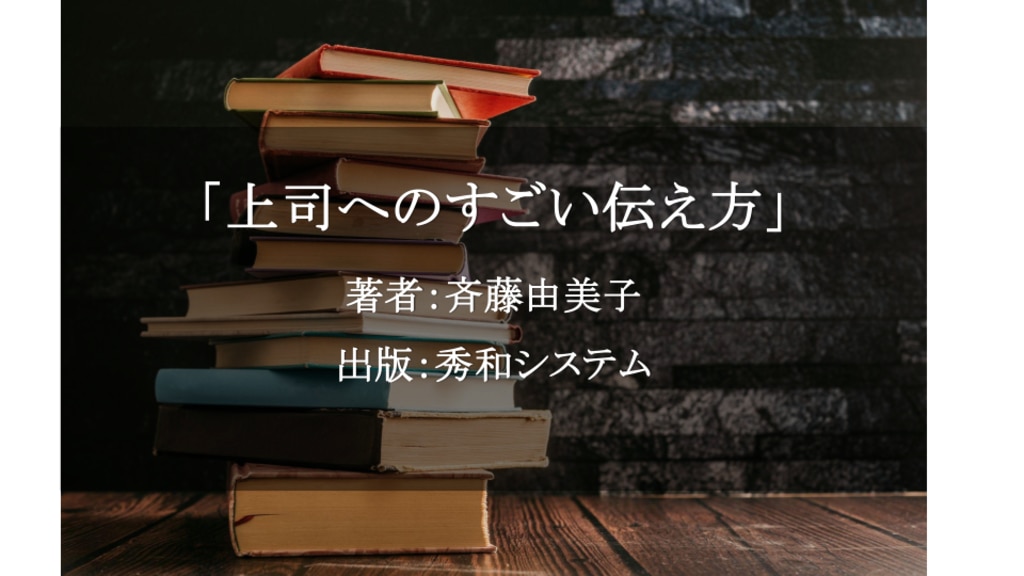
対上司×スキル・対処法不足タイプにおすすめの本1冊目は、斉藤由美子著の「上司へのすごい伝え方」です。
出版社 | 秀和システム |
筆者 | 斉藤由美子 |
値段 | 1,650円(税込) |
出版年月日 | 2021年4月17日 |
ページ数 | 240ページ |
詳細(出版社公式サイト) | |
Kindle | あり |
本の概要
本書は、ソーシャルスタイル理論(※)を活用して職場でのコミュニケーションを円滑にし、上司との関係を改善するための具体的な方法を解説した本です。
具体的な内容は以下のとおりです。
【目次】
|
このように、職場で「なぜか苦手な上司」に悩む人々に向けて、ソーシャルスタイル理論を活用した具体的なコミュニケーション術が解説されています。
※ソーシャルスタイル理論:コミュニケーションのタイプを4つに分類する理論
おすすめポイント
この本のおすすめポイントは、上司を4つのタイプに分類し、それぞれのタイプに適した伝え方を具体的に解説している点です。
上司とのコミュニケーションに「性格や相性のせいにしない具体策」が持てるというのは、非常に心強いのではないでしょうか。
例えば、本書では以下のようなコミュニケーション方法を提案しています。
ソーシャルスタイル理論 | 上司を4タイプに分類し、それぞれの特徴と対応方法を解説されている |
タイプ別コミュニケーション術 | 上司のタイプ別に具体的な行動例が紹介されている |
自分自身のタイプ診断 | 自分のコミュニケーションスタイルを理解し、それを上司との関係性に活かす方法が提案されている |
オンライン時代の対応法 | ZOOMやLINEなどデジタルツールを使ったコミュニケーションでも、相手のタイプ別に適切な言い回しや行動例が紹介されている |
実際に読者からは以下のような声が寄せられています。
【読者レビュー】
|
こうしたことから、「ソーシャルスタイル理論」を活用したタイプ別対応法や、自分自身の診断方法は読者から高評価を得ていることが分かります。
本書を読むのがおすすめな人は以下のとおりです。
こんな人におすすめ |
|
仕事ができる人に変わる上司への接し方3選
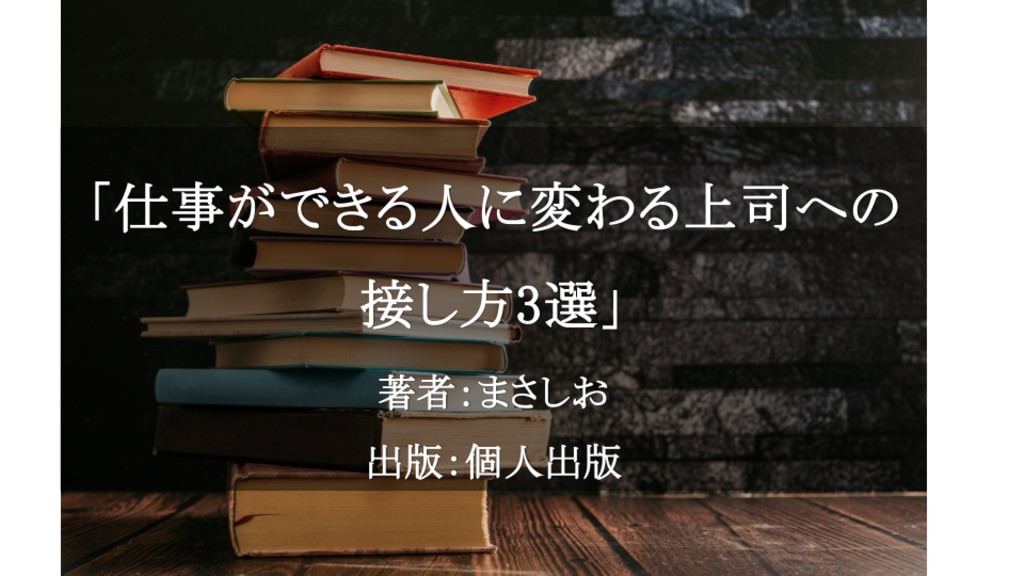
対上司×スキル・対処法不足タイプにおすすめの本2冊目は、まさしお著の「仕事ができる人に変わる上司への接し方3選」です。
出版社 | 個人出版 |
筆者 | まさしお |
値段 | 1,320円(税込) |
出版年月日 | 2023年7月27日 |
ページ数 | 142ページ |
詳細(出版社公式サイト) | なし |
Kindle | あり |
本の概要
本書は上司との関係を円滑にし、仕事で成果を上げるための具体的なコミュニケーション術を解説した本です。
上司の期待に応える方法を明確にし信頼を築くことで、効率的に仕事を進めるための実践的なコミュニケーション方法が紹介されています。
具体的な内容は以下のとおりです。
【目次】
|
このように、この本は「指示に従う」「役割の責任を果たす」「報連相を徹底する」というシンプルでありながらも重要な3つのポイントをメインに解説しています。
おすすめポイント
この本は、上司とのコミュニケーションには、「指示に従う」「役割の責任を果たす」「報連相を徹底する」の3つが重要だとシンプルかつベーシックな主張をしている点が魅力です。
コミュニケーション術に関する本にはさまざまなテクニックが掲載されていますが、意識すべきことは3つだと言いきってもらえると安心できるのではないでしょうか。
そんな本書は、具体的には以下のような内容を解説しています。
指示に従う | 上司からの指示を正確に理解し、期待以上の成果を出す方法が解説されている |
役割の責任を果たす | 上司からの評価が向上するように自信の役割を果たす方法を紹介している |
報連相を徹底する | 報連相のタイミングや内容について具体的なポイントを解説している |
実際にこの本を読んだ読者からは、以下のような声が挙がっています。
【読者レビュー】
|
このように、シンプルでベーシックな内容ながらも、具体的なコミュニケーション方法を学べる点が読者から高く評価されています。
本書を読むのに特におすすめな人は以下のとおりです。
こんな人におすすめ |
|
まず、ちゃんと聴く。
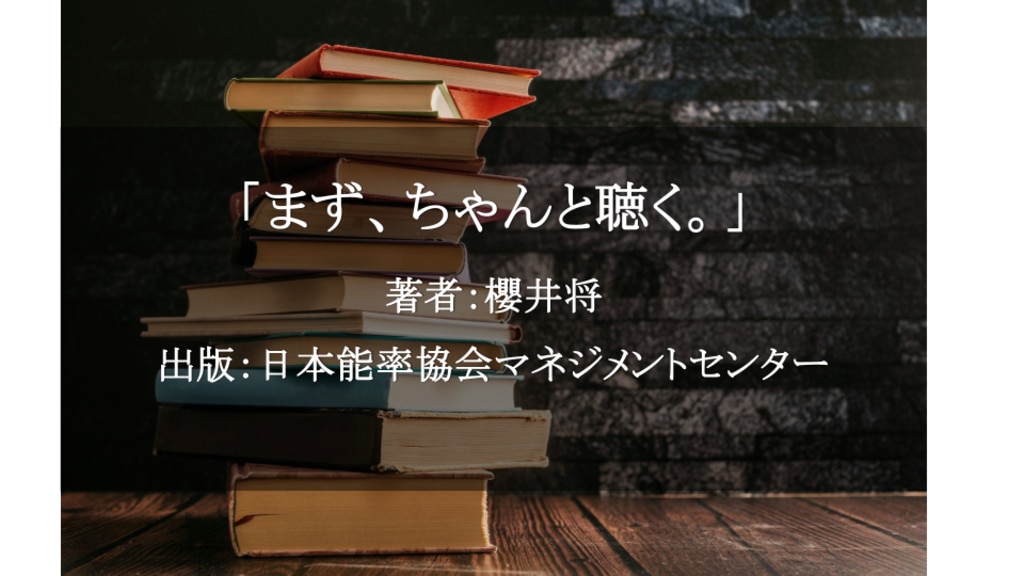
対上司×スキル・対処法不足タイプにおすすめの本3冊目は、櫻井将著の「まず、ちゃんと聴く。」です。
出版社 | 日本能率協会マネジメントセンター |
筆者 | 櫻井将 |
値段 | 1,870円(税込) |
出版年月日 | 2023年10月13日 |
ページ数 | 320ページ |
詳細(出版社公式サイト) | |
Kindle | あり |
本の概要
この本はコミュニケーションの質を高めるために「聴く」ことの重要性を理論的かつ実践的に解説している本です。
具体的な内容は以下のとおりです。
【目次】
|
目次から分かるように、「聴く」と「伝える」の両立によってコミュニケーションを改善し、人間関係や組織運営を円滑にするための具体的な方法を提案してくれる内容となっています。
おすすめポイント
この本は上司とのコミュニケーションに限定して書かれているわけではありませんが、「聴く」と「伝える」のバランスを取る技術が、上司との関係構築に役立つはずです。
具体的には、以下のようなコミュニケーション方法が紹介されています。
聴くことの重要性 | 相手の話をじっくり聴く姿勢の重要性が解説されている |
聴く・伝えるの両立 | 聴くだけでなく、適切に伝える技術も解説されている |
心理的安全性の構築 | 聴き手と話し手の間で心理的安全性をつくることの重要性が解説されている |
実際にこの本を読んだ人からは、以下のような声が挙がっています。
【読者レビュー】
|
このように、本書は紹介された「聴き方」「伝え方」によって上司とのコミュニケーションがスムーズになったと高く評価されています。
この本が特におすすめな人は以下のとおりです。
こんな人におすすめ |
|
対同僚・部下 × 気疲れ・ストレスタイプにおすすめの本3選

次に同僚や部下の態度・発言に気疲れやストレスを感じる人に、おすすめの本を以下3冊ご紹介します。
同僚や部下の態度・発言に気疲れやストレスを感じる人におすすめの本3選 |
◆困った上司・やっかいな同僚/エイミー・ギャロ ◆職場の同僚のフォローに疲れたら読む本/佐藤 恵美 ◆部下をもつ人の職場の人間関係/水島広子 |
それぞれ見ていきましょう。
困った上司・やっかいな同僚
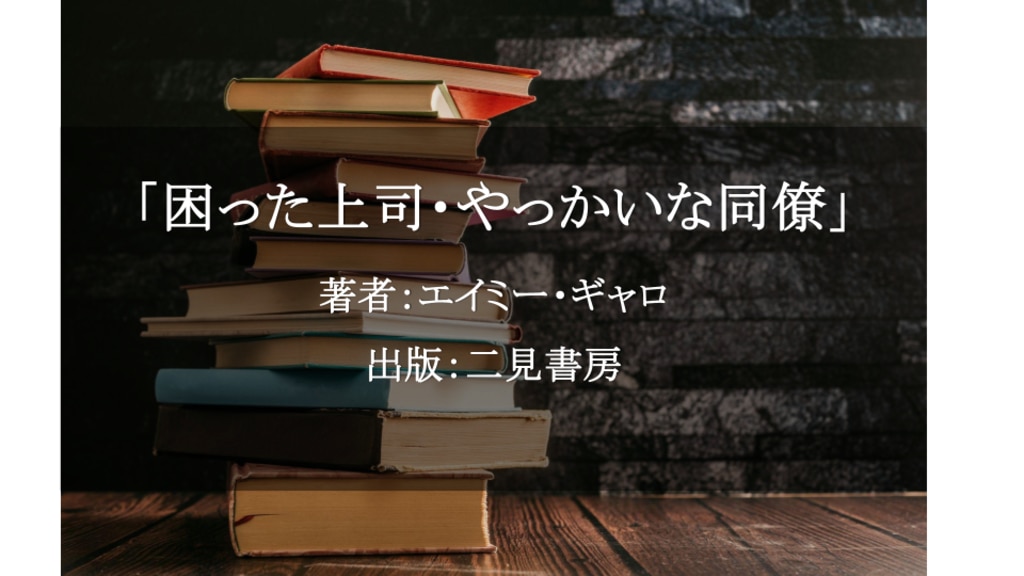
対同僚・部下×気疲れ・ストレスタイプにおすすめの本1冊目はエイミー・ギャロ著の「困った上司・やっかいな同僚」です。
出版社 | 二見書房 |
筆者 | エイミー・ギャロ |
値段 | 1,980円(税込) |
出版年月日 | 2023年6月23日 |
ページ数 | 336ページ |
詳細(出版社公式サイト) | |
Kindle | あり |
本の概要
この本は職場においてストレスを引き起こす「困った人たち」からのストレス対処法を学べる一冊です。
具体的には以下のような内容が紹介されています。
【目次】
|
このように本書は、職場で悩む多くの人々に寄り添いながら、実践的な解決策を提示し、さまざまな職場環境で役立つノウハウが詰まっています。
おすすめポイント
本書の魅力は、職場でストレスを引き起こす「困った人たち」を8つのタイプに分類し、それぞれの特徴を理解した上で効果的なストレス対処法を提案している点にあります。
さらには9つの原則を活用することで、職場の人間関係を劇的に改善し、ストレスを軽減する実践的な方法を学ぶこともできます。
具体的には、以下のような内容が紹介されています。
困った人たちの | ・不安を抱えた上司 など、8つのタイプを紹介し、それぞれの特徴と攻略法を解説している |
9つの原則 | 人間関係の問題解決のために守るべき原則が具体的に示されている |
実際に読者からは以下のような声が寄せられています。
【読者レビュー】
|
このように本書の内容が関係改善やストレス改善につながるといった評価を得ていることがうかがい知れます。
この本は以下のような人に特におすすめです。
こんな人におすすめ |
|
職場の同僚のフォローに疲れたら読む本
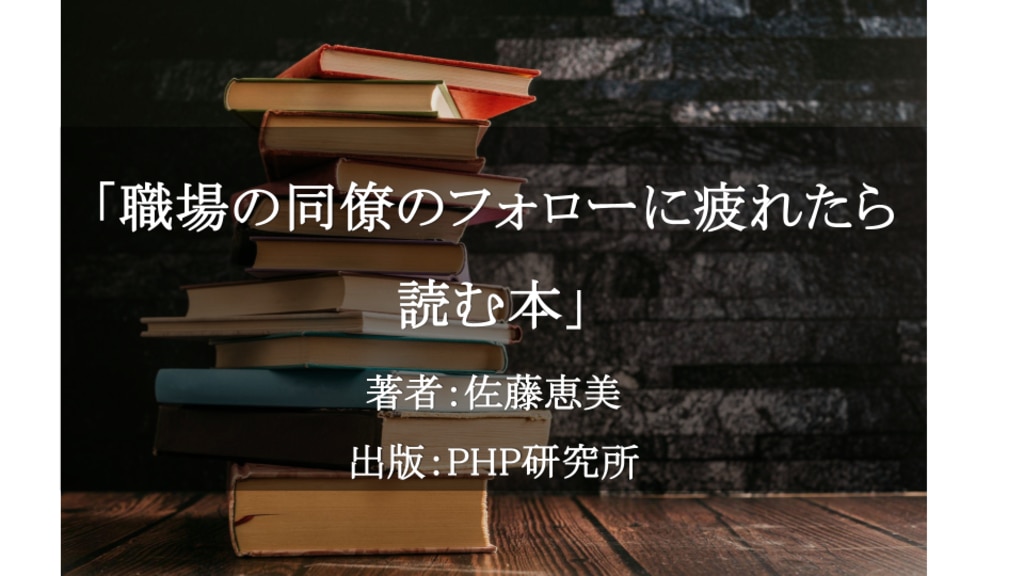
対同僚・部下×気疲れ・ストレスタイプにおすすめの本2冊目は佐藤 恵美著の「職場の同僚のフォローに疲れたら読む本」です。
出版社 | PHP研究所 |
筆者 | 佐藤恵美 |
値段 | 1,760円(税込) |
出版年月日 | 2024年7月25日 |
ページ数 | 256ページ |
詳細(出版社公式サイト) | |
Kindle | あり |
本の概要
本書は労働者メンタルヘルスの専門家である著者が、20年間で1万人以上の相談実績をもとに、同僚へのフォローによるストレスを軽減する方法や、自分自身を守る術を解説しています。
具体的には以下のような内容が紹介されています。
【目次】
|
職場で「助け合い」や「協力」の名目で行われる過剰なフォローによる負担に悩む人々に向けて、ストレス軽減と自己防衛術を提供してくれる一冊です。
おすすめポイント
この本の魅力は、労働者メンタルヘルスの専門家である著者が、1万人以上の働く人の相談に乗ってきた経験に基づいて、効果があると実感しているメソッドを厳選して紹介している点です。
例えば、以下のような内容が紹介されています。
「自分にエネルギーを補充する」技術 | 心身を回復させる具体的なメソッドが紹介されている |
疲れきらない技術 | 職場でストレスを最小限に抑えるためのコミュニケーション術や、適切な距離感の保ち方が解説されている |
「職場と自分の関係性」を見直す方法 | 自分自身の捉え方や働き方を見直すことで、ストレスから解放される方法が紹介されている |
実際に読者からは以下のような声が寄せられています。
【読者レビュー】
|
この本は同僚に感じるストレスについて幅広くカバーしており、上記のように読者から「気持ちが軽くなった」「共感できる」と高評価を得ています。
この本は以下のような人に特におすすめです。こんな人におすすめ
こんな人におすすめ |
|
部下をもつ人の職場の人間関係
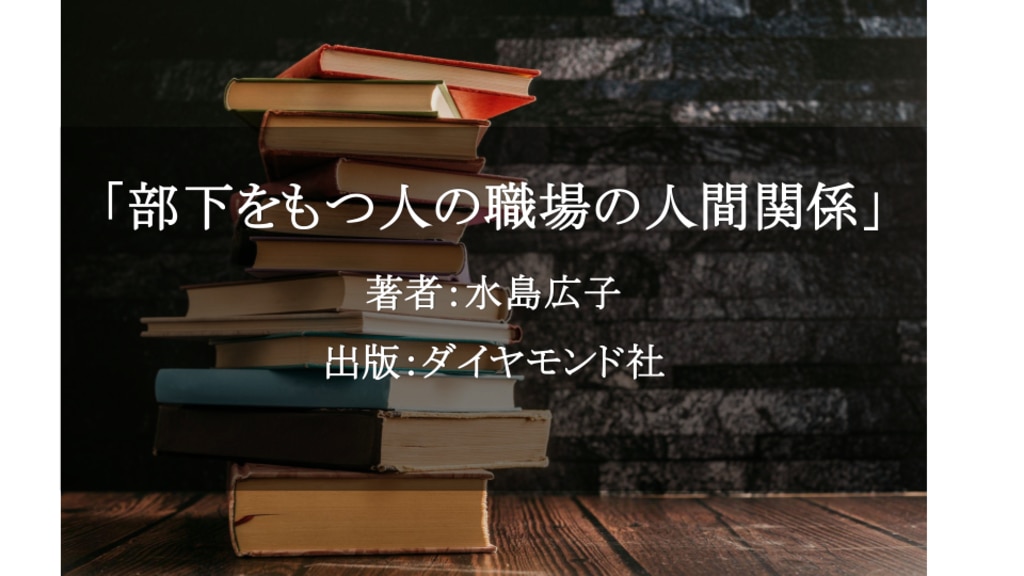
対同僚・部下×気疲れ・ストレスタイプにおすすめの本3冊目は水島広子著の「部下をもつ人の職場の人間関係」です。
出版社 | ダイヤモンド社 |
筆者 | 水島広子 |
値段 | 1,540円(税込) |
出版年月日 | 2015年11月 |
ページ数 | 232ページ |
詳細(出版社公式サイト) | |
Kindle | あり |
本の概要
この本は対人関係療法の第一人者である著者が、部下との人間関係の悩みを解消し、より良いコミュニケーションを築くための具体的な方法を解説した本です。
具体的には以下の内容が紹介されています。
【目次】
|
このように部下とのコミュニケーションに悩む中間管理職やリーダー層には必読の内容となっています。
おすすめポイント
この本のおすすめポイントは、単なる「上司力の教科書」ではなく、部下との間にある見えない溝(=役割期待のずれや価値観のギャップ)をどう埋めるかを丁寧に解説してくれる点にあります。
例えば、以下のような内容が詳しく書かれています。
「聴く力」を活用した信頼構築 | 部下の話を聴く際の、相手を尊重したコミュニケーション技術が紹介されている |
「話す力」を鍛える具体的な方法 | 部下へのフィードバックや指導の際、誤解や摩擦を減らし円滑なコミュニケーションを行うための方法が書かれている |
実際に読者からは以下のような声が寄せられています。
【読者レビュー】
|
上司として「うまくやらなきゃ」と肩に力が入りすぎている人にとって、部下と本音で向き合い、ストレスを減らすための具体策が詰まった良書といえるでしょう。
こんな人におすすめ |
|
対同僚・部下 × スキル・対処法不足タイプにおすすめの本3選

次に自身の態度・発言などによって同僚や部下との関係がうまくいかない人に、おすすめの本を以下3冊ご紹介します。
自身の態度・発言などによって同僚や部下との関係がうまくいかない人におすすめの本3選 |
◆気持ちよく人を動かす/高橋浩一 ◆わかりあえないことから/平田オリザ ◆どう伝えればわかってもらえるのか? 部下に届く 言葉がけの正解/吉田 幸弘 |
それぞれ見ていきましょう。
気持ちよく人を動かす
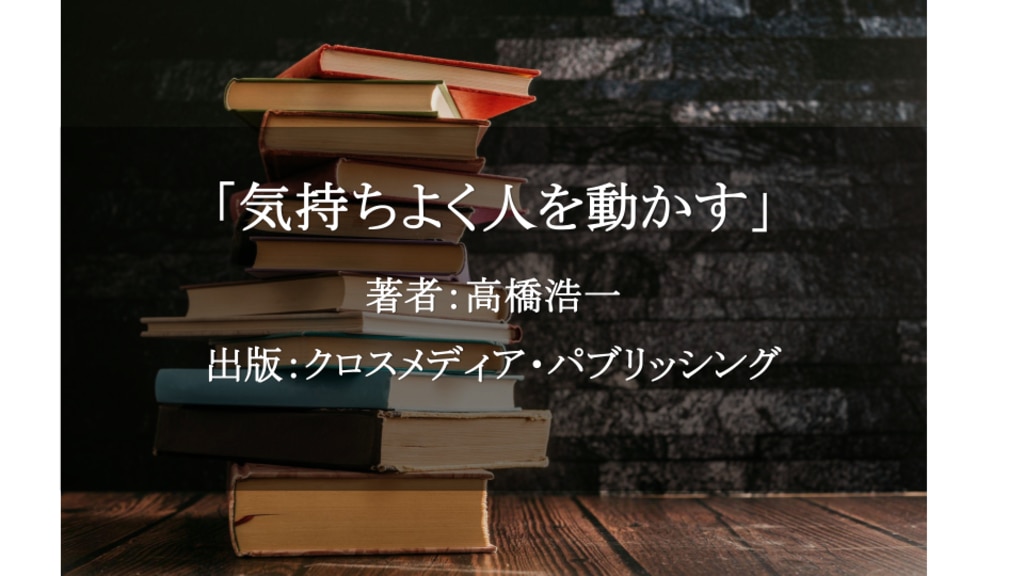
対同僚・部下×スキル・対処法不足タイプにおすすめの本1冊目は高橋浩一著の「気持ちよく人を動かす」です。
出版社 | クロスメディア・パブリッシング |
筆者 | 高橋浩一 |
値段 | 1,738円(税込) |
出版年月日 | 2021年9月1日 |
ページ数 | 296ページ |
詳細(出版社公式サイト) | |
Kindle | あり |
本の概要
この本は職場やビジネスシーンで「人に気持ちよく動いてもらう」ための具体的な方法を体系化した本です。
具体的には以下の内容が解説されています。
【目次】
|
このように7つの「人を動かすためのスキル」を紹介し、相手を表面的に説得するのではなく心からの合意によって動いてもらう方法を解説しています。
おすすめポイント
この本の魅力は、相手に心から納得してもらい、ストレスなく動いてもらう実践的なコミュニケーション術が学べるという点です。
具体的には以下のような内容が解説されています。
|
実際に読者からは以下のような声が寄せられています。
【読者レビュー】
|
本書の考え方は部下との関係に悩む読者から高評価を得ており、リーダー層や中間管理職にとって有益な内容となっています。
こんな人におすすめ |
|
わかりあえないことから
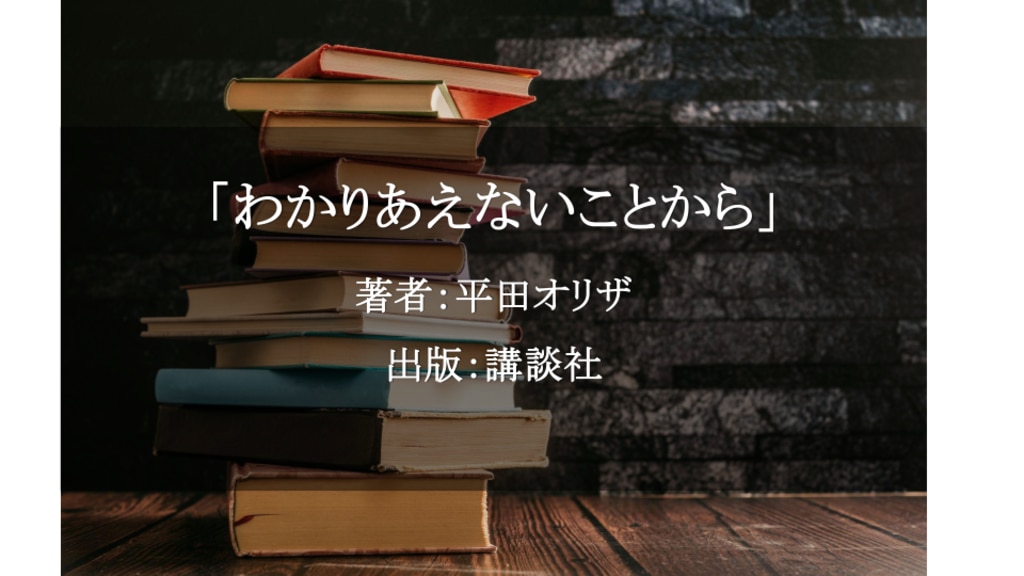
対同僚・部下 × スキル・対処法不足タイプにおすすめの本2冊目は平田オリザ著の「わかりあえないことから」です。
出版社 | 講談社 |
筆者 | 平田オリザ |
値段 | 968円(税込) |
出版年月日 | 2012年10月18日 |
ページ数 | 232ページ |
詳細(出版社公式サイト) | |
Kindle | あり |
本の概要
この本はコミュニケーション能力とは何かを問い直し、「完全にわかりあうことは不可能」という前提に立ちながらも、対話を通じて共有できる部分を探し、関係性を築く方法を提案してくれる本です。
具体的には、以下の内容が書かれています。
【目次】
|
このように、この本では「わかりあえない」という現実を受け入れた上で、対話によって共有できる部分を探し、関係性を築くための具体的な方法を示してくれます。
おすすめポイント
この本のおすすめポイントは、「わかりあえない相手」との関係性を築く方法を提案してくれる点です。
特に部下や同僚に限定した内容ではないものの、同僚や部下との職場での価値観の違いや意見の食い違いに悩む人にとって、関係性を築くヒントとなるでしょう。
例えば、以下のような具体的なコミュニケーション方法が紹介されています。
|
実際に読者からは以下のような声が寄せられています。
【読者レビュー】
|
このように同僚や部下とのコミュニケーションについて「わかりあえない」という前提に立ち、対話をしていくことが関係改善につながったと読者から高評価を得ています。
こんな人におすすめ |
|
どう伝えればわかってもらえるのか? 部下に届く 言葉がけの正解
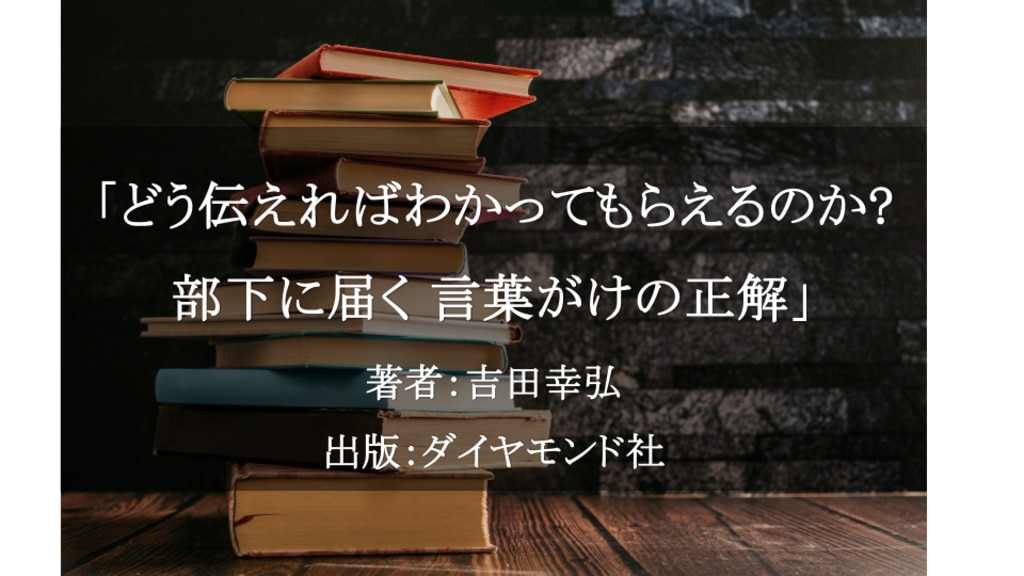
対同僚・部下 × スキル・対処法不足タイプにおすすめの本3冊目は吉田幸弘著の「どう伝えればわかってもらえるのか? 部下に届く 言葉がけの正解」です。
出版社 | ダイヤモンド社 |
筆者 | 吉田幸弘 |
値段 | 1,540円(税込) |
出版年月日 | 2020年6月 |
ページ数 | 224ページ |
詳細(出版社公式サイト) | |
Kindle | あり |
本の概要
この本は部下とのコミュニケーションに悩むリーダー向けに、部下の行動を促し、成長を後押しするための具体的な「言葉がけ」の技術を解説した本です。
以下の内容が本書で解説されています。
【目次】
|
このように本書は、適切な言葉選びによって部下のモチベーションや成長を促進する方法を提案してくれる一冊です。
おすすめポイント
この本のおすすめは、部下に行動を促しながら信頼関係を築くための「言葉がけ」が具体的なシチュエーションごとに紹介されている点です。
例えば、以下のような内容が本書で紹介されています。
|
実際に読者からは以下のような声が寄せられています。
【読者レビュー】
|
このように、具体的なシーン別フレーズや実践しやすい方法が紹介されているため、実際に効果があったと読者から高評価を得ています。
こんな人におすすめ |
|
誰に対しても気疲れ・ストレスを感じるタイプにおすすめの本4選

次に、誰に対しても、気疲れやストレスを感じる人に、おすすめの本を以下4冊ご紹介します。
職場の誰に対しても気疲れやストレスを感じる人におすすめの本3選 |
◆反応しない練習/草薙龍瞬 ◆自分の小さな「箱」から脱出する方法/アービンジャー・インスティチュート ◆嫌われる勇気/岸見一郎・古賀史健 ◆「あの人がいるだけで会社がしんどい……」がラクになる/井上智介 |
それぞれ見ていきましょう。
反応しない練習
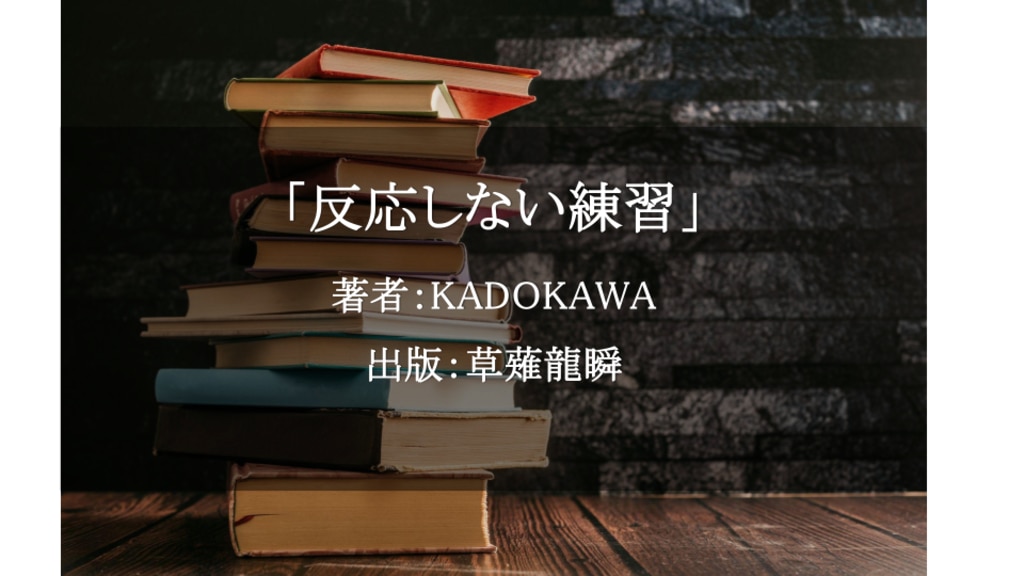
誰に対しても気疲れ・ストレスを感じるタイプにおすすめの本1冊目は草薙龍瞬著の「反応しない練習」です。
出版社 | KADOKAWA |
筆者 | 草薙龍瞬 |
値段 | 1,430円(税込) |
出版年月日 | 2015年7月31日 |
ページ数 | 224ページ |
詳細(出版社公式サイト) | |
Kindle | あり |
本の概要
この本は仏教の教えをもとに、心のムダな反応を抑えることで悩みや苦しみから解放され、人生をよりラクに生きるための具体的な方法を解説した本です。
具体的には以下のような内容が紹介されています。
【目次】
|
このように本書では、「心の反応」を観察してコントロールする練習を通じて、ストレスや不安から解放され、自分らしい生き方を目指すことができます。
おすすめポイント
この本は日常の中で「心のムダな反応を抑える」ための実践的な方法が紹介されている点が魅力です。
例えば、以下のような内容が本書では解説されています。
反応する前に理解する | 職場でイライラしたり不安を感じたりしたときに一歩引いて考えるための方法 |
「良し悪しを判断しない」視点 | 行動について「良い」「悪い」と決めつけないで無駄なストレスを減らす方法 |
マイナス感情で損しない | 怒りや不安などの感情に振り回されず、自分自身の心を守るための具体的な練習法 |
「他人の目から自由になる」考え方 | 他人の評価よりも自分の基準を大切にする方法 |
こうした内容が、職場のあらゆる人間関係におけるストレスを軽減するのに役立つでしょう。
実際に読者からは以下のような声が寄せられています。
【読者レビュー】
|
このように、本書は職場で生じる人間関係のストレスに効くため、以下のような人に特におすすめです。
こんな人におすすめ |
|
自分の小さな「箱」から脱出する方法
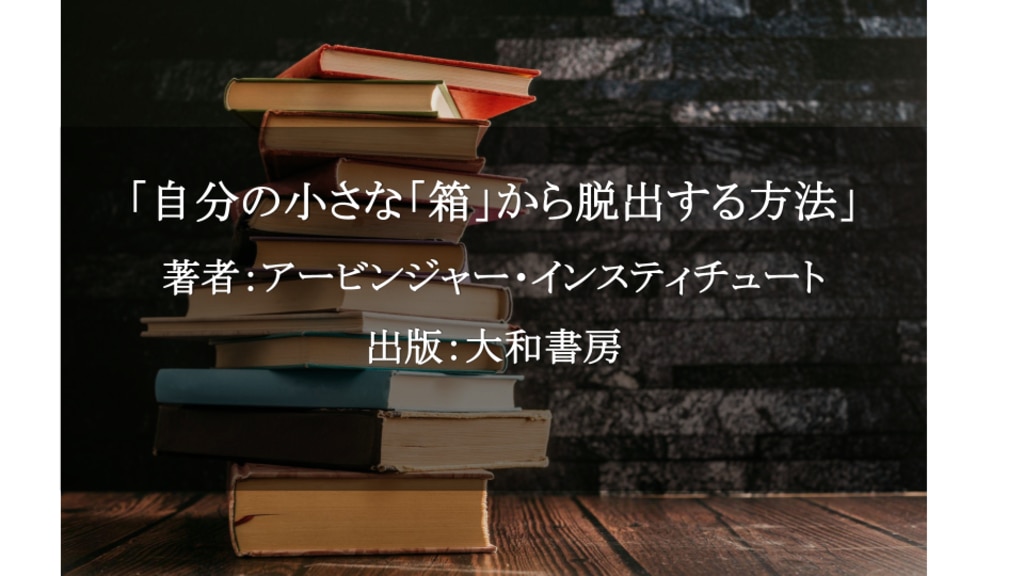
誰に対しても気疲れ・ストレスを感じるタイプにおすすめの本2冊目は草薙龍瞬著の「自分の小さな「箱」から脱出する方法」です。
出版社 | 大和書房 |
筆者 | アービンジャー・インスティチュート |
値段 | 1,760円(税込) |
出版年月日 | 2006年10月1日 |
ページ数 | 280ページ |
詳細(出版社公式サイト) | |
Kindle | あり |
本の概要
人間関係のトラブルの原因となる「自己欺瞞(箱)」を理解し、その状態から抜け出すことで、職場などでの人間関係を改善する方法を提案してくれる本です。
具体的には、以下の内容が解説されています。
【目次】
|
このように人間関係のトラブルの原因を自分の中に見つけ、その状態から抜け出すことで人間関係を改善するための実践的なガイドブックとなっています。
おすすめポイント
この本は理論だけでなく、実際の職場や日常生活に即した具体例がストーリー形式で豊富に描かれている点が魅力です。
一流企業に勤める「主人公のトム」のストーリーをもとに
- 箱(=自己欺瞞)とは何か
- なぜ箱に入ってしまうのか
- 箱から脱出するにはどうすればいいのか
が描かれており、自分自身の状況と照らし合わせながら読めるため、人間関係を改善しストレスを軽減するための具体的な方法がわかりやすくなっています。
実際に読者からは以下のような声が寄せられています。
【読者レビュー】
|
このように箱から脱出する方法がわかりやすく描かれているため、信頼関係の構築やストレス軽減に実際に効果があり、読者から評価を得ています。
こんな人におすすめ |
|
嫌われる勇気
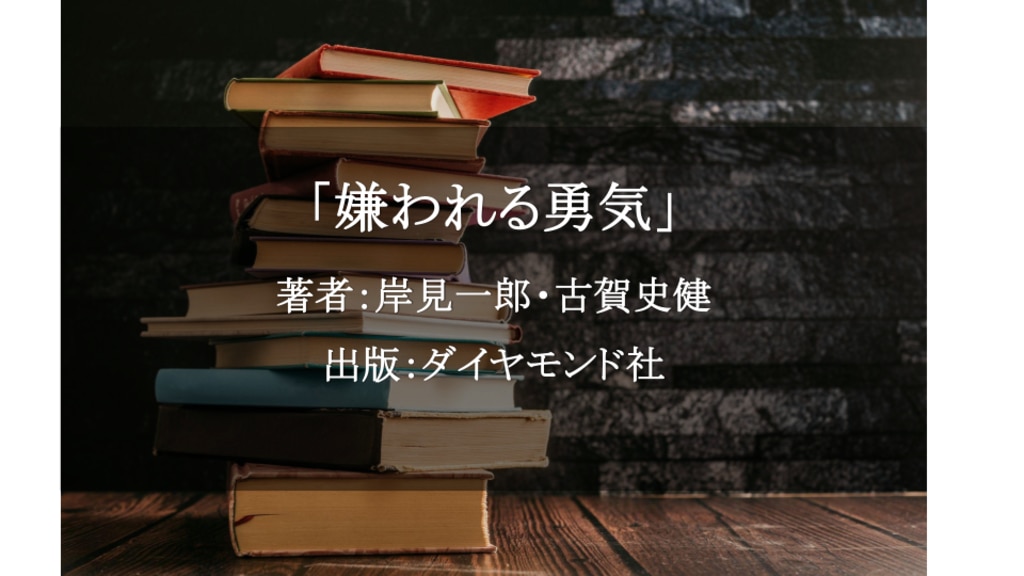
誰に対しても気疲れ・ストレスを感じるタイプにおすすめの本3冊目は岸見一郎・古賀史健著の「嫌われる勇気」です。
出版社 | ダイヤモンド社 |
筆者 | 岸見一郎・古賀史健 |
値段 | 1,650円(税込) |
出版年月日 | 2013年12月 |
ページ数 | 296ページ |
詳細(出版社公式サイト) | |
Kindle | あり |
本の概要
この本は心理学者アルフレッド・アドラーの「アドラー心理学」をもとに、他人の評価や期待に縛られず、自分らしく自由に生きるための方法を対話形式で解説した自己啓発書です。
具体的には以下の内容が紹介されています。
【目次】
|
このように、「他人から嫌われることを恐れず、自分自身を尊重することで充実した人生を送る」ためのヒントが詰まった一冊といえるでしょう。
おすすめポイント
この本の魅力は、ストーリー形式で難解なアドラー心理学の内容を読み進めやすいようにしてくれている点です。
「『哲人』のもとを訪ねた青年」がさまざまなことを哲人に問いただすという設定で、二人の会話によって物語のように話が展開していきます。
哲人が話す内容に、青年がリアクションをすることで、哲学的な難しい話も、おもしろく、わかりやすく伝わるようになっています。
サクサク読み進めながらも、職場の人間関係の中でダメージを受けづらくなるマインド形成のヒントが得られるはずです。
実際に読者からは以下のような声が寄せられています。
【読者レビュー】
|
このように、「課題の分離」「共同体感覚」「承認欲求から自由になる」といった具体的なアプローチについて、読者から評価を得ていることがわかるでしょう。
こんな人におすすめ |
|
職場のめんどくさい人から自分を守る心理学
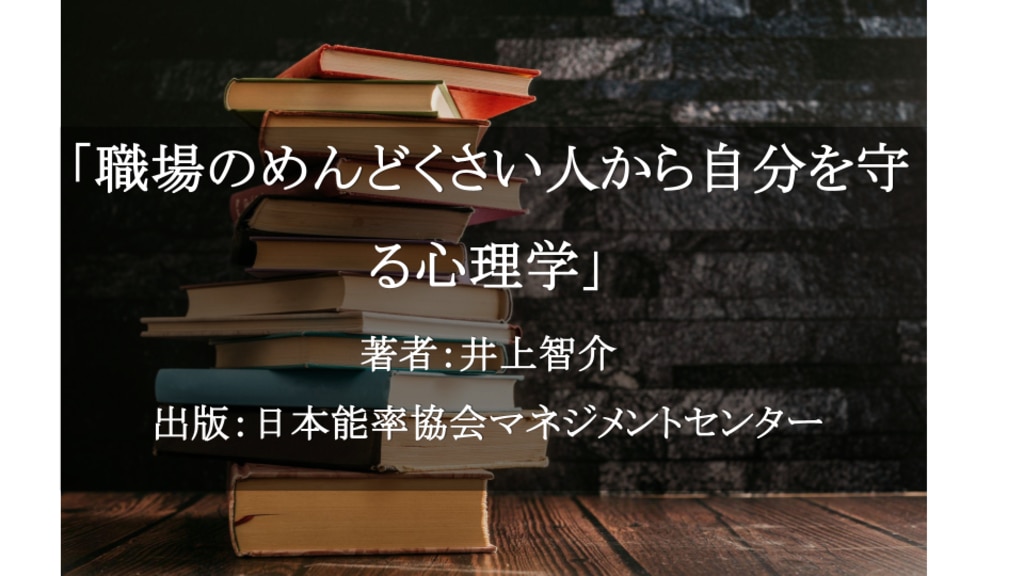
誰に対しても気疲れ・ストレスを感じるタイプにおすすめの本4冊目は井上 智介著の「職場のめんどくさい人から自分を守る心理学」です。
出版社 | 日本能率協会マネジメントセンター |
筆者 | 井上智介 |
値段 | 1,650円(税込) |
出版年月日 | 2021年12月21日 |
ページ数 | 256ページ |
詳細(出版社公式サイト) | |
Kindle | あり |
本の概要
「職場のめんどくさい人から自分を守る心理学」は、職場の「めんどくさい人」との関係に悩む人に向けて、具体的な対処法や心理学的なアプローチを解説した本です。
以下は本書の主な目次です。
【目次】
|
このように、職場の人間関係に悩む人々に寄り添いながら、自分自身を守るための具体的な対処法やメンタルケア方法を解説してくれます。
おすすめポイント
本書は、苦手な職場の人から自分を守るために、具体的なシーン別に対処法を解説してくれている点が魅力です。
例えば、以下のようなシーン別に対処法が書かれており、イメージが湧きやすく、実践しやすくなっています。
- 自分に都合の悪いことは無視してくる場合
- 失敗は部下のせいにして成果は自分の手柄にする場合
- 評価が不公平だと感じる場合
- 嫌味ばかり言われる場合
本書に関して、上司との関係に悩む読者からは以下のような声があります。
【読者レビュー】
|
このように、職場の人の発言や態度から自分を守るノウハウが学べたり、持つべきマインドが分かる良書となっています。
特に以下に当てはまる人におすすめの書籍といえるでしょう。
こんな人におすすめ |
|
誰に対してもスキル・対処法が不足しているタイプにおすすめの本3選

次に自身の態度・発言などによって職場での人間関係がうまくいかない人に、おすすめの本を以下3冊ご紹介します。
自身の態度・発言などによって職場での人間関係がうまくいかない人におすすめの本3選 |
◆人を動かす/D・カーネギー ◆LISTEN──知性豊かで創造力がある人になれる/ケイト・マーフィ ◆心理的安全性のつくりかた/石井遼介 |
それぞれ見ていきましょう。
人を動かす/D・カーネギー
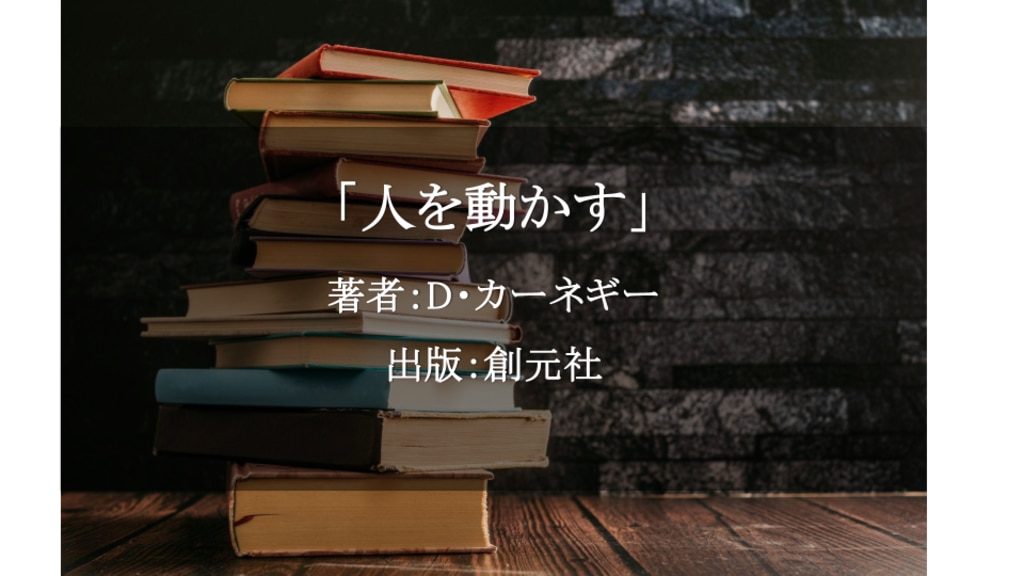
誰に対してもスキル・対処法が不足しているタイプにおすすめの本1冊目はD・カーネギー著の「人を動かす」です。
出版社 | 創元社 |
筆者 | デール・カーネギー |
値段 | 2,200円(税込) |
出版年月日 | 2023年9月4日(改訂新装版) |
ページ数 | 352ページ |
詳細(出版社公式サイト) | |
Kindle | あり |
本の概要
この本はカーネギーが人間関係の本質を探求し、人を動かすための30の原則を体系化した自己啓発書です。
具体的には以下の内容が掲載されています。
【目次】
|
このように他者との信頼関係や他者への影響力を高められ、時代を超えて役立つ普遍的な30の原則を学べる一冊となっています。
おすすめポイント
この本の魅力は、他者との関係を円滑にし、影響力を高めるための具体的なテクニックが30の原則にまとめられ、これさえ読めばあらゆる人間関係の改善に役立てられる点にあります。
具体的には、以下のような内容が紹介されています。
人を動かす3原則 | 相手の立場や考え方を尊重するための考え方を解説 |
人に好かれる6原則 | 笑顔や名前を覚えることなど、簡単ながら好感度を高めるのに効果的なコミュニケーション術を解説 |
人を説得する12原則 | 職場での衝突や不和を防ぐ方法を解説 |
人を変える9原則 | 相手に抵抗感を与えずに行動変容を促すために効果的な方法を提案 |
この本を読んだ読者からは以下のような声が寄せられています。
【読者レビュー】
|
本書は初版からおよそ90年経過しているにもかかわらず読み継がれており、人間関係の本質をとらえた普遍的な内容で、実践しやすい内容となっています。
その結果、上記のレビューのように実際に読者から高評価を得ているのです。
本書を読むのに特におすすめな人は以下のとおりです。
こんな人におすすめ |
|
LISTEN──知性豊かで創造力がある人になれる
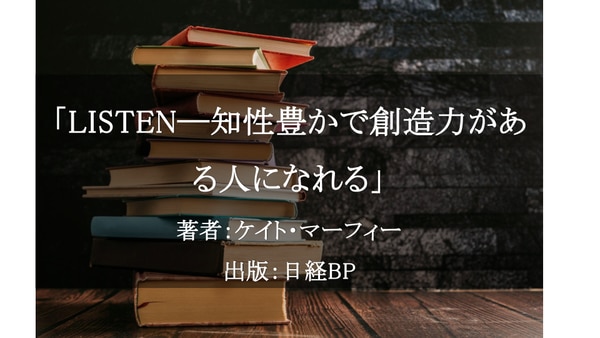
誰に対してもスキル・対処法が不足しているタイプにおすすめの本2冊目はケイト・マーフィ著の「LISTEN──知性豊かで創造力がある人になれる」です。
出版社 | 日経BP |
筆者 | ケイト・マーフィ |
値段 | 2,420円(税込) |
出版年月日 | 2021年08月09日 |
ページ数 | 504ページ |
詳細(出版社公式サイト) | |
Kindle | あり |
本の概要
この本は「聴く」ことの重要性を科学的視点から解き明かし、深く聴くことで人間関係を改善し、知性や創造力を高める方法を提案する本です。
具体的な内容は以下のとおりです。
【目次】
|
目次からも分かるように、現代社会で失われつつある「聴く力」の重要性を再認識させ、深い聴き方を身に付けることで人間関係や創造性、知性を高める方法を提案する一冊となっています。
おすすめポイント
この本は「聴く力」という切り口で、コミュニケーションを改善する方法を学べる点が魅力です。
巷のコミュニケーションに関する本ではあらゆるテクニックの紹介がされているため「どこから手を付ければいいのかわからない」といったケースもありますが、この本は「聴く」ことに集中して解説されているため、気軽に実践できます。
例えば、以下のような内容が解説されています。
信頼関係を深める | 相手に安心感を与え、信頼関係を築くために、相手の話を深く聴く方法を解説 |
「沈黙」を活用する | 深い対話を可能にするため、会話中の沈黙を活用することを提案 |
偏見や先入観を排除した | 偏見や先入観を排除して聴く方法の解説 |
「質問力」で深い対話を促す | 相手の考えや感情に触れるための問いかけ方を解説 |
このように相手が誰であっても応用しやすい「聴く」テクニックを習得すれば、職場のあらゆる人間関係の改善を目指せるでしょう。
実際に読者からは以下のような声が寄せられています。
【読者レビュー】
|
このように「聴く」に特化したアプローチで、人間関係の改善に効果があったという声も挙がっており、読者からは高評価を得ています。
こんな人におすすめ |
|
心理的安全性のつくりかた
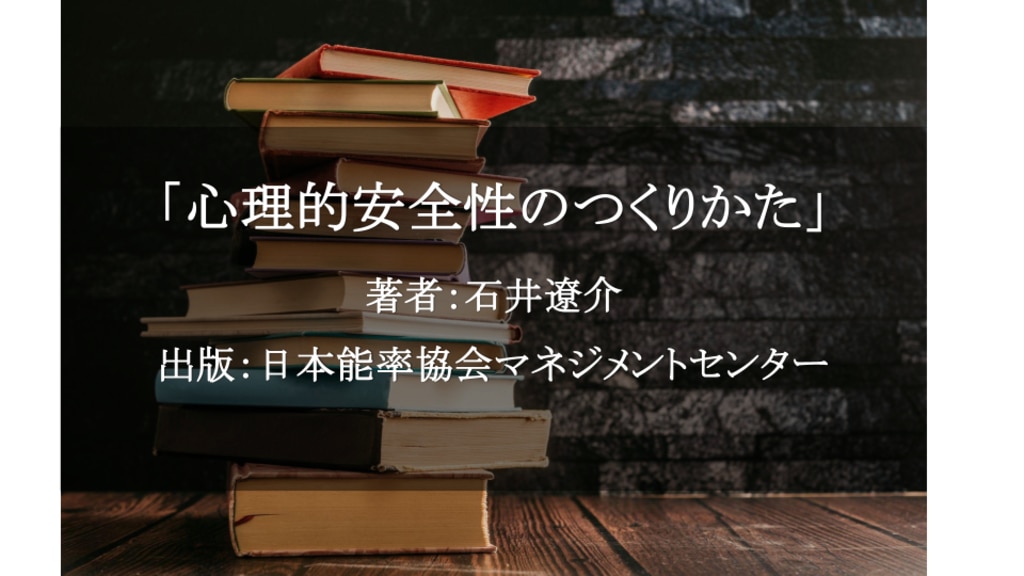
誰に対してもスキル・対処法が不足しているタイプにおすすめの本3冊目は石井遼介著の「心理的安全性のつくりかた」です。
出版社 | 日本能率協会マネジメントセンター |
筆者 | 石井遼介 |
値段 | 1,980円(税込) |
出版年月日 | 2020年09月01日 |
ページ数 | 336ページ |
詳細(出版社公式サイト) | |
Kindle | あり |
本の概要
この本は職場やチームにおける「心理的安全性(※)」を高めるための具体的な方法を、日本の組織文化に合わせて解説しています。
本書の具体的な内容は以下のとおりです。
【目次】
|
このように心理的安全性を高めるための行動・スキル・制度・仕組みまで、ソフトとハード両面から具体策を提示してくれています。
※心理的安全性:組織やチームにおいて、自分の意見や気持ちを安心して表現できる状態のこと
おすすめポイント
この本のおすすめポイントは、「日本の現場に根ざした具体的な行動レベル」で心理的安全性を高める方法を科学的に学べる点にあります。
具体的には、以下のような内容が記載されています。
4因子 | 日本において心理的安全性が満たされている会社には「話しやすさ」「助け合い」「挑戦」「新奇歓迎」という4つの因子が揃っていることを解説 |
4因子を行動に分解 | 4因子を満たすために「実際にどんな行動を取ればよいか」を解説 |
チーム内のより良い人間関係の構築には、心理的安全性は不可欠と言えます。特定の相手ではなく、チームや組織全体で人間関係の改善を目指したい場合には非常に役立つ内容となっています。
実際に読者からは以下のような声が寄せられています。
【読者レビュー】
|
このように、特にチーム運営に悩む人たちから高く評価されています。
本書は、以下に当てはまる人におすすめです。
こんな人におすすめ |
|
読むだけでは意味がない!読んだことを実践するのが重要

ここまで人間関係に関する本をポジション別にご紹介しましたが、これらの本を「読みっぱなし」にしてしまっては、課題は解決しません。本から学んだことを実践に活かすのが重要です。
なぜなら、結果を出すのは知識ではなく「行動」だからです。
例えば「同僚とのコミュニケーションが上手くいかず、毎回気まずい空気になる」という悩みを抱えたAさんを想像してみてください。
Aさんはこの課題を解決するために、「コミュニケーションの技術」について書かれた本を読み、「自分の主張は、相手の立場を認め、共感した上で伝える」といったポイントを知りました。
そこでAさんは、本にあった「否定せず受け止める」「共感を伝える一言」を意識的に使うようにした結果、以前のようなギスギスした空気が生まれにくくなっていきました。
もしAさんが本を読んだだけで終わっていたら、何も変わらなかったでしょう。実践してこそ、結果が変わるのです。
したがって、本を読んだ後は学んだことを実践しましょう。
ただし、本の内容を実践に活かすのは簡単なことではありません。
本の内容を理解したつもりでも、実践しようとすると、
- 自分の状況ではどう行動すればいいの?
- 学んだことを何から実践すればいいの?
と悩んでしまい、行動ができないこともあるのです。
そこで次章では、人間関係の本で学んだことを実践で活用するためのポイントを解説します。
ポイントを理解して、学んだことを活用し、人間関係の課題を解決できるようになりましょう。
人間関係の本で学んだことを実践に活かすための3つのポイント

人間関係にまつわる本で学んだことを実践で活用するためのポイントは以下の3つです。
人間関係にまつわる本で学んだことを実践で活用するための3つのポイント |
|
それぞれ詳しく見ていきましょう。
簡単な行動からひとつずつ実践する
実践で本から学んだことを活用するためのポイント1つめは「簡単な行動からひとつずつ実践する」ことです。
本には豊富なノウハウが詰め込まれています。
そのため、一度にさまざまなノウハウを試そうとすると、何から手をつければいいのかわからなくなってしまうでしょう。
さまざまなノウハウを試した結果、キャパオーバー状態に陥り、途中で挫折してしまうおそれもあります。
そのため、学んだことは全部やろうとせず、簡単なことからひとつずつ実践していくことが重要です。
以下のポイントを参考にしながら、ひとつずつ実践していきましょう。
本の内容を簡単な行動からひとつずつ実践していくためのポイント |
(1)本を読みながら「これは自分に活かせそう」と感じた箇所に付箋を貼る (2)読了後、付箋を見返して「すぐに試せそう」「自分にとって難易度の低そう」なものを1つ選ぶ (3)実践するタイミングと場面を決める (4)1つのことが習慣化してきたら、次のトピックを実践する |
本に書かれた内容を自分に置き換えて考える
実践で本から学んだことを活用するためのポイント2つめは「本に書かれた内容を自分に置き換えて考える」ことです。
ただ本を読んだだけでは、書いてあることは全て「他人事」で終わってしまいます。
いざ実践に活かそうと思っても、自分の状況に置き換えて理解していないため、どう行動していいのか迷ってしまうでしょう。
そうならないためにも、
「これは明日の上司とのコミュニケーションで早速使えそう」
「部下との1on1に効果がありそう」
といったように、自身の現場に当てはめて考えることで、読んだ内容がイメージしやすくなり、「自分ための解決策」に変わるため、実行しやすくなります。
したがって、本を読む際には「どこで使えそうか」を常に考えながら読むことをおすすめします。
本の内容を自分に置き換えて考える際は以下のポイントを押さえておくと、より行動しやすくなるため、参考にしましょう。
「どこで使うか」を想定しながら読むためのポイント |
|
振り返りをする
実践で本から学んだことを活用するためのポイント3つめは「振り返りをする」ことです。
人間関係の改善に役立つ本を読んだあと、その内容を実践して終わりにするのではなく、きちんと振り返りを行うことが、次につながる学びになります。
例えば、Aさんが「職場での対人コミュニケーション」について書かれた本を読み、「相手の意見を否定せず、まずは受け止めてから自分の意見を伝える」というテクニックを知ったとします。
その内容をもとに、気まずくなりがちな同僚との会話の場で、実際に試してみました。
そして会話のあと、以下のように振り返ってみると、
なぜうまくいったのか? 何が足りなかったのか? 次はどうすればいいのか? |
このように、「うまくいった点」も「足りなかった点」も、振り返ることで具体的なヒントに変わります。
そうすることで、本から得た知識が、より自分に合った「実践的なノウハウ」として磨かれていくのです。
実践したら、ぜひ毎回この3点を振り返ってみてください。
- なぜうまくいったのか?
- 何が足りなかったのか?
- 次はどうすればいいのか?
組織内の人間関係を改善するには研修の実施もおすすめ

チームや組織全体で人間関係を改善したいという場合は、研修の実施をおすすめします。
というのも、全員が同じ人間関係にまつわる研修プログラムに参加することで、以下の効果が期待できるからです。
|
株式会社LDcubeでは、対人関係上の問題やチームワークの円滑化を図れるLIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広く支援しています。
無料体験会なども行っていますので、お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
まとめ
本記事では人間関係にまつわる本をお悩み別に以下18冊ご紹介しました。
【悩み別のおすすめ本一覧】
悩みの対象 | 悩みのタイプ | おすすめの本 |
|---|---|---|
対上司 | 【気疲れ・ストレスタイプ】 上司の態度・発言に気疲れやストレスを感じる | |
【対人スキル・対処法不足タイプ】 自身の態度・発言などによって上司との関係がうまくいかない | ||
対同僚・ 部下 | 【気疲れ・ストレスタイプ】 同僚や部下の態度・発言に気疲れやストレスを感じる | |
【対人スキル・対処法不足タイプ】 自身の態度・発言などによって同僚や部下との関係がうまくいかない | ||
全般 | 【気疲れ・ストレスタイプ】 誰に対しても態度・発言に気疲れやストレスを感じる | |
【対人スキル・対処法不足タイプ】 誰に対しても自身の態度・発言などによって人間関係がうまくいかない |
本記事が人間関係に関する本を探すあなたの参考になれば幸いです。
株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。