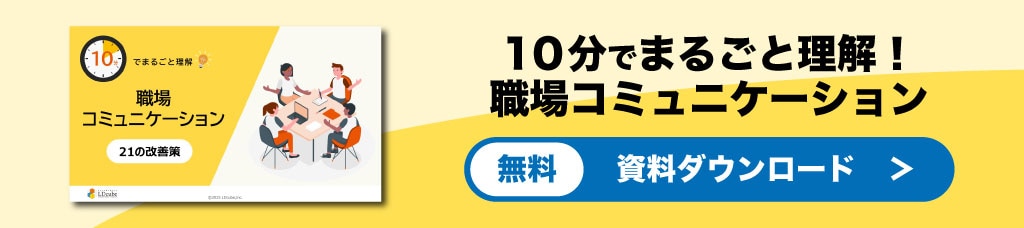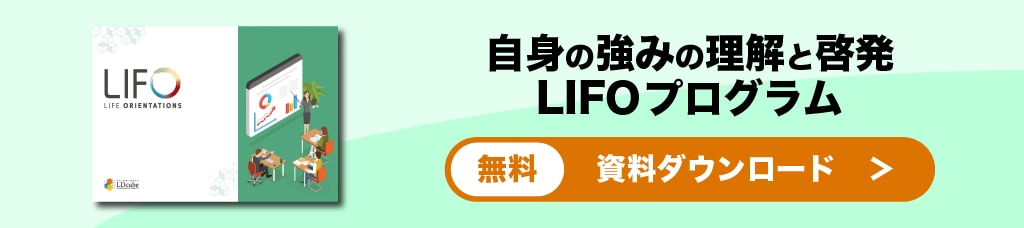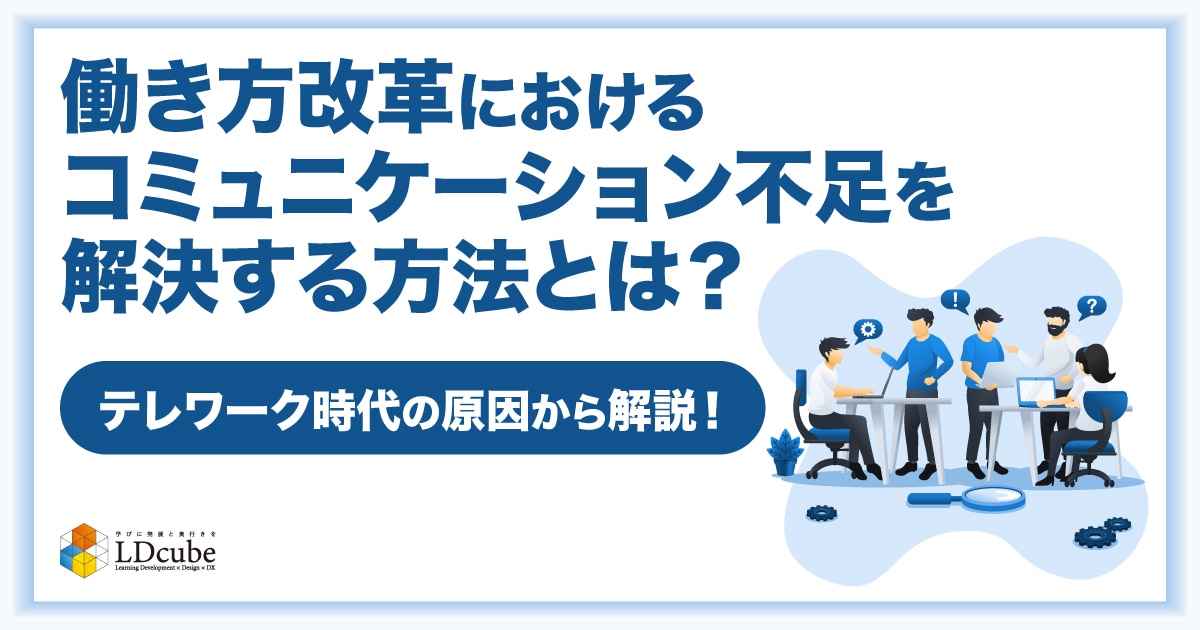
働き方改革におけるコミュニケーション不足を解決する方法とは?原因から解説!
働き方改革の推進に伴い、多くの企業でテレワークやフレックスタイム制度が導入される中、社内コミュニケーション不足が新たな課題として浮上しています。
特に、勤務場所や時間の多様化により、これまで当たり前だった「顔を合わせての会話」や「雑談による情報共有」の機会が激減し、業務の効率低下や社員の孤立感、チームワークの低下といった問題が生じています。
働き方改革を推進しながらも、組織の一体感や業務の質を維持するには、新たなコミュニケーション戦略が不可欠です。
本記事では、働き方改革時代に起きがちなコミュニケーション不足の実態とその影響を分析し、具体的な解決策として5つの効果的戦略を紹介します。また、コミュニケーション改革を成功させるための実践ポイントや、活用できるツール・サービスについても解説します。
多様な働き方を認めつつ、組織としての結束力と生産性を高めるためのヒントとして、ぜひ参考にしてください。
▼コミュニケーションについては下記で詳しく解説しています。
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
目次[非表示]
- 1.働き方改革でのコミュニケーション不足は職場単位で解決しよう
- 2.働き方改革で深刻化するコミュニケーション不足の実態
- 3.働き方改革時代にコミュニケーション不足が生じる主な原因
- 3.1.物理的な接点数減少による、情報共有機会の喪失
- 3.2.心理的安全性の欠如が生み出すコミュニケーション障壁
- 3.3.部門・チーム間の連携不足とサイロ化現象
- 3.4.企業理念やビジョンの共有不足による一体感の欠如
- 4.働き方改革におけるコミュニケーション不足を解消する5つの方針
- 4.1.①日常的なコミュニケーション量の確保と質の向上
- 4.2.②雑談と1対1対話の機会創出による関係構築
- 4.3.③役職・スキルに応じたコミュニケーション方法の最適化
- 4.4.④社内情報の積極的発信と共有プラットフォームの活用
- 4.5.⑤業務外のつながりによる組織活性化と一体感醸成
- 5.働き方改革でのコミュニケーション不足解消を成功させる実践ポイント
- 5.1.経営陣からの重要性の発信
- 5.2.自己診断ツールの導入
- 5.3.職場単位でのワークショップの実施
- 5.4.社内で共通言語化を図る
- 6.働き方改革でのコミュニケーション不足解消には職場単位での研修が最適
- 7.働き方改革でのコミュニケーション不足解消ならLIFO®がおすすめ!
- 8.LIFOを活用して社内トレーナーがコミュケーション研修を展開している事例
- 9.まとめ:働き方改革とコミュニケーション活性化で組織力を高めよう
働き方改革でのコミュニケーション不足は職場単位で解決しよう

働き方改革が進む現代の企業では、テレワークやフレックスタイム制の導入により、社員間のコミュニケーション不足が大きな課題となっています。以前のように同じ場所で同じ時間に働くことが減り、対面でのコミュニケーションの機会が失われつつあるのです。
こうした課題に対して、組織全体での一律の施策だけでは十分な効果が得られないことが多くあります。
なぜなら、各部門・チームによって業務内容や求められるコミュニケーションの質・量は大きく異なるからです。開発部門では深い議論の場が必要かもしれませんが、営業部門では迅速な情報共有が重視されるなど、職場ごとに最適なコミュニケーション方法は異なります。
職場単位での解決アプローチには、以下のようなメリットがあります。
まず、その職場特有の課題に焦点を当てた対策が可能になります。また、小規模なグループでの取り組みは変化への抵抗が少なく、改善策の実行と調整がしやすいという利点もあります。さらに、メンバー全員が当事者意識を持って参加できるため、持続的な改善が期待できます。
本記事では、働き方改革時代におけるコミュニケーション不足の実態と原因を分析した上で、職場単位で実践できる効果的な解決策を紹介します。
各チームの特性を生かしながら、心理的安全性を高め、ICTツールも効果的に活用することで、柔軟な働き方と活発なコミュニケーションを両立させる方法を探っていきましょう。
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
働き方改革で深刻化するコミュニケーション不足の実態

働き方改革の推進により、テレワークやフレックスタイム制といった柔軟な勤務形態が普及する一方で、従来の対面コミュニケーションが減少し、新たな課題が浮上しています。
HR総研による「社内コミュニケーションに関するアンケート2024」では、回答者の86%が「社内コミュニケーション不足は業務の障害になる」と回答しており、多くの企業がこの問題に直面していることがわかります。
働き方の多様化が進む中、コミュニケーション不足の実態とその影響を正確に把握することが、効果的な対策の第一歩となります。
テレワークとフレックス制度がもたらす新たな課題
テレワークとフレックスタイム制の導入は、働く場所と時間の自由度を高めた一方で、従来のオフィス環境では自然と生まれていたコミュニケーションの機会を大きく減少させました。
これにより、次のような新たな課題が生じています。
まず、情報共有の質と量の低下が挙げられます。対面でのちょっとした会話や表情から読み取れていた情報が失われ、業務上の小さな変更や状況の微妙な変化が伝わりにくくなっています。また、「仕事とプライベートのオンオフが調整しづらい」「悩みを相談できる人がいない」といった問題も発生しています。
さらに、オンラインでのコミュニケーションは意図的に行う必要があるため、コミュニケーションの心理的ハードルが上がっています。特に新入社員や異動してきたばかりの社員は、誰に何を聞けばよいのかわからず、孤立を感じやすい状況にあります。このような環境では、社員間の信頼関係の構築も難しくなっています。
コミュニケーション不足が企業経営に与える悪影響
コミュニケーション不足は、単なる会話の減少にとどまらず、企業経営に深刻な影響を及ぼします。まず最も直接的な影響として、業務効率の低下が挙げられます。情報共有が不十分だと、同じ作業の重複や手戻りが増え、組織全体の生産性が低下します。
また、問題の早期発見・解決が難しくなります。よくある事例として、担当者が進捗の遅れを報告せず、最終段階で問題が発覚してチーム全体が対応に追われるという事態が発生しています。これは心理的安全性の欠如が原因で、問題を早期に共有できない環境が組織パフォーマンスを著しく低下させた例です。
さらに、長期的にはイノベーションの停滞や組織の硬直化を招きます。多様な視点や意見の交換が減ることで、新しいアイデアが生まれにくくなり、変化への対応力も弱まります。最終的には社員のエンゲージメント低下や離職率の上昇にもつながり、企業の持続的成長を阻害する要因となるのです。
▼コミュニケーション不足の解決策については下記で詳しく解説しています。
⇒職場のコミュニケーション不足の効果的な解決策とは?原因と対策まで解説!
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
働き方改革時代にコミュニケーション不足が生じる主な原因

働き方改革の進展により、柔軟な勤務形態が広がる一方で、なぜコミュニケーション不足が深刻化しているのでしょうか。その背景には、単に物理的な接点が減少しただけでなく、組織文化や心理的要因なども複雑に絡み合っています。
ここでは、コミュニケーション不足を引き起こす、4つの主要な原因を掘り下げていきます。これらの原因を正確に理解することが、効果的な対策を講じる第一歩となるでしょう。
物理的な接点数減少による、情報共有機会の喪失
テレワークやフレックスタイム制の導入により、社員が同じ時間・同じ場所で働く機会が大幅に減少しました。この変化は、従来のオフィス環境では当たり前に存在していた、偶発的な情報交換の機会を奪っています。
オフィスでは、廊下での立ち話やランチタイムの会話、他部署の様子が自然と目に入るといった何気ない接点が情報共有の重要なチャネルとなっていました。しかし、リモートワーク環境では、こうした自然発生的なコミュニケーションが失われ、すべてが意図的なアクションを必要とします。
Zoomやチャットツールでの会話は目的指向型になりがちで、業務に直結しない雑談や偶然の気付きが生まれにくい環境となっています。結果として、公式な会議では共有されないような情報や、ささいだが重要な状況変化が伝わりにくくなっているのです。
心理的安全性の欠如が生み出すコミュニケーション障壁
コミュニケーション不足の根底には、心理的安全性の欠如という課題が潜んでいます。
心理的安全性とは、自分が他人の反応に恐れや羞恥心を感じることなく、思うままに発言し行動できる状況を指します。Google社が実施した「プロジェクト・アリストテレス」でも、チームの生産性を高める最重要要素として注目された概念です。
よくある事例では、担当者が業務の進捗遅れを報告できずにいたところ、最終段階で問題が発覚し、チーム全体が大きな負担を強いられました。この背景には、「自分に能力がないと思われたくない」「上司の怒りを買うことが怖い」という心理があったのです。
特に日本企業では、失敗を厳しく問う文化や完璧主義的な価値観が根強く残っていることがあります。こうした環境では、問題や疑問を率直に共有することへの心理的ハードルが高くなり、結果として重要な情報が適時に伝わらないという悪循環が生じやすくなるのです。
心理的安全性の提唱者であるエイミー・C・エドモンドソン博士も「心理的安全性が低く、成果プレッシャーが強い組織では間違いが起きやすい」とアラートしています。
▼心理的安全性については下記で詳しく解説しています。
⇒エドモンドソン博士の視点を解説!心理的安全性がビジネスに必要な理由とは?
部門・チーム間の連携不足とサイロ化現象
多くの企業では、コミュニケーションの範囲が限定的で、チームや部門をまたぐやり取りが十分に行われていない「サイロ化」が進行しています。個人が自分の業務だけに集中し、他部署の状況や全体最適を考慮しない状態が常態化している組織も少なくありません。
例えば、営業部門がクライアントから得た製品に関するフィードバックが開発部門に共有されなければ、改善の機会を逃してしまいます。また、同様の課題に別部署が既に取り組んでいるにもかかわらず、情報共有がないために重複した作業が行われるといった非効率も発生します。
働き方改革による物理的な分散が進むと、こうした部門間のサイロ化はさらに進行しやすくなります。オンラインのコミュニケーションツールが普及していても、異なる部署間における自発的な交流は減少傾向にあり、組織全体としての情報流通が滞りがちになっているのです。
企業理念やビジョンの共有不足による一体感の欠如
企業理念やビジョンが全社員に浸透していない組織では、一体感が不足しがちで、積極的な情報共有も行われにくくなります。
社員が自社の存在価値や社会的責任、目指すべき方向性を理解していなければ、「なぜコミュニケーションが重要なのか」という基本的な動機付けも弱くなってしまいます。
働き方改革を進める多くの企業では、「法令遵守」や「残業削減」といった表面的な側面だけが強調され、「なぜ働き方を変えるのか」「それによってどんな未来を実現したいのか」といった本質的なビジョンが共有されていないケースが見受けられます。
日本の企業文化に特徴的な「以心伝心」の考え方も、多様な働き方の中では逆効果になることがあります。「言わなくても分かるだろう」「いい感じでよろしく」といった曖昧なコミュニケーションは、テレワーク環境では誤解や混乱を招きやすく、結果として組織内の分断を深める要因となりうるのです。
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
働き方改革におけるコミュニケーション不足を解消する5つの方針

コミュニケーション不足の原因を理解したところで、次はその解消に向けた具体的な方針を考えていきましょう。ここでは、職場単位で実践できる5つの方針を紹介します。
これらの方針は、テレワークやフレックスタイム制といった柔軟な働き方を維持しながらも、組織内のコミュニケーションを活性化させることを目指しています。
いずれの方針も、トップダウンで一方的に押し付けるのではなく、職場のメンバー全員が主体的に参加し、自分たちの職場環境に合わせてカスタマイズしていくことが成功の鍵となります。
①日常的なコミュニケーション量の確保と質の向上
まず求められるのは、日常的なコミュニケーション量の確保です。テレワーク環境では、オフィスでの偶発的な会話が失われるため、意図的にコミュニケーション機会を創出する必要があります。
具体的には、1日の就業時間、業務内容、成果、その他情報をチーム全員で共有するルーティンを確立することが効果的です。
朝のオンラインミーティングや、日報の共有、チャットツールでの進捗報告など、形式はさまざま考えられますが、重要なのは定期性と全員参加です。これにより、メンバー間で安心感や一体感が生まれます。
また、コミュニケーションの質も重要です。「見える化ツール」などを活用し、PCの利用ログなど客観的なデータをベースにした情報共有を行うと、より実態に即した議論が可能になります。
これは単なる監視ではなく、チーム全体の業務状況を可視化することで、適切な支援や負荷分散につなげる取り組みです。
②雑談と1対1対話の機会創出による関係構築
テレワークが当たり前となった今こそ、かつてオフィスで自然に行われていた雑談の価値を再認識し、意図的にその機会を創出することが重要です。
雑談専用のオンラインチャットルームを設けたり、オンラインランチ会を企画したりして、業務に直接関係のない会話の場をつくりましょう。こうした他愛ない会話が、実は人間関係の潤滑油となり、後の業務連携をスムーズにする基盤となります。
上司からのトップダウンではなく、部下主導のボトムアップ形式で企画すると、参加へのハードルが下がり自発的な交流が促進されます。
また、1対1での対話の機会も大切です。「1on1ミーティング」と呼ばれるこの手法は、上司と部下が定期的に対話を行うもので、対面でもオンラインでも実施可能です。
この場では、目標管理や業務進捗確認だけでなく、悩みの相談や将来のキャリアについてなど、普段の会議では話しにくい内容も共有できます。心理的安全性を高め、信頼関係を深める重要な機会となるでしょう。
▼職場コミュニケーションにおける雑談の効用は下記で解説しています。
⇒職場コミュニケーションのカギは雑談にあり|組織的に効果を出すコツを解説!
③役職・スキルに応じたコミュニケーション方法の最適化
チームや組織を管理する立場にある方は、メンバー一人一人の特性に合わせたコミュニケーション方法を採用することが効果的です。同じアプローチを全ての社員に適用するのではなく、役職やスキルレベル、個人の特性に応じて最適化を図りましょう。
例えば、業務に不慣れな若手社員には、こまめに進行状況を確認し、必要に応じて具体的な指示を出すことが安心感につながります。一方、業務に習熟している中堅・ベテラン社員には、ある程度の自主性に委ね、成果物や重要な節目での報告を求める程度が適切でしょう。
また、コミュニケーションの頻度だけでなく、方法も個人によって最適なものが異なります。文字によるチャットが得意な人もいれば、音声通話の方がスムーズに意思疎通できる人もいます。
「若手社員は質問事項があれば必ず連絡を入れる」「中堅社員は案件が50%完了した時点で報告する」など、明確なガイドラインを設けることで、部下が自主的にコミュニケーションを取る文化を醸成できます。
④社内情報の積極的発信と共有プラットフォームの活用
インターネットの発達により、社外だけでなく社内に向けた情報共有も手軽に実行できるようになりました。このメリットを生かし、企業内の情報流通を活性化させましょう。
効果的な社内情報共有プラットフォーム:
|
これらを通じて、業務ノウハウや経営層からのメッセージ、各部門の取り組みなどを積極的に発信することが効果的です。これにより、社員は自分の会社で何が起きているのかを把握できるだけでなく、企業のビジョンや方向性に対する理解も深まります。
特に働き方改革の文脈では、なぜ改革が必要なのか、どのような未来を目指しているのかといった本質的なメッセージを継続的に発信することが重要です。
単なる「残業削減」ではなく、「生産性向上とワークライフバランスの実現」など、ポジティブな目標として共有することで、社員の納得感と参加意欲を高めることができます。
技術面では、MS365などのインフラを導入することで、場所を問わず同じ情報にアクセスできる環境を提供し、チャットや電話会議など多様なコミュニケーション手段を確保することも効果的です。
⑤業務外のつながりによる組織活性化と一体感醸成
業務だけでなく、業務外での交流機会を意図的に設けることも、組織のコミュニケーション活性化に有効です。特に物理的な接点が減少している現代では、こうした取り組みの重要性が増しています。
業務外での交流機会の例:
|
仕事以外での接点をつくることで、普段の業務では見えない社員の一面や能力が発見されることもあります。企業側が開催費用を負担すれば参加のハードルが下がり、より多くの社員が交流できるでしょう。
リラックスした雰囲気での会話からは、業務中には生まれにくい斬新なアイデアが浮かぶことも少なくありません。異なる部署のメンバー同士が知り合うきっかけにもなり、後の部門間連携にも良い影響を与えます。
また、こうした活動を通じて「この会社で働くことが楽しい」「一緒に働く仲間がいる」という感覚が強まれば、テレワーク中の孤独感も軽減され、会社への帰属意識や仕事へのモチベーションも向上するでしょう。
業務とプライベートのバランスを取りながら、無理のない範囲で交流の場を設けることが大切です。
▼会社内のコミュニケーション活性化の取り組みについては下記で詳しく解説しています。
⇒会社内のコミュニケーション活性化の取り組みとは?重要性と効果的な施策13選を解説
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
働き方改革でのコミュニケーション不足解消を成功させる実践ポイント

前章で紹介した5つの方針を実際に組織に定着させるには、具体的な実践ポイントを押さえる必要があります。コミュニケーション改革は一朝一夕に実現するものではなく、継続的な取り組みが求められます。
ここでは、職場単位でコミュニケーション不足を解消するための4つの実践ポイントを紹介します。これらのポイントを踏まえることで、理想論に終わらない実効性のある改革が可能になるでしょう。
経営陣からの重要性の発信
コミュニケーション改革を成功させる第一歩は、経営陣からの明確なメッセージ発信です。組織のトップが「なぜコミュニケーションが重要なのか」「どのようなコミュニケーションを目指すのか」を具体的に語ることで、全社的な意識改革が始まります。
経営陣自身が率先してコミュニケーションの模範を示すことも重要です。定期的な対話の場を設けたり、オープンに質問を受け付けたりする姿勢を見せることで、「この会社では意見を言っても大丈夫」という安心感が醸成されます。
単なる「残業削減」や「効率化」といった表面的な目標ではなく、「社員一人一人が能力を発揮できる環境づくり」など、コミュニケーション改革の本質的な意義を共有することで、現場の納得感と参画意識を高めることができるでしょう。
自己診断ツールの導入
コミュニケーション改革を効果的に進めるには、現状の客観的な把握が不可欠です。そのために、自己診断ツールの導入が有効です。
代表的なものとしては、LIFO®やDiSC®、MBTI®などの行動特性診断があります。これらのツールを活用することで、コミュニケーションスタイルの違いを客観的に理解できるようになります。
診断結果はチーム内で共有し、お互いの特性や傾向について理解を深めましょう。例えば、「私はディテールを重視するタイプなので、細部まで確認したがる傾向があります」といった形で自己開示を行うことで、誤解を減らし、効果的なコミュニケーションが可能になります。
職場単位でのワークショップの実施
コミュニケーション改革は、全社一律のルールだけでは効果が限定的です。各職場の特性に合わせたアプローチが必要であり、そのために職場単位でのワークショップが有効です。
10〜15人程度の少人数グループで、自己診断の結果の共有から始めます。お互いの行動特性の特徴を理解し合うことで、コミュニケーションを取りやすくなることを実感することから始めます。
その上で、「現在のコミュニケーション上の課題は何か」「理想的なコミュニケーション状態とは」などをテーマに対話を行います。重要なのは、参加者全員が発言できる雰囲気づくりです。ファシリテーターを置き、発言の偏りを防ぐ工夫も大切です。
ワークショップの成果として、各職場で独自のコミュニケーションルールを作成するのも効果的です。「朝のチェックインは必須」「週報はこのフォーマットで」など、具体的で実行可能なルールを自分たちで決めることで、順守率も高まります。
社内で共通言語化を図る
コミュニケーション改革を定着させるには、組織内で「良いコミュニケーションとは何か」を共通言語化することが重要です。曖昧な概念を具体化し、全員が同じイメージを持つことで、改革の方向性が明確になります。
日本特有の「以心伝心」文化から脱却し、「明確に言語化する」「質問を歓迎する」「定期的なフィードバックを行う」など、具体的なコミュニケーション行動を定義しましょう。これらを社内ハンドブックやイントラネットに掲載し、常に参照できるようにすることも効果的です。
また、定期的な振り返りの場を設け、「今月のコミュニケーション改善MVP」を表彰するなど、ポジティブな強化策を取り入れることも考えられます。コミュニケーションの改善を評価する仕組みを作ることで、社員の意識改革と行動変容を促進できるでしょう。
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
働き方改革でのコミュニケーション不足解消には職場単位での研修が最適

働き方改革でのコミュニケーション不足解消には、個人単位の学習だけでなく、職場単位での研修が極めて効果的です。実際の職場メンバーと共に学び、実践することで、即座に職場の雰囲気改善につなげることができます。
ここでは、なぜ職場単位での研修が効果的なのか、その理由と期待される効果について解説します。
職場メンバーがそろっている
職場単位での研修では、日常的に共に働くメンバーが一堂に会して学ぶことができます。これにより、研修で学んだコミュニケーション手法を、その場で実践的に試すことができます。
また、普段の業務の中での具体的な課題や改善点について、チーム全体で認識を共有し、解決策を考えることができます。
研修での学びを即座に実務に反映できる環境があることは、スキル定着の観点からも大きなメリットとなります。
職場の認識を変えることができる
職場全体で研修を受けることで、コミュニケーションに関する共通認識を形成することができます。
例えば、「雑談は業務の妨げになる」という古い価値観を、「適切な雑談は職場の活性化に重要である」という新しい認識に更新することが可能です。
全員が同じ内容を学ぶことで、新しいコミュニケーション方法を実践する際の心理的なハードルを下げ、職場全体での行動変容を促進することができます。
▼職場単位でのコミュニケーション研修が有効な理由については下記で詳しく解説しています。
⇒職場の活性化につなげる方法とは?アイデアやポイントを紹介!
働き方改革でのコミュニケーション不足解消ならLIFO®がおすすめ!
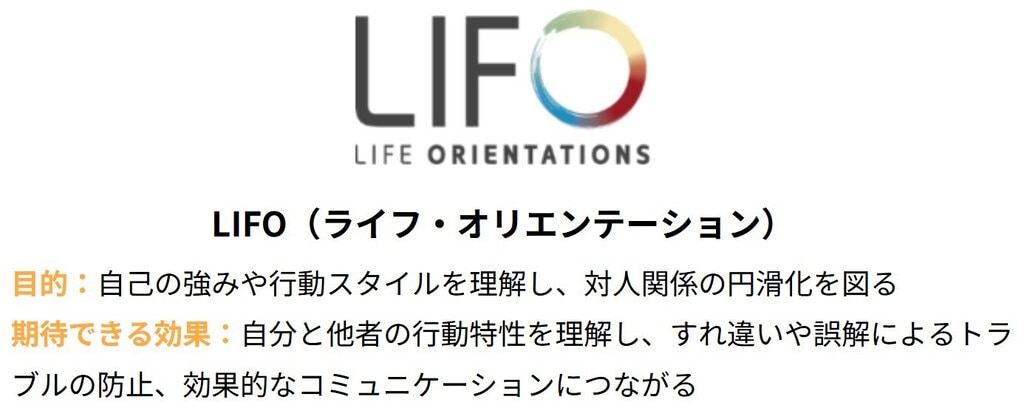
働き方改革でのコミュニケーション不足解消なら自己診断ツールLIFO(Life Orientations)を活用した職場単位でのワークショップがおすすめです。
なぜなら、LIFOプログラムは心理学や行動科学をベースにして組み立てられた行動特性診断をベースに、職場単位でワークショップを行うためのワークブックなどのツールも体系的にそろえられているからです。
また、体系立てられたツールの使い方を社内トレーナーの方々にライセンス提供もされており、社内トレーナーの方々が職場単位でワークショップを展開していくことも可能です。下記に概要を紹介します。
自己診断ツールLIFOとは
LIFO(Life Orientations)は、個人の行動スタイルを診断する自己診断ツールです。このツールは、自分の強みや行動パターンを理解するために役立ちます。
LIFOは4つの基本スタイルに基づいており、これらのスタイルはそれぞれ異なる行動特性や価値観を持っています。
自分がどのスタイルに属しているかを知ることで、より良いコミュニケーション方法やストレス時の行動傾向を把握することができます。
LIFOを活用したコミュニケーション研修
LIFOを活用したコミュニケーション研修では、まず参加者が自己診断を行い、自分の行動スタイルを理解します。
この診断結果をもとに、どのようにして他者と効果的にコミュニケーションをとるかを学びます。
研修では以下のような内容が含まれます。
|
LIFO®プログラムは社内トレーナーで展開可能
LIFO®プログラムは、これまでの活用実績と実用性から、企業内でのトレーニングにおいて自信を持っておすすめできるプログラムです。
社内展開にあたっては、特定の準備と手続きを経ることで、コストを抑えながら、外部講師に委託したかのように、社内トレーナーによる効果的なプログラムを展開することが可能です。
以下に、その流れを詳しく説明します。
|
LIFOを活用して社内トレーナーがコミュケーション研修を展開している事例

背景・課題
リコージャパン株式会社では、2010年の販売会社統合以降、各支社の固有の課題に対応できず、教育施策が本部主導で一方的になるなどの課題がありました。
また、コロナ禍以降、会食などの機会が減ったことにより、コミュニケーションの希薄化を招いていました。これらの課題を解決するために、社員自らが強みや弱みを理解し合い、横のつながりを強化する取り組みが求められていました。
LIFOプログラム(社内トレーナーライセンス)の導入
その中で、LIFO(Life Orientations)を導入しました。LIFOの活用を通じて、社員一人一人の個性を診断し、自己理解と他者理解を促進しました。
これにより、非公式なコミュニケーションが減少する中でも、社員同士の相互理解を深めるための新たな手段を提供することができるようになりました。
また、LIFOプログラムライセンスを取得することで、社内トレーナーが自主的に研修を行えるようになり、組織風土改革を進めました。
LDcubeとの協力により、多様なワークショップを展開し、各支社・部門が抱える具体的な課題に対応できるようになりました。
社内展開
プログラムの展開においては、事前のLIFO診断、ワークショップの実施、職場での実践、効果検証のサイクルを組み込みました。
参加者は、研修後の職場実践を通じて得られたスキルを評価し合い、PDCAサイクルを回すことで、持続的なスキルアップを図っています。
ラーニングプラットフォーム「UMU」を活用し、受講者同士が学び合う環境も整備しました。
社内トレーナーによる研修実施後の反応
導入後、プログラム受講者の満足度は高く、多くの支社で「対人関係」や「マネジメント能力」などにおいて数値的な改善が見られました。
LIFOを活用したレクチャーは「人」の問題の解決に寄与し、特にアウトプット重視の体験学習が効果的でした。
UMUの活用と一連の学習サイクルの設計により、事務局の負担軽減と学習効果の向上が実現しました。
今後に向けて
今後は、各支社や部門の課題に寄り添い、人材育成を継続的にサポートすることで、社員個々の自己成長と組織全体の活性化をさらに推進する予定です。
また、LIFO以外のライセンスプログラムも組み合わせ、人材育成のプログラムラインナップを増やしていきます。
これにより、組織内のさまざまな課題を解決し、全体の一体感をさらに高められることを期待しています。
▼本事例はインタビュー記事の一部です。インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。
⇒リコージャパン株式会社様 ライセンスプログラム導入事例
まとめ:働き方改革とコミュニケーション活性化で組織力を高めよう
本記事では、働き方改革時代におけるコミュニケーション不足の課題と、その解消に向けた具体的な方針・実践ポイントを紹介してきました。
テレワークやフレックスタイム制といった柔軟な働き方は、多くのメリットをもたらす一方で、従来の対面コミュニケーションを前提とした組織運営にはさまざまな課題を突きつけています。
私たちが直面しているのは、単なる「会話量の減少」という表面的な問題ではありません。物理的な接点減少、心理的安全性の欠如、部門間のサイロ化、企業理念の共有不足といった複合的な要因が、組織のコミュニケーション不全を引き起こしているのです。
こうした課題に対応するためには、日常的なコミュニケーション量の確保と質の向上、雑談や1対1での対話の機会創出、役職・スキルに応じたコミュニケーション方法の最適化、社内情報の積極的発信、業務外のつながりの促進といった多角的なアプローチが有効です。
そして、これらの取り組みを成功させるためには、経営陣からの明確なメッセージ発信、自己診断ツールの導入、職場単位でのワークショップ実施、コミュニケーションの共通言語化といった実践ポイントを押さえることが重要です。
特に強調したいのは、組織全体の一律対応ではなく、職場単位でのきめ細かな取り組みの重要性です。各職場の業務特性や構成メンバーに合わせた施策を、当事者意識を持って推進することが、コミュニケーション改革を成功に導く鍵となります。
株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。