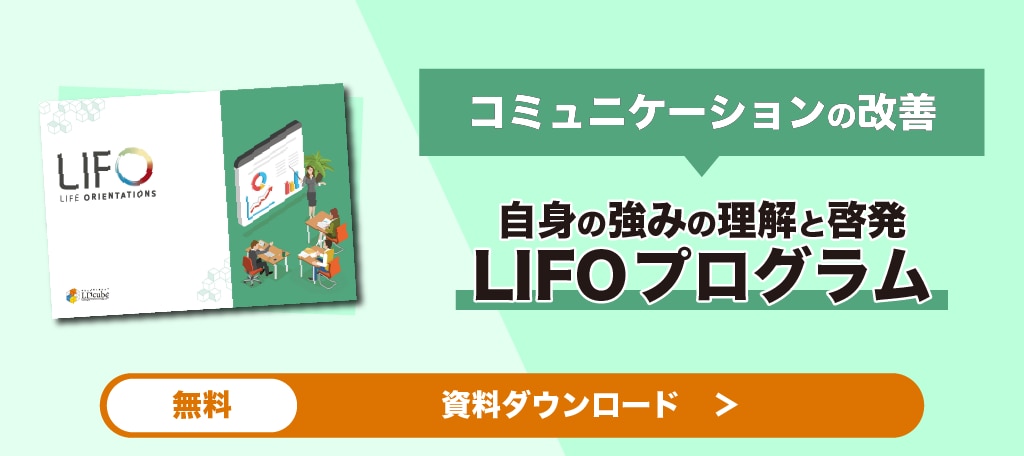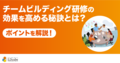チームビルディング研修を企業で行う際のポイントとは?おすすめ展開法も紹介!
ビジネス環境が複雑化し変化の速度が増す現代において、組織の競争力を高めるためにはチームの結束力と生産性の向上が不可欠です。
多くの企業がその重要性を認識し、チームビルディング研修を導入していますが、「どのような手法を選べばよいのか」「効果を最大化するにはどうすればよいのか」と悩む担当者も少なくありません。
チームビルディング研修とは、単なるレクリエーションではなく、メンバー同士の相互理解を深め、コミュニケーションを活性化し、共通の目標に向かって協力し合える組織づくりを目指す取り組みです。
適切に実施することで、社員のモチベーション向上、心理的安全性の確立、創造性の発揮など、さまざまな効果が期待できます。
ただし、チームの状況や組織の課題によって最適な研修方法は異なります。
本記事では、企業におけるチームビルディング研修の基本から、効果的な手法、そして成功に導く5つのステップまで、研修担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
実践的な事例も交えながら、あなたの組織に最適なチームビルディング研修の導入方法をご紹介します。
▼チームビルディングについてはテーマに合わせて下記で解説しています。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
目次[非表示]
チームビルディング研修を企業が導入する目的と効果

企業がチームビルディング研修を導入する背景には、メンバー同士の協力体制を強化し、組織としての成果を高めたいというニーズがあります。
単なる親睦会とは異なり、目的志向型の取り組みとして、多くの企業で活用されています。
企業向けチームビルディング研修の目的
チームビルディング研修は、チームをメンバーが同じ目標に向かって協力し合える組織にしていく研修です。
企業が導入する主な目的は、実施する対象によって異なります。
全社を対象とした場合は、会社への帰属意識を高め、企業理念や価値観の共有を図ることが目的となります。
管理職層に対しては、部下の能力を引き出し、目標達成に向けたチームビルディングのスキルを習得させることを目指します。
中堅社員に対しては、管理職とメンバーの橋渡し役としての意識づけを行い、チーム内の潤滑油となる役割を認識させます。
新入社員に対しては、主体的に動ける環境づくりの一環として、早期にチームに溶け込むためのサポートを行います。
いずれの場合も、「集団」と「チーム」の違いを理解し、単なる人の集まりではなく、共通の目標に向かって協力し合える組織づくりを目指しています。また、チーム内のコミュニケーションを活性化させ、相互理解を深めることで、職場の雰囲気改善や業務効率の向上につなげる狙いもあります。
チームビルディング研修が企業にもたらす具体的効果
適切にデザイン・実施されたチームビルディング研修は、企業にさまざまな効果をもたらします。まず最も顕著な効果として、チームの結束力が強化されることが挙げられます。
メンバー同士が互いの強みや特性を理解し合うことで、チームとしての一体感が生まれ、組織の連携がスムーズになります。
また、研修を通じて活性化されたコミュニケーションは、日常業務にも好影響を与えます。
情報共有がスムーズになり、問題解決のスピードが向上するだけでなく、新たなアイデアが生まれる土壌も形成されます。
特に普段の業務では見えにくい各メンバーの個性や能力が可視化されることで、適材適所の人材配置にもつながります。
さらに、共通の目標に向かって協力し合う経験は、業務における協力体制の強化にも寄与します。
部門間の壁を越えた協力関係の構築や、社内のサイロ化防止にも効果を発揮します。
実際に多くの企業では、チームビルディング研修の実施後に、問題解決のスピードアップや業務プロセスの改善、創造的なアイデアの増加など、具体的な業務パフォーマンスの向上が感じられています。
このように、チームビルディング研修は単なる親睦行事ではなく、企業の組織力強化と業務効率化に直結する重要な人材育成施策として位置づけられています。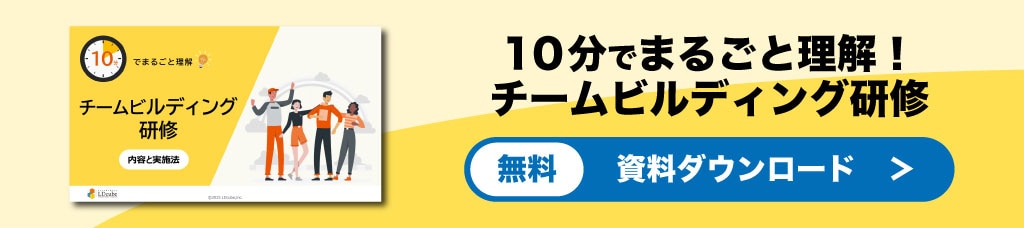
企業がチームビルディング研修の実施に至る課題

企業がチームビルディング研修を実施する背景には、組織内で顕在化しているさまざまな課題があります。
これらの課題は、ビジネス環境の変化や働き方の多様化に伴い、多くの企業で共通して見られるようになっています。
企業内コミュニケーションが不足している
近年、テレワークの普及やデジタルコミュニケーションへの移行により、従来のような対面でのコミュニケーション機会が減少しています。
特にコロナ禍以降、急速に広がったリモートワークは、業務上の情報共有は維持できても、雑談や偶発的な交流の機会を大きく減少させました。
オンラインツールを介したコミュニケーションでは、非言語情報(表情や身ぶり)が伝わりにくく、ニュアンスの誤解や心理的距離感が生じやすくなっています。
また、部署間の交流機会も減少し、組織のサイロ化が進行するケースも見られます。
このようなコミュニケーション不足は、チームの一体感の欠如や情報共有の停滞を招き、業務効率の低下につながっています。
職場での働き方が多様化している
フレックスタイム制やリモートワーク、ジョブ型雇用の導入など、働き方の多様化が進んでいます。
時間や場所を共有しない働き方が増えたことで、チームメンバー同士が顔を合わせる機会が減少し、連帯感の醸成が難しくなっています。
また、プロジェクト単位での業務増加により、一時的に組織される「仮設チーム」での仕事も増加しています。
こうしたチームでは、短期間で効果的な協働体制を構築する必要がありますが、メンバー同士の関係構築に十分な時間をかけられないケースも多く見られます。
働き方の多様化は業務の柔軟性を高める一方で、チームとしての結束力やアイデンティティーの形成を難しくしています。
チームメンバーの多様性が進んでいる
現代のビジネス環境では、新卒採用のみならずキャリア採用も増えていることや、異なる部署や専門性を持つメンバーが集まって1つのプロジェクトを遂行するケースが増えています。
こうした多様なバックグラウンドを持つメンバーによるチームでは、それぞれが培ってきた業務プロセスや思考様式の違いから、すれ違いや誤解が生じやすくなっています。
特にプロジェクトチームの場合、元の組織で培われた価値観や業務手法の違いにより、違和感や疎外感を覚えるメンバーも少なくありません。
各自の専門性や強みを生かしつつ、チームとして一つの方向に進むためには、互いの違いを理解し、尊重し合える関係性の構築が不可欠です。多様性はイノベーションの源泉となる一方で、調整コストの増加につながることもあります。
働く人の価値観が多様化してきている
世代や文化的背景による価値観の違いも、チームビルディングの課題となっています。
特に若手社員と中堅・シニア層との間では、キャリア観や仕事へのアプローチが大きく異なることがあります。
例えば、ワークライフバランスを重視する世代と、仕事を通じた自己実現を重視する世代では、働く目的そのものが異なることもあります。
また、グローバル化に伴い、多様な国籍や文化的背景を持つメンバーが同じチームで働くケースも増えています。
こうした価値観の多様性は、新たな視点や創造性をもたらす一方で、チームの方向性や目標設定において合意形成を難しくする要因ともなっています。
多様な価値観を持つメンバーが共通の目標に向かって協力するためには、互いの考え方を尊重し、対話を通じて共通認識を形成することが重要です。
弊社は社員の約半数がキャリア採用であり、男女比も約半々です。価値観の多様化を実感しています。
筆者が株式会社ビジネスコンサルタントで営業チームのマネジャーをしていた時は、男性中心で新卒プロパーの社員だけで、同じ価値観で動いていたこともあり、今思うとチームづくりは楽でした。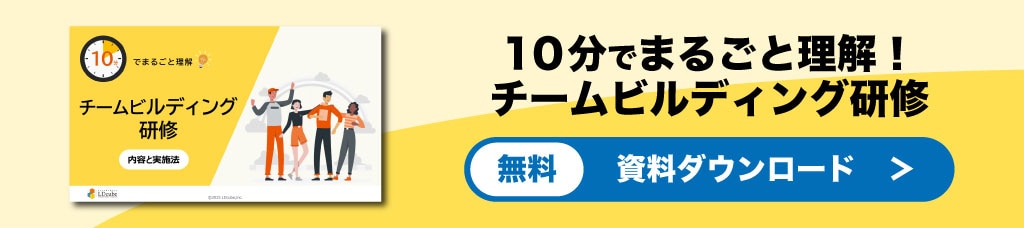
チームビルディング研修への企業の期待

企業がチームビルディング研修に投資する背景には、さまざまな期待や目標があります。
単なる親睦行事ではなく、ビジネス成果に直結する人材開発・組織開発施策として、多くの企業が具体的な効果を期待しています。
組織のパフォーマンス(業績)向上
企業がチームビルディング研修に期待する最も基本的な効果は、組織全体のパフォーマンス向上です。
個々のメンバーが持つスキルや能力を最大限に発揮できる環境を整えることで、チーム全体の成果向上を目指しています。
特に、複雑な問題解決や創造的なアイデア創出が求められる場面では、多様な視点や専門性を持つメンバーが効果的に協働することで、個人の総和以上の成果を生み出すことが期待されています。
また、チーム内の意思決定プロセスが最適化されることで、変化の激しいビジネス環境への対応力も高まります。
実際に多くの企業では、チームビルディング研修後に問題解決のスピードアップや、顧客対応の質が向上するなどの成果が報告されています。
組織・職場の一体感の醸成
チームビルディング研修を通じて、組織や職場の一体感を高めることも重要な期待の1つです。
メンバー間の心理的安全性や相互信頼が高まることで、率直な意見交換や建設的な対話が可能となり、職場の雰囲気が改善します。
特に重要な効果として
|
このような一体感は、長期的な組織の安定と成長に不可欠です。
業務の生産性向上
チームビルディング研修は、日常の業務効率や生産性の向上にも貢献します。
メンバー間のコミュニケーションが活性化することで、情報共有がスムーズになり、業務の重複や手戻りが減少します。
また、各メンバーの役割と責任が明確になることで、タスク分担の最適化や意思決定の迅速化が実現し、業務プロセス全体の効率化につながります。
さらに、チーム内の協力体制が強化されることで、業務負荷の偏りが解消され、メンバー全体のワークライフバランスも改善します。
このように、チームビルディング研修は、単なる人間関係の改善だけでなく、具体的な業務パフォーマンスの向上という実務的な効果ももたらします。
人材の定着・離職率の低下
良好な職場環境と強いチームの絆は、従業員の定着率向上にも大きく貢献します。
チームビルディング研修によって構築された信頼関係や心理的安全性の高い職場では、メンバーが互いにサポートし合う文化が育まれ、職場での孤立感や疎外感が軽減されます。
特に若手社員にとっては、チームの一員として認められ、貢献できる実感を持つことが、組織への定着意欲を高める重要な要素となります。
また、世代や専門性を超えた交流は、キャリア発達の面でもポジティブな影響をもたらします。
このように、チームビルディング研修は採用コストの削減や知識・スキルの組織内保持という観点からも、企業に大きな価値をもたらします。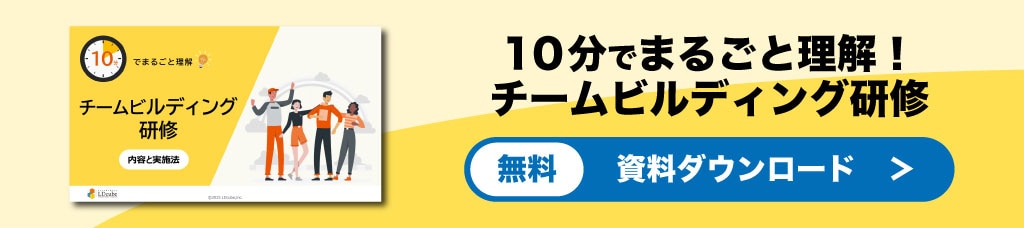
企業が行うチームビルディング研修2つの方法

チームビルディング研修を企業内で実施する方法は、大きく分けて「社内トレーナーを養成する方法」と「外部講師に委託する方法」の2つがあります。
それぞれに特徴があり、企業の状況や目的に応じて選択する必要があります。
社内トレーナーを養成して実施する
社内トレーナーを養成してチームビルディング研修を実施する方法は、長期的な人材育成戦略の一環として効果的です。
社内の人材がトレーナーとなることで、自社の組織文化や特有の課題を踏まえた研修プログラムのデザイン・実施が可能となります。
また、日常業務の中でも継続的なフォローアップができる点が大きなメリットです。
【社内トレーナー方式のメリット】
|
特に複数の部署や拠点で継続的に研修を実施したい場合に適しています。
一方で、トレーナーの育成に初期投資が必要であることや、社内の人間関係が研修の効果に影響する可能性がある点には注意が必要です。また、社内だけでは最新のトレンドや専門的知識を取り入れにくいというデメリットもあります。
外部講師に委託して実施する
外部の専門家や研修会社に委託してチームビルディング研修を実施する方法は、専門性があり質の高い研修を短期間で導入したい場合に適しています。
外部講師は多様な企業での実施経験を持ち、効果的なプログラムやファシリテーションのノウハウを蓄積しています。
【外部講師に委託するメリット】
|
特に初めてチームビルディング研修を導入する場合や、組織に大きな変革が必要な場合に効果的です。
一方で、費用面での負担が大きくなる傾向があること、企業文化や組織特性の理解に時間がかかる場合があること、研修後のフォローアップが限定的になりがちな点などがデメリットとして考えられます。
外部講師を選定する際には、自社の目的に合ったプログラム内容か、予算内で収まるか、研修後のサポート体制はあるか、中長期的に社内トレーナーを養成して内製化できる体制があるかどうかなど、複数の研修会社を比較検討することが重要です。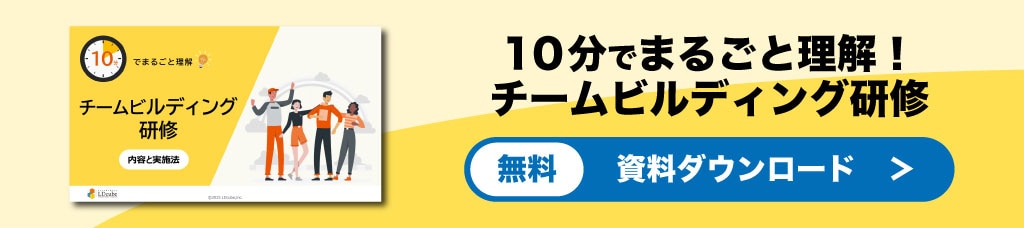
企業が行うチームビルディング研修に必要な要素

効果的なチームビルディング研修を実施するためには、いくつかの重要な要素を組み込む必要があります。
これらの要素が適切に組み合わさることで、単なるレクリエーションではなく、実際の業務パフォーマンス向上につながる意義のある研修となります。
チーム(職場)単位で取り組むこと
チームビルディング研修は、実際に日常業務を共にするチームや職場単位で実施することが重要です。
個人単位で参加する一般的な研修と異なり、実際の業務関係にあるメンバー同士で行うことで、現実の人間関係や課題に即した学びが得られます。
また、研修で得た気づきや改善点を実務に直接生かしやすく、研修効果の持続性も高まります。
特にプロジェクトの立ち上げ時や組織変更後など、チームの形成初期段階での実施が効果的です。
チームメンバーの自己理解を促すこと
効果的なチームビルディングの第一歩は、各メンバーが自己理解を深めることです。
自分の強みや特性、価値観、コミュニケーションスタイルなどを客観的に認識することで、チームへの貢献の仕方が明確になります。
研修では、行動特性診断ツールなどを活用した自己分析や、「仕事の進め方の好み」などを共有するワークを取り入れることで、自己開示を促し、チーム内での役割を意識する機会を提供します。
チームメンバー同士の相互理解を促すこと
チームとして機能するためには、メンバー同士が互いを理解し合うことが不可欠です。
研修では、行動特性診断ツールを活用した強みの共有や、バックグラウンドやキャリアに関する情報交換など、通常の業務では聞けない情報を交換する機会を設けることが重要です。
これにより、「なぜそのように考え、行動するのか」という背景への理解が深まり、互いの違いを尊重しながら協働する基盤が形成されます。
共通の目標に向かって取り組むアクティビティー
チームビルディング研修の核となるのが、共通の目標達成に向けて協力するアクティビティーです。
ペーパータワー(紙でタワーを作り高さを競う)やボール回し(チーム全員がボールに触れる時間を短縮する)などのゲームを通じて、役割分担、コミュニケーション、意思決定などのチームプロセスを体験します。
これらのアクティビティーは単純なゲームに見えますが、チームの協力体制や問題解決能力を可視化し、実務におけるチームワークの重要性を体感する貴重な機会となります。
ゲームの時にはお互いに声を掛け合えるのに、業務の時には声を掛け合えないのはなぜかなどを振り返るきっかけを提供してくれます。
演習後のリフレクション
アクティビティーを実施するだけでは学びは限定的です。
その体験から教訓を引き出し、実務に応用するためには、適切なリフレクション(振り返り)が不可欠です。
「何が起きたか」「なぜそうなったか」「実務ではどのように生かせるか」という流れで振り返りを行うことで、表面的な体験が深い学びに変わります。
特に社内コミュニケーションの活性化、チームへの貢献、リーダーシップ発揮などの観点から振り返ることで、実践的な気付きが得られます。
ガイドラインの設定
チームビルディング研修の効果を発揮させるには、研修で学んだことを踏まえ、翌日から職場でどのような行動を取るかということの明確なガイドラインの設定が重要です。
【ガイドラインの例】
|
これらのガイドラインより、メンバーはガイドラインに沿った言動を取るようになります。
チームビルディング研修に参加した職場メンバーで意見を出し合いガイドラインを作成することで、ガイドラインの実行力が高まります。
また、研修の最後には行動宣言セッションを設け、学びを実務に生かすためのコミットメントを形成することも重要です。これにより、研修効果の持続性が高まり、実際の業務改善につながります。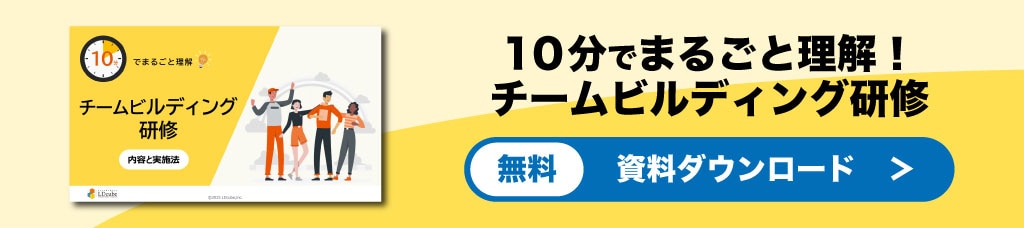
企業のチームビルディング研修を成功させる5ステップ

チームビルディング研修は、単発のイベントとして終わらせるのではなく、事前準備から事後フォローまで一連のプロセスとして捉えることが成功の鍵です。
ここでは、企業がチームビルディング研修を成功させるための5つのステップを紹介します。
ステップ1:チームビルディング研修の目標を明確化する
まず、チームビルディング研修を通じて達成したい目標を明確にすることが重要です。
「チームワークの向上」といった漠然とした目標ではなく、自社の経営課題や組織の現状分析を踏まえた具体的な目標を設定しましょう。
例えば「部門間の連携不足による情報共有の遅れを解消する」「新たなプロジェクトチームの立ち上げを加速する」など、より具体的な課題に紐づけることで、研修の効果測定もしやすくなります。
この段階では、組織の現状点検も併せて行い、チーム内のコミュニケーションパターンや意思決定プロセスなど、具体的に改善したい点を特定することが有効です。目標が明確になれば、それに適した研修内容を選択する判断基準も明確になります。
ステップ2:企業内の研修対象者と実施規模を決定する
次に、研修の対象者と実施規模を決定します。
チームビルディング研修は、全社的に実施する場合と、特定のチームや部署だけを対象にする場合があります。目的や予算、リソースに応じて適切な範囲を設定しましょう。
全社的に実施する場合は、共通の企業文化や価値観の醸成に効果的ですが、準備やコストの負担が大きくなります。
一方、新設されたプロジェクトチームや課題を抱える特定の部署など、限定的に実施する場合は、より具体的な課題解決に焦点を当てることができます。
ステップ3:社内トレーナーか外部講師による実施かを決定する
研修の実施方法として、社内トレーナーを育成して行うか、外部の専門講師に委託するかを決定します。
両者にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、自社の状況に合わせて選択することが重要です。
社内トレーナーによる実施は、自社の文化や課題を熟知している点、継続的な実施が容易である点、長期的にはコスト効率が良い点などがメリットです。
一方、外部講師による実施は、専門的な知識や豊富な事例を活用できる点、客観的な視点からのアドバイスが得られる点などがメリットとなります。
また、初回は外部講師に依頼し、徐々に社内トレーナーを育成していくハイブリッド型のアプローチも効果的です。
ステップ4:自社に最適な研修プログラムを選択する
目標、対象者、実施方法が決まったら、具体的な研修プログラムを選択します。
チームビルディング研修には、ペーパータワーやボール回しなどの「お手軽なゲーム形式」、社内運動会などの「体を動かすアクティビティー形式」、数日間にわたる「合宿形式」、対話を中心とした「対話形式」など、さまざまな手法があります。
選択にあたっては、参加者の特性(年齢層、職種、チームの成熟度など)や、達成したい目標、利用可能な時間や予算、実施環境などを考慮します。
また、対話とアクティビティーを組み合わせるなど、複合的なプログラム設計も効果的です。重要なのは、単に楽しいだけでなく、実務に関連する学びが得られるプログラムを選ぶことです。
ステップ5:研修後の職場でのフォロー体制を構築する
チームビルディング研修の効果を持続・定着させるためには、研修後のフォロー体制が不可欠です。
研修直後に振り返りの時間を設けるだけでなく、1カ月後、3カ月後など定期的なフォローアップセッションを計画し、学びがどのように業務に生かされているか、ガイドラインが守られているかを確認します。
また、日常業務の中で研修の学びを実践できる機会を意図的に創出することも重要です。
例えば、会議の進行方法を研修で学んだ手法に沿って変更したり、定期的にチームの状態をチェックする仕組みを導入したりするなど、具体的な行動変容を促す取り組みが効果的です。
さらに、研修の効果を定量的・定性的に測定し、次回の研修改善に生かすPDCAサイクルを確立することも、長期的な組織開発の視点では重要なステップです。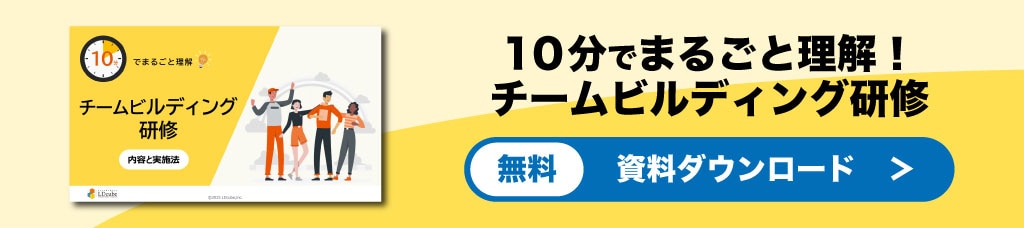
社内トレーナーがいればフォローアップしやすい

チームビルディング研修の効果を最大化するためには、研修後のフォローアップが不可欠です。
特に社内トレーナーを育成して研修を実施している企業では、その後のフォローアップがスムーズに行える点が大きなメリットとなります。
社内の状況や課題、組織文化などを把握している
社内トレーナーの最大の強みは、自社の組織文化や現場の実情を深く理解していることです。
外部講師では把握しにくい社内特有の課題、各部署の力関係、過去の取り組みの経緯などを熟知しているため、研修内容を実務に落とし込む際のギャップを最小限に抑えることができます。
例えば、チームビルディング研修で学んだコミュニケーション手法を実際の会議や日常業務に適用する際、「あの部署とのやり取りではこういう点に注意が必要」「過去にこういう取り組みがうまくいかなかったのはこういう理由がある」といった具体的なアドバイスが可能です。
また、自社の業界特有の事情や業務特性を踏まえた応用方法を提案できるため、「理想論と現実のギャップ」に悩むことなく、実践的な改善につなげられます。
さらに、組織特有の専門用語や略語、暗黙知を共有しているため、コミュニケーションがスムーズで、細かなニュアンスまで含めた指導が可能です。
これにより、研修内容の誤解や解釈の違いによる混乱を防ぎ、一貫した方向性でのチーム育成を実現できます。
スケジュール調整や短時間でのフォローが可能
社内トレーナーがいることの大きなメリットとして、フォローアップの柔軟性が挙げられます。
外部講師の場合、スケジュール調整や追加セッションの実施にはコストや時間の制約がありますが、社内トレーナーであれば比較的容易に対応できます。
【社内トレーナーによる柔軟なフォロー例】
|
「今日の会議でこんな問題が起きたけど、どう対処したらいい?」といった具体的な相談にもその場で応じられるため、学びを実践に生かす機会を逃しません。
さらに、社内トレーナーは普段から組織内にいるため、研修内容の実践状況を日常的に観察し、必要に応じてフィードバックを提供することができます。
これにより、小さな変化や成果を見逃さず、適切なタイミングで強化したり、軌道修正したりすることが可能となります。
こうした「見えないフォロー」が、チームビルディング研修の効果を持続させ、組織文化として定着させる上で非常に重要な役割を果たします。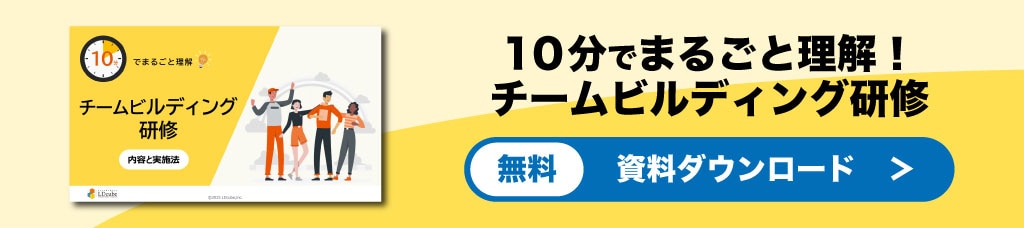
チームビルディング研修ならLIFO®がおすすめ!
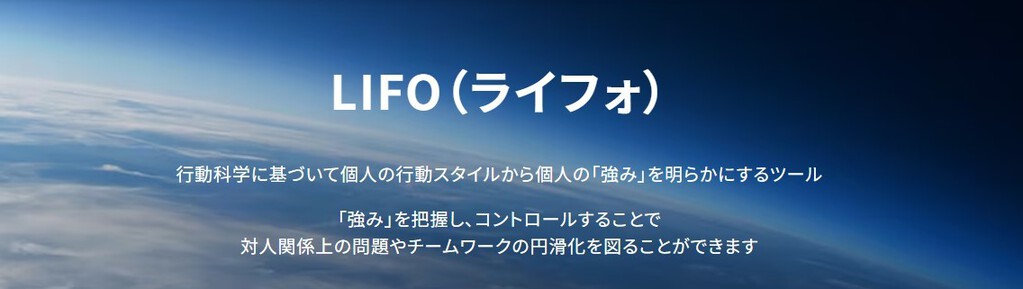
チームビルディング研修には自己診断ツールLIFO(Life Orientations)を活用した職場単位でのワークショップがおすすめです。
なぜなら、LIFOプログラムは心理学や行動科学をベースにして組み立てられた行動特性診断をベースに、職場単位でワークショップを行うためのワークブックなどのツールも体系的にそろえられているからです。
また、体系立てられたツールの使い方を社内トレーナーの方々にライセンス提供もされており、社内トレーナーの方々が職場単位でワークショップを展開していくことも可能です。下記に概要を紹介します。
自己診断ツールLIFOとは
LIFO(Life Orientations)は、個人の行動スタイルを診断する自己診断ツールです。
このツールは、自分の強みや行動パターンを理解するために役立ちます。
LIFOは4つの基本スタイルに基づいており、これらのスタイルはそれぞれ異なる行動特性や価値観を持っています。
自分がどのスタイルに属しているかを知ることで、より良いコミュニケーション方法やストレス時の行動傾向を把握することができます。
LIFOを活用したコミュニケーション研修
LIFOを活用したコミュニケーション研修では、まず参加者が自己診断を行い、自分の行動スタイルを理解します。
この診断結果を基に、どのようにして他者と効果的にコミュニケーションを取るかを学びます。
研修では以下のような内容が含まれます。
自己理解の深化 | 診断結果を基に、自分のコミュニケーションスタイルの特徴を深掘りします。 どのような場面でどのように行動するのかを具体的に把握します。 |
他者理解の促進 | 他のスタイルを持つ人との違いを理解することで、より効果的な関わり方を学びます。 これにより、誤解や摩擦を減らすことが可能になります。 |
実践的スキルの習得 | ワークショップやロールプレイを通じて、実際のコミュニケーション場面でどのようにLIFOの知見を活用するかを練習します。 |
フィードバックと改善 | 実践後にフィードバックを受け、自分のコミュニケーションスタイルの改善点を明確にします。 LIFOを取り入れた研修に参加することで、個人のコミュニケーションスタイルを理解し、それをベースに他者との関係を改善するスキルを獲得できます。 これにより、職場や日常生活でのコミュニケーションがよりスムーズで効果的になることが期待できます。 |
LIFO®プログラムは社内トレーナーで展開可能
LIFO®プログラムは、これまでの活用実績と実用性から、企業内でのトレーニングにおいて自信を持っておすすめできるプログラムです。
社内展開にあたっては、特定の準備と手続きを経ることで、コストを抑えながら、外部講師に委託したかのように、社内トレーナーによる効果的なプログラムを展開することが可能です。以下に、その流れを詳しく説明します。
ライセンスの取得 | 社内トレーナーによりLIFO®プログラムを実施するには、トレーナーがLIFO®プログラムの公式ライセンスを取得することが必要です。 ライセンスを取得するために、LIFO®プラグラムライセンス取得講座を受講します。LIFO®プログラムの考え方や実施方法を正しく理解し、それを他者に伝えるためのスキルを学びます。 講座の最後にある試験に合格すると、ライセンスを取得することができます。 |
教材の購入 | ライセンス取得と並行して、プログラムを社内で展開するためには、必要な教材やツールを購入する必要があります。 教材は、LIFO®プログラムのさまざまなテーマに応用できる構成になっており、研修実施の目的に合わせて教材を選択し、購入できます。 教材には、診断ツール、フィードバック用の資料、ワークブックなどが含まれており、これらを用いることで、社内トレーナーは一貫して高品質なトレーニングを提供することができます。 |
社内トレーナー による展開 | ライセンスと教材がそろったら、社内トレーナーはプログラムを社内で展開する準備が整います。 組織の文化やニーズに精通しているため、社内トレーナーは、LIFO®プログラムを適切にアレンジして展開することができます。 これにより、参加者はより実践的な、日常業務につながる研修を受けることが可能です。 |
LIFOを活用して社内トレーナーが研修を展開している事例

背景・課題
リコージャパン株式会社では、2010年の販売会社統合以降、各支社の固有の課題に対応できず、教育施策が本部主導で一方的になるなどの課題がありました。
また、コロナ禍以降、会食などの機会が減ったことにより、コミュニケーションの希薄化を招いていました。これらの課題を解決するために、社員自らが強みや弱みを理解し合い、横のつながりを強化する取り組みが求められていました。
LIFOプログラム(社内トレーナーライセンス)の導入
その中で、LIFO(Life Orientations)を導入しました。LIFOの活用を通じて、社員一人一人の個性を診断し、自己理解と他者理解を促進しました。
これにより、非公式なコミュニケーションが減少する中でも、社員同士の相互理解を深めるための新たな手段を提供することができるようになりました。
また、LIFOプログラムライセンスを取得することで、社内トレーナーが自主的に研修を行えるようになり、組織風土改革を進めました。
LDcubeとの協力により、多様なワークショップを展開し、各支社・部門が抱える具体的な課題に対応できるようになりました。
社内展開
プログラムの展開においては、事前のLIFO診断、ワークショップの実施、職場での実践、効果検証のサイクルを組み込みました。
参加者は、研修後の職場実践を通じて得られたスキルを評価し合い、PDCAサイクルを回すことで、持続的なスキルアップを図っています。
ラーニングプラットフォーム「UMU」を活用し、受講者同士が学び合う環境も整備しました。
社内トレーナーによる研修実施後の反応
導入後、プログラム受講者の満足度は高く、多くの支社で「対人関係」や「マネジメント能力」などにおいて数値的な改善が見られました。
LIFOを活用したレクチャーは「人」の問題の解決に寄与し、特にアウトプット重視の体験学習が効果的でした。
UMUの活用と一連の学習サイクルの設計により、事務局の負担軽減と学習効果の向上が実現しました。
今後に向けて
今後は、各支社や部門の課題に寄り添い、人材育成を継続的にサポートすることで、社員個々の自己成長と組織全体の活性化をさらに推進する予定です。
また、LIFO以外のライセンスプログラムも組み合わせ、人材育成のプログラムラインナップを増やしていきます。
これにより、組織内のさまざまな課題を解決し、全体の一体感をさらに高められることを期待しています。
▼本事例はインタビュー記事の一部です。インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。
⇒リコージャパン株式会社様 ライセンスプログラム導入事例
まとめ:効果的なチームビルディング研修で企業の組織力と結束力を高めよう
企業で行うチームビルディング研修のポイントとは?おすすめ展開法も紹介!について案内してきました。
チームビルディング研修は単なるレクリエーションではなく、組織の業績向上に直結する戦略的な人材育成施策です。
現代の企業環境では、コミュニケーションの不足、働き方の多様化、メンバーや価値観の多様性など、さまざまな要因がチームの結束力形成を難しくしています。
しかし、適切に設計・実施されたチームビルディング研修を通じて、これらの課題を乗り越え、強固なチーム基盤を構築することが可能です。
研修の実施にあたっては、目標の明確化からフォロー体制の構築まで、一連のプロセスとして捉えることが重要です。
特に、研修後の職場での実践とフォローアップが効果持続の鍵となります。
社内トレーナーの育成は、長期的な視点でチームビルディングを企業文化として定着させるための有効な選択肢となるでしょう。
組織力と結束力を高めるチームビルディング研修を導入し、変化の激しいビジネス環境を勝ち抜く強いチームづくりに取り組んでみてはいかがでしょうか。
株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。
無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。