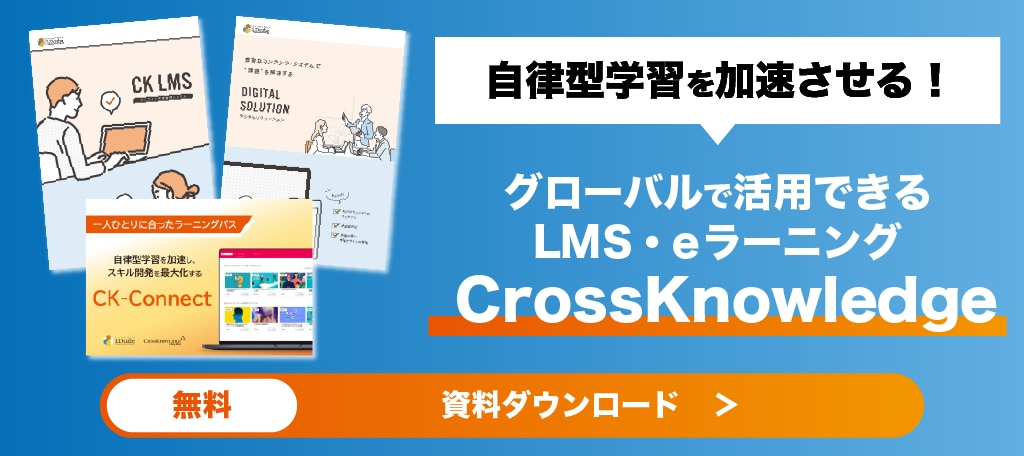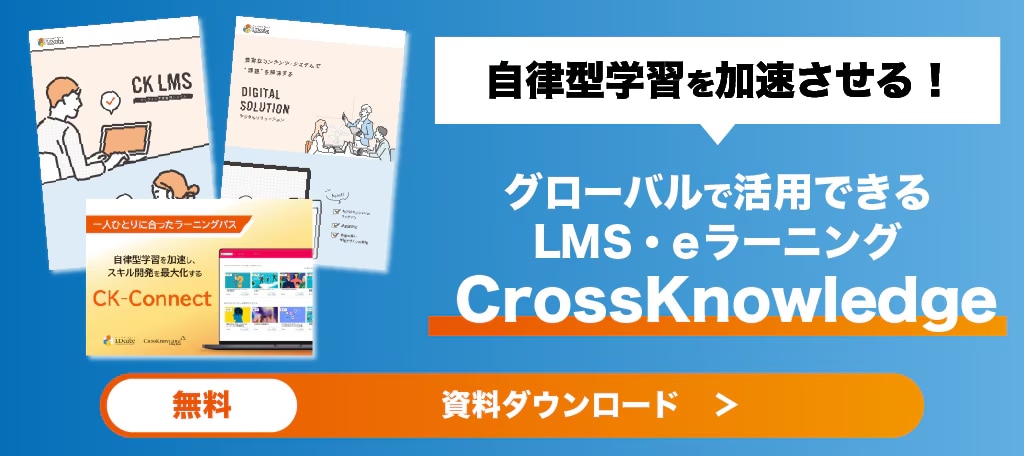パッケージ型eラーニング活用ガイド|メリットや選び方・おすすめコースを解説
企業の人材育成において、効率的かつ効果的な研修方法を模索している担当者の方は多いのではないでしょうか。
近年、普及が進んでいる「eラーニングパッケージ」は、時間や場所を選ばず学習できる柔軟性と、コスト効率の良さから注目を集めています。しかし、初めて導入を検討する際には、「どのような種類があるのか」「自社に合ったシステムの選び方」「具体的な導入手順」など、さまざまな疑問が浮かぶことでしょう。
本記事では、eラーニングパッケージの基本から、選び方、導入のポイントまでを網羅的に解説します。従来の集合研修との比較や、導入時に直面しがちな課題とその解決策も紹介しているので、人材育成担当者の方にとって、eラーニング導入の羅針盤となることでしょう。
2025年に注目されているパーソナライズ学習など、最新のeラーニングトレンドも踏まえながら、貴社の人材育成を効率化・高度化するために役立つ情報をお届けします。本記事を参考に、貴社に最適な企業向けeラーニングを選定し、スムーズな導入を実現しましょう。
▼LMSやeラーニングについてテーマに合わせて以下で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
- eラーニングで得られる効果とは?目的別に徹底解説!
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
目次[非表示]
- 1.eラーニングパッケージの活用で人材育成の効率を高めよう
- 2.eラーニングパッケージとは?
- 3.eラーニングパッケージの3つのメリット
- 4.eラーニングパッケージの2つのデメリット
- 5.eラーニングパッケージの選び方
- 5.1.eラーニングパッケージの特徴
- 5.2.階層(新人社員・中堅社員・管理職など)に合わせて選ぶ
- 5.3.目的(リーダーシップ・セールス・コンプライアンスなど)に合わせて選ぶ
- 5.4.一人一人(個人別)の課題に合わせて選ぶ
- 5.5.予算に応じて費用対効果の高いパッケージを選ぶ
- 6.eラーニングパッケージ導入の重要ポイント
- 7.eラーニングパッケージ導入後の効果を最大化する運用術
- 7.1.効果的な社内周知とラーニングキャンペーンの実施
- 7.2.学習進捗の可視化と効果測定
- 7.3.必須コースとパーソナライズコースを組み合わせる
- 7.4.集合研修と効果的に組み合わせる
- 7.5.社内トレーナーが運用する
- 8.パーソナライズ学習でeラーニング受講率100%を達成した事例
- 9.eラーニングパッケージのおすすめはCrossKnowledge
- 10.まとめ:自社に最適なパッケージ型eラーニングを選んで教育効果を最大化しよう
eラーニングパッケージの活用で人材育成の効率を高めよう

企業の人材育成において、効率的かつ効果的な研修方法を模索されている担当者の方が多いのではないでしょうか。
eラーニングパッケージは、そのような悩みを解決する有力な選択肢となります。既に整備されたコンテンツをすぐに活用できるため、自社で一から教材を作成する手間を省き、質の高い研修を迅速に提供できます。
eラーニングパッケージは手軽に導入できる
eラーニングパッケージの最大の特徴は、専門知識がなくても簡単に導入できる点です。あらかじめ教材コンテンツが用意されているため、システム導入後すぐに学習をスタートできます。また、多くのパッケージ型サービスは直感的な管理画面を備えており、ITに詳しくない担当者でも受講者の登録や進捗管理が容易に行えます。
さらに、初期設定の手間も最小限で済むため、導入から運用までのリードタイムが短いのも魅力です。企業内の人材育成ニーズにすぐに対応できるため、急な研修要請にも柔軟に対応できます。専門家が監修した質の高いコンテンツをすぐに利用できるため、教育の質を担保しながらスピーディーな展開が可能となります。
集合研修との組み合わせがしやすい
eラーニングパッケージは、従来の集合研修と組み合わせることで、より効果的な学習環境を構築できます。例えば、基礎知識の習得はeラーニングで行い、実践的なスキルやディスカッションは集合研修で行うというブレンド型の学習スタイルが注目されています。
このアプローチにより、集合研修の時間をより効率的に使うことができます。参加者が事前にeラーニングで基礎知識を習得していれば、集合研修ではより深い議論や実践的な演習に時間を割くことができるのです。また、集合研修後のフォローアップやスキル定着のためにeラーニングを活用することで、学習の継続性も確保できます。
eラーニングパッケージ+社内トレーナーが効果的
eラーニングパッケージと社内トレーナーを組み合わせることで、標準化された良質な教材と、自社の実情に即した個別指導両方のメリットを享受できます。社内トレーナーは、eラーニングで学んだ内容と実際の業務をつなげる架け橋となり、学習効果を高める重要な役割を担います。
例えば、eラーニングで学んだ心理的安全性の作り方について、実際の職場でとのように生かすか、社内トレーナーが具体的なアドバイスを提供することで、知識を実践に結びつけることができます。
また、社内トレーナーが受講者の進捗状況を確認し、必要に応じたサポートを行うことは、学習のモチベーションを維持し、脱落を防ぐことにもつながります。
このような組み合わせにより、標準化された知識習得と個別の実践力強化を両立した効果的な人材育成が実現します。
▼社内トレーナーについては下記で詳しく解説しています。
eラーニングパッケージとは?

eラーニングを導入する際、「パッケージ」というワードをよく目にするかもしれません。
ここでは、eラーニングパッケージの基本的な概念と特徴、種類について解説します。自社に最適なeラーニングを選ぶための基礎知識を身に付けましょう。
eラーニングパッケージの定義と基本的な特徴
eラーニングパッケージとは、あらかじめコンテンツが用意されたeラーニングコースのことです。
ビジネスマナーや新入社員研修、リーダーシップ、ハラスメントなど、テーマに沿って必要なコンテンツをひとまとめに提供します。汎用的なテーマの教材があらかじめ整備されているため、導入後すぐに学習を開始できる点が大きな特徴です。
eラーニングシステムの基本機能である学習進捗管理、受講者管理、テスト機能なども備えており、オールインワンで人材育成のためのツールとして活用できます。多くの場合、動画やテキスト、クイズなど、さまざまな形式のコンテンツが含まれており、学習者の理解度や興味に合わせた多様な学習体験を提供できます。
パッケージ型とプラットフォーム型の違い
eラーニングシステムは大きく分けて「パッケージ型」と「プラットフォーム型」の2種類があります。両者の主な違いは、コンテンツの提供方法にあります。
パッケージ型は既に完成したコンテンツがセットになっているため、すぐに利用できる反面、自社独自のコンテンツを追加する柔軟性は制限されます。一方、プラットフォーム型は、コンテンツを自社で内製する必要があるため、学習開始までに時間とコストがかかりますが、自社の特性に合わせたオリジナルのコンテンツを作成できます。
パッケージ型は専門的な知識がなくても導入・運用でき、特に汎用的な研修内容を効率的に提供でいるのが強みです。プラットフォーム型は自社独自のノウハウや業務手順などの教育に適しており、カスタマイズ性を重視する場合に選ばれます。
eラーニングパッケージの種類(階層別・目的別・個人別)
eラーニングパッケージは、提供内容によってさまざまな種類に分類できます。
階層別パッケージは、組織内の役職や経験に応じて、新入社員、中堅社員、管理職といった階層に向けてコンテンツを提供します。それぞれの階層に必要なスキルや知識に焦点を当てることで、段階的なキャリア開発を支援します。
目的別パッケージは、リーダーシップ、セールススキル向上、コンプライアンス教育など、特定のテーマに特化したコンテンツを提供します。組織の課題や強化したい分野に合わせて選択できます。
個人別パッケージは、一人一人の学習ニーズや習熟度に応じてカスタマイズできるコンテンツを提供します。パーソナルサーベイの結果に基づいて個別の学習パスを設定できるなど、パーソナライズされた学習体験を実現します。
これらの種類を理解し、自社の教育目的や対象者に合わせて最適なパッケージを選択することが重要です。
▼すぐに活用できるeラーニングパッケージは下記で紹介しています。
⇒https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning_package
eラーニングパッケージの3つのメリット

eラーニングパッケージの導入を検討する際、そのメリットを理解することが重要です。
ここでは特に重要な3つのメリットについて詳しく解説します。自社の人材育成における課題解決にどのように貢献するのか、具体的なメリットを見ていきましょう。
①導入コストと時間の大幅削減
eラーニングパッケージの最大のメリットは、導入にかかるコストと時間を大幅に削減できる点です。eラーニングコンテンツを自社で一から作成する場合、教材設計、シナリオ作成、動画撮影・編集、システム構築など、多くの工程と専門知識が必要となります。
これらの作業を外部に委託すると、相応のコストがかかります。また、完成までに数ヶ月を要することもあります。eラーニングパッケージを選ぶことで、これらのコストと時間を大幅に削減でき、限られた予算と期間で効果的な研修を実現できます。
②専門家監修の高品質なコンテンツをすぐに活用
パッケージ型eラーニングのもう一つの大きなメリットは、各分野の専門家が監修した高品質なコンテンツをすぐに活用できる点です。自社で教材を作成する場合、その分野の専門知識を持ったスタッフの確保や外部専門家への依頼が必要となります。
パッケージ型では、業界のベストプラクティスや最新動向を反映した高品質なコンテンツが提供されるため、専門知識がない担当者でも安心して導入できます。また、定期的にコンテンツが更新されるサービスも多く、常に最新の情報を学習者に提供することが可能です。
③管理・運用の負担が少なく担当者の工数削減
eラーニングパッケージは、導入後の管理・運用の負担も比較的に軽減されます。多くのサービスでは、受講者の進捗管理、成績管理、修了証の発行などの機能が標準搭載されており、管理者はダッシュボードから簡単に全体の状況を把握できます。
また、システムのメンテナンスやアップデートもサービス提供元が担当するため、自社での技術的な対応が不要です。これにより、人材育成担当者は運用管理よりも、学習効果の向上や受講者のフォローなど、より価値の高い業務に注力できるようになります。
結果として、限られた人的リソースを効率的に活用した人材育成が実現します。
eラーニングパッケージの2つのデメリット
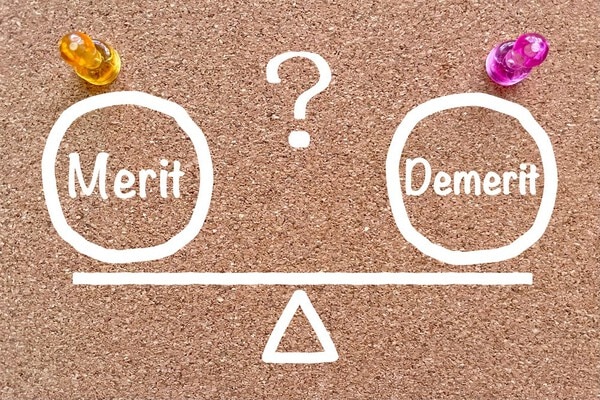
eラーニングパッケージには多くのメリットがある一方で、いくつかの制約やデメリットも存在します。導入を検討する際には、これらのデメリットも理解した上で判断することが重要です。
ここでは、特に注意すべき2つのデメリットについて解説します。
①自社の独自ニーズに対応できない場合がある
eラーニングパッケージの最大のデメリットは、自社特有の業務プロセスやノウハウを教育するためのコンテンツが含まれていない点です。
汎用的なビジネススキルや知識についてのコンテンツは充実していますが、例えば「自社独自の営業手法」や「特定の業界に特化した専門知識」などの教育には不向きな場合があります。
この問題に対処するには、eラーニングパッケージと集合研修や社内トレーナーによる指導を組み合わせるハイブリッド型の教育アプローチが効果的です。汎用的な知識はパッケージで学習し、自社特有のノウハウは対面形式で補完することで、両方のメリットを最大化できます。
②カスタマイズ性に制限がある
2つ目のデメリットは、既存コンテンツのカスタマイズに制限がある点です。多くのeラーニングパッケージでは、コンテンツの内容を変更することは難しく、自社の文化や状況に合わせた事例や用語に置き換えることができない場合があります。
このような制限を克服するには、独自コンテンツの追加が可能なパッケージ型サービスを選ぶことが重要です。最近のサービスでは、既存コンテンツへ補足資料の追加や、オリジナルコンテンツと組み合わせた学習パスの作成ができるものも増えています。
また導入前に、どの程度のコンテンツ追加が可能か、サービス提供元に具体的に確認することをおすすめします。
eラーニングパッケージの選び方

eラーニングパッケージを導入する際には、自社の教育ニーズに合ったサービスを選ぶことが成功の鍵となります。多くのパッケージの中から最適なものを選ぶためには、いくつかの重要な視点があります。
ここでは、eラーニングパッケージの特徴を踏まえた選び方と、具体的な選定基準について解説します。
eラーニングパッケージの特徴
eラーニングパッケージには主に2つのタイプがあります。
「コース設計タイプ」は、テーマごとにまとめられたコンテンツをパッケージ化しており、初心者コースや管理職コースなど階層や職種、テーマ別に構成されています。
一方、「定額制タイプ」は、提供されている全てのコンテンツが閲覧可能で、自社に合ったものをピックアップして利用できます。
選ぶ際には、管理のしやすさ、カスタマイズ性、配信方法の柔軟性などを確認することが重要です。
また、ユーザー管理機能やレポート機能など、運用に必要な機能が備わっているかもチェックしましょう。サービスによって価格やコンテンツの質にも差があるため、トライアルや無料体験を活用して実際に使い勝手を確かめることをおすすめします。
階層(新人社員・中堅社員・管理職など)に合わせて選ぶ
企業内の階層に応じた教育を提供したい場合は、階層別のパッケージを選ぶことが効果的です。
新入社員向けには、ビジネスマナーや基本スキルを包括的に学べるコンテンツが充実したパッケージを選びましょう。
中堅社員向けには、モチベーション管理やコーチングなど、職場の要として管理職へのステップも見据えたコンテンツなどがおすすめです。
管理職向けには、リーダーシップやマネジメント、評価・フィードバックスキルなどを学べるパッケージが適しています。
階層別に選ぶ際のポイントは、その階層に求められる役割や責任を明確にし、それに合致したスキル開発を提供できるかどうかを基準にすることです。また、キャリアパスに沿って段階的に学習できる構成になっているかも確認しましょう。
目的(リーダーシップ・セールス・コンプライアンスなど)に合わせて選ぶ
特定のスキルや知識の向上を目的とする場合は、目的別のパッケージを選ぶことが効果的です。
例えば、営業力強化が目的なら、セールススキルやネゴシエーション、商談プロセスなどを体系的に学べるパッケージを選びます。コンプライアンス教育が目的なら、法令遵守やハラスメント防止など、必要なテーマをカバーしているかを確認します。
目的別に選ぶ際のポイントは、その分野の専門家が監修しているかどうかと、実践的な内容が含まれているかどうかです。単なる知識の伝達だけでなく、ケーススタディーやシミュレーションなど、実務に生かせる要素が含まれているパッケージを選ぶことで、学習効果が高まります。
一人一人(個人別)の課題に合わせて選ぶ
従業員一人一人の異なるニーズや課題に対応したいなら、個人別のカスタマイズが可能なパッケージを選びましょう。パーソナライズ機能を備え、個々の課題に応じた学習パスを提供できるサービスが理想的です。
個人別に選ぶ際のポイントは、学習者が自分のペースで進められるか、自分の興味や必要性に応じてコンテンツを選択できるかという柔軟性です。
また、学習履歴や成績が可視化され、個人の成長を確認できる機能も重要です。さらに、AI技術を活用して学習者の行動パターンから最適なコンテンツを推奨する機能があれば、より効果的な学習が期待できます。
予算に応じて費用対効果の高いパッケージを選ぶ
eラーニングパッケージの価格は、1ユーザーあたり月額数百円から数千円と幅広く、初期費用も無料から数十万円までさまざまです。限られた予算内で最大の効果を得るためには、費用対効果を重視した選択が必要です。
費用対効果を評価する際は、単に価格の安さだけでなく、コンテンツの質と量、更新頻度、サポート体制なども考慮しましょう。例えば、定額制で多数のコンテンツが利用可能なサービスは、多様な教育ニーズに対応できる点で費用対効果が高い場合があります。
また、受講者数によって料金が変動するケースもあるため、自社の規模に合った料金プランを選ぶことも重要です。無料トライアルを活用して、実際の使用感と効果を確認してから導入を決めるのが賢明です。
eラーニングパッケージ導入の重要ポイント

eラーニングパッケージを導入する際には、単に人気のあるサービスを選ぶだけでは不十分です。自社の状況や目的に合ったシステムを選び、効果的に活用するためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
ここでは、導入成功のために確認すべき4つの重要ポイントについて解説します。
自社の教育目的と研修対象者を明確にする
eラーニングパッケージを導入する前に、「なぜ導入するのか」「誰に対して実施するのか」を明確にすることが最も重要です。例えば、新入社員のビジネススキル向上が目的なのか、全社員のコンプライアンス意識強化が目的なのか、管理職のリーダーシップ開発が目的なのかによって、最適なパッケージは異なります。
具体的な目標を設定しておくことで、導入後の効果測定も可能になります。また、対象者の規模やITリテラシーレベル、学習環境(デバイスやネットワーク環境)なども事前に把握しておくことが重要です。これらの情報を基に、対象者に最適な学習体験を提供できるパッケージを選びましょう。
コンテンツの質と量を確認する
パッケージに含まれるコンテンツの質と量は、学習効果を左右する重要な要素です。
コンテンツの質を確認する際のポイントとしては、専門家による監修がされているか、分かりやすい説明や具体例が充実しているか、視覚的な要素(図表やイラスト、動画など)が効果的に活用されているかなどが挙げられます。
また、コンテンツの量については、単に数が多いことが良いわけではなく、自社の教育ニーズをカバーする範囲と深さを備えているかが重要です。
トライアルやデモを活用して、実際のコンテンツを確認することをおすすめします。さらに、コンテンツの更新頻度も確認し、常に最新の情報が提供されるかどうかもチェックしましょう。
使いやすいUIとサポート体制を確認する
eラーニングシステムがいくら優れたコンテンツを提供していても、使いにくければ学習効果が大幅に低下します。
学習者が直感的に操作できるインターフェースと、管理者が効率的に運用できる管理画面を備えているかを確認しましょう。特に、受講の開始や進捗確認、テスト受験などの基本操作がシンプルで分かりやすいことが重要です。
また、導入時や運用中のサポート体制も重要なチェックポイントです。電話やメールでのサポート対応時間、マニュアルやFAQの充実度、トラブル発生時の対応フローなどを事前に確認しておくと安心です。
特に初めてeラーニングを導入する場合は、手厚いサポートが受けられるサービスを選ぶことをおすすめします。
既存の人材育成施策との組み合わせ可否を確認する
eラーニングパッケージは単体で導入するよりも、既存の研修プログラムや人材育成施策と組み合わせることで、より高い効果を発揮します。
例えば、集合研修の事前学習や事後フォローとしてeラーニングを活用したり、OJTと並行して基礎知識を補強するためにeラーニングを導入したりする方法が考えられます。
そのため、パッケージを選ぶ際には、自社の既存の教育体系にどのように組み込めるかを検討することが重要です。
具体的には、集合研修の内容と重複せずに補完できるコンテンツが含まれているか、研修効果を高めるためのブレンド学習が可能か、他のシステム(人事システムやLMSなど)との連携が可能かなどを確認しましょう。
eラーニングパッケージ導入後の効果を最大化する運用術

eラーニングパッケージを導入しただけでは、十分な効果を得ることはできません。導入はあくまでスタート地点であり、その後の運用方法によって教育効果に大きな差が生まれます。
ここでは、eラーニングパッケージの効果を最大化するための5つの運用術について解説します。これらの方法を取り入れることで、学習者の参加率や修了率、そして何より学習効果を高めることができるでしょう。
効果的な社内周知とラーニングキャンペーンの実施
eラーニングの効果を高めるためには、まず社内での認知度を高め、学習意欲を喚起することが重要です。
導入時には、eラーニング導入の目的や利用方法、期待される効果などを明確に伝える説明会やオリエンテーションを実施しましょう。また、学習を促進するための「ラーニングキャンペーン」も効果的です。
例えば、月間学習テーマの設定や、学習達成者の表彰、部門対抗の学習コンテスト、修了証の発行など、ゲーミフィケーション要素を取り入れた施策が学習のモチベーション向上に役立ちます。
経営層や管理職が率先して学習に取り組む姿勢を見せることも、全社的な学習文化の醸成に大きく貢献します。
学習進捗の可視化と効果測定
eラーニングの効果を最大化するためには、学習進捗の可視化と効果測定が欠かせません。多くのパッケージ型eラーニングシステムには、ダッシュボード機能やレポート機能が搭載されています。これらの機能を活用して、受講率や修了率、テスト結果などのデータを定期的に確認しましょう。
進捗が芳しくない学習者には個別にフォローを行い、全体的に進捗が遅れている場合は運用方法の見直しを検討します。また、学習前後でのスキル評価や業務パフォーマンスの変化を測定することで、eラーニングの実際の効果を把握することができます。これらのデータは、経営層への報告や次年度の教育計画立案にも活用できます。
必須コースとパーソナライズコースを組み合わせる
学習効果を高めるためには、全員が受講すべき「必須コース」と、個々のニーズに応じた「パーソナライズコース」をバランスよく組み合わせることが効果的です。
コンプライアンスや基本的なビジネススキルなど、全社共通の内容は必須コースとして設定し、確実に受講してもらいましょう。
同時に、職種や役職、個人の課題に応じて選択できるコースも用意することで、学習者の自主性や学習意欲を高めることができます。
例えば、四半期ごとに必須コース1つと選択コース2つを設定するなど、計画的かつ柔軟な学習プランを提案することが、継続的な学習習慣の定着につながります。
▼パーソナライズ学習については下記で詳しく解説しています。
⇒パーソナライズ学習とは?進化する人材育成手法について解説!
集合研修と効果的に組み合わせる
eラーニングと集合研修を効果的に組み合わせる「ブレンデッドラーニング」は、それぞれの長所を活かした効果的な学習方法です。
例えば、集合研修の前にeラーニングで基礎知識を学習しておくことで、集合研修では基礎説明を省略し、実践的なワークやディスカッションに多くの時間を割くことができます。
また、集合研修後にeラーニングでフォローアップ学習を行うことで、研修内容の定着を図ることもできます。このようなブレンデッドラーニングを設計する際は、eラーニングと集合研修それぞれの役割を明確にし、内容が重複せず、相互に補完し合う形にすることが重要です。
▼ブレンデッドラーニングについては下記で詳しく解説しています。
⇒ブレンデッドラーニングとは?研修で「行動変容」を生み出す実践手順を解説!
社内トレーナーが運用する
eラーニングパッケージの効果を最大化するためには、社内トレーナーの存在が大きな役割を果たします。
社内トレーナーは、eラーニングの内容と実際の業務をつなぐ架け橋となり、学習した知識やスキルを実践に生かすサポートを行います。そのために、社内トレーナーに、eラーニングの内容を十分に理解してもらい、学習者からの質問に答えられるようにしておくことが重要です。
また、定期的なフォローアップセッションを開催し、eラーニングで学んだ内容の振り返りや実践での活用方法について議論する場を設けることも効果的です。社内トレーナーがいることで、eラーニングが単なる「こなすべき課題」ではなく、実務に直結した意味のある学習になります。
▼社内トレーナーについては下記で詳しく解説しています。
⇒社内トレーナー導入における成功のコツとは?ポイントを解説
パーソナライズ学習でeラーニング受講率100%を達成した事例

支援事例:専門商社(400名)
【これまでの課題】
- eラーニングを「必修」にしなければ学習しない
- 流し見で「完了」することが目的になってしまっている
- 業務が忙しくて受講することを忘れてしまう …など
【受講率100%を実現】
- 「必修」「受講期限」の設定がない中で、受講率100%を実現
- 診断結果基に自動でリコメンドされるコースを自主的に受講
- 1人平均5.7コースの受講(多い人は16コースの受講)
今回のポイント |
|
お客さまの声
eラーニングパッケージのおすすめはCrossKnowledge

eラーニングパッケージのおすすめはCrossKnowledge(クロスナレッジ)です。CrossKnowledgeのeラーニングは、リーダーシップやマネジメントなどを学ぶための効果的な手段として世界中の企業やビジネスパーソンに活用されています。特徴を紹介します。
|
また、企業としても社員のスキルアップを効率的かつ持続的に支援するためのソリューションとして最適です。
具体的には下記のパッケージコースを提供しています。
◆階層別
|
◆目的別
|
▼ 詳しくは下記をご覧ください。
⇒https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning_package
まとめ:自社に最適なパッケージ型eラーニングを選んで教育効果を最大化しよう
本記事では、パッケージ型eラーニングの基本的な特徴から選び方、導入のポイント、そして効果を最大化する運用術まで幅広く解説してきました。
パッケージ型eラーニングは、既に整備された質の高いコンテンツをすぐに活用できる点が最大の魅力です。導入コストと時間の削減、専門家監修の高品質なコンテンツの活用、管理・運用の負担軽減といったメリットがあり、多くの企業において人材育成の効率化に役立っています。
もちろん、自社独自のニーズへの対応やカスタマイズ性に制限があるというデメリットもありますが、集合研修や社内トレーナーとの組み合わせによって補完することが可能です。
パッケージ型eラーニングの選択の際は、自社の教育目的や対象者を明確にし、階層別・目的別・個人別のニーズに合ったパッケージを選ぶことが重要です。そして導入後は、効果的な社内周知、学習進捗の可視化、必須コースとパーソナライズコースの組み合わせなどの運用術を実践することで、その効果を最大限に引き出すことができるでしょう。
人材育成は企業の持続的な成長の源泉です。パッケージ型eラーニングを活用して、効率的かつ効果的な教育体制を構築し、組織全体の能力向上につなげていきましょう。
LDcubeはCrossKnowledge社のパートナーであり、世界中で高い評価を得ているビジネススキルを学ぶための学習コンテンツを提供しています。
また、CrossKnowledgeの提供するCK-Connectを活用することで、パーソナライズ学習を実現することも可能です。パーソナライズ学習は、未来の学習のあり方を変える可能性を秘めています。無料のデモ体験会なども行っていますので、お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。