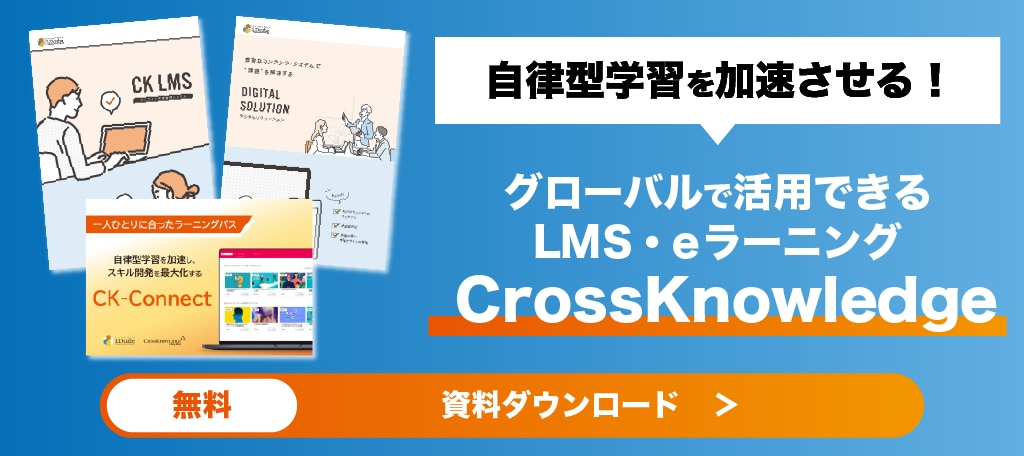企業向けeラーニングシステム完全ガイド|これからの時代の社員教育法を解説!
近年のビジネス環境では、人材育成の効率化と高度化が企業の競争力を左右する重要な要素となっています。その中で注目を集めているのが「企業向けeラーニング」です。
eラーニングとは、インターネットを活用して場所や時間を問わず学習できる環境を提供するシステムであり、従来の集合研修に比べてコスト削減や学習効果の向上といったメリットをもたらします。
2025年現在、テレワークの普及やグローバル化の加速により、企業向けeラーニングの需要はさらに高まっています。しかし、数多くのシステムが存在する中で、自社に最適なものを選定し、効果的に導入・運用するには専門的な知識が必要です。
本記事では、企業向けeラーニングの基礎知識から、システムのタイプ別の特徴、選定ポイント、そして導入から運用までの具体的なステップまでを徹底解説します。さらに、導入時によくある課題とその解決策も紹介し、貴社の人材育成を成功に導くためのガイドとなる情報をお届けします。
eラーニング導入を検討している担当者の方はもちろん、既存システムの見直しを考えている方にも参考になる内容となっています。
▼LMSやeラーニングについてテーマに合わせて以下で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
目次[非表示]
- 1.企業向けeラーニングで人材育成を加速させよう
- 2.企業向けのeラーニングとは?
- 3.企業向けeラーニングシステムの2つのタイプ
- 4.企業に最適なeラーニングの選定ポイント
- 4.1.教材コンテンツの質と量
- 4.2.パッケージコースの有無
- 4.3.パーソナライズ学習の実現
- 4.4.自社に必要な言語対応
- 4.5.学習管理機能と分析機能
- 4.6.マルチデバイス対応とモバイルラーニング
- 4.7.適切なコスト構造と過不足のない料金プラン
- 5.企業向けeラーニング導入の6ステップ
- 5.1.①導入前の課題整理と目標設定
- 5.2.②自社に必要なeラーニングタイプの判別
- 5.3.③教育体系と連動したeラーニング体系の構築
- 5.4.④効果的な学習設計
- 5.5.⑤社内プロモーションと学習意欲を高める仕組みづくり
- 5.6.⑥学習データを活用したラーナーマーケティング
- 6.企業向けeラーニング導入時の留意点
- 6.1.自社に必要なeラーニングタイプを見誤らない
- 6.2.導入目的と効果についての説明を怠らない
- 6.3.経営層を巻き込んだメッセージの発信を行う
- 6.4.eラーニングだけでなく既存研修体系と効果的に組み合わせる
- 7.パーソナライズ学習でeラーニング受講率100%を達成した事例
- 8.eラーニングパッケージのおすすめはCrossKnowledge
- 9.まとめ:企業向けeラーニングで人材育成を効率化・高度化しよう
企業向けeラーニングで人材育成を加速させよう

企業の成長には人材育成が欠かせません。特に近年は働き方の多様化やDX推進により、時間や場所を選ばない学習環境の構築が求められています。そこで注目されているのが、企業向けeラーニングです。
eラーニング・オンライン研修は実は効果が高い
「eラーニングは集合研修に比べて効果が低い」という印象を持つ方もいますが、実はそれは誤解です。eラーニングの特性を生かした設計をすることで、高い学習効果を得ることができます。
eラーニングは学習者のペースで進められるため、理解度に合わせた学習が可能になります。特に反復学習が必要な内容や基礎知識の習得には効果的です。また、動画や音声、テキストなど多様なメディアを組み合わせることで、学習スタイルの異なる社員それぞれに適した学びを提供できます。
さらに、学習データを分析することで、従来の集合研修では把握しづらかった「誰がどの程度理解しているか」を可視化できるため、効果測定や追加フォローも容易になります。
▼研修のデジタル化については下記で詳しく解説しています。
⇒研修のデジタル化で効果を高める方法とは?集合だけでは足りない要素を解説!
学習の利便性向上で人材育成を加速させる
eラーニングの最大の魅力は、学習の利便性が大幅に向上することです。これにより、人材育成のスピードと質を同時に高めることが可能になります。
時間や場所を選ばず学べるという特性は、忙しいビジネスパーソンにとって大きなメリットです。出張中の移動時間や隙間時間を活用して学習できるため、業務への影響を最小限に抑えながら学びを継続できます。また、各拠点に分散している社員に対して、均質な教育機会を提供できる点も見逃せません。
クラウド型のeラーニングシステムであれば、常に最新の教材にアクセスでき、市場の変化や技術の進化に即応した学習内容を提供できます。さらに、学習コンテンツをモジュール化することで、個々の社員のニーズやレベルに応じたカスタマイズが可能になり、より効率的な人材育成を実現できるのです。
企業向けのeラーニングとは?

企業向けeラーニングとは、インターネットを活用して社員教育や研修を行うシステムです。従来の集合研修と比較して、時間や場所の制約を受けにくく、個々の学習進度に合わせた教育を実現します。
eラーニングの基本的な仕組み
eラーニングは主に「教材コンテンツ」と「学習管理システム(LMS)」の2つの要素で構成されています。
教材コンテンツは学習者に提供される学習素材です。テキスト、画像、動画、音声などの形式があり、これらを組み合わせることで効果的な学習体験を提供します。一方、学習管理システム(LMS)は、コンテンツの配信、進捗管理、成績管理などを行うプラットフォームです。
LMSの主な機能には、ユーザー管理、教材の配信、学習進捗の追跡、テスト・アンケートの実施、レポート機能などがあります。これらの機能により、管理者は誰がどの程度学習を進めているかを把握し、適切なフォローアップが可能になります。
個人向けeラーニングとの違い
企業向けeラーニングは、個人向けeラーニングと比較していくつかの特徴的な違いがあります。
最も大きな違いは、管理機能の充実度です。企業向けeラーニングでは、複数の社員の学習状況を一元管理できる機能が必須となります。また、部署や役職ごとに異なる教材を割り当てる機能や、学習データを分析する機能なども備えています。
さらに、セキュリティー面も重視されています。企業の機密情報を含む教材を扱う場合もあるため、アクセス制限やデータ保護の機能が強化されています。コンテンツ面では、ビジネススキルやコンプライアンス、業界特有の専門知識など、企業特有のニーズに対応した教材が提供されています。
企業研修における従来の課題とeラーニング
従来の集合研修では、場所や時間の調整、講師の確保、教材準備など多くの手間とコストがかかっていました。また、拠点が分散している企業では、均質な研修を提供することが難しいという課題もありました。
eラーニングはこれらの課題を解決します。場所や時間を選ばず学習できるため、業務との両立が容易になります。
また、一度作成したコンテンツは繰り返し使用できるため、長期的にはコスト削減につながります。さらに、学習データを分析することで、効果的な教育プログラムの設計も可能になります。
集合研修とeラーニングのコスト比較
集合研修とeラーニングのコスト構造は大きく異なります。集合研修では、会場費、講師料、交通費、宿泊費、教材費などの直接コストに加え、業務時間の損失という間接コストも発生します。
一方、eラーニングでは、システム導入費用とコンテンツ制作費が主なコストとなります。システム導入費用は初期費用と月額利用料に分かれることが多く、コンテンツ制作費は自社で作成するか外部から購入するかによって変動します。
例えば、全国に点在する500人規模の社員に対して1日研修を行う場合、集合研修では会場費、講師料、交通費などを合算すると1千万円を超えるコストが掛かりますが、eラーニングでは数百万円程度で実施できるケースが多いです。さらに、eラーニングでは業務との両立が容易なため、機会損失も最小限に抑えられます。
企業向けeラーニングシステムの2つのタイプ

企業向けeラーニングシステムは、大きく分けて「コンテンツ提供型」と「プラットフォーム型」の2つのタイプに分類できます。自社の状況や目的に合ったタイプを選ぶことが、成功への第一歩となります。
コンテンツ提供型eラーニングシステムの特徴
コンテンツ提供型eラーニングシステムは、豊富な研修コンテンツがあらかじめ用意されており、それらを利用して学習を進めるタイプです。このタイプは「すぐに質の高い研修を始めたい」「自社でコンテンツを作成するリソースがない」企業に適しています。
コンテンツ提供型の中でも、さらに「汎用型」と「特化型」に分けられます。汎用型は階層別研修やビジネススキル、コンプライアンスなど幅広いテーマをカバーしており、多くの企業に共通して必要な研修に対応しています。例えば、新入社員向け基礎研修や管理職研修などが該当します。
一方、特化型は特定の専門分野に特化したコンテンツを提供しています。IT技術やセキュリティー、会計知識など、専門性の高い領域の研修に適しています。特化型は専門知識を持つ講師が監修したコンテンツが多く、最新の業界トレンドや実践的なスキルを学べるというメリットがあります。
コンテンツ提供型の最大のメリットは、質の高いコンテンツをすぐに活用できる点です。特に人事部のリソースが限られている中小企業や、急速に成長しているスタートアップ企業などでは、自社で一から研修コンテンツを作るよりも、既存のコンテンツを活用する方が効率的です。
▼eラーニングコンテンツについては下記で詳しく解説しています。
⇒eラーニングコンテンツの全てがわかる!形式・対象・テーマ別に解説
プラットフォーム型eラーニングシステムの特徴
プラットフォーム型eラーニングシステムは、コンテンツはあまり持たず、自社で用意した教材をオンラインで配信・管理するための環境を提供するタイプです。「自社特有のノウハウやコンテンツがある」「既存の研修資料をオンライン化したい」企業に向いています。
プラットフォーム型の強みは、自社の業務や文化に合わせたカスタマイズが容易な点です。特に「営業ノウハウ」「製品知識」「業務マニュアル」など、自社特有の知識を共有したい場合に効果的です。また、実務に直結した内容を扱うため、学習から実践への移行がスムーズになります。
さらに、プラットフォーム型は社内のナレッジ共有を促進する効果も期待できます。例えば、ベテラン社員のノウハウを動画で記録・共有することで、暗黙知の形式知化が進み、組織全体の知的資産が蓄積されていきます。
自社に最適なタイプを選ぶには、「自社にどのようなコンテンツが必要か」「自社内にコンテンツ制作のリソースがあるか」を考慮することが重要です。また、両タイプのハイブリッドで運用するアプローチも検討価値があります。
▼学習プラットフォームについては下記で詳しく解説しています。
⇒学習プラットフォームで人材育成の効率を高めるには?おすすめ運用方法も解説!
企業に最適なeラーニングの選定ポイント

eラーニングシステムの導入を検討する際は、自社のニーズや状況に合ったものを選ぶことが重要です。以下の7つの選定ポイントを参考に、自社に最適なシステムを見極めましょう。
教材コンテンツの質と量
良質で豊富なコンテンツは、eラーニングの効果を大きく左右します。コンテンツ提供型のeラーニングシステムを選ぶ場合は、特に重視すべきポイントです。
コンテンツの質を評価する際は、講師の専門性、内容の最新性、わかりやすさなどをチェックします。特に対象とする業界や職種に関連した専門的な内容が充実しているかがポイントです。また、動画、テキスト、クイズなどさまざまな形式が組み合わされているかも確認しましょう。
コンテンツの量については、単純に本数が多いことよりも、自社のニーズをカバーする幅広いテーマがあることが重要です。特に成長段階の企業では、将来的に必要となる研修内容も視野に入れて選択するとよいでしょう。
パッケージコースの有無
効率的な人材育成には、体系化された学習コースが有効です。目的別にコンテンツがパッケージ化されているかどうかは重要な選定ポイントになります。
例えば、「新入社員研修」「中堅社員向け」「管理職研修」といった階層別のパッケージや、「マーケティング基礎」「リーダーシップ開発」などの職能別パッケージがあると、研修設計の手間が大幅に削減できます。
また、パッケージコースには学習の順序が最適化されているものが多く、体系的な知識習得を促進します。コース終了後の修了証発行機能があれば、社員のモチベーションアップにもつながります。
▼eラーニングパッケージコースについては下記で詳しく解説しています。
⇒パッケージ型eラーニング活用ガイド|メリットや選び方・おすすめコースを解説!
パーソナライズ学習の実現
社員一人一人のスキルレベルや学習スタイルに合わせた学習体験を提供できるかどうかも重要です。パーソナライズ機能は学習効果とエンゲージメントを高めます。
理想的なシステムでは、事前のパーソナルサーベイの結果に基づいて最適なコンテンツを推奨したり、学習の進捗に応じて次のステップを提案したりする機能があります。また、学習者の行動データを分析して、個人に最適化された学習パスを提供する機能も効果的です。
特に多様なスキルレベルの社員が混在する組織では、一律の研修よりもパーソナライズされた学習環境の方が効率的です。自社の状況に合わせて必要なパーソナライズ機能を見極めましょう。
▼パーソナライズ学習については下記で詳しく解説しています。
⇒パーソナライズ学習とは?進化する人材育成手法について解説!
自社に必要な言語対応
グローバル展開している企業や多国籍の社員がいる企業では、多言語対応は必須条件となります。必要な言語をサポートしているかを確認しましょう。
多言語対応には、インターフェース(メニューやボタン)の多言語化と、コンテンツ自体の多言語化があります。両方に対応しているかを確認することが重要です。特に日本語と英語以外の言語が必要な場合は、対応状況を詳しく確認してください。
また、自動翻訳機能や字幕機能があると、既存コンテンツを多言語展開する際に便利です。将来的な海外展開も視野に入れている場合は、柔軟な言語対応ができるシステムを選びましょう。
▼多言語対応のeラーニングについては下記で詳しく解説しています。
⇒多言語対応eラーニングならCrossKnowledge!ポイントを解説
学習管理機能と分析機能
充実した学習管理機能と分析機能は、eラーニングの効果を最大化し、継続的な改善を可能にします。特に重要なのは以下の機能です。
|
特に、データ分析機能が充実していると、「どの部署の受講率が低いか」「どのコンテンツが効果的か」といった情報に基づいた意思決定ができます。また、人事評価や人材配置にも活用できるデータが得られれば、戦略的な人材育成が可能になります。
▼eラーニングシステム(LMS)の機能一覧については下記で詳しく解説しています。
⇒LMSの機能一覧とは?学習管理システムの詳細内容など解説!
マルチデバイス対応とモバイルラーニング
現代のビジネスパーソンはさまざまなデバイスを使い分けています。PC、スマートフォン、タブレットなど、複数のデバイスに対応したシステムを選ぶことで、学習の機会を最大化できます。
特にスマートフォン対応は重要です。通勤時間や外出先での隙間時間を活用できるため、学習の継続性が高まります。
また、デバイス間での学習進捗の同期機能も確認しましょう。PCで始めた学習をスマートフォンで続けられるなど、シームレスな学習体験が提供できるかがポイントです。
適切なコスト構造と過不足のない料金プラン
eラーニングシステムの料金体系は多様です。自社の予算と利用規模に合った料金プランを選ぶことが重要です。
主な料金モデルには以下があります。
|
初期費用と月額費用のバランスも重要です。初期費用が安くても、長期的に見ると月額費用の積み重ねで総コストが高くなるケースもあります。また、追加機能やカスタマイズにかかる費用も確認しておくとよいでしょう。
コスト評価では、単純な料金の安さだけでなく、得られる価値とのバランスを考慮することが大切です。特に、導入後の運用サポートやコンテンツのアップデート頻度など、継続的なサービス品質も含めて判断しましょう。
▼eラーニングシステム(LMS)の費用については下記で詳しく解説しています。
⇒LMSの費用とは?3つの代表相場と形態・種類・機能による違いを徹底解説
企業向けeラーニング導入の6ステップ

eラーニングシステムを効果的に導入するためには、計画的なアプローチが不可欠です。以下の6つのステップに沿って進めることで、スムーズな導入と高い学習効果を実現しましょう。
①導入前の課題整理と目標設定
eラーニング導入の第一歩は、現状の課題を明確にし、具体的な目標を設定することです。「なぜeラーニングを導入するのか」という根本的な問いに答えることから始めましょう。
まず、自社の人材育成における課題を洗い出します。例えば「研修に参加できない社員が多い」「拠点ごとの教育レベルにばらつきがある」「研修コストが高い」などの課題があるかもしれません。これらの課題をeラーニングでどのように解決できるかを検討します。
次に、eラーニング導入によって達成したい目標を設定します。目標は具体的で測定可能なものが望ましいです。例えば「全社員の受講率を90%以上にする」「特定のスキル習得率を50%向上させる」など、数値化できる目標を設定しましょう。
このステップでは、経営層や現場の声を十分に集め、組織全体の合意形成を図ることが重要です。導入目的が明確になれば、後の選定や設計がスムーズに進みます。
②自社に必要なeラーニングタイプの判別
先に説明したコンテンツ提供型とプラットフォーム型のどちらが自社に適しているか、あるいは両方の要素が必要かを判断します。この選択は導入の成否を左右する重要なポイントです。
判断基準として、以下の点を検討しましょう。
|
例えば、IT企業で技術研修が中心なら特化型のコンテンツ提供型が、製造業で独自の作業手順やノウハウの共有が必要ならプラットフォーム型が適しているかもしれません。自社の状況を踏まえて最適なタイプを選びましょう。
③教育体系と連動したeラーニング体系の構築
eラーニングを単独の施策ではなく、自社の教育体系全体と連動させることが重要です。既存の研修プログラムとの関連性を整理し、一貫した教育体系を構築しましょう。
まず、既存の教育プログラムを棚卸しし、どの部分をeラーニングに移行するか、どの部分は従来の集合研修で行うかを決定します。例えば、知識習得はeラーニングで行い、ディスカッションやロールプレーイングは集合研修で行うといった役割分担が効果的です。
次に、階層別・職種別などの切り口でeラーニングの体系を設計します。新入社員から経営層まで一貫した学習体系があると、キャリアパスに沿った学習が可能になります。また、必須コースとオプションコースを明確に区分することで、効率的な学習を促進できます。
この段階で、学習の評価方法や修了条件なども併せて検討しておくと、後の運用がスムーズになります。
▼教育体系(研修体系)については下記で詳しく解説しています。
⇒理想的な研修体系とは?構築方法やポイントを徹底解説!
④効果的な学習設計
学習効果を高めるためには、eラーニングならではの特性を生かした学習設計が重要です。単に集合研修の内容をオンライン化するだけでは、十分な効果は得られません。
効果的な学習設計のポイントとしては、まず「マイクロラーニング」の活用が挙げられます。5〜15分程度の短いコンテンツに分割することで、集中力を維持しやすく、隙間時間での学習も可能になります。また、インタラクティブな要素(クイズ、ショートケーススタディー等)を取り入れることで、受動的な視聴から能動的な学習へと変化させることができます。
さらに、「ブレンド学習」の設計も重要です。eラーニングと集合研修、オンライン会議、実務での実践などを組み合わせることで、知識の定着と応用力の向上が期待できます。例えば、基礎知識をeラーニングで学び、その後のオンラインディスカッションで理解を深め、最後に実務で応用するといった流れです。
学習設計では、定期的な復習の機会や、学んだ内容を実践する場も意識的に設けることが効果を高めるポイントとなります。
▼学習設計(研修設計)やブレンデッドラーニングについては下記で詳しく解説しています。
⑤社内プロモーションと学習意欲を高める仕組みづくり
いかに優れたeラーニングシステムを導入しても、社員が積極的に利用しなければ効果は限定的です。導入成功の鍵は、社内での適切なプロモーションと学習意欲を高める仕組みづくりにあります。
効果的な社内プロモーションには、以下のような取り組みが有効です。
|
また、学習意欲を高める仕組みとしては、学習の「見える化」が効果的です。進捗度や取得ポイントがわかるダッシュボードの提供や、学習成果に応じたバッジやランキングの導入などがあります。
さらに、学習成果と人事評価の連動や、特定のコース修了者への特典付与なども、継続的な学習のモチベーション向上に役立ちます。
重要なのは、単なる「やらされ感」ではなく、学習が自己成長や業務改善につながるという実感を持ってもらうことです。
⑥学習データを活用したラーナーマーケティング
eラーニングの大きなメリットの1つは、詳細な学習データが取得できることです。これらのデータを活用した「ラーナーマーケティング」は、継続的な改善と効果最大化に不可欠です。
ラーナーマーケティングとは、学習者の行動データを分析し、より効果的な学習体験を提供するためのアプローチです。例えば、以下のような分析と活用が考えられます。
|
データ分析の結果は、定期的なレポートとして関係者に共有し、PDCAサイクルを回していくことが重要です。また、分析結果に基づいて個別フォローを行うことで、脱落者を減らし、全体の学習効果を高めることができます。
ラーナーマーケティングの目的は単なる利用率向上ではなく、真の学習効果と業績向上につなげることです。データを「人材育成の質を高めるための情報」として戦略的に活用しましょう。
企業向けeラーニング導入時の留意点

eラーニングを導入する際には、いくつかの重要な留意点があります。これらのポイントを事前に把握し対策を講じることで、導入の失敗リスクを大幅に低減できます。
自社に必要なeラーニングタイプを見誤らない
多くの企業がeラーニング導入に失敗する原因の一つは、自社のニーズに合わないタイプのシステムを選んでしまうことです。前述したコンテンツ提供型とプラットフォーム型の特性をよく理解し、自社の状況に合ったものを選びましょう。
例えば、自社独自のノウハウを教育したいにもかかわらず、コンテンツ提供型のみを導入すると、結局使われないシステムになってしまう可能性があります。逆に、基本的なビジネススキル研修が目的なのに、何もコンテンツがないプラットフォームだけを導入しても効果は限定的です。
選定前には、複数のサービスの無料トライアルを活用するなどして、実際の使用感を確かめることをおすすめします。また、同業他社の導入事例があれば参考にするのも有効です。
導入目的と効果についての説明を怠らない
eラーニングの導入目的と期待される効果を社内に明確に伝えることは極めて重要です。「なぜeラーニングを導入するのか」「どのような効果が期待できるのか」を丁寧に説明しなければ、社員は単なる「新しいシステムの押し付け」と捉えてしまいます。
特に、従来の集合研修に慣れている社員からは「顔を合わせない研修で効果があるのか」といった懸念の声が上がることもあります。こうした懸念に対しては、eラーニングならではのメリット(時間や場所を選ばない、自分のペースで学べる、繰り返し学習できるなど)を具体的に説明することが大切です。
また、eラーニングは「研修コストの削減」という側面もありますが、それだけを強調すると「質よりコストを優先している」という誤ったメッセージになりかねません。あくまで「より効果的な学習環境の提供」が目的であることを伝えましょう。
経営層を巻き込んだメッセージの発信を行う
eラーニング導入の成功には、経営層の理解と支援が不可欠です。経営層自らがeラーニングの意義や重要性を発信することで、組織全体の受け入れ姿勢が大きく変わります。
具体的には、導入時に経営層からのメッセージ動画をeラーニングシステム内に掲載したり、全社会議で学習の重要性について言及したりする方法があります。また、経営層自身がeラーニングを率先して受講する姿勢を見せることも効果的です。
経営層の発信では、eラーニングが会社の成長戦略や人材育成方針とどのように関連しているかを明確にすることが重要です。学習が単なる「やるべきこと」ではなく、個人と組織の成長につながる価値ある活動であるというメッセージを伝えましょう。
eラーニングだけでなく既存研修体系と効果的に組み合わせる
eラーニングは万能ではありません。既存の研修体系と適切に組み合わせることで、相乗効果を生み出すことが重要です。この「ブレンデッドラーニング」のアプローチは、単一の手法だけでは達成できない学習効果をもたらします。
例えば、知識のインプットはeラーニングで行い、グループディスカッションやロールプレーイングといった相互作用が必要な内容は集合研修で行うといった役割分担が効果的です。また、eラーニングで学んだ内容を実務で実践し、その後のフォローアップ研修で振り返るといったサイクルも学習の定着に有効です。
重要なのは、eラーニングを「研修の代替手段」ではなく「研修を補完・強化するツール」として位置付けることです。両者の強みを生かした総合的な学習環境を設計することで、真の意味で人材育成の高度化を実現することができます。
▼研修体系については下記で詳しく解説しています。
⇒理想的な研修体系とは?構築方法やポイントを徹底解説!
パーソナライズ学習でeラーニング受講率100%を達成した事例

支援事例:専門商社(400名)
【これまでの課題】
- eラーニングを「必修」にしなければ学習しない
- 流し見で「完了」することが目的になってしまっている
- 業務が忙しくて受講することを忘れてしまう ・・・など
【受講率100%を実現】
- 「必修」「受講期限」の設定がない中で、受講率100%を実現
- 診断結果基に自動でリコメンドされるコースを自主的に受講
- 1人平均5.7コースの受講(多い人は16コースの受講)
今回のポイント |
|
お客さまの声
eラーニングパッケージのおすすめはCrossKnowledge

eラーニングパッケージのおすすめはCrossKnowledge(クロスナレッジ)です。CrossKnowledgeのeラーニングは、リーダーシップやマネジメントなどを学ぶための効果的な手段として世界中の企業やビジネスパーソンに活用されています。特徴を紹介します。
|
CrossKnowledgeのeラーニングはコンテンツ提供型eラーニングでもあり、自社独自のコンテンツを搭載して展開するプラットフォーム型でもあります。企業としても社員のスキルアップを効率的かつ持続的に支援するためのソリューションとして最適です。
具体的には下記のパッケージコースを提供しています。
◆階層別
|
◆目的別
|
▼ 詳しくは下記をご覧ください。
まとめ:企業向けeラーニングで人材育成を効率化・高度化しよう
企業向けeラーニングシステム完全ガイド|これからの時代の社員教育法を解説!について紹介してきました。
企業向けeラーニングは、単なる研修のオンライン化ではなく、人材育成の効率化と高度化を実現する戦略的なツールです。
本記事で解説したように、eラーニングには「時間や場所を選ばない学習環境の提供」「コスト効率の向上」「データに基づく効果測定と改善」など、従来の研修方法にはない多くのメリットがあります。
導入にあたっては、自社のニーズと状況を踏まえた適切なシステム選定が重要です。コンテンツ提供型とプラットフォーム型のどちらが適しているか、あるいはハイブリッド型が必要かを見極め、教材コンテンツの質や量、学習管理機能、マルチデバイス対応など、さまざまな選定ポイントを総合的に検討しましょう。
また、導入から運用までの各ステップを計画的に進めることで、スムーズな導入と高い学習効果を実現できます。特に、社内プロモーションと学習意欲を高める仕組みづくりは成功の鍵となります。経営層の巻き込みや既存研修との効果的な組み合わせも忘れてはならないポイントです。
変化の激しい現代においては、eラーニングを適切に導入・運用することが、人材育成の強力な基盤となります。自社の成長戦略と連動させながら、学びの文化を育む環境として活用していきましょう。
株式会社LDcubeはCrossKnowledge社のパートナーであり、世界中で高い評価を得ているビジネススキルを学ぶための学習コンテンツを提供しています。
また、CrossKnowledgeの提供するCK-Connectを活用することで、パーソナライズ学習を実現することも可能です。パーソナライズ学習は、未来の学習のあり方を変える可能性を秘めています。無料のデモ体験会なども行っていますので、お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。