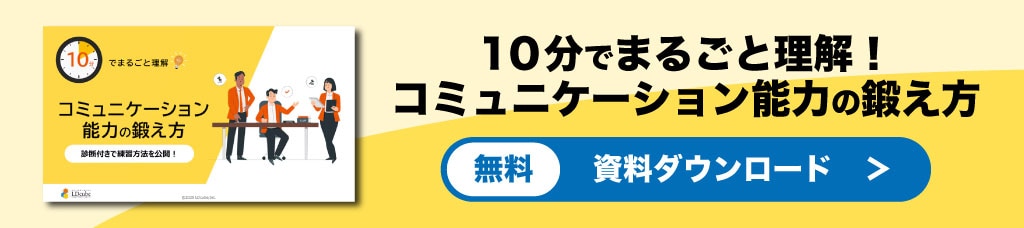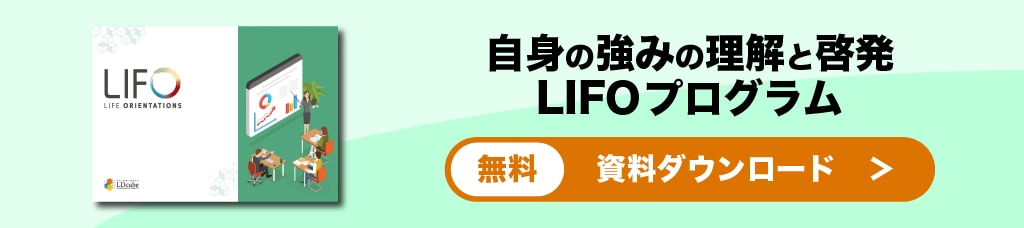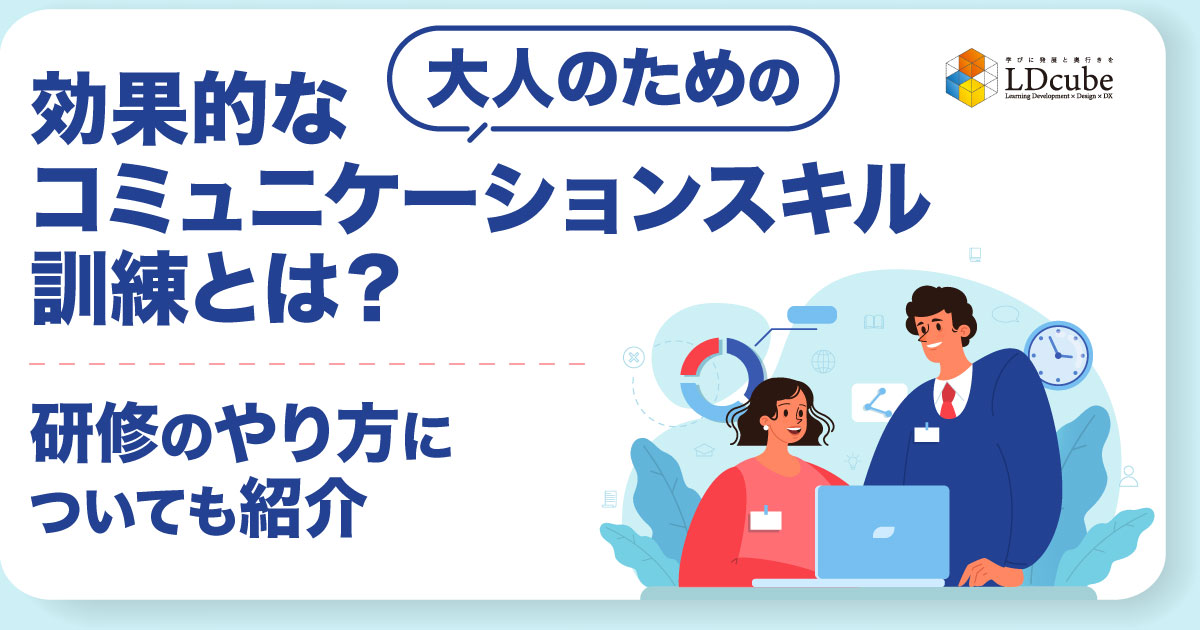
大人のための効果的なコミュニケーション能力の訓練とは?研修のやり方についても紹介
「もっとうまく自分の考えを伝えられたら」
「相手の話をちゃんと理解できていないかも」
「会議で発言できずにいつも後悔している」
このような悩みを抱える大人は決して少なくありません。社会人になってからコミュニケーションの難しさを実感する方は多く、特に仕事の場面では高度なコミュニケーション能力が求められます。
しかし、大人になってからでもコミュニケーション能力は確実に向上させることができます。それには適切な「訓練」が鍵となります。子どもの頃とは異なり、大人は経験や知識を持っているため、効果的な訓練法を実践すれば目に見える成果を上げることが可能です。
本記事では、大人のためのコミュニケーション訓練に焦点を当て、職場や日常生活ですぐに活用できる、実践的な7つの訓練法をご紹介します。聴く力、伝える力、相手の視点に立つなど、コミュニケーションのさまざまな側面を強化するための具体的な方法を解説します。
また、コミュニケーションスキルの向上には、日頃の訓練だけでなく、コミュニケーション研修を実施することが手っ取り早いです。階層別、職場単位での研修実施方法などについても解説します。
コミュニケーション能力は一朝一夕に身に付くものではありませんが、正しい方法で継続的に訓練することで、必ず向上します。この記事を通じて、あなたのコミュニケーション能力を次のレベルへと引き上げるお手伝いをします。
▼コミュニケーションについては下記で詳しく解説しています。
▼コミュニケーションのベースは自己理解です。
目次[非表示]
- 1.コミュニケーション訓練とは?大人が基本から学ぶべき重要性
- 2.大人がコミュニケーションを訓練するメリット
- 3.コミュニケーション訓練に取り組む際の大人の自己分析法
- 4.訓練になる大人向けコミュニケーション実践法7選
- 4.1.アクティブリスニング(積極的傾聴)
- 4.2.オープンクエスチョン
- 4.3.つなぎ言葉
- 4.4.PREP法(プレップ法)
- 4.5.ミラーリング
- 4.6.アサーティブコミュニケーション
- 4.7.視点取得
- 5.大人がコミュニケーション訓練を習慣化する方法
- 6.大人のコミュニケーション訓練で手っ取り早いのは研修
- 7.コミュニケーション研修ならLIFO®がおすすめ!
- 8.LIFOでコミュニケーション研修を展開した支援事例(日本新薬株式会社)
- 9.まとめ:コミュニケーション訓練で大人の社会的能力を高める方法
コミュニケーション訓練とは?大人が基本から学ぶべき重要性
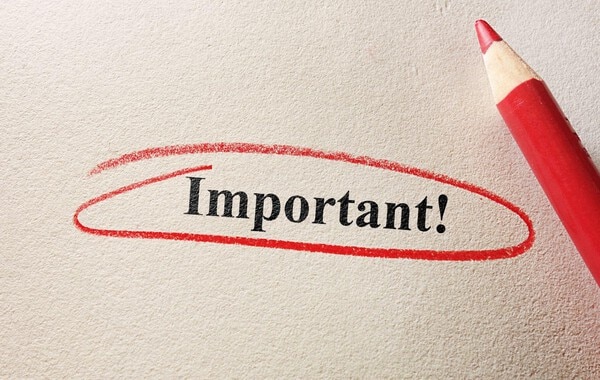
コミュニケーション訓練とは、対人関係や社会生活を円滑に営むために必要なスキルを意識的に学び、練習することです。
特に社会人として働く環境では、高度なコミュニケーション能力が求められるため、大人になってからでも体系的に学ぶ価値があります。
社会人に必要なコミュニケーション能力の実態
現代の職場環境では、専門的なスキルと同じくらいコミュニケーション能力が重視されています。企業が新入社員に求める能力のトップにコミュニケーション能力が挙げられることが多く、技術や知識よりも優先されることもあります。
職場では具体的に次のようなコミュニケーション能力が求められています。
|
こうした能力が不足していると、仕事の効率低下、人間関係のトラブル、さらには心理的ストレスの原因になることもあります。
特に専門性が高い職種ほど、専門知識を相手に分かりやすく伝える能力が重要になってきます。
大人になってからのコミュニケーション習得の特徴と可能性
「コミュニケーション能力は生まれつきの才能」と思われがちですが、実際には適切な訓練方法さえあれば、大人になってからでも十分に習得可能なスキルです。むしろ、大人の学習には以下のような特徴があります。
大人のコミュニケーション学習の特徴として、目的意識が明確であること、実践的な経験を既に持っていること、自己分析能力が高いことなどが挙げられます。これらの特徴を生かすことで、効率的に学習を進めることができます。
また、大人の学習は「認知的アプローチ」と「行動的アプローチ」を組み合わせることで効果が高まります。つまり、コミュニケーションの原理を理解する知識面の学習と、実際に練習して身に付ける実践面の訓練を並行して行うことが重要です。
大人の場合、自分の課題を自覚していることが多いため、ピンポイントで訓練することも可能です。例えば、「会議での発言が苦手」「上司への報告がうまくできない」など、具体的な課題に対して効果的な訓練法を選ぶことができます。
コミュニケーション訓練がもたらす仕事と人間関係への効果
適切なコミュニケーション訓練を継続的に行うことで、仕事と人間関係の両面で大きな効果が期待できます。
仕事面では、情報の伝達ミスが減少し、業務効率が向上します。特にチームでの協働作業がスムーズになり、プロジェクトの成功率も高まります。また、顧客やクライアントとのやり取りも円滑になるため、ビジネスチャンスの拡大にもつながります。
人間関係面では、誤解やトラブルが減少し、職場の人間関係が改善します。自分の意図を正確に伝えられるようになるだけでなく、相手の立場や気持ちを理解する力も高まるため、信頼関係の構築にも役立ちます。
コミュニケーション訓練は、単なるビジネススキルの向上だけでなく、人生の質を高める重要な取り組みだといえるでしょう。次章では、具体的にどのようなメリットがあるのかを詳しく見ていきます。
大人がコミュニケーションを訓練するメリット

コミュニケーション訓練は、大人にとって単なる対人スキルの向上だけでなく、職業人生に大きな影響をもたらします。ここでは、大人がコミュニケーション訓練に取り組むことで得られる具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。
スキルアップにつながる
コミュニケーション訓練は、実は多くの仕事に関連するスキルの基盤となります。効果的なコミュニケーション能力を身に付けることで、以下のようなスキルが総合的に向上します。
まず、相手の話を正確に理解する「傾聴スキル」が向上することで、指示の見落としやミスが減少します。また、自分の考えを論理的に整理して伝える「プレゼンテーションスキル」も磨かれるため、会議や商談での説得力が増します。
さらに、チームメンバーとの関係構築に必要な「対人関係スキル」や、問題が発生した際に建設的に対処する「交渉・調整スキル」も同時に向上するため、複雑な人間関係の中でも円滑に業務を進められるようになります。
これらのスキルは単独で身に付けようとすると大変ですが、コミュニケーション訓練を通して体系的に学ぶことで、効率的にスキルアップを図ることができます。
仕事力が向上し、生産性が高まる
コミュニケーション能力の向上は、日々の業務パフォーマンスに直接的な影響をもたらします。コミュニケーションが円滑になることで、チーム内での情報共有がスムーズになり、業務の重複や手戻りが減少します。
具体的には、報告・連絡・相談(ホウレンソウ)の質が向上することで、上司や同僚との認識のズレが少なくなります。また、質問や依頼を適切に行えるようになることで、必要な情報やサポートを効率的に得られるようになります。
このように、コミュニケーション訓練は業務効率を高め、結果として個人とチーム全体の生産性向上に貢献します。
キャリアアップにつながる
優れたコミュニケーション能力は、キャリア形成においても大きなアドバンテージとなります。多くの企業では、管理職や上級ポジションへの昇進において、専門スキルだけでなくコミュニケーション能力も重要な評価基準となっています。
リーダーシップを発揮するためには、チームメンバーとの信頼関係構築や、ビジョンの共有、適切なフィードバックの提供などが不可欠です。これらは全て高度なコミュニケーションスキルに基づいています。コミュニケーション訓練を通じてこれらのスキルを磨くことで、リーダーとしての資質を高めることができます。
転職や面接の場面でも、自分の強みや実績を効果的に伝えられる人は有利です。コミュニケーション訓練によって培われたスキルは、キャリアの節目においても大きな武器となるでしょう。
コミュニケーション訓練に取り組む際の大人の自己分析法

コミュニケーション訓練を効果的に進めるためには、まず自分のコミュニケーションスタイルや課題を正確に把握することが重要です。大人の場合、長年の経験から無意識に形成された習慣やパターンがあるため、客観的な自己分析が訓練の第一歩となります。
ここでは、コミュニケーション訓練に取り組む際に役立つ自己分析の方法を紹介します。これらの方法を組み合わせることで、より効果的な訓練計画を立てることができるでしょう。
自分で振り返る
自己分析の基本は、これまでのコミュニケーション経験を振り返ることです。具体的な方法としては、日常のコミュニケーションで感じた違和感や苦手意識を書き出してみましょう。
例えば、「会議で発言するとき緊張する」「初対面の人との会話が続かない」「自分の意見をはっきり言えない」など、具体的な場面や状況とともに記録します。また、うまくいったコミュニケーションの例も同様に振り返ることで、自分の強みを把握することができます。
この振り返りでは、以下のポイントに注目するとより効果的です。
|
こうした構造化された振り返りを通じて、自分のコミュニケーションパターンを客観的に把握することができます。
他者から指摘をもらう
自己分析だけでは気付かない課題もあるため、信頼できる他者からのフィードバックを得ることも重要です。同僚、上司、家族や友人など、あなたのコミュニケーションスタイルをよく知る人に率直な意見を求めましょう。
フィードバックを求める際には、「私のコミュニケーションで改善すべき点はありますか?」といった漠然とした質問ではなく、「会議での私の発言は明確で分かりやすいですか?」「報告の際に不足している情報はありますか?」など、具体的な質問をすることがポイントです。
また、フィードバックをもらう際には、防衛的にならず、オープンな姿勢で聞くことが大切です。批判ではなく、成長のための貴重な情報として受け止めましょう。もらったフィードバックは記録しておき、定期的に見直すことで、自分の変化や成長を確認することができます。
自己診断ツールを活用する
客観的な自己分析を行うために、コミュニケーションスタイルの自己診断ツールを活用する方法もあります。現在はオンラインで利用できるさまざまな診断ツールがあり、自分のコミュニケーションの特徴を数値化して把握することができます。
代表的なコミュニケーションスタイル診断には、「LIFO」「DiSC」などがあります。これらの診断ツールを使うことで、自分のコミュニケーションスタイルの傾向や、強み・弱みを客観的に把握することができます。
診断結果を参考にすることで、「直接的な表現を好む」「データを重視した論理的なやり取りが苦手」などの特徴が分かり、重点的に訓練すべき領域が明確になります。ただし、診断結果はあくまで参考として捉え、自分自身の経験や感覚とも照らし合わせながら総合的に判断することが大切です。
▼LIFOについては下記をご覧ください。
⇒LIFO|LDcube
課題を明確にする
自己の振り返り、他者からのフィードバック、自己診断ツールの結果を基に、自分のコミュニケーション上の課題を具体的に明確化します。この段階では、「コミュニケーションが苦手」といった漠然とした認識から、より具体的な課題へと落とし込むことが重要です。
例えば、「話す速度が速すぎる」「話す内容が詳細すぎて、要点が伝わりにくい」「相手の話を最後まで聞かずに割り込んでしまう」など、具体的な行動レベルで課題を特定します。
また、課題を明確にする際は、「いつ」「どのような状況で」「どのように」という観点も含めると、より具体的な改善策が考えやすくなります。
課題が明確になったら、課題に優先順位をつけて整理しましょう。全ての課題を一度に解決しようとするのではなく、影響の大きい課題や比較的改善しやすい課題から取り組むことで、効率的な訓練が可能になります。
日々意識して訓練する
自己分析によって明確になった課題は、日常生活の中で意識的に訓練することが重要です。課題に対応した具体的な訓練計画を立て、継続的に実践していきましょう。
例えば、「聴く力を高める」という課題に対しては、日常会話の中で意識的に相手の話に集中し、要点をメモしたり、質問したりする練習をします。「簡潔に話す」という課題には、事前に話す内容の要点をまとめる習慣をつけるといった訓練方法があります。
訓練を継続するためには、以下のポイントを意識すると効果的です。
|
自己分析と訓練を繰り返すことで、自分のコミュニケーションスタイルを客観的に把握し、効果的に改善していくことができます。
▼プチ診断を通じて、コミュニケーション上の課題やトレーニング方法を疑似体験できます。
⇒【プチ診断付き】人間関係で疲れた方へ/少し気が楽になる捉え方のコツ!
訓練になる大人向けコミュニケーション実践法7選

自己分析によって課題が明確になったら、具体的な訓練に取り組みましょう。ここでは、大人のコミュニケーション能力を効果的に高める実践的なトレーニング法を7つ紹介します。
これらは日常生活やビジネスシーンですぐに活用でき、継続的に取り組むことで着実にスキルアップが期待できます。自分の課題や目標に合わせて、取り入れやすいものから始めてみましょう。
アクティブリスニング(積極的傾聴)
アクティブリスニングとは、単に相手の話を聞くだけでなく、積極的に理解しようとする聴き方です。コミュニケーションの基本となる重要なスキルで、相手の話を正確に理解するだけでなく、「しっかり聞いてもらえている」という安心感を相手に与えることができます。
アクティブリスニングの実践ポイントは以下の通りです。
|
このスキルは特に、上司からの指示を正確に理解したい場面や、顧客のニーズを把握したい場面で効果を発揮します。日常会話の中で意識して実践することで、徐々に身に付いていきます。
オープンクエスチョン
オープンクエスチョンとは、「はい」「いいえ」では答えられない、相手に考えや感情を自由に表現してもらうための質問技法です。「何」「どのように」「なぜ」などで始まる質問がこれにあたります。
この技法を使うことで、会話が広がり、相手からより多くの情報や本音を引き出すことができます。特にビジネスシーンでは、相手のニーズや懸念点を探る際に非常に有効です。
オープンクエスチョンの例としては、「この提案についてどう思いますか?」「その問題についてもう少し詳しく教えていただけますか?」などがあります。閉じた質問(「この提案は良いですか?」)に比べて、より豊かな情報を得られるでしょう。
日常会話や会議の中で意識的にオープンクエスチョンを増やしていくことで、コミュニケーションの質を高めることができます。
つなぎ言葉
つなぎ言葉とは、会話をスムーズに進行させるための短いフレーズや表現のことです。「なるほど」「それで」「ところで」などの言葉を適切に使うことで、会話の流れを整え、相手に心地よい印象を与えることができます。
つなぎ言葉は特に以下のような場面で使うと効果的です。
|
つなぎ言葉を意識的に使うことで、会話が途切れにくくなり、円滑なコミュニケーションが可能になります。特に初対面の人との会話や、緊張する場面でのコミュニケーションでは、このスキルが役立ちます。
PREP法(プレップ法)
PREP法は、「Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(結論の再確認)」という構造で話を組み立てる方法です。特にビジネスシーンで自分の意見や提案を論理的かつ説得力を持って伝えたい場合に効果的です。
例えば、「業務効率化のためにこのツールを導入すべきだ」という提案をする場合、以下のように組み立てます。
|
この構造で話すことで、聞き手は要点を理解しやすくなり、説得力も増します。プレゼンテーションやミーティングでの発言、提案書の作成など、さまざまな場面で活用できます。
ミラーリング
ミラーリングとは、相手の言葉遣いや話し方、姿勢などを自然に模倣することで、無意識のうちに相手との親和性を高める技法です。
相手と同じような言葉を使ったり、似たようなペースで話したりすることで、相手に「この人は自分と波長が合う」という感覚を持ってもらうことができます。
具体的なミラーリングの実践法には以下のようなものがあります。
|
ただし、あからさまに模倣すると不自然に感じられるため、自然な範囲で取り入れることが重要です。営業や交渉の場面で特に効果を発揮しますが、日常会話でも実践することで、より円滑な人間関係を築くことができます。
アサーティブコミュニケーション
アサーティブコミュニケーションとは、自分の権利や意見を尊重しながらも、相手の権利や意見も同様に尊重する、バランスの取れたコミュニケーション方法です。攻撃的でも受け身でもなく、適切に自己主張することが特徴です。
アサーティブなコミュニケーションでは、「私は~と思います」「私は~を希望します」というように、「I(私)」を主語にしたメッセージ(アイメッセージ)を使うことがポイントです。これにより、相手を非難せずに自分の考えや感情を伝えることができます。
例えば、「あなたはいつも締め切りを守らない」(攻撃的)ではなく、「締め切りが守られないと私は困ります。どうすれば期限内に完成できるか一緒に考えましょう」(アサーティブ)というように伝えます。
職場での意見の対立や、断りにくい依頼への対応など、さまざまな場面で役立つスキルです。
視点取得
視点取得とは、相手の立場に立って物事を考える能力のことです。相手の背景、価値観、感情を理解しようとすることで、より深いコミュニケーションが可能になります。
視点取得力を高めるためには、以下のような訓練が効果的です。
|
このスキルは特に、意見の対立がある場面や、異なる部門間のコミュニケーション、顧客対応などで重要です。相手の視点を理解することで、より適切な対応や提案ができるようになり、結果として信頼関係の構築につながります。
大人がコミュニケーション訓練を習慣化する方法

コミュニケーション技術を身に付けるためには、一度や二度の研修や学習だけでは不十分です。真のスキルとして定着させるには、日常的な習慣として継続的に訓練を行うことが欠かせません。
特に大人の場合、長年の習慣を変えることは容易ではないため、無理なく続けられる方法を工夫する必要があります。ここでは、コミュニケーション訓練を日常に組み込み、習慣化するための具体的な方法を紹介します。
毎日5分から始める継続可能なトレーニングルーティン
コミュニケーション訓練を習慣化する最も効果的な方法は、「小さく始めて、確実に継続する」ことです。まずは毎日5分程度の簡単なトレーニングから始めましょう。短時間であれば、どれだけ忙しい日でも実行することができます。
具体的なトレーニングルーティンの例として、以下のようなものが考えられます。
|
このような短いルーティンを毎日続けることで、コミュニケーションへの意識が自然と高まります。また、習慣化を促進するために、既存の習慣とひも付けるのも効果的です。
例えば、「コーヒーを飲みながらトレーニング計画を立てる」「歯磨きをしながら今日の振り返りをする」など、日常の行動とセットにすることで忘れにくくなります。
日記をつける
コミュニケーション日記をつけることは、自分の成長を可視化し、訓練を継続するモチベーションを維持するのに役立ちます。複雑な記録は続かないため、シンプルな形式で記録することがポイントです。
効果的なコミュニケーション日記には、以下のような項目を含めると良いでしょう。
|
日記は紙のノートでも、スマートフォンのアプリでも、自分が続けやすい方法で構いません。重要なのは定期的に記録し、振り返ることです。記録を積み重ねることで、自分のコミュニケーションパターンや成長過程が明確になり、さらなる改善につながります。
また、感情の変化も併せて記録することで、特定のコミュニケーション場面での感情反応に気付きやすくなります。例えば「会議で発言するときの緊張度合いが50%だった」というように数値化すると、時間の経過とともに変化を追いやすくなるでしょう。
1週間や1カ月単位で振り返る場を設定しておく
日々の小さな実践に加えて、定期的に大きな振り返りを行うことも重要です。
週に一度、または月に一度、自分のコミュニケーション訓練の成果を総合的に振り返る時間を設けましょう。この時間を予定表に入れておくことで、確実に実行できます。
定期的に振り返りを行う際には、以下のポイントを確認すると効果的です。
|
この振り返りは1人で行うこともできますが、信頼できる同僚や友人、メンターなどと一緒に行うとさらに効果的です。外部からのフィードバックを得ることで、自分では気付かない点に気付くことができます。
また、3カ月、半年、1年といった長いスパンでの振り返りも定期的に行うことで、自分のコミュニケーションスキルの成長を実感することができます。長期的な成果を感じることは、モチベーション維持に大きく貢献します。
このように、短期・中期・長期の振り返りを組み合わせることで、コミュニケーション訓練を確実に習慣化し、継続的な成長につなげることができるでしょう。
大人のコミュニケーション訓練で手っ取り早いのは研修

ここまで紹介してきた自己学習型のコミュニケーション訓練は、継続的な成長には欠かせませんが、体系的かつ効率的にスキルを習得するなら、専門家が設計した研修プログラムを受けることが最も手っ取り早い方法といえます。
研修では、専門的な知識を持ったトレーナーのもと、効果的な演習やフィードバックを通して、短期間で集中的にスキルを学ぶことができます。ここでは、企業などでよく実施されているコミュニケーション研修の形態とその特徴について解説します。
階層別でのコミュニケーション研修
階層別研修とは、職位や役職に応じて必要なコミュニケーションスキルを学ぶ研修形式です。新入社員、中堅社員、管理職など、それぞれの立場で求められるコミュニケーション能力は異なるため、階層ごとに最適化されたカリキュラムが組まれます。
新入社員向けの研修では、ビジネスマナーの基本や報告・連絡・相談(ホウレンソウ)の方法、基本的な会話スキルなどが中心となります。
中堅社員向けでは、後輩への指導法や効果的なフィードバックの伝え方、チーム内のコミュニケーション活性化などが重視されます。
管理職向けには、部下の育成に関するコミュニケーション、部門間の連携を促す交渉術、組織の方針を伝えるための説明力などが含まれます。
階層別研修の特徴は、同じ立場の参加者が集まるため、共通の課題や悩みを共有しやすく、実践的な学びが得られる点です。また、次のステップに必要なスキルを先取りして学べるため、キャリアアップの準備としても有効です。
研修では通常、講義だけでなく、ロールプレーイングやグループディスカッション、ケーススタディーなどの参加型学習が取り入れられ、実践的なスキルを身に付けることができます。
職場単位でのコミュニケーション研修
職場単位の研修は、同じ部署やチームのメンバー全員が一緒に受講する形式です。この研修の最大の特徴は、日常的にコミュニケーションを取る相手と一緒に学べる点で、チーム全体のコミュニケーション文化を改善するのに効果的です。
職場単位の研修では、チーム内の課題や目標に合わせてカスタマイズされたプログラムが提供されることが多く、例えば「会議の活性化」「部門間連携の強化」「顧客対応の改善」など、具体的なテーマに焦点を当てた内容になります。
研修の中では、チーム内のコミュニケーション上の課題を題材にしたワークショップや、メンバー間のコミュニケーションスタイルの違いを理解するアクティビティなどが行われます。これにより、お互いの特性や考え方の違いを尊重しながら、より効果的に協働するための基盤を作ることができます。
また、職場単位の研修では、研修後も同じ環境で学んだことを実践し続けられるため、研修効果の持続性が高いというメリットもあります。チーム全体が同じ言語や概念を共有することで、日常的なコミュニケーションの改善につながります。
階層別研修と職場単位での研修効果の違い
階層別研修と職場単位での研修はそれぞれ異なる効果があり、目的に応じて選択することが重要です。
階層別研修の主な効果は以下の通りです。
|
一方、職場単位での研修の効果には次のようなものがあります。
|
両方の研修をバランスよく取り入れて、個人のスキルアップとチーム全体のコミュニケーション改善の両方を達成することが理想的です。
例えば、年に1度は階層別研修で基本スキルを学び、半年に1度は職場単位で具体的な課題解決に取り組むといった組み合わせが効果的です。
自己学習と研修を組み合わせることで、コミュニケーションスキルの総合的な向上が可能になるでしょう。
コミュニケーション研修ならLIFO®がおすすめ!

組織内コミュニケーションの活性化には自己診断ツールLIFO(Life Orientations)を活用した職場単位でのワークショップがおすすめです。
なぜなら、LIFOプログラムは心理学や行動科学をベースにして組み立てられた行動特性診断をベースに、職場単位でワークショップを行うためのワークブックなどのツールも体系的にそろえられているからです。
また、体系立てられたツールの使い方を社内トレーナーの方々にライセンス提供もされており、社内トレーナーの方々が職場単位でワークショップを展開していくことも可能です。下記に概要を紹介します。
自己診断ツールLIFOとは
LIFO(Life Orientations)は、個人の行動スタイルを診断する自己診断ツールです。このツールは、自分の強みや行動パターンを理解するために役立ちます。
LIFOは4つの基本スタイルに基づいており、これらのスタイルはそれぞれ異なる行動特性や価値観を持っています。
自分がどのスタイルに属しているかを知ることで、より良いコミュニケーション方法やストレス時の行動傾向を把握することができます。
LIFOを活用したコミュニケーション研修
LIFOを活用したコミュニケーション研修では、まず参加者が自己診断を行い、自分の行動スタイルを理解します。
この診断結果を基に、どのようにして他者と効果的にコミュニケーションを取るかを学びます。
研修では以下のような内容が含まれます。
|
LIFO®プログラムは社内トレーナーで展開可能
LIFO®プログラムは、これまでの活用実績と実用性から、企業内でのトレーニングにおいて自信を持っておすすめできるプログラムです。
社内展開にあたっては、特定の準備と手続きを経ることで、コストを抑えながら、外部講師に委託したかのように、社内トレーナーによる効果的なプログラムを展開することが可能です。
以下に、その流れを詳しく説明します。
|
LIFOでコミュニケーション研修を展開した支援事例(日本新薬株式会社)
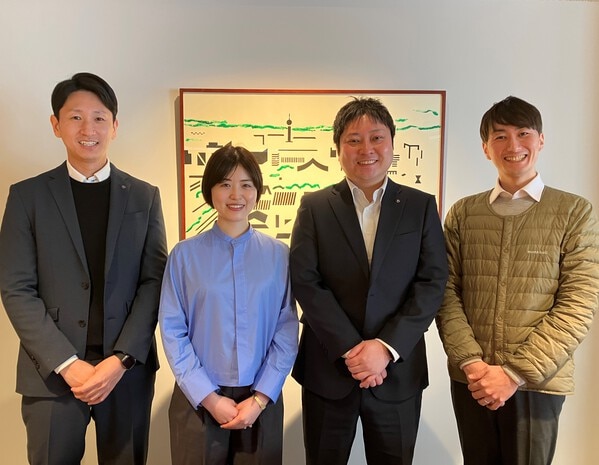
日本新薬株式会社/医薬品・機能食品事業
- 人事部 HR戦略課 課長 重野 大介 様
- 人事部 HR戦略課 岸田 祐樹 様
- 人事部 HR戦略課 土田 良平 様
- 人事部 HR戦略課 真山 結衣 様
※役職、所属は取材当時のものです。
導入前の課題
私たちの会社は、コミュニケーションの向上と変化対応力の強化を目指し、社内でいくつかの課題に直面していました。
表面的には社員同士のコミュニケーションは取れているように見えましたが、実際には意思疎通が不十分な場面も多く見受けられました。特に、マネジャーとメンバー間や異なる部署間でのコミュニケーションの円滑化が求められていたのです。
また、中途採用が増える中で、オンボーディングを円滑に進めるために、効果的なコミュニケーションツールの導入が必要でした。これに加えて、業界環境の変化に対応し、社員の変化適応力を強化する必要もありました。
出会いと導入
営業チームのコミュニケーションを円滑にするツールを模索している中で、「LIFO」と出会いました。「LIFO」の魅力は、そのプログラムの分かりやすさと社内への展開が容易な点にありました。
他のツールとは異なり、内製研修で効果的に活用できるプログラムであったため、導入を決めました。
LIFOスコア取得後に得られる詳細な個別レポートは、社員一人ひとりの特性を理解する「取扱説明書」として機能し、自己理解を深める助けとなりました。その後、役員からの強力な支持を得て、全社展開が迅速に進みました。
展開ステップと取り組み
導入当初、LIFOは営業所長研修の一環として活用され、研修を終えた所長がサブトレーナーとなり、現場での実施を推進しました。
その結果、営業所長はLIFOを用いてチームの構築とコミュニケーションの質を向上させることができました。3年目には、LIFOが全社で共通言語となり、コミュニケーションが大幅に改善しました。
現在はチーム単位でのワークショップを実施し、2024年度には新入社員を含む多くの社員が参加する予定です。この取り組みの成果は、社内だけでなく、外部からも高く評価されています。
導入後の感想・成果
LIFOプログラムの導入により、コミュニケーションの質が向上し、研修を超えて職場活用や人事戦略へのデータ活用の幅が広がりました。
結果として、3年以内の離職率も低い水準で推移しています。職場での活用可能性に関するアンケートでも高い評価を得ており、LIFOが共通言語となることで、活発なコミュニケーションと効果的な施策の運用が進んでいます。
今後の課題と取り組み
今後は、全社員を対象にLIFOを定期的に活用し、コミュニケーションの強化を継続することが重要です。特にオンボーディング施策に重点を置き、新入社員が早期に職場に馴染めるようサポートしていきます。
また、データを基にした効果的な人事戦略を構築し、社員特性に応じた配属や異動を実現することで、組織全体の最適化を目指します。最終的には、グループ企業全体での展開を見据えています。このような取り組みを通じて、社員同士の相互理解を深化させ、組織力をさらに強化していきます。
▼事例の全文は下記をご覧ください。
⇒日本新薬株式会社様 LIFO・ITS導入事例
まとめ:コミュニケーション訓練で大人の社会的能力を高める方法
大人のための効果的なコミュニケーションスキル訓練とは?研修のやり方についても紹介についてご案内してきました。
- コミュニケーション訓練とは?大人が基本から学ぶべき重要性
- 大人がコミュニケーションを訓練するメリット
- コミュニケーション訓練に取り組む際の大人の自己分析法
- 訓練になる大人向けコミュニケーション実践法7選
- 大人がコミュニケーション訓練を習慣化する方法
- 大人のコミュニケーション訓練で手っ取り早いのは研修
- コミュニケーション研修ならLIFO®がおすすめ!
- LIFOでコミュニケーション研修を展開した支援事例(日本新薬株式会社)
コミュニケーション能力は生まれつきの才能ではなく、適切な訓練と継続的な実践によって誰でも向上させることができるスキルです。特に大人になってからでも、体系的なアプローチで取り組むことで着実に成長することが可能です。
より効率的にスキルを向上させたい場合は、専門家による研修プログラムの受講も効果的です。
階層別研修では自分のキャリアステージに合ったスキルを学ぶことができ、職場単位の研修ではチーム全体のコミュニケーション文化を改善することができます。両方をバランスよく取り入れることで、個人とチーム全体の成長を促進できるでしょう。
最後に強調したいのは、コミュニケーション訓練は一時的なものではなく、生涯を通じて継続的に取り組むべき課題だということです。社会環境の変化や自分自身の役割の変化に合わせて、常に学び、実践し、改善していくことが大切です。
一歩一歩着実に訓練を重ねることで、どのような場面でも自信をもってコミュニケーションが取れるようになり、仕事でも私生活でも充実した人間関係を築くことができるでしょう。今日から、あなたもコミュニケーション訓練を始めてみませんか?
株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。