株式会社フジマート四国様
自己理解促進ツールの活用で、研修内製化と職場コミュニケーション活性化を実現
~一人一人が共通言語を基に原点へ立ち返り、行動変容で成長につなげる~

-
取組前の課題:
・内製で効果の高い人財育成施策を実行したかった。
・社員一人一人が内省し、成長しつづけるための共通言語づくりをしたかった。
-
取り組んだこと:
・LIFO・HEPのライセンスプログラムを活用し、研修の内製化とコミュニケーション活性化を実現
-
今後の展望:
・研修後の行動変容を促すためのフォローと仕組みづくりを進めたい。

株式会社フジマート四国

管理部 課長
渡邊 隆弘 様
フジマート四国は愛媛県松山市内に食品スーパーマーケット「スーパーABC」を6店舗展開。「食」を通じて地域のお客さまに「笑顔」と「元気」をお届けする企業を目指しています。
業務内容は、人事・経理・総務など、会社の後方業務全般を3名の仲間と推進。その中でも人財育成を重点課題として取り組み、従業員の方々が自己成長の実感を通じて「笑顔」で「元気」になれるよう努めています。
「内製で人財育成を進めたいが、何から手を付けるべきか分からない」
「社員一人一人の強みに焦点を当てた成長促進ツールを探している」
このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
株式会社フジマート四国様では、人財育成の共通言語ツールとしてLIFOを活用し、
効果的な人財育成の内製化、および職場コミュニケーションの活性化を促進するお取り組みをされています。
本記事では、管理部 課長の渡邊 隆弘 様にインタビューした内容をレポートします。
導入前の課題
原点に立ち戻り成長のきっかけとなる、共通言語づくりをしたい
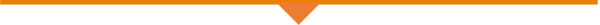
当社の親会社である株式会社フジで社内教育を担当していた頃から、ライセンスプログラムを活用していました (現在は株式会社フジより出向中) 。株式会社フジでも教育担当として社内の研修や人財育成に携わっていましたが、 当時は「何をすればよいのか分からない」という状況に直面していました。
社員の成長を支援したいという想いはありながらも、どのようなアプローチを取ればよいのか明確な答えを持っていませんでした。
そのような状況の中、株式会社LDcubeの親会社である、株式会社ビジネスコンサルタントが主催する「SDS」という公開講座を受講する機会がありました。SDSは、現在のHEP(ヒューマン・エレメント・プログラム)という講座の前身であり、深い内省を通して自己理解と行動変容につなげるプログラムです。この研修を通じて「自分にしかできないことは何か?」という問いに向き合うことができ、自己理解が深まりました。その結果、自分の強みを再認識し、それを生かす方法を考えるようになりました。この経験が自分自身の成長につながったと感じます。
当社で人財育成業務に携わることになってからは、上記のような経験を経て、「同じような気付きを社員にも提供したい」と強く思うようになりました。特に、社員が自分自身の強みを再認識し、原点に立ち戻ることができるような共通言語を社内に根付かせたいと考えました。社員一人一人が自己理解を深め、自信を持って業務に取り組める環境をつくることが、人財育成において重要だと感じていたのです。
そこで、自分が体験したような「原点に立ち戻って自分の強みを再認識できるツール」を探していました。その答えとしてたどり着いたのが「LIFO」でした。LIFOを活用することで、社員が自身の特性や強みを理解し、それを生かすことで成長できると考え、導入を検討することになりました。
出会いと導入の決め手
「強み」に焦点を当て、ヒューマンスキルを育成できるツールと感じた

~LIFO導入の決め手~
LIFOを選定した最大の理由は、その「分かりやすさ」です。特に若年層にとって理解しやすく、強みに特化した内容であるため、実際の職場で活用する際にもポジティブな関わりや指導ができるという点が魅力的でした。従来の研修では弱点を克服することに重点が置かれがちでしたが、LIFOでは強みを活かすアプローチを取るため、承認欲求の高い現代の若手社員に適していると感じました。
また、当社では新卒採用が年に2〜3名程度と少人数であるため、新入社員を含めた若手社員を対象とした研修の実施を計画していました。LIFOを活用することで、若手社員が自分の強みを理解し、成長するための基盤をつくることができると考えました。
~ヒューマンスキルの重要性~
仕事をする上で最も重要なのは、ヒューマンスキルであると考えています。近年の若手社員は、これまでの人生の中でヒューマンスキルを十分に磨く機会が少なかったため、入社後にそのスキルを向上させる環境を整えることが必要です。加えて、現在の若手社員が5〜6年後に上司や先輩になった際に、次の世代の育成を担えるような人財に成長してもらいたいと考えています。そのためにも、私自身が過去に経験したような成長体験を、若手のうちにLIFOを通じて経験し、それを部下・後輩の指導や育成に役立ててもらいたいと考えました。
~共通言語の必要性~
人財開発を進める中で、組織内に共通言語がないと円滑なコミュニケーションが難しいことを痛感しました。そのため、管理部門としても積極的に関与し、共通言語の確立に取り組んでいます。共通言語が組織に根付くことで、社員同士の理解が深まり、組織の一体感が高まることを期待しています。
私自身も「長所連結主義」という考え方を大切にしており、社員が長所に着目し、それを活かす文化を組織に定着させることが重要だと考えています。その実現のためにも、LIFOは非常に有効なツールだと感じました。
展開ステップとお取り組み
階層教育から広げる「共通言語づくり」で、職場コミュニケーション活性化

当社の管理部門に着任後、最初に取り組んだのが「共通言語づくり」です。
共通言語があることによって、自己理解と他者理解が深まり、職場でのコミュニケーションが活性化されます。加えて、部下指導などの人財育成のシーンにおいても、共通言語を基に内省を促すことができるようになります。
LIFOを共通言語として根付かせながら効果的な研修の機会を提供するため、主に以下の階層教育でLIFOプログラムを活用しました。
- 店長本部社員研修
- 主任研修
上記のように節目となる階層に対してLIFO研修を実施することで、職場での共通言語化を図っています。この取り組みにより、強みを生かす文化が根付いてきているのを実感しています。
また、研修後のフォローアップと行動変容を促すことを目的に、内省する機会を増やすことも重視し、取り組みました。

LIFOは自身の強みを理解し、業務に生かすことができることが特徴ですが、「強みの過剰使用」は非生産的であるという示唆も与えてくれます。この「強みの過剰使用」を避けるため、研修受講者に対しては定期的にスコアを測定し、1年を通じて内省を促す取り組みを行っています。
最初は網羅的に研修を実施しましたが、行動変容につながりづらいマネジャー層もいるため、行動変容を促すための仕組みや制度を整えることも必要だと考えています。
導入後の感想・成果
離職率改善に大きな成果あり、マネジャー層の行動変容は道半ば

マネジャーやリーダー層においては、うまくいった側面と、今後さらに取り組んでいかないといけない側面が見えてきました。
うまくいった側面は、職場でのコミュニケーションにおける変化です。部下指導などの指摘やフィードバックにおいては、強みや長所に焦点を当てて行うことで、ポジティブでアサーティブな指導が可能となっています。その結果、職場の心理的安全性が高まり、自己肯定感を向上させる組織文化の醸成につながっています。
今後さらに取り組んでいかないといけない側面は、当社のマネジャー層で行動スタイルの特徴に偏りがあることです。マネジャー層のLIFO診断スコアを分析したところ、「CT」スタイルが圧倒的に少ないことが分かりました。CTスタイルは、過剰使用すると横柄さが目に付くというリスクもありますが、効果的に発揮できれば、組織を動かして成果につなげることにつながるため、マネジャーには必要なスキルです。組織の健全な運営のために、意図的にCTスタイルを効果的に活用できる人財を育成することが重要だと考えています。
当社では以前から「教育の内製化」を掲げていましたが、なかなか実現できていませんでした。人財育成は経営課題として認識されていたものの、具体的な方法が見いだせず、OJTが中心となっていました。しかし、研修を実施するとしても予算が限られている中で、「それなら自分たちでやろう」という発想に切り替えて実践し、ライセンスプログラムを活用しながら研修の内製化が実現できています。
内製で研修を実施する中では、研修実施時にはさまざまな工夫も心掛けています。特に、研修の効果を高めるためには、講師が自身の言葉で伝えることが重要だと感じています。自身の成功体験や失敗体験を交えながら話すことで、受講者の姿勢が変わり、研修の理解度も向上することが分かりました。
また、以前に親会社で新入社員向けにLIFO研修を実施していた際には、離職率が大幅に下がったことがありました。そのような成功体験もあるため、今後は入社2~3年目社員を含めて、若手層に向けたLIFO研修も実施していく予定です。当社ではここ数年は新入社員研修を実施していませんでしたが、LIFOを共通言語とし、新入社員や若手社員が自己理解を深め、職場での実践に生かせるようなきっかけをつくっていきます。
受講者の声
「自己理解と他者理解」を業務に生かし、成長実感を得られた

受講者からは、「LIFOを通じて自分の強みを再認識できた」「職場でのコミュニケーションが円滑になった」という声が多く寄せられています。
研修を通じて得た気付きを業務の中で生かせるようになったことで、個々の成長につながっていると実感しています。
<受講者の声>
- コミュニケーションは自己理解から始まるということを学びました。
- 自分自身に強みが弱みになることも、その逆も起こり得るということを知れました。
- 自己理解は、自己認識と他者認識が異なることを理解することが大事だと感じました。
- 他者からのフィードバックをもらうことは正直恥ずかしさもありましたが、貴重な意見をもらうことができ、自己理解を深めることができました。
- LIFO診断で明らかになった自身の強みをさらに強化し、自分らしさを磨いていきたいです。
- 自身が好む行動スタイルや苦手とするLIFOスタイルを理解できたので、部門での共通言語としてしっかり業務に活かしていきたいです。
- 「伝える」ということの難しさと重要さを理解できました。部下とのコミュニケーションの課題も明確にすることができました。
- LIFO診断を部下とのコミュニケーションに活かし、部門のメンバーとの連携強化や成果に結び付けたいです。
- 「自分を肯定できなければ、他人も肯定できない」ため、まずは自己承認をしてあげることが大事だと学びました。
- LIFO診断により、自身の強みとともに啓発点も理解することができました。LIFO診断を自己成長につなげていきたいと思います。
取り組みにおける課題と今後の展望
行動変容の促進とフォローが、組織成長のカギ

LIFOプログラムやHEPプログラムを活用することで、社員の自己理解が深まり、成長のきっかけになっています。LIFOに関しては社内でも共通言語となりつつあり、取り組みには大きな成果を感じています。
一方で、課題として感じているのは、研修後の行動変容へつなげていくためのフォローアップや仕組みについてです。研修はあくまでもきっかけに過ぎないため、その後にいかに自身で内省を繰り返すかということが重要だと感じています。しっかり内省をしながら自己成長につなげることができるかどうかは、現状は個々人によってバラつきが大きい状況です。
本当の意味で人財育成を考えるのであれば、教育機会のみならず、成長のきっかけや刺激を提供するための仕組みや制度づくりも必要だと考えています。
また、「心理的安全性の高い職場づくり」についても、個人的には今後意識して取り組みたいポイントの1つです。心理的安全性が低い職場では、創造性や自発性が発揮しにくくなります。社員一人一人が創造性や自主性を発揮し、生き生きと働くことができる職場づくりをしていきたいと考えています。そのためにも、LIFOやHEPを活用しながら、マネジャー層を中心に行動変容を促していくことが必要です。
今後も、継続的にライセンスプログラムを活用した内製研修を実施し、そのたびに理解を深めることで、「上司を認める、相手を認める、自分を認める」という組織風土を醸成していきたいと考えています。また、ジョブローテーションを活用することで、多様な経験を積む機会を提供し、成長を促す環境を整えていきます。
最終的には、組織全体で強みを生かし合い、共通言語を基にした人財育成を推進することで、より良い職場環境を築いていくことを目指しています。
関連記事
Contact
人材育成でお悩みの方は、お気軽にご相談ください
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
人材育成に関する
お役立ち資料はこちらから
お電話でのお問い合わせはこちら
平日9:00~17:30

