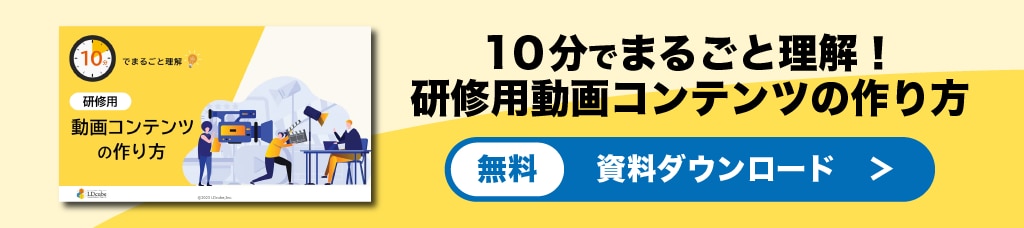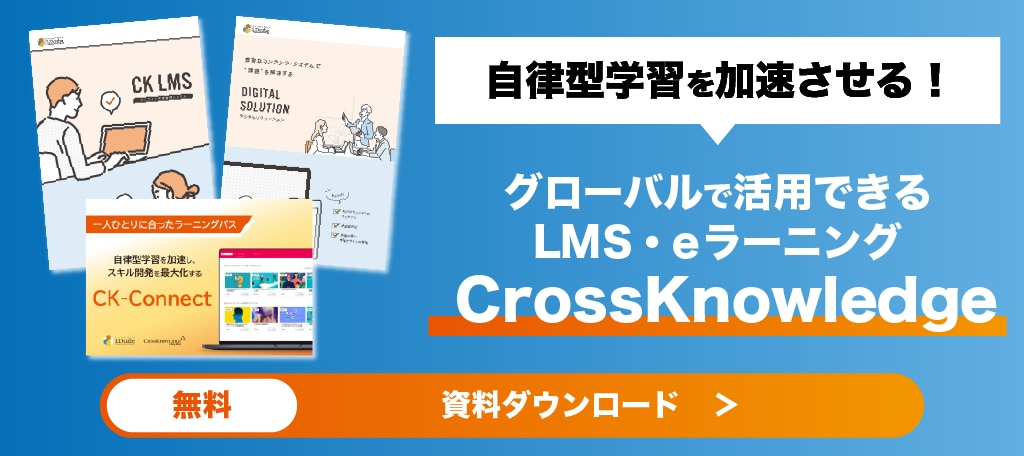LMS(学習管理システム)で効果的な動画研修を展開する方法とは?|5つの重要ポイント
企業の研修や人材育成において、LMS(学習管理システム)と動画コンテンツの組み合わせが注目を集めています。多様な働き方が広がる現代では、時間や場所に縛られない、効率的な学習環境の構築が求められており、LMSを活用した動画研修がその解決策として期待されているのです。
しかし、「LMSで本当に効果的な動画研修ができるのか」「どのように活用すれば最大の効果が得られるのか」と悩む担当者も少なくありません。
実際、LMSはテキストや資料をと音声などを組み合わせた学習コンテンツの管理を出発点として開発されてきたため、動画活用においてはさまざまな課題や制約が存在することがあります。ストレージ容量の問題や配信方法の制約、視聴ログの分析機能の限界など、本格的な動画研修を実施する上での障壁が少なからず存在します。
一方で、適切な方法でLMSと動画を組み合わせることができれば、テキストだけでは伝えきれない複雑な技術や知識の効率的な共有、学習者のエンゲージメント向上、理解度の深化など、大きなメリットを得ることができます。
本記事では、LMSを活用した動画研修の基本概念から実践的な活用法、そしてLMSの限界を超えるための専門システムとの連携まで、効果的な研修を実現するための5つの重要ポイントを徹底解説します。企業規模や業種に合わせたベストプラクティスも紹介していますので、あなたの組織に最適なLMS動画活用の道筋が見つかるはずです。
▼LMSについてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。
▼動画研修についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。
▼研修用動画コンテンツの作り方については下記にまとめています。
目次[非表示]
人材育成のデジタル化にはLMSと動画が不可欠

企業における人材育成は、デジタル化の波を受けて大きく変化しています。特に新型コロナウイルスの影響により、対面での集合研修から、時間や場所を選ばないオンライン研修へのシフトが加速しました。
このデジタル化の流れの中で、特に注目されているのが「LMS(Learning Management System)」と「動画コンテンツ」の組み合わせです。従来のテキストベースの学習から、より効果的で柔軟な動画を活用した学習へと進化する企業が増えています。
LMSと動画を組み合わせることで、企業は効率的かつ効果的な人材育成の仕組みを構築することができるのです。
LMSに動画を載せて運用する
LMSは「eラーニングを運用・管理するためのシステム」であり、学習コンテンツの配信や進捗管理、テスト実施などの機能を備えています。従来のLMSはテキストベースの研修に利用されることが多かったですが、近年では動画によるコンテンツ配信ニーズの高まりに応え、動画管理機能を搭載した製品も増えてきました。
LMSに動画コンテンツを載せて運用することで、テキストだけでは伝えにくい実技やプロセスの説明、複雑な情報の視覚化が可能になります。
また、社内の専門家や経営層からのメッセージを生き生きと伝えることができ、研修の質と魅力が大幅に向上します。
学習行動のデータが蓄積する
LMSと動画を組み合わせた学習環境の大きなメリットとして、受講者の学習行動に関するデータが自動的に蓄積される点が挙げられます。基本的なデータとしては「誰がどの動画をいつ視聴したか」「どこまで視聴したか」「何回再生されたか」などの情報が取得できます。
さらに高機能なシステムでは、動画内のどの部分で再生を停止したか、早送りしたか、繰り返し視聴した部分はどこかなど、より詳細な学習行動を把握することができます。
これらのデータは単なる受講管理にとどまらず、コンテンツの改善や個々の社員の理解度把握に活用できる貴重な資産となります。
データを活用して効果と効率を高める
蓄積された学習行動データは、人材育成の効果と効率を高めるための重要な情報源です。例えば、多くの受講者が理解に苦しんでいる箇所(再生の多いコンテンツ、理解度クイズの点数が低いコンテンツ)を特定し、そのテーマについて補足説明の追加を行うことができます。
また、受講完了率の低い動画コンテンツについては、長さや内容、表現方法の見直しを検討する材料となります。個人レベルでは、特定の分野での学習進捗が遅い社員をシステムが自動的に検出し、個別フォローの必要性を管理者に通知することも可能です。
さらに、動画視聴と小テストや実践的なタスクの結果を組み合わせて分析することで、「どのような動画コンテンツが実際のスキル向上や業務改善に寄与しているか」を科学的に検証できます。
このようなデータドリブンなアプローチにより、研修投資対効果(ROI)の最大化を実現し、限られた予算と時間の中で最も効果的な人材育成プログラムを構築することが可能になるのです。
このように、LMSと動画の組み合わせは、単なるコンテンツ配信の枠を超えて、企業の人材育成戦略全体を支える基盤となります。
▼研修のデジタル化や人材育成の自動化については下記で詳しく解説しています。
LMSでの動画活用の基本と現状

企業の研修担当者がLMSで動画を活用するためには、まず基本的な知識を押さえておく必要があります。LMSと動画は別々のものとして発展してきましたが、現在では相互に補完し合う関係になっています。
本章では、LMSでの動画活用に関する基本的な概念や定義から、最新のトレンド、そして実際の学習効果について解説します。これらの知識は、効果的な動画研修環境を構築するための基盤となるでしょう。
LMSと動画研修の定義と基本機能
LMSは、eラーニングを運用・管理するためのシステムです。言い換えれば「eラーニング学習を行うための自社専用サイト」のようなイメージで、学習コンテンツの配信から受講者管理、進捗状況の把握、テスト実施まで一元的に行うことができます。
一方、動画研修とは文字通り動画コンテンツを用いた学習のことで、テキストでは伝えにくい内容や手順を視覚的に伝えることができる特徴があります。
LMSの基本機能としては、コース作成・管理、ユーザー管理、進捗管理、テスト・評価機能、レポーティング機能などが挙げられます。動画機能に関しては、従来のLMSでは基本的なアップロード・再生機能程度しか備えていませんでしたが、近年では動画に特化した機能を強化したLMSも登場しています。
例えば、動画内に自動で字幕を表示する機能や動画から自動で理解度クイズを作成する機能など、学習体験を向上させるLMSも増えてきています。
企業研修における動画活用のトレンド
企業研修における動画活用は近年急速に広がっており、いくつかの明確なトレンドが見られます。最も顕著な傾向として、「マイクロラーニング」の台頭が挙げられます。これは5〜10分程度の短い動画を用いて研修を行い、必要な情報を必要なタイミングで効率的に学ぶ手法です。
従来の長時間にわたる集合研修とは異なり、忙しい業務の合間に短時間で学習できるため、受講者の負担を軽減し、学習の継続性を高める効果があります。
また、実際の業務シーン・操作画面をそのまま録画して教材化する「スクリーンキャプチャ型」の動画研修も増加しています。特にITシステムの操作手順やサービス対応マニュアルなど、実際の作業を視覚的に確認できる教材が求められています。
さらに、「ソーシャルラーニング」の要素を取り入れ、動画コンテンツに対して受講者同士が質問やコメントを付け、知識を共有・発展させる取り組みも注目されています。
このようなインタラクティブな要素は、一方通行になりがちな動画学習の欠点を補い、能動的な学習を促進します。
LMSと動画の組み合わせがもたらす学習効果
LMSと動画を組み合わせることで得られる学習効果は多岐にわたります。
まず、情報の伝達・理解という観点では、テキストのみの学習に比べて動画は視覚と聴覚の両方に訴えかけるため、複雑な概念や手順の理解が容易になります。
また、LMSが持つ「学習管理」の強みと、動画コンテンツが「視覚的インパクト」の組み合わさることで、効果的な学習サイクルを構築できます。具体的には、動画視聴→理解度確認テスト→フォローアップ学習という流れを設計しやすくなり、単に動画を見せるだけでなく、確実な知識定着を図ることができます。
さらに、LMSで動画学習を管理することで、「いつでもどこでも学べる」というオンライン学習のメリットを最大化できます。特に営業職や店舗スタッフなど、デスクワークが中心ではない従業員にとっては、移動時間や隙間時間にスマートフォンで動画研修を受けられる環境は非常に価値があります。
このように時間や場所の制約を取り払うことで、研修の効率性と柔軟性が大幅に向上し、企業全体の学習文化の醸成につながります。
LMSでの動画配信の課題

LMSを利用して動画研修を行おうとする際に、多くの企業がさまざまな課題に直面します。LMSは元々テキストベースの学習管理を目的に開発されてきたシステムであるため、動画コンテンツの扱いに関しては機能的な制約が存在するケースが少なくありません。
ここでは、LMSを用いた動画配信・管理における主な課題を詳しく解説します。これらの課題を事前に理解しておくことで、適切なシステム選択や運用方法の検討に役立てることができるでしょう。
LMSを使用して動画研修を実施する際に最初に直面する問題が、ストレージ容量の制限です。動画ファイルはテキストや画像と比較して圧倒的にファイルサイズが大きく、多くのLMSのストレージでは容量不足になりやすいという特徴があります。
一般的なLMSでは、ストレージ容量は5GB〜20GB程度に設定されていることが多く、これは概ね3時間〜12時間程度の動画しか保存できない容量です。高画質の動画で考えると、1時間あたり1.5GBほどのストレージを消費します。企業研修では部署・地域ごとに別々の動画を配信したいケースや、継続的に研修動画を追加していくケースが多いため、この程度の容量ではすぐに限界に達してしまいます。
また、容量の問題以外にも、一定以上のファイルサイズのコンテンツはLMS上にアップロードできないよう制限をかけているシステムも多く存在します。例えば、「100MB以上のファイルはアップロードできない」という制限があると、高品質の動画や長時間の研修動画を1本のファイルとして扱うことができません。
このような制約により、「長期的に動画を追加・蓄積して、オンライン研修を充実させたい」という企業の要望を満たせないケースが少なくありません。
LMSでの動画活用の効果を高める5つのポイント

前章で解説したように、LMSでの動画活用にはさまざまな課題が存在します。
しかし、適切な対策を講じることで、これらの課題を克服し、効果的な動画研修環境を構築することは十分に可能です。
ここでは、LMSを使った動画研修の効果を最大化するための5つの重要ポイントを詳しく解説します。これらのポイントを押さえることで、限られたリソースの中でも質の高い動画研修を実現し、受講者の学習効果を高めることができるでしょう。
動画研修に適したLMSの選定
LMSでの動画活用の成否を左右する最も重要な要素の1つが、適切なLMSの選定です。すべてのLMSが同じように動画に対応しているわけではなく、製品によって機能や性能に大きな差があります。
動画研修に適したLMSを選ぶ際は、以下の点を重視して比較検討することをおすすめします。
まず最も基本的な要素として、十分なストレージ容量が確保できるかどうかを確認しましょう。前述の通り、動画ファイルは容量が大きいため、最低でも20GB以上のストレージが提供されるLMSが望ましいといえます。
また、必要に応じてストレージを増設できるシステムであれば、将来的な拡張性も確保できます。
次に重要なのが、動画の配信方式です。受講者の利便性を考慮すると、ダウンロード方式ではなくストリーミング配信に対応しているLMSを選ぶべきです。
これにより、受講者はすぐに視聴を開始でき、端末の容量を圧迫する心配もありません。
LMS配信用の動画コンテンツの最適化方法
LMSで配信する動画コンテンツは、システムの制約や視聴環境を考慮して最適化することが重要です。適切に最適化された動画は、ストレージ容量の節約だけでなく、受講者の視聴体験の向上にもつながります。
まず技術的な観点では、適切な解像度と圧縮設定が重要です。企業研修で使用する動画の場合、映画やエンターテインメント用途ほどの高画質は必要ありません。720p(HD画質)程度の解像度で十分視認性は確保できますし、適切な圧縮設定を行うことで、画質をそれほど落とさずにファイルサイズを削減することも可能です。
コンテンツの長さについても最適化が必要です。近年注目されている「マイクロラーニング」の考え方に基づけば、1本あたり5〜10分程度の短い動画に分割することが効果的です。長時間の動画は受講者の集中力が途切れやすく、学習効果も低下します。内容ごとに適切に分割し、必要な情報を必要なタイミングで学べるようにしましょう。
また、内容面での最適化も忘れてはなりません。冗長な説明や不要な情報は削除し、核となる重要ポイントに焦点を当てた簡潔な内容にすることで、学習効率が高まります。視覚的な補助(テキストのポップアップ、図表の活用など)を取り入れることで、より理解しやすいコンテンツになります。特に手順や操作を説明する場合は、クローズアップやハイライト表示などの編集技術を活用すると効果的です。
LMSでの動画研修の受講率を向上させる工夫
どれだけ質の高い動画コンテンツを用意しても、実際に受講者が視聴してくれなければ意味がありません。LMSでの動画研修の受講率を高めるためには、以下のような工夫が効果的です。
第1に、インタラクティブ要素を取り入れることで受動的な視聴から能動的な学習へと転換させましょう。具体的には、学習の途中で小テストを挿入する、重要なポイントでクイズに回答させる、アンケートで意見を聞くなどの仕掛けを取り入れます。
こうした双方向性のある要素は、単調になりがちな動画学習に変化をつけ、集中力を維持するのに役立ちます。
第2に、ソーシャル機能を活用することも有効です。動画コンテンツにコメント機能を設け、受講者同士が質問や意見を交換できる場を提供しましょう。
また、特に優れた質問や気付きを共有する「いいね!ボタン」などがあれば、他の受講者の学習意欲も高まります。
こうしたコミュニティー感覚は、特にリモートワークが増えた現代において、孤独感を軽減し学習へのモチベーションを維持するのに役立ちます。
|
さらに、動画研修の存在を社内に適切に周知することも重要です。サービス開始時には社内メール等で告知し、その価値や活用方法を明確に伝えましょう。
時には経営層からのメッセージを含めることで、組織として学習を重視していることを示すことができます。
動画研修の効果を正確に測定する指標設定
LMSでの動画研修を継続的に改善していくためには、その効果を正確に測定するための指標設定が不可欠です。適切な指標を設定し、定期的にデータを分析することで、投資対効果(ROI)の最大化や研修内容の改善につなげることができます。
基本的な指標としては、「視聴完了率」「平均視聴時間」「再生回数」などの定量的データがあります。これらは多くのLMSで標準的に取得できる情報であり、コンテンツごとの人気度や難易度を測る基礎データとなります。特に視聴完了率が低い動画については、長さや内容、説明の分かりやすさなどを見直す必要があるかもしれません。
最も重要なのは、「学習成果」の測定です。動画視聴後のテスト結果、実際の業務パフォーマンスの変化、資格取得率の向上など、研修の本来の目的に関連した指標を設定し、追跡することが理想的です。例えば、営業研修であれば成約率の変化などが考えられます。
|
LMSのセキュリティー確保
企業の研修動画には、社内の機密情報や専有知識が含まれることが少なくありません。そのため、LMSでの動画活用においては、セキュリティーの確保が非常に重要な課題となります。
適切なセキュリティー対策を講じることで、情報漏洩のリスクを最小限に抑えつつ、効果的な動画研修を実施することが可能になります。
まず基本的な対策として、ユーザー認証の強化が挙げられます。定期的にIDとパスワードの変更を促すだけでも、不正アクセスのリスクを大幅に低減できます。
また、適切なアクセス権限の設定も重要です。部署や役職に応じて視聴できる動画を制限することで、機密性の高い情報へのアクセスを必要な人物だけに限定できます。
動画の保護に関しては、ダウンロード禁止設定やストリーミング専用の配信方式を採用することが有効です。これにより、動画ファイルが社外に持ち出されるリスクを低減できます。さらに高度な保護が必要な場合は、電子透かしの挿入や視聴端末の制限などの対策も検討すべきでしょう。
|
これらのセキュリティー対策を講じることで、安全な環境で動画研修を実施することができます。ただし、過度に厳しい制限は利便性を損ない、結果的に受講率の低下につながる可能性もあるため、セキュリティーと利便性のバランスを考慮することが重要です。
企業の情報セキュリティーポリシーに準拠しつつ、ユーザーの学習体験を損なわない最適な設定を目指しましょう。
シーン別のLMSでの動画活用ベストプラクティス

LMSでの動画活用は、企業の規模や業種によって最適なアプローチが異なります。
ここでは、企業規模や業種ごとの特性を考慮した効果的な動画活用方法について解説します。自社の状況に最も適したアプローチを選択することで、限られたリソースの中でも最大限の効果を得ることができるでしょう。
それぞれの企業特性に合わせたベストプラクティスを参考に、自社にとっての最適な動画活用戦略を検討してみてください。
大規模企業におけるLMS・動画活用のコツ
大規模企業がLMSで動画研修を実施する場合、多数の従業員に対して安定した配信を行うことが最大の課題となります。数百人〜数千人規模の同時視聴が想定される環境では、安定した動作が保証されているかどうかを事前に確認しましょう。
安定稼働が実現できるLMSを選ぶことが重要です。
中小企業向けのコスト効率の高いLMS・動画活用のコツ
中小企業では、大規模な投資が難しいことを考慮し、コスト効率の高い動画活用方法を模索する必要があります。少人数から中規模の企業であれば、ライトな動画研修に特化したLMSの機能でも十分対応可能なケースが多いでしょう。
その場合、動画対応のLMSを1つ選定し、そこですべての機能を完結させる方法が最もコスト効率が高いといえます。
動画制作のコツ
動画制作においても、専門業者への外注ではなく社内リソースで作成することでコストを抑制できます。最近のスマートフォンでも高品質な動画撮影が可能ですし、無料・低コストの編集ツールも充実しています。
また、マイクロラーニングの考え方を取り入れ、1本5分程度の短い動画に情報を凝縮することで、制作・視聴両面での効率を高めることができます。受講者の学習時間を考慮すると、長時間の研修よりも短時間で集中して学べるコンテンツの方が効果的です。
業種別に見るLMS・動画活用の特化型アプローチ
業種によって必要な研修内容や効果的な動画活用方法は大きく異なります。それぞれの業種特性に合わせた動画活用戦略を考えることで、より高い学習効果を得ることができるでしょう。
製造業では、製品の組み立て手順や機械操作のマニュアル、安全教育などを動画化することが効果的です。特に複雑な製造工程は、テキストよりも動画による視覚的な説明の方が理解を促進します。この場合、作業の細部まで分かるよう複数アングルでの撮影や、クローズアップなどの技術を活用した詳細な動画コンテンツが有効です。
小売・サービス業では、接客スキルやクレーム対応などのロールプレイング型動画が効果的です。良い例・悪い例を比較したシナリオベースの動画は、特に新人教育において高い効果を発揮します。また、POPやディスプレイーなどの視覚的要素が重要な業務については、ビフォーアフター形式の動画が理解を促進します。
金融・保険業では、コンプライアンス研修や商品知識の習得など、正確な情報伝達が求められる場面が多く、視聴完了の証跡管理機能が重要です。また、内容の更新頻度も高いため、簡単に動画を差し替えられるシステムを選ぶことがポイントとなります。
このように業種ごとの特性を考慮し、最も効果的な動画コンテンツとLMS機能の組み合わせを検討することで、研修効果を最大化することができます。いずれの業種においても、一方通行の情報提供にとどまらず、視聴後のフォローアップやアクションラーニングと組み合わせることで、真の業務改善につなげることが重要です。
まとめ:LMS動画活用で研修効果を最大化

LMS(学習管理システム)で効果的な動画研修を展開する方法とは?|5つの重要ポイントについて紹介してきました。
- 人材育成のデジタル化にはLMSと動画が不可欠
- LMSでの動画活用の基本と現状
- LMSでの動画配信の課題
- LMSでの動画活用の効果を高める5つのポイント
- シーン別のLMSでの動画活用ベストプラクティス
効果を最大化するには、システム選択、コンテンツ最適化、受講率向上策、効果測定、セキュリティー確保の5ポイントが重要です。バランスよく押さえることで研修効果が高まります。
ストレージ制限や配信制約、分析機能不足などの課題も、紹介した対策で克服可能です。企業規模や業種によって最適なアプローチは異なるため、自社の特性に合った戦略が成功の鍵となります。ライトな研修ならLMS機能で十分ですが、本格的な動画研修には専用システムの導入やLMSとの連携も検討する価値があります。
効果的な人材育成環境の構築に向けて、本記事を参考に一歩踏み出し、デジタル時代の人材開発を推進してください。
株式会社LDcubeはCrossKnowledgeの日本国内の公式パートナーとしてLMSやeラーニング・マイクロラーニングなどの提供などを行っています。
また無料のデモIDやデモ体験会、活用事例・導入事例の紹介、料金の案内なども行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。