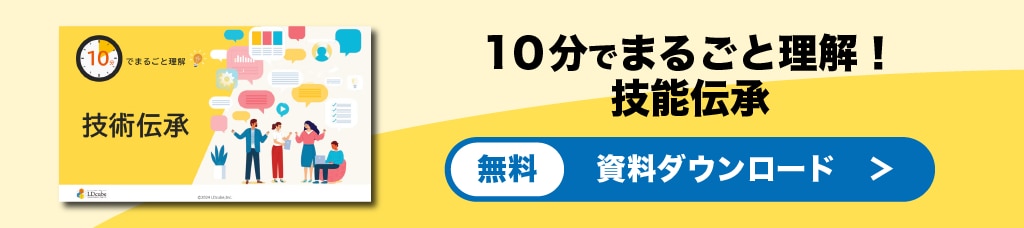建設業界における技術伝承の課題と解決策とは?デジタル化の方法など解説!
最近の建設業界において、技術や技能の伝承の重要性が再認識されている背景には、高齢化と退職ラッシュがもたらす「技術の空洞化」の深刻化があります。
建設現場では、長年の経験に基づく職人技が欠かせませんが、ベテラン社員の退職によってその技術が失われつつあります。
高齢化が進む中で、こうしたノウハウが属人化してしまい、組織全体に共有されないまま失われるリスクが高まっています。この問題は、企業の競争力や現場の安全性に影響を及ぼす重大な課題です。
さらに、若手人材の不足と育成環境の整備の遅れも、技術伝承を難しくしています。若手の確保が難しい現状では、即戦力を求めるがあまり、育成に十分な時間を割けないという声が多く聞かれます。
世代間のコミュニケーションギャップも、技術伝承を妨げる大きな要因となっています。ベテランと若手の間で価値観やコミュニケーションスタイルが異なり、伝承が思うように進まないケースが多発しています。
こうした課題を解決するためには、技術伝承の仕組み化が急務です。技術を見える化し、デジタルツールを活用した効果的な技術教育の仕組みを構築することが求められます。
若手が安心して学び成長できる環境を整えるには、育成プログラムの確立やベテラン社員の役割再定義が不可欠です。また、企業全体で「教え合う」文化を育むことが、持続可能な技術伝承体制の構築につながります。
本記事では、技術伝承が注目されている背景やうまくいかない理由、具体的な進め方や事例について解説していきます。ぜひ最後までお読みいただき、実践に向けたヒントを見つけてください。
▼技術伝承については下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
▼技術伝承については下記に資料にまとめています。
目次[非表示]
- 1.なぜ今「技術伝承」が建設業界で注目されているのか
- 1.1.高齢化と退職による技術の空洞化
- 1.2.若手不足と育成の難しさ
- 2.建設業界で技術伝承がうまくいかない5つの理由
- 2.1.属人化されたノウハウ
- 2.2.同じ現場が2度とない
- 2.3.教える時間・仕組みの不足
- 2.4.若手とのコミュニケーションギャップ
- 2.5.デジタル活用の遅れ
- 3.技術伝承の成功事例(建設業界の実例紹介)
- 4.建設業界で技術伝承を促進するための具体的な方法
- 4.1.技術の見える化(マニュアル・動画・図面)
- 4.2.若手育成プログラムの設計
- 4.3.ベテラン社員・シニア社員の役割再定義
- 4.4.デジタルツール(eラーニングなど)の導入
- 4.5.組織文化としての「教え合い」の醸成
- 5.建設業界での技術伝承がもたらすメリット
- 5.1.若手の定着率アップ
- 5.2.組織力・現場力の強化
- 5.3.品質・安全性の向上
- 5.4.企業ブランドの向上
- 5.5.持続可能な人材育成体制の構築
- 6.建設業界で技術伝承のデジタル化のステップ
- 6.1.経営層を含めた目的の設定
- 6.2.プロジェクトチームの編成
- 6.3.必要な項目の洗い出し
- 6.4.部署ごとにコンテンツ作成
- 6.5.プラットフォーム上に整理
- 6.6.現場での活用・ブラッシュアップ
- 7.まとめ:技術伝承はデジタル化しよう
なぜ今「技術伝承」が建設業界で注目されているのか

今、建設業界で技術伝承が注目されています。その理由について解説します。
高齢化と退職による技術の空洞化
建設業界では、ベテラン社員の高齢化と定年退職が進み、現場の技術やノウハウが失われる「技術の空洞化」が深刻な課題となっています。
建設業は長年の経験によって培われる職人技や現場対応力が重要な業界です。しかし、団塊世代を中心としたベテラン層が定年退職を迎える中、彼らが持つ暗黙知や現場の勘が十分に継承されないまま失われてしまうケースが増えています。これは、業務の属人化や技術の言語化・体系化が進んでいないことが原因です。
技術の空洞化は、企業の競争力や安全性に直結する問題です。今こそ、技術伝承の仕組みづくりが急務であり、ベテラン社員の知見を形式知として残す取り組みが求められています。
若手不足と育成の難しさ
建設業界では若手人材の確保が難しく、育成にも時間と労力がかかるため、技術伝承が思うように進まない状況が続いています。
若手の建設業離れが進む中、現場には即戦力を求める声が強く、育成に十分な時間を割けない企業が多く存在します。また、若手社員とベテラン社員の価値観やコミュニケーションスタイルの違いも、技術伝承の障壁となっています。OJTが機能しない、教える側に余裕がないなど、育成環境の整備が追いついていないのが現状です。
若手不足と育成の難しさは、技術伝承の根幹に関わる課題です。単なる知識の共有ではなく、若手が安心して学べる環境づくりと、教える側の意識改革が必要です。
▼技術伝承については下記にまとめています。
建設業界で技術伝承がうまくいかない5つの理由

建設業界で技術伝承はなかなかうまくいかないことが多いです。うまくいかない理由について解説します。
属人化されたノウハウ
建設業界では、技術やノウハウが個人に依存しているため、技術伝承がうまく進まないケースが多く見られます。現場で必要とされる技術は、長年の経験や勘に基づく「暗黙知」が多く、文書化や標準化がされていないのです。
結果として、ベテラン社員が退職すると、その人しか知らないノウハウが失われてしまいます。属人化された技術は、教える側も「どう教えればいいか分からない」と感じやすく、伝承の障壁となります。
技術伝承を進めるには、ノウハウの属人化を解消し、誰でも理解・再現できる形で技術を「見える化」することが不可欠です。
同じ現場が2度とない
建設業では、現場ごとに条件が異なるため、同じ状況で技術を教えることが難しく、技術伝承が進みにくい傾向があります。
建設現場は、地形、気候、構造、工期などが毎回異なり、同じ作業でも求められる対応が変わります。そのため、過去の経験をそのまま若手に教えることができず、技術の汎用化や体系化が困難になります。現場ごとの「1回限りの対応」が多く、技術の蓄積がしづらいのです。
技術伝承を進めるには、現場ごとの違いを前提にしつつ、共通する原則や判断基準を整理し、応用力を育てる教育が求められます。
教える時間・仕組みの不足
現場の忙しさや人手不足により、技術を教える時間や仕組みが確保できず、技術伝承が後回しになってしまっています。
建設現場では納期や安全管理が最優先されるため、教育や技術伝承に割ける時間が限られています。また、教える側も「教えるより自分でやった方が早い」と感じてしまい、育成の機会が失われがちです。体系的なOJTや教育制度が整っていない企業も多く、技術伝承が属人的・偶発的になっています。
技術伝承を進めるには、教える時間を業務の一部として確保し、仕組みとして育成を組み込むことが重要です。
若手とのコミュニケーションギャップ
世代間の価値観やコミュニケーションスタイルの違いが、技術伝承の障壁となっています。
ベテラン社員は「見て覚えろ」「現場で学べ」というスタイルで育ってきていますが、若手は「丁寧に教えてほしい」「理由を知りたい」と考える傾向があります。このギャップが、教える側のストレスや、教わる側の不満につながり、技術伝承の機会を減らしてしまいます。
ある企業では、若手が「なぜこの方法なのか」を質問したところ、ベテランが「いいから黙ってやれ」と返答し、関係が悪化しました。結果として、若手は質問しづらくなり、技術を深く理解する機会を失いました。
技術伝承を円滑に進めるには、世代間の違いを理解し、互いに歩み寄るコミュニケーションの工夫が必要です。
デジタル活用の遅れ
建設業界では、技術伝承におけるデジタルツールの活用が遅れており、情報の共有や教育が非効率になっています。
多くの建設企業では、紙のマニュアルや口頭での指導が中心で、動画やナレッジ共有ツールなどのデジタル活用が進んでいません。これにより、技術の蓄積や再利用が難しく、若手が自分のペースで学ぶ機会も限られています。
ある企業では、さまざまな作業を動画で記録する取り組みを始めたところ、若手の理解度が向上し、現場での学習が進みました。
技術伝承を効率化するには、デジタルツールの導入と活用を進め、情報を誰でもアクセスできる形で蓄積することが重要です。
技術伝承の成功事例(建設業界の実例紹介)

建設業でデジタル学習環境をベースに企業内大学を立ち上げた事例を紹介します。
社員数:100名以上
事業:土木建築工事、建設工事の設計と監理
取り組み後の成果
■ 若手社員の知識習得レベルの底上げ
若手社員が中心となり、自身が新入社員だった頃の目線を思い出しながらコンテンツ作成を行い、2年間で600個が完成しました。
これにより、初めて業務を覚える新入社員にとっても分かりやすく、必要な情報が十分にそろった学習環境を提供することができました。
また、マイクロラーニングの考え方に基づき、全ての動画コンテンツの長さを5分以内収めました。これによって、隙間時間に効果的な学習をすることが可能になりました。
その結果、新入社員の知識習得レベルの底上げにつながりました。
■ OJT格差の是正とコミュニケーションの活性化
コンテンツを活用した教育によって社員の学習の機会が標準化されたことで、OJT格差が縮小しました。
また、業務内容については新入社員と若手社員がベテラン社員に習い、現場で活用するスマートフォンやタブレットなどについては上司が新入社員と若手社員から学ぶという動きも出てくるようになりました。
この動きは、ベテラン社員と新入社員、若手社員のコミュニケーションの活性化にもつながっています。
■ 入社希望者の増加
デジタル学習環境(プラットフォーム)を導入したことが、県内の入社希望者数の増加につながりました。
新卒の採用説明会やメディアの取材においてデジタル学習環境を使った取り組みを紹介し、企業の教育体制の優位性をアピールしました。
その結果、県内の学生が選ぶ建設業知名度ランキングで1位を獲得しました。そのおかげで、多くの学生から選ばれる企業となりました。
取り組みの詳細
■ 全社プロジェクトの立ち上げ
課題解決のため、人を介さず業務知識が学べるコンテンツの配信環境を構築するプロジェクトを立ち上げました。
まずは各現場で「わが社の新人に必要な学習内容は何か」という観点で棚卸しを行いました。
このプロジェクトの初期は、中堅社員をコンテンツ作成作業の中心に据えました。
■ 全社員アンケートを実施
現場所長や各部署の社員を対象とした「現場に配属になった際に覚えてほしいこと」アンケートを実施しました。
そこで集まった声を基にし、業務フローと照らし合わせながら、必要なコンテンツリストをブラッシュアップしました。
■ コンテンツ作成のサポート体制を強化
中堅社員の目線でコンテンツ作成を行った結果、自身が新入社員だった頃の感覚を忘れていることもあり、どのようなポイントを伝えれば新入社員にとって分かりやすいかという観点が抜けた内容になっていました。
また、コンテンツ一つ一つの情報量が多いことや、自身が普段当たり前のように行っている業務を、コンテンツに落とし込むことができないという課題が浮上しました。
そこで具体的な作業に関するコンテンツ作成を若手社員が担当するように切り替えました。
さらに、各部に配置したアシスタントによる動画撮影・編集のバックアップなど、コンテンツ作成サポートの強化を行いました。
課題・背景
■ 技術教育に十分な時間を割けない
ベテラン社員が現場作業に追われ、若手社員の技術教育を十分にできていないという課題がありました。
また、時間だけでなく、人員にも余裕がないため、本来教えるべき技術やノウハウが現場で伝達できていないという事態に陥っていました。
■ OJT格差と離職率が上昇
現場のOJTは主にベテラン社員が担当していましたが、人によって言うことが違う、厳しい口調の上司が多いなど、 OJT格差がありました。
その結果、若手社員の離職率が高くなり、新入社員の採用に悪影響が出ました。
建設業界で技術伝承を促進するための具体的な方法

建設業界で技術伝承を促進するための具体的な方法についてポイントを紹介していきます。
技術の見える化(マニュアル・動画・図面)
技術伝承を進めるには、ベテラン社員のノウハウを「見える化」し、誰でも理解・再現できる形で残すことが重要です。
建設現場では、経験に基づく暗黙知が多く、言語化されていない技術が多く存在します。これらをマニュアルや動画などの形で記録することで、若手が自分のペースで学べるようになり、技術の属人化を防ぐことができます。また、標準化された情報は、品質や安全性の向上にもつながります。
技術の見える化は、技術伝承の第一歩です。誰もがアクセスできる形でノウハウを残すことで、継続的な人材育成が可能になります。
若手育成プログラムの設計
技術伝承を促進するには、若手社員が段階的に成長できる育成プログラムの設計が不可欠です。
若手は経験が浅く、いきなり現場で高度な技術を求められると不安やストレスを感じやすくなります。体系的な育成プログラムを設けることで、基礎から応用まで段階的に学べる環境が整い、定着率や成長スピードが向上します。また、育成の進捗を可視化することで、指導者側も適切な支援がしやすくなります。
若手育成プログラムは、技術伝承の土台です。計画的な育成設計により、若手が安心して成長できる環境を整えることが重要です。
ベテラン社員・シニア社員の役割再定義
技術伝承を進めるには、ベテラン社員の役割を「教える人」として再定義し、育成に積極的に関わってもらうことが必要です。
ベテラン社員は豊富な経験と知識を持っていますが、現場作業に追われていると、技術を教える時間が取れません。役割を「技術伝承者」として明確にすることで、若手育成に集中できる環境が整い、技術の継承がスムーズになります。また、ベテラン自身も「教えること」にやりがいを感じるようになります。
ある企業では、定年後の再雇用制度を活用し、シニア社員を「技術教育担当」として配置。若手へのOJTやマニュアル作成を担ってもらった結果、技術の継承が進み、現場の品質も向上しました。
ベテランの役割を再定義することで、技術伝承の担い手が明確になります。教える文化を育てるためにも、制度的な支援が重要です。
デジタルツール(eラーニングなど)の導入
技術伝承を効率化するには、eラーニングなどのデジタルツールを活用し、学習の機会を拡充することが効果的です。
現場では時間や場所の制約が多く、対面での教育が難しい場面もあります。デジタルツールを使えば、いつでもどこでも学習が可能になり、若手の理解度や習熟度を高めることができます。また、動画やクイズなどを組み合わせることで、実践的な学びが可能になります。
デジタルツールの導入は、技術伝承の加速につながります。学習のハードルを下げ、継続的な教育を可能にする仕組みとして活用すべきです。
組織文化としての「教え合い」の醸成
技術伝承を根付かせるには、「教え合う文化」を組織全体で育てることが不可欠です。
技術伝承は一部の人だけが担うものではなく、組織全体で取り組むべき課題です。教えることが評価される風土や、質問しやすい雰囲気があることで、若手社員も積極的に学び、ベテラン社員も自然に教えるようになります。心理的安全性が高い職場では、知識の共有が活発になり、技術の定着も進みます。
「教え合い」の文化は、技術伝承の土壌です。制度と風土の両面から支援することで、持続可能な人材育成が実現します。
▼技術伝承のデジタル化については下記で詳しく解説しています。
⇒技術伝承のデジタル化を進めるメリットとは?7つの実践ステップを解説!
建設業界での技術伝承がもたらすメリット

建設業界で技術伝承を効果的に行うことはいくつかのメリットをもたらします。そのメリットについて解説します。
若手の定着率アップ
技術伝承が進むことで、若手社員の定着率が向上し、組織の安定性が高まります。
若手社員は「成長できる環境」や「学べる機会」を重視しています。技術伝承がしっかり行われている職場では、若手が安心して学び、仕事に自信を持てるようになります。結果として、離職率が下がり、長期的な人材確保につながります。
若手の定着には、技術伝承が不可欠です。育成の仕組みがあることで、若手が「ここで働き続けたい」と思える職場になります。
組織力・現場力の強化
技術伝承は、個人のスキルだけでなく、組織全体の力を底上げする効果があります。
技術が属人化していると、特定の人がいないと現場が回らない状況になりがちです。技術伝承によって、知識やノウハウが組織全体に共有されることで、特定の人がいなくても一定の品質を保つことができるようになります。これにより、チームとしての対応力や生産性が向上します。
技術伝承は、組織力の強化につながります。個人依存から脱却し、現場全体の力を高めることが可能です。
品質・安全性の向上
技術伝承が進むことで、施工品質と現場の安全性が向上し、事故やトラブルのリスクを減らすことができます。
建設現場では、経験に基づく判断や細かな作業手順が品質と安全に直結します。技術が正しく伝承されていないと、ミスや不注意による事故が発生しやすくなります。逆に、技術が体系的に共有されていれば、誰が作業しても一定の品質と安全基準を守ることができます。
技術伝承は、品質と安全の土台です。現場の安定運営には、確かな技術の継承が欠かせません。
企業ブランドの向上
技術伝承を重視する企業は、社外からの信頼が高まり、企業ブランドの向上につながります。
技術力のある企業は、顧客や協力会社から「安心して任せられる」と評価されます。特に、若手社員がしっかり育っている企業は、将来性や安定性があると見なされ、採用や営業面でも有利になります。技術伝承は、企業の姿勢や価値観を示す重要な要素です。
ある建設会社では、新卒の採用説明会やメディアの取材においてデジタル学習環境を使った取り組みを紹介し、企業の教育体制の優位性をアピールしました。
その結果、県内の学生が選ぶ建設業知名度ランキングで1位を獲得しました。そのおかげで、多くの学生から選ばれる企業となりました。
技術伝承は、企業の信頼とブランド力を高める戦略的な取り組みです。外部への発信も含めて、積極的に進める価値があります。
持続可能な人材育成体制の構築
技術伝承は、持続可能な人材育成体制を構築するための基盤となります。
一時的な育成ではなく、継続的に人材を育てる仕組みがあることで、企業は長期的に安定した成長が可能になります。技術伝承を制度化・仕組み化することで、誰が教えるか、何を教えるかが明確になり、育成が属人的にならずに済みます。
持続可能な人材育成には、技術伝承の仕組みが不可欠です。企業の未来を支える基盤として、今から整備を進めることが重要です。
建設業界で技術伝承のデジタル化のステップ

建設業界で技術伝承を進めていく際のステップについて順を追って説明します。
経営層を含めた目的の設定
技術伝承のデジタル化を成功させるには、経営層を巻き込んだ明確な目的設定が不可欠です。
技術伝承のデジタル化は、単なる業務改善ではなく、組織全体の生産性や人材育成に直結する戦略的な取り組みです。経営層がその重要性を理解し、明確な目的を示すことで、現場の協力を得やすくなり、全社的な推進力が生まれます。
ある建設会社では、「技術の属人化を解消し、若手の育成スピードを2倍にする」という目標を経営層が掲げ、全社で技術伝承のデジタル化に取り組みました。結果として、現場の協力体制が整い、短期間で動画マニュアルの整備が進みました。
経営層が旗振り役となり、目的を明確にすることで、技術伝承のデジタル化は組織全体のプロジェクトとして機能しやすくなります。
プロジェクトチームの編成
技術伝承のデジタル化を推進するには、部門横断型のプロジェクトチームを編成することが重要です。
現場の実情を反映したコンテンツを作成するには、現場をよく知る人材の協力が不可欠です。経営企画部門などが事務局となり、各部門から管理者と若手社員を1名ずつ選出することで、現場視点と育成視点の両方を取り入れたバランスの良いチームが構成できます。
ある企業では、経営企画部が主導してプロジェクトチームを立ち上げ、施工部門・設計部門・安全管理部門などから管理職と若手を選出しました。若手の「分かりにくいポイント」とベテランの「伝えたい技術」をすり合わせながら、実践的な教材を作成しました。
プロジェクトチームの編成は、技術伝承の質を左右します。現場と経営の橋渡し役を担う体制づくりが成功の鍵です。
必要な項目の洗い出し
効果的な技術伝承には、まず「何を伝えるべきか」を明確にする必要があります。
技術伝承の対象は多岐にわたりますが、全てを網羅しようとすると非効率になります。業務の中で特に属人化している作業や、ミスが起きやすい工程、若手がつまずきやすいポイントなどを優先的に洗い出すことで、伝承すべき技術の優先順位が明確になります。
必要な項目の洗い出しは、技術伝承の土台です。現場の実態に即した優先順位をつけることで、効率的なデジタル化が実現します。
部署ごとにコンテンツ作成
技術伝承のコンテンツは、各部署が主体となって作成することで、実践的で現場に即した内容になります。
部署ごとに業務内容や必要な技術が異なるため、現場を熟知したメンバーが中心となってコンテンツを作成することが重要です。また、若手社員の視点を取り入れることで、「教える側の視点」と「学ぶ側の視点」の両方を反映した、分かりやすい教材が完成します。
部署ごとのコンテンツ作成は、現場に根ざした技術伝承を実現するための鍵です。現場の声を反映した教材づくりが、実効性を高めます。
プラットフォーム上に整理
作成した技術伝承コンテンツは、誰でもアクセスできるプラットフォーム上に整理・蓄積することが重要です。
せっかく作成したコンテンツも、必要な時に見つけられなければ意味がありません。動画、マニュアル、図面などを一元管理できるプラットフォームを活用することで、情報の検索性が高まり、現場での活用が進みます。また、更新やバージョン管理も容易になります。
ある企業では、プラットフォームを活用し「企業内大学」を設置し、部門別、カテゴリ別にコンテンツを整理しました。検索機能を強化したことで、現場からのアクセスしやすくなり、活用が定着しました。
プラットフォームへの整理は、技術伝承の「使われる仕組み」を作るステップです。誰でも簡単にアクセスできる環境が、継続的な活用を支えます。
現場での活用・ブラッシュアップ
技術伝承のコンテンツは、現場で実際に使いながら改善を重ねることで、より実用的なものになります。
一度作ったコンテンツも、現場で使ってみると「分かりにくい」「現実と合っていない」といった課題が見えてきます。現場でのフィードバックを基に、定期的に内容を見直し、改善を重ねることで、技術伝承の精度と効果が高まります。
ある企業では、現場での動画マニュアル使用後にアンケートを実施し、「もっと手元をアップで見たい」「音声解説があると助かる」といった声を反映。改善を重ねた結果、若手の理解度が向上し、教育時間の短縮にもつながりました。
技術伝承は「作って終わり」ではありません。現場での活用と改善を繰り返すことで、実践的なナレッジが蓄積されていきます。
▼技術伝承の事例については下記で詳しく解説しています。
⇒技術伝承の成功事例5選と人材育成の極意を徹底解説
まとめ:技術伝承はデジタル化しよう
建設業界における技術伝承の課題と解決策とは?デジタル化の方法など解説! について紹介してきました。
なぜ今「技術伝承」が建設業界で注目されているのか
建設業界で技術伝承がうまくいかない5つの理由
技術伝承の成功事例(建設業界の実例紹介)
建設業界で技術伝承を促進するための具体的な方法
建設業界での技術伝承がもたらすメリット
建設業界で技術伝承のデジタル化のステップ
本記事では、建設業界における技術伝承の重要性とその課題、さらには具体的な改善策について解説しました。
まず、建設業界が直面する技術の空洞化という深刻な問題があります。これは、ベテラン社員の退職によるノウハウの喪失が原因で、業務の属人化や暗黙知の共有不足が主な原因です。これを解決するためには、単なるマニュアル化を超えた「見える化」が必要です。
次に、若手の育成がうまく進まない現状についても紹介しました。若手社員の確保と育成が困難な中で、即戦力を期待される一方、育成環境が整備されていないという二重の課題に直面しています。ここでは、若手が安心して学べるような育成プログラムの設計や、ベテラン社員の役割を見直すことが必要です。特に、教え合いの文化を醸成し、コミュニケーションギャップを埋めることが不可欠と言えます。
そして、デジタルツールの導入や活用が進むことで、体系的な技術伝承の加速が期待できます。成功事例では、企業内大学の設立やコンテンツの標準化が行われ、若手の知識習得が促進されることで、若手の定着率が向上し、組織全体の力が底上げされたケースを紹介しました。技術伝承のデジタル化には、経営層の積極的な関与と明確な目的設定が求められます。
これらの取り組みは、単に現場の力を高めるだけでなく、企業全体のブランド力や信頼性の向上にもつながります。持続可能な人材育成体制の構築に向けて、今こそ全社を挙げて技術伝承を進めるべき時です。
株式会社LDcubeはこれまでの組織活性化や人材育成で培ったノウハウを生かしながら、これからの時代に適した人材を効果的に育成する環境構築を支援しています。
新入社員研修から管理職研修などの研修会の支援、社内トレーナーの育成支援、技術伝承に向けたLMSの導入と運用の支援などの支援実績も多くあります。
一度ご事情をお伺いできれば、貴社の状況にフィットした人材育成のご提案をさせていただくことができます。
各種ツールの無料のデモ体験会や研修プログラムの無料体験会、導入事例の紹介なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。