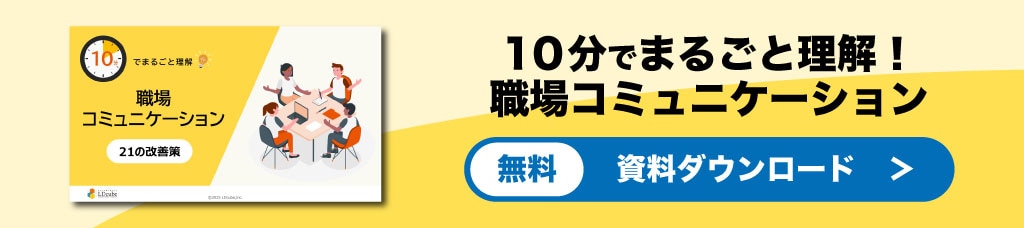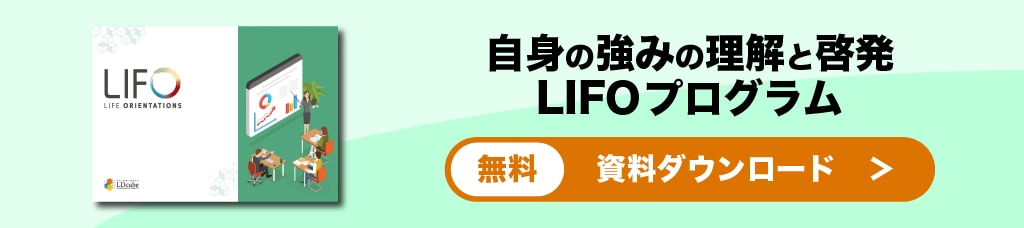働きやすい職場づくりのためのコミュニケーション改革とは?ポイントを解説!
企業の成功を左右する重要な要素として、近年ますます注目を集めているのが「働きやすい職場環境」です。生産性向上、人材確保、そして従業員満足度の向上を図るためには、働きやすい職場づくりが不可欠となっています。
しかし、その実現に向けて、多くの企業が見落としがちで核心的な要素があります。それが「コミュニケーション」です。
特にリモートワークの普及によって、従来の対面を前提としたコミュニケーション手法が通用しなくなり、組織内の情報共有や関係構築に新たな課題が生まれています。世代間ギャップによるコミュニケーションスタイルの違いも、職場の一体感を損なう要因となっています。
では、どのようにすれば真に働きやすい職場を実現できるのでしょうか?その答えは、戦略的なコミュニケーション改革にあります。単に情報伝達を効率化させるだけでなく、心理的安全性を確保し、部門を超えた協力関係を構築し、多様な働き方を支援するコミュニケーション環境を整えることが重要です。
本記事では、働きやすい職場づくりを実現するための具体的なコミュニケーション改革の7つのポイントを紹介します。
組織パフォーマンスと従業員エンゲージメントを向上させる実践的な方法から、すでに成功を収めている企業の事例まで、すぐに取り入れられる施策を解説します。これらのポイントを理解し実践することで、あなたの組織も「働きたい」と思われる職場へと変わるはずです。
▼コミュニケーションについては下記で詳しく解説しています。
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
目次[非表示]
- 1.働きやすい職場づくりとコミュニケーションの密接な関係
- 2.働きやすい職場づくりを阻む、現代のコミュニケーション上の課題
- 3.働きやすい職場づくりのためのコミュニケーション改革7つのポイント
- 3.1.① 心理的安全性を生み出す、オープンな対話文化の構築
- 3.2.② ミーティングを活用した、効果的なフィードバックの実践
- 3.3.③ ハイブリッド環境に最適なコミュニケーションツールの選定と活用
- 3.4.④ 雑談から生まれるアイデアを促進するオフィスレイアウト設計
- 3.5.⑤ 人材育成を加速させる双方向コミュニケーションの仕組みづくり
- 3.6.⑥ 部門間の壁を取り払う交流イベントの企画と実施
- 3.7.⑦ リモートワーカーの孤独感の解消
- 4.働きやすい職場づくりを実現するコミュニケーション改革のコツ
- 4.1.「職場単位」でワークショップを実施する
- 4.2.「共通言語」となる自己診断ツールを活用する
- 4.3.コミュニケーション改革に向けたガイドラインを設定する
- 4.4.翌日からガイドラインに沿って行動する
- 5.コミュニケーション研修を社内講師で展開した支援事例
- 6.働きやすい職場づくりに向けたコミュニケーションの改善ならLIFOがおすすめ!
- 7.まとめ:働きやすい職場づくりを成功させるコミュニケーション改革のポイント
働きやすい職場づくりとコミュニケーションの密接な関係

近年、企業が人材確保や業績向上のために「働きやすい職場づくり」に注力する動きが活発化しています。働きやすい職場の条件は多岐にわたりますが、特に重要な要素が「コミュニケーション」です。
良好なコミュニケーションが取れている職場は、情報伝達がスムーズになるだけでなく、従業員のモチベーションやチームワークの向上、組織全体の生産性向上にも直結します。
働きやすい職場づくりに不可欠な5つのコミュニケーション要素
働きやすい職場環境を構築するには、いくつかの重要なコミュニケーション要素が不可欠です。ここでは不可欠な要素を5つ紹介します。
①「情報共有」の円滑さ
上司と部下、同僚間での情報共有がスムーズに行われることで、業務の進行に必要な情報が適切なタイミングで共有され、効率的な業務遂行が可能になります。
②「心理的安全性」の確保
心理的安全性とは、自分の意見や考えを表明しても否定されないという安心感のことです。この安心感があることで、従業員は新しいアイデアを提案したり、問題点を指摘したりすることができます。
|
③「フィードバック文化」の醸成
適切なタイミングでの建設的なフィードバックは、業務の質向上と個人の成長につながります。
④「立場を超えた対話」の機会
職位や部署に関係なく、自由に意見交換ができる環境は、新しいアイデアや改善点の発見を促進します。
⑤「多様な働き方」に対応したコミュニケーション
リモートワークなど働き方が多様化する中、時間や場所に縛られないコミュニケーション手段の確立が必要です。
▼心理的安全性やフィードバックについては下記で詳しく解説しています。
職場コミュニケーションが組織パフォーマンスに与える影響
良好な職場コミュニケーションは、組織のパフォーマンスにさまざまな影響を与えます。例をいくつかご紹介します。
まず「問題解決の迅速化」があります。コミュニケーションが円滑な職場では、問題発生時に速やかに情報が共有され、早期解決が可能になります。
次に「業務効率の向上」があります。必要な情報が適切なタイミングで共有されることで、無駄な作業や重複作業を減らせます。また、会社全体の方針が共有されることで、自分の業務の位置づけを理解し、より効果的に業務を遂行できます。
また、「イノベーションの促進」があります。異なる部署や立場の人々が自由に意見を交換できる環境では、多様な視点からのアイデアが生まれやすくなります。
さらに「チームワークの強化」と「ミスやトラブルの早期発見」も見逃せません。良好なコミュニケーションを通じて信頼関係が構築され、チーム協力体制が強化されるとともに、小さなミスも早期に発見・対処できるようになります。
質の高いコミュニケーションが従業員エンゲージメントを高める理由
質の高いコミュニケーションは、従業員エンゲージメントを高めます。その理由は下記のように、5つあります。
まず「帰属意識の向上」があります。コミュニケーションを通じて会社の方針や価値観が共有されることで、従業員は組織の一員としての意識を強めます。経営者や上司からの直接的なコミュニケーションは、従業員自身が「認められている」という実感を生み出します。
次に「自己の価値への認識」です。適切なフィードバックにより、従業員は自分の貢献が認められていると感じ、モチベーションが向上します。
また、「職場での人間関係の充実」も重要です。日常的なコミュニケーションで同僚との関係が深まることで、職場が居心地の良い場所となり、離職率の低下にもつながります。
さらに「成長機会の認識」と「会社への貢献意欲の強化」があります。上司とのコミュニケーションでキャリアパスを明確にし、自分の仕事が会社全体の目標達成にどのようにつながるかを理解することで、より積極的に貢献しようという意欲が高まります。
質の高いコミュニケーションにより、従業員は「仕事をこなす」から「会社の成功に貢献する」という意識へと変化し、これが従業員エンゲージメントの向上につながるのです。
▼従業員エンゲージメントを高める方法については下記で詳しく解説しています。
⇒エンゲージメントを高める18の施策とは?─効果的な取り組みと成功ポイントを解説!
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
働きやすい職場づくりを阻む、現代のコミュニケーション上の課題

働きやすい職場づくりを進める上で、現代特有のコミュニケーション課題が数多く存在します。テクノロジーの進化や働き方の多様化、世代構成の変化など、さまざまな要因が新たな課題をもたらしています。
これらを理解し適切に対処することが、働きやすい職場づくりの第一歩となります。
リモートワーク時代の職場コミュニケーションの変化
リモートワークの普及は、職場コミュニケーションのあり方を根本から変えました。「同じ空間における自然な対話」が減少し、代わりにビデオ会議やチャットツールを介したコミュニケーションが主流となっています。
最も大きな課題は、非言語コミュニケーションの欠如です。対面では自然と伝わる表情や身ぶり、声のトーンなどの微妙なニュアンスが、デジタルツールを介すると伝わりにくくなります。
また、「随時のコミュニケーション」から「計画的なコミュニケーション」への移行も課題です。オフィスの廊下での会話や昼食時の雑談といった自然発生的な情報交換の機会が失われています。
リモートワークが続くと、「チームの一体感がなくなり、従業員が何を感じているのか、何に悩んでいるのか把握しにくくなる」という問題も生じやすくなります。
職場メンバーの世代間ギャップの存在
現代の職場では、デジタルネイティブ世代からベテラン世代まで、幅広い年齢層の従業員が共に働いています。この多様性は組織に豊かな視点をもたらす一方、コミュニケーション上の課題も生み出しています。
職場メンバーの世代間ギャップにより、コミュニケーションスタイルの違いが顕著です。若い世代はチャットツールを好み、簡潔なコミュニケーションを好む傾向がある一方、年配の世代は対面での会話や詳細な文書を重視する傾向があります。
職場メンバーの世代の違いによって、価値観の違い生じます。Z世代はワークライフバランスを重視する傾向がある一方、従来の世代は仕事への献身を美徳とする文化で育ってきました。こうした違いが互いの行動の解釈に影響し、誤解を生じさせることがあります。
コミュニケーション不足
現代の職場における根本的な課題の一つが、コミュニケーション量の不足です。リモートワークの増加や業務の専門化、組織の肥大化により、必要な情報が適切に共有されないケースが増えています。
その結果、「伝えたつもりだったけど伝わってなかった」という事態が頻発し、初歩的なミスが増加します。これにより業務の重複や手戻りが発生し、効率が低下します。
また、各部署や個人の「孤独化」による組織の一体感の喪失や、新入社員教育の困難さも問題となっています。オフィスの雰囲気が分からない状況での業務習得は難しくなり、職場文化の継承や暗黙知の共有が十分に行われないリスクがあります。
さらに、メンタルヘルスの観点からも「1人で仕事をしすぎるのは良くない」というリスクが指摘されています。コミュニケーション不足は孤独感や疎外感を生み出し、従業員の心理的健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
▼コミュニケーション不足の解決策については下記で詳しく解説しています。
⇒職場のコミュニケーション不足の効果的な解決策とは?原因と対策まで解説!
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
働きやすい職場づくりのためのコミュニケーション改革7つのポイント

ここまで解説してきたように、働きやすい職場づくりには質の高いコミュニケーションが不可欠であり、現代企業はさまざまな課題に直面しています。では具体的に、どのようなコミュニケーション改革を行えば、真に働きやすい職場を実現できるのでしょうか。
ここでは、コミュニケーション改革を成功させるための7つの重要ポイントを紹介します。
① 心理的安全性を生み出す、オープンな対話文化の構築
働きやすい職場づくりの土台となるのが、心理的安全性に基づくオープンな対話文化です。
心理的安全性とは、自分の意見や考えを表明しても否定されたり馬鹿にされたりしないという安心感のことです。この安心感があってこそ、メンバーは自由に発言し、創造的なアイデアを提案できるようになります。
心理的安全性の構築には、まず経営者や管理職からの率先垂範が重要です。上層部が自らの失敗や学びを率直に共有することで、「失敗を恐れず、学びとして共有する文化」が醸成されます。
また、日常的な対話の質にも気を配る必要があります。下記のようなことを念頭に置き、否定的な言葉の使用を減らし、代わりに建設的な言葉遣いを心がけましょう。
|
▼心理的安全性を高めるコミュニケーションについては下記で詳しく解説しています。
⇒心理的安全性を高めるコミュニケーションのあり方とは?本質と具体策について解説!
② ミーティングを活用した、効果的なフィードバックの実践
効果的なフィードバックは、働きやすい職場づくりにおいて重要な要素です。ミーティングを活用して、定期的かつ建設的なフィードバックの機会を設けることで、組織全体のパフォーマンス向上と個人の成長を促進できます。
効果的なフィードバックのカギは、「具体性」と「行動指向」です。「もっと頑張ってほしい」といった抽象的な言葉ではなく、「○○のプレゼンテーションでは、データの具体例を3つ以上入れるとより説得力が増すと思います」といった具体的で行動に結びつく表現を心がけましょう。
定期的なチームミーティングでは、プロジェクトの進捗だけでなく、チームとしての強みや改善点についても話し合う時間を設けることが大切です。例えば、「先週うまくいったこと」「改善できること」「来週に向けた行動計画」といった項目を定例会議のアジェンダに組み込むことで、継続的な改善サイクルを構築できます。
また、フィードバックは双方向であることが重要です。上司から部下へのフィードバックだけでなく、部下から上司へ、あるいは同僚間でのフィードバックも奨励する文化をつくりましょう。
▼心理的安全性やフィードバックについては下記で詳しく解説しています。
⇒効果的なフィードバックのやり方とは?心構えと具体的な手法を解説!
③ ハイブリッド環境に最適なコミュニケーションツールの選定と活用
リモートワークとオフィスワークが混在するハイブリッド環境では、適切なコミュニケーションツールの選定と活用が働きやすさのカギを握ります。単にツールを導入するだけでなく、それらを組織文化や業務フローに合わせて最適化することが重要です。
まず、コミュニケーションの目的に応じたツールの使い分けを明確にしましょう。下記のように使い分けのガイドラインを作成し、全社で共有することで、コミュニケーションの効率化が図れます。
|
ツールの選定においては、使いやすさとセキュリティーのバランスを考慮することが大切です。また、全ての従業員がツールを効果的に使えるよう、定期的なトレーニングや使用ガイドラインの提供も欠かせません。
ハイブリッド環境では、リモートワーカーが情報格差を感じないような配慮も重要です。例えば、オフィスでの対面ミーティングにはリモート参加者のための画面を設置し、チャットや共有ドキュメントに議事録をリアルタイムで残すなどの工夫が効果的です。
④ 雑談から生まれるアイデアを促進するオフィスレイアウト設計
働きやすい職場づくりにおいて、オフィスの物理的環境は思いのほか大きな影響を持ちます。特に、計画された会議だけでなく、自然発生的な雑談やカジュアルな対話から生まれるアイデアや情報交換の価値は計り知れません。
まず重要なのは、従業員が自然に出会い、交流できる「オープンスペース」の設置です。カフェエリアや休憩スペースなど、仕事から少し離れてリラックスできる場所は、部門や階層を超えた自然な交流を生み出します。
また、集中作業向けの静かなブース、チーム討議のためのミーティングスペース、創造的な対話ができるラウンジスペースなど、多様な作業環境を用意することで、従業員は最適な場所を選んで効率よく働けるようになります。
オフィス内の動線設計も重要なポイントです。異なる部署や機能を持つエリアを結ぶ通路や階段、エレベーターホールなどを工夫することで、普段接点のない従業員同士が自然に出会う機会を増やせます。
⑤ 人材育成を加速させる双方向コミュニケーションの仕組みづくり
働きやすい職場づくりにおいて、人材育成は極めて重要な要素ですが、その成否を左右するのが双方向コミュニケーションの質です。従来の一方的な指導や研修だけでなく、互いに学び合い、成長し合える仕組みを構築することで、人材育成のスピードと効果を大きく高めることができます。
効果的なのは、メンター制度の導入です。経験豊富な先輩社員と若手社員をペアリングし、定期的な対話の機会を設けることで、形式的な研修では得られない実践的なノウハウや暗黙知の共有が可能になります。ただし、これは単なる「教える-教わる」の関係ではなく、互いに学び合う関係性を目指すべきです。
次に、社内勉強会やナレッジシェアリングの場の創設も有効です。例えば、毎月1回、異なる部署のメンバーが自分の専門知識や成功事例を共有する「学習交流会」セッションを開催することで、組織全体の知識レベルを底上げできます。
また、下記のように、他の取り組みもあります。
|
1on1ミーティングも、効果的な人材育成の手法です。上司と部下が定期的に1対1で対話する時間を設け、業務の進捗だけでなく、キャリア目標や成長に必要なスキル、直面している課題などについて話し合います。
⑥ 部門間の壁を取り払う交流イベントの企画と実施
組織が大きくなるにつれて生じがちな「サイロ化」(部門ごとの分断)は、働きやすい職場づくりにおいて大きな障壁となります。部門間の壁を取り払い、組織全体としての一体感と協力体制を構築するためには、意図的な交流イベントの企画と実施が効果的です。
最も基本的なアプローチは、部門横断プロジェクトの実施です。異なる部署からメンバーを集め、共通の課題解決や新しい取り組みに協働で当たることで、自然と部門間の相互理解と協力関係が生まれます。
より気軽な交流機会として、ランチタイム交流会の実施も有効です。例えば、毎週水曜日のランチタイムを「クロスランチデー」として、異なる部署のメンバーがランダムにグループ分けされて一緒に食事をする機会を設けるといった取り組みが考えられます。
定期的な社内交流イベントも効果的です。スポーツ大会、社内ハッカソン、ボランティア活動、季節のお祝いイベントなど、業務とは異なる文脈での交流は、同僚の新たな一面を発見する機会となります。
⑦ リモートワーカーの孤独感の解消
リモートワークが一般化する中、働きやすい職場づくりにおいて避けて通れないのが「リモートワーカーの孤独感」への対応です。物理的な距離があっても心理的な距離を縮め、帰属意識を持って働ける環境を整えることが、組織全体のパフォーマンス向上につながります。
まず取り組みたいのが、オンラインコーヒーブレイクの導入です。例えば、週に2〜3回、15〜30分程度の気軽なオンライン雑談の時間を設け、業務とは関係ない話題で交流する機会をつくります。
また、オンラインでのチームビルディング活動も効果的です。バーチャルクイズ大会、オンラインランチ会など、共通の体験を通じてチームの絆を強化する活動を定期的に行うことで、距離を超えた一体感を醸成できます。
下記のような取り組みもおすすめです。
|
情報格差の解消も重要です。オフィスで自然と共有される情報や雑談から生まれる気付きが、リモートワーカーには届きにくいという課題があります。
これを解消するために、「週間ニュースレター」のような形で、オフィスでの出来事や雑談から生まれたアイデアを定期的に共有する仕組みをつくりましょう。
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
働きやすい職場づくりを実現するコミュニケーション改革のコツ

ここまで、働きやすい職場づくりのためのコミュニケーション改革の重要性と具体的なポイントについて見てきました。しかし、「理解はできたけれど、実際にどう始めればいいのか」と悩む方も多いでしょう。
コミュニケーション改革は一朝一夕で成し遂げられるものではありませんが、適切なステップを踏んで進めれば、確実に前進させることができます。ここでは、明日から実践できるコミュニケーション改革のコツについて、段階的に解説します。
「職場単位」でワークショップを実施する
コミュニケーション改革の第一歩として、「職場単位」でワークショップを実施することが効果的です。全社一斉ではなく、部署やチーム単位の少人数で行うことで、より具体的な課題抽出と解決策の検討が可能になります。
ワークショップでは、まず現状のコミュニケーション上の課題を洗い出します。ブレインストーミングやKJ法などを活用し、「情報共有が不十分」「部門間の連携が取れていない」といった問題点を付箋紙などで可視化しましょう。この際、「誰が」という個人の責任追及ではなく、「何が」という状況や仕組みに焦点を当てることが重要です。
次に、理想的なコミュニケーションの状態について話し合います。「どのような情報がどのタイミングで共有されるべきか」「上司と部下、部署間ではどのようなコミュニケーションが望ましいか」といった具体的なイメージを共有します。現状と理想のギャップを明確にすることで、取り組むべき課題の優先順位付けがしやすくなります。
ワークショップのファシリテーターは、可能であれば外部の専門家や他部署のメンバーに依頼するのが望ましいでしょう。内部の人間だと既存のパワーバランスや先入観が働き、本音の議論が難しくなる場合があります。
ワークショップの成果は必ず文書化し、参加者全員で共有するとともに、定期的な振り返りの機会を設けることで、改革の進捗を確認していきましょう。
▼職場単位で行うことが有効な理由については下記で詳しく解説しています。
⇒職場の活性化につなげる方法とは?アイデアやポイントを紹介!
「共通言語」となる自己診断ツールを活用する
コミュニケーション改革を進める上で、メンバー間の相互理解を促進するための「共通言語」を持つことが重要です。この役割を果たすのが、コミュニケーションスタイルや行動特性を診断する自己診断ツールです。
代表的なものとしては、LIFO®やDiSC®、MBTI®などの行動特性診断があります。これらのツールを活用することで、コミュニケーションスタイルの違いを客観的に理解できるようになります。
診断結果はチーム内で共有し、お互いの特性や傾向について理解を深めましょう。例えば、「私はディテールを重視するタイプなので、細部まで確認したがる傾向があります」といった形で自己開示を行うことで、誤解を減らし、効果的なコミュニケーションが可能になります。
また、診断結果の共有で下記のような効果を得ることができます。
|
▼共通言語づくりの重要性については下記で詳しく解説しています。
⇒会社のコミュニケーション活性化のカギとは?カギは「共通言語」!施策や事例を紹介
コミュニケーション改革に向けたガイドラインを設定する
ワークショップや自己診断ツールを通じて課題と改善方向性が見えてきたら、次のステップとして具体的なコミュニケーションガイドラインを設定しましょう。ガイドラインは、組織内のコミュニケーションに関する「ルール」や「約束事」を明文化したものです。
ガイドライン作成のポイントは、メンバー全員が参加して策定することです。トップダウンで押し付けられたルールではなく、自分たちで考えて決めたルールほど守られやすいものはありません。
ガイドラインの内容は、抽象的な理念ではなく、具体的で実行可能な項目にすることが重要です。例えば、「リモートワーク時は、朝と夕方にチャットで業務状況を共有する」「会議では、発言していない人に積極的に意見を求める」などの具体的な行動レベルで記述します。
また、ガイドラインは一度作ったら終わりではなく、定期的に見直しとアップデートを行うことも大切です。3カ月に1度程度、見直しミーティングを設け、実態に合わせて柔軟に修正していきましょう。
翌日からガイドラインに沿って行動する
コミュニケーション改革の最も重要なステップは、実際に「行動する」ことです。どんなに素晴らしいガイドラインを作成しても、それが日常の行動に反映されなければ意味がありません。
行動変容を促すには、最初から大きな変化を求めるのではなく、小さな一歩から始めることが効果的です。例えば、「今日は会議中に発言していない人に積極的に意見を求めよう」「今日はフィードバックを1人に行おう」といった具体的で達成可能な小さな目標を設定し、実践してみましょう。
また、行動の変化を継続させるには、進捗の可視化が効果的です。例えば、「フィードバックカレンダー」を作成し、毎日のフィードバック実施状況を記録する、週1回のチーム会議で先週のコミュニケーションについて良かった点を共有するなど、定期的に振り返りと共有を行う仕組みをつくりましょう。
リーダーやマネジャーが率先して新しいコミュニケーション方法を実践することも重要です。リーダー自身が率先して変化を体現し、その姿を見せることが、組織全体の変革を促す強力な推進力となります。
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
コミュニケーション研修を社内講師で展開した支援事例

社員数: 2,000名以上
事業:医薬品、機能食品の製造・販売
導入前の課題
コロナ禍による営業スタイルの変化と職場のコミュニケーション減少
~打開のカギを握るのは営業所長~
製薬業界の取り巻く環境変化の一つとして、withコロナ時代においてテレワークが推進され、営業所内での「対面でのコミュニケーション」は圧倒的に減少していました。
特にコロナ前まではできていた横や斜め(同僚間や別部門)の関わりが少なくなり、業務上の全ての判断や相談がラインの上長に集中するようになりました。出社することで自然と社内情報が入ってきていた環境が、コロナ禍によりなくなってしまいました。
また、MR(医薬情報担当者)の情報提供活動においてもオンラインでの対応が求められるようになり、新しい方法を模索しないといけない状況になりました。
営業所内の目標達成や職場内のコミュニケーション向上のカギは営業所長が握っていることから、営業所長がリーダーシップを発揮し、問題解決をしていくための方法を探していました。
取り組みの詳細
営業所長による職場ワークショップを完全オンラインで実施
~半年間で7割以上の営業所に展開~
MRを取り巻く環境変化に合わせて、マインドやスキル強化の一つとしてLIFOプログラムの導入を決めました。3年でLIFOを社内の共通言語にすることを目指して、まずは2020年5月に営業部門の教育担当4名がLIFOプログラムライセンスを取得しました。
次に営業所長がリーダーシップを発揮し、自職場の問題解決を行うスキルを習得するために、営業所長対象にマネジメント実践スキル講座(MSS認定講座)を実施しました。講座を通じて、職場の問題解決のための道具とスキルを身に付けた営業所長は各職場にてチームづくりワークショップを実施しました。
4名のプログラムライセンス取得者(ライセンシー)は営業所長への個別指導や相談会など、職場展開に向けてのサポートを積極的に行いました。コロナ禍ということもあり、プログラムライセンス取得から、MSS認定、ワークショップ実施まで全てオンラインで実施し、半年間で7割以上の営業所に展開していきました。
2021年度以降、新任営業所長はMSS認定講座を受講し、LIFOという道具とスキルを身に付ける機会を作っています。2023年度現在では全ての営業所でチームづくりワークショップの実施が完了し、2巡目以降は各職場の課題に合わせてタイムマネジメントや期待役割などのテーマで実施しています。
導入の成果
「コミュニケーションの改善が期待できる!」「他部署へもLIFOを推薦したい!」の声多数
ワークショップ実施後に行ったアンケートでは、7割以上の方が「LIFO診断を受けて、自己理解ができた」、「部署内のグループワークの実施により他者理解ができた」、「LIFOの実施によりコミュニケーションの改善が期待できる」と回答をいただいています。
また、営業所長の9割近くの方が「LIFOの導入を他部署へも推薦したい」と回答いただきました。
タイムマネジメントのワークショップを実施した営業所においては、チーム活動を効果的に進めるためのガイドラインを決めることで、チームの結束力が高まったといった声もありました。
営業部門での評判を聞き、人事部門でもLIFOプログラムライセンスを取得し、経営幹部を巻き込むと同時に、本社の各部門においてもワークショップを順次進めています。導入から3年が経過し、LIFOが社内の共通言語になりつつあります。
▼事例全文は下記をご覧ください。
⇒日本新薬株式会社様LIFO・ITS導入事例
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
働きやすい職場づくりに向けたコミュニケーションの改善ならLIFOがおすすめ!
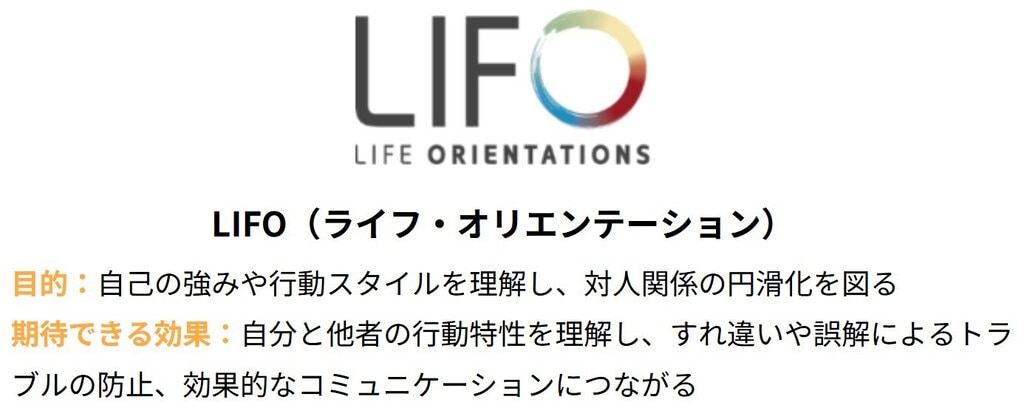
部下とのコミュニケーション改善のためには、コミュニケーション能力を高めることが必要です。
そこで役立つのがコミュニケーション研修です。研修を通じて、自分の強みと改善点を具体的に把握し、実践的なスキルを身に付けることができます。
そこで一つの有力なツールとして「LIFO(ライフォ)」があります。
自己診断ツールLIFOとは
LIFO(Life Orientations)は、個人の行動スタイルを診断する自己診断ツールです。このツールは、自分の強みや行動パターンを理解するために役立ちます。
LIFOは4つの基本スタイルに基づいており、これらのスタイルはそれぞれ異なる行動特性や価値観を持っています。
自分がどのスタイルに属しているかを知ることで、より良いコミュニケーション方法やストレス時の行動傾向を把握することができます。
LIFOを活用したコミュニケーション研修
LIFOを活用したコミュニケーション研修では、まず参加者が自己診断を行い、自分の行動スタイルを理解します。この診断結果を基に、どのように他者と効果的にコミュニケーションを取るかを学びます。
研修では以下のような内容が含まれます。
|
LIFOを取り入れた研修に参加することで、個人のコミュニケーションスタイルを理解し、それをベースに他者との関係を改善するスキルを獲得できます。
これにより、職場や日常生活でのコミュニケーションがよりスムーズで効果的になることが期待できます。
まとめ:働きやすい職場づくりを成功させるコミュニケーション改革のポイント
働きやすい職場づくりのためのコミュニケーション改革とは?ポイントを解説!について紹介してきました。
- 働きやすい職場づくりとコミュニケーションの密接な関係
- 働きやすい職場づくりを阻む、現代のコミュニケーション上の課題
- 働きやすい職場づくりのためのコミュニケーション改革7つのポイント
- 働きやすい職場づくりを実現するコミュニケーション改革のコツ
- コミュニケーション研修を社内講師で展開した支援事例
- 働きやすい職場づくりに向けたコミュニケーションの改善ならLIFOがおすすめ!
- まとめ:働きやすい職場づくりを成功させるコミュニケーション改革のポイント
働きやすい職場は単なる物理的環境や制度だけでなく、そこで交わされるコミュニケーションの質が大きく影響することが明らかになりました。
コミュニケーション改革を成功させるカギは、まず「心理的安全性」を基盤とした対話文化を構築することです。メンバー全員が自由に意見を表明でき、失敗を恐れずに挑戦できる環境があってこそ、真の意味での働きやすさが実現します。
また、現代のハイブリッド環境に適したコミュニケーションツールの選定と活用、雑談から生まれるアイデアを促進するオフィスレイアウト、部門間の壁を取り払う交流イベントなど、多角的なアプローチが重要です。特にリモートワークが増加する中、オンラインとオフラインをシームレスにつなぐ工夫が求められています。
コミュニケーション改革は一朝一夕には実現しません。職場単位でのワークショップ実施、共通言語となる自己診断ツールの活用、具体的なガイドラインの設定と実践という段階的なプロセスを踏むことで、着実に前進させることができます。
重要なのは、「理解」から「行動」へのステップです。小さな一歩から始め、継続的に実践していくことで、組織文化としてのコミュニケーションの質が徐々に向上していきます。
そして、質の高いコミュニケーションが実現する職場では、従業員のエンゲージメントと組織のパフォーマンスが共に高まり、真の意味での「働きやすい職場」が実現するのです。
株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。