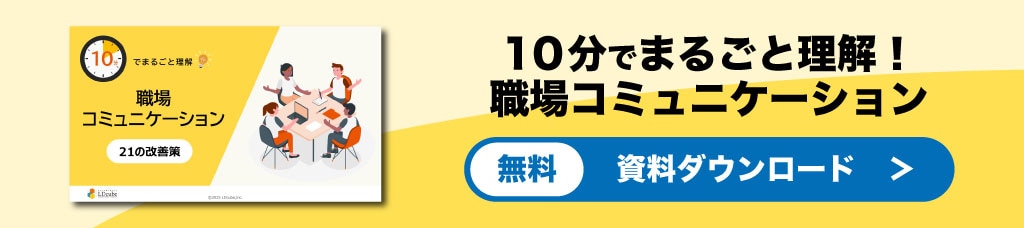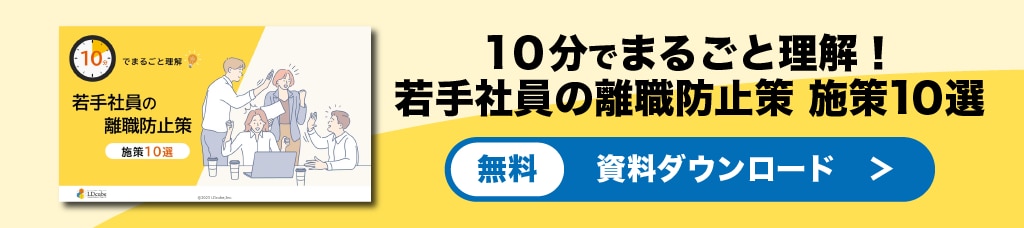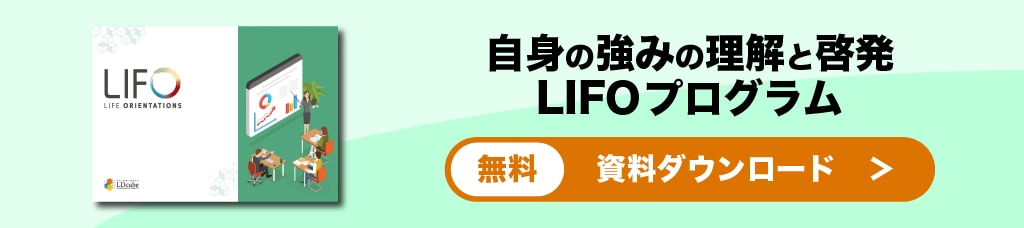社員同士のコミュニケーション活性化の秘訣とは?重要性から事例まで紹介!
近年、テレワークやハイブリッドワークの普及により、企業における社員コミュニケーションの重要性が改めて注目されています。「社内の情報共有がうまくいかない」「部署間の連携が取れていない」「社員の孤立感が高まっている」など、多くの企業が社員コミュニケーションに関する課題を抱えているのではないでしょうか。
人材コンサルティング企業のエン・ジャパン株式会社の調査によれば、退職理由の第1位は「職場の人間関係」であり、全体の46%を占めています。また、HR総研の調査では、社員間のコミュニケーション不足が業務の障害になると考える企業は全体の9割以上に上ります。
社員コミュニケーションの低下は、単なる職場の雰囲気の問題だけではなく、業務効率の低下、モチベーションの低下、離職率の上昇、ひいては顧客満足度の低下など、企業経営に深刻な影響を及ぼします。一方で、適切な施策によって社員コミュニケーションを活性化させることができれば、生産性の向上やイノベーションの創出など、多くのメリットが期待できます。
本記事では、社員コミュニケーションの活性化によって組織力を高める7つの秘訣と具体的な施策をご紹介します。オンライン、オフラインそしてハイブリッドな働き方それぞれに適した実践的なアプローチを解説していますので、貴社の課題解決にぜひお役立てください。
▼コミュニケーションについては下記で詳しく解説しています。
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
目次[非表示]
- 1.社員同士のコミュニケーション活性化に最適な方法!
- 1.1.職場単位でワークショップを行う
- 1.2.自己診断ツールを活用する
- 2.社員同士のコミュニケーションの希薄化が招く5つの経営リスク
- 3.社員同士のコミュニケーション改善がもたらす4つの経営メリット
- 4.オンラインで実現する、効果的な社員同士のコミュニケーション施策
- 5.オフィス環境で社員同士のコミュニケーションを促進する具体策
- 6.ハイブリッドワーク時代に適した社員同士コミュニケーション戦略
- 7.社員同士コミュニケーション改善を成功させる実践ステップ
- 7.1.社員同士のコミュニケーション状況の現状を把握する
- 7.2.自社の課題に合ったコミュニケーションツールを選定する
- 7.3.経営層が率先してコミュニケーション改善を行う
- 7.4.効果的な施策を展開する
- 7.5.定期的な効果測定を行う
- 8.社員同士のコミュニケーション活性化には職場単位での研修が最適
- 9.社員同士のコミュニケーション活性化ならLIFO®がおすすめ!
- 10.LIFOを活用して社内トレーナーがコミュケーション研修を展開している事例
- 11.まとめ:社員コミュニケーション強化で組織力を高めよう
社員同士のコミュニケーション活性化に最適な方法!

社員同士のコミュニケーションを活性化させるには、単に「もっと話しましょう」と呼びかけるだけでは不十分です。組織的かつ戦略的なアプローチが必要になります。
ここでは、特に効果的な二つの方法をご紹介します。職場の状況に合わせて取り入れてみましょう。
職場単位でワークショップを行う
コミュニケーション活性化の第一歩として、職場単位でのワークショップの実施が効果的です。ワークショップでは、日常業務から離れた環境で、社員同士が互いの考えや価値観を共有し、理解を深める機会を提供できます。
特に効果的なワークショップのテーマとしては以下が挙げられます。
|
ワークショップの実施は1度きりにせず、定期的に実施することをおすすめします。定期的に実施することで、日常のコミュニケーションにも良い影響を与えます。
また、外部の専門家を招くことで、客観的な視点や専門知識を取り入れることができ、効果を高められるでしょう。
自己診断ツールを活用する
コミュニケーションスタイルの自己診断ツールを活用することも非常に効果的です。これらのツールを使うことで、社員一人一人が自分のコミュニケーションの特徴や強み、改善点を客観的に把握できるようになります。
自己診断ツールの活用メリットには次のようなものがあります。
|
診断結果をチーム内で共有することで、「なぜあの人はそのような反応をするのか」という疑問が解消され、相互理解が深まります。
ただし、診断結果の共有は強制ではなく、あくまで自発的に行うよう配慮しましょう。
また、診断結果はあくまで参考情報であり、個人を評価するためのものではないことを明確にしておくことも重要です。
▼職場単位でワークショップに取り組むことの効果については下記で詳しく解説しています。
⇒職場の活性化につなげる方法とは?アイデアやポイントを紹介!
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
社員同士のコミュニケーションの希薄化が招く5つの経営リスク

社員間のコミュニケーションが希薄化すると、組織にとってさまざま負の影響をもたらします。HR総研の調査では、約7割の企業が「社内コミュニケーションに課題がある」と感じているという結果が出ています。
そのような課題が解決されないまま放置されると、以下の5つの深刻な経営リスクへと発展する可能性があります。
情報共有の遅れが引き起こす、業務効率の著しい低下
コミュニケーション不足は、まず情報共有の遅れや不足につながります。重要な情報が適切なタイミングで関係者に届かないことで、意思決定の遅れや不適切な判断を招きます。
具体的なリスクとしては以下が挙げられます。
|
こうした非効率な状況が積み重なると、企業全体の生産性低下につながり、競争力の低下を招きかねません。
社員の孤立感増加によるモチベーション低下
コミュニケーション不足は、社員の孤立感を高め、モチベーションの低下を引き起こします。特にテレワークが普及した現在、この傾向はより顕著になっています。
孤立感がもたらす具体的な問題には、以下が挙げられます。
|
モチベーションが低下した社員が増えると、組織全体の活力が失われ、イノベーションが生まれにくい環境になってしまいます。
人間関係の悪化による離職率上昇
人間関係の悪化は離職の大きな要因となります。エン・ジャパンの調査によると、退職理由の第1位は「職場の人間関係が悪い」(46%)となっています。
人間関係の悪化が離職につながるプロセスには、以下が挙げられます。
|
離職率の上昇は、採用コストの増加、ナレッジの喪失、チームワークの崩壊など、多方面において負の影響をもたらします。
▼人間関係については下記で詳しく解説しています。
⇒「人間関係で疲れて仕事を辞めたい」と思ったら、すべきこととは?ポイント解説!
部署間の連携不足がもたらす組織の分断
コミュニケーション不足は、特に部署間で顕著になりがちです。いわゆる「サイロ化」と呼ばれる現象で、各部署が独自の目標だけを追求し、全体最適を見失うリスクがあります。
部署間連携不足の具体的な影響は下記のようなものです。
|
組織の分断は、企業としての一体感を失わせ、経営方針の浸透も困難にします。
社内コミュニケーション不足が顧客満足度に与える悪影響
社内のコミュニケーション不足は、最終的に顧客満足度の低下にもつながります。社員間で情報が適切に共有されないと、顧客に対して一貫性のないサービスや対応をしてしまう恐れがあります。
顧客満足度低下のプロセスは下記のよう減少となって現れます。
|
顧客満足度の低下は直接的な売上減少につながるだけでなく、企業の評判を傷つけ、長期的な成長の妨げにもなり得ます。
▼コミュニケーション不全については下記で詳しく解説しています。
⇒職場でのコミュニケーション不全の原因と改善策!管理職が実践すべき対策とは
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
社員同士のコミュニケーション改善がもたらす4つの経営メリット

社員間のコミュニケーションを改善することで、組織にはさまざまなポジティブな変化がもたらされます。効果的なコミュニケーションは、単なる情報交換の円滑化にとどまらず、企業の業績や組織風土にも大きく貢献します。
ここでは、経営的視点から見た4つのメリットについて解説します。
チームワーク強化による生産性向上
良好なコミュニケーションは、チームワークを強化し、結果として生産性の向上につながります。情報共有がスムーズに行われることで、業務の重複が減少し、効率的な協働が可能になります。
生産性向上のメカニズム
|
実際、社内コミュニケーションが活性化した企業では、会議時間の短縮、決裁プロセスの迅速化など、目に見える形で業務効率の改善が報告されています。
個人の能力を最大限に引き出し、チーム全体のパフォーマンスを高める効果があるのです。
▼チームワークを高めるチームビルディング研修については下記で詳しく解説しています。
⇒チームビルディング研修を企業で行う際のポイントとは?おすすめ展開法も紹介!
活発な意見交換から生まれるイノベーションの創出
コミュニケーションが活発な組織では、異なる視点や専門知識を持つ社員間の意見交換が促進され、新たなアイデアやイノベーションが生まれやすくなります。
イノベーション創出のポイント
|
例えば、日常的な雑談や部署を超えた交流の中から、思いがけない製品アイデアや業務改善案が生まれることがあります。
社員が自由に意見を交わせる風土を醸成することで、企業の競争力強化につながるイノベーションの確率が高まります。
社内情報共有の質向上による顧客対応力の向上
社内のコミュニケーション改善は、顧客対応力の向上にも直結します。特に顧客接点のある部門(営業、カスタマーサポートなど)と、バックオフィス部門(開発、生産など)との連携が強化されることで、顧客満足度が大きく向上します。
顧客対応力向上の具体例
|
顧客対応力の向上は、顧客満足度の上昇、リピート率の向上、さらには口コミによる新規顧客獲得などの形で、企業の収益向上にもつながります。
サービス・プロフィット・チェーン理論でも示されているように、社内の満足度向上が顧客満足につながる好循環を生み出すのです。
エンゲージメント向上で実現する離職率の大幅低下
良好なコミュニケーション環境は、社員のエンゲージメント(会社への愛着や貢献意欲)を高め、離職率の低下に貢献します。社員が自分の意見や貢献が認められていると感じることで、職場への帰属意識が強まります。
エンゲージメント向上のポイント
|
エンゲージメントの向上は、離職率の低下だけでなく、採用コストの削減、組織内の知識・スキルの獲得につながります。加えて、社員による前向きな口コミが増えることで、優秀な人材の獲得機会の増加も期待できます。
社員のモチベーションと定着率を高めることは、持続的な企業成長の基盤となるのです。
▼若手社員の離職防止策については下記にまとめています。
オンラインで実現する、効果的な社員同士のコミュニケーション施策

テレワークやリモートワークの普及に伴い、オンラインでのコミュニケーション手段の重要性が高まっています。対面でのコミュニケーションが制限される中でも、適切なツールと運用方法を選択することで、効果的な社員間コミュニケーションを実現できます。
ここでは、特に効果的なオンラインコミュニケーション施策を4つご紹介します。
ビジネスチャットツールを活用した日常的な情報共有
ビジネスチャットツールは、メールよりも気軽に素早く情報を共有できるため、日常的なコミュニケーションに最適です。Slack、Chatwork、LINE WORKSなどのツールを導入することで、場所や時間を問わず社員間の情報共有が可能になります。
効果的な活用方法
|
特に「雑談チャンネル」の設置は、オフィスでの偶発的な会話の代替として機能し、社員間の距離感を縮める効果があります。
ただし、チャットツールの乱用による情報過多を防ぐため、利用ガイドラインを設けることも重要です。
参加者全員が発言するオンラインミーティング
オンライン会議では、発言者が固定化しがちという課題があります。これを解消するために、参加者全員が発言する機会を意図的に設けることが効果的です。
全員参加型会議の実現方法
|
特に重要なのは、発言しやすい雰囲気づくりです。「間違った意見はない」という心理的安全性を確保するファシリテーションを心がけましょう。
また、会議の目的や議題を事前に明確に共有し、準備時間を確保することも参加者の発言を促進します。
リモートでも一体感を生み出すバーチャル社内イベント
オンライン環境でも、社内イベントを開催することで一体感や親睦を深めることができます。工夫次第で、対面のイベントに負けない盛り上がりを創出できるでしょう。
バーチャルイベントの成功例
|
イベントの開催頻度は、四半期に1回程度が理想的です。また、参加は強制ではなく任意とし、参加しやすい雰囲気づくりを心がけましょう。事前に小さな準備物(お菓子や飲み物など)を配布することで、参加意欲を高める効果も期待できます。
オンライン環境でも効果を発揮する1on1ミーティング
1on1ミーティング(上司と部下の定期的な1対1の面談)は、オンライン環境でも非常に効果的なコミュニケーション手段です。特にリモートワークでは、日常的な会話機会が減少するため、計画的な1on1の実施が重要になります。
オンライン1on1の効果的な実施方法
|
1on1では、業務の進捗確認だけでなく、キャリア目標や悩み相談など、広範なテーマを扱うことができます。
上司からの一方的な指示や評価の場ではなく、双方向のコミュニケーションの場として活用することで、信頼関係の構築とモチベーション向上につながります。
▼1on1ミーティングについては下記で詳しく解説しています。
⇒1on1ミーティングとは?目的ややり方、効果を高める工夫を解説!
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
オフィス環境で社員同士のコミュニケーションを促進する具体策

オフィス環境でのコミュニケーションには、オンラインにはない直接的な相互作用の強みがあります。表情や身ぶり、声のトーンなど非言語情報も含めた豊かなコミュニケーションが可能です。
ここでは、オフィスの特性を生かした具体的なコミュニケーション促進策を紹介します。
ランチタイムやコーヒーブレイクを活用した交流促進
食事や休憩の時間を利用した交流は、業務の流れを遮ることなく自然なコミュニケーションを促進できる理想的な機会です。リラックスした雰囲気の中で行われる会話は、公式な会議では得られない発見や関係構築につながります。
効果的な取り組み例
|
このような工夫により、普段接点の少ない社員同士の会話機会を自然に創出できます。
全体会議や朝礼を通じた効果的な情報共有
部署や階層を超えた全体会議や朝礼は、情報共有とともに一体感を醸成する重要な機会です。単なる報告の場ではなく、社員間の交流や相互理解を深める場としても活用できます。
効果的な実施のポイント
|
特に、各部署からの短時間の発表を取り入れることで、普段は知る機会のない他部署の活動への理解が深まります。
また、定期的に経営層からのメッセージを含めることで、会社の方向性や価値観の共有にもつながります。
部署の壁を取り払う交流イベントの企画
部署を超えた交流イベントは、日常業務では接点の少ない社員同士のつながりを作る絶好の機会です。普段とは異なる環境での交流は、新たな関係構築や相互理解の促進に効果的です。
おすすめのイベント例
|
偶発的な交流を生み出すオフィスレイアウトの設計
オフィスの物理的環境は、社員の交流頻度や質に大きな影響を与えます。計画的にレイアウトを設計することで、自然な出会いと会話が生まれる環境をつくることができます。
効果的なレイアウトの特徴
|
特に、部署間の物理的な壁を最小限にすることで、偶発的な部門間交流が生まれやすくなります。
また、経営層のデスクを一般社員と同じフロアに配置することで、階層を超えたコミュニケーションも促進されます。
プロジェクトや業務内容に応じて柔軟に座席を変更できるフリーアドレス制も、多様な社員との交流機会を増やす効果があります。
▼職場コミュニケーションでの雑談の効用については下記で詳しく解説しています。
⇒職場コミュニケーションのカギは雑談にあり|組織的に効果を出すコツを解説!
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
ハイブリッドワーク時代に適した社員同士コミュニケーション戦略

ハイブリッドワークの普及により、オフィス勤務とリモートワークが混在する環境における効果的なコミュニケーション戦略が求められています。
特に重要なのは、勤務形態による情報格差や心理的な分断を防ぎ、全社員が平等に参加できる仕組みづくりです。
ここでは、ハイブリッド環境に特化した5つのコミュニケーション戦略を紹介します。
職場単位のワークショップできっかけをつくる
ハイブリッド環境では、意図的にコミュニケーションの機会をつくる必要があります。定期的なワークショップの開催は、その効果的な手段の一つです。
特に、リモート勤務者とオフィス勤務者が混在するチームでは、全員が対等に参加できる設計が重要です。
効果的なワークショップの特徴
|
例えば、四半期ごとに「チームビジョン共創ワークショップ」を開催し、オンラインホワイトボードツールを活用して全員が意見を出し合う取り組みが効果的です。
これにより、勤務形態に関わらず一体感を醸成できます。
出社組とリモート組の情報格差を解消する具体的な取り組み
ハイブリッド環境で最も注意すべきは、オフィスでの「廊下会議」や偶発的な情報共有から、リモートワーカーが疎外されることです。
意識的な対策を講じなければ、情報や人間関係の格差が生じてしまいます。
情報格差解消の具体策
|
特に重要なのは「デジタルファースト」の考え方です。会議の議事録、決定事項、進捗状況など、すべての重要情報をまずはデジタルツール上で共有することで、どこにいても同じ情報にアクセスできる環境を整えましょう。
ハイブリッド環境に最適化された会議設計と運営手法
ハイブリッド会議は、対面のみやオンラインのみの会議とは異なる工夫が必要です。特に、リモート参加者が部外者扱いされないよう、意識的な設計と運営が求められます。
ハイブリッド会議成功のポイント
|
特に有効なのは会議序盤でガイドラインを共有することです。例えば、今日は誕生日が1月の人から順に発言していくようにするなどを共有します。これにより、発言の機会を意識的に平等に分配し、リモート参加者が発言しやすくなります。
会議の冒頭でリモート参加者から順に発言を求めるなど、具体的な工夫を取り入れましょう。
時間や場所を問わず参加できる社内活動
ハイブリッド環境では、特定の時間や場所に縛られない社内活動が重要になります。全員が参加しやすい形式で企画することで、勤務形態による分断を防ぎます。
効果的な社内活動例
|
例えば「30日歩数チャレンジ」のようなイベントでは、各自が好きな時間に参加でき、結果をオンラインで共有することで一体感を生み出せます。多くの会社で歩数記録アプリを活用したウォーキングイベントなどを取り入れ、自然なコミュニケーション活性化に成功しています。それと同時に、リモートワークで運動不足になり勝ちは生活習慣を是正することにもつながります。
オンラインとオフラインのコミュニケーションを融合させる方法
最も効果的なハイブリッドコミュニケーションは、オンラインとオフラインの良さを掛け合わせたものです。
それぞれの特性を理解し、状況に応じて最適な手段を選択できる柔軟な体制が理想的です。
融合のポイント
|
例えば日常のやりとりはチャットツールで行いつつ、月に一度の全体会議では対面を重視するといった使い分けが効果的でしょう。
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
社員同士コミュニケーション改善を成功させる実践ステップ

コミュニケーション改善を一時的なイベントや取り組みではなく、持続的な成果につなげるためには、計画的なアプローチが必要です。
場当たり的な施策ではなく、現状分析から効果測定までを含む体系的なステップを踏むことで、効果的な改善を実現しましょう。
ここでは、成功に導く5つの実践ステップを解説します。
社員同士のコミュニケーション状況の現状を把握する
まず、自社のコミュニケーションの現状を客観的に把握することが重要です。感覚的な判断ではなく、データに基づいた分析を行うことで、効果的な改善策を導き出せます。
現状把握の方法
|
例えば、「社内コミュニケーションに関する満足度」「情報共有のしやすさ」「他部署との連携のしやすさ」などの項目について5段階評価を行うアンケートは、現状を数値化する効果的な手段です。
また、「最も課題を感じる点」を調査することで、重点的に改善すべきポイントが明確になります。
自社の課題に合ったコミュニケーションツールを選定する
現状分析で特定された課題に基づき、最適なコミュニケーションツールを選定します。
市場には多様なツールが存在するため、自社の規模や業務特性、社員の技術リテラシーなどを考慮した選択が重要です。
選定時のチェックポイント:
|
特にシンプルな操作性は導入成功の鍵となります。いくら機能が充実していても、使いこなせなければ意味がありません。また、情報セキュリティーも重要な観点です。
経営層が率先してコミュニケーション改善を行う
コミュニケーション改善を組織全体に浸透させるには、経営層のコミットメントと率先垂範が不可欠です。トップダウンの姿勢が示されることで、全社的な取り組みとしての正当性が確立されます。
経営層の役割:
|
例えば、経営層が率先してチャットツールで情報発信を行ったり、ランチタイムに異なる部署の社員と食事をしたりする姿勢は、社内に大きな影響を与えます。
中堅・中小企業では特に、「経営層と社員」のコミュニケーションが課題と感じられているケースが多いため、経営層の積極的な関与が重要です。
効果的な施策を展開する
現状分析と課題特定に基づき、具体的な施策を計画・実行します。効果的な施策展開のポイントは、短期的な施策と中長期的な施策をバランスよく組み合わせることです。
展開のポイント
|
施策を展開する際は、「何のためにこの施策を行うのか」という目的を明確に伝えることが重要です。
単に「コミュニケーションを良くするため」ではなく、「情報共有を円滑にして顧客対応力を高めるため」など、具体的なゴールを示すことで、社員の理解と協力が得られやすくなります。
定期的な効果測定を行う
施策の実施後も、定期的な効果測定と改善のサイクルを回すことが重要です。PDCAサイクルを通じて、形骸化を防ぎ、継続的な改善を実現します。
効果測定の方法:
|
効果測定の結果は必ず社員にフィードバックし、改善の成果を共有することが重要です。「このような変化が生まれました」と具体的に伝えることで、取り組みの意義が実感され、モチベーション向上にもつながります。
例えば、「部署間の情報共有に関する満足度が20%向上しました」など、具体的な数値で示すと効果的です。
また、期待した効果が得られない場合も、正直に共有し、原因分析と改善策の検討を行うことが大切です。失敗を隠さず、学びとして生かす姿勢こそが、真のコミュニケーション改善の土台となります。
▼効果測定については下記で詳しく解説しています。
⇒研修の効果測定を行い、成果につなげる方法とは?ツール活用法も解説!
▼コミュニケーション不足の解決策については下記で詳しく解説しています。
⇒職場のコミュニケーション不足の効果的な解決策とは?原因と対策まで解説!
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
社員同士のコミュニケーション活性化には職場単位での研修が最適

社員同士のコミュニケーション活性化には、個人単位の学習だけでなく、職場単位での研修が極めて効果的です。実際の職場メンバーと共に学び、実践することで、即座に職場の雰囲気改善につなげることができます。
ここでは、なぜ職場単位での研修が効果的なのか、その理由と期待される効果について解説します。
職場メンバーがそろっている
職場単位での研修では、日常的に共に働くメンバーが一堂に会して学ぶことができます。これにより、研修で学んだコミュニケーション手法を、その場で実践的に試すことができます。
また、普段の業務の中での具体的な課題や改善点について、チーム全体で認識を共有し、解決策を考えることができます。
研修での学びを即座に実務に反映できる環境があることは、スキル定着の観点からも大きなメリットとなります。
職場の認識を変えることができる
職場全体で研修を受けることで、コミュニケーションに関する共通認識を形成することができます。
例えば、「雑談は業務の妨げになる」という古い価値観を、「適切な雑談は職場の活性化に重要である」という新しい認識に更新することが可能です。
全員が同じ内容を学ぶことで、新しいコミュニケーション方法を実践する際の心理的なハードルを下げ、職場全体での行動変容を促進することができます。
▼職場単位でのコミュニケーション研修が有効な理由については下記で詳しく解説しています。
⇒職場の活性化につなげる方法とは?アイデアやポイントを紹介!
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
社員同士のコミュニケーション活性化ならLIFO®がおすすめ!

社員同士のコミュニケーション活性化なら自己診断ツールLIFO(Life Orientations)を活用した職場単位でのワークショップがおすすめです。
なぜなら、LIFOプログラムは心理学や行動科学をベースにして組み立てられた行動特性診断をベースに、職場単位でワークショップを行うためのワークブックなどのツールも体系的にそろえられているからです。
また、体系立てられたツールの使い方を社内トレーナーの方々にライセンス提供もされており、社内トレーナーの方々が職場単位でワークショップを展開していくことも可能です。下記に概要を紹介します。
自己診断ツールLIFOとは
LIFO(Life Orientations)は、個人の行動スタイルを診断する自己診断ツールです。このツールは、自分の強みや行動パターンを理解するために役立ちます。
LIFOは4つの基本スタイルに基づいており、これらのスタイルはそれぞれ異なる行動特性や価値観を持っています。
自分がどのスタイルに属しているかを知ることで、より良いコミュニケーション方法やストレス時の行動傾向を把握することができます。
LIFOを活用したコミュニケーション研修
LIFOを活用したコミュニケーション研修では、まず参加者が自己診断を行い、自分の行動スタイルを理解します。
この診断結果をもとに、どのようにして他者と効果的にコミュニケーションをとるかを学びます。
研修では以下のような内容が含まれます。
|
LIFO®プログラムは社内トレーナーで展開可能
LIFO®プログラムは、これまでの活用実績と実用性から、企業内でのトレーニングにおいて自信を持っておすすめできるプログラムです。
社内展開にあたっては、特定の準備と手続きを経ることで、コストを抑えながら、外部講師に委託したかのように、社内トレーナーによる効果的なプログラムを展開することが可能です。
以下に、その流れを詳しく説明します。
|
LIFOを活用して社内トレーナーがコミュケーション研修を展開している事例

背景・課題:
リコージャパン株式会社では、2010年の販売会社統合以降、各支社の固有の課題に対応できず、教育施策が本部主導で一方的になるなどの課題がありました。
また、コロナ禍以降、会食などの機会が減ったことにより、コミュニケーションの希薄化を招いていました。これらの課題を解決するために、社員自らが強みや弱みを理解し合い、横のつながりを強化する取り組みが求められていました。
LIFOプログラム(社内トレーナーライセンス)の導入:
その中で、LIFO(Life Orientations)を導入しました。LIFOの活用を通じて、社員一人一人の個性を診断し、自己理解と他者理解を促進しました。
これにより、非公式なコミュニケーションが減少する中でも、社員同士の相互理解を深めるための新たな手段を提供することができるようになりました。
また、LIFOプログラムライセンスを取得することで、社内トレーナーが自主的に研修を行えるようになり、組織風土改革を進めました。
LDcubeとの協力により、多様なワークショップを展開し、各支社・部門が抱える具体的な課題に対応できるようになりました。
社内展開:
プログラムの展開においては、事前のLIFO診断、ワークショップの実施、職場での実践、効果検証のサイクルを組み込みました。
参加者は、研修後の職場実践を通じて得られたスキルを評価し合い、PDCAサイクルを回すことで、持続的なスキルアップを図っています。
ラーニングプラットフォーム「UMU」を活用し、受講者同士が学び合う環境も整備しました。
社内トレーナーによる研修実施後の反応:
導入後、プログラム受講者の満足度は高く、多くの支社で「対人関係」や「マネジメント能力」などにおいて数値的な改善が見られました。
LIFOを活用したレクチャーは「人」の問題の解決に寄与し、特にアウトプット重視の体験学習が効果的でした。
UMUの活用と一連の学習サイクルの設計により、事務局の負担軽減と学習効果の向上が実現しました。
今後に向けて:
今後は、各支社や部門の課題に寄り添い、人材育成を継続的にサポートすることで、社員個々の自己成長と組織全体の活性化をさらに推進する予定です。
また、LIFO以外のライセンスプログラムも組み合わせ、人材育成のプログラムラインナップを増やしていきます。
これにより、組織内のさまざまな課題を解決し、全体の一体感を更に高められることを期待しています。
▼本事例はインタビュー記事の一部です。インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。
⇒リコージャパン株式会社様 ライセンスプログラム導入事例
まとめ:社員コミュニケーション強化で組織力を高めよう
社員同士のコミュニケーション活性化の秘訣とは?重要性から事例まで紹介!について案内してきました。
- 社員同士のコミュニケーション活性化に最適な方法!
- 社員同士のコミュニケーションの希薄化が招く5つの経営リスク
- 社員同士のコミュニケーション改善がもたらす4つの経営メリット
- オンラインで実現する、効果的な社員同士のコミュニケーション施策
- オフィス環境で社員同士のコミュニケーションを促進する具体策
- ハイブリッドワーク時代に適した社員同士コミュニケーション戦略
- 社員同士コミュニケーション改善を成功させる実践ステップ
- 社員同士のコミュニケーション活性化には職場単位での研修が最適
- 社員同士のコミュニケーション活性化ならLIFO®がおすすめ!
- LIFOを活用して社内トレーナーがコミュケーション研修を展開している事例
コミュニケーションの希薄化は単なる人間関係の問題にとどまらず、情報共有の遅れや業務効率の低下、離職率の上昇など、企業経営に直結する重大なリスクをもたらします。一方で、コミュニケーションの活性化は、チームワークの強化やイノベーションの創出、エンゲージメント向上などの大きなメリットにつながります。
今日のビジネス環境は、テレワーク、オフィスワーク、そしてそれらを組み合わせたハイブリッドワークと、多様な働き方が共存する時代です。それぞれの環境に適したコミュニケーション施策を選択し、組み合わせることが重要です。オンライン環境ではビジネスチャットツールや1on1ミーティング、オフィス環境ではランチ交流やオフィスレイアウトの工夫、ハイブリッド環境では情報格差の解消やオンオフ融合イベントなど、状況に応じた取り組みが効果を発揮します。
コミュニケーション改善を一時的なブームで終わらせないためには、現状把握から効果測定までの体系的なステップを踏むことが大切です。特に経営層の率先垂範は、取り組みの成功に大きく影響します。改善の目的や意義を明確に示し、PDCAサイクルを回し続けることで、持続的な効果を生み出せるでしょう。
社員同士のコミュニケーションは、企業の最も基本的な土台であり、競争力の源泉でもあります。「うちは大丈夫」と思っている企業こそ、一度立ち止まって自社のコミュニケーション状況を見直してみてください。組織の潜在能力を最大限に引き出し、社員一人一人が生き生きと働ける環境づくりに、ぜひ今日から取り組んでみましょう。
株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。