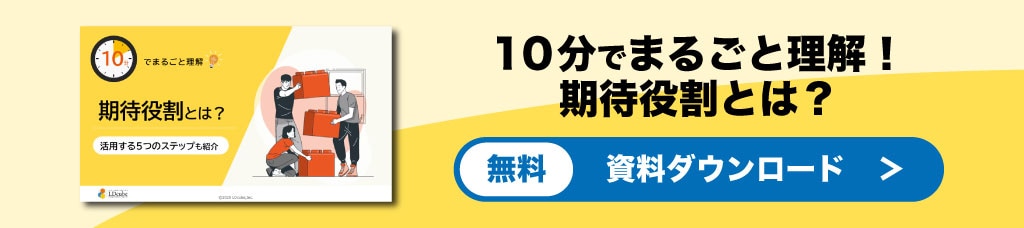期待役割とは?人を生かしパフォーマンス向上につなげるステップを解説!
「メンバーが何をすべきか分からない」
「評価に対する不満が絶えない」
「チームの成果が思うように上がらない」
このような課題を抱える管理職の方は多いのではないでしょうか。
これらの問題の根本原因は、期待役割の不明確さにあります。期待役割とは、組織やチームが個人に期待している具体的な役割のことで、単なる業務内容ではなく「どのように頑張ってほしいか」を明確化したものです。
従来の目標設定では「営業目標○○万円」といった数値のみが示されがちですが、期待役割では「新規顧客開拓に注力する」「既存顧客との関係深化を図る」「後輩へのOJTをしっかりやってほしい」など、具体的な行動指針まで含めて定義します。
リモートワークや多様な働き方が広がる現代において、期待役割の明確化は組織運営の重要な要素となっています。メンバーが自分の役割を正確に理解し、主体的に行動できる環境を整えることで、チーム全体のパフォーマンス向上と評価制度の透明性を実現できます。
本記事では、期待役割の基本概念から具体的な設定方法、実践的な対話手法まで体系的に解説します。
▼関連記事はこちらから。
▼期待役割については資料にまとめています。下記からダウンロードできます。
目次[非表示]
期待役割とは何か

組織やチームが円滑に機能するためには、メンバー一人一人が自分に求められている役割を正確に理解し、実行することが不可欠です。しかし、多くの職場では「何をどの程度頑張ればよいのか分からない」という状況が生まれがちです。
期待役割の定義と基本概念
期待役割とは、組織やチームが個人に対して期待している具体的な役割のことです。単に「営業担当」や「マネジャー」といった職位上の役割ではなく、チームの目標達成に向けて「どのように頑張ってほしいか」を具体的に言語化したものを指します。
例えば、営業職のメンバーに対しても、新規顧客開拓を重視するのか、既存顧客との関係維持を優先するのか、あるいは後輩指導に力を入れてほしいのかによって、期待役割は大きく異なります。これらの期待を明確に伝えることで、メンバーは自分のエネルギーを適切な方向に向けることができるのです。
期待役割は、業務遂行に関する期待だけでなく、チーム内での立ち位置や貢献方法についても定義されます。リーダーシップを発揮してほしいのか、専門性を生かしてサポートしてほしいのか、これらの期待が明確になることで、組織全体のパフォーマンスが向上します。
制度的役割と期待役割の違い
制度的役割と期待役割には明確な違いがあります。制度的役割は職務記述書や組織図に記載された公式な役割で、基本的に変更されることはありません。一方、期待役割は組織の状況やメンバーの成長に応じて柔軟に調整される動的な概念です。
制度的役割が「何をするか」を定義するのに対し、期待役割は「どのようにするか」「どの程度の成果を期待するか」といった質的な側面まで含みます。例えば、同じ主任という制度的役割でも、経験豊富なベテランと昇進したばかりの新任者では、期待される役割の内容や水準が異なるのが自然です。
また、期待役割は複数の視点から構成されます。上司からの期待、同僚からの期待、部下からの期待、そして本人の自己期待など、さまざまな立場からの期待を統合して形成されるのが特徴です。これにより、一方的な役割の押し付けではなく、関係者全体の合意に基づいた役割設定が可能になります。
期待役割はチーム状況により変化する
期待役割の特徴で特に重要なのは、チームの状況や事業環境の変化に応じて柔軟に調整されることです。プロジェクトの進行段階、チームメンバーの構成変更、市場環境の変化などにより、求められる役割は常に変化します。
例えば、新規事業立ち上げフェーズでは革新性や挑戦的な姿勢が期待されるメンバーも、事業が軌道に乗った段階では安定的な運営や効率化への貢献が期待されるかもしれません。このような変化に対応するため、期待役割は定期的に見直し、更新していく必要があります。
また、リモートワークの普及や働き方の多様化により、従来の固定的な役割分担では対応できない状況も増えています。時短勤務のメンバーや在宅勤務中心のメンバーに対しては、勤務形態に適した期待役割を設定することで、全員が最大限の力を発揮できる環境を整えることができるのです。
期待役割の構成要素
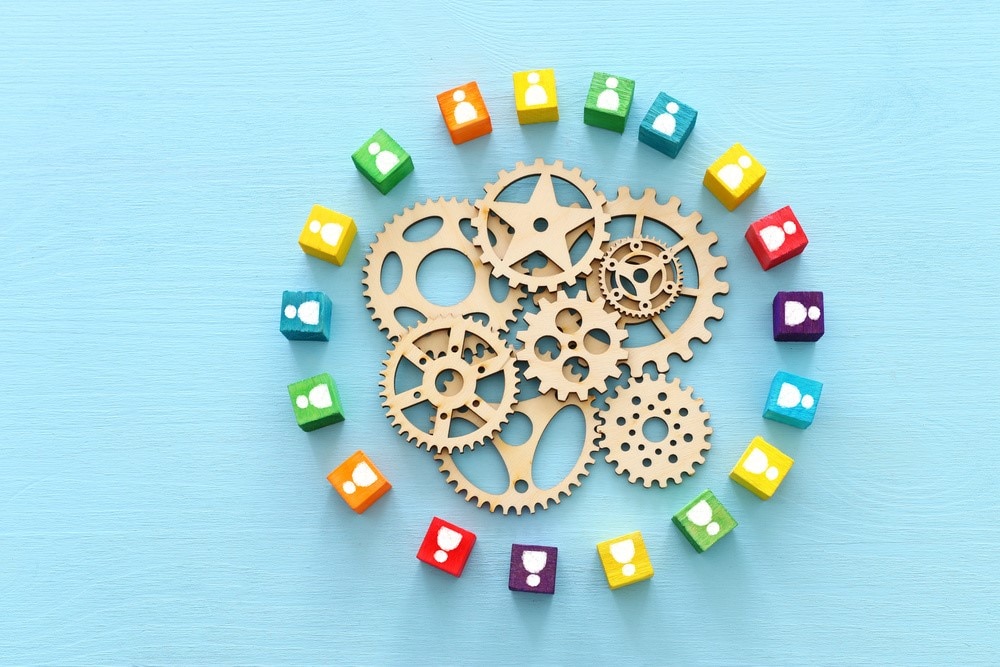
期待役割は単一の視点から形成されるものではありません。組織内のさまざまな立場の人々からの期待が重なり合い、複合的に構成されています。これらの多面的な期待を理解し統合することで、より効果的な役割遂行が可能になります。
①自分で考える自分への期待役割
自分への期待は期待役割の出発点となる重要な要素です。個人が自分自身に対して設定する期待であり、キャリアビジョンや価値観、強みを生かしたい領域などが反映されます。
自分への期待を明確にするためには、まず自分の強みや専門性を客観的に把握することが必要です。これまでの経験で得意としてきた分野、同僚から評価される能力、さらに伸ばしたいスキルなどを整理することで、自分がチームにどのような価値を提供したいかが見えてきます。
また、自己期待にはキャリア目標も含まれます。将来どのようなビジネスパーソンになりたいか、どのようなリーダーシップを発揮したいかという長期的な視点も、現在の期待役割設定に影響を与えます。
ただし、自己期待だけが先行してしまうと、組織のニーズとのミスマッチが生じる可能性があるため、他者からの期待との調整が不可欠です。
②上司から期待されている役割
上司からの期待は、期待役割の中でも特に重要な位置を占めます。上司は組織目標の達成責任を負っており、部下に対する期待はその目標実現に直結しているからです。
上司の期待には、業務遂行に関する具体的な成果目標だけでなく、働き方や姿勢に関する期待も含まれます。
例えば、積極的な提案を期待されているのか、確実な実行力を期待されているのか、あるいは他のメンバーへの影響力を期待されているのかによって、日々の行動指針は大きく変わります。
|
上司の期待を正確に理解するためには、定期的なコミュニケーションが欠かせません。
on1ミーティングや目標設定面談を通じて、上司からの期待を具体的に把握し、自分の理解とのずれがないかを確認することが重要です。
③同僚から期待されている役割
同僚からの期待は、日常的な業務遂行や協働の観点から形成されます。チームワークを重視する現代の職場において、同僚からの期待の重要性は益々高まっています。
同僚からの期待の特徴は、相互依存関係に基づいていることです。お互いが業務で連動しているため、1人の役割遂行が他のメンバーの成果に直接影響します。例えば、情報共有の頻度やタイミング、意思決定への関与の仕方、問題解決時のサポート方法などに対する期待があります。
同僚からの期待を把握するためには、日常的な対話やフィードバックの機会を設けることが有効です。プロジェクトの振り返りやチームミーティングの際に、お互いに期待することを率直に話し合う文化を築くことで、より良い協働関係を構築できます。
また、同僚からの期待は職位や経験年数によって異なります。先輩としての指導的な役割を期待されることもあれば、新しい視点や専門知識を期待されることもあります。自分の立ち位置を理解し、適切な役割を果たすことがポイントです。
④後輩から期待されている役割
後輩からの期待は、指導やサポートに関連することが多く、組織の人材育成という重要な機能を担います。経験の浅いメンバーにとって、先輩の存在は学習の機会そのものであり、その期待に応えることは組織全体の成長につながります。
後輩からの期待の内容は多岐にわたります。業務面での指導から、職場での立ち回り方、キャリア形成のアドバイスまで、幅広い領域での期待があります。
また、単に教えるだけでなく、相談しやすい存在であることや、失敗を許容する包容力なども期待される要素です。
|
後輩からの期待に応えることは、自分自身の成長にもつながります。人に教えることで自分の理解が深まり、異なる視点を得ることで新たな気付きが生まれます。
また、指導経験は将来的なリーダーシップ開発にも役立ちます。
⑤他部門・他組織から期待されている役割
現代のビジネス環境では、組織の枠を越えた期待も重要な要素となっています。部門間連携や外部パートナーとの協働が日常的になっている中で、自部門以外からの期待を理解し応えることが求められます。
他部門からの期待は、主に業務連携や情報共有に関するものが中心となります。外部組織からの期待については、取引先や協力会社との関係において重要となります。単なる窓口としての機能だけでなく、組織の代表としての振る舞いや、win-winの関係構築への貢献が期待されます。
これらの期待に応えるためには、自分の専門性を組織横断的にどう活用できるかを考える視点が必要です。また、異なる組織文化や価値観を理解し、適切なコミュニケーションを取る能力も求められます。
期待役割が解決する組織課題

多くの組織が直面している課題の根本には、メンバー間の期待のずれや役割の不明確さがあります。期待役割を適切に設定し運用することで、これらの課題を解決することが可能です。
役割分担が曖昧な状況
「誰が何をやるべきか分からない」という状況は、多くの組織で見られる深刻な問題です。特に複数のメンバーが関わるプロジェクトや、部門をまたがる業務において、責任の所在が曖昧になりがちです。
この問題が発生する主な原因は、職務記述書や組織図だけでは実際の業務の詳細や優先順位が伝わらないことにあります。同じ「営業担当」でも、新規開拓に注力すべきか、既存顧客のフォローを重視すべきかが明確でなければ、メンバーは迷いながら業務を進めることになります。
期待役割の導入により、各メンバーの具体的な責任範囲と期待される成果が明確になります。例えば、「既存顧客との関係を維持し、定期的なフォローアップを通じて追加受注の機会をつくる」といった具体的な期待を設定することで、メンバーは迷うことなく業務に集中できるようになります。
また、期待役割は重複や抜け漏れの防止にも効果的です。チーム全体の期待役割を俯瞰することで、同じ業務を複数の人が担当している無駄や、誰も担当していない重要業務を発見できます。これにより、効率的で漏れのない役割分担が実現します。
評価制度への不満がある状況
「頑張っているのに評価されない」「評価基準が分からない」といった評価制度への不満は、多くの組織で見られる課題です。この問題の背景には、評価者と被評価者の間での期待値のずれがあります。
従来の評価制度では、職位や職種に基づいた画一的な評価項目が設定されることが多く、個人の強みや貢献の多様性が十分に反映されないケースがあります。同じマネジャーでも、リーダーシップが得意な人と専門性で貢献する人では、評価されるべきポイントが異なるはずです。
期待役割で評価制度を補完することで、より公平で納得感のある評価が可能になります。期待役割が明確であれば、評価時に「期待されていることに対して、どの程度貢献できたか」について共通認識を持つことが可能です。また、個人の強みや状況に応じた期待役割を設定することで、画一的でない評価が実現します。
|
離職率が高い状況
人材の定着は多くの組織にとって重要な課題です。離職の要因はさまざまですが、「自分の役割や価値が分からない」「成長実感が得られない」といった理由も少なくありません。
期待役割は、メンバーに対して組織からの明確な期待を示すことで、自分の存在価値を実感させる効果があります。「この人にはこんなことを期待している」というメッセージは、メンバーの自己肯定感や組織への帰属意識を高めます。
また、期待役割は成長の道筋を示す機能も持ちます。現在の期待役割を達成された後、次のステップでどのような役割が期待されるかが見える化されることで、キャリアパスが分かりやすくなります。この将来への展望は、長期的な所属意欲を高める重要な要因となります。
さらに、期待役割に基づく定期的な対話は、メンバーの状況や意向を把握する機会としても機能します。期待役割の調整を通じて、メンバーの変化するニーズに対応することで、組織への満足度を維持できます。
社員のモチベーションが低い状況
モチベーションの低下は、個人の問題というよりも組織的な課題として捉える必要があります。多くの場合、「何のために頑張るのか分からない」「自分の貢献が見えない」といった状況がモチベーション低下の原因となっています。
期待役割は、メンバーの働く意味や目的を明確にする効果があります。自分に期待されていることが具体的に分かることで、日々の業務に意味を見いだしやすくなります。また、期待に応えることで得られる達成感は、内発的なモチベーションを高める重要な要素です。
期待を感じることは、心理学的にも重要な意味を持ちます。他者からの期待は、自分の能力や可能性を認められているというシグナルであり、自己効力感の向上につながります。この自己効力感の向上は、挑戦意欲や学習意欲の向上をもたらし、結果として高いパフォーマンスを生み出します。
また、期待役割に基づく成果は、組織やチームへの貢献として可視化されるため、貢献実感を得やすくなります。自分の働きがチーム全体の成功にどう貢献しているかが明確になることで、仕事への誇りや満足感が高まります。
期待役割を活用する5つのステップ

期待役割の効果を最大化するためには、体系的なアプローチが必要です。ここでは、チーム全体で期待役割を共有し、活用するための実践的な5つのステップをご紹介します。
ステップ1:職場でのワークショップの機会を設ける
期待役割の導入には、メンバー全員が参加できるワークショップの場を設けることから始まります。最低でも2時間程度の時間を確保し、参加者が集中できる環境を整える必要があります。
ワークショップの冒頭では、期待役割の目的と意義について参加者全員で共有します。「なぜこの取り組みを行うのか」「どのような効果が期待できるのか」を明確に伝えることで、参加者の理解と協力を得ることができます。
|
ファシリテーターの役割も重要です。管理職が進行する場合は、指示的になりすぎないよう注意し、メンバーの自発的な発言を促す姿勢が求められます。
ステップ2:各メンバーが他メンバーに期待する役割を書き出す
参加者一人一人が他のメンバーに対する期待役割を書き出します。この段階では、具体的で建設的な期待を表現することが重要です。
期待役割を書き出す際のポイントは、抽象的な表現を避け、具体的な行動や成果に焦点を当てることです。「頑張ってほしい」ではなく、「新規顧客開拓において月3件のアポイント獲得を目指してほしい」といった具体的な期待を記述します。
|
メンバー1人につき3項目程度の期待役割を設定し、15〜20分程度で書き出しを完了します。時間はメンバーの数に応じて調整します。
ステップ3:期待役割を伝える人を決め、1人ずつ発表する
期待役割を伝える人を決め、その人に対して他メンバーから1人ずつ期待役割を伝えていきます。誰から始めてもよいので、まずは伝える人を決めます。そしたら、機械的にその右隣の人から順に発表していくスタイルで進めていきましょう。
期待役割を伝える人に対して、各メンバーの発表時間は2~3分程度を目安とし、全員が期待役割を伝えていきます。期待を伝える側は、なぜその期待を持ったのかの背景や理由も含めて説明することで、より深い理解が得られます。
発表の際に心掛けるべきポイントは、批判的な表現を避け、ポジティブな期待として伝えることです。具体的なエピソードや体験を交えながら伝えることで、期待の根拠が明確になり、受け手の納得感が高まります。
ステップ4:期待役割を伝えられたメンバーが感想を述べる
他メンバー全員から期待役割を伝えられた人は最後に感想を述べます。一方的な期待の伝達ではなく、期待を聞いてどのように感じたかなどを共有することで相互理解を深めることができます。
感想を述べる際には、まず期待を聞いた率直な気持ちを共有してもらいます。次に、伝えられた期待に対する自分なりの理解や解釈を確認し、認識のずれを解消します。
|
このやり取りを通じて、より現実的で実現可能な期待役割へと調整していくことができます。
ステップ5:全てのメンバーが終わるまで続ける
全員の期待役割交換が完了するまで、ステップ3と4を繰り返します。5~6名程度のチームであれば、全員の期待役割交換に1~1.5時間程度を要します。
全員の期待役割交換が完了したら、ワークショップ全体の振り返りを行います。参加者が感じた気付きや学び、今後のアクションプランについて話し合い、期待役割を文書化して参加者全員で共有します。
期待役割の交換は効果あり

期待役割の交換プロセスがもたらす効果は、単なる役割分担の明確化にとどまらず、チームの根本的な働き方や関係性を変革する力を持っています。
多くの組織でこの手法が導入され、具体的な成果を上げている背景には、確かな理由があります。
期待する役割は実は伝えられていないことが多い
日常の職場において、私たちは他のメンバーに対してさまざまな期待を抱いています。しかし、その期待が適切に伝えられているかというと、実際にはそうでないケースが大半です。
「言わなくても分かってもらえるだろう」「明確に伝えると押し付けがましく感じられるかもしれない」といった心理的な障壁が、期待の伝達を妨げています。
この状況は、期待する側と期待される側の双方にとって望ましくない結果をもたらします。期待する側は、「なぜ思うように動いてもらえないのか」という不満を抱き、期待される側は「何を求められているのか分からない」という不安を感じることになります。
特に日本の職場文化では、直接的な期待の表明が避けられる傾向があります。「察してもらう」ことを前提とした暗黙のコミュニケーションが多用されるため、期待のずれが生じやすい環境にあります。
期待役割交換ワークショップは、このような文化的背景を踏まえ、構造化された安全な場で期待を明確に伝え合う機会を提供します。
また、期待が伝えられない理由として、期待する側自身が自分の期待を明確に言語化できていないケースも多くあります。
漠然とした期待や感情的な期待では、相手に伝えることは困難です。期待役割交換のプロセスを通じて、期待する側も自分の考えを整理し、言語化する機会を得ることができます。
期待を感じるとエンゲージメントが高まる
心理学の研究において、他者からの期待は個人のモチベーションや自己効力感に大きな影響を与えることが明らかになっています。
適切な期待を受けることで、人は自分の能力や価値を認められていると感じ、より高いパフォーマンスを発揮する傾向があります。
この現象は「ピグマリオン効果」としても知られており、教育現場やビジネス環境において広く確認されています。期待を感じることで、以下のような心理的変化が生じます。
|
期待役割交換では、この心理的効果を組織的に活用します。メンバー一人一人が明確な期待を受けることで、自分の存在価値や組織への貢献可能性を実感できるようになります。
さらに、期待を受けることは承認欲求の充足にもつながります。
マズローの欲求階層理論においても、承認欲求は重要な位置を占めており、この欲求が満たされることで、より高次の自己実現への動機が生まれます。期待役割は、日常的な承認の仕組みとして機能し、継続的なモチベーション維持に貢献します。
期待を感じることでエンゲージメントが高まる効果は、個人レベルにとどまらず、チーム全体のパフォーマンス向上にも波及します。
各メンバーが高いエンゲージメントを持って業務に取り組むことで、チーム全体の生産性や創造性が向上し、組織目標の達成がより確実になります。
また、エンゲージメントの高いメンバーは、自然と他のメンバーにも良い影響を与え、組織全体のポジティブな循環を生み出すことにつながります。
期待役割を活用した対話とマネジメント

期待役割を一度設定して終わりではなく、継続的な対話とマネジメントの仕組みとして活用することで、その効果を最大化することができます。日常的な運用の中で期待役割を適切に活用するための具体的な手法をご紹介します。
期待役割を軸とした1on1の進め方
1on1ミーティングは、期待役割を継続的に確認する最も効果的な場面の一つです。従来の1on1では話題が散漫になりがちですが、期待役割を軸とすることで、より有意義な対話が可能になります。
1on1での期待役割活用は、まず現在の期待役割の進捗確認から始まります。設定された期待役割に対して、どの程度達成できているか、どのような取り組みを行っているかを具体的に話し合います。
単純な達成度の確認にとどまらず、取り組み過程での気付きや学び、直面している課題についても深く掘り下げることが重要です。
次に、期待役割を遂行する中で生じた新たなニーズや変化について話し合います。業務環境の変化や本人のスキル向上により、当初設定した期待役割の調整が必要になることがあります。
|
1on1では、期待役割に関連する成長機会についても積極的に話し合います。
現在の期待役割を通じてどのようなスキルを伸ばしたいか、将来的にどのような役割を担いたいかといった展望を共有することで、個人の成長とチームの発展を両立させることができます。
社内トレーナーによる期待役割ワークショップの実施
期待役割の効果を組織全体に浸透させるためには、社内トレーナーによるワークショップの継続的な実施が有効です。外部の専門家に依存するのではなく、社内でワークショップを運営できる体制を構築することで、継続性とコスト効率を両立できます。
社内トレーナーの育成では、まずワークショップの進行スキルを身に付けることから始まります。参加者の心理的安全性を確保し、建設的な対話を促すファシリテーションスキルは、期待役割ワークショップの成功に不可欠です。
社内トレーナーのメリットは、組織の文化や特性を深く理解していることです。外部の講師では気付きにくい組織固有の課題や特徴を踏まえたワークショップ設計が可能になります。また、参加者との信頼関係を構築しやすいため、より率直で深い対話を促すことができます。
ワークショップの実施頻度については、新入社員の入社時期や組織改編のタイミングに合わせて定期的に開催することを推奨します。既存チームでも1年に1度は期待役割の見直しワークショップを実施することで、変化する環境に対応した期待役割の調整が可能になります。
定期的な期待役割の見直しとアップデート手法
期待役割は固定的なものではなく、組織の状況や個人の成長に応じて継続的に見直し、アップデートしていく必要があります。適切な見直しサイクルと効果的なアップデート手法を確立することで、期待役割を常に有効なツールとして活用できます。
見直しのタイミングは、組織の評価サイクルに合わせることが一般的です。四半期ごとの業績レビューや半期ごとの人事評価のタイミングで、期待役割の達成状況と適切性を検証します。また、組織構造の変更や新規プロジェクトの開始など、大きな変化があった際には、期待役割の見直しを行うことが重要です。
見直しプロセスでは、まず現在の期待役割の妥当性を多角的に評価します。設定時の前提条件が変化していないか、期待される成果レベルが適切か、個人の能力やキャリア志向との整合性が保たれているかを確認します。
|
アップデートの際には、関係者全員の合意を得ることが重要です。一方的な変更ではなく、本人の意向や他のメンバーからの期待も踏まえた調整を行います。
見直し結果は必ず言語化し、関係者で共有することで、アップデート後の期待役割への理解と納得感を高めることができます。
期待役割ワークショップならLIFO

期待役割を交換するワークショップなら、自己診断ツールとワークブックがセットになっているLIFOプログラムがおすすめです。期待役割ワークショップは社内トレーナーが診断とワークブックを使って展開することもできます。
■自己診断ツール「LIFO」とは
LIFO®(Life Orientations)は、自己理解を深めるための非常に有効な自己診断ツールです。
このツールは、個々の行動スタイルや価値観を分析し、どのような状況でその人が最も力を発揮するのかを理解する手助けをします。
LIFOは、行動特性やコミュニケーションスタイルを4つに分類することで、個人の強みを明らかにします。これにより、自己理解を深め、効率的なコミュニケーションやチームワークの向上を図ることが可能です。
■LIFOを使った期待役割ワークショップ
LIFOを活用した期待役割ワークショップは、チームや組織内での役割理解を深めるための優れた手法です。このワークショップでは、参加者がLIFO診断を通じて自身の自然な行動スタイルを理解し、それがチームでどのように機能するかを学びます。
具体的には、個々の強みや弱みを認識し、それを元にチーム内での役割を最適化します。
例えば、LIFO診断により「自分が新しいことに取り組むことに強みがある」ことを知った参加者は、ワークショップでその強みを共有し、チームの新しいプロジェクトにおいて創造的な側面を担当することなどがあります。
このように、LIFOを用いたワークショップは、各メンバーが自分の強みや啓発課題を共有し、自分の強みを生かせる役割や、自分の成長のためにチャレンジすべき役割などについての理解を深め、チームで期待役割を交換することでチームのパフォーマンスが向上することが期待されます。
まとめ:期待役割を交換しよう
期待役割とは?人を生かしパフォーマンス向上につなげるステップを解説!について紹介してきました。
期待役割とは何か
期待役割の構成要素
期待役割が解決する組織課題
期待役割を活用する5つのステップ
期待役割の交換は効果あり
期待役割を活用した対話とマネジメント
期待役割ワークショップならLIFO
期待役割は、組織のさまざまな課題を解決し、チーム力を最大化する強力な考え方です。役割分担の曖昧さ、評価制度への不満、モチベーション低下といった課題に対して、期待役割の明確化と継続的な対話を通じて、根本的な改善を図ることができます。
成功の鍵は、5つのステップを踏んだワークショップから始まり、1on1や定期的な見直しを通じて継続的に運用することです。期待を明確に伝え合い、お互いの成長を支援する文化を築くことで、メンバー一人一人のエンゲージメントが向上し、チーム全体のパフォーマンスが飛躍的に高まります。
まずは小さなチームから期待役割交換を試してみることから始めてみてください。
株式会社LDcubeでは、期待役割の効果的な活用に向けて、LIFO診断を活用した「職場での期待役割交換ワークショップ」のツールや、社内トレーナーの養成を支援しています。関心のある方はお気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。