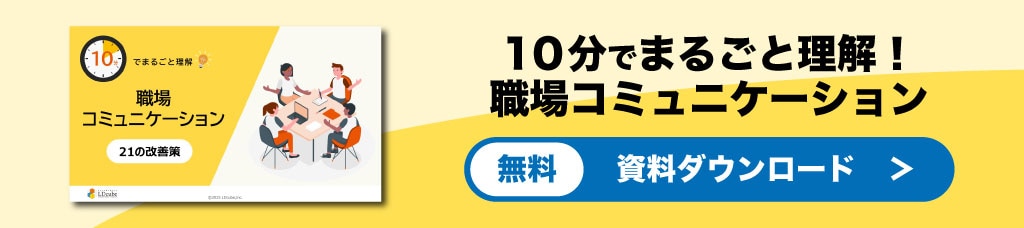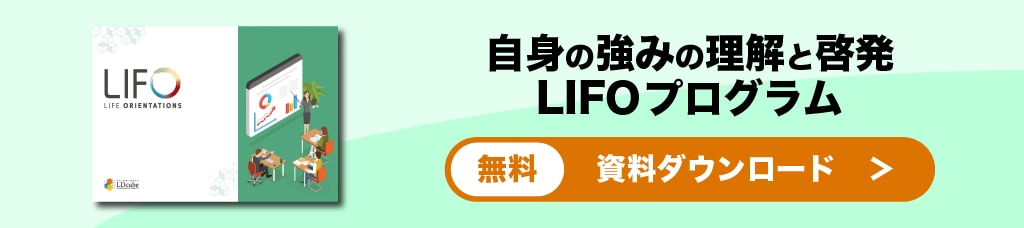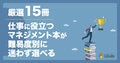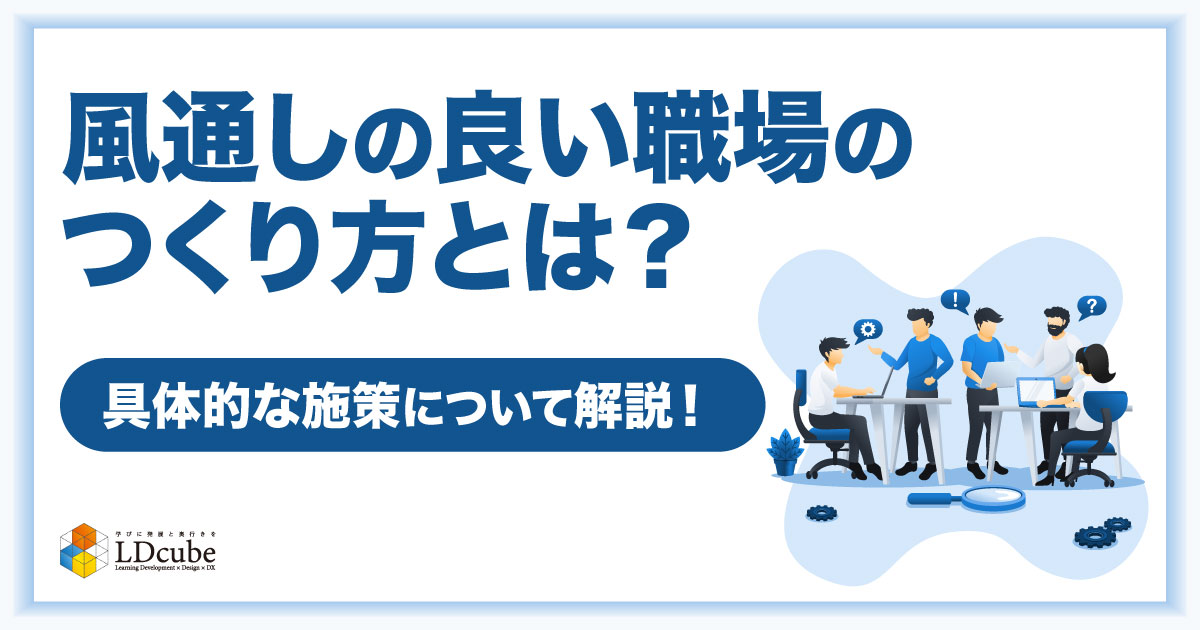
風通しの良い職場のコミュニケーションとは?具体的な施策について解説!
「風通しの良い職場にしたい」
「社内コミュニケーションを活性化させたい」
と考えていても、具体的に何から手をつければいいのか迷ってしまうことはありませんか?職場のコミュニケーション不足や情報の滞りは、生産性の低下や従業員の満足度減少、さらには離職率の上昇にもつながりかねない重要な課題です。
特に近年は、リモートワークの普及やハイブリッドワークの定着により、従来の対面中心のコミュニケーション手法だけでは不十分な状況が生まれています。しかし、適切な施策を導入することで、物理的な距離があっても風通しの良い職場環境を構築することは十分に可能です。
風通しの良い職場とは、従業員が自由に意見を交換でき、社内のコミュニケーションが活発で、心理的安全性が確保された環境を指します。このような環境では、問題の早期発見・解決が可能になるだけでなく、イノベーションが生まれやすく、従業員のエンゲージメントも高まります。
本記事では、人事担当者や管理職の方々に向けて、すぐに実践できる13のコミュニケーション施策を紹介します。基本的な取り組みから管理職が実践すべき手法、従業員同士の関係を深める戦略まで、段階的に解説していきます。ぜひ自社の状況に合わせて取り入れてみてください。
▼コミュニケーションについては下記で詳しく解説しています。
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
目次[非表示]
- 1.風通しの良い職場でのコミュニケーションとは?
- 2.職場の風通しを良くする基本的コミュニケーション施策5選
- 2.1.定期的な1on1ミーティングでコミュニケーションの機会をつくる
- 2.2.フリーアドレス制度で部署間のコミュニケーション障壁を取り除く
- 2.3.オープンなコミュニケーションスペースを確保する(リアル・バーチャル)
- 2.4.デジタルツールで時間や場所に縛られない情報共有を実現する
- 2.5.社内イベントで部門を超えたコミュニケーションを促進する
- 3.風通しの良い職場づくりのために管理職が実践すべきコミュニケーション手法4選
- 4.社員同士の風通しを良くするコミュニケーション施策4選
- 4.1.部署横断プロジェクトで職場を超えたコミュニケーションを生み出す
- 4.2.読書・対話会で学びながらコミュニケーションの機会をつくる
- 4.3.定期的なワークショップで社員の多様な意見を引き出す
- 4.4.ランチ会や懇親会で非公式なコミュニケーションを促進する
- 5.風通しの良い職場づくりにむけたコミュニケーション活性化には職場単位での研修が最適
- 6.風通しの良い職場づくりにむけたコミュニケーション活性化ならLIFO®がおすすめ!
- 7.LIFOを活用して社内トレーナーがコミュケーション研修を展開している事例
- 8.まとめ:風通しの良い職場コミュニケーションを継続的に改善しよう
風通しの良い職場でのコミュニケーションとは?

「風通しの良い職場」という言葉をよく耳にしますが、具体的にどのような状態を指すのでしょうか。それは、従業員が自由に意見を交換でき、社内のコミュニケーションが活発に行われている環境のことです。
このような職場では、情報が滞ることなく流れ、心理的安全性が高く保たれているため、イノベーションが生まれやすく、従業員の定着率も高まります。ここでは、風通しの良い職場でのコミュニケーションの特徴について詳しく見ていきましょう。
言いたいことが言いたいときに言える
まず1つ目の特徴は、従業員が「言いたいことを言いたいときに言える」環境が整っていることです。これは単に発言の自由があるというだけでなく、タイミングを逃さずに意見や提案ができる状態を指します。
例えば、会議の場に限らず、日常業務の中でも気付いたことをすぐに共有できる雰囲気があることがその一例です。このような環境では、問題が小さなうちに発見され、早期解決につながりやすくなります。
また、アイデアが生まれたときにすぐに共有できるため、イノベーションが促進されます。従業員は自分の意見が尊重されていると感じ、積極的に発言するようになるでしょう。
言いたいことを言いたい人に言える
2つめの特徴は、「言いたいことを言いたい人に言える」という点です。職場にはさまざまな階層や部署があり、情報が特定の人にしか届かないという状況が生じやすいものです。
風通しの良い職場では、役職や部署の壁を越えて、直接必要な相手とコミュニケーションが取れる環境が整っています。
例えば、一般社員が役員に直接提案できたり、異なる部署間でもスムーズに情報交換ができたりします。このような環境では、情報の伝達が早く正確になり、組織全体の意思決定のスピードと質が向上します。また、従業員は自分の声が届くと実感できるため、帰属意識も高まります。
かまえなく自由に言える
3つ目の特徴は、「かまえなく自由に言える」ことです。つまり、過度に形式ばったり、言葉を選んだりすることなく、自然体で意見を述べられる状態を指します。これには心理的安全性が非常に重要です。
心理的安全性とは、批判や拒絶を恐れずに安心して発言できる状態のことです。このような環境では、従業員は失敗を恐れずにチャレンジする姿勢を持ち、新しいアイデアや提案を積極的に出すようになります。
また、多様な視点が尊重されるため、チームワークが強化され、職場の雰囲気も明るくなるでしょう。
不作法ではなく、しこりを残さない
最後に、風通しの良いコミュニケーションは「不作法ではなく、しこりを残さない」という特徴があります。オープンなコミュニケーションを推進するあまり、マナーやルールを無視した発言が許されるわけではありません。互いを尊重し、建設的な対話を心掛けることが大切です。
意見の対立や衝突があっても、それが個人攻撃にならず、問題解決に向けた健全な議論として成立することが重要です。
このようなコミュニケーションスタイルを実現するためには、適切なフィードバックの方法や、相手の立場に立って考える姿勢、そして対話のスキルを組織全体で育成していくことが不可欠です。
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
職場の風通しを良くする基本的コミュニケーション施策5選

風通しの良い職場を実現するためには、具体的な施策を計画的に導入していくことが重要です。ここでは、組織全体で取り組める基本的なコミュニケーション施策を5つご紹介します。
これらの施策は比較的導入しやすく、効果も実感しやすいものばかりです。職場環境の改善を目指す第一歩として、ぜひ参考にしてください。
定期的な1on1ミーティングでコミュニケーションの機会をつくる
1on1ミーティングは、上司と部下が一対一で定期的に対話する機会を設けるものです。日常業務では言いづらい課題や悩み、キャリアの展望などを自由に話し合える場となります。
このミーティングを通じて、従業員の声を直接拾い上げることができ、早期に課題を発見することも可能です。
効果的な1on1ミーティングを実施するポイントは以下のとおりです。
|
▼1on1ミーティングについては下記で詳しく解説しています。
⇒1on1ミーティングとは?目的ややり方、効果を高める工夫を解説!
フリーアドレス制度で部署間のコミュニケーション障壁を取り除く
フリーアドレス制度は、固定席を廃止し、従業員が毎日自由に席を選べるようにする働き方です。この制度を導入することで、普段接点のない部署の人と隣り合わせになる機会が生まれ、自然と部署を超えたコミュニケーションが促進されます。
フリーアドレスを導入する際のポイントとしては、完全自由ではなくある程度のゾーニングを設けること、適切なICTツールでのサポート、そして個人の荷物を保管するロッカーの設置などが挙げられます。
また、導入前には従業員への十分な説明と準備期間を設けることで、スムーズな移行が可能になります。
オープンなコミュニケーションスペースを確保する(リアル・バーチャル)
従業員が自由に集まり、意見を交わしたりリフレッシュしたりできるスペースを設けることも効果的です。これはリアルな空間だけでなく、オンライン上のバーチャルスペースも含みます。
例えば、オフィス内にカフェスペースやラウンジを設けたり、オンラインチャットの雑談チャンネルを作ったりする方法があります。
このようなスペースがあることで、インフォーマルなコミュニケーションが活性化され、従業員同士の信頼関係が構築されます。
また、リラックスした会話の中から新しいアイデアや発見が生まれることも多く、組織のイノベーションを促進する力にもなります。
デジタルツールで時間や場所に縛られない情報共有を実現する
現代の職場では、さまざまなデジタルコミュニケーションツールを活用することで、時間や場所に縛られない情報共有が可能になっています。
チャットツール、ビデオ会議システム、プロジェクト管理ツール、社内SNSなどを導入することで、リモートワーク環境でも風通しの良いコミュニケーションを維持できます。
ただし、ツール導入だけでは効果は限定的です。以下の点に注意しましょう。
|
社内イベントで部門を超えたコミュニケーションを促進する
定期的な社内イベントの開催は、普段接点の少ない部門間のコミュニケーションを促進する絶好の機会です。これには、研修やワークショップのような業務関連のものから、スポーツ大会や忘年会などのレクリエーション的なものまで、さまざまな形態があります。
特に効果的なのは、異なる部署のメンバーが混ざるようなチーム編成で行うイベントです。例えば、部署横断のプロジェクトコンペティションや、ランダムに編成されたチームでの社内運動会などが考えられます。
このようなイベントを通じて、普段の業務では見られない一面を知ることができ、新たな人間関係の構築につながります。
▼会社内のコミュニケーション活性化の取り組みについては下記で詳しく解説しています。
⇒会社内のコミュニケーション活性化の取り組みとは?重要性と効果的な施策13選を解説
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
風通しの良い職場づくりのために管理職が実践すべきコミュニケーション手法4選

風通しの良い職場づくりにおいて、管理職の役割は非常に重要です。なぜなら、管理職の言動や態度が組織の雰囲気を大きく左右するからです。
どれだけ制度を整えても、管理職自身がオープンなコミュニケーションを実践していなければ、真の風通しの良さは実現しません。ここでは、管理職が実践すべき具体的なコミュニケーション手法を4つご紹介します。
管理職は組織の中間に位置し、上下のコミュニケーションの橋渡し役を担っています。経営層の方針や戦略を現場に伝えるとともに、現場の声や課題を経営層にフィードバックする重要な役割があります。したがって、管理職自身のコミュニケーションスタイルが組織全体の風通しに大きな影響を与えるのです。
また、部下は上司の言動を常に観察しています。管理職がどのようにコミュニケーションを取るかは、部下のロールモデルとなり、チーム全体のコミュニケーションスタイルに波及していきます。
以下では、管理職が率先して実践すべきコミュニケーション手法について詳しく見ていきましょう。
管理職自らが情報発信や共有する機会を増やす
管理職が率先して情報を発信・共有することは、風通しの良い職場づくりの第一歩です。経営方針や決定事項、部門の目標や進捗状況など、従業員が知るべき情報を積極的に伝えることで、組織全体の透明性が高まります。
さらに進んだ例では、「オープンブック経営」の考え方を取り入れ、財務情報を含む会社の状況を従業員と広く共有する企業もあります。このような透明性の高い情報共有は、従業員の当事者意識を高め、目標達成に向けた主体的な行動を促します。
効果的な情報共有のポイントは以下の通りです。
|
このような取り組みにより、従業員は組織の動きを理解しやすくなり、自分の仕事の意義や方向性を見失うことなく働けるようになります。
また、情報が隠されているという不信感が解消され、組織への信頼感が高まるという効果も期待できます。
管理職自らが失敗談を積極的に開示する
管理職が自らの失敗談やミスを隠さず、オープンに共有することは、心理的安全性を高める上で非常に効果的です。完璧を装う上司の下では、部下も同様に失敗を隠そうとしますが、失敗を認め、そこからの学びを共有する上司の下では、部下も安心して挑戦できる環境が生まれます。
「しくじり先生」と呼ばれる失敗共有イベントを開催し、失敗事例を共有し合う企業も増えています。これは単に失敗を共有するだけでなく、そこから得られた学びや改善策を議論する場として機能しています。管理職がこうしたイベントの先頭に立ち、自らの失敗を赤裸々に語ることで、「失敗は学びの宝庫」という文化が醸成されます。
失敗談を共有する際は、単に「こんなミスをした」という事実だけでなく、「何を学んだか」「どう改善したか」という点まで伝えることが重要です。これにより、失敗が成長の機会として捉えられる文化が醸成され、組織全体のレジリエンス(回復力)も高まります。
また、失敗を共有する際のトーンも重要です。自己批判に終始するのではなく、冷静に事実を分析し、建設的な教訓を引き出す姿勢が望ましいでしょう。このような姿勢は、部下にとって強力なロールモデルとなり、組織全体の学習文化を育む基盤となります。
心理的安全性を高めるため失敗を責めない
風通しの良い職場では、失敗やミスが発生した際の対応が非常に重要です。管理職は、失敗した個人を責めるのではなく、なぜその失敗が起きたのかというプロセスや環境に目を向けるべきです。失敗を個人の問題ではなく、組織の学習機会として捉える姿勢が必要です。
エイミー・エドモンドソン教授の研究によれば、心理的安全性が高い職場では、失敗は「非難の対象」ではなく「学習の機会」として扱われます。
具体的なアプローチとしては、失敗が起きた際に「誰のせいか」ではなく「何が起きたのか」「どうすれば防げるのか」という観点で話し合いを進めることが効果的です。
例えば、「5つのなぜ」という手法を用いて、表面的な原因ではなく根本原因を突き止めることで、同様の失敗を防ぐための本質的な対策を講じることができます。
また、失敗の大小を問わず、システムやプロセスの改善につなげる姿勢が重要です。小さな失敗や「ヒヤリ・ハット」の段階で改善することで、大きな事故や損失を未然に防ぐことができます。
こうした予防的アプローチを根付かせるためには、管理職が「報告してくれてありがとう」と感謝の意を示し、改善活動を積極的に評価することが効果的です。
このようなアプローチを一貫して実践することで、従業員は失敗を恐れずにチャレンジする姿勢を持ち、より創造的なアイデアを生み出せるようになります。そして、この「チャレンジの文化」こそが、イノベーションの源泉となるのです。
▼心理的安全性については下記で詳しく解説しています。
⇒「心理的安全性」その本質・作り方とは?今すぐ取り組みたい20の具体策を解説!
部下の意見を積極的に取り入れる
管理職が部下の意見やアイデアを積極的に聞き、可能な限り採用することも重要です。これにより、従業員は自分の意見が尊重され、組織に貢献していると実感できます。また、現場の声を生かすことで、より実効性の高い施策を打ち出せるというメリットもあります。
また、「反対意見を歓迎する」姿勢も重要です。全員が同意する案よりも、反対意見や異なる視点を含めて検討された案の方が、多くの場合より質の高い結果につながります。
例えば、重要な意思決定の前に必ず「悪魔の代弁者」を立て、案に対する批判的検討を行う方法を取り入れている企業もあります。これにより、見落としや問題点を事前に発見し、より堅牢な計画を立てることができています。
意見を取り入れる際のポイントとしては、以下が挙げられます。
|
このような取り組みを継続することで、従業員の当事者意識が高まり、組織全体の活性化につながります。
部下の意見を積極的に取り入れる管理職のもとでは、部下は「自分の意見が組織を動かす」という実感を得やすくなり、自発的な改善提案が次々と生まれる好循環へとつながります。
▼部下とのコミュニケーションについては下記で詳しく解説しています。
⇒部下とのコミュニケーションが見違える方法とは?上司が成果を引き出すポイントを解説
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
社員同士の風通しを良くするコミュニケーション施策4選

風通しの良い職場づくりには、管理職のリーダーシップだけでなく、社員同士の水平的なコミュニケーションも欠かせません。同僚間の活発な交流は、情報共有を促進し、相互理解を深め、チームワークを強化します。
ここでは、社員同士のコミュニケーションを活性化するための効果的な施策を4つご紹介します。これらの施策は、組織の風土や状況に合わせてカスタマイズしながら導入してみてください。
社員同士のコミュニケーションは、組織の知識創造の基盤となります。野中郁次郎教授の「SECIモデル」によると、暗黙知を形式知へと変換し、組織に蓄積していくには、社員間の対話や協働が欠かせません。特に異なる専門性や背景を持つ社員間の交流は、新たな視点や発想を生み出す源泉となります。
また、リモートワークの普及により、偶発的な出会いや雑談の機会が減少している現代では、意図的に社員同士のコミュニケーション機会を創出することが、より一層重要になっています。オンラインとオフラインを効果的に組み合わせた施策を検討していきましょう。
部署横断プロジェクトで職場を超えたコミュニケーションを生み出す
部署横断プロジェクトは、異なる部門のメンバーが共通の目標に向かって協働する機会を提供します。日常業務では接点のない社員同士が交流することで、新たな人間関係が構築され、組織全体のコミュニケーション網が広がります。
効果的な部署横断プロジェクトの例としては、新製品開発チーム、業務改善タスクフォース、社内イベント企画委員会などが挙げられます。これらのプロジェクトでは、メンバーが各自の専門知識や視点を持ち寄ることで、多角的な思考が促進され、イノベーションが生まれやすくなります。
また、プロジェクト終了後も構築された人間関係は維持され、部門間の連携がスムーズになるという効果も期待できます。
部署横断プロジェクトを成功させるポイントは、明確な目標設定、適切なメンバー選定、十分な権限委譲、そして成果の可視化と評価です。
特に重要なのは、プロジェクトの成果を組織全体で共有し、参加メンバーの貢献を適切に評価することです。これにより、次のプロジェクトへの参加意欲が高まり、組織全体の協働文化が醸成されます。
読書・対話会で学びながらコミュニケーションの機会をつくる
社内読書会や対話会は、知識の共有とコミュニケーションを同時に促進する効果的な施策です。特定のビジネス書や専門書を題材に、参加者が感想や気付きを共有することで、多様な視点に触れる機会となります。
読書・対話会を実施する際のポイントは以下の通りです。
|
このような活動を通じて、業務に直結する知識だけでなく、多様な価値観や考え方についても理解が深まり、日常のコミュニケーションの質も向上します。
また、読書や対話を通じた「学びの共同体」意識が醸成され、組織全体の知的好奇心や成長志向が高まるという効果も期待できます。
弊社でも毎週月曜日の夕方に定期的に開催しています。
▼読書・対話会については下記で詳しく解説しています。
⇒会社内での読書会(対話会)のやり方とは?展開ステップやコツを解説!
定期的なワークショップで社員の多様な意見を引き出す
定期的なワークショップの開催は、社員の多様な意見やアイデアを引き出す効果的な方法です。通常の会議とは異なり、ワークショップではファシリテーターの進行のもと、参加者全員が主体的に考え、発言する機会が保証されます。
リモートワーク環境でも効果的なワークショップを実施するため、デジタルツールを活用している企業も増えています。
例えば、オンラインホワイトボードやデジタル付箋ツールを使ったブレーンストーミング、オンライン投票システムを活用した意思決定プロセスなど、対面と同等以上の参加感と効果を得られる工夫がされています。
効果的なワークショップを実施するためには、テーマ設定が重要です。業務改善、新サービスのアイデア出し、組織の課題解決など、参加者が主体的に考えたくなるようなテーマを選びましょう。
また、ワールドカフェやアイデアソン、デザイン思考など、多様な手法を取り入れることで、参加者の興味を引き出し、活発な意見交換を促進できます。ワークショップを通じて生まれたアイデアや提案は、可能な限り実際の業務に反映することで、参加者のモチベーション向上にもつながります。
さらに、ワークショップの効果を最大化するためには、「心理的安全性」の確保が不可欠です。批判を恐れずに発言できる環境づくりのため、冒頭でグラウンドルール(基本ルール)を共有したり、ファシリテーターが積極的に介入して全員の発言機会を保証したりするなどの配慮が必要です。
ランチ会や懇親会で非公式なコミュニケーションを促進する
ランチ会や懇親会などのインフォーマルな場は、普段の業務では見られない社員の一面を知る貴重な機会となります。リラックスした雰囲気の中で交わされる会話は、信頼関係の構築やストレス軽減につながり、職場全体のコミュニケーションを活性化します。
また、「テーマ別懇親会」も効果的です。趣味や関心事をテーマにした懇親会を開催することで、部署や役職を超えた共通の話題で盛り上がれます。例えば、「読書好きの会」「マラソン部」「料理研究会」など、業務とは異なる文脈での交流が、新たな人間関係構築の糸口となります。
特にリモートワークが増える中では、オンライン上でのインフォーマルな交流の場も重要です。例えば、「オンライン・コーヒーブレーク」と称した15分間のビデオ会議セッションや、オンラインゲームを通じたチームビルディングなど、物理的な距離を超えた交流方法も積極的に取り入れるべきでしょう。
このような非公式な交流の場を効果的に活用するためのポイントとしては、以下が挙げられます。
|
これらの非公式なコミュニケーションの場を通じて構築された人間関係は、業務上のコミュニケーションをよりスムーズにし、組織全体の風通しを良くする基盤となります。
また、リラックスした環境での対話は、日常業務では出てこないようなアイデアや気付きをもたらすことも少なくありません。
このような「セレンディピティ(偶然の発見)」を促す場として、インフォーマルなコミュニケーションの機会を積極的に設けることが重要です。
▼職場のコミュニケーションについて、21の改善策をまとめました。下記からダウンロードできます。
風通しの良い職場づくりにむけたコミュニケーション活性化には職場単位での研修が最適

風通しの良い職場づくりにむけたコミュニケーション活性化には、個人単位の学習だけでなく、職場単位での研修が極めて効果的です。実際の職場メンバーと共に学び、実践することで、即座に職場の雰囲気改善につなげることができます。
ここでは、なぜ職場単位での研修が効果的なのか、その理由と期待される効果について解説します。
職場メンバーがそろっている
職場単位での研修では、日常的に共に働くメンバーが一堂に会して学ぶことができます。これにより、研修で学んだコミュニケーション手法を、その場で実践的に試すことができます。
また、普段の業務の中での具体的な課題や改善点について、チーム全体で認識を共有し、解決策を考えることができます。
研修での学びを即座に実務に反映できる環境があることは、スキル定着の観点からも大きなメリットとなります。
職場の認識を変えることができる
職場全体で研修を受けることで、コミュニケーションに関する共通認識を形成することができます。
例えば、「雑談は業務の妨げになる」という古い価値観を、「適切な雑談は職場の活性化に重要である」という新しい認識に更新することが可能です。
全員が同じ内容を学ぶことで、新しいコミュニケーション方法を実践する際の心理的なハードルを下げ、職場全体での行動変容を促進することができます。
▼職場単位でのコミュニケーション研修が有効な理由については下記で詳しく解説しています。
⇒職場の活性化につなげる方法とは?アイデアやポイントを紹介!
風通しの良い職場づくりにむけたコミュニケーション活性化ならLIFO®がおすすめ!

風通しの良い職場づくりにむけたコミュニケーション活性化なら自己診断ツールLIFO(Life Orientations)を活用した職場単位でのワークショップがおすすめです。
なぜなら、LIFOプログラムは心理学や行動科学をベースにして組み立てられた行動特性診断をベースに、職場単位でワークショップを行うためのワークブックなどのツールも体系的にそろえられているからです。
また、体系立てられたツールの使い方を社内トレーナーの方々にライセンス提供もされており、社内トレーナーの方々が職場単位でワークショップを展開していくことも可能です。下記に概要を紹介します。
自己診断ツールLIFOとは
LIFO(Life Orientations)は、個人の行動スタイルを診断する自己診断ツールです。このツールは、自分の強みや行動パターンを理解するために役立ちます。
LIFOは4つの基本スタイルに基づいており、これらのスタイルはそれぞれ異なる行動特性や価値観を持っています。
自分がどのスタイルに属しているかを知ることで、より良いコミュニケーション方法やストレス時の行動傾向を把握することができます。
LIFOを活用したコミュニケーション研修
LIFOを活用したコミュニケーション研修では、まず参加者が自己診断を行い、自分の行動スタイルを理解します。
この診断結果をもとに、どのようにして他者と効果的にコミュニケーションをとるかを学びます。
研修では以下のような内容が含まれます。
|
LIFO®プログラムは社内トレーナーで展開可能
LIFO®プログラムは、これまでの活用実績と実用性から、企業内でのトレーニングにおいて自信を持っておすすめできるプログラムです。
社内展開にあたっては、特定の準備と手続きを経ることで、コストを抑えながら、外部講師に委託したかのように、社内トレーナーによる効果的なプログラムを展開することが可能です。
以下に、その流れを詳しく説明します。
|
LIFOを活用して社内トレーナーがコミュケーション研修を展開している事例

背景・課題:
リコージャパン株式会社では、2010年の販売会社統合以降、各支社の固有の課題に対応できず、教育施策が本部主導で一方的になるなどの課題がありました。
また、コロナ禍以降、会食などの機会が減ったことにより、コミュニケーションの希薄化を招いていました。これらの課題を解決するために、社員自らが強みや弱みを理解し合い、横のつながりを強化する取り組みが求められていました。
LIFOプログラム(社内トレーナーライセンス)の導入:
その中で、LIFO(Life Orientations)を導入しました。LIFOの活用を通じて、社員一人一人の個性を診断し、自己理解と他者理解を促進しました。
これにより、非公式なコミュニケーションが減少する中でも、社員同士の相互理解を深めるための新たな手段を提供することができるようになりました。
また、LIFOプログラムライセンスを取得することで、社内トレーナーが自主的に研修を行えるようになり、組織風土改革を進めました。
LDcubeとの協力により、多様なワークショップを展開し、各支社・部門が抱える具体的な課題に対応できるようになりました。
社内展開:
プログラムの展開においては、事前のLIFO診断、ワークショップの実施、職場での実践、効果検証のサイクルを組み込みました。
参加者は、研修後の職場実践を通じて得られたスキルを評価し合い、PDCAサイクルを回すことで、持続的なスキルアップを図っています。
ラーニングプラットフォーム「UMU」を活用し、受講者同士が学び合う環境も整備しました。
社内トレーナーによる研修実施後の反応:
導入後、プログラム受講者の満足度は高く、多くの支社で「対人関係」や「マネジメント能力」などにおいて数値的な改善が見られました。
LIFOを活用したレクチャーは「人」の問題の解決に寄与し、特にアウトプット重視の体験学習が効果的でした。
UMUの活用と一連の学習サイクルの設計により、事務局の負担軽減と学習効果の向上が実現しました。
今後に向けて:
今後は、各支社や部門の課題に寄り添い、人材育成を継続的にサポートすることで、社員個々の自己成長と組織全体の活性化をさらに推進する予定です。
また、LIFO以外のライセンスプログラムも組み合わせ、人材育成のプログラムラインナップを増やしていきます。
これにより、組織内のさまざまな課題を解決し、全体の一体感を更に高められることを期待しています。
▼本事例はインタビュー記事の一部です。インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。
⇒リコージャパン株式会社様 ライセンスプログラム導入事例
まとめ:風通しの良い職場コミュニケーションを継続的に改善しよう
本記事では、風通しの良い職場でのコミュニケーションの特徴と、それを実現するための13の施策を紹介してきました。風通しの良い職場をつくるためには、単発の取り組みではなく、継続的な改善が欠かせません。組織全体、管理職、そして社員一人一人がそれぞれの立場で取り組むことで、徐々に組織文化として定着していきます。
重要なのは、全ての施策を一度に導入しようとするのではなく、自社の状況や課題に合わせて優先度を決め、段階的に実施していくことです。また、定期的に効果を測定し、必要に応じて施策の調整や改善を行うことも大切です。組織の風通しは、日々の小さな積み重ねによって徐々に良くなっていくものだということを忘れないでください。
風通しの良い職場は、従業員の働きがいを高め、創造性を引き出し、組織の持続的な成長につながります。これからも継続的にコミュニケーションを改善する取り組みを行い、全員が安心して意見を交わせる、活気あふれる職場を目指していきましょう。
株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。