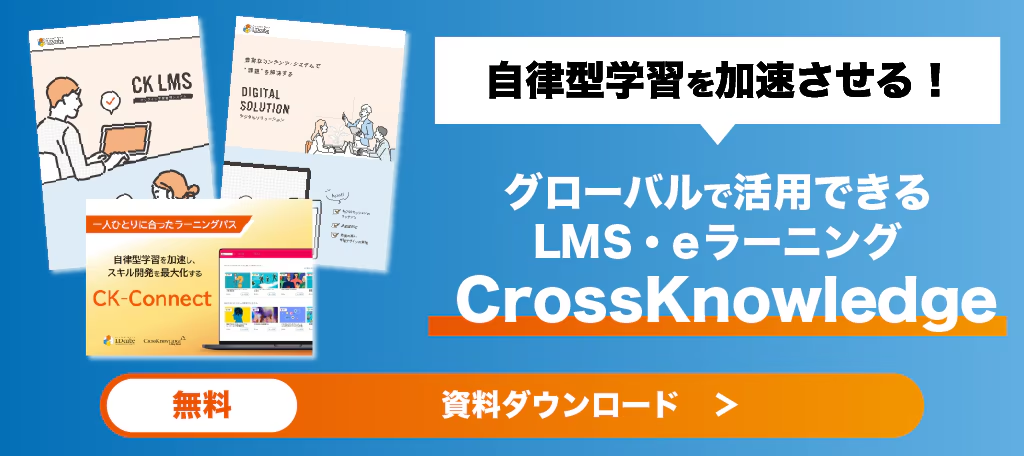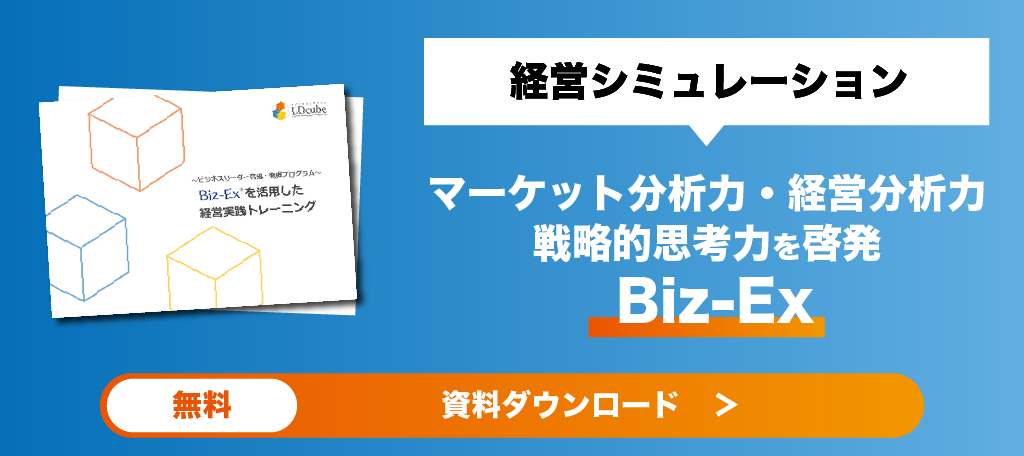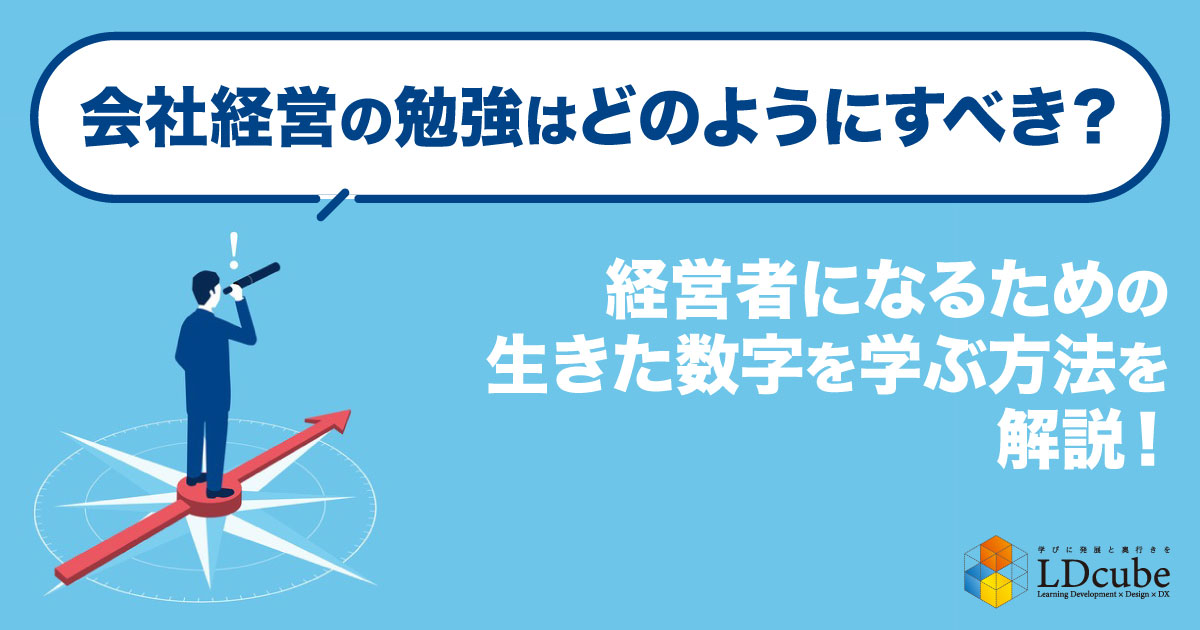
会社経営の勉強はどのようにすべき?生きた数字を学ぶ方法を解説!
「経営の勉強を始めたいけれど、何から手をつければ良いか分からない」「忙しい中で効率的に経営知識を身に付けたい」そんな悩みを抱えるビジネスパーソンや経営者候補の方は少なくありません。
それではなぜ、今経営を学ぶ必要があるのでしょうか?それは現場の仕事の延長線上に経営者の道はないからです。
起業する以外で経営者になるべくキャリアアップを目指そうと思ったら、経営の勉強をする必要があるのです。そのため、多くのビジネスパーソンが分かりやすい経営の勉強法を探しています。
実際、経営に必要な知識は財務・マーケティング・組織運営など多岐にわたり、体系的に学ぶのは容易ではありません。本格的に勉強しようと思えばお金もかかります。しかし、変化の激しいビジネス環境で競争力を維持し、会社を持続的に成長させるためには、ビジネスパーソン自身の継続的な学習が不可欠です。
本記事では、多くの企業の人材育成を支援してきた経験を基に、会社経営の勉強を効果的に進める具体的な方法や「生きた数字」を学ぶ方法をご紹介します。経営に必要な基本知識から体系的な学習ステップ、忙しいビジネスパーソンでも実践できる勉強法まで、実務に直結する内容を網羅的に解説していきます。
参考にできる資格試験や学習を継続していくためのコツも紹介します。
▼経営についての勉強法などについては下記で詳しく解説しています。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
目次[非表示]
- 1.会社経営の勉強は「生きた数字」で学ぼう
- 2.会社経営の勉強が重要な理由
- 3.会社経営の勉強で身に付けるべき基本知識
- 3.1.経営の全体像
- 3.2.財務・会計の基本知識
- 3.3.マーケティングと営業の基本
- 3.4.組織運営と人材マネジメント
- 4.会社経営の勉強を体系的に進める5つのステップ
- 4.1.ステップ1:現状の学習課題を明確化する
- 4.2.ステップ2:学習目標と優先順位を設定する
- 4.3.ステップ3:基礎知識を体系的に習得する
- 4.4.ステップ4:経営シミュレーションで「生きた数字」を学ぶ
- 4.5.ステップ5:継続的な学習習慣を確立する
- 5.会社経営の効果的な勉強方法
- 5.1.経営シミュレーションによる疑似体験
- 5.2.書籍による学習
- 5.3.eラーニングなどのオンライン学習
- 5.4.セミナーや研修プログラムへの参加
- 5.5.資格試験を活用した勉強
- 6.会社経営の勉強には覚悟が必要
- 7.会社経営の勉強にはCrossKnowledgeのeラーニングがおすすめ
- 8.会社経営の勉強にはBiz-Exでの経営シミュレーションがおすすめ
- 9.まとめ:会社経営の勉強で競争力のある組織を築こう
会社経営の勉強は「生きた数字」で学ぼう

会社経営の勉強において、「生きた数字」を理解することは非常に重要です。
その効果的な学び方として、経営シミュレーションの活用が挙げられます。経営シミュレーションは、経営者が日々直面する意思決定や、それに伴う経済的な結果を仮想的に体験できる学習ツールです。これを通じて、参加者は状況により変動する「生きた数字」から学び、意思決定内容と結果(数字)の因果関係を深く理解することができます。
シミュレーションは特定のケースに基づいて設計されているため、参加者はケース内の代表取締役となって仮想状況下で当事者として経営判断を求められます。
例えば、マーケットの需要変動や競合他社の動向など、多様な要因を考慮し、意思決定する必要があります。このようにして、実際の経営環境と同様に投資判断を行ったり、コスト削減策を講じたりすることで、数字の背後にある意味を具体的に感じ取ることができます。
さらに、経営シミュレーションはフィードバックループを提供します。意思決定が売上や利益にどのように影響するのか、またその影響がどのように現れるのかを確認できます。これが「生きた数字」の意味合いです。
たとえ失敗しても、それを反省材料として次期の意思決定に生かすことができます。このように、経営シミュレーション経験は、実際の経営では時間もコストもかかる学びを短期間で反復的に経験できる大きなメリットがあります。
また、シミュレーションは多様なシナリオを安全な環境で試すことができるため、リスクを恐れずに大胆な仮説を検証できます。これにより、参加者は新しいビジネスモデルやマーケティング戦略を模索し、その成果を数字で評価する感覚を養えます。結果的に、このような経験は実際の経営活動において迅速かつ適切な意思決定を下すための直感と判断力を磨くことにつながります。
従って、経営シミュレーションを通じて「生きた数字」を学ぶことは、理論と実践を強固に結びつける貴重な経験であり、実世界での成功に向けた確固たる基盤を築くのに役立ちます。
会社経営の勉強が重要な理由

現場の延長線上に経営があるわけではない
営業や技術開発などの現場業務と経営業務は、根本的に異なる性質を持っています。現場では特定の機能や部門での成果が重視されるため、個々のプロジェクトや業務に集中し、具体的な目標を達成することが求められます。
一方で、経営はそれらの個別の目標を束ねて、企業全体としての最適化を図ることが重要です。現場での成功体験をそのまま経営に適用しようとすると、「部分最適」に陥り、全体としてのパフォーマンスが低下する可能性があります。これが起こる理由は、現場での優先的な課題と全社の優先的な課題は必ずしも一致しないからです。
経営者には、各部門の専門性を理解しつつ、全体を俯瞰する視点が必要です。これにより、異なる部門間での連携や資源配置の最適化が可能となり、組織全体の目標達成に向けた戦略的な判断を下すことができます。
経営には専門知識・スキルが求められる
経営には多岐にわたる専門知識とスキルが必要であり、これらを理解せずに適切な経営判断を行うのは困難です。特に重要な領域として、以下の4つが挙げられます。
|
これらの知識やスキルは、現場の経験だけでは自然に身に付くことはありません。体系的な学習と実践を通じて、経営者としての能力を高めることが必要です。経営者は、常に新しい情報を取り入れ、変化する環境に適応するための準備を怠らないことが求められます。
知的理解と実践・経験値が必要
経営力向上には理論的知識と実践経験の両輪が不可欠です。知識だけでは机上の空論になりがちで、実際の状況に適用することが難しいことがあります。
例えば、市場トレンドや消費者の行動を理解するためのマーケティング理論を知っていても、それを特定のビジネス環境に適用するには実践経験が必要です。一方、経験だけでは体系的な理解に欠け、複雑な問題を的確に分析・解決する能力が限られることがあるため、理論に基づいた知識の土台が不可欠です。
経営知識を持つことで、同じ経験をしても得られる学びの質が格段に向上します。知識と経験の組み合わせにより、戦略の立案や問題解決においてより柔軟で効果的なアプローチが可能となります。また、経営環境の急激な変化に対応するためには、過去の経験に加えて継続的な新しい知識の習得が必要です。
このような学習機会を活用することで、経験値の不足を補い、より短期間で経営力を向上させることが可能となるのです。
会社経営の勉強で身に付けるべき基本知識

経営者が習得すべき知識は多岐にわたりますが、まずは以下の4つの基本領域を体系的に学ぶことが重要です。これらの知識は相互に関連し合い、総合的な経営力の基盤となります。
経営の全体像
経営の全体像とは、企業が長期的に成功を収めるための戦略と運営についての全体的な活動を指します。これには、企業のビジョンやミッションを明確にし、それを基に短期および長期の目標を設定することが含まれます。
経営には、財務、マーケティング、生産、人事、法務など、多岐にわたる分野が関与しており、これらを統合して最適な意思決定を行うことが求められます。具体的には、資源の効果的な配分、リスク管理、市場における競争優位性の確立や維持、組織文化の醸成などが含まれます。
また、経営者は企業を取り巻く環境変化に迅速に対応し、持続的な成長を目指さなければなりません。このように、経営は個々の活動が独立して行われるのではなく、各要素が連携し合っていることを理解し、全体として企業の目指す方向へ進んでいくことが重要です。
財務・会計の基本知識
財務・会計は「経営の言語」と呼ばれ、経営者にとって必須の知識です。損益計算書(P/L)で収益性を、貸借対照表(B/S)で財務の健全性を、キャッシュフロー計算書(C/S)で資金の流れを把握します。
これらの財務諸表を読み解くことで、自社の経営状態を客観的に評価し、根拠のある経営戦略を立案できます。
|
これらの知識により、数字に基づいた経営判断が可能になります。
マーケティングと営業の基本
市場での競争優位を築くには、マーケティングと営業の体系的な理解が不可欠です。マーケティングでは市場分析、顧客セグメンテーション、ポジショニング戦略を学び、営業では顧客との関係構築から成約、継続取引までのプロセスを習得します。
特に重要なのは、集客から顧客生涯価値(CLV)の最大化までの一連の流れを設計することです。デジタル化が進む現代では、オンラインとオフラインを統合したマーケティング戦略も必要です。
現代ではデジタルマーケティングの知識は必須です。経営者自らがデジタルマーケティングについての知見と、一部の実務(コンテンツの発信など)を担いながらマーケットと対話していく姿勢が重要です。
また、見込み客のフォローアップや既存顧客との関係維持により、安定した収益基盤を構築する手法とそれらのデジタル化を図ることも学ぶべき重要な要素です。これからの時代はリソース不足との戦いです。AIなどを積極的に取り入れ、リソース不足を解消していくことも不可欠です。
組織運営と人材マネジメント
企業の成長には優秀な人材の確保と育成が不可欠です。組織運営では採用、育成、評価、報酬の仕組みを体系的に設計し、従業員のモチベーションと生産性を最大化します。
特に中小企業では属人的な業務が多くなりがちですが、仕組み化を進めることで組織の安定性と成長性を両立できます。
|
これらの知識により、人材を最大の経営資源として活用できるようになります。
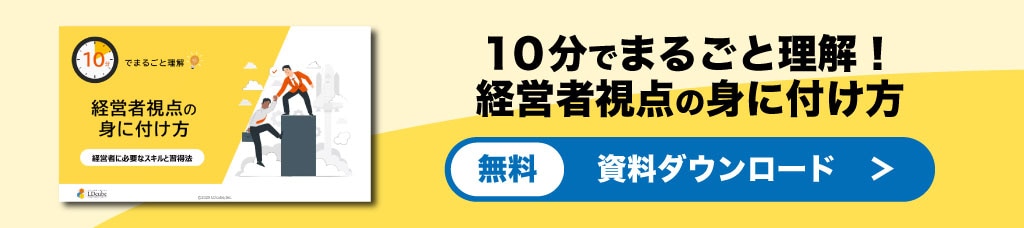
会社経営の勉強を体系的に進める5つのステップ

効果的な経営学習には計画的なアプローチが不可欠です。以下の5つのステップに従って学習を進めることで、限られた時間を最大限に活用し、実践的な経営力を身に付けることができます。
ステップ1:現状の学習課題を明確化する
まず自身の経営知識とスキルの現状を客観的に把握します。経営の主要分野(財務・会計、マーケティング、組織運営、戦略立案など)について、それぞれの理解度と実践経験を5段階で評価してください。
同時に、現在直面している経営課題や、今後1~3年で解決したい問題を具体的にリストアップします。この作業により、学習の優先順位が明確になり、効率的な学習計画を立てられます。
また、定期的に自己評価を見直すことで、学習の進捗を確認し、必要に応じて計画を修正することも重要です。
ステップ2:学習目標と優先順位を設定する
現状分析を基に、具体的で測定可能な学習目標を設定します。
「財務諸表を読めるようになる」ではなく、「3カ月以内に自社の損益分岐点を正確に算出し、改善策を3つ以上立案する」といった具体的な目標が効果的です。
学習分野の優先順位は、緊急度と重要度のマトリックスを用いて決定します。
|
この分類により、限られた学習時間を最も効果的に配分できます。
ステップ3:基礎知識を体系的に習得する
優先順位に従って基礎知識の習得を開始します。この段階では幅広い分野の基本を押さえることが重要で、特定分野への偏重は避けるべきです。
経営の全体像を把握するため、各分野の要素をバランスよく学習します。基本概念、フレームワーク、計算方法などを習得し、経営用語の正確な理解も心がけます。学習方法としては、信頼できる書籍やeラーニングプログラムを活用し、資格試験(中小企業診断士など)の受験も知識の体系化に効果的です。
筆者も体系的な学習に中小企業診断士試験の教材を活用しました。日商簿記検定などもありますが、社長となる経営者は経理の細部まで理解する必要はないため、簿記検定は意味がないかもしれません。
ただし、簿記3級程度の知識がないと財務会計について理解ができません。まったく学習したことがない人は基礎から学べる簿記3級から始めるもの1つの手です。
ステップ4:経営シミュレーションで「生きた数字」を学ぶ
基礎知識の習得後は、実践的な経営シミュレーションにより「生きた数字」を体験します。
経営シミュレーションでは、仮想企業の経営を疑似体験し、意思決定の結果を数値で確認できます。このアプローチにより、理論知識と実践の橋渡しが可能になります。
|
このステップにより、知識を実践で活用する能力が大幅に向上します。
ステップ5:継続的な学習習慣を確立する
経営環境は常に変化するため、継続的な学習が不可欠です。日常業務に学習時間を組み込み、習慣化することが成功の鍵となります。
週単位で学習計画を立て、毎日学習時間を確保します。また、学んだ知識を実務で積極的に活用し、その結果を振り返ることで学習効果を最大化できます。経営者同士の勉強会やセミナーへの参加も、継続的な学習のモチベーション維持に効果的です。
さらに、業界トレンドや新しい経営手法についても定期的に情報収集し、既存の知識体系をアップデートしていくことが重要です。
会社経営の効果的な勉強方法

経営の勉強にはさまざまなアプローチがありますが、学習目的と自身の状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。独学で学ぶことができますが、完全な独学では学習に偏りが出てしまう可能性があり危ないです。時に外部のリソースなども効果的に活用して学習を進めることをお勧めします。以下に、特に効果的な5つの学習方法とその活用法を紹介します。
経営シミュレーションによる疑似体験
経営シミュレーションは「生きた数字」を体験できる最も実践的な学習方法です。経営シミュレーションでは、仮想企業の経営を通じて戦略思考や財務会計の大切さを実体験できます。
参加者は限られた資源の中で投資判断、価格設定、人員配置などの経営判断を行い、その結果を財務諸表で確認します。このプロセスにより、理論知識と実践のギャップを埋めることができます。
|
実際のリスクなしに多様な経営状況を経験できるため、新任経営者には特に有効な学習方法です。
書籍による学習
書籍は最も費用対効果の高い学習方法の1つです。著者が数十年かけて蓄積した経営経験や研究成果を、数時間で習得できる点が大きなメリットです。
成功している経営者の多くが読書家であることからも、その効果は実証されています。体系的な学習には経営学の基本書を、特定分野の深掘りには専門書を活用します。経営雑誌の定期購読により、最新のトレンドや事例も継続的に収集できます。
ただし、読書で得た知識を「知っているだけ」で終わらせず、実務での活用を意識することが重要です。また、自分の専門分野や興味のある領域に偏らず、幅広い分野の書籍を選択することで、経営の全体像を把握できます。
eラーニングなどのオンライン学習
デジタル技術の発達により、オンライン学習の質と利便性が大幅に向上しています。
eラーニングプラットフォームでは、体系化された経営コースを自分のペースで受講でき、動画、テキスト、演習問題を組み合わせた効果的な学習が可能です。
移動時間やスキマ時間を活用できるため、忙しい経営者にとって非常に効率的な学習方法です。
|
ただし、一方向的な学習になりがちなため、質問や議論の機会を別途確保することが推奨されます。
セミナーや研修プログラムへの参加
セミナーや研修は、短期間で専門知識を効率的に習得できる学習方法です。専門家による体系化された講義内容と、その場での質疑応答により、理解度を深めることができます。
また、他の参加者との交流を通じて、新たな視点や実践事例を学ぶ機会も得られます。セミナーは主催者の目的により内容が異なるため、事前に主催者の背景と目的を確認することが重要です。
|
投資対効果を最大化するため、学習目的を明確にしてセミナーを選択することが大切です。
資格試験を活用した勉強
資格取得を目標とした学習は、体系的な知識習得と学習継続のモチベーション維持に効果的です。
中小企業診断士などの資格は、経営に直結する知識を体系的に学べます。試験という明確な目標があることで、学習計画を立てやすく、継続しやすいというメリットがあります。
|
ただし、資格取得自体が目的化しないよう注意し、実務での活用を常に意識することが重要です。投資した時間に見合う実践的な価値を得られるよう、自社の課題と関連性の高い資格を選択しましょう。
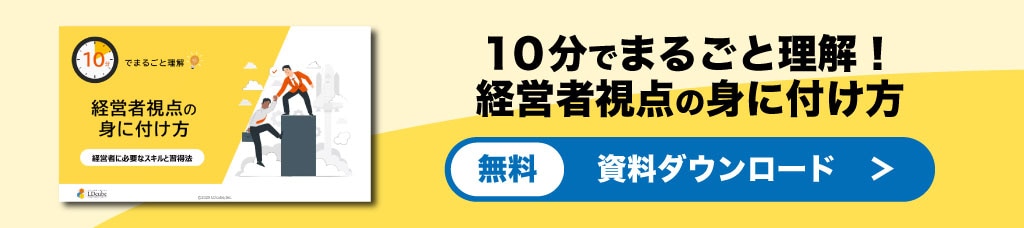
会社経営の勉強には覚悟が必要

経営の勉強の重要性を理解していても、実際に継続して学習を続けることは簡単ではありません。現実的な困難を理解し、適切な覚悟を持って学習に臨むことが成功への第一歩となります。
勉強には時間がかかる
経営に必要な知識は膨大で、短期間で習得できるものではありません。財務・会計、マーケティング、組織運営、戦略立案など、各分野の基礎を理解するだけでも相当な時間を要します。
特に初心者の場合、基本的な経営用語の理解から始める必要があり、実践レベルに到達するまでには数年の継続的な学習が必要です。忙しい日常業務の中で学習時間を確保することも大きな挑戦です。
しかし、この時間投資は将来の経営成果に直結するため、長期的な視点で取り組むことが重要です。
苦手な領域も存在する
経営者といえども万能ではなく、得意分野と苦手分野が存在します。
営業出身者にとって財務・会計は難しく感じられるかもしれませんし、技術者出身者にはマーケティングが苦手に思えるかもしれません。しかし、経営では全ての分野の基礎知識が必要であり、苦手だからといって避けて通ることはできません。
苦手分野に対しては特に時間をかけ、基礎から丁寧に学習することが大切です。
投げ出さずに続けるモチベーション維持
経営の勉強で最も困難なのは、長期間にわたって学習を継続することです。日々の業務に追われて学習時間が確保できなかったり、学習内容が実務に生かされていないと感じたりすると、モチベーションが低下しがちです。継続のためには明確な目標設定と進捗の可視化が重要です。
短期目標と長期目標を設定し、定期的に達成状況を確認します。また、学習仲間を見つけたり、経営者同士の勉強会に参加したりすることで、継続的な学習環境をつくることも効果的です。
学習した知識を実務で積極的に活用し、その成果を実感することで、学習への動機を維持し続けることができます。
会社経営の勉強にはCrossKnowledgeのeラーニングがおすすめ
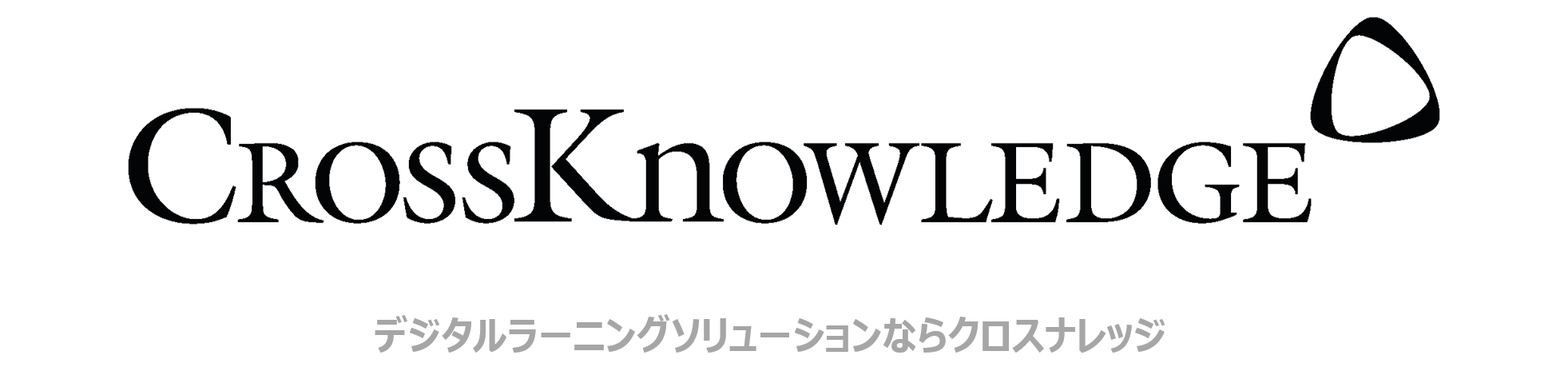
CrossKnowledgeのeラーニングプラットフォームは、経営について学ぶための効果的な手段として世界中の企業やビジネスパーソンに活用されています。特徴を紹介します。
|
これらの特徴を持つCrossKnowledgeのeラーニングは、経営について効果的に学びたいビジネスパーソンにとって価値ある学習ツールといえるでしょう。
また、企業としても社員のスキルアップを効率的かつ持続的に支援するためのソリューションとして最適です。
▼CrossKnowledgeの特徴については下記で詳しく解説しています。
⇒グローバル企業が人材育成で選ぶeラーニングのポイントとCrossKnowledgeの可能性
会社経営の勉強にはBiz-Exでの経営シミュレーションがおすすめ

Biz-Exでの経営シミュレーションは、経営意思決定力を実践的に磨くために非常に効果的な方法です。ここでは、その理由について説明します。
|
Biz-Exの経営シミュレーションは、理論を実践に変換し、リアルなビジネス場面での経営意思決定力を発揮するための準備を整える機会を提供します。
この実践的なアプローチは、意思決定力を大幅に向上させるための強力な学習ツールです。
▼Biz-Exについては下記で詳しく解説しています。
⇒経営シミュレーションとは?人材育成の新手法・研修について解説
経営シミュレーションを活用している支援事例

新人行員が経営者のパートナーの地位獲得を目指して【Biz-Ex活用事例】
社員数:1,000名以上
事業:金融業
導入前の課題
A銀行は、地方都市でのトップバンクとして、その存在感を示し続けています。しかし、バブル崩壊後の資産価値の急激な減少を経験したことで、「安全性第一」という考え方が組織全体に深く根付いていました。
こうした背景から、A銀行は安定した業績を維持してきました。しかし、東日本大震災やコロナ禍などの経験を経て、再び活性化する市場において、経営者の「投資行動に寄り添う」姿勢が求められるようになりました。
従来の融資方針が顧客である経営者の思考と乖離している状況が明らかになり、このギャップを埋めるため、新人行員を「経営者のパートナー」として育成する必要に迫られました。
そこで、30年間の固定観念を乗り越え、新しいマインドを持つ行員を育成するために、新入行員35名に対して、まっさらな状態で経営者的思考を学ばせるマインドセット研修を行うことにしました。
課題解決策
新人行員の育成において最も重要だったのは、経営者の思考をどのように理解させるか、ということでした。新入行員たちは基礎的なアカウンティングやファイナンスを座学で学んでいたものの、それらの知識が実際の経営や投資活動とどう結びつくのかを実感していませんでした。
そこで、このギャップを埋めるために、A銀行は『Biz-Ex』という経営シミュレーションプログラムを導入することにしました。Biz-Exは、実際の経営者の立場をシミュレーションしながら、財務諸表や市況分析を行い、経営の意思決定を体験する研修プログラムです。
新入行員が現地での研修に取り組むことで、時間的な余裕を持ちながらも実践的な学びを得ることができました。研修中には、専属コーチがフォローを行い、理解度に応じたサポートを提供することで、個々の学習効果を最大限に引き出しました。
経営シミュレーション実施中の受講者の様子
経営シミュレーションの初期段階では、予想通り経営成績に個人差が見られました。しかし、Biz-Ex専属コーチのアドバイスのおかげで、2期目以降は差が縮まり、全体的な理解度が向上しました。
プログラムは個人の判断力を磨くことを重視していましたが、同期間での情報交換も奨励され、学習が促進されました。各期の決算発表では経営成績が公開され、健全な競争心が触発されました。これによって、新人行員たちは協力し合い、同時に互いに競争しながら積極的に学んでいました。
こうした取り組みを通じて、受講者たちは経営活動へのコミットメントを高め、組織人としても社会人としても必要なマインドを醸成しました。
さらに、Biz-Exで得た経営分析スキルや思考力を社内でアピールする機会にもなり、個々の能力が認められる場が提供されました。
まとめ:会社経営の勉強で競争力のある組織を築こう
会社経営の勉強はどのようにすべき?経営者になるための生きた数字を学ぶ方法を解説!について紹介してきました。
会社経営の勉強は「生きた数字」で学ぼう
会社経営の勉強が重要な理由
会社経営の勉強で身に付けるべき基本知識
会社経営の勉強を体系的に進める5つのステップ
効果的な会社経営の勉強方法
会社経営の勉強には覚悟が必要
会社経営の成功には体系的な学習が不可欠です。従来の座学だけでなく、経営シミュレーションによる「生きた数字」での実践的な学習が特に重要となります。
本記事で紹介した5つのステップに従い、現状分析から目標設定、基礎知識の習得、シミュレーション体験、継続的な学習習慣の確立まで、計画的に進めることで効果的な経営力向上が実現できます。
学習には時間と覚悟が必要ですが、その投資は必ず組織の競争力向上という形で還元されます。まずは自身の学習課題を明確にし、今日から経営学習の第一歩を踏み出しましょう。
株式会社LDcubeは経営意思決定力を高めるための経営シミュレーションプログラム『Biz-Ex』や経営について学ぶためのeラーニングなどのサービスを提供しています。
無料のデモ体験会なども行っていますので、お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。