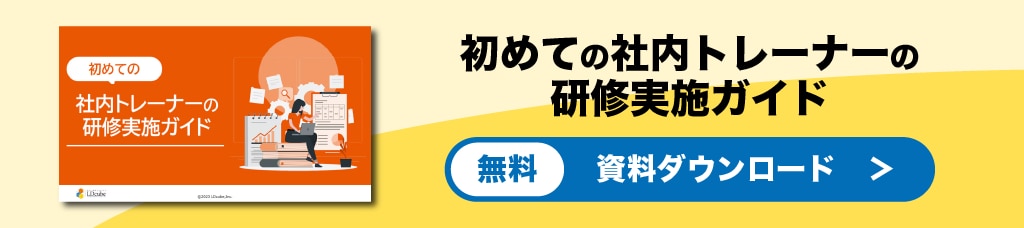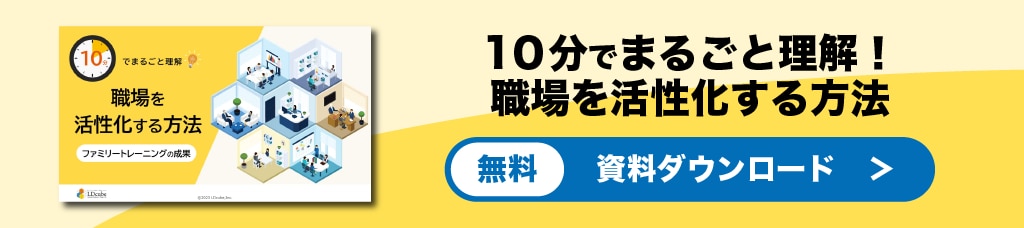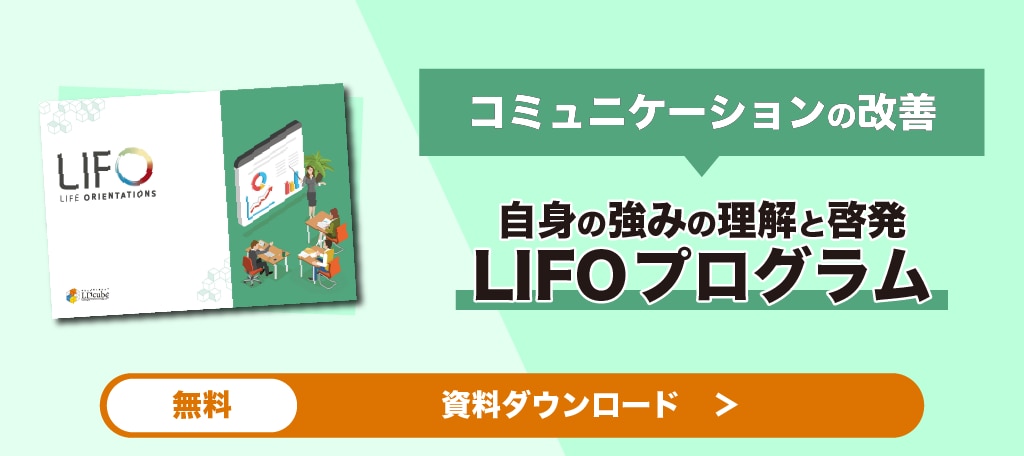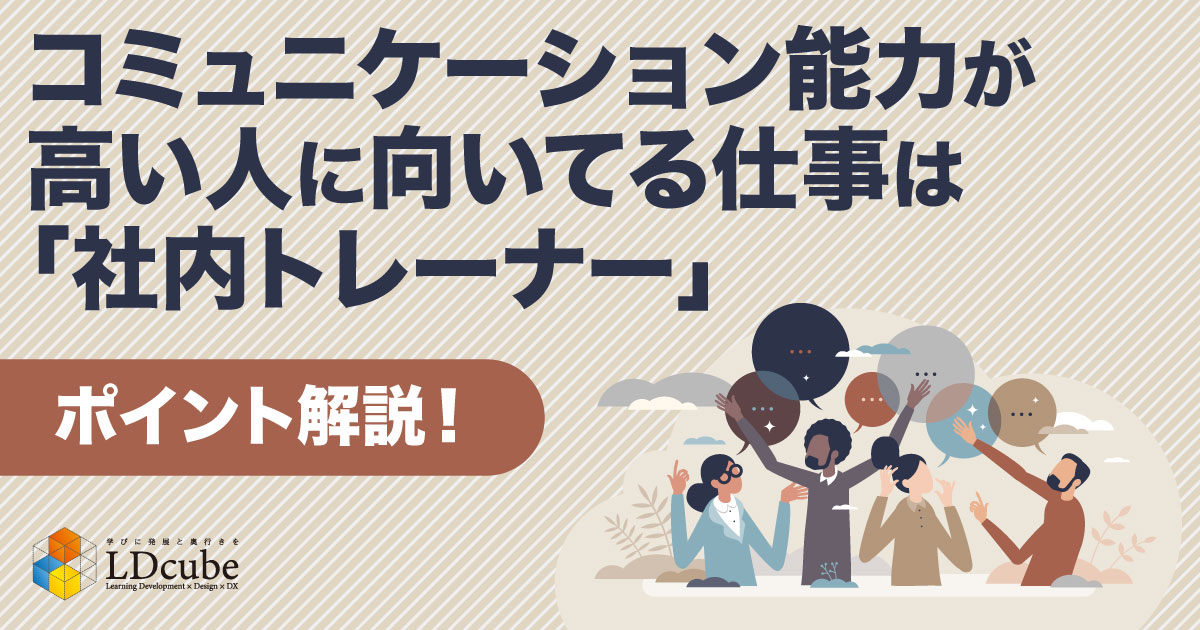
コミュニケーション能力が高い人に向いてる仕事は「社内トレーナー」|ポイント解説!
「自分はコミュニケーション能力が高いと思うけれど、どんな仕事が向いてるんだろう?」
「人と話すことが得意だから、この強みを生かせる職業に就きたい」
そんな風に考えている方は多いのではないでしょうか。コミュニケーション能力は、現代のビジネスシーンにおいて最も重要視されるスキルの1つです。しかし、単に「人と話すのが好き」というだけでは、自分に最適な職種を見つけることは難しいものです。
コミュニケーション能力が高い人には、相手の話を深く聞く傾聴力、状況に応じて柔軟に対応する適応力、そして相手に分かりやすく伝える表現力などを備えているといった特徴があります。これらの能力を最大限に生かせる仕事を選ぶことで、やりがいを感じながら成果を上げることができるでしょう。
本記事では、コミュニケーション能力が高い人に向いている仕事を紹介します。各職種の特徴や必要なスキルに加えて、実は向いている職種として「社内トレーナー」があります。社内トレーナーについても事例を交えて紹介します。
▼社内トレーナーの方向けの特集ページを作りました! | |
▼コミュニケーションについては下記で詳しく解説しています。
▼コミュニケーションのベースは自己理解です。
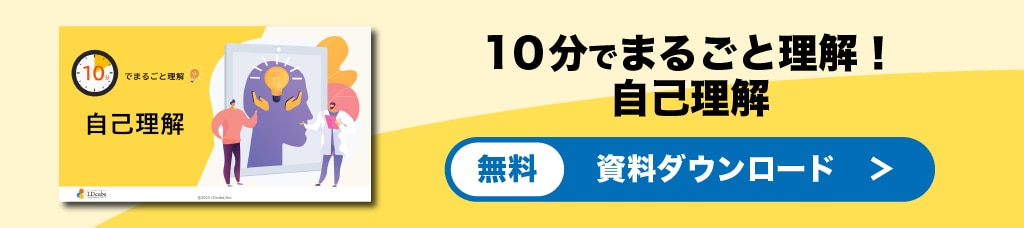 ▼社内トレーナー向けのガイドは下記からダウンロードできます。
▼社内トレーナー向けのガイドは下記からダウンロードできます。
目次[非表示]
実は、コミュニケーション能力が高い人に向いてる仕事は「社内トレーナー」

コミュニケーション能力が高い人に最も適した職種の1つが「社内トレーナー」です。社内トレーナーは企業内で社員の研修や教育を担当する専門職で、高度なコミュニケーションスキルが求められます。
近年、企業における人材育成の重要性が高まる中で、社内トレーナーの需要は増加していると考えられます。
弊社LDcubeが実施した調査では、
|
ということが明らかになりました。
デジタル化の進展や働き方の多様化により、従来の画一的な研修では対応できない個別ニーズへの対応が求められており、職場単位での研修実施や受講者一人一人との細やかなコミュニケーションが重要になっています。
また、リモートワークの普及により、オンライン研修での効果的なファシリテーション能力も新たに重要視されています。
|
コミュニケーション能力が高い人の特徴

コミュニケーション能力が高い人には共通する特徴があります。これらの特徴を理解することで、自分自身の強みを客観的に把握し、適切な職種選択につなげることができます。
現代社会では、テクノロジーの発達によりさまざまなコミュニケーション手段が利用可能になっていますが、本質的なコミュニケーション能力の重要性は変わりません。むしろ、対面、電話、メール、チャット、ビデオ会議など多様な手段を使い分ける柔軟性がより重要になっています。
また、グローバル化の進展により、異なる文化的背景を持つ人々とのコミュニケーション機会も増加しており、多様性への理解と配慮も現代のコミュニケーション能力に欠かせない要素となっています。
|
コミュニケーション能力が高い人に向いてる仕事の特徴

コミュニケーション能力を最大限に生かせる仕事には、いくつかの共通した特徴があります。これらの特徴を理解することで、自分の強みを発揮できる職場環境を見つけやすくなります。
現代の労働環境では、AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入により定型的な業務の自動化が進んでいます。しかし、人間同士の複雑なやりとりや創造的な問題解決が必要な業務では、依然として人間のコミュニケーション能力が不可欠です。
このような背景から、コミュニケーション能力を持つ人材の価値は今後さらに高まっていくと予想されます。
|
コミュニケーション能力が高い人に向いてる仕事(業界)

コミュニケーション能力を生かせる業界は多岐に亘ります。以下の7つの業界では、特にコミュニケーションスキルが重要視され、キャリア発展の可能性も豊富です。
|
コミュニケーション能力が高い人に向いてる仕事(職種)

コミュニケーション能力を直接的に生かせる具体的な職種をご紹介します。これらの職種では、コミュニケーションスキルが業務成果に直結し、キャリア形成においても重要な要素となります。
デジタル化が進む現代においても、人と人とのつながりを基盤とする、これらの職種の重要性は変わりません。むしろ、テクノロジーが発達することで、より高度で専門的なコミュニケーション能力が求められるようになっています。
AIやチャットボットでは対応できない複雑な感情や状況への配慮、創造的な問題解決、信頼関係の構築など、人間ならではの価値を提供することが期待されています。
|
コミュニケーション能力が高い人に向いてるのは営業関連が多い

コミュニケーション能力が高い人に最も適した職種として営業関連の仕事が挙げられることが多いのには、明確な理由があります。営業職の特徴とコミュニケーション能力の親和性について詳しく見ていきましょう。
営業職は、企業の収益に直接的に貢献する重要な職種であり、その成果がコミュニケーション能力に大きく依存するため、この能力を持つ人材が高く評価される傾向があります。
また、営業職での経験は他の職種への転職においても高く評価されることが多く、キャリアの汎用性という観点からも魅力的な選択肢となっています。さらに、成果が数値で明確に表れるため、自分の成長を実感しやすく、モチベーションを維持しやすい職種でもあります。
|
コミュニケーション能力が高い人に向いてる仕事に就くことメリデメ
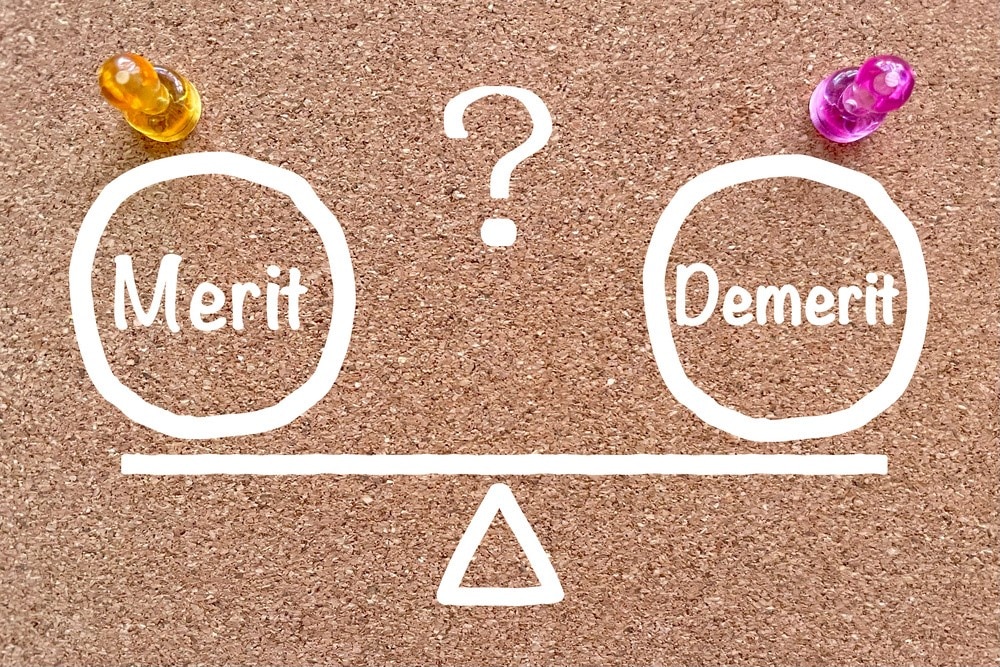
コミュニケーション能力が高い人に向いてる仕事に就くことにはメリットもある反面、一方ではデメリットもあります。仕事を選ぶ際にはメリット、デメリットを理解した上で選択することが重要です。
コミュニケーション能力が高い人に向いてる仕事のメリット
コミュニケーション能力が高い方にとって、そのスキルを生かせる仕事に就くことには多くのメリットがあります。まず、コミュニケーションが得意な人は他者との関係性を築くのが上手であるため、職場での人間関係を良好に保ちやすいです。
したがって、チームワークが求められる環境でも効果的に働けるのです。また、顧客やクライアントとの円滑なやりとりを通じて信頼を築くことで、顧客満足度が向上し、これがビジネスの成功に直接貢献するでしょう。
さらに、優れたコミュニケーションスキルは説得力や交渉力をも高めるため、営業やマーケティング、人事といった職種で成果を上げられる可能性が高まります。最後に、自分の意見やアイデアを効果的に伝えることができるため、昇進やキャリアパスの拡大といった面でもポジティブな影響があります。
コミュニケーション能力が高い人が向いてる仕事に就くことのデメリット
一方で、コミュニケーション能力が高いことがかえって特定の仕事でデメリットとなる場合もあります。
まず、コミュニケーションに長けているために、周囲からその役割を過大に期待されることがあります。これにより、プレッシャーやストレスを感じることがあり、精神的に疲弊する可能性があります。
また、常に他者と関わるため、時間やエネルギーを大きく消耗し、個人的な業務を後回しにしてしまうこともあります。そして、対人スキルに自信があるあまり、他者との意見が対立した場合に柔軟性を欠く事態に陥ることもあります。
さらに、コミュニケーションに重きを置く職場では、過剰な情報のやりとりに振り回されることがあり、生産性が低下するリスクも伴います。これらのデメリットを理解し、バランスを取ることが重要です。
コミュニケーション能力が高い人の次の仕事は「社内トレーナー」

コミュニケーション能力を生かしてキャリアを発展させたい人にとって、社内トレーナーは理想的な職種の1つです。しかし、この職種に到達するためには戦略的なキャリア形成が必要になります。
社内トレーナーという職種は、企業の人材戦略において重要性が増している専門職です。働き方改革、デジタルトランスフォーメーション、グローバル化など、現代企業が直面する課題に対応するためには、従業員の継続的なスキルアップが不可欠です。
そのため、効果的な人材育成を担う社内トレーナーの需要は今後さらに高まることが予想しており、コミュニケーション能力を生かしたい人にとって魅力的なキャリアパスです。
|
社内トレーナーがコミュケーション研修を展開している事例

背景・課題:
リコージャパン株式会社では、2010年の販売会社統合以降、各支社の固有の課題に対応できず、教育施策が本部主導で一方的になるなどの課題がありました。
また、コロナ禍以降、会食などの機会が減ったことにより、コミュニケーションの希薄化を招いていました。これらの課題を解決するために、社員自らが強みや弱みを理解し合い、横のつながりを強化する取り組みが求められていました。
LIFOプログラム(社内トレーナーライセンス)の導入:
その中で、LIFO(Life Orientations)を導入しました。LIFOの活用を通じて、社員一人一人の個性を診断し、自己理解と他者理解を促進しました。
これにより、非公式なコミュニケーションが減少する中でも、社員同士の相互理解を深めるための新たな手段を提供することができるようになりました。
また、LIFOプログラムライセンスを取得することで、社内トレーナーが自主的に研修を行えるようになり、組織風土改革を進めました。
LDcubeとの協力により、多様なワークショップを展開し、各支社・部門が抱える具体的な課題に対応できるようになりました。
社内展開:
プログラムの展開においては、事前のLIFO診断、ワークショップの実施、職場での実践、効果検証のサイクルを組み込みました。
参加者は、研修後の職場実践を通じて得られたスキルを評価し合い、PDCAサイクルを回すことで、持続的なスキルアップを図っています。
ラーニングプラットフォーム「UMU」を活用し、受講者同士が学び合う環境も整備しました。
社内トレーナーによる研修実施後の反応:
導入後、プログラム受講者の満足度は高く、多くの支社で「対人関係」や「マネジメント能力」などにおいて数値的な改善が見られました。
LIFOを活用したレクチャーは「人」の問題の解決に寄与し、特にアウトプット重視の体験学習が効果的でした。
UMUの活用と一連の学習サイクルの設計により、事務局の負担軽減と学習効果の向上が実現しました。
今後に向けて:
今後は、各支社や部門の課題に寄り添い、人材育成を継続的にサポートすることで、社員個々の自己成長と組織全体の活性化をさらに推進する予定です。
また、LIFO以外のライセンスプログラムも組み合わせ、人材育成のプログラムラインナップを増やしていきます。
これにより、組織内のさまざまな課題を解決し、全体の一体感を更に高められることを期待しています。
▼本事例はインタビュー記事の一部です。インタビュー記事全文はこちらからご覧ください。
⇒リコージャパン株式会社様 ライセンスプログラム導入事例
まとめ:コミュニケーション能力を生かして社内トレーナーへ
コミュニケーション能力が高い人に適した職業として「社内トレーナー」が注目されています。社内トレーナーは企業内で研修や教育を担当し、高度なコミュニケーションスキルを生かして社内の人材育成を推進する役割を担います。
デジタル化や働き方の多様化により、従来の画一的な研修では対応しきれない「個々のニーズへの対応力」が求められており、主体的に受講者と関わる細やかなコミュニケーション能力が不可欠です。
LDcubeの調査によれば、62%の企業で社内トレーナーによる研修が実施されており、特に1001名以上の組織では5名以上の社内トレーナーが活躍しています。これは、組織に合わせた柔軟な研修の構築や、受講者の理解度を把握し行動変容に向けたフォローアップが求められているためです。社内トレーナーは、研修効果を最大化するための環境作りや相互理解を深める役割を担い、組織全体の成長を支えます。
コミュニケーション能力が高い人には、傾聴力、言語・非言語の双方向コミュニケーション能力、状況に応じた柔軟なスタイル調整力が共通して見られます。これらのスキルは、社内トレーナーとして活躍する上で非常に役立ちます。トレーナーは、経営層から現場の社員までの橋渡し役を務めます。ニーズを正確に把握し、経営戦略を伝達する重要な職務を担うため、多岐に亘るコミュニケーション能力が求められます。
教育関連や広告業界、介護や医療などの職種と同様に、社内トレーナーの職務は、人との関わりが多く、コミュニケーションスキルが成果に直結する特性があります。現代のリモートワークの普及により、オンライン研修でのファシリテーション能力も新たに求められるスキルとなっており、これを有するトレーナーは一層その価値が高まっています。
実際の事例として、リコージャパン株式会社では、社内トレーナーを活用してLIFOプログラムを導入し、社員同士の相互理解を促進しました。この取り組みは、各部門の課題に即した研修を行い、社内の一体感を高めることに成功しています。したがって、高いコミュニケーション能力を持つ人にとって、社内トレーナーはキャリアを発展させるための魅力的な選択肢となります。
株式会社LDcubeでは、LIFO®プログラムを活用した研修会、eラーニング、LIFO®プログラムの社内インストラクター養成など幅広くご支援をしています。
無料体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。