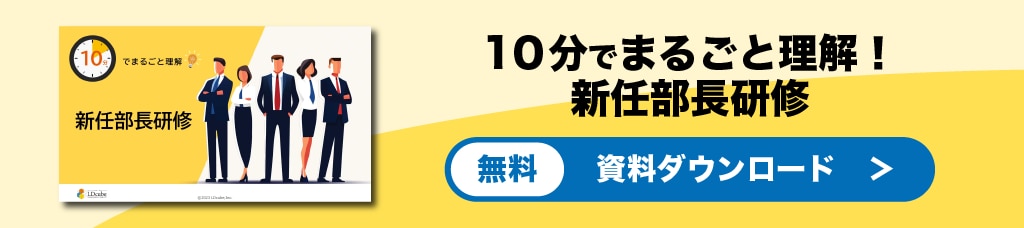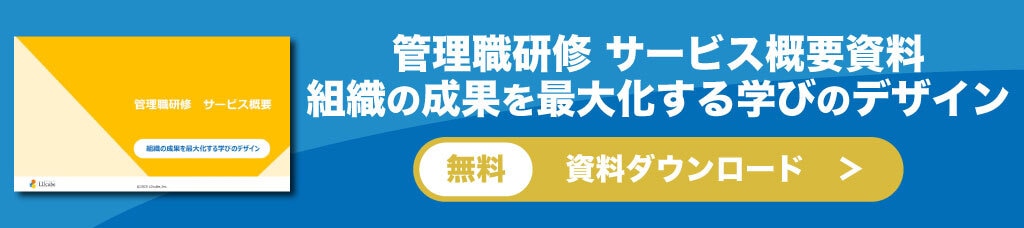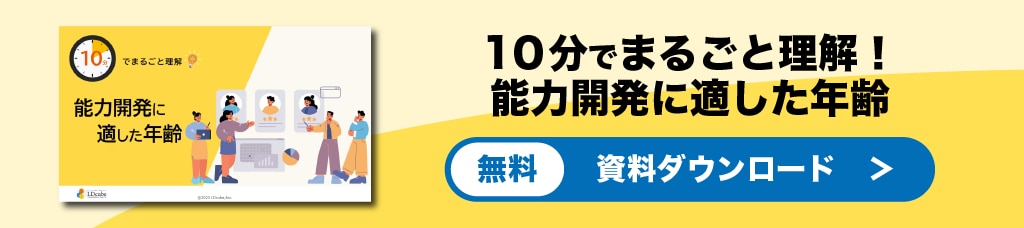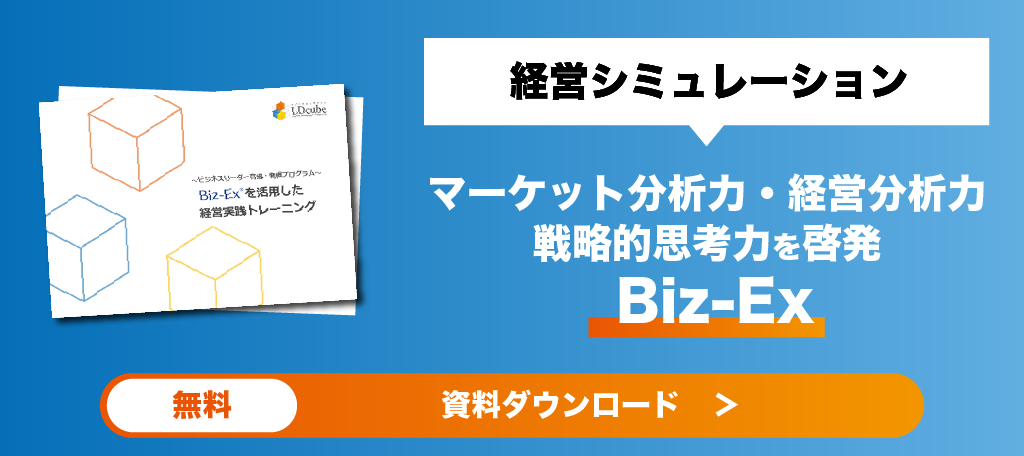新任部長研修とは?内容やポイント、部長になる人の特徴を紹介!
新しい部長に就任することは、一人のビジネスパーソンにとって大きなステップです。
しかし、新任部長がその役割を果たし、成功を収めるためには特別な研修が欠かせません。
多くの企業が新任部長研修を導入していますが、その内容が実際の経営にどれほど役立つかについて疑問を持つこともしばしばです。
特に、戦略的な経営判断や部門全体のパフォーマンスを管理するスキルが求められる場面では、単なる理論では不十分です。
まず、新任部長が直面する一般的な課題を考えてみましょう。新任部長には新しいポジションでの活躍が期待されますが、同時に役割に伴う責任やプレッシャーも感じることが多くあります。
例えば、大規模なプロジェクトの管理、チームのモチベーション維持、効果的な意思決定など、これまでとは異なる判断が求められます。
このような状況で適切なトレーニングやサポートがなければ、新任部長はストレスを感じ、パフォーマンスが低下するリスクがあります。
本記事では、新任部長研修を成功させるための具体的な方法を紹介します。特に、経営シミュレーションの導入が効果的な手段となりえます。
経営シミュレーションを通じて経営に関する高度な判断を事前に経験することで、新たなリーダーが自信を持ってチームを導き、組織全体のパフォーマンスを向上させることができます。
この機会に、実践的で効果的な研修プログラムを構築し、持続可能な成長を支える強力なリーダーを育成しましょう。
株式会社LDcubeはこれまで講師派遣型の部長研修や公開型の講座での部長研修、アセスメントの場面で多くの部長クラスの人材を見てきた経験を踏まえ、新任部長研修についての考え方などを解説していきます。
▼管理職研修や幹部育成についてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。
- 自己啓発でマネジメントを学び、生かすポイントとは?キャリアアップに生かすコツも紹介
- 役員研修とは何か?経営力強化と組織変革に必要なこと!
- 管理職研修の種類とは?3種類(上級・中間・新任)でテーマ・ポイントを解説!
- 経営幹部育成の落とし穴?効果的な育成のポイントなど解説!
- サクセッションプランとは?次世代の経営人材の育成についても解説!
- 経営意思決定とは?成功させるポイントや練習方法などを解説!
- 経営スキルとは具体的に何を指す?経営者に必要な15個の能力に分解して詳しく解説
- 次世代の経営者を育成する!新時代の人材教育ソリューション!
- 経営の勉強は何をすべきか?実践スキルを身に付ける効果的な方法を解説
- 次世代リーダー研修とは?開発すべき能力や実践に繋がるコツを解説
▼記事をまとめた資料は下記からダウンロードできます。
目次[非表示]
- 1.新任部長研修の主な内容
- 2.部長に求められる役割とは
- 3.部長と課長との違い
- 4.部長になる人の特徴(カギは経営視点)
- 4.1.事業環境を理解し、戦略的に思考できる
- 4.2.組織全体を見渡し、適切なリソース配分を行える
- 4.3.組織の持続可能性を追求できる
- 5.経営視点を高めるためには経営シミュレーションが最適
- 5.1.戦略的な思考の理解
- 5.2.意思決定能力の向上
- 5.3.結果と責任の理解
- 5.4.実際のビジネスリスクなしに経験を積む
- 6.経営シミュレーションなら「Biz-Ex(ビジックス)」
- 7.まとめ
新任部長研修の主な内容

部長には、組織の幹部としての役割を適切に遂行し、変化に対応していくために、多岐にわたるスキルと知識が求められます。
主には社内の階層別研修や新任部長対象のセミナーや外部のコンサルティング会社が実施している定型研修への参加などを通じて学びます。
会社が研修を用意していることもあれば、新任部長が自ら検索して研修や公開セミナー、eラーニングコースなどを探すこともあります。研修内容には下記のような要素が含まれます。
|
学ぶべきことが多岐に亘るため、新任部長研修を通じて体系的に学ぶことが効果的です。部長を目指す人は課長の時から、ビジネススキルや組織運営に必要なリーダーシップ、効果的なマネジメントを行うための知識とスキルを少しづつ身につけていくことがポイントです。
これにより、組織全体のパフォーマンスを向上させ、持続的な成長を実現することが期待されます。
▼部長は役員候補でもあります。次世代の経営者育成については下記をご覧ください。
⇨次世代の経営者を育成する秘訣!新時代の人材教育ソリューション!
部長に求められる役割とは

部長の役割は社員寄りではなく経営者寄りであり、組織の運営と成果をリードする重要なものであり、いくつかの主要な部分に分けることができます。
|
これらの多岐にわたる役割を果たすためには、部長自身が戦略的かつ実行力がある経営能力を持ち、リーダーシップを発揮し、効果的にコミュニケーションを取る能力が求められます。
部長と課長との違い

部長と課長の違いはさまざまですが、一つの大きな違いは管理する範囲とレベルです。
部長と課長は一般的に企業組織における、異なる階層の管理職でそれぞれが担う役割と責任に違いがあります。部長は課長よりも上位の役職です。
部長は一つまたは複数の部門または課の全体を指導・管理します。その目的や方針を設定し、戦略的な意思決定を行い、部門全体の業績を監視します。
部長は企業全体の運営や決策においても重要な役割を果たすことが求められ、上層部と情報を共有し、意思決定に参画することもあります。
一方で、課長は部門の一部(つまり課やチーム等)を担当します。
課長は部門内の特定領域に焦点を当て、その部分の業務運営や業績を管理します。
業務内容や目標達成に向けた計画を立案し、チームメンバーをリードしサポートする役割を果たします。
部長は課長よりも広い範囲を管理し、組織全体の戦略や方針を視野に入れることが求められます。
一方、課長はより特定の業務やチームを管理し、日常業務の実施と管理にフォーカスを置きます。
それぞれの役職に応じたスキルが必要です。
部長は組織全体のビジョン達成に向けて、多くの従業員や複数のチームを指導・管理し、全体の業績向上に貢献する戦略的な視野とリーダーシップスキルが求められます。
課長は、特定の業務領域に集中し、その業務遂行を効果的に管理・指導し、該当部分の業績向上に貢献するための能力とスキルが求められます。
上記のように部長と課長は役割や責任範囲が違います。
しかし、新任部長層や若手の部長は、部長に昇格したのに、役割の認識が変わらず課長の延長線上の仕事をしてしまうということがよく起こります。部長=大課長とならないよう注意が必要です。
▼現任の部長がOJTで時期部長を育成することも重要です。
⇒OJTでの経営幹部育成とは?~次世代は現役世代にしか育てられない!?~
部長になる人の特徴(カギは経営視点)

部長になる人は、管理者としての基礎がしっかりしていること、課長としての実績があり、人事評価でも高い評価を得ている、コンプラインスに対しての意識も高く、自己啓発に取り組み自分を成長させていこうとする姿勢があることなどが特徴としてあげられます。
特に重要なのが、経営視点です。部長と課長は違いますが、その違いの大きな点は経営視点の有無です。課長は与えられたリソースの中でうまくやりくりすることが求められますが、部長は経営視点を持ち、リソースの調達からリソース配分を行い、結果を出すことが求められます。
経営視点とは、組織全体を見据えた視野で、その組織が取り組むべき戦略や方向性を考え、行動を決定する方法論や思考のことを指します。
組織全体の経済的側面、競争力、成長性、持続可能性などを考慮しながらその組織を運営していく視点を意味します。
経営視点を持つということは以下のようなことを意味しています。
(経営視点をもつということ)
|
事業環境を理解し、戦略的に思考できる
市場の動向、競合他社の戦略、法規制の変更など、外部環境を適切に解釈し、組織の戦略をこれに適応させるための洞察を持ちます。
そして、長期的なビジョンと目標を設定し、それに到達するための戦略を立案します。しかもそれが妥当で実行可能なものであることを確認します。
組織全体を見渡し、適切なリソース配分を行える
部門やチームの視点だけでなく、組織全体を俯瞰(ふかん)し、全体がどう動いているか、どのような状況に対してどのような対応が必要か、全体として最適なものは何かを理解し、決定します。
その上で、ビジョン達成に利用可能なリソース(人的、財務的、物的など)を最も効率的かつ効果的に利用する方法を理解し、決定します。
組織の持続可能性を追求できる
単なる短期的な成功だけでなく、中長期的な視野に立った組織の持続可能性を重視し、それに対してどのように取り組むべきかを考えます。
組織の成長に向け、強化すること、変えること、変えないことなどを整理し、必要があれば経営会議などで変革案を提案し、実際に自社の変革活動が実行できることが必要です。
このように、経営視点を持つということは、いわゆる「森を見る」視点を持つということです。
つまり、個々の木(部門やチーム)にフォーカスを置くだけでなく、森全体(組織全体)に視野を広げる並行した視点を持つことを意味します。
それにより、局所的な成功だけでなく組織全体としての成功を追求することが可能となります。
▼経営者視点については下記で詳しく解説しています。⇒経営者視点とは?企業の今と今後の業績を上げるポイントを解説!
経営視点を高めるためには経営シミュレーションが最適

経営シミュレーションは、ビジネスの状況をシミュレーションすることで、経営視点を養うための最適な手法となります。
経営シミュレーションは即時性のあるフィードバックを提供します。
学習者が経営の意思決定を行い、その結果を予測・理解できる安全な学習環境を提供します。
経営シミュレーションを活用することが部長=大課長の枠を超え、経営視点を啓発する秘訣です。
経営シミュレーションを通じて下記を得ることができます。
(経営シミュレーションで得られること)
|
戦略的な思考の理解
経営シミュレーションは、参加者がビジネスの各側面とそれらが相互にどのように影響するかを理解することを可能にします。
市場の動向、競争の状況、財務管理など、経営に関わるさまざまな要素を一手に扱うことで、経営全体の視点で考えることを学びます。
意思決定能力の向上
経営シミュレーションは一連の意思決定を必要とします。
これらの意思決定は、さまざまなビジネスシナリオを作り出し、それに対する意思決定の影響を即座に見ることができます。
これにより良い判断力と意思決定能力を養うことができます。
結果と責任の理解
経営シミュレーションは、意思決定とその結果に対する直接的な責任を明確にします。
意思決定がビジネスの成功または失敗にどのように影響するかを直接見ることができ、その結果に対して責任を負う感覚を養います。
実際のビジネスリスクなしに経験を積む
経営シミュレーションは実際のビジネス状況を模擬したものであるため、リスクを伴わずに経験を積みつつ学習することができます。
失敗から学び、戦略や計画を改良することが可能です。
▼経営シミュレーションについては下記で詳しく解説しています。
⇒経営シミュレーションとは?人材育成の新手法・研修について解説
経営シミュレーションなら「Biz-Ex(ビジックス)」

Biz-Ex(ビジックス)は、経営シミュレーションアプリであり、会社経営のシーンをシミュレーションしながら体験的に学べるという特徴を持っています。
学習者は一貫して経営トップの立場で15期目の企業経営を引き継ぎ、自らの意思決定をもとに6期分の経営活動を経験します。
これは、従来の幹部育成の研修と一味違った形です。
それは、ロジカルシンキング・戦略・マーケティング・ファイナンス・アカウンティング・組織人事論・ビジネスプラン等についてインプットして学ぶということではなく、それらの知識やスキルを学習してきたとして、実際に使えるものになっているかどうか実践を通じて確認するというものです。
アプリ上の経営状況をシミュレーションできる環境の中で、自らの意思決定による経営活動を行い、企業の成長を目指します。
このプログラムは専属講師によるオンラインでのコーチングと組み合わせて進められ、受講者のシミュレーション結果と学習行動データをフィードバックすることで、受講者の強みや改善点を見つけ出すことに役立ちます。
経営シミュレーションを活用した人材育成の取り組みを通じて、経営視点を啓発することで、部長=大課長となってしまうことを回避し、部長としての役割発揮につなげていくことが可能です。
▼Biz-Exについてはwebサイトでもご案内しています。⇒経営シミュレーション実践型eラーニング Biz-Ex
まとめ
成功する新任部長になるための研修!日本の上級管理職育成の秘訣とは?について解説してきました。部長は組織の幹部として、課長と比べより大きな範囲と責任を担っています。
しかし、新任部長のうちは、部長としての役割や果たさねばならない責任についての理解が及ばず、課長の延長線上の仕事、部長=大課長となってしまうことも少なくありません。
その状態から脱し、部長としての責務を全うするためには経営視点の啓発が必要です。
経営視点を啓発するためソリューションとして、リスクの少ない経営シミュレーションを活用して、企業経営者の立場を疑似体験することがとても効果的です。
Biz-Exは良質な経営体験ができる経営シミュレーションです。新任部長の経営視点の啓発に活用してみてはいかがでしょうか。
株式会社LDcubeでは、良質な経営体験を提供する経営シミュレーション「Biz-Ex」を提供しております。
また、経営シミュレーションを行うとビジネススキルを学ぶ必要性を痛感される方もいらっしゃいます。
そのようなニーズに応え、さまざまなテーマについてのeラーニングコンテンツや世界レベルのMBA教授によるマイクロラーニングなどのサービスを提供しております。
無料のデモ体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。
▼関連資料は下記よりダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。