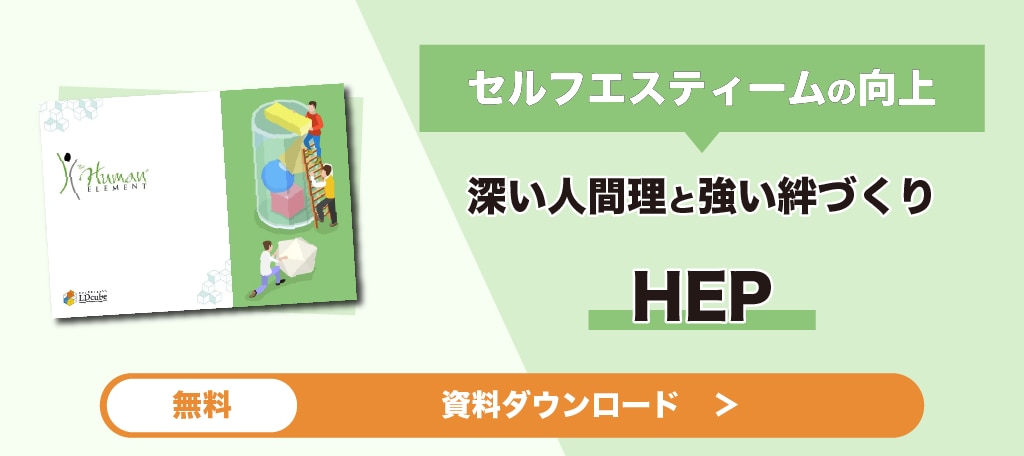武庫川女子大学様
大学生が「自己肯定感を高める講座」を受講【2024年度】
「自分って、こんな人だったんだ」――気付きから始まる、自己理解と対話の旅

武庫川女子大学

兵庫県西宮市にキャンパスを置く武庫川女子大学は、2029年で80周年を迎えます。13学部21学科(※2025年4月から)の総合女子大学として自立した女性を育んでいます。
HP:https://www.mukogawa-u.ac.jp/
経営学部:https://sba.mukogawa-u.ac.jp/
武庫川女子大学では、社会と協働した実践的な学びを促進する、「実践学習」にも力を入れて取り組んでいます。
はじめに
武庫川女子大学では、実践的な学びを重視した教育プログラムを数多く展開しています。
その一環として、2024年度に開講された授業では、
「自己理解」と「他者理解」を深めることをテーマにした特別なワークショップを実施しました。
本授業は、学生一人一人が“自分自身を知る”ことから始まり、その気付きを基に
「他者とどのように関わるか」「自分らしく生きるとは何か」を考える学びの機会となりました。
今回の授業では、自己肯定感(セルフエスティーム)を高めるための講座「ヒューマン・エレメント プログラム」の一部を体験。
さらに、学生たちはその学びを同世代に伝えるプロジェクトを企画・実施し、自らの気付きを広げる実践にも挑戦しました。
体験した学生たちの感想からは、「自分と向き合うことの難しさと大切さ」
「他者と本音で関わることの温かさ」「自分を好きになれるという感覚」が伝わってきます。
以下は、参加学生11名の気付きをまとめたものです。
目次
- 導入: なぜ今、セルフエスティームなのか
- 授業の概要: 学びと実践の2ステップ
- 受講生の声(一部抜粋): プログラムをきっかけに、自分の“本音”に気づいた学生たち
- 受講生の声 詳細①: 意外な自分、受け入れられなかった気持ち、その先にあったもの
- 受講生の声 詳細②: 「思っていた自分」と「診断結果の自分」のズレ
- 受講生の声 詳細③: ネガティブな自分に潜んでいた“防衛”の気持ち
- 受講生の声 詳細④: 「自己肯定感は、生まれつきじゃない」〜“育てていけるもの”としての自己理解〜
- プログラムエッセンス: ヒューマン・エレメントプログラムとのつながり
- まとめ: 未来へのヒントは「自分を知ること」から
導入:
なぜ今、セルフエスティームなのか
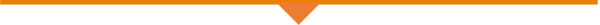
現代の若者が直面する「自己肯定感の低さ」は、メンタルヘルスや人間関係、キャリア形成にまで影響を及ぼす重要な課題となっています。
そのような中で、「自分を大切にする力=セルフエスティーム」を高めることの大切さが、教育現場でも注目されています。
授業の中心にあるのは、「人は誰でも“ありのままの自分”で価値がある」という考え方です。社会の中で他者と関わる中で、「自分はどのように見られているか」「何を期待されているのか」といった視点に引っ張られがちな今の若い世代にこそ、「自分自身を受け入れる力=セルフエスティーム」を高めることが必要だと私たちは考えました。
本授業では、学生がまず自身のセルフエスティームと向き合うプログラムを体験し、その学びを同世代へどのように広めていくかについて検討しました。最終的に、各チームが検討結果を発表し、意見交換を行いました。 これは単なる知識のインプットにとどまらず、実践と振り返りを通じた“自己理解の深化”の場でもありました。

授業の概要:
学びと実践の2ステップ

この授業では、次の2つのステップを軸に構成しました。
STEP
01
セルフエスティームを高める体験型講座
学生たちは、自己理解を深め、自分の感情や価値観に気付くためのワークに取り組みました。
「ありのままの自分を受け止める」「他者との比較ではなく、自分との対話を大切にする」といったテーマをベースにしたこの講座は、多くの学生にとって“初めて”の自己探究の場となりました。
STEP
02
同世代に広げるプロジェクト
学んだ内容を自分たちの言葉で発信するプロジェクトにも取り組みました。学生たちは、セルフエスティームという概念が自分たちにとってどれほど大切なものかを実感し、それを必要としている人たちにどう届けるかを真剣に考えました。
具体的には、中学生や高校生向けの授業で活用する案や、面接を控えた学生のための自己理解ツールとしての応用、さらには子育て中の保護者に向けてセルフエスティームを基軸とした情報共有の場を提供するなど、多様な可能性を検討しました。
ニーズ調査や市場分析を行い、オリジナルのプレゼンテーション資料を作成するなど、実社会を意識した実践的な取り組みが展開されました。
最後には、その過程を通して、自分自身のセルフエスティームの状態を振り返りました。
例えば、「もっと積極的に他者に働きかけるべきだったのに行動できなかった」ことや、「葛藤が起こりそうな場面を無意識に回避してしまった」ことなど、自分の行動や反応を見つめ直し、なぜそのとき行動できなかったのか、自分は何を恐れていたのかを深く考える機会となりました。
実践の場面だったからこそ、上記のような率直な振り返りが数多く生まれました。
受講生の声(一部抜粋):
プログラムをきっかけに、自分の“本音”に気づいた学生たち


自分の思っていた特性とは違う部分に気づき、驚いた。自己分析を通して自分を理解する過程が楽しかった。
自分の価値観に自信を持つことができた。今まで気づかなかった感情や思考に出会えて、新しい自分を発見できた。


グループワークで初めて本音で話せる場に出会い、他者との関わり方が変わった。
自己肯定感が低いと思っていたが、自分の強みを再認識でき、前向きに考えられるようになった。

受講生の声 詳細①:
意外な自分、受け入れられなかった気持ち、その先にあったもの

「私って、みんなといるのが好きなタイプだと思っていた。でも、診断結果は意外にも“ひとりの時間も心地いい”という特性が強いと出ていたんです」
プロジェクトに参加したある学生が、ふり返りの中で語ってくれた言葉です。
この取り組みでは、3回にわたって「エレメント診断」を受け、そこで得た結果をもとに自己理解を深める時間をもちました。最初の診断「エレメントB」では、自分の性格傾向や対人関係のスタイルが明らかになります。彼女は、自分を「みんなと一緒にいるのが好きなタイプ」だと考えていましたが、診断では「仲間性」が予想より低く、「一人でも楽しめる力」が強いと出ました。これに驚きつつも、ふり返ると「たしかに自分から誰かを誘うより、誘われるのを待つタイプかも」と納得していきました。
「統制」の項目でも、自分が「リーダー的に場を仕切りたい」と思っていたつもりが、実際には「人に流されやすい側」だったことに気づき、少しショックを受けたそうです。でも、「過去を振り返ると、いつも誰かの意見に乗っかっていたな」と、静かに自己理解が進んでいきました。
受講生の声 詳細②:
「思っていた自分」と「診断結果の自分」のズレ

診断結果に戸惑ったのは、彼女だけではありませんでした。
「私は周りのみんなを大切に思っているつもりだったのに、診断では“他人を重要だと感じにくい”という傾向が出て、すごく驚きました。なんでなんだろう?と考えました」
そのような声が他の学生からも上がりました。
一方で、「周りから自分が重要だと思われたい」という気持ちは強く、「自分ではそう見られていないと感じている」という言葉もありました。自己重要感が低く、「自分は大切にされていないのでは」と感じていたことに、改めて気付いたという学生もいました。
受講生の声 詳細③:
ネガティブな自分に潜んでいた“防衛”の気持ち

また、診断の中で「私は人に好感を持っている」や「私はみんなに好かれていると思うか?」という問いに対して、低いスコアを出した学生がいました。
「私は昔から“人に期待しない”ようにしていたんです。期待して裏切られるのが怖くて。だから、自分の気持ちを最初から抑えるクセが付いていたみたいです」
この気付きの裏には、失敗や拒絶を経験した中で身に付いた“防衛反応”があったのだと、彼女は語ってくれました。期待することで傷つくのが怖いから、最初から「期待しないように」していた。
そのことに気付き、彼女は静かに自分を受け入れつつ、これからは少しずつ変わりたいと感じているようでした。
受講生の声 詳細④:
「自己肯定感は、生まれつきじゃない」〜“育てていけるもの”としての自己理解〜

3回目の診断「エレメントS」では、「自己行動」「自己感情」「自己受容」など、自分に対する評価の傾向を見ていきます。
ここでも、「自己行動」のスコアが低く、「周りの意見に流されやすい」と感じた学生や、「自己感情」で自分を否定的にとらえがちだと気付いた学生が多くいました。
でも、プロジェクトを通じて彼らは一様にこう語っていました。
「自己肯定感って、持っている・持っていないの問題ではなくて、“育てていけるもの”なんだと思った」
「診断で得た気付きは、これからの自分に生かせるって前向きに思えるようになった」
自分を知ることは、時に怖くて痛みを伴う作業です。しかし、そこに“気付き”と“他者との対話”があることで、少しずつ「ありのままの自分」にOKを出す力が育っていきます。
学生たちの変化はゆるやかで、でも確実に「自分を受け入れていく力」を強めていきました。
プログラムエッセンス:
ヒューマン・エレメントプログラムとのつながり

この授業でのアプローチは、心理学に基づいた自己理解と人間関係改善の手法「ヒューマン・エレメントプログラム」のエッセンスを応用しています。
ヒューマン・エレメントでは、「自己受容」が対人関係の改善にもつながるという考えのもと、感情や自己イメージに深く向き合うことを重視します。
今回の授業でも、学生たちは“他人にどう思われるか”ではなく、“自分がどう感じているか”に焦点を当てることで、自然と他者への接し方も変わっていく実感を得ていました。
まとめ:
未来へのヒントは「自分を知ること」から

これから社会に出ていく若者たちにとって、「自分を知り、自分を大切にできること」は、どんな知識やスキルにも勝る“生きる力”になると信じています。
セルフエスティームを高める授業は、まさにその“出発点”。
これからも、多くの若い世代がこの体験を通じて、自分自身の価値に気付き、周囲とのよりよい関係を築いていくきっかけとなることを願っています。
これらの言葉からもわかるように、学生たちは自分を見つめ直す体験を通して、これまで気付かなかった感情や価値観に出会い、自分自身を少しずつ肯定できるようになっていきました。
セルフエスティームを高めることは、自信を持って他者と関わる力を育み、これからの社会で自分らしく生きていくための土台になります。この授業での学びと実践は、まさにその第一歩だったのです。
今後も、こうした“自分を知る・受け入れる”ことから始まる教育が、若い世代の可能性を広げるきっかけになっていくことを願っています。

関連記事
Contact
人材育成でお悩みの方は、お気軽にご相談ください
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
人材育成に関する
お役立ち資料はこちらから
お電話でのお問い合わせはこちら
平日9:00~17:30