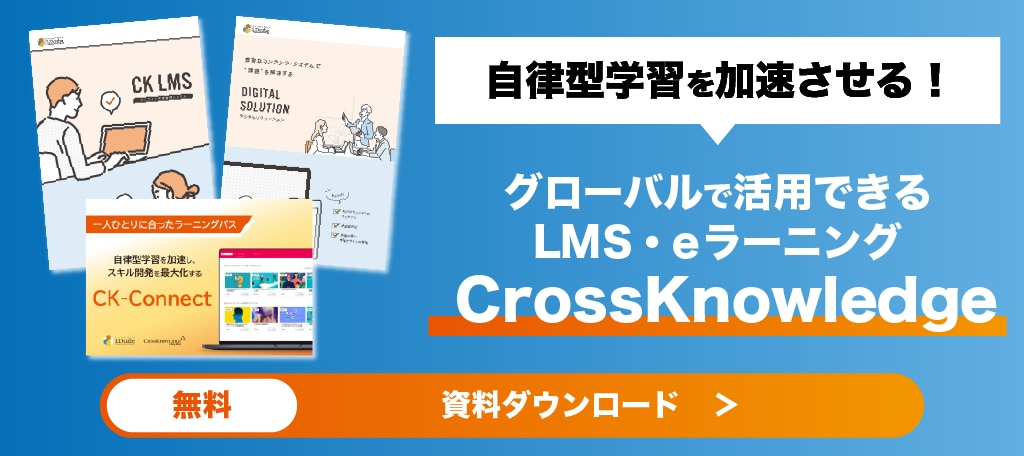LMS(学習管理システム)の構築方法とは?導入に失敗しないポイントを解説!
社内教育のデジタル化が進む現在、LMS構築は多くの企業にとって重要な課題となっています。しかし、「自社に合ったLMSをどう構築すべきか」「失敗しない導入方法とは」という疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
LMS構築には主に「既存システムの導入」「専門会社への開発委託」「自社での構築」という3つの方法があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。また、クラウド型とオンプレミス型の選択や、人事システムとの連携、シングルサインオン対応など、検討すべきポイントは多岐にわたります。
本記事では、LMS構築を成功させるために、導入前の検討事項から構築方法の選び方、コストと期間の目安、よくある失敗例まで徹底解説します。これからLMS構築に取り組む方々にとって、プロジェクトの羅針盤となる完全ガイドを目指しました。失敗しないLMS構築で、貴社の人材育成を次のレベルへ引き上げましょう。
▼LMSについてはテーマに合わせて下記で詳しく解説しています。
▼LMS選定ポイントについては下記にまとめています。
目次[非表示]
LMSは自社構築ではなくクラウドにすべき

LMS(学習管理システム)の導入を検討する際、まず考えるべきことは構築方法です。
現在のビジネス環境においては、自社内にサーバーを設置するオンプレミス型よりも、クラウド型を選択することが多くの企業にとって合理的な選択となっています。
世の中はクラウド化の流れ
企業システムのDX化が急速に進む中、多くの業務システムがクラウドサービス(SaaS)へと移行しています。
この流れは単なるトレンドではなく、ビジネス環境の変化に適応するための戦略的な選択といえます。リモートワークの普及に伴い、場所や時間に制約されず学習できる環境の需要が高まっていることも、クラウド型LMSの普及を後押ししています。
構築の工数とコスト面
クラウド型LMSとオンプレミス型を比較すると、構築にかかる工数とコストに大きな違いがあります。
クラウド型は、サーバー構築や専門的なIT知識が不要で、最短5日程度での導入が可能です。対してオンプレミス型は、サーバーの準備から設定、セキュリティー対策まで多くの工程が必要で、一般的に1カ月以上の導入期間を要します。
コスト面でも、クラウド型は初期投資を抑えられるサブスクリプション型の料金体系が一般的です。オンプレミス型ではサーバー購入費やライセンス費用などの初期投資に加え、保守運用コストも継続的に発生します。
|
新たなテクノロジーを取り込みやすい
クラウド型LMSにおける最大のメリットの一つが、常に最新のテクノロジーを活用できる点です。クラウドサービスでは、ベンダーが定期的にシステムをアップデートするため、ユーザー側の負担なく最新機能を利用できます。
特に近年は、AIによる学習コンテンツのレコメンデーションや学習分析機能など、先進的な技術がLMSに組み込まれています。クラウド型であれば、こうした新技術をいち早く取り入れられるため、学習効果の向上や運用効率化につながります。
|
LMSを構築することとは?

LMS構築とは、組織の教育・研修ニーズに合わせて学習管理システム(LMS)を導入し、設定・カスタマイズして実際に運用できる状態にするプロセスを指します。
単にシステムを導入するだけでなく、組織の学習管理プロセス全体を設計・実装することを含みます。
LMS(学習管理システム)の基本機能と役割
LMS(Learning Management System)は、eラーニングをはじめとする教育コンテンツの配信や学習状況の管理を一元的に行うためのシステムです。主な機能と役割は以下の通りです。
まず、コンテンツ管理機能では、さまざまな形式の学習教材を登録・配信できます。ユーザー管理機能では、学習者の情報管理や権限設定が可能です。進捗管理機能により、受講状況や完了状況をリアルタイムで把握できます。また、テスト・評価機能では、理解度の測定や成績管理が行えます。
|
LMS自社構築のメリット
LMSを自社で構築する場合、いくつかの重要なメリットがあります。最も大きなメリットは、自社のニーズに完全に合わせたカスタマイズが可能な点です。特殊な業務フローや独自の教育体系に対応したシステムを実現できます。
また、既存の社内システム(人事システムやグループウェアなど)との緊密な連携も実現しやすくなります。データの連携や認証の一元化などを自社の要件通りに設計できるため、業務効率の向上につながります。
|
LMS自社構築が適している組織の特徴
全ての組織に自社構築が適しているわけではありません。自社構築が特に効果的な組織には、いくつかの特徴があります。
まず、大規模な従業員数を持つ企業では、ライセンス料の削減や大量のユーザー管理の効率化という観点から自社構築のメリットが大きくなります。また、特殊な業務プロセスやコンプライアンス要件がある組織、例えば金融機関や医療機関などでは、独自の要件に対応するためのカスタマイズの自由度が重要となります。
|
LMSを構築する3つの方法

LMSを組織に導入する際には、大きく分けて3つの構築方法があります。
それぞれにメリット・デメリットがあり、自社の状況や目的に応じて最適な方法を選択することが重要です。
クラウドサービスの活用
クラウドサービスの活用は、現在最も一般的なLMS構築方法です。これは既存のLMSをクラウド上で利用するもので、迅速かつ手軽な導入が可能です。システム構築の専門知識がなくても始められる点が大きな魅力です。
クラウド型LMSの主なメリットは、導入までの時間が短いことです。多くの場合、契約してから数日~数週間で利用開始できます。また、初期投資を抑えられるサブスクリプション型の料金体系が一般的で、利用規模に応じた柔軟な拡張も可能です。
|
内製での自社構築
自社のITリソースを活用してLMSを内製する方法です。完全に自社のニーズに合わせた設計が可能で、既存システムとの緊密な連携も実現しやすいというメリットがあります。
内製での自社構築の最大のメリットは、カスタマイズの自由度の高さです。独自の業務フローや特殊な要件にも柔軟に対応できます。また、長期的に見れば外部サービスのライセンス料が不要になるため、コスト削減につながる可能性もあります。
|
外部委託での自社構築
システム開発の専門会社に外部委託する方法は、自社開発と既製品導入の中間的な選択肢です。専門的な知識と経験を持つベンダーのノウハウを活用しながら、ある程度カスタマイズされたシステムを構築できます。
外部委託開発のメリットは、専門家の知見を生かした質の高いシステム構築が期待できる点です。LMS構築の経験豊富な会社であれば、過去の事例やベストプラクティスを踏まえた提案も可能です。
|
LMS構築のコストと期間
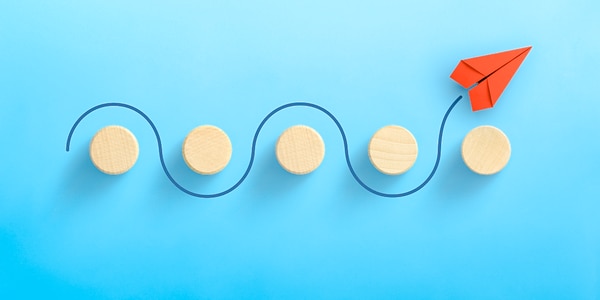
LMS構築を検討する際、予算と導入までのスケジュールは重要な検討要素です。構築方法によってコストと期間は大きく異なります。
初期費用と運用コスト
LMS構築にかかるコストは、「初期費用」と「運用コスト」に大別できます。初期費用には、システム構築費用、環境整備費用、初期データ登録費用などが含まれます。また、教材コンテンツを新規に作成する場合は、教材制作費も初期費用としてかかってきます。
一方、運用コストには、システムの保守・管理費用、クラウドサービスの場合はライセンス料金、教材の更新費用などが含まれます。長期的な視点では、この運用コストが累積的に大きな金額になることもあるため、初期費用だけでなく運用面のコストも含めた総コストで検討することが重要です。
|
3つの構築方法別の予算
LMSの構築方法によって、必要な予算は大きく異なります。一般的な目安として、以下のような予算感が考えられます。
クラウド型LMSの場合、初期費用は比較的低く抑えられます。一般的な中小企業であれば、初期設定費用として数十万円程度から導入可能なサービスも多くあります。月額利用料は、ユーザー数に応じて変動することが一般的ですが、1人当たり数百円から数千円程度が多いです。
自社開発の場合は、開発規模にもよりますが、数千万円以上の予算が必要となることが多いです。開発工数や必要な機能の複雑さによって大きく変動します。
|
3つの構築方法別の導入期間の目安
LMS導入にかかる期間も、選択する構築方法によって大きく異なります。適切な導入スケジュールを立てるための目安を解説します。
クラウド型LMSの場合、最も短期間での導入が可能です。標準機能のみの利用であれば、契約から1週間~1カ月程度で運用開始できるケースが多いです。ただし、人事システムとの連携やシングルサインオンなどのカスタマイズを行う場合は、さらに1~2ヶ月程度が必要になることもあります。
自社開発の場合は、要件定義から設計、開発、テスト、リリースまで含めると、一般的に半年~1年以上の期間を要します。
|
LMS構築時に大切なこと

LMSの構築を成功させるためには、単にシステムを導入するだけでは不十分です。組織の教育・研修戦略と整合したLMS活用計画が必要であり、構築段階から運用まで見据えた準備が重要となります。
LMSを構築して成し遂げたいこと(目的)を整理する
LMS構築の第一歩は、「なぜLMSを導入するのか」という目的の明確化です。単に「eラーニングをしたい」「他社が導入しているから」という理由では、導入後に活用されない「宝の持ち腐れ」になりかねません。
具体的な目的としては、研修・教育の質を向上させたい、学習記録を一元管理したい、教育のDX化を進めたい、研修・教育の効率化を図りたいなど、さまざまな視点が考えられます。これらの目的を組織の経営目標や人材育成方針と結びつけて整理することで、LMS導入の意義が明確になります。
|
目的達成のための最適な手段を選ぶ
目的が明確になったら、それを達成するための最適な手段を選定します。これは単にLMSの製品選びだけでなく、構築方法の選択も含みます。
まず、目的達成に必要な機能要件をリストアップします。例えば、多言語対応、モバイルアクセス、社内システム連携、分析機能など、優先度をつけて整理しましょう。次に、クラウド型、自社開発、委託開発のどの構築方法が適しているかを検討します。
|
運用も視野に入れて体制をつくる
LMS構築の成功は、システム導入だけでなく、その後の運用で決まります。構築段階から将来の運用を見据えた体制づくりが重要です。
まず、システム管理者や教材作成・管理担当者など、運用に必要な人的リソースを確保します。特に教材コンテンツの作成・更新は継続的な取り組みが必要なため、担当者の配置や外部リソースの活用計画を立てておくことが重要です。
|
LMS構築後の運用に必要なこと

LMSの構築が完了した後、実際に効果的な運用を行うためにさまざまな準備と継続的な作業が必要になります。これらのステップを計画的に進めることで、LMSの価値を最大化し、組織の学習文化の定着につなげることができます。
学習者情報・組織情報の登録
LMS運用の第一歩は、学習者と組織の情報を正確にシステムに登録することです。多くのLMSでは、CSVファイルなどを使った一括登録機能があり、効率的にデータ登録が可能です。
登録する情報には、基本的な個人情報(氏名、メールアドレス、社員IDなど)に加え、所属部署や役職などの組織情報も含まれます。特に組織階層の設定は、部門別の学習状況分析や権限管理に重要です。
|
人事異動の際の情報の更新
組織では定期的な人事異動が発生するため、LMS内の情報を最新の状態に保つ仕組みが必要です。情報更新を怠ると、誤った対象者に学習コンテンツが配信されるなどの問題が生じます。
効率的な情報更新のためには、人事異動や組織改編が行われたタイミングで人事システム情報をLMSに取り込むことです。APIやデータ連携の仕組みを構築することで、人事情報の変更が自動的にLMSに反映されるようにすることも可能ですが、人事異動や組織改編の頻度によってどこまでのシステム連携が必要かを考えましょう。
人事異動が年に1回の場合、システム連携しなくても、そのタイミングでデータを取り込んで更新することでも十分対応ができます。
|
既存コンテンツの選定
LMSの効果的な活用には、質の高い学習コンテンツが不可欠です。まずは社内に既存の教材(マニュアル、研修資料、動画など)があれば、それらをLMSで活用できるか検討します。
既存コンテンツを選定する際は、内容の正確性や最新性、形式の互換性などを評価基準とします。また、モノによっては著作権やライセンスの確認も重要です。
|
独自コンテンツの作成
既存コンテンツだけでは不十分な場合や、組織固有のノウハウを体系化する場合は、独自のeラーニングコンテンツを作成します。コンテンツ制作には、専門的なスキルや時間が必要です。
コンテンツ制作のアプローチとしては、社内リソースを活用する方法と、専門業者に委託する方法があります。社内制作の場合は、教材作成ツールを導入し、担当者の育成も必要となります。
|
対象者ごとの学習コース設計
効果的な学習体験を提供するには、対象者の特性や学習目的に合わせたコース設計が必要です。一律のコンテンツを全員に配信するのではなく、階層別、職種別、経験レベル別などに最適化されたコースを設計します。
コース設計では、必修コースと選択コースの区分、学習順序の設定、前提条件の設定などを行います。また、キャリアパスに沿った学習パスを設定することで、長期的な人材育成にも貢献します。
|
学習コースの配信設定
設計したコースを適切なタイミングで対象者に配信するための設定を行います。配信設定では、開始日・終了日の設定、受講期限の設定、修了条件の設定などが含まれます。
計画的な配信スケジュールの立案は重要です。
例えば、繁忙期を避けた配信や、関連する業務イベントに合わせた配信など、学習効果を高める工夫が可能です。
|
学習者へのリマインドなどのプロモーション
LMSを導入しても、自発的に学習する文化が定着していない組織では、学習者への積極的な働きかけが必要です。効果的なプロモーション活動により、LMSの利用率と学習効果を高めることができます。
基本的なプロモーション施策としては、自動リマインドメールの設定、未受講者へのフォローアップ、学習進捗状況の可視化などがあります。
|
LMS構築後の運用で大切なこと

LMSを構築し、基本的な運用体制を整えた後、システムを組織の人材育成に効果的に活用するためには、いくつかの重要なポイントがあります。
学習者中心で運用する
LMS運用で最も重要なのは、学習者の視点に立った運用です。どんなに高機能なシステムでも、利用者にとって使いにくければ定着しません。学習者中心の運用とは、利用者の学習体験を最優先に考えるアプローチです。
具体的には、シンプルで直感的なユーザーインターフェースの設計、分かりやすい操作ガイドの提供、学習しやすい環境づくりなどが含まれます。
|
経営層を巻き込んだメッセージの発信
LMSの活用を組織に定着させるには、経営層の関与が不可欠です。トップダウンでの推進力があることで、組織全体の優先順位が明確になり、学習文化が醸成されやすくなります。
経営層には、LMSを通じた学習の重要性や、経営目標との関連性を明確にしたメッセージを発信してもらいましょう。
|
集合研修などもLMSで運用する
LMSはeラーニングだけでなく、集合研修を含めた全ての研修・教育活動の管理プラットフォームとして活用できます。集合研修とオンライン学習を組み合わせたブレンディッドラーニングの運用基盤として活用することで、LMSの価値が最大化します。
具体的には、集合研修の申込管理、事前・事後学習の提供、研修資料の配布、アンケート収集などをLMSで一元管理します。
|
eラーニングパッケージなども活用する
全ての学習コンテンツを自社で開発するのは時間とコストがかかります。市販のeラーニングパッケージや外部コンテンツを適切に活用することで、効率的にコンテンツを充実させることができます。
特にビジネススキルやコンプライアンスなど、業界共通の普遍的な内容については、高品質の外部コンテンツが多数存在します。
|
データを活用したPDCA
LMSの大きなメリットは、学習活動に関するさまざまなデータを収集・分析できる点です。これらのデータを活用して、継続的にPDCAサイクルを回すことが成功の鍵となります。
収集すべきデータには、受講率、修了率、テスト結果、学習時間、アンケート結果などがあります。これらのデータを定期的に分析し、問題点や改善点を特定します。
|
LMS構築時に避けるべき4つの失敗

LMS構築プロジェクトは、適切な計画と実行がなければ、期待した成果を得られないだけでなく、組織の時間と資源の無駄遣いにつながるリスクがあります。
構築が目的となり学習者が置き去りにされる
LMS構築プロジェクトでよく見られるのが、システム導入自体が目的化してしまい、本来の目的である「学習者の育成」が忘れられてしまうケースです。特に技術的な側面に注目するあまり、実際にシステムを使う学習者の視点が欠落してしまう危険性があります。
この失敗を避けるためには、プロジェクトの計画段階から学習者の代表を参加させ、定期的にユーザビリティーテストを実施することが有効です。
|
経営層の関心が低い状態で構築が進む
経営層の理解とサポートなしに進めるLMSプロジェクトは、多くの場合困難に直面します。予算不足、人的リソースの確保の難しさ、全社展開の困難さなど、さまざまな障壁が生じることになります。
経営層の関心を高めるためには、LMS導入が経営目標達成にどう貢献するかを明確に示すことが重要です。
|
運用を見据えた体制づくりができずに、運用が進まない
LMSの導入に成功しても、その後の運用体制が整っていなければ、せっかくのシステムも十分に活用できません。特によくある失敗は、運用担当者の役割が明確でない、担当者の育成が不十分、または兼務で負担が大きすぎるといった状況です。
この失敗を避けるには、構築フェーズの早い段階から運用計画を立て、必要なリソースを確保しておくことが重要です。
|
教育コンテンツ整備が進まない
優れたLMSを導入しても、質の高い教育コンテンツが不足していては、その価値を十分に発揮できません。コンテンツ整備の難しさや工数を過小評価してしまうことは、LMS構築プロジェクトでよく見られる失敗の一つです。
特に、初期コンテンツの準備に注力するあまり、その後の継続的な運用体制づくりを怠ると、時間の経過とともにコンテンツが陳腐化し、LMSの利用価値が低下していきます。
この問題を解決するには、コンテンツ整備計画を綿密に立て、既存教材の活用や外部コンテンツの導入など、効率的なアプローチを検討することが重要です。
|
クラウド型LMSでパーソナライズ学習を実現し受講率100%を達成した事例

支援事例:専門商社(400名)
【これまでの課題】
- eラーニングを「必修」にしなければ学習しない
- 流し見で「完了」することが目的になってしまっている
- 業務が忙しくて受講することを忘れてしまう ・・・など
【受講率100%を実現】
- 「必修」「受講期限」の設定がない中で、受講率100%を実現
- 診断結果を基に自動でリコメンドされるコースを自主的に受講
- 1人平均5.7コースの受講(多い人は16コースの受講)
★今回のポイント
- パーソナライズ学習:パーソナル診断結果を基にした個々人に合わせた学習コンテンツを自動配信
- いつでも学べる環境:学習者が必要なときに必要な学習にアクセスできる環境
- 学習データの蓄積:学習者の学習状況をトラッキングするために学習行動のデータを取得
★お客さまの声
- 社内ではeラーニングを導入しても、結局やってくれないのではないかという声が出ていました。なぜなら、eラーニングを「必修」にしないと学習者が積極的に取り組まないといったことがあったからです。同じことを繰り返していても効果は上がらないと思っていましたが、パーソナライズ学習を取り入れたところ、受講率が100%になったので正直驚きました。
- また、これまではコンテンツ数にも限りがあり、自社のオリジナルコンテンツの搭載ができなかったのですが、自社オリジナルコンテンツの搭載もできるようになったことで、学習してもらう幅が広がりました。
- また、診断結果のレポートには、自身の強みや課題の啓発だけではなく、職場メンバーとの関係性の中で起こりうることや周囲が必要なことについてもアドバイスがあり、そのレポートを基に、他メンバーと対話することで、職場の中でのコミュニケーションが取りやすくなり、仕事がスムーズに進むようになりました。
LMS構築にはCrossKnowledgeがおすすめ

LMSの構築にはCrossKnowledge(クロスナレッジ)がおすすめです。CrossKnowledgeのLMS・eラーニングは、リーダーシップやマネジメントなどを学ぶための効果的な手段として世界中の企業やビジネスパーソンに活用されています。特徴を紹介します。
|
CrossKnowledgeのeラーニングはコンテンツ提供型eラーニングでもあり、自社独自のコンテンツを搭載して展開するプラットフォーム型でもあります。企業としても社員のスキルアップを効率的かつ持続的に支援するためのソリューションとして最適です。
具体的には下記のパッケージコースを提供しています。
◆階層別
- 新入社員パッケージ
- OJT担当者パッケージ
- 中堅社員パッケージ
- 新任管理職パッケージ
- ベテラン管理職パッケージ
- キャリア採用者パッケージ
◆目的別
- リーダーシップパッケージ①②
- AI時代のリーダーシップパッケージ
- コンプラ/ハラスメントパッケージ
- ダイバーシティパッケージ
- ストレスマネジメントパッケージ
- 営業向けパッケージ
- 経営コースパッケージ
- キャリア開発パッケージ
- ビジネスに不可欠な思考法パッケージ
- マーケティング/ファイナンスパッケージ
詳しくは下記をご覧ください。
⇒https://ldcube.jp/service/crossknowledge/elearning_package
まとめ:LMS構築を成功に導くために
LMS(学習管理システム)の構築方法とは?導入に失敗しないポイントを解説!について紹介します。
- LMSは自社構築ではなくクラウドにすべき
- LMS構築とは?
- LMS構築の3つの方法
- LMS構築のコストと期間
- LMS構築時に大切なこと
- LMS構築後の運用に必要なこと
- LMS構築後の運用で大切なこと
- LMS構築時に避けるべき4つの失敗
- クラウド型LMSでパーソナライズ学習を実現し受講率100%を達成した事例
LMS構築を成功させるためには、システム導入という技術的側面だけでなく、組織の人材育成戦略全体を視野に入れた取り組みが必要です。本記事で解説したように、まず構築方法の選択では、多くの企業にとってクラウド型LMSが優位性を持っています。構築にあたっては、明確な目的設定、適切な予算・期間の確保、そして運用体制の整備が重要な要素となります。
成功の鍵は、テクノロジーではなく「人」にあります。学習者中心の設計と運用、経営層の積極的な関与、質の高いコンテンツの継続的な提供、そして収集したデータを生かした改善サイクルの確立。これらがそろって初めて、LMSは組織の人材育成を強力に推進するツールとなります。
LMSは導入してからが本当のスタートです。長期的な視点で計画を立て、組織全体で取り組む姿勢を持って、人と組織の成長を支えるLMS構築に挑戦してみましょう。
株式会社LDcubeはCrossKnowledgeの日本国内の公式パートナーとしてLMSやeラーニング・マイクロラーニングなどの提供などを行っています。
また無料のデモIDやデモ体験会、活用事例・導入事例の紹介、料金の案内なども行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。