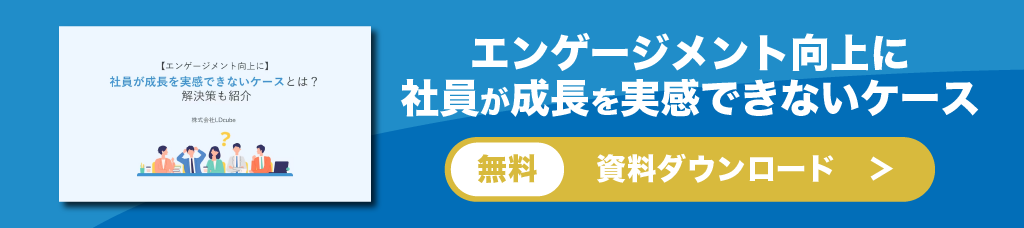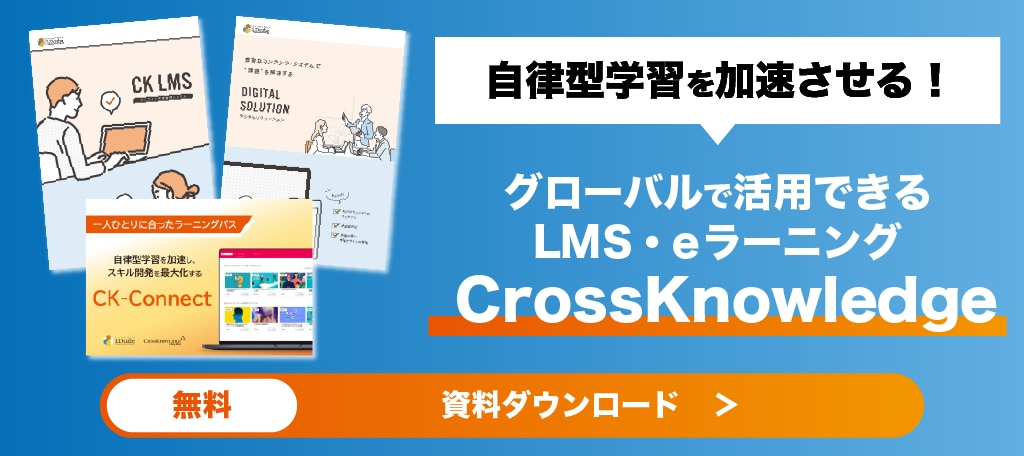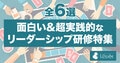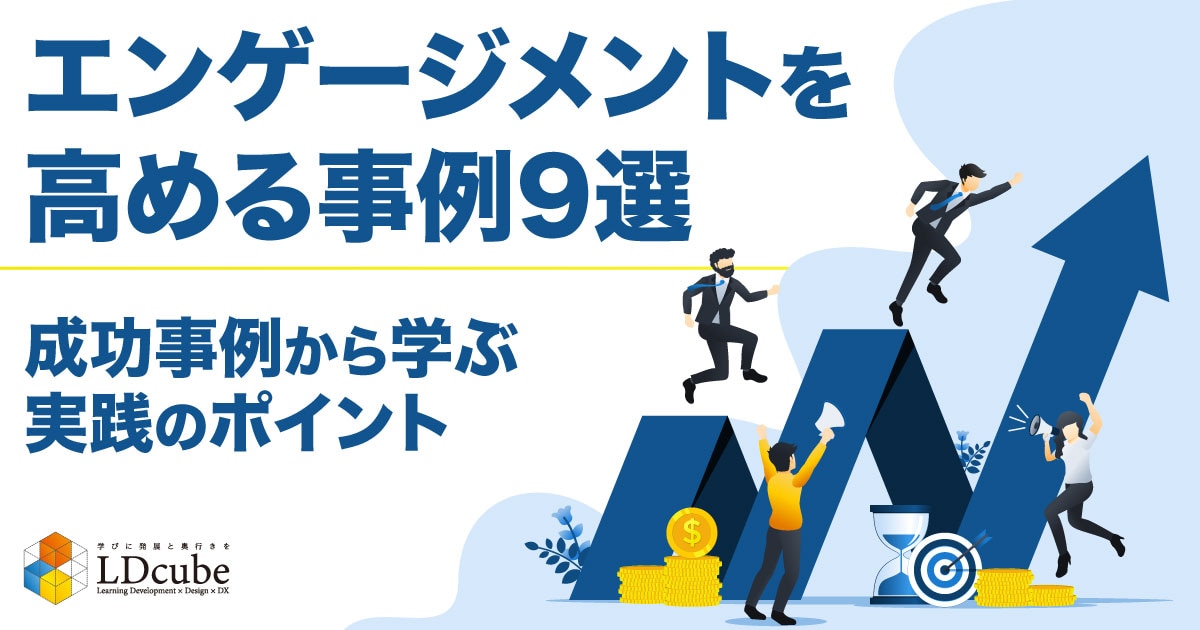
エンゲージメントを高める好事例9選|成功例から学ぶ実践のポイント!
「エンゲージメントを高める事例ってどんなのがある?もう離職率は高いし社員からは不満だらけでどうにかしたい」
「エンゲージメントを高める事例を参考に、うちの会社もマネできないかな?もっと社員の主体性を引き出したいんだよなあ」
従業員のエンゲージメントを高めて、自社の現状を改善したいと思っても、どのように取り組めばいいのかいまいち具体的にイメージするのは難しいですよね。
そこで、本記事ではエンゲージメントを高めることに成功した企業事例を合計9つ紹介していきます。
※企業名をクリックするとすぐに該当箇所に飛べるようになっています。
エンゲージメントを高めることができた事例9選 | |||
|---|---|---|---|
企業名 | 課題 | 施策 | 改善・向上したこと |
業績悪化 | 従業員と会社の価値観をすり合わせ | ・業績改善 | |
社員との不協和音 | 行動指針を策定し、従業員に共有 | 社内の一体化 | |
エンドユーザーの心の獲得 | エンゲージメントサーベイの導入 | ・従業員のエンゲージメント向上 | |
コマツらしく会社を持続 | 会社の基本的な心構えや信念をまとめて配布 | ・業績好調 | |
業績悪化 | ・挙手性による会議への参加 | ・業績改善 | |
業績悪化 | ・ビジョンの共有 | ・業績改善 | |
離職率の高さ | ・経営理念の浸透 | ・離職率低下 | |
人材の確保が困難 | 働き方と休み方の見直し | ・休みの取得率向上 | |
社員側との意思疎通が | ・コミュニケーションの重視 | ・信頼感の構築 | |
各企業が課題解決のためにエンゲージメントを高める施策に取り組んだところ、エンゲージメントの改善だけでなく、ほかの側面でも向上が見られました。
従業員のモチベーションやスキルアップ、会社の方針との共感によって、いい変化をもたらしたのです。
とはいえ、エンゲージメントを高める施策はただやって終わり、ではなく実際に効果があるかきちんと確認しながら施策を打つことが重要です。
そのまま施策を打って終われば、手間や時間だけが無駄になってしまう可能性も否定できません。
そこで本記事では、エンゲージメントを高める事例とともに以下の内容をお伝えします。
本記事を読んでわかること |
|
ぜひ本記事を読み進め、エンゲージメントを高める事例について理解を深めていきましょう。
▼エンゲージメントについてはテーマごとに下記で詳しく解説しています。
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
目次[非表示]
- 1.エンゲージメントを高める事例1. スターバックス
- 2.エンゲージメントを高める事例2. ユーザベース
- 3.エンゲージメントを高める事例3. LIXIL
- 4.エンゲージメントを高める事例4. コマツ
- 5.エンゲージメントを高める事例5. 株式会社丸井グループ
- 6.エンゲージメントを高める事例6. 株式会社LIFULL
- 7.エンゲージメントを高める事例7. 株式会社福井
- 8.エンゲージメントを高める事例8. 山口労災病院
- 9.エンゲージメントを高める事例9. 株式会社ハンナ
- 10.エンゲージメントを高める事例から学ぶ実践のポイント
- 10.1.会社のビジョンをわかりやすく共有する
- 10.2.社内コミュニケーションの円滑化を促進する
- 10.3.成長できる環境を整える
- 10.4.ワークライフバランスの改善をする
- 11.エンゲージメントを高めるには定期的に測定してアップデートしていくのが大事
- 12.まとめ
エンゲージメントを高める事例1. スターバックス

会社概要 | |
社名 | スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 |
業界 | 飲食業の小売業 |
従業員数 | 5,510名 |
スターバックスはアメリカ発祥のコーヒーチェーン店で、エンゲージメントの高い企業として有名です。
しかし今よりもエンゲージメントが低かった2007年頃、スターバックスは業績の悪化が止まらない時期がありました。
抱えていた課題
スターバックスは、売上高は伸びていても、利益の低い状況に陥っていました。
経営陣はどうにかすべく、経営の合理化を図りますが、より悪化の一途とたどります。
経営の合理化とは簡単にいえば数字を見てドライに割り切って行動することで、人員を2割カットすれば人件費が2割減って、利益が上がるというような考え方です。
スターバックスは経営を合理化するために店舗でコーヒー豆をひかず、別のセンターでまとめてひくことにした結果、コーヒーの香りのしない店になりました。
売上を増やすために店舗数の拡大化を図った結果、バリスタが足りなくなり、研修が不十分でも店頭に立たせてコーヒーの味も落ちました。
2007年の米国の消費者レポートでは、ハンバーガーチェーン店のマックよりもコーヒーの味が低評価となっていたのです。
そこでこのままではいけないと案じたスターバックスの創業者のハワード・シュルツ氏が、施策を打ちました。
実際におこなった施策
ハワード・シュルツ氏は一度退任していたもののCEOに最就任し「原点回帰すべし」としてスタバらしさを考えました。
そのなかにあった施策のひとつが、パートナーと呼ぶバリスタとの心の絆を取り戻すことです。
スターバックスが正しいと感じたことにパートナーが共感しているか、本気でやりたいと感じているかを重視したのです。
手っ取り早く売上を上げるための合理化は正しいのか、パートナーが働きたい場所になるのか、こういったことを視野に入れ、店舗でコーヒー豆をひく方法に戻しました。
さらに全米7100店舗を一斉に半日閉店して、バリスタを教育しなおしました。
教育が不十分なバリスタを店頭に出しても本人は不安になり、お客さまには美味しいコーヒーを飲んでもらえず誰もが満足する結果にはなりません。
また日本においてもスターバックスの指導ではあれをするように、これをするように、という方法はとらずパートナーの気持ちを重視します。
「今の接客はなぜうまくいったんでしょう?」「これからどんな力を磨いていきたいですか?」など常にパートナーの気持ちに沿った問いかけで、パートナーに自ら考えてもらう方法で成長させていきます。
スターバックスの考えを押しつけることなく、パートナー個々の価値観とすりあわせていくのです。
だからこそスターバックスの考え方に共感して、「こんな風に働きたい」「こう動いたらお客さまに喜んでもらえる」といった行動に移ります。
パートナーをともにスターバックスを作り上げる対等な立場として捉え、役員会でも「パートナーやお客さまがこの場に座っていたら、どのように考え、発言するか意識すべき」と伝えて大切にしています。
このようなパートナーと会社が共感できるか、ということを重視した施策を実施した結果、次のような効果を得ることができました。
エンゲージメント施策の効果
結果的にスターバックスの業績は改善し、今でも多くの人に愛されるコーヒーチェーン店として日本では1,991店舗を構えています。
スターバックスには、サービスに関するマニュアルがありません。
ただ「お客様が何をしてほしいかを考えてサービスしよう」ということだけです。
しかしこれだけにもかかわらず、パートナーにはコーヒーカップに絵を描いたり、注文を迷っている方におすすめのドリンクを紹介したり、パートナー自身が顧客のニーズに応えようとする意識があります。
これはスターバックスへのエンゲージメントから来るものであり、パートナーの顧客のため、店舗のために何かしたいという自発的な行動につながっているのです。
一度は業績が悪化したものの、スターバックスは従業員であるパートナーを意識し、会社の価値観と個人の価値観を共感させながらエンゲージメントを高めた結果、不振を乗り越えて会社の成長につながりました。
〈参考〉
日本の人事部「マニュアルのないスターバックスは、なぜエンゲージメントを高められるのか(前編)」
東洋経済オンライン「よみがえったスタバに学ぶ、「らしさ」の経営」
エンゲージメントを高める取り組みに関する問い合わせはこちらから!
エンゲージメントを高める事例2. ユーザベース
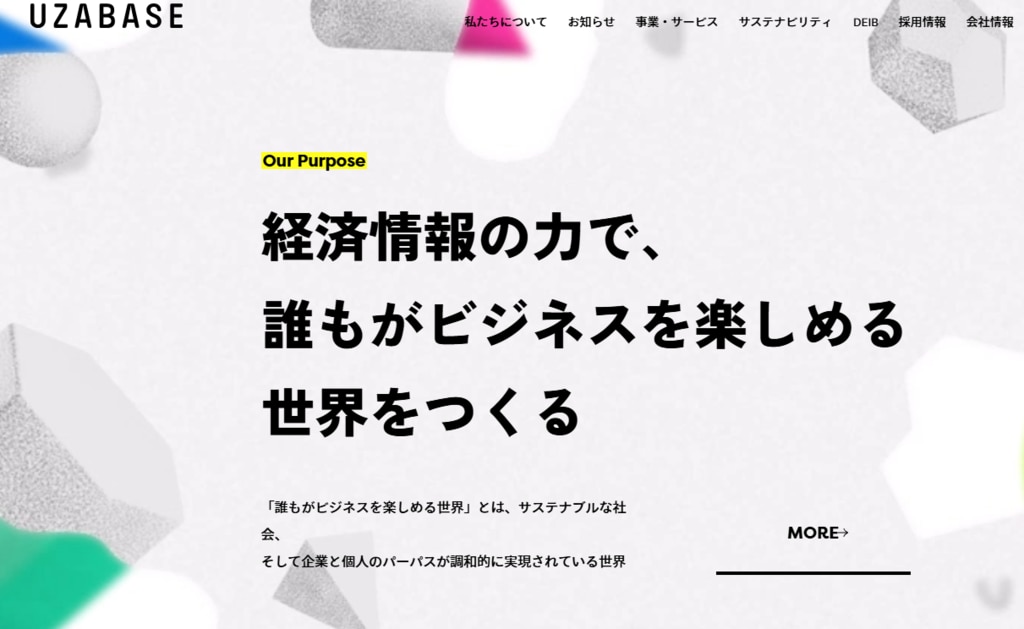
出典:ユーザベース
会社概要 | |
社名 | ユーザベース |
業界 | 企業・業界分析のためのオンライン情報プラットフォーム「SPEEDA」やソーシャル機能を兼ね備えた経済ニュースプラットフォーム「NewsPicks」を運営 |
従業員数 | 1,093名 |
ユーザベースは、エンゲージメントの高い会社としてよく知られています。
2020年にビジネスパーソン向けのオンラインメディア「ダイヤモンド・オンライン」で発表された社員の「エンゲージメント」が高い企業ランキング・ベスト50ではユーザベースが1位を獲得しました。
ではなぜ従業員のエンゲージメントが高いのか、ユーザベースのエンゲージメントが高い理由のひとつは、「会社と従業員がミッションやバリューを共有する」ことです。
ユーザベースは2008年に3人の共同経営者で創業後、10年ほどで急成長を遂げ、右肩上がりで業績が伸びています。
しかし、ずっと順調だったわけではなく以下のような課題を抱えていました。
抱えていた課題
創業から4年が過ぎた2012年頃は、社員との不協和音に悩まされたといいます。
原因は会社の方向性が、社員に伝わっていなかったからです。
これまで3人の共同創業者は、創業前から会社が目指す「ミッション」や大切にする価値観である「バリュー」について共通の認識をもっていました。
しかし社員には「背中を見せていれば学びとってもらえる」「目の前の作業をこなすことが先」と言語化していなかったのです。
事業内容を拡大しながら社員が30~40人に増え、資金調達やプラットフォームの開発などに追われ、社長は社員のフォローにまで手が回っていませんでした。
その頃の飲み会では多くの社員がネガティブな内容ばかり話しており、社長である自分たちのいない場所ではさらにいろいろと話し合っているのではないかと感じ、内部崩壊の恐れがあると危機感を覚えました。
そこで共同経営者3人だけでなく社員にも伝わるよう、「バリュー」をきちんと言語化すべきと考えたそうです。実際におこなった施策は以下の通りです。
実際におこなった施策
以下「7つのルール」を作り、ユーザベースの行動指針を策定しました。
- 自由主義で行こう
- 創造性がなければ意味がない
- ユーザーの理想から始める
- スピードで驚かす
- 迷ったら挑戦する道を選ぶ
- 渦中の友を助ける
- 異能は才能
これらを実施した結果、以下のような成果を得ることができました。
エンゲージメント施策の効果
ルールを発表した日の飲み会では多くの社員からの質問が飛び交い、ルールを真正面から理解しようとする姿に、社長は発信力不足を痛感したそうです。
普段の会話からなんとなく通じているだろうではなく、形にして伝えるべきだったと猛省したのです。
そして7つのルールが策定されてからは経営者が社員に何を求めるのか、行動や姿勢が明確になり、社員の迷いがなくなったことで、ユーザベースの不協和音が嘘のように消えました。
ユーザベースの事例では経営側だけでなく、社員も共同の価値観をもつことがエンゲージメントの向上大きく貢献することを意味しています。
〈参考〉
SUPER CEO「世界を狙う組織のつくり方~ユーザベース崩壊の危機を救った「7つのルール」~」
エンゲージメントを高める事例3. LIXIL

出典:LIXIL
会社概要 | |
社名 | 株式会社 LIXIL |
業界 | 水まわり製品や建材製品の開発・提供 |
従業員数 | 53,834名 |
LIXILは水まわり製品や建材製品の開発・提供をおこなっており、自宅の窓やドア、洗面台などにLIXILの商品を使われている方も多いのではないでしょうか。
さまざまな場面で商品を見かけるので、経営が順調そうなLIXILに課題があるのか疑問を抱く方もいるかもしれません。
しかし実は、以下のような課題を抱えていました。
抱えていた課題
LIXILはエンドユーザーのニーズ把握の方法に課題を抱えていました。
少子高齢化による人口減少は、新築の着工戸数に影響を与えています。
住宅業界の業績へ大きな影響をもたらしており、住宅設備に自社商品を提供しているLIXILも例外ではありませんでした。
そこで今後は新築だけではなく、リフォーム市場への注力が欠かせなくなっていきます。
しかし工務店や住宅建築事業社がかかわることの多い新築事業と比較すると、リフォーム事業は施工主であるエンドユーザーが主体です。
そのためエンドユーザーのニーズをいかに掴むかが、重要なのです。
エンドユーザーのニーズを把握できれば、ニーズを満たして商品提供をして心を掴み、利益につなげられます。
そのためにLIXILがとった施策は、以下です。
実際におこなった施策
LIXILはショールームコーディネーターのエンゲージメントが、ユーザーニーズの把握に欠かせないとして高めることに注力しました。
エンドユーザーとの接点は全国にあるショールームであり、ショールームコーディネーターを通じて製品を知ります。
ショールームコーディネーター自身が満足していない会社の提供する商品を、エンドユーザーに満足してもらえないと考えたのです。
エンゲージメントを高めるにあたって、LIXILは従業員エクスペリエンス((従業員が会社で経験するあらゆる体験)を分析するために「Qualtrics EmployeeXM」を導入しました。
従業員が会社を好きになる・働きがいを感じるプロセスや経験を把握するためで、エンゲージメント向上につながります。
Qualtrics EmployeeXMは自社で設問の設定からサーベイの配布と進捗管理、結果分析までをおこなえるシステムで、自由度の高い調査が可能です。
たとえば国内従業員2万4000人を対象にした在宅勤務に関する調査では、約2週間で情報収集でき、人事施策へ反映できました。
タイムリーに施策をとれるので、従業員の不満を長期間溜めることなく改善へつなげられ、エンゲージメントの向上を図れるのです。
これらを実施した結果、以下のような成果を得ることができました。
エンゲージメント施策の効果
2025年3月現在LIXILが公表している従業員のエンゲージメントは71%と、多くの従業員が肯定的な回答をしています。
従業員エクスペリエンスを分析し、改善を計り続けることで、多くの従業員が会社に対して好意的な意識をもっていることがわかります。
そして2025年3月期には、目標としていたリフォーム売上構成比50%を達成しました。
「Qualtrics EmployeeXM」を導入した2020年は、リフォーム関連売上比率が37%だったものの、2025年には51%となり、LIXILは新築依存を克服できたとしています。
実際に商品を使うエンドユーザーに対して、現場の従業員が大きな影響を与えることをLIXILは認識しています。
だからこそいかに従業員に自社や自社商品へ愛着をもっているか、エンゲージメントを重視し、LIXILは課題を克服しました。
〈参考〉
qualtrics「顧客と従業員のエクスペリエンスを向上させるXMソリューション」
NEC「LIXIL、従業員と顧客のエクスペリエンス向上でクラウド型データ分析活用」
LIXIL「働きがいのある職場」
SAP News Center「LIXILが実践する従業員エンゲージメント向上と顧客志向の徹底」
エンゲージメントを高める事例4. コマツ

出典:コマツ
会社概要 | |
社名 | コマツ (登記社名:株式会社 小松製作所) |
業界 | 建設・鉱山機械、ユーティリティ(小型機械)、林業機械、産業機械など |
従業員数 | 連結 65,738名 |
コマツは世界中に251社を抱える大きなグループ会社で、外国人比率は70%にのぼるグローバルな企業です。
企業間取引が主でありながら、CMも放映しているので会社の名前を知っている人も多いでしょう。
そのようなコマツが抱えていた課題は、以下です。
抱えていた課題
コマツは100年を超える長い歴史をもつ会社で、全世界で事業を展開しています。
さまざまな国や地域の価値観や文化で組織が構成されており、いかにコマツがコマツらしく会社を持続的に運営していくためにはどうすべきか、が課題でした。
コマツはグローバルに事業を展開していくうえで、社員のエンゲージメント向上は会社の持続的成長に欠かせないと考えたのです。
そこで2012年の4月に従業員エンゲージメントを向上させるべく、以下の施策を打ちました。
実際におこなった施策
コマツはエンゲージメントを高めるために「コマツウェイ」を強化しました。
2006年に策定されたコマツウェイは、創業者の思いをベースにしながら基本的な心構えや信念といったコマツの価値観がまとめられたものです。
- グローバルにここだけは守り続けたい
- 人が変わっても、脈々と受け継いでいってほしい
- 先輩が築き上げてきた、成功・失敗の経験
会社の想いや目標に共感して同じ視点で一緒に会社を成長させていくには、コマツウェイで会社の方針をわかりやすく理解してもらう必要がありました。
そのコマツウェイを全社員が対応できるよう、15カ国語に多言語化して以下3つの内容に再編して配布しました。
- トップマネジメント編、
- 全社員共通編(モノ作り編)
- ブランドマネジメント編
どの階級の社員にでも対応できるようにし、コマツにいる限りずっと活用できる冊子にしたのです。
そして管理職層へはコマツウェイにおける説明会をおこない、さらに管理職層から現場の従業員へ考え方や心構えを伝えてもらい浸透を強化させました。
現場の従業員のエンゲージメントを高めるには、遠い立場の存在ではなく直属の上司からのアプローチが欠かせないからです。
管理職層へ説明会を実施するとともに教育・研修体制を整備し、管理職層からは現場へアプローチできる環境を作り上げた結果、コマツがとったエンゲージメント施策では以下のような効果がありました。
エンゲージメント施策の効果
直近の2023年度エンゲージメントサーベイの好意的回答の割合は以下となっており、従業員の過半数がコマツへのエンゲージメントが高い状況です。
- グローバル:80
- 国内:69
直近の自己都合離職率は1.26%と低く、日本の平均離職率15.4%を大いに下回っています。
(出典:厚生労働省「-令和5年雇用動向調査結果の概況-」)
そしてコマツがエンゲージメントを高めるべく行動した結果、2012年は1.98兆円だった売上が2025年の3月現在で3.99兆円にのぼっており、事業は順調に進んでいるといえるでしょう。
コマツは会社の方針を国や階級を問わず、全社員にわかりやすく浸透させることで同じ視点をもってもらい、エンゲージメントを高めた結果、会社を持続的に成長させ続けている事例です。
〈参考〉
コマツ「成長戦略によるESGの課題解決」
コマツ「多様な能力開発機会の提供とエンゲージメントの向上」
imajina「従業員エンゲージメントの向上が、企業成長を促進させる」
厚生労働省「人材育成の取り組み - コマツ」
エンゲージメントを高める事例5. 株式会社丸井グループ
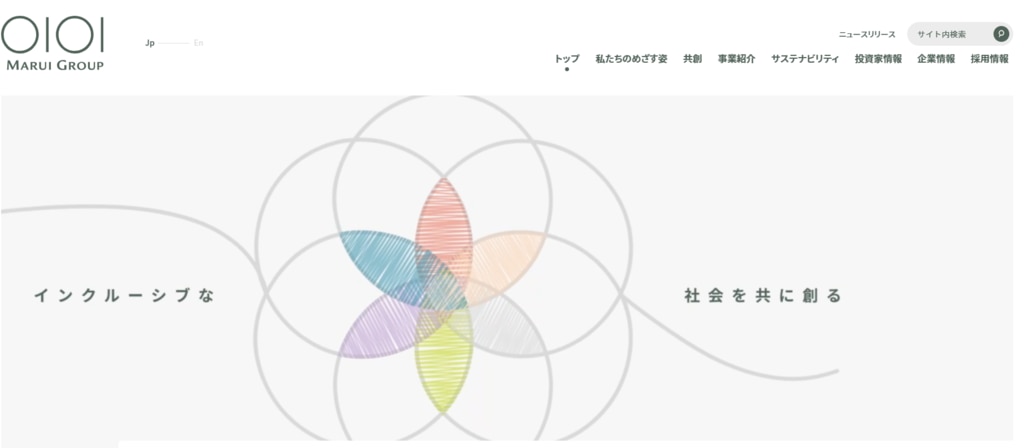
出典:株式会社丸井グループ
会社概要 | |
社名 | 株式会社丸井グループ |
業界 | 小売事業、フィンテック事業(金融分野×IT技術)をおこなうグループ会社の経営計画・管理など |
従業員数 | 4,290名 |
株式会社丸井グループは、人的資本経営における取り組みを充実させており、エンゲージメント高い会社です。
そんな株式会社丸井グループでは、以前以下のような課題を抱えていました。
抱えていた課題
2009年〜2011年頃、貸金業法の改正を含むさまざまな影響で業績が悪化し、赤字でした。
組織風土改革、カルチャー改革が重要であると認識し、株式会社丸井グループを根本的に変える必要があったといいます。
当時は会議に参加するメンバーは黒いスーツを着た男性ばかりで、居眠りをしている人もおり、活気はまったくなかったといいます。
このような状況下で、株式会社丸井グループは人的資本経営に取り組んでいくこととなり、以下の施策に取り組み、従業員のやりがいや連帯感などのエンゲージメントを高めました。
実際におこなった施策
株式会社丸井グループが人的資本経営に取り組み、エンゲージメントを高めている施策は以下です。
- 手上げの文化
- グループ間職種変更異動
手上げの文化は参加したい人に手を挙げてもらい、その人たちだけを招く会議の開催です。
本当にやる気のある人たちだけを集めることで高いやりがいをもってもらえ、会議の活性化も狙えます。
そしてグループ間職種変更移動は、株式会社丸井グループの小売やフィンテック、ITや物流、住宅関連、証券などさまざまな事業をまたいで異動できる制度です。
簡単にいえば、社内で転職しているようなものです。
2022年3月期において異なる職種へ異動した社員は77%にのぼり、86%が異動後に成長を実感していると回答しています。
このグループ間職種変更異動も手上げの文化でおこなっており、社員のやりたい気持ちを引き立たせることにつながっています。
このような株式会社丸井グループの取り組みにより、以下のような効果を得ました。
エンゲージメント施策の効果
2009年の株式会社丸井グループの純利益は-87億5,000万円でしたが、2024年3月には246億6,000万円と黒字になりました。
そして社員が主体的に動く会社になったことで、10年で以下のようにエンゲージメントが向上しました。
- 自分が仕事のうえで何を期待されているかわかっている:2012年 46% 2022年 80%
- 自分が職場で尊重されていると感じる:2012年 28% 2022年 66%
- 自分の強みを活かしてチャレンジしている:2012年 38% 2022年 52%
現在の株式会社丸井グループの中期経営会議では、
- 女性社員も当たり前に参加・発表
- 男性社員も服装がカジュアルに
- 居眠りしている人はおらず、みんな活き活きして会議に参加 など
2008年頃と雰囲気がまったく異なっています。
株式会社丸井グループは手上げの文化やグループ間職種変更異動から社員の自主性を高め続けており、今後は新たな事業としてアニメ事業を展開し、更なる利益を見込んでいます。
株式会社丸井グループはやりたいと感じた社員、誰もが生き生きと働けるような施策でエンゲージメントを高めた結果、利益にしっかりとつなげています。
〈参考〉
丸井グループ「丸井グループの人的資本経営 #2」
リクルートワークス研究所「丸井グループ/本質的な問いに向き合い 10年かけて「 人的資本」を拡大」
Unipos(ユニポス)「丸井グループさんに人的資本経営について教えてもらいました|田中弦のCEOBlog-vol.8」
エンゲージメントを高める事例6. 株式会社LIFULL

出典:株式会社LIFULL
会社概要 | |
社名 | 株式会社LIFULL |
業界 | 不動産情報サービス事業、不動産事業者向け事業など |
従業員数 | 1,925 名 |
株式会社LIFULLは不動産情報サービス事業や不動産事業者向け事業などをおこなっている会社です。
日本最大級といえる不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME'S(ライフル ホームズ)」を活用したことのある方は多いのではないでしょうか。
そんな株式会社LIFULLの抱えていた課題は、以下です。
抱えていた課題
メンバー同志の連携がなく、共通のビジョン実現を目指す「チーム」になれず業績・組織どちらも危機的な状況でした。
社員はモチベーションが下がり、移動や転職を考えるほど仕事の意義を見失っていた状況です。
LIFULL HOME’S事業本部 新UX開発部の菅野氏は、業績改善によってメンバーのモチベーションは上がると考え、有効だと思われる手法をバンバン打っていきました。
しかし多少業績が上向く程度で、モチベーションは上がらなかったそうです。
そんなときに利用したのがエンゲージメントを中心とした人事課題の解決ツール「モチベーションクラウド」です。
組織の状態を調べたところ最低レベルのスコアだったことから、業績改善よりやり方の見直しが必要だと気づきました。
業績改善ではなく、エンゲージメントを高める方向に動いたのです。
実際におこなった施策
株式会社LIFULLがエンゲージメントを高めるためにおこなった施策は以下です。
- ビジョンをチームで浸透し、戦略の設計
- 担当大臣制
- 1on1
まずは顧客へどんな価値提供をするかビジョンを考えたうえで、やりたいと思った施策の提案、戦略への落とし込みをしました。
ミーティングを通してチームで話し合い、全員でストーリー作りをおこなったのです。
そして戦略をしっかり実行するために、担当大臣制を取り入れ仕事を1人1個もつことにしました。
サイト解析大臣なら各企画担当者が自分の施策解析だけでなく全体を俯瞰して解析をする、結びつけ担当大臣なら店舗とマーケターの距離を縮め情報流通をするといった、一部だけにとどまらない役割です。
さらに1on1の時間これまでより長くし、一人ひとりの心にビジョンや戦略が根付いているか確認するようにしました。
このような施策によって得られた、株式会社LIFULLの効果は以下のとおりです。
エンゲージメント施策の効果
業績は昨対300%と大きく改善。
まず共通したビジョンを抱えられるようになり、戦略を実行する基盤が整いました。
さらに仕事の悩みだけでなくキャリアやパーソナルの悩みが相談できる環境が整い、包括的に課題解決できるようになったことで、メンバーとの信頼関係を構築できました。
これにより今までバラバラで仕事をしていた部署内が、自分たちはいいものを広めているという自身とともに、ひとつの目標に向かってチーム全体で取り組む姿勢に変わったのです。
株式会社LIFULLでは、何年もKPI(業務のパフォーマンスを計測する指標)を達成できていなかったといいます。
しかし今回の事例では数字だけでなくエンゲージメントを高めるほうへ意識することで、結果的に業績UPが付いてくることを株式会社LIFULLは示しました。
〈参考〉
モチベーションクラウド「ビジョンと仕事を結びつけ、売上昨対300%の組織へ」
エンゲージメントを高める事例7. 株式会社福井

出典:株式会社福井
会社概要 | |
社名 | 株式会社福井 |
業界 | 堺打刃物の製造・卸売、農園芸・ガーデニング用品や工具・DIY用品・アウトドア用品の取り扱い |
従業員数 | 118名 |
株式会社福井は創業1912年の100年以上続く、老舗企業です。
しかし事業経営はずっと順調だったわけではなく、以下のような課題を抱えた時期もありました。
抱えていた課題
2008年〜2016年は業績が伸びているものの、株式会社福井は離職率の高さに頭を悩ませていました。
採用数=離職数と、まったく人材が定着しなかったのです。
コミュニケーションも一方通行で社員から経営者が話しかけられるときは「◯月◯日付で会社を辞めさせてください」という退職の話だったそうです。
このように人がなかなか定着しないなか、株式会社福井がなぜ100年続いたのか考えた社長は社員の力だと気づき、エンゲージメントの重要性を痛感しました。
そこで以下のような取り組みで、エンゲージメントを高めることに着手しました。
実際におこなった施策
- 経営理念の浸透
- 1on1
- エンゲージメントサーベイの実施
まずは経営理念を浸透させることから始めました。
「共に喜ぶ」という理念があったものの、ただの言葉になっているだけだったため、会社がどう考えてどう接しているかを基本方針としてことあるごとに伝えるようにして浸透させました。
社員と家族が株式会社福井では最上段としており、社員に「大切にしている」ことをきちんとメッセージで伝えるように心がけたといいます。
また1on1を開始し、デスクではできない話を、腹を割ってするようにしました。
1on1は部下のための時間として捉えており、ときには傷口に塩を塗るような話もし、常に本気で話し合っています。
質の良さを追求するために幹部全体で研修や議論の場も作っていることも、ただの自己満足ではなく社員のためになる施策といえるでしょう。
そして取り組んで終わりではなく、エンゲージメントサーベイの実施で現状を把握し、取り組みの成果を見ながら改善していきます。
株式会社福井がこれまでのやりかたに、反省すべき点が多かったと回顧したことは少なくありません。
しかし今の現状を受け止め、この先を見据えてエンゲージメントを高める施策を打ったことで、以下のような効果を得ています。
エンゲージメント施策の効果
- 離職率低下
- 社風の変化
- 業績向上
まずは課題となっていた離職率が下がりました。
定着率が上がっただけでなく、新卒採用においても人材が集まるようになったといいます。
大手企業にとられてしまいやすい国公立大学卒の方や、語学に優れた方、理系卒の方に入社してもらえるようになり、会社を成長させる人材確保につながりました。
また一方通行のコミュニケーションではなくなり、普段口数の少ない社員からも「会社のためにこんなことはどうか」といったアイデアも生まれたことも大きな変化です。
エンゲージメントを高めることでもちろん業績にもいい影響を与え、売上は38億円と13年連続で増加し、会社として持続的に成長できています。
株式会社福井は現状に満足せず、次の100年に向けても社員と家族を大切にしながらエンゲージメント経営を進めています。
<参考>
Wevox「離職に課題があった老舗企業がエンゲージメント経営で「採用と定着」に強みを持つ組織に!【Teamwork Sessionレポート】」
エンゲージメントを高める事例8. 山口労災病院

出典:山口労災病院
会社概要 | |
社名 | 山口労災病院 |
業界 | 労働災害や職業性疾病などへの診療 |
従業員数 | 不明 |
山口労災病院は労働災害や職業性疾病などへの診療をおこなっている病院で、現在では病床数308床、24診療科を有する総合病院です。
できる限り患者がベッドで寝たきりにならないよう、山口労災病院の看護師はナースステーションではなくベッドサイドを支点として看護する方法で、積極的に離床を促しながら退院支援をおこなっています。
そんな山口労災病院は、以下のような課題を抱えていました。
抱えていた課題
夜勤のできる看護師の離職が多く、人材の確保が難しい状況で、原因は夜勤中のシフトにあると考えられました。
以前の夜勤の働き方はインターバルが意識されておらず昼夜遷移が激しい状態で、体内環境を整えるサーカディアンリズムとはほど遠く、ストレスや体調不良につながってもおかしくない状況です。
1カ月に2連休を2回確保するルールも土日祝日の確保はできておらず、プライベートの充実とはほど遠い状況でした。
ベッドサイドで先輩が看護を見せながら教育する方式をとっていましたが、スキルのある中堅看護師が夜勤のない施設へ転職してしまうため、人手が足りないだけでなく、看護の質に影響を与えていたのです。
このままでは若い看護師が育たず、今の看護にも影響が出ているため、以下の施策を山口労災病院はとりました。
実際におこなった施策
山口労災病院は働き方と休み方を見直しました。
勤務間のインターバルは以下3つの選択肢から組みます。
変更前の例)
休み-深夜-深夜-日勤-準夜-準夜-休み
準夜-準夜、深夜-深夜など
変更後)
1.準夜-準夜-休み-深夜-深夜-休み-休み
2.準夜-休み-深夜-深夜-休み(準夜-準夜-休み-深夜-休み)
3.準夜-休み―深夜-休み
変更前と比較して、しっかり休みを確保できていることをおわかりいただけるでしょう。
深夜前の入りの休みだけは勤務間隔を23時間30分しか確保できないため、時間外勤務手当(深夜割増)の対象としています。
さらに夜勤に関連しない休みを増やし、土日祝日の2連休もしっかり確保しました。
このような休みをきちんと取れ、プライベートの時間も確実に取れる環境にしたことで、山口労災病院のエンゲージメントは以下のように変わりました。
エンゲージメント施策の効果
エンゲージメント向上への取り組み前の2021年と取り組み後の2022年について、どのように休めるようになったか、比較をまとめました。
【2021年】
夜勤に関連しない休み:4.17日/月
全体の休みの38%
土日祝日における夜勤に関連する休みの割合:23%
【2022年】
夜勤に関連しない休み:2.76日/月
全体の休みの25%
土日祝日における夜勤に関連する休みの割合:14.8%
夜勤に関連しない休みは減った結果、土日祝日も含めてきちんとプライベートとして休めるようになり、休日を効果的に取得できているといえるでしょう。
さらに1か月に2回の連休取得ルールも守れ、2回のうち1回は土日祝日での2連休を取得、また3連休の取得割合もUPしました。
結果的に以下のように、毎年5~6月にかけて実施しているストレスチェックでエンゲージメントの改善が見られました。
- ワークエンゲージメント(仕事から活力を得ており仕事に誇りがもてる)のストレス:改善率13%
- 仕事が時間内に終わらない:改善率16.6%
- ワークライフバランスポジティブ(仕事により自分の生活も充実):改善率9%
- 仕事のコントロール:改善率22.5%
山口労災病院はワークライフバランスをきちんと整えたことで、これまでのように離職を選択肢とする思考になりにくい、仕事へのやりがいや誇りを感じられる職場環境に変わった事例です。
エンゲージメントを高める事例9. 株式会社ハンナ

出典:株式会社ハンナ
会社概要 | |
社名 | 株式会社ハンナ |
業界 | 道路貨物運送業 |
従業員数 | 150名 |
株式会社ハンナは44期を迎えた、道路貨物運送業を担う会社です。
現社長は3代目となる下村 由加里氏ですが、以下のような課題を抱えていました。
抱えていた事例
3代にわたる長期経営のなかで、歴代の社長が採用した社員の性格や考え方が世代ごとに異なっていました。
これにより、下村氏が就任時に掲げた経営戦略が、一部の社員から合意を得られにくい状況となってしまいます。
過去に賃金体系を変更したときに経営陣と社員側との意思疎通が不十分だった結果、不満を抱えたままの社員もいました。
さまざまな原因で多くの社員が不満を抱えるなかで初めての死亡事故が起き、さらには経営陣と社員側が対立するといった数々の問題が生じました。
結果的に多数の社員の離職し、同業他社に助けてもらいながら業務をこなすことになり、会社を続けていくには社員との関わり方の見直しが必須となったのです。
あらゆる方面における課題が山積みになった株式会社ハンナは、エンゲージメントを高めるために、次の施策をとりました。
実際におこなった施策
- コミュニケーションを重視する
- 社員を大切にする(例:24時間365日営業にシフト)
- 経営方針を確認する
株式会社ハンナはまず、6年かけて社員と丁寧にコミュニケーションを重ねました。面談が1日15人にのぼることもあるほどです。
そして自社の考えとして5S(整理、整頓、清掃、清潔、しつけ)を実施できること、自分自身も周囲の人(家族、同僚等)も大切にできることを求め、会社の方針をしっかり伝えていきます。
社員を大切にすることを会社は重視し、社員自身でも自分を大切にしてもらえるよう求めたのです。
実際に介護や育児をしている人のために、希望する時間で働けるよう株式会社ハンナは24時間365日営業にシフトしました。
「良いワークのためには良いライフが必要」という考えのもと、社員には家族や同僚、顧客にも配慮しながらワークライフバランスを重視してもらい、エンゲージメント向上につなげました。
そして既存の社員とこれからの社員のエンゲージメントを向上し続けるために、採用時には自社の経営方針や考え方にマッチする人であるか、を念頭に以下2つを重視します。
- 採用時に自社の価値観に沿った人材か確認する
- 入社後も経営層と面談を続け、企業風土や価値観を理解してもらう
既存の社員と同じく5Sをきちんと実施でき、周囲を大切にできる人材であることが第一です。
自社の価値観と初めから合わないのであれば、お互いのためにも採用を見送る選択肢をもちました。
さらに入社後は期間を空けながら社長または取締役と4回の面談を実施し、経営者が社員の考えを直接聞き、社員からも会社の考えを聞くチャンスを設けました。
株式会社ハンナは粘り強く社員の話を聞くように心がけ、コミュニケーションを密にとることにしたのです。
その結果、以下のような施策の効果がありました。
エンゲージメント施策の効果
株式会社ハンナが企業として何を重要視している会社なのか、どれだけ社員を大切にしているかが社員にきちんと浸透し、共感を得ることに成功した結果、社員が自発的に会社のために取り組むように変わりました。
健康経営の認証※1を奈良県で初めて取得するときに尽力したのは、社長と同年代のパートを何十年も続けた社員だったといいます。
SNSでは広報のために新入社員が自発的にTikTokで踊って、多くの人の目に触れるようにもしました。このとき、気難しい部長も新入社員から踊るよう促され、つい踊ってしまうほどの社内の雰囲気の良さも魅力です。
さらに「社員を大切にする会社」という評判が広まり、入社希望者が増加しました。
2023年の4~6月は30~40名の応募が殺到し、11人を採用しています。
※1健康経営の認証:経済産業省に認定されるホワイト企業のステータス
株式会社ハンナの社長は多くの社員が抱いていた不満に対して諦めず、真剣に向き合いました。
今では社内全体で課題解決に取り組む魅力的な会社として、持続的に成長しています。
〈参考〉
働き方・休み方改善ポータルサイト「株式会社ハンナ」
健康経営の広場「【IKIGAI企業インタビュー】物流の2024年問題はドライバーの地位を上げるチャンス。“社員ファースト”経営が人財を創る(株式会社ハンナ)」
土地活用ラボ「第1回 働き方改革で、柔軟性がある職場、社員が人生を全うできる職場を準備する」
エンゲージメントを高める事例から学ぶ実践のポイント

ここまで、エンゲージメントを高める事例を解説しました。
そのなかでエンゲージメントを高めるには必須といえる、積極的に取り入れるべきポイントについて解説していきます。
エンゲージメントを高めるためには、以下4つを意識してください。
|
順番に解説します。
会社のビジョンをわかりやすく共有する
エンゲージメントを高めるには、会社のビジョンをわかりやすく共有することが大切です。
会社がどのような方向性で事業を進めたいのか、社員がわからず共感できなければ迷いや不安感などが生じてエンゲージメントは高まりません。
たとえば「3. エンゲージメントを高める事例2. ユーザベース」の事例では、社員にはいわなくても見ていればわかってくれているはず、という認識を経営者たちはもっていました。
しかし実際はまったく伝わっておらず、業績と反比例するような形で心が離れていきました。
「いわなくても伝わっている」は間違いなのです。
会社がこれからどう動いていくか、こんな思いで働いてほしいという意思をわかりやすく伝えることが社員も同じ思いをもって行動できる動機付けにつながるのです。
実際ユーザベースは7つのルールを作ったことで、社員と経営者が共感して同じ目標に進むことができ、順調に経営を続けられています。
会社のビジョンは経営側だけでなく、社員一人ひとりがわかるようにし、日頃から以下のような方法で共有するようにしましょう。
会社のビジョンをわかりやすく共有する手段 |
|
社内コミュニケーションの円滑化を促進する
社内でスムーズにコミュニケーションをとれる環境はエンゲージメント向上につながります。
「上司に話がしづらい」「会社は全然社員のことをわかっていない」このような環境ではエンゲージメントは高まりません。
社内コミュニケーションが円滑になると個々ではなくチームで目標に進んでいけ、モチベーションの相乗効果を期待できまます。
その結果、アイデアが出たり個々の知識やスキルを存分に発揮しやすくなったりして、目標達成につながります。
事実「7. エンゲージメントを高める事例6. 株式会社LIFULL」の事例では、グループ長一人がどれだけ頑張っても業績は改善しませんでした。
しかしミーティングや1on1などを重ねてエンゲージメントが高まり、チーム全体で取り組める状況になったとき、これまで達成できなかった数値目標を満たして昨対300%の業績を得ることが叶いました。
社内コミュニケーションの円滑化は仕事をしやすくなるだけでなく、エンゲージメントが高まることで同じ方向性で全員が向かっていけるようになるため、結果として会社の目標達成につながります。
以下のような方法をとり積極的に社内コミュニケーションをとってエンゲージメント向上を図りましょう。
社内コミュニケーションを円滑化する手段 |
|
成長できる環境を整える
社員が成長できる環境を整えることは、エンゲージメントが向上します。
やりがいを見い出し、こうなりたいという思いが出ると、会社を引っ張っていく意識が大きくなるからです。
「6. エンゲージメントを高める事例5. 株式会社丸井グループ」を見ておわかりいただけるように、エンゲージメントが高くなったことで、会社にとって良い結果をもたらしています。
手を挙げれば誰もが経営にかかわる会議に参加でき、自分のやりたい職種へチャレンジできる環境を得られるシステムが株式会社丸井グループにはあります。
これまでは眠っている人がいるほど活気がなかった会議で、現在は多くの社員が生き生きと声を挙げられるようになりました。
以前のままとりあえず店舗の管理者が会議に参加する、という状況では、エンゲージメントは向上せず、活気のないままで業績も浮上しなかった可能性すらあるでしょう。
以下のような社員が成長できる環境を整えることで、会社を支える力となってくれ成長を大きく促します。
成長できる環境を整える手段 |
|
ワークライフバランスの改善をする
ワークライフバランスの改善は、エンゲージメントを高めます。
常にプライベートを犠牲にして働き続ければ心身の健康維持はままならず、意欲は落ちて離職につながりやすくなります。
貴重な人材を失うことにもなるため、ワークライフバランスの改善は必須です。
実際に「9. エンゲージメントを高める事例8. 山口労災病院」では、休み方と働き方についてワークライフバランスの見直しを図った結果、社員のエンゲージメントが高まり、働きやすさを感じています。
以下のような方法でワークライフバランスを整え、人材の定着とパフォーマンスの発揮を促しましょう。
ワークライフバランスを改善する手段 |
|
エンゲージメントを高めるには定期的に測定してアップデートしていくのが大事

エンゲージメントを高めるには、定期的な測定をして施策のアップデートが必要です。
ただ施策を打っても、実際に社員へ響いているかわからないからです。
普段の勉強をきちんと理解できているか測るのにテストがあるように、エンゲージメントも定期的に測定することで意味がある施策なのか、それとも別の施策に切り替えるべきなのか判断が付きます。
ダイエットも数値で目に見えて効果がわかるほど、モチベーションが上がるでしょう。
継続的に取り組む環境作りにはエンゲージメントに取り組む側にとって定期的な測定が欠かせません。
「5. エンゲージメントを高める事例4. コマツ」でも定期的にエンゲージメントサーベイをおこなっており、目標を掲げながら施策に取り組んでいます。
さらに高まった自社のエンゲージメントを公表することで、企業イメージの向上にもつながりやすくなり、メリットは大きいです。
ただしエンゲージメントサーベイはさまざまな企業からツールが提供されているため、自社に合ったものを選ぶ必要があります。
以下のようなポイントを比較しながら、エンゲージメントサーベイに使用するツールを選びましょう。
エンゲージメントサーベイツールの比較ポイント |
|
エンゲージメントを高めるならLDcubeのLMSがおすすめ |
エンゲージメントを高めるなら、弊社LDcubeの提供するLMS(Learning Management System)の活用がおすすめです。 LMSは自社の教育プログラムをデジタル化させられる学習管理システムで、従業員の方の継続的な成長やスキルアップを促せます。 新入社員や中堅層など、従業員の階層別にパッケージが分かれているので、個々に合ったプログラムを学習でき、効率的に学べる特徴があります。 多言語対応しているので日本国内だけでなくグローバルな企業さまでもご活用いただけ、学習数時間や場所も選びません。 LMSなら今のスキルをさらにアップさせることはもちろん、リスキングによって別の分野の知識を習得することもできるため、グループ間で幅広い事業を担っている企業さまにもご活用いただけます。 従業員の方のエンゲージメント向上をお考えでしたらぜひ一度、LDcubeへご相談ください |
まとめ
エンゲージメントを高める事例について、ご理解いただけましたでしょうか。
最後に、本記事の要点についてまとめていきます。
◎本記事で紹介したエンゲージメントを高めることができた事例は、以下9つです。
エンゲージメントを高めることができた事例9選 | |||
|---|---|---|---|
企業名 | 課題 | 施策 | 改善・向上したこと |
業績悪化 | 従業員と会社の価値観をすり合わせ | ・業績改善 ・自発的な行動の発生 | |
社員との不協和音 | 行動指針を策定し、従業員に共有 | 社内の一体化 | |
エンドユーザーの心の獲得 | エンゲージメントサーベイの導入 | ・従業員のエンゲージメント向上 ・リフォーム売上比率目標達成 | |
コマツらしく会社を持続 | 会社の基本的な心構えや信念をまとめて配布 | ・業績好調 ・持続的に成長の成功 | |
業績悪化 | ・挙手性による会議への参加 ・グループ間職種変更異動 | ・業績改善 ・自発的な行動の発生 ・新たな事業の展開 | |
業績悪化 | ・ビジョンの共有 ・コミュニケーションの強化 | ・業績改善 ・チームとして機能 | |
離職率の高さ | ・経営理念の浸透 ・1on1 ・エンゲージメントサーベイの実施 | ・離職率低下 ・社風の変化 ・業績向上 | |
人材の確保が困難 | 働き方と休み方の見直し | ・休みの取得率向上 ・ストレスチェック改善 | |
社員側との意思疎通が 不十分 | ・コミュニケーションの重視 ・従業員ファースト ・経営方針を確認 | ・信頼感の構築 ・自発的な行動の発生 ・入社希望者の増加 | |
◎エンゲージメントを高めるためには、以下4つの施策を実践してください。
|
◎エンゲージメントを高めるには定期的に測定してアップデートしていくのが大事です。
ぜひ本記事を参考に、自社のエンゲージメントを高めてください。
LDcubeが提供する『CrossKnowledge CK-Connect』は、従業員の個性・強み・課題に即した学びを提供して、エンゲージメント向上につなげられる学習管理システム(LMS)です。
パーソナリティ診断に基づいて、強みを伸ばし、課題を補うための推奨コースを提案して、一人一人に最適な学びを創出します。
活用方法や導入メリットがわかる資料を無料で公開していますので、ぜひこの機会にダウンロードしてみてはいかがでしょうか。
▼従業員のエンゲージメントを上げるアワードについては以下も併せてご覧ください。
⇒従業員のエンゲージメントを上げるアワードの作り方【成功事例付きで解説】
▼関連資料はこちらからダウンロードできます。
▼関連記事はこちらから。