パナソニック株式会社くらしアプライアンス社様
ITSを活用し、成功体験の繰り返しだけではない、新たな「モノづくり」へ変革
~技術伝承を実現して国内基盤を強化する、そのための新たな人財育成のかたち~

-
取組前の課題:
・技術伝承に向けた国内基盤の整備が必要だった。
・多様な力を育む人材育成体制の再構築が求められた。
-
取り組んだこと:
・ITSとFISH!のライセンスプログラムを活用し、モノづくり現場の若手教育と、変革推進力を向上
-
今後の展望:
・ITSを組織文化や共通言語として定着させ、全員が活用できる環境を整備したい。

パナソニック株式会社
くらしアプライアンス社
人事センター モノづくり学校/人材開発部 企画管理課 主務
中島 昭一 様
パナソニック株式会社の社内分社であるくらしアプライアンス社は、生活家電・デバイス製品の開発・製造や食サービスなどを行っています。100年育んできたくらしに寄りそう力で、 人と地球の未来に続く、感動の商品をサービスを創造しています。
中島様は、社内のモノづくり学校という人財育成機関において、モノづくりに携わる人材が必要とする基本的な技能や技術を習得するための、教育体系の整備から研修講師まで担っています。
「モノづくり現場の体系的な教育を実施したいが、やり方が分からない」
「今までのやり方から変革していくための人財育成を実現したい」
このようなお悩みや想いをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
パナソニック株式会社くらしアプライアンス社様では、モノづくり現場の専門教育において、
革新的思考啓発のツールとしてITSを活用し、今までにないモノづくりへの変革と、
それを実現するための人財育成を促進するお取り組みをされています。
本記事では、人事センター モノづくり学校および人材開発部 企画管理課 主務の中島 昭一 様に
インタビューした内容をレポートします。
導入前の課題
今までのやり方から変革していくための人財育成の必要性
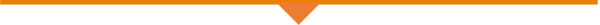
当社では、当時、海外への生産移管を進める一方で、国内事業の強化にも取り組んでいました。海外に生産機能を移す一方で、国内では既存のリソースを最大限に活用し、組織力の強化を目指していました。
しかし、いざ海外への生産移管を進めると、モノづくりに対する考え方や文化の違いに直面し、スムーズな移行が難しいという課題が浮き彫りになりました。また、コア技術の伝承が想定以上に困難であることも明らかになりました。
さらに、国内にモノづくりの技能を継承できる基盤がなければ、技術の伝承は成り立たないという結論に至り、「国内回帰」へと方向転換しました。その一環として、技能伝承および国内基盤の強化を目的に、新卒採用の再開を決定しました。しかし、当時当社では長年にわたり新卒採用を停止していたため、採用活動自体が難航しました。新入社員を迎え入れても、気がつけば社内で最も年齢の近い先輩が40歳という状況になっており、20年間にわたって人材育成が行われていなかったこと、そして指導者の不在が大きな課題となっていました。

こうした背景を踏まえ、当社では「モノづくり学校」という人材育成機関を設立し、体系的な人材育成を進めてきました。「モノづくり学校」は、モノづくりに携わる人材が必要とする基本的な技能や技術を習得することを目的として設立しました。
しかし、人材育成をより広い視点で捉えた際、技能・技術の習得だけでは十分ではないと感じるようになりました。そのため、ヒューマンスキルやコンセプチュアルスキルといった要素も育成の対象に含める方針へとシフトしました。
こうして人材育成の幅を広げていく中で、ちょうど新卒採用を本格的に再開するタイミングとも重なりました。そのため、従来とは異なる、新しい視点での取り組みが必要だと考えるようになりました。
これまでは「モノづくり現場に特化した育成」を中心に据えていましたが、より多角的な視点から人材育成に取り組むことが重要だと考えるに至りました。
出会いと導入の決め手
シンプルさと実践的なフレームワークに感じた、組織改革の可能性

~出会いのきっかけ~
2004年頃、労働組合の書記長対象研修の一環としてITSの短縮版研修を受講しました。当時、組織としては労働組合活動の変革を模索しており、現状の育成方法に限界を感じていました。新たな労働運動のあり方を検討する切り口として、執行委員を対象にITSを活用した2泊3日の宿泊研修を実施し、リアルテーマでの企画書づくりを行いました。
その後、組織改革の必要性が高まる中で、新たな人材育成の方法を模索していました。特に、従来の「モノづくり現場だから」という固定観念に縛られず、体系的な育成手法を導入することが求められていました。
~導入の決め手~
モノづくり学校の設立を検討する中で、実践的かつ柔軟な教育手法の必要性を痛感していました。従来のOJTだけでは新たな発想を取り入れることが難しく、また、年齢層のギャップを埋める仕組みが不足していました。
ITSを改めて検討した際に、以下の点が導入の決め手となりました。
①シンプルかつ実践的な学習アプローチ
研修を通じて得た知識を、すぐに現場で活かすことができる仕組みが整っている点に魅力を感じました。
②発想の転換を促すフレームワーク
モノづくりの現場では「成功体験の積み重ね」が基本とされていますが、それだけではなく「新しい視点を持つこと」の重要性に気付くことができるツールであると判断しました。
③人材育成の共通言語としての活用可能性
技術継承や教育に関する考え方を統一し、社内の誰もが共通のフレームワークで議論できる環境をつくることができると期待しました。
このように、ITSの導入は単なる研修プログラムではなく、組織改革の一環として活用できると感じました。
展開ステップとお取り組み
成功体験の繰り返し、「それだけではない」モノづくりへ

当社の「モノづくり学校」では、技能技術伝承とモノづくり系社員の基礎を形成することを目的に、以下のような考え方で取り組みを展開しています。
<基本方針>
一人ひとりの自主性を活かし チャレンジし続ける人材を育てる!
<目指す人材像>
全社員がお客様と向き合う会社へ!変革を目指し、事業成長の幹となる
- 共に学び(チームワーク)
- 自ら考え(シンキング)
- 前に踏み出す(チャレンジ)

<教育施策と取り組み>
①人を育てる/人が育つ 現場の実現
②モノづくり大事の風土醸成
③地域技能振興を通じた社会貢献 パナソニックファンづくり
- 新入社員教育
高卒・高専卒・大卒入社者の新入社員教育 - 中堅社員教育
階層研修等による現場リーダー育成
技能五輪訓練によるTOP技能人財育成 - 全社横串活動
モノづくり技能大会運営、技能検定取得支援 など - 海外人材教育
ローカル責任者育成(課題設定~解決力開発) - 産官学連携活動
中学生モノづくり教室
高校生機械組立仕上研修

上記の取り組みの中で、「2.中堅社員教育」における専門スキル研修において、ITSプログラムを活用しています。
製造現場では、成功体験の繰り返しが重要視されてきました。しかし、今後の変化に対応するためには、新たな発想が求められます。そのため、ITSプログラムの「発散・収束・実践化」のスキルは、これからのモノづくりの現場に必要なスキルなのです。
また、FISH!(フィッシュ)という、LDcubeが提供するもう1つのライセンスプログラムも活用しています。FISH!プログラムは、「仕事を楽しむ」「相手を楽しませる」「相手に向き合う」「態度を決める」という分かりやすく奥の深い哲学を活用した、職場活性化プログラムです。FISH!哲学を活用し、一人一人が活性化された職場について考え、いきいきした職場を実現するきっかけをつくります。
このプログラムを、実習生の配属前研修のカリキュラムに必ず入れることで、「働く」ということを学んでもらっています。学生の延長ではなく、「働くってどういうことだろう?」ということを考えてもらっています。受講者は特に、「楽しむ」というキーワードについて関心が高い印象です。職場の人を思い浮かべながら、「自分にできることは何か?」という行動まで落とし込んでもらっています。
ITSについては、今後さらに活用範囲をさらに広げ、社外のパートナー企業との共同研修や異業種交流の場でも活用していく計画です。こうした取り組みを通じて、より実践的なスキルの習得を促し、組織全体の成長につなげていきたいと考えています。
導入後の感想・成果
ITSのファンが増え、受講者の発想の柔軟性が向上した

ITSを受講した社員からは、柔軟な発想を阻害していたのは「自分自身のものごとの捉え方」であることへの気付きや、発想を促す手法が分かりやすく「多くの人に受講して欲しい」などの意見が多く寄せられています。
また、受講者の声として「発散が意外と簡単だった」という意見が多く聞かれます。しかし、実践化の部分に関してはまだ課題が残っており、現場の上司の巻き込みやOJTなどを通じたフォローアップが必要と考えています。
具体的な成果という点ではまだ明確に答えられませんが、受講者の発想の柔軟性が向上したと感じます。
研修で身に付けたことを現場で生かすにはまだ慣れと実践が必要ですが、着実にITSの考え方は広まってきていると感じます。

受講者の声
自身の「思考の箍(たが)」に気付き、職場での活用のヒントを得られた

ITSの技法を学び、「アイデア創造を妨げる、自身の思考の箍に気付いた」「ITSのテクニックを活用すれば、可能性を広げられる」といった声が多く上がりました。
<発散技法>
- まさに、思考の箍に気付かされるとともに、アイデア出しを妨げていることを痛感した
- テクニックの切り口も分かりやすく、慣れることでアイデア出しにつながると感じた
- 使いこなすための機会設定に対して、思考の箍をかけてしまっている自分に気付いた
- 創造的という言葉に対して無意識に思考の箍をはめていたが、テクニックを知ることで自分の可能性を引き出すことができることが理解できた
- みんなが発散思考で話し合うことができれば、職場のコミュニケーションの活性化にもつながると感じた
<収束・実践化技法>
- アイデアを絞り込み、磨けあげるための視点について、体系的に学ぶことができた
- 日常的に収束的な思考で業務を進めてきていると感じたが、より具体的に理解した上で手法を使うことで、より効果的なアイデアにつながると感じた
- ロードマップを中心において、作成するために必要な切り口が収束技法の中に盛り込まれていることがよく分かった
- ロードマップをしっかりと仕上げることは、チームで仕事を進める上でも非常に重要であると感じた
取り組みにおける課題と今後の取り組み
業務への活用促進のためのフォローアップに注力したい

ITSの導入後、一定の成果が見られた一方で、いくつかの課題も浮き彫りになりました。まず、受講者の中には、ITSの概念を理解していても、実際の業務に落とし込むのが難しいと感じる声がありました。特に、従来の業務スタイルが根付いている部門では、新しいアプローチを受け入れるまでに時間がかかる傾向がありました。
さらに、受講者のスキル定着のためのフォローアップ体制が十分ではなく、研修後に実践を促す仕組みが必要であると感じました。そのため、今後はフォローアップ面談の強化や、現場の工場長の理解促進を強化し、受講後のサポートを充実させる方針です。
今後の取り組みとしては、ITSの活用範囲をさらに広げるため、異業種交流への参加者拡大などを図っていきます。また、他業界の事例を学ぶことで、新たな視点を取り入れる機会を増やし、より実践的なスキルの習得を目指します。
最終的には、ITSを単なる研修プログラムではなく、組織文化の一部、そして共通言語として根付かせることが目標です。そのために、ITSの重要性を社内に浸透させ、全員が共通のフレームワークを活用できる環境を整えていきます。
関連記事
Contact
人材育成でお悩みの方は、お気軽にご相談ください
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
人材育成に関する
お役立ち資料はこちらから
お電話でのお問い合わせはこちら
平日9:00~17:30

